お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

直違の紋に誓って
篠川翠
歴史・時代
かつて、二本松には藩のために戦った少年たちがいた。
故郷を守らんと十四で戦いに臨み、生き延びた少年は、長じて何を学んだのか。
二本松少年隊最後の生き残りである武谷剛介。彼が子孫に残された話を元に、二本松少年隊の実像に迫ります。

平隊士の日々
china01
歴史・時代
新選組に本当に居た平隊士、松崎静馬が書いただろうな日記で
事実と思われる内容で平隊士の日常を描いています
また、多くの平隊士も登場します
ただし、局長や副長はほんの少し、井上組長が多いかな

お江戸を指南所
朝山みどり
歴史・時代
千夏の家の門札には「お江戸を指南所」とおどけた字で書いてある。
千夏はお父様とお母様の三人家族だ。お母様のほうのお祖父様はおみやげを持ってよく遊びに来る。
そのお祖父様はお父様のことを得体の知れない表六玉と呼んでいて、お母様は失礼ね。人の旦那様のことをと言って笑っている。
そんな千夏の家の隣りに、「坊ちゃん」と呼ばれる青年が引っ越して来た。
お父様は最近、盗賊が出るからお隣りに人が来てよかったと喜こぶが、千夏は「坊ちゃん」はたいして頼りにならないと思っている。
そんなある日、友達のキヨちゃんが行儀見習いに行くことが決まり、二人は久しぶりに会った。
二人はお互いの成長を感じた。それは嬉しくてちょっと寂しいことだった。
そして千夏は「坊ちゃん」と親しくなるが、お隣りの幽霊騒ぎは盗賊の手がかりとなり、キヨちゃんが盗賊の手引きをする?まさか・・・

GAME CHANGER 日本帝国1945からの逆襲
俊也
歴史・時代
時は1945年3月、敗色濃厚の日本軍。
今まさに沖縄に侵攻せんとする圧倒的戦力のアメリカ陸海軍を前に、日本の指導者達は若者達による航空機の自爆攻撃…特攻 で事態を打開しようとしていた。
「バカかお前ら、本当に戦争に勝つ気があるのか!?」
その男はただの学徒兵にも関わらず、平然とそう言い放ち特攻出撃を拒否した。
当初は困惑し怒り狂う日本海軍上層部であったが…!?
姉妹作「新訳 零戦戦記」共々宜しくお願い致します。
共に
第8回歴史時代小説参加しました!

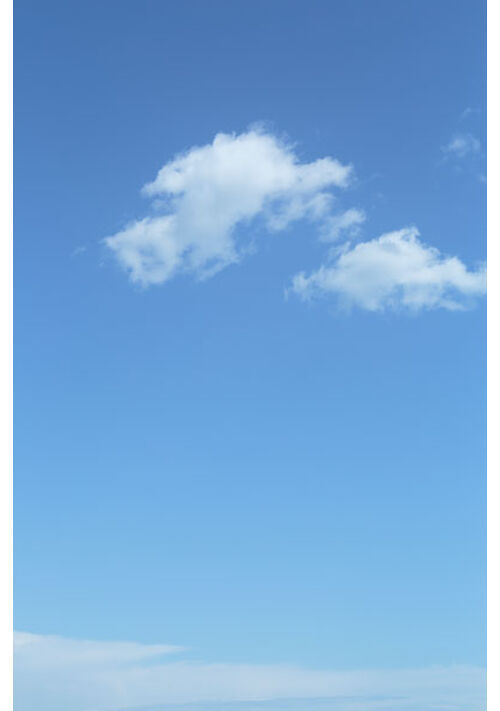


狩野岑信 元禄二刀流絵巻
仁獅寺永雪
歴史・時代
狩野岑信は、江戸中期の幕府御用絵師である。竹川町狩野家の次男に生まれながら、特に分家を許された上、父や兄を差し置いて江戸画壇の頂点となる狩野派総上席の地位を与えられた。さらに、狩野派最初の奥絵師ともなった。
特筆すべき代表作もないことから、従来、時の将軍に気に入られて出世しただけの男と見られてきた。
しかし、彼は、主君が将軍になったその年に死んでいるのである。これはどういうことなのか。
彼の特異な点は、「松本友盛」という主君から賜った別名(むしろ本名)があったことだ。この名前で、土圭之間詰め番士という武官職をも務めていた。
舞台は、赤穂事件のあった元禄時代、生類憐れみの令に支配された江戸の町。主人公は、様々な歴史上の事件や人物とも関りながら成長して行く。
これは、絵師と武士、二つの名前と二つの役職を持ち、張り巡らされた陰謀から主君を守り、遂に六代将軍に押し上げた謎の男・狩野岑信の一生を読み解く物語である。
投稿二作目、最後までお楽しみいただければ幸いです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















