お気に入りに追加
69
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

伊緒さんのお嫁ご飯
三條すずしろ
ライト文芸
貴女がいるから、まっすぐ家に帰ります――。
伊緒さんが作ってくれる、おいしい「お嫁ご飯」が楽しみな僕。
子供のころから憧れていた小さな幸せに、ほっと心が癒されていきます。
ちょっぴり歴女な伊緒さんの、とっても温かい料理のお話。
「第1回ライト文芸大賞」大賞候補作品。
「エブリスタ」「カクヨム」「すずしろブログ」にも掲載中です!

十年目の結婚記念日
あさの紅茶
ライト文芸
結婚して十年目。
特別なことはなにもしない。
だけどふと思い立った妻は手紙をしたためることに……。
妻と夫の愛する気持ち。
短編です。
**********
このお話は他のサイトにも掲載しています

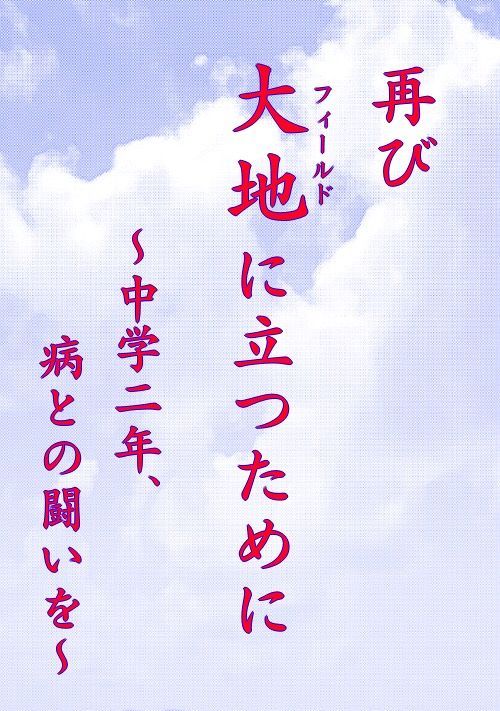
再び大地(フィールド)に立つために 〜中学二年、病との闘いを〜
長岡更紗
ライト文芸
島田颯斗はサッカー選手を目指す、普通の中学二年生。
しかし突然 病に襲われ、家族と離れて一人で入院することに。
中学二年生という多感な時期の殆どを病院で過ごした少年の、闘病の熾烈さと人との触れ合いを描いた、リアルを追求した物語です。
※闘病中の方、またその家族の方には辛い思いをさせる表現が混ざるかもしれません。了承出来ない方はブラウザバックお願いします。
※小説家になろうにて重複投稿しています。

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない
月島日向
ライト文芸
俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。
人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。
2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)
。
誰も俺に気付いてはくれない。そう。
2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。
もう、全部どうでもよく感じた。

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち
ヒロワークス
ライト文芸
女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。
クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。
それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。
そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!
その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。

セクスカリバーをヌキました!
桂
ファンタジー
とある世界の森の奥地に真の勇者だけに抜けると言い伝えられている聖剣「セクスカリバー」が岩に刺さって存在していた。
国一番の剣士の少女ステラはセクスカリバーを抜くことに成功するが、セクスカリバーはステラの膣を鞘代わりにして収まってしまう。
ステラはセクスカリバーを抜けないまま武闘会に出場して……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















