お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

私のいなくなった世界
タキテル
青春
人はいつか死ぬ。それは逃れられない定め――
ある日、有近樹。高校二年の女子校生は命を落とした。彼女は女子バスケ部のキャプテンに就任した日の事だった。十七歳で人生もこれからであり、輝かしい未来があるとその時は思っていた。しかし、ある帰り道に樹はゲームに夢中になっている男子小学生の姿を目撃する。男子小学生はゲームに夢中になり、周りが見えていなかった。その時、大型のトラックが男子小学生に襲いかかるのを見た樹は身を呈して食い止めようとする。気づいた時には樹は宙に浮いており、自分を擦る男子小学生の姿が目に写った。樹は錯覚した。自分は跳ねられて死亡してしまったのだと――。
そんな時、樹の前に謎の悪魔が現れた。悪魔は紳士的だが、どことなくドSだった。悪魔は樹を冥界に連れて行こうとするが、樹は拒否する。そこで悪魔は提案した。一ヶ月の期間と五回まで未練の手助けするチャンスを与えた。それが終わるまで冥界に連れて行くのを待つと。チャンスを与えられた樹はこの世の未練を晴らすべく自分の足跡を辿った。死んでも死にきれない樹は後悔と未練を無くす為、困難に立ちふさがる。そして、樹が死んだ後の世界は変わっていた。悲しむ者がいる中、喜ぶ者まで現れたのだ。死んでから気づいた自分の存在に困惑する樹。
樹が所属していた部活のギクシャクした関係――
樹に憧れていた後輩のその後――
樹の親友の大きな試練――
樹が助けた男児の思い――
人は死んだらどうなるのか? 地獄? 天国? それは死なないとわからない世界。残された者は何を思って何を感じるのか。
ヒロインが死んだ後の学校生活に起こった数々の試練を描いた青春物語が始まる。
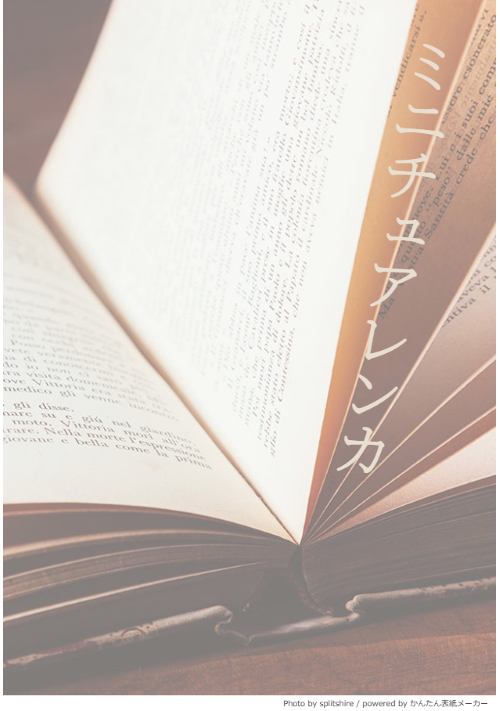
ミニチュアレンカ
白妙スイ@書籍&電子書籍発刊!
青春
電車通学をしている高校生の美雪(みゆき)には最近気になるひとがいた。乗っている間じゅう、スマホをずっと見つめている男子高校生。
いや、気になっているのは実のところ別のものである。
それは彼のスマホについている、謎のもの。
長方形で、薄くて、硬そうで、そして色のついた表面。
どうやらそれは『本』らしい。プラスチックでできた、ミニチュアの本。
スマホの中の本。
プラスチックの本。
ふたつが繋ぐ、こいのうた。

あの虹をもう一度 ~アカシック・ギフト・ストーリー~
花房こはる
青春
「アカシック・ギフト・ストーリー」シリーズ第8弾。
これは、実際の人の過去世(前世)を一つのストーリーとして綴った物語です。
多忙の父母の代わりに連は乳母に育てられた。その乳母も怪我がもとで田舎に帰ってしまう。
数年後、学校の長期休みを期に乳母の田舎へと向かう。
そこで出会った少年ジオと共に今まで経験したことのないたくさんのことを学ぶ。
歳月は流れ、いつしかそのジオとも連絡がつかなくなり・・・。

月夜の理科部
嶌田あき
青春
優柔不断の女子高生・キョウカは、親友・カサネとクラスメイト理系男子・ユキとともに夜の理科室を訪れる。待っていたのは、〈星の王子さま〉と呼ばれる憧れの先輩・スバルと、天文部の望遠鏡を売り払おうとする理科部長・アヤ。理科室を夜に使うために必要となる5人目の部員として、キョウカは入部の誘いを受ける。
そんなある日、知人の研究者・竹戸瀬レネから研究手伝いのバイトの誘いを受ける。月面ローバーを使って地下の量子コンピューターから、あるデータを地球に持ち帰ってきて欲しいという。ユキは二つ返事でOKするも、相変わらず優柔不断のキョウカ。先輩に贈る月面望遠鏡の観測時間を条件に、バイトへの協力を決める。
理科部「夜隊」として入部したキョウカは、夜な夜な理科室に来てはユキとともに課題に取り組んだ。他のメンバー3人はそれぞれに忙しく、ユキと2人きりになることも多くなる。親との喧嘩、スバルの誕生日会、1学期の打ち上げ、夏休みの合宿などなど、絆を深めてゆく夜隊5人。
競うように訓練したAIプログラムが研究所に正式採用され大喜びする頃には、キョウカは数ヶ月のあいだ苦楽をともにしてきたユキを、とても大切に思うようになっていた。打算で始めた関係もこれで終わり、と9月最後の日曜日にデートに出かける。泣きながら別れた2人は、月にあるデータを地球に持ち帰る方法をそれぞれ模索しはじめた。
5年前の事故と月に取り残された脳情報。迫りくるデータ削除のタイムリミット。望遠鏡、月面ローバー、量子コンピューター。必要なものはきっと全部ある――。レネの過去を知ったキョウカは迷いを捨て、走り出す。
皆既月食の夜に集まったメンバーを信じ、理科部5人は月からのデータ回収に挑んだ――。

この命が消えたとしても、きみの笑顔は忘れない
水瀬さら
青春
母を亡くし親戚の家で暮らす高校生の奈央は、友達も作らず孤独に過ごしていた。そんな奈央に「写真を撮らせてほしい」としつこく迫ってくる、クラスメイトの春輝。春輝を嫌っていた奈央だが、お互いを知っていくうちに惹かれはじめ、付き合うことになる。しかし突然、ふたりを引き裂く出来事が起きてしまい……。奈央は海にある祠の神様に祈り、奇跡を起こすが、それは悲しい別れのはじまりだった。
孤独な高校生たちの、夏休みが終わるまでの物語です。


彗星と遭う
皆川大輔
青春
【✨青春カテゴリ最高4位✨】
中学野球世界大会で〝世界一〟という称号を手にした。
その時、投手だった空野彗は中学生ながら152キロを記録し、怪物と呼ばれた。
その時、捕手だった武山一星は全試合でマスクを被ってリードを、打っては四番とマルチの才能を発揮し、天才と呼ばれた。
突出した実力を持っていながら世界一という実績をも手に入れた二人は、瞬く間にお茶の間を賑わせる存在となった。
もちろん、新しいスターを常に欲している強豪校がその卵たる二人を放っておく訳もなく。
二人の元には、多数の高校からオファーが届いた――しかし二人が選んだのは、地元埼玉の県立高校、彩星高校だった。
部員数は70名弱だが、その実は三年連続一回戦負けの弱小校一歩手前な崖っぷち中堅高校。
怪物は、ある困難を乗り越えるためにその高校へ。
天才は、ある理由で野球を諦めるためにその高校へ入学した。
各々の別の意思を持って選んだ高校で、本来会うはずのなかった運命が交差する。
衝突もしながら協力もし、共に高校野球の頂へ挑む二人。
圧倒的な実績と衝撃的な結果で、二人は〝彗星バッテリー〟と呼ばれるようになり、高校野球だけではなく野球界を賑わせることとなる。
彗星――怪しげな尾と共に現れるそれは、ある人には願いを叶える吉兆となり、ある人には夢を奪う凶兆となる。
この物語は、そんな彗星と呼ばれた二人の少年と、人を惑わす光と遭ってしまった人達の物語。
☆
第一部表紙絵制作者様→紫苑*Shion様《https://pixiv.net/users/43889070》
第二部表紙絵制作者様→和輝こころ様《https://twitter.com/honeybanana1》
第三部表紙絵制作者様→NYAZU様《https://skima.jp/profile?id=156412》
登場人物集です→https://jiechuandazhu.webnode.jp/%e5%bd%97%e6%98%9f%e3%81%a8%e9%81%ad%e3%81%86%e3%80%90%e7%99%bb%e5%a0%b4%e4%ba%ba%e7%89%a9%e3%80%91/

土俵の華〜女子相撲譚〜
葉月空
青春
土俵の華は女子相撲を題材にした青春群像劇です。
相撲が好きな美月が女子大相撲の横綱になるまでの物語
でも美月は体が弱く母親には相撲を辞める様に言われるが美月は母の反対を押し切ってまで相撲を続けてる。何故、彼女は母親の意見を押し切ってまで相撲も続けるのか
そして、美月は横綱になれるのか?
ご意見や感想もお待ちしております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















