7 / 36
共感覚について
しおりを挟む
「えっと、少しは知ってるみたいだけど改めて自己紹介? すると、周船寺唯です」
「俺は桔梗院柊」
二人は照れながら名前を言った。
二人は気まずさから、なかなか話題を切りだせずにいた。それが五分ほど続き、間の持たなくなった柊は先に話題を切りだそうと名前を呼ぶと。
「周船寺さん」
「桔梗院くん」
物の見事に言葉が被った。
唯は譲る気などないらしく、目に炎が灯っているんじゃないかと思わせるほど力が籠っていた。
唯は食い気味に。
「さ、先にいい?」
柊は、特に先に聞きたいと思うこともなかったので、
「い、いいよ?」
笑顔で返した。
唯はゆっくりと深呼吸をして心を落ち着かせているみたいだった。しばらくして、決心がついたようで、口を開く。
「私、性格とか感情を味として感じるの」
「それで味が! って言ってたのか」
柊は驚きのあまり、驚くことができなかった。
「うん……」
――でも、味で感じるって、どんな感覚なんだろう? 意外と便利そうだけど。
人の感情が分かれば、争いなど起きないのではないか。相手の気持ちを理解することができれば。
――それに、相手の感情や性格が分かるって、面白そう。
「便利そうだし、面白そうだね」
「本当にそう思う?」
「面白そう、だって、俺からしたらそれって不思議な感覚だからさ?」
「面白くなんかないよ」
急に唯は落ち込んだ表情を見せた。唯は弱弱しく言ったのだが、どこか凄みがあり、柊は喉を詰まらせてしまう。唯の見せた表情には楽しいことなど一度もなかったような――絶望。まさにそんな言葉が似合うような顔だった。
その表情を見た柊は、直ぐに冷静になって考えてみた。本当に面白いのかと。
――もし、本人の意思に反して感情を取り入れてしまうのなら?
取り入れたくない感情をも受け取ってしまうのなら。そう考えた柊は、面白いと思った考えを反転させた。
「ごめん、辛い……よね?」
故意に使えるのだとすれば、誰しもが欲しいと思うだろう。好きな人ができれば、自分に好意があるかを知りたい。それが、言葉を介さなくても得られるのだから。
けれど、それは逆に言えば、嫌われていれば言葉を介さずとも知り得ることができるということ。それが、もし意識とは反して情報を脳に送り込まれるのだとすれば。辛いなどでは到底言い表せない。
「嫌われてたら……分かるってことだよね?」
柊が確かめるように聞くと。
「分かるなんてもんじゃないよ」
「どういうこと?」
「他の人に向けられた感情も受け入れてしまうんだよ?」
唯が言ったことは、柊に嫌悪を抱いた人がいたとすれば、その感情もまるで自分に向けられているかのように感じるということ。
――面白い? 楽しそう? アホだろ、俺。
相手の感情が分かれば争いなど起きない、なんてことはない。むしろその逆。心で思うだけで口にはださない感情などいくらでもある。
それがもし全て伝わってくるのだとすれば、楽しいはずがない。
柊は話題を変えるように、
「どうして俺は周船寺さんからして味がしないんだ?」
返って来た言葉は、分からないだった。
性格や感情が味として感じる、というのならば、その味がしない自分とは何もない人間なのか? とも考えてみたけれど、性格は分からなくても、柊は感情があることだけは自信を持って言えた。
今、唯の話には興味が、好奇心があったから。
「俺って、周船寺さんにとっては性格なし、感情のない人間ってことになるの?」
確かめるように聞いてみたけれど、この答えも分からないだった。
今、唯が何を考えているかは本人にしか分からないけれど、初めて味のしない人に出会ったとすれば、怖いに尽きると柊は考えた。
今までなら直ぐに分かっていた、嫌われているのか、好かれているのか。それらが分からない。
感情を読み取って相手の考えを理解してきた唯にとって、言葉は信用にならないかもしれないけれど、それでも柊は伝えたかった。
「俺は周船寺さんのこと嫌いじゃないからね?」
昼休みに唯のことを気味悪がっていた人は数多くいたけれど、自分はそうじゃないのだと。
その言葉を信じたかどうか柊には分からないけれど、唯は顔を上げ、キョトンとて何度も目を瞬かせている。
「うん……」
信じてもらえたか分からいけれど、少しだけ元気を取り戻しているように思えた。
「よかったら、詳しく聞かせてほしいんだけど」
唯は何かを考えるような素振りを少しだけ見せたあと表情を固めて、
「さっきも言ったけど、性格とか感情を味として感じるの」
「うん」
「味だけじゃなく、温度、質感を脳が感じる共感覚を持ってるの」
――きょうかんかく……?
「その、きょうかんかくって……何?」
柊は眉を顰め、初めての言葉を聞いたかのように首を傾げた。
「えっと、代表的なのは文字、音、数、人に色が見える、数字が図形に見える……とか」
そういった類のことを、柊は以前にテレビで聞いたことがあり、そのときも楽しそう、面白そうと考えていた。
「テレビで見たことがある。計算が恐ろしく速い人とかだったような」
「うん。性格を色で感じるって人もいるらしいけど、私はそれが色じゃなくて味として感じる共感覚者」
そして、お互いに言葉をだせずに沈黙が訪れた。
唯が語ったような感覚がもし自分にもあればどう思うだろうかと柊は考えたけれど、想像もできなかった。
唯は不安にさいなまれたような顔をした後俯く。
共感覚者、分かりあえる人などいないと言い切ってもいい感覚を持った唯が、おそらく誰にも言ってこなかったであろう秘密を吐露してくれた。
それにどれほどの勇気が必要だったのか、正常な柊には到底理解できない。
「どうして味がしないか、だけど……田舎者だからかな?」
「え?」
柊は自分なりにどうして味がしないのかを考え、真剣に言ったつもりだったけれど、唯はただただ唖然としていた。
「そんなわけないじゃない」
「やっぱり?」
真面目に答えただけあって、まともに突っ込まれると気恥ずかしくなって顔が熱くなっていることが分かった。唯から顔を背けて、頭を掻いていると。
「そんなわけ、ないよ」
少し声が笑っているように思えた。
唯の顔を見てみると、少しだけ口角が上がっていた。
「やっと笑ってくれた」
「……?」
「さっきまでほんと死にそうな顔してたからこんな顔で。だから、良かった、笑ってくれて」
柊は唯の真似と、俯いていたときの、精気の感じられない表情をして少しだけ笑った。
その笑顔につられてか、唯も笑ってくれる。
「その、唯の共感覚って自分の意志で誰かの感情を感じることができるの?」
自分の意思で感じ取れるのなら、面白い、楽しいかもしれない。けど、全てを感じ取るなら真逆となる。
どんなふうに受け取っているのか、唯しかわからない。もしや、仮にということをなくすため、柊は聞いた。
「自分の意志とは関係なく起こるの。そこに、刺激……私の場合性格や感情? があれば」
性格や感情など、誰もが持ち合わせているもの。つまり、唯は常時何かしらの感情を味として脳が感じているということ。
柊のもし、といった考えは実に的を射ていた。
――そこに人がいれば何かしらを感じるってこと……だよな? 頭がおかしくなっても不思議じゃないんじゃないか? そんなのって。
「例えば……どんな風に? それと、この人がこんな味だとかって分かるの?」
味、温度、質感。どういった性格や感情のときにそれらを受け取るのか、また、それらを誰から感じ、区別することができるのか純粋に柊は興味があった。
「んー、性格だと……優しい人とかは甘く感じるし、嘘吐きはすごく苦い。感情の場合は、怒ってたら痛いくらい辛く感じるし、好奇心があれば酸っぱく感じる」
「すごく苦いってことは、少し苦いだとなにか違うの?」
「少しだったら臆病な人とか、内気な性格の人……かな?」
同じ味でも、強弱によって大きな違いがあるようにも繋がりがあるようにも思えた。
「もしかしてだけど、厳しい人とかって、少しだけ辛いとか?」
「厳しいっていうか、意地っ張りなのかな?」
柊は少しでも唯のことを理解しようとしてみたけれど、思い違いで終わる。
「温度だと、温かいのは情熱的だし、逆に冷たいのはそのまま冷たい人って感じかな? これは分かりやすいと思う」
イメージとしては、しっくりくるものだった。
「質感だけど、これはあんまり分かってないけど、驚いているときはチクチクと尖ったものが刺さってくるような感覚……かな?」
「実際にそれって舌で感じてるの?」
「舌っていうか、脳……なのかな?」
人間は舌で感じたものは大脳の味覚中枢に伝えられ、味として感じる。そう考えてしまえば、脳で感じていると言われても違和感は無かった。
舌を経由せずに脳へと味が送られる。
「それと、区別できるか、だよね?」
「うん」
「できるし、できない……かな?」
「どういうこと?」
柊は眉根を寄せて首を傾げて聞く。
すると、唯は立ち上がって、三メートルくらい離れたところまで歩いて止まった。
「……このくらいの距離で、人がそんなにいなかったら区別できる」
言い終わると椅子に戻ってきて、ゆっくりと腰を下ろした。
「一人くらいだったら五、六メートルくらいなら大丈夫……かな?」
唯は何かを考えるような顔をして、
「近くても、人が多すぎると誰が誰かは分からない。声みたいなものかな?」
「声?」
「うん。集会とかで皆がワイワイ騒いでいると、近くの人だと分かるけど、遠くの人だと分からないよね?」
身の回り程度なら正確に誰が喋ったかは分かる。分かるけれど、それは知り合いというときのこと。知り合いでもなければ、近くても誰が話したか分からないときもある。
耳を澄まさずとも、周囲の声や少し離れた声まで聞こえてくる。それは意志とは無関係に。
声を味に置き換えれば、唯がどんな世界を感じているのか、ほんの少し分かったような気がした。
「誰がどんな性格、感情を持っているか分からないけど、感じる……ってことか」
「そんなところだね。もう大分と慣れはしたけど」
「慣れって……」
唯は心配させないようなのか、ひきつりながらも笑顔を作ろうとしていた。
柊は、自分なりの考えを嘘偽りなく話そうと思った。勇気を持って話してくれた唯に少しでも今の感情を伝えたかったから。
「今までの話を聞いて、思ったことを言ってもいい?」
唯は無言で頷いた。
「俺には唯みたいな共感覚がないからあんまり分かんないんだけどさ。相手の気持ちが分からないことが普通だから、味を感じるっていうのが面白いって思ったんだ」
一呼吸置いてから。
「普通は相手のことなんて分からない。今周船寺さんがしっかり聞いているように見えるけど、実は今日の晩御飯何かなーとか考えてても俺には分からない」
「そんなこと考えてないよ!」
「例えばだって、例えば」
目付きを鋭くして怒る唯に、柊は少し笑って返した。また真剣な顔になって。
「分からないからこそ、相手のことを、相手の気持ちを理解しようって思うんだよ。こんなこと言われたら嫌だろうな、こんなこと言えば喜ぶだろうなって」
なかなかそんなことしてる人いないけど、と苦笑気味に付け加えた。
唯は真剣そうな眼差しで、押し黙って聞いてくれている。
「今、俺は周船寺さんがどんなこと思ってるか詳しくは分からないけど……」
柊は声のトーンを落として。
「怖いよね、俺のこと」
唯が口を開こうとしたので、それよりも早く柊は言葉を続ける。
「言わなくてもいいよ、きっと怖いはずだから」
――怖くないはずが無いんだよ、だって、今まで分かっていたことが急に分からなくなるんだから。
次に言う言葉を頭の中で考えると、少し気恥ずかしくなった柊は頭を掻いて気を紛らわせようとした。
「こんなこと言うの可笑しいかもしれないけどさ、怖いっていうのが普通なんだよ俺たちかしたら。人間って、相手のことが分からないから分かろうとするんだと思う」
なんか説教臭いよねと、付け加えて笑った。
柊は立ち上がり、後ろのポケットから財布を取りだす。
「何か飲み物いる?」
「いいよ、自分でだすから!」
唯は両手を開いて見せて拒んできた。
「さっきここに来る前、入口横の自動販売機をチラッと見たんだけどさ、変な物買っても知らないよ?」
柊は嫌な、悪だくみをしている笑みを唯に見せて、唯に財布を開かせないように仕向ける。
「俺は桔梗院柊」
二人は照れながら名前を言った。
二人は気まずさから、なかなか話題を切りだせずにいた。それが五分ほど続き、間の持たなくなった柊は先に話題を切りだそうと名前を呼ぶと。
「周船寺さん」
「桔梗院くん」
物の見事に言葉が被った。
唯は譲る気などないらしく、目に炎が灯っているんじゃないかと思わせるほど力が籠っていた。
唯は食い気味に。
「さ、先にいい?」
柊は、特に先に聞きたいと思うこともなかったので、
「い、いいよ?」
笑顔で返した。
唯はゆっくりと深呼吸をして心を落ち着かせているみたいだった。しばらくして、決心がついたようで、口を開く。
「私、性格とか感情を味として感じるの」
「それで味が! って言ってたのか」
柊は驚きのあまり、驚くことができなかった。
「うん……」
――でも、味で感じるって、どんな感覚なんだろう? 意外と便利そうだけど。
人の感情が分かれば、争いなど起きないのではないか。相手の気持ちを理解することができれば。
――それに、相手の感情や性格が分かるって、面白そう。
「便利そうだし、面白そうだね」
「本当にそう思う?」
「面白そう、だって、俺からしたらそれって不思議な感覚だからさ?」
「面白くなんかないよ」
急に唯は落ち込んだ表情を見せた。唯は弱弱しく言ったのだが、どこか凄みがあり、柊は喉を詰まらせてしまう。唯の見せた表情には楽しいことなど一度もなかったような――絶望。まさにそんな言葉が似合うような顔だった。
その表情を見た柊は、直ぐに冷静になって考えてみた。本当に面白いのかと。
――もし、本人の意思に反して感情を取り入れてしまうのなら?
取り入れたくない感情をも受け取ってしまうのなら。そう考えた柊は、面白いと思った考えを反転させた。
「ごめん、辛い……よね?」
故意に使えるのだとすれば、誰しもが欲しいと思うだろう。好きな人ができれば、自分に好意があるかを知りたい。それが、言葉を介さなくても得られるのだから。
けれど、それは逆に言えば、嫌われていれば言葉を介さずとも知り得ることができるということ。それが、もし意識とは反して情報を脳に送り込まれるのだとすれば。辛いなどでは到底言い表せない。
「嫌われてたら……分かるってことだよね?」
柊が確かめるように聞くと。
「分かるなんてもんじゃないよ」
「どういうこと?」
「他の人に向けられた感情も受け入れてしまうんだよ?」
唯が言ったことは、柊に嫌悪を抱いた人がいたとすれば、その感情もまるで自分に向けられているかのように感じるということ。
――面白い? 楽しそう? アホだろ、俺。
相手の感情が分かれば争いなど起きない、なんてことはない。むしろその逆。心で思うだけで口にはださない感情などいくらでもある。
それがもし全て伝わってくるのだとすれば、楽しいはずがない。
柊は話題を変えるように、
「どうして俺は周船寺さんからして味がしないんだ?」
返って来た言葉は、分からないだった。
性格や感情が味として感じる、というのならば、その味がしない自分とは何もない人間なのか? とも考えてみたけれど、性格は分からなくても、柊は感情があることだけは自信を持って言えた。
今、唯の話には興味が、好奇心があったから。
「俺って、周船寺さんにとっては性格なし、感情のない人間ってことになるの?」
確かめるように聞いてみたけれど、この答えも分からないだった。
今、唯が何を考えているかは本人にしか分からないけれど、初めて味のしない人に出会ったとすれば、怖いに尽きると柊は考えた。
今までなら直ぐに分かっていた、嫌われているのか、好かれているのか。それらが分からない。
感情を読み取って相手の考えを理解してきた唯にとって、言葉は信用にならないかもしれないけれど、それでも柊は伝えたかった。
「俺は周船寺さんのこと嫌いじゃないからね?」
昼休みに唯のことを気味悪がっていた人は数多くいたけれど、自分はそうじゃないのだと。
その言葉を信じたかどうか柊には分からないけれど、唯は顔を上げ、キョトンとて何度も目を瞬かせている。
「うん……」
信じてもらえたか分からいけれど、少しだけ元気を取り戻しているように思えた。
「よかったら、詳しく聞かせてほしいんだけど」
唯は何かを考えるような素振りを少しだけ見せたあと表情を固めて、
「さっきも言ったけど、性格とか感情を味として感じるの」
「うん」
「味だけじゃなく、温度、質感を脳が感じる共感覚を持ってるの」
――きょうかんかく……?
「その、きょうかんかくって……何?」
柊は眉を顰め、初めての言葉を聞いたかのように首を傾げた。
「えっと、代表的なのは文字、音、数、人に色が見える、数字が図形に見える……とか」
そういった類のことを、柊は以前にテレビで聞いたことがあり、そのときも楽しそう、面白そうと考えていた。
「テレビで見たことがある。計算が恐ろしく速い人とかだったような」
「うん。性格を色で感じるって人もいるらしいけど、私はそれが色じゃなくて味として感じる共感覚者」
そして、お互いに言葉をだせずに沈黙が訪れた。
唯が語ったような感覚がもし自分にもあればどう思うだろうかと柊は考えたけれど、想像もできなかった。
唯は不安にさいなまれたような顔をした後俯く。
共感覚者、分かりあえる人などいないと言い切ってもいい感覚を持った唯が、おそらく誰にも言ってこなかったであろう秘密を吐露してくれた。
それにどれほどの勇気が必要だったのか、正常な柊には到底理解できない。
「どうして味がしないか、だけど……田舎者だからかな?」
「え?」
柊は自分なりにどうして味がしないのかを考え、真剣に言ったつもりだったけれど、唯はただただ唖然としていた。
「そんなわけないじゃない」
「やっぱり?」
真面目に答えただけあって、まともに突っ込まれると気恥ずかしくなって顔が熱くなっていることが分かった。唯から顔を背けて、頭を掻いていると。
「そんなわけ、ないよ」
少し声が笑っているように思えた。
唯の顔を見てみると、少しだけ口角が上がっていた。
「やっと笑ってくれた」
「……?」
「さっきまでほんと死にそうな顔してたからこんな顔で。だから、良かった、笑ってくれて」
柊は唯の真似と、俯いていたときの、精気の感じられない表情をして少しだけ笑った。
その笑顔につられてか、唯も笑ってくれる。
「その、唯の共感覚って自分の意志で誰かの感情を感じることができるの?」
自分の意思で感じ取れるのなら、面白い、楽しいかもしれない。けど、全てを感じ取るなら真逆となる。
どんなふうに受け取っているのか、唯しかわからない。もしや、仮にということをなくすため、柊は聞いた。
「自分の意志とは関係なく起こるの。そこに、刺激……私の場合性格や感情? があれば」
性格や感情など、誰もが持ち合わせているもの。つまり、唯は常時何かしらの感情を味として脳が感じているということ。
柊のもし、といった考えは実に的を射ていた。
――そこに人がいれば何かしらを感じるってこと……だよな? 頭がおかしくなっても不思議じゃないんじゃないか? そんなのって。
「例えば……どんな風に? それと、この人がこんな味だとかって分かるの?」
味、温度、質感。どういった性格や感情のときにそれらを受け取るのか、また、それらを誰から感じ、区別することができるのか純粋に柊は興味があった。
「んー、性格だと……優しい人とかは甘く感じるし、嘘吐きはすごく苦い。感情の場合は、怒ってたら痛いくらい辛く感じるし、好奇心があれば酸っぱく感じる」
「すごく苦いってことは、少し苦いだとなにか違うの?」
「少しだったら臆病な人とか、内気な性格の人……かな?」
同じ味でも、強弱によって大きな違いがあるようにも繋がりがあるようにも思えた。
「もしかしてだけど、厳しい人とかって、少しだけ辛いとか?」
「厳しいっていうか、意地っ張りなのかな?」
柊は少しでも唯のことを理解しようとしてみたけれど、思い違いで終わる。
「温度だと、温かいのは情熱的だし、逆に冷たいのはそのまま冷たい人って感じかな? これは分かりやすいと思う」
イメージとしては、しっくりくるものだった。
「質感だけど、これはあんまり分かってないけど、驚いているときはチクチクと尖ったものが刺さってくるような感覚……かな?」
「実際にそれって舌で感じてるの?」
「舌っていうか、脳……なのかな?」
人間は舌で感じたものは大脳の味覚中枢に伝えられ、味として感じる。そう考えてしまえば、脳で感じていると言われても違和感は無かった。
舌を経由せずに脳へと味が送られる。
「それと、区別できるか、だよね?」
「うん」
「できるし、できない……かな?」
「どういうこと?」
柊は眉根を寄せて首を傾げて聞く。
すると、唯は立ち上がって、三メートルくらい離れたところまで歩いて止まった。
「……このくらいの距離で、人がそんなにいなかったら区別できる」
言い終わると椅子に戻ってきて、ゆっくりと腰を下ろした。
「一人くらいだったら五、六メートルくらいなら大丈夫……かな?」
唯は何かを考えるような顔をして、
「近くても、人が多すぎると誰が誰かは分からない。声みたいなものかな?」
「声?」
「うん。集会とかで皆がワイワイ騒いでいると、近くの人だと分かるけど、遠くの人だと分からないよね?」
身の回り程度なら正確に誰が喋ったかは分かる。分かるけれど、それは知り合いというときのこと。知り合いでもなければ、近くても誰が話したか分からないときもある。
耳を澄まさずとも、周囲の声や少し離れた声まで聞こえてくる。それは意志とは無関係に。
声を味に置き換えれば、唯がどんな世界を感じているのか、ほんの少し分かったような気がした。
「誰がどんな性格、感情を持っているか分からないけど、感じる……ってことか」
「そんなところだね。もう大分と慣れはしたけど」
「慣れって……」
唯は心配させないようなのか、ひきつりながらも笑顔を作ろうとしていた。
柊は、自分なりの考えを嘘偽りなく話そうと思った。勇気を持って話してくれた唯に少しでも今の感情を伝えたかったから。
「今までの話を聞いて、思ったことを言ってもいい?」
唯は無言で頷いた。
「俺には唯みたいな共感覚がないからあんまり分かんないんだけどさ。相手の気持ちが分からないことが普通だから、味を感じるっていうのが面白いって思ったんだ」
一呼吸置いてから。
「普通は相手のことなんて分からない。今周船寺さんがしっかり聞いているように見えるけど、実は今日の晩御飯何かなーとか考えてても俺には分からない」
「そんなこと考えてないよ!」
「例えばだって、例えば」
目付きを鋭くして怒る唯に、柊は少し笑って返した。また真剣な顔になって。
「分からないからこそ、相手のことを、相手の気持ちを理解しようって思うんだよ。こんなこと言われたら嫌だろうな、こんなこと言えば喜ぶだろうなって」
なかなかそんなことしてる人いないけど、と苦笑気味に付け加えた。
唯は真剣そうな眼差しで、押し黙って聞いてくれている。
「今、俺は周船寺さんがどんなこと思ってるか詳しくは分からないけど……」
柊は声のトーンを落として。
「怖いよね、俺のこと」
唯が口を開こうとしたので、それよりも早く柊は言葉を続ける。
「言わなくてもいいよ、きっと怖いはずだから」
――怖くないはずが無いんだよ、だって、今まで分かっていたことが急に分からなくなるんだから。
次に言う言葉を頭の中で考えると、少し気恥ずかしくなった柊は頭を掻いて気を紛らわせようとした。
「こんなこと言うの可笑しいかもしれないけどさ、怖いっていうのが普通なんだよ俺たちかしたら。人間って、相手のことが分からないから分かろうとするんだと思う」
なんか説教臭いよねと、付け加えて笑った。
柊は立ち上がり、後ろのポケットから財布を取りだす。
「何か飲み物いる?」
「いいよ、自分でだすから!」
唯は両手を開いて見せて拒んできた。
「さっきここに来る前、入口横の自動販売機をチラッと見たんだけどさ、変な物買っても知らないよ?」
柊は嫌な、悪だくみをしている笑みを唯に見せて、唯に財布を開かせないように仕向ける。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

米国海軍日本語情報将校ドナルド・キーン
ジユウ・ヒロヲカ
青春
日本と米国による太平洋戦争が始まった。米国海軍は大急ぎで優秀な若者を集め、日本語を読解できる兵士の大量育成を開始する。後の日本文化研究・日本文学研究の世界的権威ドナルド・キーンも、その時アメリカ海軍日本語学校に志願して合格した19歳の若者だった。ドナルドの冒険が始まる。

夏の抑揚
木緒竜胆
青春
1学期最後のホームルームが終わると、夕陽旅路は担任の蓮樹先生から不登校のクラスメイト、朝日コモリへの届け物を頼まれる。
夕陽は朝日の自宅に訪問するが、そこで出会ったのは夕陽が知っている朝日ではなく、幻想的な雰囲気を纏う少女だった。聞くと、少女は朝日コモリ当人であるが、ストレスによって姿が変わってしまったらしい。
そんな朝日と夕陽は波長が合うのか、夏休みを二人で過ごすうちに仲を深めていくが。


通学路
南いおり
青春
幼なじみの瀬川一華と野上哲也は中学生の頃から付き合っている。高校3年生になる直前の春休みにある事件が起こる。そのことが2人の歯車を狂わせ始めた。
私が執筆している、「通学路の秘密」の別バージョンです。

hypocrisy[偽善]
calm
青春
白牙 銀 (びゃくが ぎん)
今作の主人公。
引きこもったせいで弱々しい語りになってしまったが、元々の根はしっかりとしている。
ある出来事がきっかけで登校拒否になってしまった。
金剛 魁真 (こんごう かいま)
主人公の数少ない友人。
主人公のことを心配しているが、なかなか誘い出せないことに少しやきもきしている。
主人公の身内以外で唯一、主人公の登校拒否の理由を知っている。
明るい性格だが、たまに闇に墜ちる。
真川 琥珀 (さながわ こはく)
主人公や金剛のクラスの学級委員。
はっきりと物を言う性格で、なよなよと部屋にこもっている主人公にイライラしている。
しかし、優しいところもあるようで、金剛からは「ツンデレ」と言われている。
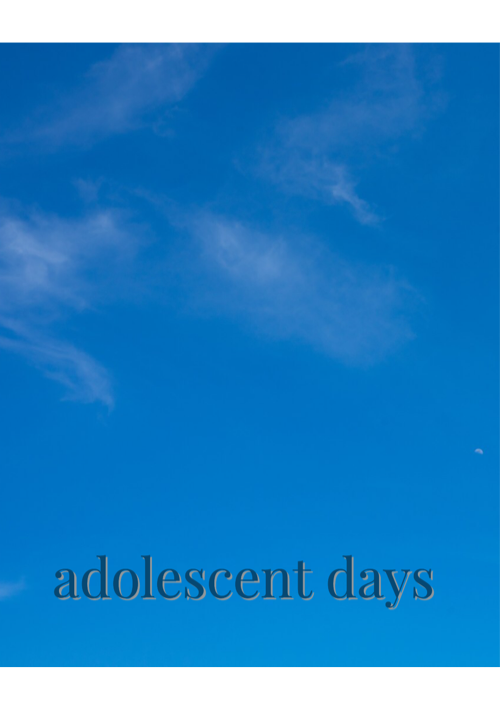
adolescent days
wasabi
青春
これは普通の僕が普通では無くなる話
2320年
あらゆる生活にロボット、AIが導入され人間の仕事が急速に置き換わる時代。社会は多様性が重視され、独自性が評価される時代となった。そんな時代に将来に不安を抱える僕(鈴木晴人(すずきはると))は夏休みの課題に『自分にとって特別な何かをする』という課題のレポートが出される。特別ってなんだよ…そんなことを胸に思いながら歩いていると一人の中年男性がの垂れていた…

不自由ない檻
志賀雅基
青春
◆広さに溺れて窒息する/隣人は与えられすぎ/鉄格子の隙間も見えない◆
クラスの女子の援助交際を真似し始めた男子高校生の日常……と思いきや、タダの日常という作者の目論見は外れました。事件を起こした主人公にとって化学の講師がキィパーソン。初期型ランクルに乗る三十男。特許貸しでカネに困っていない美味しい設定。しかしストーリーはエピグラフ通りのハード進行です。
更新は気の向くままでスミマセン。プロットも無いですし(!)。登場人物は勝手に動くわ、どうなるんでしょうかねえ? まあ、究極にいい加減ですが書く際はハッピーエンドを信じて綴る所存にて。何故なら“彼ら”は俺自身ですから。
【エブリスタ・ノベルアップ+にも掲載】

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















