10 / 30
3.二度と前には進めない
3-①
しおりを挟む
「もうすっかり秋ねえ」
恵美子さんが、ショーケースのなかを見ながらため息をついた。夏のあいだひんやりとした光を放っていた水ようかんや、本物の葛を使っているのが売りのあんみつが消えて、栗まんじゅうやもみじの形をした練りきりがあたたかな色味をまとって、そこでお客さんを待っていた。
「そうですね」
このごろ急に空気が乾燥したからか、答える声がのどに張りついた。軽く咳払いをして、不快感を拭う。不調の芽みたいなものが、のどの奥にひそんでいる予感が、最近ずっと離れない。
「年取ると時間が経つのがあっというまだわあ。まゆちゃんはまだ若いから、毎日充実してるでしょお」
背をぽんぽん叩かれるけれど、返事をするのすら億劫だった。
わたしの生活の、どこが充実しているというのだろう。週の半分を雪深堂で過ごし、ショッピングモールのフードコートで真登と食事をし、残りの半分は家でじっと息をひそめているわたしの生活の、どこが充実しているのだろう。
「最近急に冷えてきたけど、寒くない? エアコン入れようか、それともちっちゃいストーブいるかしらあ」
「いいえ、ちょうどいいです」
何十回、何百回も交わした会話を、恵美子さんは昔を忘れてしまったひとみたいにくり返す。わたしも、いろんなことを忘れて、なにもわからないひとになれたらいいのに。
「いらっしゃいませ」
店のまえに自転車が止まり、恵美子さんくらいの年の女性がゆっくりとのれんから顔を覗かせた。
「いらっしゃいませえ、あらあ、近藤さん」
いつもありがとうございますう、と恵美子さんが頭をさげる。わたしもよく知っている、雪深堂の常連だ。背が低く、下からうかがうように目を合わせるのが癖で、いやらしい笑いかたと町のうわさ話ばかりしていくのが気持ち悪くて、苦手なひとだった。
「おまんじゅうを十個ね、包んでほしいの。これからひとがくるもんで」
近藤さんはわたしの姿なんて見えてないみたいに、真正面にいるわたしではなく、恵美子さんに声をかけた。恵美子さんも、動こうとしたわたしを制して、おまんじゅうをショーケースから取りだす。
手持無沙汰だった。無視された手前、会話の糸口もない。普段ならおしゃべりな近藤さんも、かばんの持ち手で重ねた指先でゆっくりとリズムを刻んでいる。完全に、わたしの存在が透明になる。店内には近藤さんの鼻唄とも呼吸とも取れる音と、恵美子さんがおまんじゅうを包む紙のこすれが響いていた。
また、のどに不快感を覚える。うつむいてこほん、とひとつ咳をして顔をあげると、近藤さんと目が合った。瞬間、近藤さんがちいさく笑ったのがわかった。
「まゆちゃん、だったわよね。それ、彼氏から?」
下品な笑みだった。ふっくらした指をあげ、つつく。とっさに身体が動揺に飲まれそうになって、顔がひきつった。咳を抑えたわたしの右の薬指には、真登からもらった指輪がある。
「……はい、そうです」
「まあ、いいわね!」
「あらあ、まゆちゃん、そうなのお」
ごまかせなかった自分を、ひどく後悔した。紙袋を手にした恵美子さんが、会話に交じってきたからだ。
「宮下自動車のうちの子でしょお」
「あら、あそこひとりっ子じゃなかった? 跡取り息子とつきあってるなんていいわね」
話がレールに乗ってしまった。この町独特の文法で、やりとりがつづく。
「でもあそこたしか中退じゃなかった? まだ早いわよね」
「そんなこと言ったらまゆちゃんも中退だものねえ。まだまだよねえ」
よけいな情報が、またよけいな情報を連れてくる。もう、その場にいるわたしの存在は関係なかった。ただ、薄笑いを浮かべて立っているだけだ。
「まゆちゃんもそうなの? じゃあちゃんとお仕事しなきゃ」
「そんなあ、宮下さんの子はちゃんとおうち継ぐんでしょうから、仕事なんてしなくてもいいのよお。女は家を守るのが役目なんだからあ」
「そうね、わたしたちもそうしてきたんだもの、それが女の仕事よ」
耳にべったりと張りつく恵美子さんの声と、ぬらぬらとした近藤さんの笑顔が、わたしの周囲を埋め尽くし迫ってくる。息が、できない。
「あの!」
おおきな声を出したわたしに、ふたりが驚いたように身体を縮めた。怒りか、哀しみか、正体のわからない感情で指が震える。肩で息をしているのがわかった。
「……具合悪いので、帰ってもいいですか」
言いわけのつもりだったけれど、ほんとうだった。悪寒がする。顔が腫れぼったくて、目をうまく開けていられない。
「ほんとだ、まゆちゃん、顔が真っ赤よ」
「帰って帰ってえ。うちは大丈夫だからあ」
ありがとうございます、を口のなかだけで言いながら、奥の廊下へと足を踏みだす。背後で聞きとれない音量で交わされるひそひそ話をしているのがわかったけれど、いまはとにかく、この場所から逃げたかった。ここから逃げだしたところで、いく場所なんてないのだけれど。
店に戻ると、近藤さんはいなかった。さっきほどいたばかりの髪が、まだ重力に抗っていて頭が痛い。
「おつかれさまでした」
お辞儀をして、ガラス戸を抜ける。後ろから追いかけてくる恵美子さんの「あったかくして寝るのよお」の声は、聞こえないふりをした。雪深堂を出てすぐ、指輪をはずしてお財布にしまった。いまはどうしても、つけていることができなかった。
商店街を歩いていると、アーケードの屋根に押しこめられた風が、勢いを持ってえりあしをさらっていく。朝はすこしも寒くなかったのに、いまは身体の表面をさすられているような寒気が、風が吹くたびに襲ってきた。
そういえば、恵美子さんから言われたのではなく、自分から仕事を早退したのははじめてだった。仮病を使ったわけじゃないのに、自分の意志で早く帰るなんて、まるで高校を辞める直前のころみたいで、気分が悪い。高校に通っていたときのことなんて、ずっと忘れていた。
その瞬間を最悪だと思った日のことも、こんなに簡単にひとは忘れてしまうのだ。だとしたらわたしはいったい、何百回何千回の「最悪」を味わえば済むのだろう。
真登は、いま、このときも働いている。高校にいたときよりもずっと生き生きと、一生懸命に自分のやるべきことに向きあっている。高校を中退していることなんて関係ないと胸を張れるくらい、まっとうに生きている。
わたしは、そんな真登と並び立つことはできない。
身体が重い。足を引きずるように歩いて、あの夏の日、ひと目見た里恵ちゃんの姿を思いだす。ぬいぐるみみたいにふんわりしていた里恵ちゃんのシルエットが、綿がしぼんでしまったみたいに不自然に細くなっていた。彼女はあんなになっても働いている。わたしみたいに、ちょっと気分が悪いからって仕事を早く抜けたりしない。
情けない。ぎしぎしと心が軋んで、からっぽの胸に音を立てる。トートバッグのなかの辞書が、いつもより重い。
もういやだ、もう、いやだ。
立っていられない。道端にうずくまりそうになったときだった。カーディガンのポケットに入れたスマートフォンが、ヴヴヴと震える。
真登の動物的勘はこんなときにでも発揮されるのかと、恐るおそるメッセージを確認した。
『まゆ、久しぶり。今日は仕事? これから会えないかな』
文末に添えられたクマの絵文字を見て、目をつぶり、もう一度見る。彼女が好んで使う、彼女そっくりの絵文字だ。信じられなかった。差出人は、里恵ちゃんだった。返信する内容を考える時間ももったいないと思った。手のなかから滑り落としそうになりながら、スマートフォンを操作する。
『まゆ?』
「り、里恵ちゃん」
まぎれもない、里恵ちゃんの声だった。里恵ちゃんとの電話は久しぶりだった。声を聞いたのは、いったいいつが最後だっただろう。
『なあに、また泣いてるの』
「ううん、泣いてない」
里恵ちゃんが、たのしそうに笑っていた。夏の盛り、そっと盗み見た彼女のようすからは、想像できない笑いかただった。
『それで、これから会えるかな』
「うん、会いたい」
電話に乗った声が自分でもおどろくくらい切実な色を帯びていて、また里恵ちゃんが電波の向こうで笑った。ずっと会いたかった。「高校辞めちゃった」と報告をした、まだ浅い春のころ。それきり里恵ちゃんとは顔を合わせていない。
『じゃあ、一時間後に迎えにいくね』
そう言って、里恵ちゃんはきっかり一時間後に家まで迎えにきてくれた。彼女が大切に乗っている、まんまるな軽のブラウン。そしてその運転席に乗る里恵ちゃんのあたたかな笑顔を見た瞬間に、涙がこぼれそうになった。
「元気だった?」
乗るやいなや、里恵ちゃんが「昨日はなに食べた?」くらいの、とても軽い調子で口を開いた。訊きたいのはわたしのほうだ。シートベルトを締める手を止めて、運転席に身を乗りだす。
「里恵ちゃん、最近はつかれてない? ちゃんと食べてる?」
エネルギーに満ちた表情から、その心配はないとわかっていたけれど、訊かずにはいられなかった。
やっぱり知ってたか、と眉をさげ、里恵ちゃんはすぐに笑った。
「もう大丈夫。心配かけてごめんね。それもね、着いたら話すね」
うん、と返事をして、わたしはよろこびに胸が張り裂けそうだった。うれしければ笑い、哀しければ泣き、腹が立てば怒る彼女の、人形のようになってしまった顔がちらつく。こわくて遠ざけていた、里恵ちゃんの元通りの姿に浮かれた。そして元気になったようすを、わたしに見せたいと思ってくれたのだということに浮足立った。自分の体調が悪いことなんて、すっかり忘れていた。
助手席に乗りこんで、わたしは里恵ちゃんの横顔ばかり見ていた。おでこ、鼻先、そしてあごをつなぐやわらかな線が、秋の透き通った陽射しに負けずひかりを放つ。
里恵ちゃんが車を止めたのは、尾板のはずれにあるちいさな喫茶店だった。古い家屋が多いこの町ではめずらしいログハウス造りで、少ないながらもお客さんが途切れることのないお店だった。里恵ちゃんとも、真登とも、よく訪れる馴染みの場所だ。
車を降りると、空気がずいぶん冷えていた。忘れていた悪寒が背筋を襲い、くしゃみが出る。
「寒い? 早くはいろ」
店の主人は顔見知りの女性で、笑顔とともに迎え入れてくれた。店内は木材独特の香りであたたかく、ドア一枚隔てただけなのに、尾板の町じゃないみたいだった。
テーブル席につき、里恵ちゃんはカフェオレ、わたしはロイヤルミルクティーを注文する。ふたりいっしょに、焼きたてのワッフルも頼んだ。バニラのアイスクリームが乗ったさくさくのワッフルにナイフを入れ、口に運ぶ。あたたかい部屋で、冷たいアイスと熱々のワッフルを食べる背徳的な状況が気持ちいい。
「それでね、今日はまゆに話があるの」
聴いてくれる? と、ロイヤルミルクティーに口をつけるわたしに里恵ちゃんは言った。里恵ちゃんの頼んだカフェオレからも、ゆっくりと湯気がのぼっている。窓ガラスの向こうに広がる、収穫を待つ育ちきった稲のひかりを背負った里恵ちゃんがひどくうつくしくて、彼女の姿を表現することばをいますぐ辞書で調べたいと思った。
「うん、もちろん、聴かせて」
「ありがとう」
里恵ちゃんの声は、乾いていてすこしくすんだ水色をしている。細かい糸が絡まった、かさかさしたわたあめみたいだと思う。食べたことがなくてもわかる。あんまり甘ったるくなくて、たしかに噛んだ感触があったのに、気づいたら忘れてしまうほどさらりと口のなかで溶けていくはかない味がするのだ。
わたしはそのわたあめを、もう二度と食べることができない高級なお菓子を食べる気持ちで口に含み、味わう。さらりと甘い、里恵ちゃんの声。
すう、とひとつ息を吸って、里恵ちゃんは緊張した面持ちで声を発した。
「わたしね、結婚するの」
甘さに浸っていた頭から、いっさいの五感が消えたのがわかった。
「体調を崩してたときに、ずっとそばにいてくれたひとでね」
地面が木の床から砂地に変わり、芸術家の描いた時計のように視界が歪んだ。
「あのときの姿見られてたら、もうなにもこわくないかなあって」
わたしがことばを飲みこめていないのも知らず、里恵ちゃんはどんどんことばを紡ぐ。
「こんな気持ちになるの、生まれてはじめてなの」
頭が真っ白。身を切られる思い。表現としては知っていたことばの意味を、わたしも「生まれてはじめて」、痛いほど理解した。
「言えてよかった。まゆがいちばん大事だから、いちばんに伝えたかったの」
かきあげたえりあしから伸びるうなじを光に晒して、里恵ちゃんはそう言って笑った。コーラルピンクの唇が、すっとやさしげな弧を描く。その左薬指に指輪がはまっていることに、いま、はじめて気づいた。
踏ん張ろうと力を入れても、足の下からどんどん砂が流れ出ていって、まっすぐ座っていることができない。目のまえのカップに入ったロイヤルミルクティーの水面がゆらゆらと不規則に揺れて、目を閉じても気分が悪い。足元にそっと寄り添う店内のあたたかさも、いまは不快だった。そのまま、さっき飲みこんだワッフルと、だれにも秘密にしていたことばを吐きだしてしまいたい衝動に駆られる。この不安定な世界で、わたしの人生なんて終わってしまえばいいと思った。
知りたくなかった。それ以外の感情が、浮かんでこなかった。
湧きあがる吐き気に耐えきれず、口元を手で覆う。
「やだ、うれしいけど泣かないで」
ちがう。泣いてなんかいない。ちがう。いますぐにでも泣いてしまいそうだ。ただただ、驚きに身体が、心がついていかない。
やっぱり、わたしは正しくないから、罰が当たったのだ。まっとうに生きていないから、歩む道を正されたんだ。
その瞬間、次にとるべき行動を、動かない脳みそを一生懸命動かして、いくつもいくつも考えた。聞こえるはずがないパソコンのハードディスクが回るときみたいな音さえ、耳に届く気がする。
身体を起こし、里恵ちゃんをまっすぐに見つめる。戸惑ったようすでも、すでにだれかのものになっていても、彼女はやはりきれいで、わたしのヒーローである里恵ちゃんのままだった。
「……そっか、そうなんだ。知らなかった」
そう言う以外に、なんと言えばよかったのだろう。伝えたいことばはたくさんあった。でもわたししか知らない秘密をことばにしてしまったら、それはだれかにとってのほんとうになってしまう。
「ずっと黙っててごめんね。ちゃんと決まるまでは待ちたくて。でも、まゆにいちばんに教えたのはほんとだよ」
里恵ちゃんが胸のまえで両手を合わせ、祈るように目を閉じてほほえんだ。その姿があまりにきれいで、もし目のまえの里恵ちゃんが絵画なら、キャンバスごと引き裂いてしまいたいと思った。
わたしのことが「いちばん大事」だと言うのに、里恵ちゃんはわたしを選んではくれなかった。選ばれないのなら、いちばんになんてなりたくなかった。「いちばん」だなんて、気休めを聞きたくなかった。
背もたれとのあいだに挟んだかばんの、お財布をつよく握る。どうしてみんな、自分のいちばんが誰かなんて、簡単に口にできるのだろう。わたしみたいに間違っていないからだろうか、それとも、わたしみたいに重く鈍った想いじゃないからだろうか。
里恵ちゃんが、身体を壊していたことが真実とは思えない笑顔で、たのしそうに話している。ずっと会って話したかったのに、わたしはすっかり冷めたワッフルを口に運びながら、うわの空で相槌を打つことしかできなかった。
恵美子さんが、ショーケースのなかを見ながらため息をついた。夏のあいだひんやりとした光を放っていた水ようかんや、本物の葛を使っているのが売りのあんみつが消えて、栗まんじゅうやもみじの形をした練りきりがあたたかな色味をまとって、そこでお客さんを待っていた。
「そうですね」
このごろ急に空気が乾燥したからか、答える声がのどに張りついた。軽く咳払いをして、不快感を拭う。不調の芽みたいなものが、のどの奥にひそんでいる予感が、最近ずっと離れない。
「年取ると時間が経つのがあっというまだわあ。まゆちゃんはまだ若いから、毎日充実してるでしょお」
背をぽんぽん叩かれるけれど、返事をするのすら億劫だった。
わたしの生活の、どこが充実しているというのだろう。週の半分を雪深堂で過ごし、ショッピングモールのフードコートで真登と食事をし、残りの半分は家でじっと息をひそめているわたしの生活の、どこが充実しているのだろう。
「最近急に冷えてきたけど、寒くない? エアコン入れようか、それともちっちゃいストーブいるかしらあ」
「いいえ、ちょうどいいです」
何十回、何百回も交わした会話を、恵美子さんは昔を忘れてしまったひとみたいにくり返す。わたしも、いろんなことを忘れて、なにもわからないひとになれたらいいのに。
「いらっしゃいませ」
店のまえに自転車が止まり、恵美子さんくらいの年の女性がゆっくりとのれんから顔を覗かせた。
「いらっしゃいませえ、あらあ、近藤さん」
いつもありがとうございますう、と恵美子さんが頭をさげる。わたしもよく知っている、雪深堂の常連だ。背が低く、下からうかがうように目を合わせるのが癖で、いやらしい笑いかたと町のうわさ話ばかりしていくのが気持ち悪くて、苦手なひとだった。
「おまんじゅうを十個ね、包んでほしいの。これからひとがくるもんで」
近藤さんはわたしの姿なんて見えてないみたいに、真正面にいるわたしではなく、恵美子さんに声をかけた。恵美子さんも、動こうとしたわたしを制して、おまんじゅうをショーケースから取りだす。
手持無沙汰だった。無視された手前、会話の糸口もない。普段ならおしゃべりな近藤さんも、かばんの持ち手で重ねた指先でゆっくりとリズムを刻んでいる。完全に、わたしの存在が透明になる。店内には近藤さんの鼻唄とも呼吸とも取れる音と、恵美子さんがおまんじゅうを包む紙のこすれが響いていた。
また、のどに不快感を覚える。うつむいてこほん、とひとつ咳をして顔をあげると、近藤さんと目が合った。瞬間、近藤さんがちいさく笑ったのがわかった。
「まゆちゃん、だったわよね。それ、彼氏から?」
下品な笑みだった。ふっくらした指をあげ、つつく。とっさに身体が動揺に飲まれそうになって、顔がひきつった。咳を抑えたわたしの右の薬指には、真登からもらった指輪がある。
「……はい、そうです」
「まあ、いいわね!」
「あらあ、まゆちゃん、そうなのお」
ごまかせなかった自分を、ひどく後悔した。紙袋を手にした恵美子さんが、会話に交じってきたからだ。
「宮下自動車のうちの子でしょお」
「あら、あそこひとりっ子じゃなかった? 跡取り息子とつきあってるなんていいわね」
話がレールに乗ってしまった。この町独特の文法で、やりとりがつづく。
「でもあそこたしか中退じゃなかった? まだ早いわよね」
「そんなこと言ったらまゆちゃんも中退だものねえ。まだまだよねえ」
よけいな情報が、またよけいな情報を連れてくる。もう、その場にいるわたしの存在は関係なかった。ただ、薄笑いを浮かべて立っているだけだ。
「まゆちゃんもそうなの? じゃあちゃんとお仕事しなきゃ」
「そんなあ、宮下さんの子はちゃんとおうち継ぐんでしょうから、仕事なんてしなくてもいいのよお。女は家を守るのが役目なんだからあ」
「そうね、わたしたちもそうしてきたんだもの、それが女の仕事よ」
耳にべったりと張りつく恵美子さんの声と、ぬらぬらとした近藤さんの笑顔が、わたしの周囲を埋め尽くし迫ってくる。息が、できない。
「あの!」
おおきな声を出したわたしに、ふたりが驚いたように身体を縮めた。怒りか、哀しみか、正体のわからない感情で指が震える。肩で息をしているのがわかった。
「……具合悪いので、帰ってもいいですか」
言いわけのつもりだったけれど、ほんとうだった。悪寒がする。顔が腫れぼったくて、目をうまく開けていられない。
「ほんとだ、まゆちゃん、顔が真っ赤よ」
「帰って帰ってえ。うちは大丈夫だからあ」
ありがとうございます、を口のなかだけで言いながら、奥の廊下へと足を踏みだす。背後で聞きとれない音量で交わされるひそひそ話をしているのがわかったけれど、いまはとにかく、この場所から逃げたかった。ここから逃げだしたところで、いく場所なんてないのだけれど。
店に戻ると、近藤さんはいなかった。さっきほどいたばかりの髪が、まだ重力に抗っていて頭が痛い。
「おつかれさまでした」
お辞儀をして、ガラス戸を抜ける。後ろから追いかけてくる恵美子さんの「あったかくして寝るのよお」の声は、聞こえないふりをした。雪深堂を出てすぐ、指輪をはずしてお財布にしまった。いまはどうしても、つけていることができなかった。
商店街を歩いていると、アーケードの屋根に押しこめられた風が、勢いを持ってえりあしをさらっていく。朝はすこしも寒くなかったのに、いまは身体の表面をさすられているような寒気が、風が吹くたびに襲ってきた。
そういえば、恵美子さんから言われたのではなく、自分から仕事を早退したのははじめてだった。仮病を使ったわけじゃないのに、自分の意志で早く帰るなんて、まるで高校を辞める直前のころみたいで、気分が悪い。高校に通っていたときのことなんて、ずっと忘れていた。
その瞬間を最悪だと思った日のことも、こんなに簡単にひとは忘れてしまうのだ。だとしたらわたしはいったい、何百回何千回の「最悪」を味わえば済むのだろう。
真登は、いま、このときも働いている。高校にいたときよりもずっと生き生きと、一生懸命に自分のやるべきことに向きあっている。高校を中退していることなんて関係ないと胸を張れるくらい、まっとうに生きている。
わたしは、そんな真登と並び立つことはできない。
身体が重い。足を引きずるように歩いて、あの夏の日、ひと目見た里恵ちゃんの姿を思いだす。ぬいぐるみみたいにふんわりしていた里恵ちゃんのシルエットが、綿がしぼんでしまったみたいに不自然に細くなっていた。彼女はあんなになっても働いている。わたしみたいに、ちょっと気分が悪いからって仕事を早く抜けたりしない。
情けない。ぎしぎしと心が軋んで、からっぽの胸に音を立てる。トートバッグのなかの辞書が、いつもより重い。
もういやだ、もう、いやだ。
立っていられない。道端にうずくまりそうになったときだった。カーディガンのポケットに入れたスマートフォンが、ヴヴヴと震える。
真登の動物的勘はこんなときにでも発揮されるのかと、恐るおそるメッセージを確認した。
『まゆ、久しぶり。今日は仕事? これから会えないかな』
文末に添えられたクマの絵文字を見て、目をつぶり、もう一度見る。彼女が好んで使う、彼女そっくりの絵文字だ。信じられなかった。差出人は、里恵ちゃんだった。返信する内容を考える時間ももったいないと思った。手のなかから滑り落としそうになりながら、スマートフォンを操作する。
『まゆ?』
「り、里恵ちゃん」
まぎれもない、里恵ちゃんの声だった。里恵ちゃんとの電話は久しぶりだった。声を聞いたのは、いったいいつが最後だっただろう。
『なあに、また泣いてるの』
「ううん、泣いてない」
里恵ちゃんが、たのしそうに笑っていた。夏の盛り、そっと盗み見た彼女のようすからは、想像できない笑いかただった。
『それで、これから会えるかな』
「うん、会いたい」
電話に乗った声が自分でもおどろくくらい切実な色を帯びていて、また里恵ちゃんが電波の向こうで笑った。ずっと会いたかった。「高校辞めちゃった」と報告をした、まだ浅い春のころ。それきり里恵ちゃんとは顔を合わせていない。
『じゃあ、一時間後に迎えにいくね』
そう言って、里恵ちゃんはきっかり一時間後に家まで迎えにきてくれた。彼女が大切に乗っている、まんまるな軽のブラウン。そしてその運転席に乗る里恵ちゃんのあたたかな笑顔を見た瞬間に、涙がこぼれそうになった。
「元気だった?」
乗るやいなや、里恵ちゃんが「昨日はなに食べた?」くらいの、とても軽い調子で口を開いた。訊きたいのはわたしのほうだ。シートベルトを締める手を止めて、運転席に身を乗りだす。
「里恵ちゃん、最近はつかれてない? ちゃんと食べてる?」
エネルギーに満ちた表情から、その心配はないとわかっていたけれど、訊かずにはいられなかった。
やっぱり知ってたか、と眉をさげ、里恵ちゃんはすぐに笑った。
「もう大丈夫。心配かけてごめんね。それもね、着いたら話すね」
うん、と返事をして、わたしはよろこびに胸が張り裂けそうだった。うれしければ笑い、哀しければ泣き、腹が立てば怒る彼女の、人形のようになってしまった顔がちらつく。こわくて遠ざけていた、里恵ちゃんの元通りの姿に浮かれた。そして元気になったようすを、わたしに見せたいと思ってくれたのだということに浮足立った。自分の体調が悪いことなんて、すっかり忘れていた。
助手席に乗りこんで、わたしは里恵ちゃんの横顔ばかり見ていた。おでこ、鼻先、そしてあごをつなぐやわらかな線が、秋の透き通った陽射しに負けずひかりを放つ。
里恵ちゃんが車を止めたのは、尾板のはずれにあるちいさな喫茶店だった。古い家屋が多いこの町ではめずらしいログハウス造りで、少ないながらもお客さんが途切れることのないお店だった。里恵ちゃんとも、真登とも、よく訪れる馴染みの場所だ。
車を降りると、空気がずいぶん冷えていた。忘れていた悪寒が背筋を襲い、くしゃみが出る。
「寒い? 早くはいろ」
店の主人は顔見知りの女性で、笑顔とともに迎え入れてくれた。店内は木材独特の香りであたたかく、ドア一枚隔てただけなのに、尾板の町じゃないみたいだった。
テーブル席につき、里恵ちゃんはカフェオレ、わたしはロイヤルミルクティーを注文する。ふたりいっしょに、焼きたてのワッフルも頼んだ。バニラのアイスクリームが乗ったさくさくのワッフルにナイフを入れ、口に運ぶ。あたたかい部屋で、冷たいアイスと熱々のワッフルを食べる背徳的な状況が気持ちいい。
「それでね、今日はまゆに話があるの」
聴いてくれる? と、ロイヤルミルクティーに口をつけるわたしに里恵ちゃんは言った。里恵ちゃんの頼んだカフェオレからも、ゆっくりと湯気がのぼっている。窓ガラスの向こうに広がる、収穫を待つ育ちきった稲のひかりを背負った里恵ちゃんがひどくうつくしくて、彼女の姿を表現することばをいますぐ辞書で調べたいと思った。
「うん、もちろん、聴かせて」
「ありがとう」
里恵ちゃんの声は、乾いていてすこしくすんだ水色をしている。細かい糸が絡まった、かさかさしたわたあめみたいだと思う。食べたことがなくてもわかる。あんまり甘ったるくなくて、たしかに噛んだ感触があったのに、気づいたら忘れてしまうほどさらりと口のなかで溶けていくはかない味がするのだ。
わたしはそのわたあめを、もう二度と食べることができない高級なお菓子を食べる気持ちで口に含み、味わう。さらりと甘い、里恵ちゃんの声。
すう、とひとつ息を吸って、里恵ちゃんは緊張した面持ちで声を発した。
「わたしね、結婚するの」
甘さに浸っていた頭から、いっさいの五感が消えたのがわかった。
「体調を崩してたときに、ずっとそばにいてくれたひとでね」
地面が木の床から砂地に変わり、芸術家の描いた時計のように視界が歪んだ。
「あのときの姿見られてたら、もうなにもこわくないかなあって」
わたしがことばを飲みこめていないのも知らず、里恵ちゃんはどんどんことばを紡ぐ。
「こんな気持ちになるの、生まれてはじめてなの」
頭が真っ白。身を切られる思い。表現としては知っていたことばの意味を、わたしも「生まれてはじめて」、痛いほど理解した。
「言えてよかった。まゆがいちばん大事だから、いちばんに伝えたかったの」
かきあげたえりあしから伸びるうなじを光に晒して、里恵ちゃんはそう言って笑った。コーラルピンクの唇が、すっとやさしげな弧を描く。その左薬指に指輪がはまっていることに、いま、はじめて気づいた。
踏ん張ろうと力を入れても、足の下からどんどん砂が流れ出ていって、まっすぐ座っていることができない。目のまえのカップに入ったロイヤルミルクティーの水面がゆらゆらと不規則に揺れて、目を閉じても気分が悪い。足元にそっと寄り添う店内のあたたかさも、いまは不快だった。そのまま、さっき飲みこんだワッフルと、だれにも秘密にしていたことばを吐きだしてしまいたい衝動に駆られる。この不安定な世界で、わたしの人生なんて終わってしまえばいいと思った。
知りたくなかった。それ以外の感情が、浮かんでこなかった。
湧きあがる吐き気に耐えきれず、口元を手で覆う。
「やだ、うれしいけど泣かないで」
ちがう。泣いてなんかいない。ちがう。いますぐにでも泣いてしまいそうだ。ただただ、驚きに身体が、心がついていかない。
やっぱり、わたしは正しくないから、罰が当たったのだ。まっとうに生きていないから、歩む道を正されたんだ。
その瞬間、次にとるべき行動を、動かない脳みそを一生懸命動かして、いくつもいくつも考えた。聞こえるはずがないパソコンのハードディスクが回るときみたいな音さえ、耳に届く気がする。
身体を起こし、里恵ちゃんをまっすぐに見つめる。戸惑ったようすでも、すでにだれかのものになっていても、彼女はやはりきれいで、わたしのヒーローである里恵ちゃんのままだった。
「……そっか、そうなんだ。知らなかった」
そう言う以外に、なんと言えばよかったのだろう。伝えたいことばはたくさんあった。でもわたししか知らない秘密をことばにしてしまったら、それはだれかにとってのほんとうになってしまう。
「ずっと黙っててごめんね。ちゃんと決まるまでは待ちたくて。でも、まゆにいちばんに教えたのはほんとだよ」
里恵ちゃんが胸のまえで両手を合わせ、祈るように目を閉じてほほえんだ。その姿があまりにきれいで、もし目のまえの里恵ちゃんが絵画なら、キャンバスごと引き裂いてしまいたいと思った。
わたしのことが「いちばん大事」だと言うのに、里恵ちゃんはわたしを選んではくれなかった。選ばれないのなら、いちばんになんてなりたくなかった。「いちばん」だなんて、気休めを聞きたくなかった。
背もたれとのあいだに挟んだかばんの、お財布をつよく握る。どうしてみんな、自分のいちばんが誰かなんて、簡単に口にできるのだろう。わたしみたいに間違っていないからだろうか、それとも、わたしみたいに重く鈍った想いじゃないからだろうか。
里恵ちゃんが、身体を壊していたことが真実とは思えない笑顔で、たのしそうに話している。ずっと会って話したかったのに、わたしはすっかり冷めたワッフルを口に運びながら、うわの空で相槌を打つことしかできなかった。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

六華 snow crystal 8
なごみ
現代文学
雪の街札幌で繰り広げられる、それぞれのラブストーリー。
小児性愛の婚約者、ゲオルクとの再会に絶望する茉理。トラブルに巻き込まれ、莫大な賠償金を請求される潤一。大学生、聡太との結婚を夢見ていた美穂だったが、、

じれったい夜の残像
ペコかな
恋愛
キャリアウーマンの美咲は、日々の忙しさに追われながらも、
ふとした瞬間に孤独を感じることが増えていた。
そんな彼女の前に、昔の恋人であり今は経営者として成功している涼介が突然現れる。
再会した涼介は、冷たく離れていったかつての面影とは違い、成熟しながらも情熱的な姿勢で美咲に接する。
再燃する恋心と、互いに抱える過去の傷が交錯する中で、
美咲は「じれったい」感情に翻弄される。


六華 snow crystal 4
なごみ
現代文学
雪の街、札幌で繰り広げられる、それぞれの愛のかたち。part 4
交通事故の後遺症に苦しむ谷の異常行動。谷のお世話を決意した有紀に、次々と襲いかかる試練。
ロサンゼルスへ研修に行っていた潤一が、急遽帰国した。その意図は? 曖昧な態度の彩矢に不安を覚える遼介。そんな遼介を諦めきれない北村は、、

【完結】カワイイ子猫のつくり方
龍野ゆうき
青春
子猫を助けようとして樹から落下。それだけでも災難なのに、あれ?気が付いたら私…猫になってる!?そんな自分(猫)に手を差し伸べてくれたのは天敵のアイツだった。
無愛想毒舌眼鏡男と獣化主人公の間に生まれる恋?ちょっぴりファンタジーなラブコメ。
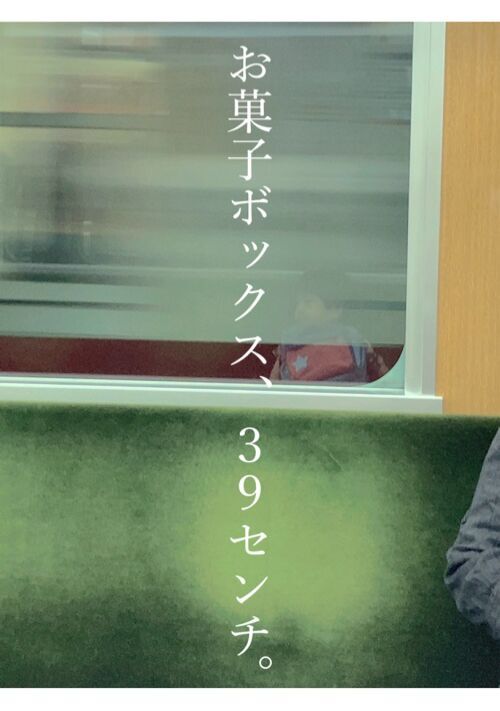

泥に咲く花
臣桜
現代文学
裕福な環境に生まれ何不自由なく育った時坂忠臣(ときさかただおみ)。が、彼は致命的な味覚障碍を患っていた。そんな彼の前に現れたのは、小さな少女二人を連れた春の化身のような女性、佐咲桜(ささきさくら)。
何にも執着できずモノクロの世界に暮らしていた忠臣に、桜の存在は色と光、そして恋を教えてくれた。何者にも汚されていない綺麗な存在に思える桜に忠臣は恋をし、そして彼女の中に眠っているかもしれないドロドロとした人としての泥を求め始めた。
美しく完璧であるように見える二人の美男美女の心の底にある、人の泥とは。
※ 表紙はニジジャーニーで生成しました

極悪家庭教師の溺愛レッスン~悪魔な彼はお隣さん~
恵喜 どうこ
恋愛
「高校合格のお礼をくれない?」
そう言っておねだりしてきたのはお隣の家庭教師のお兄ちゃん。
私よりも10歳上のお兄ちゃんはずっと憧れの人だったんだけど、好きだという告白もないままに男女の関係に発展してしまった私は苦しくて、どうしようもなくて、彼の一挙手一投足にただ振り回されてしまっていた。
葵は私のことを本当はどう思ってるの?
私は葵のことをどう思ってるの?
意地悪なカテキョに翻弄されっぱなし。
こうなったら確かめなくちゃ!
葵の気持ちも、自分の気持ちも!
だけど甘い誘惑が多すぎて――
ちょっぴりスパイスをきかせた大人の男と女子高生のラブストーリーです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















