14 / 39
4.はじめて知る
4-③
しおりを挟むセシリアが遅い朝食を食べている間に、出発の準備もすっかり整っていたので、早速、大国ゼフィランスに向かうコトを告げる。
とにかく、アゼリア王国の権力が届く範囲から、逃げないとね
思い入れも何にもない、あの国の為に、もう、あんな苦しい思いしたくないし
グレンは少しだけ微妙な顔をしたが、何も言わずに頷いて、今までセシリアが使っていた椅子とテーブルを馬車の中にしまい、御者台へと向かう。
お腹が、ポテポテコロコロした感じになったレオと、グリフォンの雛
私の周りを走る姿、なんか可愛くて、癒されるわぁ~……
ほっこりしているセシリアの視線の先で、ルリは、ちょっと首を傾げてから、楽しそうに走り回っていたレオとグリフォンの雛を捕獲する。
「アタシは、こいつら連れて先に入ってるよ…リアもユナも、さっさとはいっといで」
ルリはそう言って、捕まえた2人を左右の腕に抱えて、馬車の中に入っていた。
うふふふ……おチビちゃん達も、馬車に入ったコトだし、私達も入りますか
「それじゃ、私達も馬車に入ろうか、ユナ」
「うん」
ユナと手を繋ぎ、セシリアは楽し気に馬車に乗るのだった。
全員が馬車に乗り、忘れ物が無いコトを確認し、グレンは馬車を出発させた。
「あっ…動き始めた……たぶん、この馬車って、それなりに良いモノなんだろうけど、けっこう振動がきついよねぇ………」
セシリアの言葉に、ルリが首を傾げる。
「こんなモンじゃないのかい?…アタシが檻に入れられて乗せられたモノはもっとガタガタいってたけど?」
「う~ん……ユナは記憶が無いから…わからないなぁ……」
などと話している間に、レオとグリフォンの雛は、セシリアが寄りかかるのに使っていたクッションのひとつに、ひっつい2人で眠っていた。
「あらあら……もう、ねむっちゃったのねぇ~…ふふふふ…可愛いわぁ~…」
異種族だけど、兄弟みたいに育ってくれるかなぁ~…
それにしても、はたから観たアレは、いっちゃなんだけど
かなり、面白かったなぁ……はぁ~……
この世界って、ラノベあるある的に、ろくな娯楽が無いからねぇ……
ずぅ~っと、つらく苦しい生活だったけど、今は自由なんだから
これからの今生は、豊かなスローライフを目指すわよ
勿論、それには豊かな食生活も欠かせないわ
大国…それも帝国と付く強国なら、色々な作物の種とかもあるだろうし
辺境に行く前に、色々と仕入れないとねぇ………
香辛料に、作物の種、出来れば薬草の種も欲しいわねぇ
下手すっと、お金よりも、物々交換が主流のところもあるだろうしね
……っと、今日こそは、グレンに金貨とかの価値を聞かないと
たしか、デュバインが崩したお金も入れたって言ってたけど
何処にいれたのかなぁ?
次の休憩の時にでも、探して聞かないとね
ああ、あと、聞こうと思っていたコト思い出したわ
「あっ…そうだ…ルリ、聞こうと思っていたんだけど、昨日のお肉とか、どうしてんの?」
「うん?どうしてんの?ってはどういう意味だい?」
「いや、だって…魔道具の冷凍庫とか無いでしょ?あのままだったら、腐っちゃうでしょ?」
セシリアの説明に、ルリがなるほどと言う表情で頷く。
「ああ、そういう意味かい……それなら、ほら…あの一角に積み込んで、アタシが《時止め》の魔法をかけておいたよ」
その言葉で、ルリが特殊な魔獣であるコトを、改めて知る。
同時に、させなくて良い魔力の消費をさせたことに罪悪感を感じる。
なんと言っても、今のルリは、極度な栄養失調に魔力だって不安定た妊娠中なのだから。
できるなら、出産した後、身体が癒えるまで、無理をさせたくないと思ったいただけに、自分の失態に頭痛を覚えつつ言う。
「えっとね……その……アイテムボックスあるんだけど」
セシリアの言葉に、バッと振り返ったルリが言う。
「本当に?」
「うん…この腕輪がアイテムボックス…あと、マジックポーチもあるよ」
私の言葉に、ルリは脱力して言う。
「そういうのは、早く言って欲しかったわぁ……アイテムボックスやマジックポーチがあるなら、アタシが無理して《時止め》使わなくてよかったんじゃない………」
クテっとしてみせるルリに、セシリアは腰に着けなおしたばかりのマジックポーチをはずして言う。
「なんなら、マジックポーチ、ルリが持つ?」
セシリアの言葉に、ちょっと悩む素振りをみせてから、ルリは首を振って言う。
「いいや、それだったら、そのマジックポーチはユナに持たせな……アタシは狩りをするから、持っているのにむかないよ」
「ああ…そっか……それじゃ、このマジックポーチはユナが持っててね」
昨日の魔獣も、ルリが獲ったって言ってたっけ
解体されていたから、どんな魔獣だったか知らないけど
たぶん、聞かない方が良いよね……
正体を知って食べられなくなるのはイヤだもん
「はい……ユナが持つね………ルリお姉ちゃん、マジックポーチに入れるから、もう《時止め》をはずして良いよぉ…魔力を食うんでしょ」
「ああ、助かるよ……流石に、ずっと《時止め》を維持すると、魔力が減るからねぇ……こんなに、弱った身体じゃなきゃぁ……たいしたコトないんだけどねぇ……はぁ~…」
ルリが《時止め》を解除したと同時に、ユナが壷などに入ったモノを次々としまう。
そして、今着ないような衣類など、直ぐ使わないモノを次々とマジックポーチに入れて行く。
保存食や水の壷なども、すべてマジックポーチの中に消え、馬車の中が広くなったコトで、セシリアはちょっと落ち込む。
嗚呼…いくらテンパリ状態だからって、気付こうよ私
最初からこうしたら、もっと馬車の中を広く使えたんだよねぇ
「ふふふふ…随分と広くなったねぇ……これなら、アタシも本体の姿なっても良いねぇ…昨日、リアが毛皮を被っても寒そうに寝てたからね……本体で添い寝してやれるよ」
ルリの言葉に、セシリアは内心でちょっとウホッとする。
うわぁ~…モフモフのルリの添い寝……凄く楽しみぃ~……うふふふ
猫型魔獣のルリに、もふりついて寝る夢想にちょっとうっとりするセシリアに、ルリが尋ねる。
「そう言えば、あの『隠蔽結界』とかいうヤツ解いたのかい?」
ルリの言葉に、セシリアは馬車の天井の上を視る。
あははは………張ったまま忘れていたわ………どうしようかなぁ?
このままでも、大丈夫だとは思うけど…ここは、それとなくルリに聞いてみよう
「あっ…張ったままだったわ……でも…このままでも支障ないから良いかな?」
セシリアの言葉に、ルリは頭痛を覚えたようにこめかみに指先をあてていう。
「あるに決まっているだろう……リアは、弱っているんだよ」
と、静かな叱責に、肩を竦め、ペロッと舌を出し、てへぺろをしつつ、隠蔽結界を解除するのだった。
今の私がやっても、可愛くないかもだけど、てへぺろしかないわ
あ~あ…ルリに怒られちゃった
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

こもごも
ユウキ カノ
現代文学
とある田舎町に住むまゆは、幼なじみの里恵ちゃんのことが好きだった。
年上である里恵が社会人になり、顔を合わせることが難しくなっても、変わらず里恵ちゃんを想い続けている。
その一方で、まゆには同じく幼なじみである恋人・真登(まさと)がいた。
高校を中退し、家族との会話もなくなってしまったまゆ。
週の半分はアルバイトをして、残り半分は家でじっとしているだけの生活のなかで、里恵ちゃんへの想い、真登との関係、両親とのかかわりについて考えをめぐらせる。
参考文献
山田忠雄・柴田武ほか編、二〇一二年『新明解国語辞典』第七版、三省堂。



Hand in Hand - 二人で進むフィギュアスケート青春小説
宮 都
青春
幼なじみへの気持ちの変化を自覚できずにいた中2の夏。ライバルとの出会いが、少年を未知のスポーツへと向わせた。
美少女と手に手をとって進むその競技の名は、アイスダンス!!
【2022/6/11完結】
その日僕たちの教室は、朝から転校生が来るという噂に落ち着きをなくしていた。帰国子女らしいという情報も入り、誰もがますます転校生への期待を募らせていた。
そんな中でただ一人、果歩(かほ)だけは違っていた。
「制覇、今日は五時からだから。来てね」
隣の席に座る彼女は大きな瞳を輝かせて、にっこりこちらを覗きこんだ。
担任が一人の生徒とともに教室に入ってきた。みんなの目が一斉にそちらに向かった。それでも果歩だけはずっと僕の方を見ていた。
◇
こんな二人の居場所に現れたアメリカ帰りの転校生。少年はアイスダンスをするという彼に強い焦りを感じ、彼と同じ道に飛び込んでいく……
――小説家になろう、カクヨム(別タイトル)にも掲載――
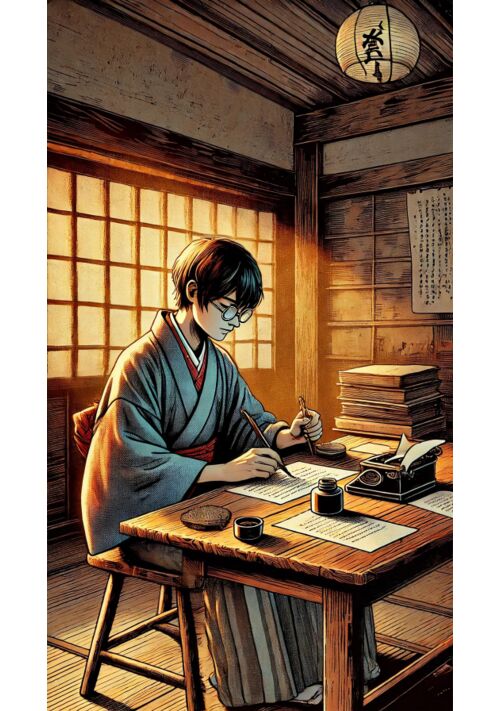

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















