お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

何の変哲もない違和感
遊楽部八雲
ミステリー
日常に潜む違和感を多彩なジャンル、表現で描く恐怖の非日常!
日本SFのパイオニア、星新一を彷彿とさせる独特な言い回し、秀逸な結末でお送りする至高の傑作短編集!!

春の残骸
葛原そしお
ミステリー
赤星杏奈。彼女と出会ったのは、私──西塚小夜子──が中学生の時だった。彼女は学年一の秀才、優等生で、誰よりも美しかった。最後に彼女を見たのは十年前、高校一年生の時。それ以来、彼女と会うことはなく、彼女のことを思い出すこともなくなっていった。
しかし偶然地元に帰省した際、彼女の近況を知ることとなる。精神を病み、実家に引きこもっているとのこと。そこで私は見る影もなくなった現在の彼女と再会し、悲惨な状況に身を置く彼女を引き取ることに決める。
共同生活を始めて一ヶ月、落ち着いてきたころ、私は奇妙な夢を見た。それは過去の、中学二年の始業式の夢で、当時の彼女が現れた。私は思わず彼女に告白してしまった。それはただの夢だと思っていたが、本来知らないはずの彼女のアドレスや、身に覚えのない記憶が私の中にあった。
あの夢は私が忘れていた記憶なのか。あるいは夢の中の行動が過去を変え、現実を改変するのか。そしてなぜこんな夢を見るのか、現象が起きたのか。そしてこの現象に、私の死が関わっているらしい。
私はその謎を解くことに興味はない。ただ彼女を、杏奈を救うために、この現象を利用することに決めた。

全5章 読者への挑戦付き、謎解き推理小説 「密室の謎と奇妙な時計」
葉羽
ミステリー
神藤葉羽(しんどう はね)は、ある日、推理小説を読みふけっているところへ幼馴染の望月彩由美(もちづき あゆみ)からのメッセージを受け取る。彩由美は、学校の友人から奇妙な事件の噂を聞きつけたらしく、葉羽に相談を持ちかける。
学校の裏手にある古い洋館で起こった謎の死亡事件——被害者は密室の中で発見され、すべての窓と扉は内側から施錠されていた。現場の証拠や死亡時刻は明確だが、決定的なアリバイを持つ人物が疑われている。葉羽は彩由美と共に事件に首を突っ込むが、そこには不可解な「時計」の存在が絡んでいた。

お家に帰る
原口源太郎
ミステリー
裕福な家庭の小学三年生、山口源太郎はその名前からよくいじめられている。その源太郎がある日、誘拐犯たちにさらわれた。山奥の小屋に監禁された源太郎は、翌日に自分が殺されてしまうと知る。部屋を脱出し、家を目指して山を下りる。
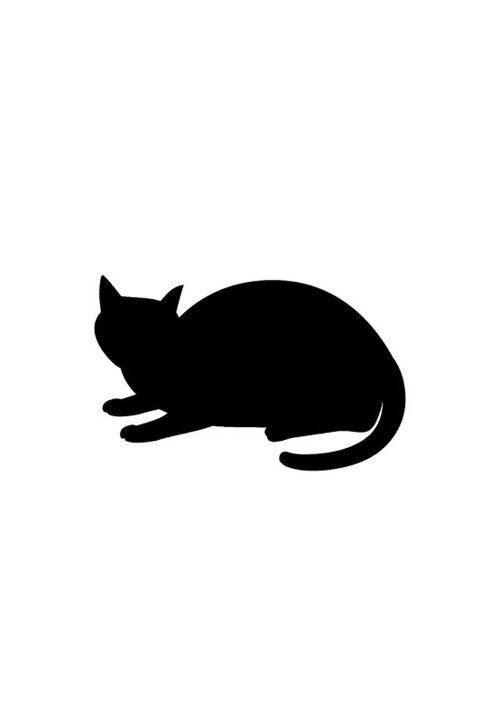
名探偵あやのん(仮)
オヂサン
ミステリー
これはSAISONというアイドルグループのメンバーである「林あやの」さんと、その愛猫「タワシ」をモデルにした創作ナゾトキです。なお登場人物の「小島ルナ」も前述のSAISONのメンバー(正確には小島瑠那さん)です。
元々稚拙な文章の上、そもそもがこのSAISONというグループ、2人の人となりや関係性を知ってる方に向けての作品なので、そこを知らない方は余計に???な描写があったり、様々な説明が不足に感じるとは思いますがご容赦下さい。
なお、作中に出てくるマルシェというコンカフェもキャストも完全なフィクションです(実際には小島瑠那さんは『じぇるめ』というキチンとしたコンカフェを経営してらっしゃいます)。

交換殺人って難しい
流々(るる)
ミステリー
【第4回ホラー・ミステリー小説大賞 奨励賞】
ブラック上司、パワハラ、闇サイト。『犯人』は誰だ。
積もり積もったストレスのはけ口として訪れていた闇サイト。
そこで甘美な禁断の言葉を投げかけられる。
「交換殺人」
その四文字の魔的な魅力に抗えず、やがて……。
そして、届いた一通の封筒。そこから疑心の渦が巻き起こっていく。
最後に笑うのは?
(全三十六話+序章・終章)
※言葉の暴力が表現されています。ご注意ください。
※この作品はフィクションです。実在の人物・団体とは関係ありません。

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。
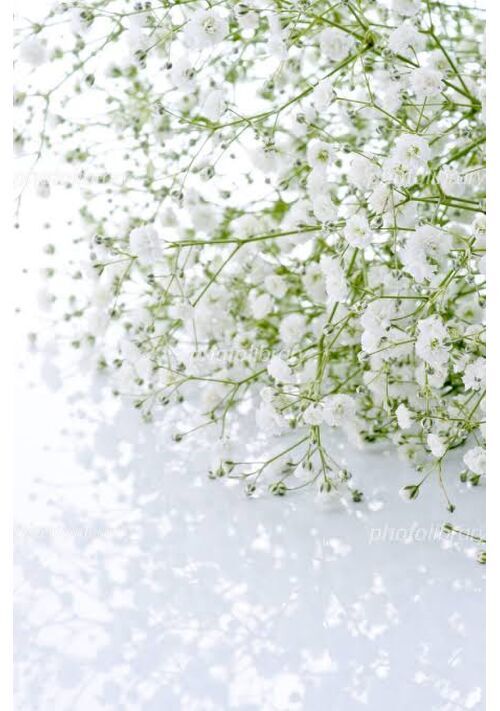
夢喰人ーユメクイビトー
レイト.
ミステリー
あなたは、怖い夢や悲しかった時の夢を食べてくれる「夢喰人」と言う怪人が存在したら「夢」を食べてもらいますかーー?
誰しもが一度は体験した事がある「悪夢」。
大抵の人は、悪夢を見ることがあっても「怖い夢だったな…」「災厄だ…」と言った形であまり気にも留めていない。ましてや、どんな夢だったのかも覚えていない事もある。
その一方で、悪夢に魘される人も多い。現実で悲惨な光景をみたり、体験をしたりと言った経緯で毎晩のように魘され生活に支障が生じる人も中にはいる。
そんな悪夢に魘される人の前に現れ夢を食べてくれる怪人「夢喰人」ーー。
高校二年の田中 優希は、夢喰人の噂を親友の工藤 和也に教えてもらった。
そんな、怪人なんてよくある怪談や都市伝説の類だと思っていた。
優希にはなぜ和也がそんな噂を教えてくれたのか心当たりがある。
親友だから、世間話、暇つぶし程度に言った事ではない。
和也は「夢喰人」を探しているからだ。
和也は、小さい頃からたまに同じ悪夢を見ることがある。
高校二年生になってからそれは、頻度を増し和也を苦しめていた。和也の兄 工藤 正は、和也達と川遊びをしてる最中に不幸なことに川に流されて亡くなってしまった。それっきり、和也はトラウマを抱え悪夢を見るようになってしまった。
悲惨なトラウマを忘れる事はできない、でもいつまでも悪夢に魘される必要なんてないと思う優希は、和也の手助けができないか考えていた。
優希自身も、とある夢に悩まされているから気持ちがわかる。
そうな、事を心に思いながらーー。
そんな、ある日 突然 和也は悪夢を見なくなった。原因はわからないがこれで魘される事はないと少し何処か引っかかる感じがしたが安心した。
しかし、和也は一部の兄に関する記憶が改変されていた。
本当の彼を知っているのは、優希だけになってしまう。どうして、記憶までもが改変されているのかと疑問を浮かべていた。
ある事を、思い出してしまう。
夢を食ってくれる怪人「夢喰人」の事をけれども優希は、空想上の怪人なんているはずがないと考えていた。
一学年上の先輩 長澤 綾野が悪夢に魘されている事を知るまでは・・・。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















