2 / 6
表現方法、一人称
しおりを挟む
○表現は統一すべきか
他の創作論をたくさん読んできたわけではありませんが、「漢字を開く、開かない」といった表現についての話はあまり見たことがありません。しかし、そうした実際的かつ悩ましい執筆の問題もしておくべきだと私は思います。以下に拙作を用いて具体例を示したいと思います。
尚、いずれも私の没作品となります。
「石造りの長い橋の上には、朝早くから来城者が列をなして並んでいた。朝陽がちょうど橋脚の下部から昇ってきて、皆の顔をまぶしく照らした」――『エルフと魔女とミステリー』
「漢字を開く、開かない」といいました。たとえば「列をなして」の「なして」は、「成して」と書くこともできます。しかし私は漢字を開いて「なして」とひらがなで書きました。
なぜか。私の判断として、「『成して』と書くのは一般的ではないから」が最も大きな理由となりますが、「一文の中に漢字が多く読みにくくなるため」という理由もあります。
また、「朝陽がちょうど橋脚の下部から昇ってきて」の「朝陽」は、「朝日」と書いてもいいはずですが、私の感覚として「朝日」では「朝の太陽そのもの」を表すため、「朝の太陽光」として「朝陽」を採用したのです。
さらに「昇ってきて」は「上ってきて」でも間違いではないですが…書き手の皆さんはどちらを採用されますか。やはり私の感覚として「朝陽」は「昇る」しかありません。もしかすると「登る」と書く人もおられるかもしれません。辞書的には間違いですが、小説における表現としては間違いとはいえません。
最後に、「皆の顔をまぶしく照らした」の「まぶしく」は、「眩しく」の漢字を開いています。これは先ほどの「なして」より「漢字を開く、開かない」で分かれるのではないかと思います。私は基本的に”開く派”ですが、硬派な作品なら「眩しく」と漢字で書く可能性はあります。つまり、表現は作品によって変える必要があるのです。ですので、表現はあえて統一すべきではないと思います。
とはいえ、例外はつきものです。「私ルール」でも「俺ルール」でも「個人ルール」でも呼び方は何でも構いませんが、書き手も”中堅”なら、おおよそ自身の文体を理解し、定まってくるはず。
私の作品を読んでいただけますと、おわかりいただけるかと思いますが、私の場合、「言う」は「いう」、「行く」は「いく」あるいは「ゆく」、「分かる」は「わかる」と、必ず漢字を開いて書いてあります。これは私のルール、執筆時の方針です。どの作品であっても表現が統一されています。
他にも、「私」と書いた場合、発話者の性別は男性で、「わたし」なら女性です。
「あの方が告白するまで待つ、というのはいかがですか。こちらから先に断るというのは……」
「いえ、断るなら早い方がいいと思うんです……常連のお客様を一人、失ってしまうかもしれないので、マスターには申し訳ないんですけど……」
「私のことはどうぞお気遣いなく。ただ本当に……よろしいのですか?」
「はい。いまのわたしには恋をする余裕はないですし、一方通行の恋は、どうやっても実らないじゃないですか」――『喫茶エレーナの事件簿』
「言う」と「行く」の漢字をなぜ必ず開くのか、これにもちゃんと理由があります、といってもかなり個人的な理由ですが。
それは、私の大好きな作家、大沢在昌さんがそういう風に書かれているからです。私の家の本棚には、大沢さんだけの本が一杯に入った場所があります。つまり、それだけ氏の本を読んだ結果、だいたいの作風や文体は似てくるわけです(おこがましいですけども)。
あと、実際的な話として、「言う」や「行く」は頻繁に使う表現ですので、漢字を開いてひらがな書きにした方が見た目にすっきりする、という理由もあります。
一方、「分かる」は最近まで統一されておらず、作品によって表記に揺れがありました。現在は統一しています。「よく分かる」とう意味で、「解る」とわざわざ書いていたこともありましたが、今はしていません。
ただし、「道が分かれる」、「意見が分かれる」など、「分岐する」、「分離する」といった場合は「分」を使います。
また、発話者の性別を「私」と「わたし」で書き分けている理由ですが、これは一見してわかりやすいという、読者への配慮が主な理由です。もう一つは、私の中で女性は優しいイメージですので、漢字の硬いイメージとは合わないと思うから、開くわけですね。
長年書き続けるうちに、だいたいどの書き手も「漢字を開く」ようになるのではないかと思うのですが、反対に「漢字に戻す」ケースもあります。たとえば、「今」です。
私はむかし、ずっと「いま」と書き続けていました。それがこの一年のうちに「今」と”閉じる”ようになったんですね。なぜか。これは自分でもよくわかりませんが、フィーリングでしょうね、実にいいかげんなものです。
○人称の問題(一人称について)
「人称がわかりません」とか、「一人称の方が書くのが簡単」とか、「三人称は書くのが難しいし、読者に受けない」とか、人称の話は時々目にします。「今さら」と思われる人もいるでしょうが、おさらいだと思って少しお付き合いください。
一人称小説とは、「私」や「俺」など、語り手(=視点人物)を主語とする小説のことです。「わたしは~」と語るわけですから、必然的に書き手の思いや考えが作品に反映する(しやすい)のではないかと思われます。
俺は、森の中に倒れていたところを、偶然通りかかったエルフに助けられた。
エルフってのは、わざわざ言うまでもないかもしれないが、尖った耳が特徴の、人型の種族だ。
色白の彼女は家(異世界マンションの102号室)の中に俺を担ぎ込み、ベッドの上で休ませてくれていた。――『異世界マンションの管理人を任されました』
私が二十代だったころは「俺」を使った一人称小説もいくつか書いていましたが、今はもう無理ですね、「おれは~」などと語れません、「私は~」がしっくりきます。
一人称小説の良い所は、常に語り手が一人と定まっているため、視点のブレが起きにくい所です。
「ねえ、どうなの!? 結婚するのしないの!!?? はっきりしなさいよ!!」
とうとう彼女が腕を伸ばして俺の首を絞めてきた。
「うっ、うわあやめっ――!!」
「結婚するって言いなさいよ!!! さあ!!!」
ドッタンバッタンしていると、ガンガンガンと扉を叩く音がする。
「ネクロちゃーーん! いるのはわかってんのよ~~、出てきなさーーい!」
女性の声だ。
俺の首を絞めていた手が、ふっと緩まる。
「あわわわどうしよう……」
急にあわてふためく彼女。
もしかして、この子の名前はネクロっていうのかな?――『異世界マンションの管理人を任されました』
出会ったばかりで名前のわからない相手であるため、「俺」は首を絞めてくる相手を「彼女」というしかない。「彼女」の名前を知るには、本人に喋らせる、訊き出す、といった展開もあり得ますが、ここでは別の女性を登場させ、「彼女」の名前を呼ばせることにより、「俺」は「彼女」の名前が「ネクロ」だと知る展開になっています。
たとえば、初めて会ったのに相手の名前を知っていたらおかしいですよね。ですから拙作の例で、「とうとうネクロが腕を伸ばして俺の首を絞めてきた」と書いてはダメなのです。しかし、一人称小説でこうした視点のブレが起きることはまれで、起きるとすれば単に書き慣れていないからだといえるでしょう。
他の創作論をたくさん読んできたわけではありませんが、「漢字を開く、開かない」といった表現についての話はあまり見たことがありません。しかし、そうした実際的かつ悩ましい執筆の問題もしておくべきだと私は思います。以下に拙作を用いて具体例を示したいと思います。
尚、いずれも私の没作品となります。
「石造りの長い橋の上には、朝早くから来城者が列をなして並んでいた。朝陽がちょうど橋脚の下部から昇ってきて、皆の顔をまぶしく照らした」――『エルフと魔女とミステリー』
「漢字を開く、開かない」といいました。たとえば「列をなして」の「なして」は、「成して」と書くこともできます。しかし私は漢字を開いて「なして」とひらがなで書きました。
なぜか。私の判断として、「『成して』と書くのは一般的ではないから」が最も大きな理由となりますが、「一文の中に漢字が多く読みにくくなるため」という理由もあります。
また、「朝陽がちょうど橋脚の下部から昇ってきて」の「朝陽」は、「朝日」と書いてもいいはずですが、私の感覚として「朝日」では「朝の太陽そのもの」を表すため、「朝の太陽光」として「朝陽」を採用したのです。
さらに「昇ってきて」は「上ってきて」でも間違いではないですが…書き手の皆さんはどちらを採用されますか。やはり私の感覚として「朝陽」は「昇る」しかありません。もしかすると「登る」と書く人もおられるかもしれません。辞書的には間違いですが、小説における表現としては間違いとはいえません。
最後に、「皆の顔をまぶしく照らした」の「まぶしく」は、「眩しく」の漢字を開いています。これは先ほどの「なして」より「漢字を開く、開かない」で分かれるのではないかと思います。私は基本的に”開く派”ですが、硬派な作品なら「眩しく」と漢字で書く可能性はあります。つまり、表現は作品によって変える必要があるのです。ですので、表現はあえて統一すべきではないと思います。
とはいえ、例外はつきものです。「私ルール」でも「俺ルール」でも「個人ルール」でも呼び方は何でも構いませんが、書き手も”中堅”なら、おおよそ自身の文体を理解し、定まってくるはず。
私の作品を読んでいただけますと、おわかりいただけるかと思いますが、私の場合、「言う」は「いう」、「行く」は「いく」あるいは「ゆく」、「分かる」は「わかる」と、必ず漢字を開いて書いてあります。これは私のルール、執筆時の方針です。どの作品であっても表現が統一されています。
他にも、「私」と書いた場合、発話者の性別は男性で、「わたし」なら女性です。
「あの方が告白するまで待つ、というのはいかがですか。こちらから先に断るというのは……」
「いえ、断るなら早い方がいいと思うんです……常連のお客様を一人、失ってしまうかもしれないので、マスターには申し訳ないんですけど……」
「私のことはどうぞお気遣いなく。ただ本当に……よろしいのですか?」
「はい。いまのわたしには恋をする余裕はないですし、一方通行の恋は、どうやっても実らないじゃないですか」――『喫茶エレーナの事件簿』
「言う」と「行く」の漢字をなぜ必ず開くのか、これにもちゃんと理由があります、といってもかなり個人的な理由ですが。
それは、私の大好きな作家、大沢在昌さんがそういう風に書かれているからです。私の家の本棚には、大沢さんだけの本が一杯に入った場所があります。つまり、それだけ氏の本を読んだ結果、だいたいの作風や文体は似てくるわけです(おこがましいですけども)。
あと、実際的な話として、「言う」や「行く」は頻繁に使う表現ですので、漢字を開いてひらがな書きにした方が見た目にすっきりする、という理由もあります。
一方、「分かる」は最近まで統一されておらず、作品によって表記に揺れがありました。現在は統一しています。「よく分かる」とう意味で、「解る」とわざわざ書いていたこともありましたが、今はしていません。
ただし、「道が分かれる」、「意見が分かれる」など、「分岐する」、「分離する」といった場合は「分」を使います。
また、発話者の性別を「私」と「わたし」で書き分けている理由ですが、これは一見してわかりやすいという、読者への配慮が主な理由です。もう一つは、私の中で女性は優しいイメージですので、漢字の硬いイメージとは合わないと思うから、開くわけですね。
長年書き続けるうちに、だいたいどの書き手も「漢字を開く」ようになるのではないかと思うのですが、反対に「漢字に戻す」ケースもあります。たとえば、「今」です。
私はむかし、ずっと「いま」と書き続けていました。それがこの一年のうちに「今」と”閉じる”ようになったんですね。なぜか。これは自分でもよくわかりませんが、フィーリングでしょうね、実にいいかげんなものです。
○人称の問題(一人称について)
「人称がわかりません」とか、「一人称の方が書くのが簡単」とか、「三人称は書くのが難しいし、読者に受けない」とか、人称の話は時々目にします。「今さら」と思われる人もいるでしょうが、おさらいだと思って少しお付き合いください。
一人称小説とは、「私」や「俺」など、語り手(=視点人物)を主語とする小説のことです。「わたしは~」と語るわけですから、必然的に書き手の思いや考えが作品に反映する(しやすい)のではないかと思われます。
俺は、森の中に倒れていたところを、偶然通りかかったエルフに助けられた。
エルフってのは、わざわざ言うまでもないかもしれないが、尖った耳が特徴の、人型の種族だ。
色白の彼女は家(異世界マンションの102号室)の中に俺を担ぎ込み、ベッドの上で休ませてくれていた。――『異世界マンションの管理人を任されました』
私が二十代だったころは「俺」を使った一人称小説もいくつか書いていましたが、今はもう無理ですね、「おれは~」などと語れません、「私は~」がしっくりきます。
一人称小説の良い所は、常に語り手が一人と定まっているため、視点のブレが起きにくい所です。
「ねえ、どうなの!? 結婚するのしないの!!?? はっきりしなさいよ!!」
とうとう彼女が腕を伸ばして俺の首を絞めてきた。
「うっ、うわあやめっ――!!」
「結婚するって言いなさいよ!!! さあ!!!」
ドッタンバッタンしていると、ガンガンガンと扉を叩く音がする。
「ネクロちゃーーん! いるのはわかってんのよ~~、出てきなさーーい!」
女性の声だ。
俺の首を絞めていた手が、ふっと緩まる。
「あわわわどうしよう……」
急にあわてふためく彼女。
もしかして、この子の名前はネクロっていうのかな?――『異世界マンションの管理人を任されました』
出会ったばかりで名前のわからない相手であるため、「俺」は首を絞めてくる相手を「彼女」というしかない。「彼女」の名前を知るには、本人に喋らせる、訊き出す、といった展開もあり得ますが、ここでは別の女性を登場させ、「彼女」の名前を呼ばせることにより、「俺」は「彼女」の名前が「ネクロ」だと知る展開になっています。
たとえば、初めて会ったのに相手の名前を知っていたらおかしいですよね。ですから拙作の例で、「とうとうネクロが腕を伸ばして俺の首を絞めてきた」と書いてはダメなのです。しかし、一人称小説でこうした視点のブレが起きることはまれで、起きるとすれば単に書き慣れていないからだといえるでしょう。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。




意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております
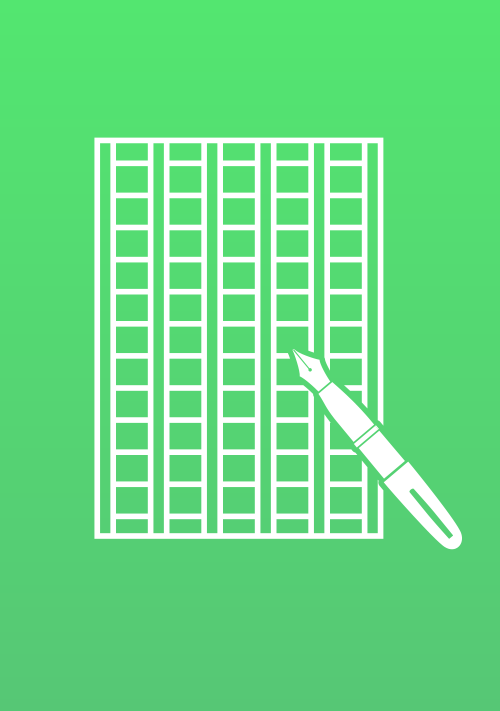
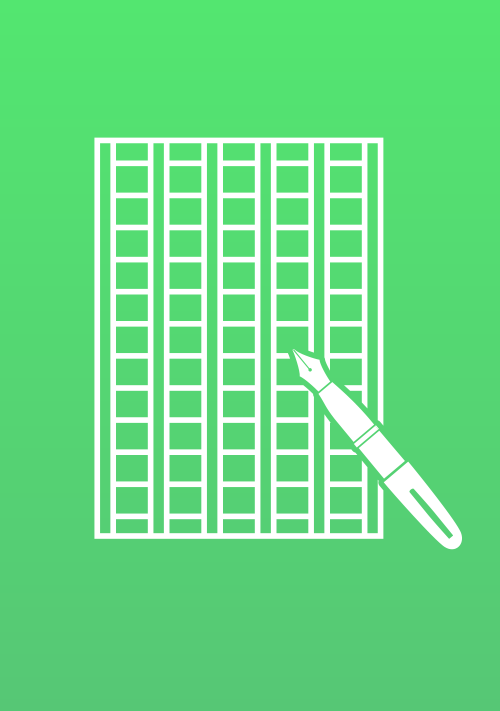
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















