175 / 209
174話「ウタのツアー」
しおりを挟む
「ツアー公演は明日からか。いよいよその日が迫ってきたな」
明日から連続でのこうえわが始まる、という、開幕前日の夜。
寛ぎのひと時を過ごしていると、ウィクトルが唐突に話しかけてきた。
「どうしたの、ウィクトル。いきなりね」
入浴は終えた。夕食もとうに終えた。今日することはもう終わっている。今の私に唯一残されている用事は、眠ることだけだ。質の良い睡眠を取り明日に備えること、それが一番大切なことだ。
「……緊張は、しないのか?」
黒い髪を櫛で手入れしつつ、ウィクトルは尋ねてくる。
「それはどういう質問?」
「勘違いしないでくれ、悪い意味ではない。ただ、ふと気になってな」
問いの意図は不明のまま。
……いや、意図なんてないのかもしれない。
「深い意味はないのね」
「あぁ」
「良かった。暗に何かを言っているのに気づけていないというパターンだったら、恥ずかしいものね」
そんな微妙に捻じ曲がった言い方をすることにも、深い意味はない。ただの気まぐれだ。何となく思いついたことを口にしているだけのこと。
「それで、緊張はするのか? しないのか?」
合間に少し関係のないやり取りが挟まってしまったが、ウィクトルはそれ以前の話の内容を忘れてはいなかった。
「今はもう慣れたわ」
「そうか。やはり、慣れるのだな」
ウィクトルは、嬉しそうでも悲しそうでもないような、感情が読み取りづらい顔をしている。ただ、目もとや口角に力が入っている様子はなかった。寛げてはいるのだろう。
「しかし、君がこうもスターになるとは思わなかったな。……失礼かもしれないが」
「失礼じゃないわよ。私だって同じように思っているわ」
「人生とは分からないもの。そう言った過去の人間は、賢かったのかもしれないな」
こんな日に限って、彼は妙なことを言う。
でも、その言葉は的を得ている。
舞台を観に行ったあの日、ミソカニに出会わなければ、きっとこんな今日にはたどり着かなかった。いや、そもそも、私があの日の舞台を観に行っていなければミソカニとの出会いすらなかったのだ。だとしたら、今この瞬間の私を作り上げたのは、舞台を観に行くきっかけを作ったリベルテだったと言えるかもしれない。
一人思考を巡らせていると、いつの間にか、ウィクトルが歩み寄ってきていた。
いきなり近づいてこられるとは。驚きだ。
「……えっと、何? どうしたの?」
ついそんなことを言ってしまった。
「私は変わった。だが、君はもっと変わった。そんな気がするな」
「……そうかしら」
もちろん私も変わっただろうが、どちらかというと、ウィクトルの方が大きく変わった気がするのだが。
「私から見れば、ウィクトルの方が変わったわよ」
「な。そうなのか」
「えぇ、そうよ。身分も変わって、性格も変わったじゃない」
「……よく分からんが、そういうものか」
なぜだろう、こんな日に限って彼が愛しくなるのは。
いつもは特別何も思わない。けれども、しばらく一緒にいられないと思った瞬間、離れたくないという感情が一気に込み上げてくる。馬鹿みたいな話だが、事実は事実なのだ。
「寂しいわね、しばらく会えなくなるのは」
だからだろうか、つい弱気な言葉を発してしまう。
心配させるべきではないのに。
「そうだな。だがリベルテは同行する。何かあれば彼に頼ると良い」
「えぇ。しばらくの間は彼を頼りにするわ」
彼への恋しさはしまっておこう。そんなものは胸の奥にしまって、今は前を向いておかなくては。そうでなくては、前へ踏み出す勇気がなくなってしまう。
翌朝、目を覚ますと枕元にリベルテが立っていた。
髪はふんわりと整っているし、服装も寝巻きのままではない。恐らく、身支度は既に済んでいるのだろう。
「……あ。リベルテ、もう起きていたのね」
「おはようございます! ウタ様。お待ちしておりました」
私が目覚めたことに気づくと、リベルテは顔面に花を咲かせる。
「ごめんなさい……寝坊した……?」
ゆっくりと上半身を縦向けつつ尋ねる。
すると彼は、首を横に振った。
「いえ! まだ時間はございますよ!」
「良かった……。正直ちょっと焦ったわ」
この大切な日の朝に寝坊したらと思うとゾッとする。たとえ日頃毎日寝坊していたとしても、今日だけは寝過ごすわけにはいかない。そのくらい大切な日だ、今日は。
「ウタ様、慌てることはございません。無理のないペースで用意なさって下さい」
「そ、そうね。ありがとう」
「朝食は既に出来上がっております」
「助かるわ」
リベルテは基本何でもできる。掃除も裁縫も料理も、それなりにこなすことできている。明日嫁に行っても活躍できそうなくらいの能力を保持しているのだ。
いや、もちろん、彼は男性だから嫁には行かないが。
そこはあくまで例え話だが。
ただ、家事能力が高くない私やウィクトルのような人間からすると、リベルテのような人物の存在はかなりありがたい。リベルテには高い価値がある、と私が感じているように、ウィクトルもまたそう感じていることだろう。
「顔を流してくるわね」
「はい! ごゆっくり」
その後、予定されていた劇場へ向かった。
同行者はリベルテのみ。
それでも、一人で行かねばならないよりは良い。こんな時にまで「ウィクトルと一緒にいたい」なんて言ってはいられないから、私は迷わずに行く。
「何かあれば気軽に申し付けて下さいね」
「えぇ。頼りにしてるわ」
リベルテも、帝国軍に勤めていた時には、こんなことになるとは思っていなかっただろう。私に付き添って劇場へ向かう瞬間なんて、きっと想像しなかったはずだ。
「ウタ様、緊張なさっているのでございますか?」
自動運転車の中で、リベルテはそんなことを言ってきた。
「え、えぇ。まぁ。そうね」
「力を抜いて、気楽に、が大切でございますよ」
それができればどんなに良いか。
私だって、望んで緊張しているわけではない。
本当ならこんな危機的状況におかれたような心境になんてなりたくない。穏やかな心でその時を迎えたい。緊張など微塵もない状態で挑めるのがベストだということは、私だって気づいている。
明日から連続でのこうえわが始まる、という、開幕前日の夜。
寛ぎのひと時を過ごしていると、ウィクトルが唐突に話しかけてきた。
「どうしたの、ウィクトル。いきなりね」
入浴は終えた。夕食もとうに終えた。今日することはもう終わっている。今の私に唯一残されている用事は、眠ることだけだ。質の良い睡眠を取り明日に備えること、それが一番大切なことだ。
「……緊張は、しないのか?」
黒い髪を櫛で手入れしつつ、ウィクトルは尋ねてくる。
「それはどういう質問?」
「勘違いしないでくれ、悪い意味ではない。ただ、ふと気になってな」
問いの意図は不明のまま。
……いや、意図なんてないのかもしれない。
「深い意味はないのね」
「あぁ」
「良かった。暗に何かを言っているのに気づけていないというパターンだったら、恥ずかしいものね」
そんな微妙に捻じ曲がった言い方をすることにも、深い意味はない。ただの気まぐれだ。何となく思いついたことを口にしているだけのこと。
「それで、緊張はするのか? しないのか?」
合間に少し関係のないやり取りが挟まってしまったが、ウィクトルはそれ以前の話の内容を忘れてはいなかった。
「今はもう慣れたわ」
「そうか。やはり、慣れるのだな」
ウィクトルは、嬉しそうでも悲しそうでもないような、感情が読み取りづらい顔をしている。ただ、目もとや口角に力が入っている様子はなかった。寛げてはいるのだろう。
「しかし、君がこうもスターになるとは思わなかったな。……失礼かもしれないが」
「失礼じゃないわよ。私だって同じように思っているわ」
「人生とは分からないもの。そう言った過去の人間は、賢かったのかもしれないな」
こんな日に限って、彼は妙なことを言う。
でも、その言葉は的を得ている。
舞台を観に行ったあの日、ミソカニに出会わなければ、きっとこんな今日にはたどり着かなかった。いや、そもそも、私があの日の舞台を観に行っていなければミソカニとの出会いすらなかったのだ。だとしたら、今この瞬間の私を作り上げたのは、舞台を観に行くきっかけを作ったリベルテだったと言えるかもしれない。
一人思考を巡らせていると、いつの間にか、ウィクトルが歩み寄ってきていた。
いきなり近づいてこられるとは。驚きだ。
「……えっと、何? どうしたの?」
ついそんなことを言ってしまった。
「私は変わった。だが、君はもっと変わった。そんな気がするな」
「……そうかしら」
もちろん私も変わっただろうが、どちらかというと、ウィクトルの方が大きく変わった気がするのだが。
「私から見れば、ウィクトルの方が変わったわよ」
「な。そうなのか」
「えぇ、そうよ。身分も変わって、性格も変わったじゃない」
「……よく分からんが、そういうものか」
なぜだろう、こんな日に限って彼が愛しくなるのは。
いつもは特別何も思わない。けれども、しばらく一緒にいられないと思った瞬間、離れたくないという感情が一気に込み上げてくる。馬鹿みたいな話だが、事実は事実なのだ。
「寂しいわね、しばらく会えなくなるのは」
だからだろうか、つい弱気な言葉を発してしまう。
心配させるべきではないのに。
「そうだな。だがリベルテは同行する。何かあれば彼に頼ると良い」
「えぇ。しばらくの間は彼を頼りにするわ」
彼への恋しさはしまっておこう。そんなものは胸の奥にしまって、今は前を向いておかなくては。そうでなくては、前へ踏み出す勇気がなくなってしまう。
翌朝、目を覚ますと枕元にリベルテが立っていた。
髪はふんわりと整っているし、服装も寝巻きのままではない。恐らく、身支度は既に済んでいるのだろう。
「……あ。リベルテ、もう起きていたのね」
「おはようございます! ウタ様。お待ちしておりました」
私が目覚めたことに気づくと、リベルテは顔面に花を咲かせる。
「ごめんなさい……寝坊した……?」
ゆっくりと上半身を縦向けつつ尋ねる。
すると彼は、首を横に振った。
「いえ! まだ時間はございますよ!」
「良かった……。正直ちょっと焦ったわ」
この大切な日の朝に寝坊したらと思うとゾッとする。たとえ日頃毎日寝坊していたとしても、今日だけは寝過ごすわけにはいかない。そのくらい大切な日だ、今日は。
「ウタ様、慌てることはございません。無理のないペースで用意なさって下さい」
「そ、そうね。ありがとう」
「朝食は既に出来上がっております」
「助かるわ」
リベルテは基本何でもできる。掃除も裁縫も料理も、それなりにこなすことできている。明日嫁に行っても活躍できそうなくらいの能力を保持しているのだ。
いや、もちろん、彼は男性だから嫁には行かないが。
そこはあくまで例え話だが。
ただ、家事能力が高くない私やウィクトルのような人間からすると、リベルテのような人物の存在はかなりありがたい。リベルテには高い価値がある、と私が感じているように、ウィクトルもまたそう感じていることだろう。
「顔を流してくるわね」
「はい! ごゆっくり」
その後、予定されていた劇場へ向かった。
同行者はリベルテのみ。
それでも、一人で行かねばならないよりは良い。こんな時にまで「ウィクトルと一緒にいたい」なんて言ってはいられないから、私は迷わずに行く。
「何かあれば気軽に申し付けて下さいね」
「えぇ。頼りにしてるわ」
リベルテも、帝国軍に勤めていた時には、こんなことになるとは思っていなかっただろう。私に付き添って劇場へ向かう瞬間なんて、きっと想像しなかったはずだ。
「ウタ様、緊張なさっているのでございますか?」
自動運転車の中で、リベルテはそんなことを言ってきた。
「え、えぇ。まぁ。そうね」
「力を抜いて、気楽に、が大切でございますよ」
それができればどんなに良いか。
私だって、望んで緊張しているわけではない。
本当ならこんな危機的状況におかれたような心境になんてなりたくない。穏やかな心でその時を迎えたい。緊張など微塵もない状態で挑めるのがベストだということは、私だって気づいている。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説



婚約者の様子がおかしい。明らかに不自然。そんな時、知り合いから、ある情報を得まして……?
四季
恋愛
婚約者の様子がおかしい。
明らかに不自然。
※展開上、一部汚い描写などがあります。ご了承ください。m(_ _)m

婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。しかしその夜……。
四季
恋愛
婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。
しかしその夜……。
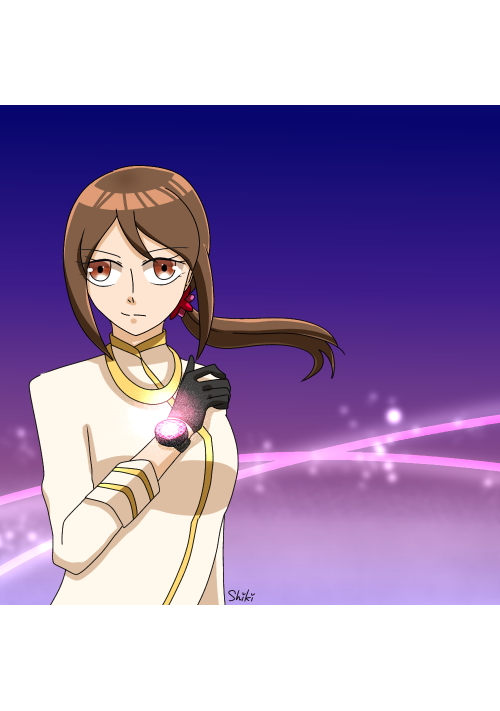
暁のカトレア
四季
恋愛
レヴィアス帝国に謎の生物 "化け物" が出現するようになり約十年。
平凡な毎日を送っていた齢十八の少女 マレイ・チャーム・カトレアは、一人の青年と出会う。
そして、それきっかけに、彼女の人生は大きく動き出すのだった。
※ファンタジー・バトル要素がやや多めです。
※2018.4.7~2018.9.5 執筆

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。

息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。~黙って耐えているのはもう嫌です~
四季
恋愛
息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















