154 / 209
153話「ウタの寂しさ」
しおりを挟む
やがて到着したのは、白く塗られた鉄製の門の前。鉄製と言っても物騒な雰囲気ではなく、芸術作品のような細やかなデザインの門である。非常に細かい形であるにもかかわらずすべての面を見事に白く塗りきれているのが凄いな、なんて関係のないことを考えてしまった。
アイーナは片手でその小さめの門を開ける。
私を門の向こう側へと導いてくれた。
それからも彼女の背を追うようにして足を動かし続ける。
地面には芝生のような草が生えていた。足の裏に、しっかりしつつも柔らかいような独特の感覚。詰め物多めの羽毛布団の上を歩いているかのようだ。
歩くこと一二分、広いところへ出た。
アイーナの家の庭なのだろうか、一面緑に覆われている。庭なら放っておいても草が生えるだろうが、そういった覆われ方ではない。素人にでも整備されていることが分かるような仕上がり。
「綺麗なところですね。お庭ですか?」
「はい。ラインがまだ小さかった頃には、いつもここで遊んだのですよ。水遊びをしたり、走り回ったり。……あの頃は幸せでした」
そう述べるアイーナの表情は、まるで秋の夕暮れのよう。また、恋人との永遠の別れを経験した女性のようでもある。腹の前で重ねた両手からさえ、虚しさをはらんだ哀愁が漂ってきている。
「こちらが現在の簡易的な墓です」
アイーナが紹介してくれたのは、庭に設置された、石造りの小さな墓。
ラインが眠る場所だった。
「息子さんの……?」
「はい。いずれはもう少し立派な物を作ろうと思っていますが」
「そうなんですね」
「ここで歌っていただきたくて。構いませんか?」
アイーナはゆっくりと頭を下げ、一礼してくれる。
私は頭を下げてもらえるような立場ではない——そう思うからこそ、礼をされると不思議な気持ちになった。
「もちろんです。歌わせて下さい」
あの時、私たちには余裕がなかった。できるなら戦いたくないと思い、殺し合いなんてしたくないと思っていた。けれども、穏やかな道を行くことはどうしてもできなくて。結局、あんな結末になってしまった。
手を取って、笑い合える道があったなら。
どんなに良かっただろう。
「ありがとうございます……! ラインも喜びます……!」
綺麗事を言っているだけと馬鹿にされるかもしれない。
なんだかんだ言って自分たちのことしか考えていないと責められるかもしれない。
どちらも事実だ。私も結局ただの人間で、己のために他者を蹴散らしてきた。だから、何と言われても責められても、反論する権利は私にはないのだろう。
それでも、今は歌を。
救われなかった命に、私がただ一つできることを。
——歌が終わり、訪れるのは静寂。
私は何も言えない。唇を結んだまま、小さな石の墓を見つめる。私は彼に対して述べられる言葉を持っていない。だから口を開けなかった。ただじっと見ていることしかできない。墓へ視線を向け、その向こうにいる何かを見つめるように、佇む。
——やがて、静寂にも終わりが来る。
歌が終わった後、第一声を発したのは、アイーナ。
「ありがとうございました」
アイーナは再び丁寧にお辞儀をして、それから少し笑みを浮かべる。
「……こちらこそ、ありがとうございました」
「いいえ。礼を述べるべきはこちらです」
「……そんなこと」
「改めて、礼を言わせて下さい。本当にありがとうございました」
歌は私に幸せをくれた。
歌うことは私を楽しくしてくれた。
けれども、なぜだろう。今はどうしても明るい気分にはなれない。
ラインと交流した時間というのは、本当に、決して長いものではなかった。それでも、彼が向けてくれた輝いた目をいまだに忘れられない。その人の記憶がどれだけ心に残るか、というのは、必ずしも過ごした時間に比例するものではないのかもしれない。
「息子もきっと喜んでいると思います」
「……私も、嬉しいです」
小さく返すと、アイーナは驚いた顔をした。
「ウタさんが? なぜ?」
俯き、暫し考える。
なぜ? にしっかりとした言葉で答えるのは簡単なことではない。
「……上手く言えないです。けど、私の歌を必要としてもらえて嬉しかった。そんな気がします」
最終的に、きちんとした返答を考えることは放棄した。思い付いた範囲で答えることにしたのだ。拙い言葉選びでもいい、と心を決めて、私は答えた。
「ウタさんの歌なら多くの人が必要としているのでは?」
「いえ、そんなものでもありません」
「まぁ。そうだったのですか。驚きました」
アイーナは困ったように少し黙った後、静かにそう言い放った。
「でも、誰か一人でも必要としてくれるなら……私はそれだけで幸せです」
綺麗なふりをしているだけの言葉。そう思われるだろうか。そんな心配が胸の内になかったかと問われれば、きっぱり「なかった」と答えることはできないかもしれない。
けれども、この時発した言葉が偽りのものでないということは確かだ。
人の心なんて不安定なもの。だが、それでも、述べた言葉は嘘ではない。もし仮に百パーセントの真実ではないとしても、少なくとも九十九パーセントは真実である。
その日の晩はアイーナの家に泊めてもらうこととなった。
彼女の家は、一人で過ごすには広過ぎるような家で、どことなく寂しげな空気が漂っている。それほど寒い日ではないというのに、廊下は妙に寒かった。足下から冷える、というような寒さである。
私は空いていた部屋に泊まらせてもらい、さらに、夕食と朝食を振る舞ってもらってしまった。申し訳なさは多少あったが、アイーナが優しく接してくれるからか、胸の苦しさはそこまで酷くはならなかった。
美味しいものを食べさせてもらい、立派なベッドで寝かせてもらって。
おかげで非常に快適な一泊二日となった。
「ありがとうございました。アイーナさん」
「いえいえ。こちらこそ、ありがとうございました。歌を披露していただけたことに心から感謝しています」
別れしな、私はアイーナと言葉を交わす。
ラインがそうであったように、彼女もまた善良な人だった。出会って二日目だというのに、離れなくてはならないことに辛さを感じる。
「アイーナさん、どうかお元気で」
「えぇ……ウタさんこそ、体調崩されないように」
私は一礼して自動運転車へ乗り込む。
またいつか会えるだろうか、アイーナに。
こうして、私の仕事は一つ終わった。
お礼として小遣い程度のお金を貰ったが、収穫はそれ以上のものがあったように思う。
アイーナは片手でその小さめの門を開ける。
私を門の向こう側へと導いてくれた。
それからも彼女の背を追うようにして足を動かし続ける。
地面には芝生のような草が生えていた。足の裏に、しっかりしつつも柔らかいような独特の感覚。詰め物多めの羽毛布団の上を歩いているかのようだ。
歩くこと一二分、広いところへ出た。
アイーナの家の庭なのだろうか、一面緑に覆われている。庭なら放っておいても草が生えるだろうが、そういった覆われ方ではない。素人にでも整備されていることが分かるような仕上がり。
「綺麗なところですね。お庭ですか?」
「はい。ラインがまだ小さかった頃には、いつもここで遊んだのですよ。水遊びをしたり、走り回ったり。……あの頃は幸せでした」
そう述べるアイーナの表情は、まるで秋の夕暮れのよう。また、恋人との永遠の別れを経験した女性のようでもある。腹の前で重ねた両手からさえ、虚しさをはらんだ哀愁が漂ってきている。
「こちらが現在の簡易的な墓です」
アイーナが紹介してくれたのは、庭に設置された、石造りの小さな墓。
ラインが眠る場所だった。
「息子さんの……?」
「はい。いずれはもう少し立派な物を作ろうと思っていますが」
「そうなんですね」
「ここで歌っていただきたくて。構いませんか?」
アイーナはゆっくりと頭を下げ、一礼してくれる。
私は頭を下げてもらえるような立場ではない——そう思うからこそ、礼をされると不思議な気持ちになった。
「もちろんです。歌わせて下さい」
あの時、私たちには余裕がなかった。できるなら戦いたくないと思い、殺し合いなんてしたくないと思っていた。けれども、穏やかな道を行くことはどうしてもできなくて。結局、あんな結末になってしまった。
手を取って、笑い合える道があったなら。
どんなに良かっただろう。
「ありがとうございます……! ラインも喜びます……!」
綺麗事を言っているだけと馬鹿にされるかもしれない。
なんだかんだ言って自分たちのことしか考えていないと責められるかもしれない。
どちらも事実だ。私も結局ただの人間で、己のために他者を蹴散らしてきた。だから、何と言われても責められても、反論する権利は私にはないのだろう。
それでも、今は歌を。
救われなかった命に、私がただ一つできることを。
——歌が終わり、訪れるのは静寂。
私は何も言えない。唇を結んだまま、小さな石の墓を見つめる。私は彼に対して述べられる言葉を持っていない。だから口を開けなかった。ただじっと見ていることしかできない。墓へ視線を向け、その向こうにいる何かを見つめるように、佇む。
——やがて、静寂にも終わりが来る。
歌が終わった後、第一声を発したのは、アイーナ。
「ありがとうございました」
アイーナは再び丁寧にお辞儀をして、それから少し笑みを浮かべる。
「……こちらこそ、ありがとうございました」
「いいえ。礼を述べるべきはこちらです」
「……そんなこと」
「改めて、礼を言わせて下さい。本当にありがとうございました」
歌は私に幸せをくれた。
歌うことは私を楽しくしてくれた。
けれども、なぜだろう。今はどうしても明るい気分にはなれない。
ラインと交流した時間というのは、本当に、決して長いものではなかった。それでも、彼が向けてくれた輝いた目をいまだに忘れられない。その人の記憶がどれだけ心に残るか、というのは、必ずしも過ごした時間に比例するものではないのかもしれない。
「息子もきっと喜んでいると思います」
「……私も、嬉しいです」
小さく返すと、アイーナは驚いた顔をした。
「ウタさんが? なぜ?」
俯き、暫し考える。
なぜ? にしっかりとした言葉で答えるのは簡単なことではない。
「……上手く言えないです。けど、私の歌を必要としてもらえて嬉しかった。そんな気がします」
最終的に、きちんとした返答を考えることは放棄した。思い付いた範囲で答えることにしたのだ。拙い言葉選びでもいい、と心を決めて、私は答えた。
「ウタさんの歌なら多くの人が必要としているのでは?」
「いえ、そんなものでもありません」
「まぁ。そうだったのですか。驚きました」
アイーナは困ったように少し黙った後、静かにそう言い放った。
「でも、誰か一人でも必要としてくれるなら……私はそれだけで幸せです」
綺麗なふりをしているだけの言葉。そう思われるだろうか。そんな心配が胸の内になかったかと問われれば、きっぱり「なかった」と答えることはできないかもしれない。
けれども、この時発した言葉が偽りのものでないということは確かだ。
人の心なんて不安定なもの。だが、それでも、述べた言葉は嘘ではない。もし仮に百パーセントの真実ではないとしても、少なくとも九十九パーセントは真実である。
その日の晩はアイーナの家に泊めてもらうこととなった。
彼女の家は、一人で過ごすには広過ぎるような家で、どことなく寂しげな空気が漂っている。それほど寒い日ではないというのに、廊下は妙に寒かった。足下から冷える、というような寒さである。
私は空いていた部屋に泊まらせてもらい、さらに、夕食と朝食を振る舞ってもらってしまった。申し訳なさは多少あったが、アイーナが優しく接してくれるからか、胸の苦しさはそこまで酷くはならなかった。
美味しいものを食べさせてもらい、立派なベッドで寝かせてもらって。
おかげで非常に快適な一泊二日となった。
「ありがとうございました。アイーナさん」
「いえいえ。こちらこそ、ありがとうございました。歌を披露していただけたことに心から感謝しています」
別れしな、私はアイーナと言葉を交わす。
ラインがそうであったように、彼女もまた善良な人だった。出会って二日目だというのに、離れなくてはならないことに辛さを感じる。
「アイーナさん、どうかお元気で」
「えぇ……ウタさんこそ、体調崩されないように」
私は一礼して自動運転車へ乗り込む。
またいつか会えるだろうか、アイーナに。
こうして、私の仕事は一つ終わった。
お礼として小遣い程度のお金を貰ったが、収穫はそれ以上のものがあったように思う。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説



婚約者の様子がおかしい。明らかに不自然。そんな時、知り合いから、ある情報を得まして……?
四季
恋愛
婚約者の様子がおかしい。
明らかに不自然。
※展開上、一部汚い描写などがあります。ご了承ください。m(_ _)m

婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。しかしその夜……。
四季
恋愛
婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。
しかしその夜……。

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。
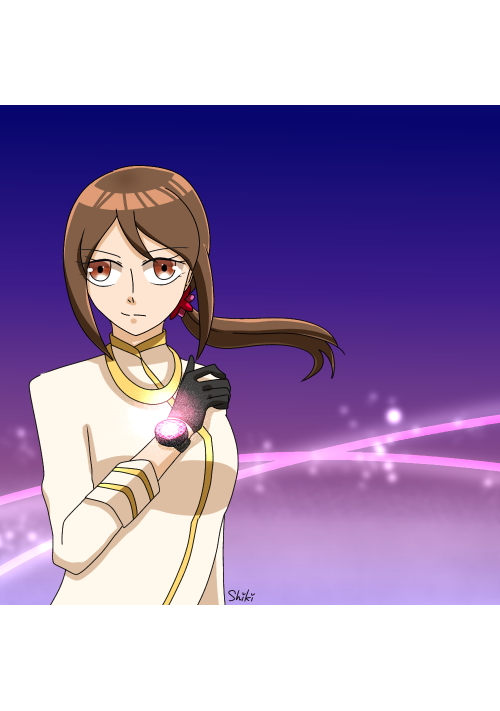
暁のカトレア
四季
恋愛
レヴィアス帝国に謎の生物 "化け物" が出現するようになり約十年。
平凡な毎日を送っていた齢十八の少女 マレイ・チャーム・カトレアは、一人の青年と出会う。
そして、それきっかけに、彼女の人生は大きく動き出すのだった。
※ファンタジー・バトル要素がやや多めです。
※2018.4.7~2018.9.5 執筆


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















