125 / 209
124話「ウィクトルの渾身の」
しおりを挟む
アナシエアとの入浴を終えて一人で穴へ帰ると、偶然ウィクトルが着替えているところだった。
立場が逆だったら「ドキッ! お着替えシーン」みたいな雰囲気になったのだろうか。
「戻ったか! 今ちょうど肌着が届いたところで——」
「……服を着て」
「すまん」
もはや私たちは家族みたいなもの。それゆえ、ウィクトルが着替えていたくらいでは特別な感情は芽生えない。心が揺れることもない。そんな初々しさはとうに消え去っている。
「で、肌着が届いたと言ったかしら」
風呂上がりの肌はまだどことなく熱を持っている。少々浸かり過ぎただろうか。
取り敢えずワラの上に腰を下ろす。
「あぁ。必要な物を尋ねられたのでな、肌着と。そうしたら、すぐに届いた」
「そうだったの」
希望してすぐに届くとは驚きだ。果実以外の食べ物はあれほど頑なに与えてくれないのに、肌着ならすぐに与えてくれるのか。果実以外の食物が貰えないのは、やはり、ラブブラブブラブラ族の文化的に用意してはならないからなのだろうか。
「肌着は君の分もある」
「えっ」
風呂上がりに着たのは、入浴前と同じものだ。
もう少し早めに貰えたら、風呂上がりに着替えられたというのに。
「二人分頼んだからな。ウタくんも着替えてはどうだ」
「頼んでくれてありがとう。でも、私もここで着替えるの?」
「面倒だろうが、着替えて心地よいことは確かだ」
少し空けて、ウィクトルは続ける。
「見られて嫌なら私は反対を向いておくことにしよう」
「……反対向かない選択肢があったことが怖いわ」
この時ばかりは飾り気のない低い声を発してしまった。
だっておかしくない? 年頃の女子が着替えるというのに、目を逸らさない選択肢が存在するなんて。反対を向いておくのが当たり前ではないの?
「これだ」
ウィクトルは何事もなかったかのように、四角く畳まれた肌着を渡してくる。
「白いのね。普通に肌着ね」
「あぁ。上半身に着用するものだ」
上半身に着用するもの……言い方。
「ありがとう。じゃ、着替えるわ」
言いたいことは色々あるが、細かいことをぐだぐだ言っても仕方がない。
それより早く着替えたい。
「反対を向く、目を閉じる、ワラに顔を突っ込む、どれがいい」
「……渾身のギャグ?」
「あぁ、冗談だ」
「何というか……ちょっと意外」
こんなタイミングで冗談をぶっ込んでこられるとは思っていなかったので少し驚いた。でも、冗談を言う余裕ができたのだと捉えたら、嬉しい気もする。
「でも、ウィクトルに冗談を言ってもらえるなんて、嬉しいわ」
「笑ってもらえないかもしれないと心配していた」
「そうね。くだらないわ。でも、ここは敢えて『ワラに顔を突っ込む』を選択したいわね」
その日の夜、眠りにつこうと横になっていたら、ウィクトルが呟いた。
「リベルテはどうしているだろう」
ワラを厚めに敷いているため、ゴツゴツした地面の上に横たわっても不快感はない。むしろ、どことなくほっこりするくらい柔らかい。
「心配?」
「そうだな……何も言わずに出てきてしまった」
ウィクトルはイヴァンの命令より私を選んでくれた。それはとても嬉しいことで。けれども、それが彼をリベルテと引き離すことになってしまったことは、嬉しいことではない。
二人は互いを必要としていた。
ウィクトルはリベルテを頼っていたし、リベルテもウィクトルを慕っていた——そんな二人を引き裂く形になってしまったことには、罪悪感を抱かずにはいられない。
「……やっぱり後悔してる?」
静寂の中、私は尋ねる。
「いや。もう悔やんではいない。どのみち君をこの手で殺めることは私にはできなかったのだから……仕方のないことだ」
私は彼を血濡れの道から救い出したかった。手を赤く染めることが、穢れることが、彼の生き甲斐でないならば。それなら、もうそんなことはさせたくないと、強くそう思った。
でも、それは正しかったのだろうか。
今になって少し不安に思ったりする。
私自身は選択を後悔してはいない。だが、ウィクトルを無理矢理引っ張ってきてしまって良かったのだろうか、という不安は存在しないわけではなくて。
「残りたかった? 向こうに。私を殺さないために無理をしたの?」
「君のせいにする気はない」
「じゃあやっぱり……残りたかったのね」
刹那、ウィクトルは勢いよく上半身を縦にした。
「違う! なぜそうなる!?」
突然の大きな声。私は戸惑うことしかできない。
その数秒後、ウィクトルは気まずそうな顔をして「……すまん」と謝罪。
私が困惑していることに気がついたみたいだ。
「だが、勘違いしないでくれ。私は未練たらたらでここにいるわけではない」
「……なら良いのだけれど」
「どんな未来が待っているのか、それは分からない。が、それでも私は君と行くと決めた。リベルテのことは気になるが……それは言っても仕方ないな。もう忘れてくれ」
その日の晩、私はアナシエアに起こされた。
「起きて。起きて下さい。ウタ」
「アナシエアさん……?」
隣のウィクトルはまだ眠ったまま。アナシエアは、私だけを起こすつもりだったのか、私が偶々先に起こされただけなのか。そこははっきりしない。が、起きるよう言われたことは事実。
「非常事態です」
「えっ……」
「先ほど、侵入者がありました。帝国の人間と思われるとのことです」
まさか追っ手?
いや、今の帝国に追っ手を出す余裕があるだろうか?
イヴァンの手の者か、ビタリーの手の者か、恐らくはそのどちらかだろう。シャルティエラもウィクトルを殺そうとしていたから、彼女の手下という可能性もゼロではないが。
「そんな……!」
「安心して下さい、ウタ。ここに攻め込んで生き延びた人間など、これまで一人もいないのですから。ただ、万が一に備え、起こしに来ました」
いつもと変わらず獅子の面をつけているアナシエアは、優しい言葉をかけてくれる。しかし、その声は、形容し難い冷たさをはらんでいた。
「あ、ありがとうございます……」
「しばらくここにいますね。安心して下さい」
「そんな。申し訳ないです」
「良いのです。ふふ。実は、帝国の人間以外には我々は親切なのですよ」
帝国の人間。それ以外の人間。
ウィクトルがどちらに分類されているのかが気になるところだ。
立場が逆だったら「ドキッ! お着替えシーン」みたいな雰囲気になったのだろうか。
「戻ったか! 今ちょうど肌着が届いたところで——」
「……服を着て」
「すまん」
もはや私たちは家族みたいなもの。それゆえ、ウィクトルが着替えていたくらいでは特別な感情は芽生えない。心が揺れることもない。そんな初々しさはとうに消え去っている。
「で、肌着が届いたと言ったかしら」
風呂上がりの肌はまだどことなく熱を持っている。少々浸かり過ぎただろうか。
取り敢えずワラの上に腰を下ろす。
「あぁ。必要な物を尋ねられたのでな、肌着と。そうしたら、すぐに届いた」
「そうだったの」
希望してすぐに届くとは驚きだ。果実以外の食べ物はあれほど頑なに与えてくれないのに、肌着ならすぐに与えてくれるのか。果実以外の食物が貰えないのは、やはり、ラブブラブブラブラ族の文化的に用意してはならないからなのだろうか。
「肌着は君の分もある」
「えっ」
風呂上がりに着たのは、入浴前と同じものだ。
もう少し早めに貰えたら、風呂上がりに着替えられたというのに。
「二人分頼んだからな。ウタくんも着替えてはどうだ」
「頼んでくれてありがとう。でも、私もここで着替えるの?」
「面倒だろうが、着替えて心地よいことは確かだ」
少し空けて、ウィクトルは続ける。
「見られて嫌なら私は反対を向いておくことにしよう」
「……反対向かない選択肢があったことが怖いわ」
この時ばかりは飾り気のない低い声を発してしまった。
だっておかしくない? 年頃の女子が着替えるというのに、目を逸らさない選択肢が存在するなんて。反対を向いておくのが当たり前ではないの?
「これだ」
ウィクトルは何事もなかったかのように、四角く畳まれた肌着を渡してくる。
「白いのね。普通に肌着ね」
「あぁ。上半身に着用するものだ」
上半身に着用するもの……言い方。
「ありがとう。じゃ、着替えるわ」
言いたいことは色々あるが、細かいことをぐだぐだ言っても仕方がない。
それより早く着替えたい。
「反対を向く、目を閉じる、ワラに顔を突っ込む、どれがいい」
「……渾身のギャグ?」
「あぁ、冗談だ」
「何というか……ちょっと意外」
こんなタイミングで冗談をぶっ込んでこられるとは思っていなかったので少し驚いた。でも、冗談を言う余裕ができたのだと捉えたら、嬉しい気もする。
「でも、ウィクトルに冗談を言ってもらえるなんて、嬉しいわ」
「笑ってもらえないかもしれないと心配していた」
「そうね。くだらないわ。でも、ここは敢えて『ワラに顔を突っ込む』を選択したいわね」
その日の夜、眠りにつこうと横になっていたら、ウィクトルが呟いた。
「リベルテはどうしているだろう」
ワラを厚めに敷いているため、ゴツゴツした地面の上に横たわっても不快感はない。むしろ、どことなくほっこりするくらい柔らかい。
「心配?」
「そうだな……何も言わずに出てきてしまった」
ウィクトルはイヴァンの命令より私を選んでくれた。それはとても嬉しいことで。けれども、それが彼をリベルテと引き離すことになってしまったことは、嬉しいことではない。
二人は互いを必要としていた。
ウィクトルはリベルテを頼っていたし、リベルテもウィクトルを慕っていた——そんな二人を引き裂く形になってしまったことには、罪悪感を抱かずにはいられない。
「……やっぱり後悔してる?」
静寂の中、私は尋ねる。
「いや。もう悔やんではいない。どのみち君をこの手で殺めることは私にはできなかったのだから……仕方のないことだ」
私は彼を血濡れの道から救い出したかった。手を赤く染めることが、穢れることが、彼の生き甲斐でないならば。それなら、もうそんなことはさせたくないと、強くそう思った。
でも、それは正しかったのだろうか。
今になって少し不安に思ったりする。
私自身は選択を後悔してはいない。だが、ウィクトルを無理矢理引っ張ってきてしまって良かったのだろうか、という不安は存在しないわけではなくて。
「残りたかった? 向こうに。私を殺さないために無理をしたの?」
「君のせいにする気はない」
「じゃあやっぱり……残りたかったのね」
刹那、ウィクトルは勢いよく上半身を縦にした。
「違う! なぜそうなる!?」
突然の大きな声。私は戸惑うことしかできない。
その数秒後、ウィクトルは気まずそうな顔をして「……すまん」と謝罪。
私が困惑していることに気がついたみたいだ。
「だが、勘違いしないでくれ。私は未練たらたらでここにいるわけではない」
「……なら良いのだけれど」
「どんな未来が待っているのか、それは分からない。が、それでも私は君と行くと決めた。リベルテのことは気になるが……それは言っても仕方ないな。もう忘れてくれ」
その日の晩、私はアナシエアに起こされた。
「起きて。起きて下さい。ウタ」
「アナシエアさん……?」
隣のウィクトルはまだ眠ったまま。アナシエアは、私だけを起こすつもりだったのか、私が偶々先に起こされただけなのか。そこははっきりしない。が、起きるよう言われたことは事実。
「非常事態です」
「えっ……」
「先ほど、侵入者がありました。帝国の人間と思われるとのことです」
まさか追っ手?
いや、今の帝国に追っ手を出す余裕があるだろうか?
イヴァンの手の者か、ビタリーの手の者か、恐らくはそのどちらかだろう。シャルティエラもウィクトルを殺そうとしていたから、彼女の手下という可能性もゼロではないが。
「そんな……!」
「安心して下さい、ウタ。ここに攻め込んで生き延びた人間など、これまで一人もいないのですから。ただ、万が一に備え、起こしに来ました」
いつもと変わらず獅子の面をつけているアナシエアは、優しい言葉をかけてくれる。しかし、その声は、形容し難い冷たさをはらんでいた。
「あ、ありがとうございます……」
「しばらくここにいますね。安心して下さい」
「そんな。申し訳ないです」
「良いのです。ふふ。実は、帝国の人間以外には我々は親切なのですよ」
帝国の人間。それ以外の人間。
ウィクトルがどちらに分類されているのかが気になるところだ。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説


婚約者の様子がおかしい。明らかに不自然。そんな時、知り合いから、ある情報を得まして……?
四季
恋愛
婚約者の様子がおかしい。
明らかに不自然。
※展開上、一部汚い描写などがあります。ご了承ください。m(_ _)m


婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。しかしその夜……。
四季
恋愛
婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。
しかしその夜……。

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。
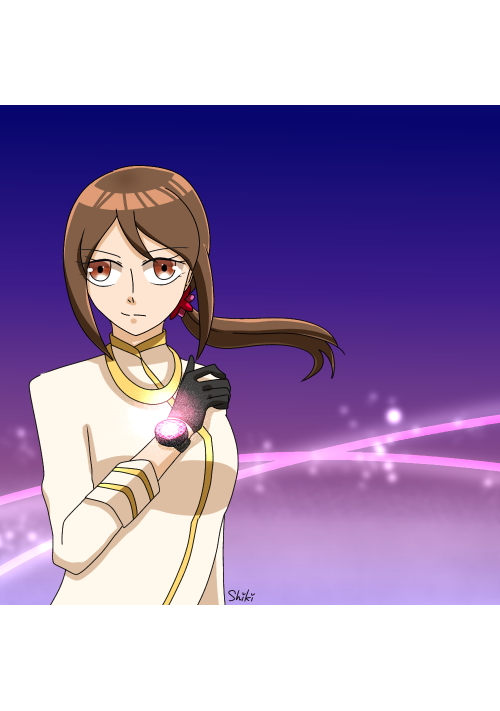
暁のカトレア
四季
恋愛
レヴィアス帝国に謎の生物 "化け物" が出現するようになり約十年。
平凡な毎日を送っていた齢十八の少女 マレイ・チャーム・カトレアは、一人の青年と出会う。
そして、それきっかけに、彼女の人生は大きく動き出すのだった。
※ファンタジー・バトル要素がやや多めです。
※2018.4.7~2018.9.5 執筆

淫らな蜜に狂わされ
歌龍吟伶
恋愛
普段と変わらない日々は思わぬ形で終わりを迎える…突然の出会い、そして体も心も開かれた少女の人生録。
全体的に性的表現・性行為あり。
他所で知人限定公開していましたが、こちらに移しました。
全3話完結済みです。

断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















