123 / 209
122話「ウタの洞窟内での生活」
しおりを挟む
その日から、ラブブラブブラブラの村での暮らしが始まった。
最初は一日だけ保護してもらうという話だったのだが、なんだかんだで、居座ることになってしまって。私はウィクトルと、薄暗い洞窟の中で過ごした。
ウィクトルは、アナシエアの配慮によって、手当てを受けられることに。
水で洗ったり、消毒効果を持つという液体を塗ったり、瞼に負った傷に処置を施してもらうことができた。
瞼という繊細な場所に負った傷。私はそれを気にしていた。それほど深い傷には見えなかったが、それでも、気にならなかったと言ったら嘘になる。外からはたいした傷でなさそうに見えても実は酷い傷だった、という可能性もゼロではない。だからこそ、心配せずにはいられなかったのである。
けれども、処置を受けられたなら、少しは安心できるというもの。
少なくともずっと放置よりは良いだろう。
ラブブラブブラブラ族の中での暮らし。それは、最初、かなり馴染めないものだった。私たち二人のための穴が用意されていたからまだ良かったけれど、特にその食生活には違和感しか覚えず。果物しか食べない、という思想が、正直理解できなかった。
私も果物を食さないわけではない。極めて苦手ということもない。だが、果物を主食のように食べるとなると、どうしても不自然さを感じてしまうのだ。用意されていた果物たちは甘くて美味しかったけれど、果物だけをがっつり食べるという行為はどうもしっくりこなくて。それは、ウィクトルも同じのようだった。
途中、私は幾度か、アナシエアに相談した。
果物以外の食べ物はないのかと。
もし果物以外の食べ物が手に入るなら分けて欲しい。そう頼んでみたけれど、アナシエアが頷くことはなかった。なんせ、彼女の頭には「果物でないものを食べる」という考えが存在しないのだ。彼女は、果実の他のものを口にすれば穢れると、本気でそう思っているようだった。
「もう何日も果物しか食べていないわね……さすがに飽きてきたわ」
「そうだな」
「ウィクトルも? 飽きてきた?」
「あぁ。少しは別のものを食べたい、と思わざるを得ない」
ここへ来てから既に数日。
特にすることもないので、私はウィクトルと二人で言葉を交わす。
「そうよね。やっぱり、もう一度頼んでみようかしら……」
「ここにいては、果物以外の食べ物を貰える可能性は低そうだ。そろそろ出るか」
ここを出る、という発想は私にはなかった。
なんせここは安全だったから。
「……外へ行くの?」
「嫌か」
「いいえ。ただ……外へ出たら、また危険な目に遭うかもしれないわ。戦いに巻き込まれる可能性だって、ゼロじゃない。せめて貴方の傷が治るまででも……ここにとどまらない?」
食生活に多少の不満はあるけれど、ここにいればイヴァンやその手下に命を狙われる心配はない。村にいれば、醜い争いに巻き込まれずに済む。
そういう意味では、ここに滞在するメリットは大きいのではないだろうか。
何事にもメリットとデメリットが存在する。どちらが大きいか、そのバランスによって、選択を変えていくことが必要。そう考えると、今は、ここに滞在することを選ぶ方が良いのではないだろうか。私はそんな風に思っている。
「だが、果物食はウタくんも嫌なのでは?」
ワラの上にあぐらをかいていたウィクトルが、私の方へ視線を向けつつ尋ねてきた。
「確かに飽きつつはあるけれど……でも、それは平気。短期間で命に影響があるわけではないし」
糖分が多そうという不安はある。
けれど、血濡れの道へ引き戻されるくらいなら、糖分過多に不安を抱く方がまだ良いかもしれない。食事量は、多少、自力で調整できるから。
「そうか。ならここで過ごすか」
「ウィクトルが嫌というなら考えるけれど。どうかしら」
「私はべつに構わない。君と共にあれるなら」
何食わぬ顔で彼はそんなことを言った。
私は「口説き文句みたいね」と苦笑しつつ返しておく。
「なら、もう少しここにいましょっか」
「そうだな」
外は夜になっただろうと推測される頃、アナシエアが私たち二人の穴に訪問してきた。
「ウタ。身を流しに行きませんか」
「アナシエアさん」
「今回は共に行きましょう?」
ここへ来てから一度は入浴した。だが、毎日は体を流せていない。ラブブラブブラブラ族には毎日体を洗うという習慣がないようだから仕方ないといえば仕方ないのだが、仕方ないと思いつつも、やはりどうしても、体を流したいと欲を持ってしまう。
だから、入浴の誘いは嬉しい。
体を洗える——それは非常に心地よいことだ。
「構わないのですか……?」
アナシエアは厳つい獅子の面を着用しているが、その声は柔らかく優しげ。その声を耳にしていたら、木漏れ日を浴びているかのような気分になってくるほどだ。
「えぇ。ウタを誘おうと思い、来たのですよ」
「ではよろしくお願いします!」
「ふふ。積極的に誘いに乗ってくれて嬉しいですよ。感謝します」
どうやら今は杖を持っていないみたいだ。両手を腹の前で重ねている。指一本一本が指先までぴんと伸びていて、育ちの良さを感じさせる。
周囲はすべて岩の風景。浴場の脇で服を脱ぐ。
松明が多めに置かれているので、他のところより明るい。それでも外にいるようで、そこで裸になるというのは何とも言えない気分になる。
「体を流し、浸かりましょう」
「は、はい」
アナシエアがなぜ私を誘ってくれたのかは、まだ不明のまま。そこに何か意図があるのか、ただ何でもなく誘っただけか、そこは明瞭になっていない。けれど、誘ってくれた意図なんて、そこまで気にすることはないのかもしれない。
木の桶を手に取り、流れている水をすくう。
水はひんやりしている。
その後、アナシエアの行動を見習って、桶の中の水を私の体にかけた。冷たい水で体を流すと、全身の毛穴が縮んでいるような気分になる。寒い。でも、気持ち良さはある。
「流せましたか?」
「もう少し待っていただけませんか」
「構いませんよ。思う存分流して下さいね」
「は、はい。ありがとうございます」
アナシエアはある程度私の自由を許してくれる。
奴隷のような扱いを受けていないということには、感謝せねばならない。
「流し終わりました」
時間をかけて体を流し、納得がいくと、私はアナシエアに完了を告げる。
「では浸かりましょう?」
「あ、はい!」
最初は一日だけ保護してもらうという話だったのだが、なんだかんだで、居座ることになってしまって。私はウィクトルと、薄暗い洞窟の中で過ごした。
ウィクトルは、アナシエアの配慮によって、手当てを受けられることに。
水で洗ったり、消毒効果を持つという液体を塗ったり、瞼に負った傷に処置を施してもらうことができた。
瞼という繊細な場所に負った傷。私はそれを気にしていた。それほど深い傷には見えなかったが、それでも、気にならなかったと言ったら嘘になる。外からはたいした傷でなさそうに見えても実は酷い傷だった、という可能性もゼロではない。だからこそ、心配せずにはいられなかったのである。
けれども、処置を受けられたなら、少しは安心できるというもの。
少なくともずっと放置よりは良いだろう。
ラブブラブブラブラ族の中での暮らし。それは、最初、かなり馴染めないものだった。私たち二人のための穴が用意されていたからまだ良かったけれど、特にその食生活には違和感しか覚えず。果物しか食べない、という思想が、正直理解できなかった。
私も果物を食さないわけではない。極めて苦手ということもない。だが、果物を主食のように食べるとなると、どうしても不自然さを感じてしまうのだ。用意されていた果物たちは甘くて美味しかったけれど、果物だけをがっつり食べるという行為はどうもしっくりこなくて。それは、ウィクトルも同じのようだった。
途中、私は幾度か、アナシエアに相談した。
果物以外の食べ物はないのかと。
もし果物以外の食べ物が手に入るなら分けて欲しい。そう頼んでみたけれど、アナシエアが頷くことはなかった。なんせ、彼女の頭には「果物でないものを食べる」という考えが存在しないのだ。彼女は、果実の他のものを口にすれば穢れると、本気でそう思っているようだった。
「もう何日も果物しか食べていないわね……さすがに飽きてきたわ」
「そうだな」
「ウィクトルも? 飽きてきた?」
「あぁ。少しは別のものを食べたい、と思わざるを得ない」
ここへ来てから既に数日。
特にすることもないので、私はウィクトルと二人で言葉を交わす。
「そうよね。やっぱり、もう一度頼んでみようかしら……」
「ここにいては、果物以外の食べ物を貰える可能性は低そうだ。そろそろ出るか」
ここを出る、という発想は私にはなかった。
なんせここは安全だったから。
「……外へ行くの?」
「嫌か」
「いいえ。ただ……外へ出たら、また危険な目に遭うかもしれないわ。戦いに巻き込まれる可能性だって、ゼロじゃない。せめて貴方の傷が治るまででも……ここにとどまらない?」
食生活に多少の不満はあるけれど、ここにいればイヴァンやその手下に命を狙われる心配はない。村にいれば、醜い争いに巻き込まれずに済む。
そういう意味では、ここに滞在するメリットは大きいのではないだろうか。
何事にもメリットとデメリットが存在する。どちらが大きいか、そのバランスによって、選択を変えていくことが必要。そう考えると、今は、ここに滞在することを選ぶ方が良いのではないだろうか。私はそんな風に思っている。
「だが、果物食はウタくんも嫌なのでは?」
ワラの上にあぐらをかいていたウィクトルが、私の方へ視線を向けつつ尋ねてきた。
「確かに飽きつつはあるけれど……でも、それは平気。短期間で命に影響があるわけではないし」
糖分が多そうという不安はある。
けれど、血濡れの道へ引き戻されるくらいなら、糖分過多に不安を抱く方がまだ良いかもしれない。食事量は、多少、自力で調整できるから。
「そうか。ならここで過ごすか」
「ウィクトルが嫌というなら考えるけれど。どうかしら」
「私はべつに構わない。君と共にあれるなら」
何食わぬ顔で彼はそんなことを言った。
私は「口説き文句みたいね」と苦笑しつつ返しておく。
「なら、もう少しここにいましょっか」
「そうだな」
外は夜になっただろうと推測される頃、アナシエアが私たち二人の穴に訪問してきた。
「ウタ。身を流しに行きませんか」
「アナシエアさん」
「今回は共に行きましょう?」
ここへ来てから一度は入浴した。だが、毎日は体を流せていない。ラブブラブブラブラ族には毎日体を洗うという習慣がないようだから仕方ないといえば仕方ないのだが、仕方ないと思いつつも、やはりどうしても、体を流したいと欲を持ってしまう。
だから、入浴の誘いは嬉しい。
体を洗える——それは非常に心地よいことだ。
「構わないのですか……?」
アナシエアは厳つい獅子の面を着用しているが、その声は柔らかく優しげ。その声を耳にしていたら、木漏れ日を浴びているかのような気分になってくるほどだ。
「えぇ。ウタを誘おうと思い、来たのですよ」
「ではよろしくお願いします!」
「ふふ。積極的に誘いに乗ってくれて嬉しいですよ。感謝します」
どうやら今は杖を持っていないみたいだ。両手を腹の前で重ねている。指一本一本が指先までぴんと伸びていて、育ちの良さを感じさせる。
周囲はすべて岩の風景。浴場の脇で服を脱ぐ。
松明が多めに置かれているので、他のところより明るい。それでも外にいるようで、そこで裸になるというのは何とも言えない気分になる。
「体を流し、浸かりましょう」
「は、はい」
アナシエアがなぜ私を誘ってくれたのかは、まだ不明のまま。そこに何か意図があるのか、ただ何でもなく誘っただけか、そこは明瞭になっていない。けれど、誘ってくれた意図なんて、そこまで気にすることはないのかもしれない。
木の桶を手に取り、流れている水をすくう。
水はひんやりしている。
その後、アナシエアの行動を見習って、桶の中の水を私の体にかけた。冷たい水で体を流すと、全身の毛穴が縮んでいるような気分になる。寒い。でも、気持ち良さはある。
「流せましたか?」
「もう少し待っていただけませんか」
「構いませんよ。思う存分流して下さいね」
「は、はい。ありがとうございます」
アナシエアはある程度私の自由を許してくれる。
奴隷のような扱いを受けていないということには、感謝せねばならない。
「流し終わりました」
時間をかけて体を流し、納得がいくと、私はアナシエアに完了を告げる。
「では浸かりましょう?」
「あ、はい!」
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説



婚約者の様子がおかしい。明らかに不自然。そんな時、知り合いから、ある情報を得まして……?
四季
恋愛
婚約者の様子がおかしい。
明らかに不自然。
※展開上、一部汚い描写などがあります。ご了承ください。m(_ _)m

婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。しかしその夜……。
四季
恋愛
婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。
しかしその夜……。

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。
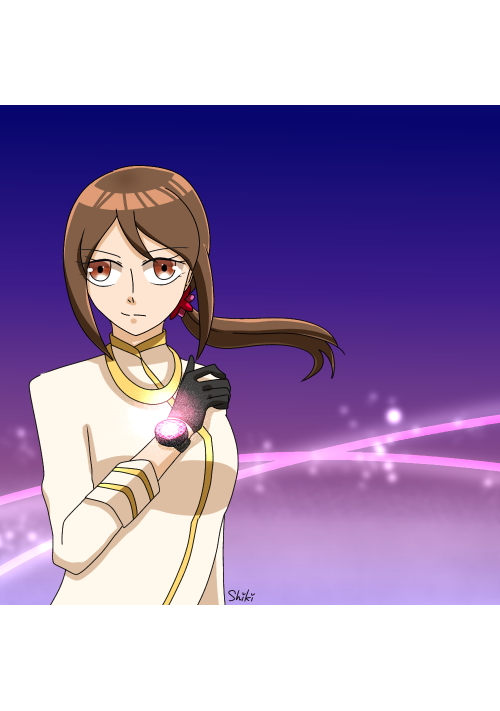
暁のカトレア
四季
恋愛
レヴィアス帝国に謎の生物 "化け物" が出現するようになり約十年。
平凡な毎日を送っていた齢十八の少女 マレイ・チャーム・カトレアは、一人の青年と出会う。
そして、それきっかけに、彼女の人生は大きく動き出すのだった。
※ファンタジー・バトル要素がやや多めです。
※2018.4.7~2018.9.5 執筆

息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。~黙って耐えているのはもう嫌です~
四季
恋愛
息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















