116 / 209
115話「ウタの悔いなき選択」
しおりを挟む
ウィクトルの後ろにいるリベルテは、オロオロしている。時に私へ目をやり、時にイヴァンに目をやりながら、主にはウィクトルの黒い背中を見つめている。
今やウィクトルは、私が知る優しいウィクトルではない。彼の見据える先にあるのが何なのかは不明だが、今の彼の見据える先にあるものは恐らく私には想像もできないようなものなのだろう。
リベルテは、そんなウィクトルに長い間付き添ってきた身。だから、慣れているのだろうな、と想像していた。しかし、今のリベルテの様子を見ていたら、慣れてはいないのではないかと思えてくる。落ち着きのない様子になっているからだ。
「あ、主……本当に、やるつもりなのでございますか……?」
「命令なら仕方ない」
「……ですよね。承知しました」
足音は近づいてくる。
戦いの火蓋が切って落とされるまで、時間はない。
でも。いくらウィクトルが実力者だとしても、軍勢からここにいるすべての人たちを護るなんてことは簡単ではないはず。そんな難しいことを平然と命じるイヴァンは、ある意味酷な人だ。
ウィクトルを信頼しているようなふりをしてはいるけれど、イヴァンは、真の意味でウィクトルを大事にはしていない。きっとそれが真実なのだろう。本当に大事に思っている者に対して無茶な命令を押し付けたりはしないはずだ。
「イクゼイクゼイクゼ!」
「こっちこっち! 早く! 突入するぞー!」
いよいよ、というような声が、入り口の向こうから聞こえてくる。
ウィクトルは僅かに俯いたまま、腰に下げていたレイピアを抜く。
——直後、広間に人が流れ込んできた。
制服をきちんと着た真面目そうな者もいれば、Tシャツにハーフパンツだけのようなラフな服装の者もいる。流れ込んできた人たちに統一感はない。寄せ集めという言葉がよく似合うような人々だ。
——そして、戦いが幕開ける。
それからのことは、理解が追いつかないため、あまり記憶に残らず。私の瞳が捉えたのは、凄まじい惨状だけ。飛び散る飛沫が視界を染め上げ、私の正気を叩き壊していく。想像を遥かに越えた戦いが、場を乱し、一つ一つの生を絶ってゆくのだった。
「ウィクトル!」
私が思わず叫んだのは、そんな乱戦の中だった。
剣一本で幾人もの敵を薙ぎ倒していっていた彼だったが、瞼を切られ、その傷を片手で押さえる。瞼を切った敵は近くにいたリベルテが術で消し飛ばしたが、ウィクトルはすぐには動けない。
イヴァンも見ているこの場所でウィクトルと親しげな行動はしないでおこうと考えていたのだが、私はたまらずついに駆け寄ってしまった。
「大丈夫なの!?」
「あぁ。……君は下がっていてくれ、危ない」
「手当てしなくちゃ」
「いや、いい。手当てなど、いちいちしている暇はない」
厳密には、ウィクトルとリベルテの二人だけが交戦しているわけではない。近づいてきた敵をワインの瓶で撃退する、というような素人丸出しの戦いを含めるならば、二人より多くの者が敵の軍勢と戦っている。
でも、それでも、数ではこちらが圧倒的に不利だ。
まともに戦える人間の数が少なすぎる。
もちろん、素人が何もできないわけではない。懸命に抗えば、撃退を成功させることだって可能だ。だが、戦闘能力を持つ者に比べれば、敵を倒すスピードは遥かに遅い。一人を追い払うのでやっと、という程度である。
「終われば手当ては受ける」
「それじゃ駄目よ……体に良くないわ……」
「今は、勝利を」
ウィクトルは迫り来る敵だけを見ている。
一応返事はしてくれるが、私の方を見てはくれない。
「ウタくんは下がっていてくれ」
「止めて、もう……こんなこと……」
言いたいことが、喉まで出かかっている。けれど、勝利だけを見つめているウィクトルに対してそれを述べることは、簡単なことではなかった。いや、簡単どころか、非常に難しいことだったのだ。だってそれは、彼が持っている意見と真逆の意見を突きつけるということだから。
ウィクトルは袖で滴る血を拭うと、接近してくる敵を剣で貫く。
これは彼の意思ではない。イヴァンの命令だ。そう思うことで、心を何とか保つことはできる。でも『保つこと』しかできない。
心が揺らぐ。ウィクトルが、人の命を終わらせることを仕事としていることなんて、最初から知っていたはずなのに。それなのに、今さら、私は動揺せずにはいられない。
私が見てきた彼は何だったの。
私が共に過ごした彼は、こんな悪魔だったというの。
「信じたくない、みたいな顔だな」
動揺し正気を失っていた私の耳に入ってきたのは、そんな言葉。
ウィクトルの声だった。
「……人殺しを見る目だ」
その時、ようやく視線が重なる。けれども、私はじっと見つめ合えず、すぐに視線を逸らしてしまった。こちらを見てほしい、少し前まではそう思っていたにもかかわらず。
「そ、そんなこと」
「気にしなくていい。誰もがそんな目で私を見る」
「待って。違うの、私……」
「何も違わない。だが君が間違っているわけでもない」
横側から襲いかかってきた男の目もとを剣の先で掠め、蹴り飛ばす。
「間違っているのは私の人生だけだ」
そう述べるウィクトルの瞳に迷いはなかった。
彼は、夜の海の水面のような静けさで、口を動かしている。
「……なんてことを言うの」
半ば無意識のうちにそんな風に返してしまった。
その瞬間の私には、どう思われるかなんて思考する余裕もなくて。
「貴方は、自分の生きてきた道を、間違いだったと……そう言うの……?」
「別の道を歩んでいれば、君の母親を殺すこともなかっただろう」
「でも、そうしたら私たち、出会うこともなかったのよ!?」
母親を殺されずに済んだとしたら、あのまま二人で幸せに暮らす未来があった。けれども、きっと、ウィクトルと出会う日は訪れなかっただろう。
退屈な世で、大好きな母親と生きてゆける平穏な人生。
それが私の一番良い人生だったと、ウィクトルはそう言うのだろうか。
「私は……それは嫌。私は、この人生に後悔はないわ。たとえこれが最善の道でなかったとしても、それでいい。苦しみも、悲しみも、残酷ささえ、貴方がいれば採算は取れる」
子どもね。
そう笑われるだろうか、こんなことを言ったら。
「ウィクトル、貴方が選ぶ道を間違えたと思うのなら、また選び直せばいいじゃない。人生なんて何度でもやり直せる。今からだって遅くはないわ、貴方だってまだ若いもの」
リベルテの不安げな視線がこちらに向いていることに気づき、少し申し訳なく思った。善良な人と知っているからこそ、不安にさせてしまっていることに罪悪感がある。
もっとも、今はそちらへ意識を向ける余裕もあまりないのだが。
「望まないのなら、戦いなんてもう止めて。そんなもの、必要ない」
「……勝利は必要だ」
「考えるのよ、ウィクトル。勝利が本当に貴方を救ってくれたことがあったの? 貴方が本当に必要としているのは、こんな血濡れの勝利なの?」
今やウィクトルは、私が知る優しいウィクトルではない。彼の見据える先にあるのが何なのかは不明だが、今の彼の見据える先にあるものは恐らく私には想像もできないようなものなのだろう。
リベルテは、そんなウィクトルに長い間付き添ってきた身。だから、慣れているのだろうな、と想像していた。しかし、今のリベルテの様子を見ていたら、慣れてはいないのではないかと思えてくる。落ち着きのない様子になっているからだ。
「あ、主……本当に、やるつもりなのでございますか……?」
「命令なら仕方ない」
「……ですよね。承知しました」
足音は近づいてくる。
戦いの火蓋が切って落とされるまで、時間はない。
でも。いくらウィクトルが実力者だとしても、軍勢からここにいるすべての人たちを護るなんてことは簡単ではないはず。そんな難しいことを平然と命じるイヴァンは、ある意味酷な人だ。
ウィクトルを信頼しているようなふりをしてはいるけれど、イヴァンは、真の意味でウィクトルを大事にはしていない。きっとそれが真実なのだろう。本当に大事に思っている者に対して無茶な命令を押し付けたりはしないはずだ。
「イクゼイクゼイクゼ!」
「こっちこっち! 早く! 突入するぞー!」
いよいよ、というような声が、入り口の向こうから聞こえてくる。
ウィクトルは僅かに俯いたまま、腰に下げていたレイピアを抜く。
——直後、広間に人が流れ込んできた。
制服をきちんと着た真面目そうな者もいれば、Tシャツにハーフパンツだけのようなラフな服装の者もいる。流れ込んできた人たちに統一感はない。寄せ集めという言葉がよく似合うような人々だ。
——そして、戦いが幕開ける。
それからのことは、理解が追いつかないため、あまり記憶に残らず。私の瞳が捉えたのは、凄まじい惨状だけ。飛び散る飛沫が視界を染め上げ、私の正気を叩き壊していく。想像を遥かに越えた戦いが、場を乱し、一つ一つの生を絶ってゆくのだった。
「ウィクトル!」
私が思わず叫んだのは、そんな乱戦の中だった。
剣一本で幾人もの敵を薙ぎ倒していっていた彼だったが、瞼を切られ、その傷を片手で押さえる。瞼を切った敵は近くにいたリベルテが術で消し飛ばしたが、ウィクトルはすぐには動けない。
イヴァンも見ているこの場所でウィクトルと親しげな行動はしないでおこうと考えていたのだが、私はたまらずついに駆け寄ってしまった。
「大丈夫なの!?」
「あぁ。……君は下がっていてくれ、危ない」
「手当てしなくちゃ」
「いや、いい。手当てなど、いちいちしている暇はない」
厳密には、ウィクトルとリベルテの二人だけが交戦しているわけではない。近づいてきた敵をワインの瓶で撃退する、というような素人丸出しの戦いを含めるならば、二人より多くの者が敵の軍勢と戦っている。
でも、それでも、数ではこちらが圧倒的に不利だ。
まともに戦える人間の数が少なすぎる。
もちろん、素人が何もできないわけではない。懸命に抗えば、撃退を成功させることだって可能だ。だが、戦闘能力を持つ者に比べれば、敵を倒すスピードは遥かに遅い。一人を追い払うのでやっと、という程度である。
「終われば手当ては受ける」
「それじゃ駄目よ……体に良くないわ……」
「今は、勝利を」
ウィクトルは迫り来る敵だけを見ている。
一応返事はしてくれるが、私の方を見てはくれない。
「ウタくんは下がっていてくれ」
「止めて、もう……こんなこと……」
言いたいことが、喉まで出かかっている。けれど、勝利だけを見つめているウィクトルに対してそれを述べることは、簡単なことではなかった。いや、簡単どころか、非常に難しいことだったのだ。だってそれは、彼が持っている意見と真逆の意見を突きつけるということだから。
ウィクトルは袖で滴る血を拭うと、接近してくる敵を剣で貫く。
これは彼の意思ではない。イヴァンの命令だ。そう思うことで、心を何とか保つことはできる。でも『保つこと』しかできない。
心が揺らぐ。ウィクトルが、人の命を終わらせることを仕事としていることなんて、最初から知っていたはずなのに。それなのに、今さら、私は動揺せずにはいられない。
私が見てきた彼は何だったの。
私が共に過ごした彼は、こんな悪魔だったというの。
「信じたくない、みたいな顔だな」
動揺し正気を失っていた私の耳に入ってきたのは、そんな言葉。
ウィクトルの声だった。
「……人殺しを見る目だ」
その時、ようやく視線が重なる。けれども、私はじっと見つめ合えず、すぐに視線を逸らしてしまった。こちらを見てほしい、少し前まではそう思っていたにもかかわらず。
「そ、そんなこと」
「気にしなくていい。誰もがそんな目で私を見る」
「待って。違うの、私……」
「何も違わない。だが君が間違っているわけでもない」
横側から襲いかかってきた男の目もとを剣の先で掠め、蹴り飛ばす。
「間違っているのは私の人生だけだ」
そう述べるウィクトルの瞳に迷いはなかった。
彼は、夜の海の水面のような静けさで、口を動かしている。
「……なんてことを言うの」
半ば無意識のうちにそんな風に返してしまった。
その瞬間の私には、どう思われるかなんて思考する余裕もなくて。
「貴方は、自分の生きてきた道を、間違いだったと……そう言うの……?」
「別の道を歩んでいれば、君の母親を殺すこともなかっただろう」
「でも、そうしたら私たち、出会うこともなかったのよ!?」
母親を殺されずに済んだとしたら、あのまま二人で幸せに暮らす未来があった。けれども、きっと、ウィクトルと出会う日は訪れなかっただろう。
退屈な世で、大好きな母親と生きてゆける平穏な人生。
それが私の一番良い人生だったと、ウィクトルはそう言うのだろうか。
「私は……それは嫌。私は、この人生に後悔はないわ。たとえこれが最善の道でなかったとしても、それでいい。苦しみも、悲しみも、残酷ささえ、貴方がいれば採算は取れる」
子どもね。
そう笑われるだろうか、こんなことを言ったら。
「ウィクトル、貴方が選ぶ道を間違えたと思うのなら、また選び直せばいいじゃない。人生なんて何度でもやり直せる。今からだって遅くはないわ、貴方だってまだ若いもの」
リベルテの不安げな視線がこちらに向いていることに気づき、少し申し訳なく思った。善良な人と知っているからこそ、不安にさせてしまっていることに罪悪感がある。
もっとも、今はそちらへ意識を向ける余裕もあまりないのだが。
「望まないのなら、戦いなんてもう止めて。そんなもの、必要ない」
「……勝利は必要だ」
「考えるのよ、ウィクトル。勝利が本当に貴方を救ってくれたことがあったの? 貴方が本当に必要としているのは、こんな血濡れの勝利なの?」
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説



婚約者の様子がおかしい。明らかに不自然。そんな時、知り合いから、ある情報を得まして……?
四季
恋愛
婚約者の様子がおかしい。
明らかに不自然。
※展開上、一部汚い描写などがあります。ご了承ください。m(_ _)m

婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。しかしその夜……。
四季
恋愛
婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。
しかしその夜……。
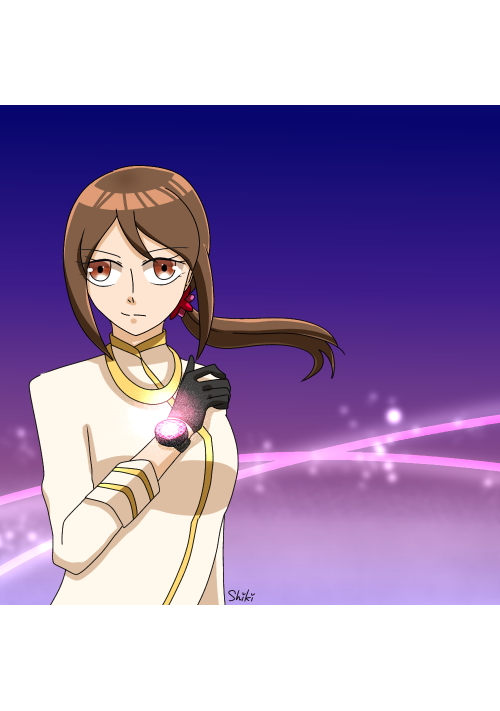
暁のカトレア
四季
恋愛
レヴィアス帝国に謎の生物 "化け物" が出現するようになり約十年。
平凡な毎日を送っていた齢十八の少女 マレイ・チャーム・カトレアは、一人の青年と出会う。
そして、それきっかけに、彼女の人生は大きく動き出すのだった。
※ファンタジー・バトル要素がやや多めです。
※2018.4.7~2018.9.5 執筆

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。

息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。~黙って耐えているのはもう嫌です~
四季
恋愛
息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















