87 / 209
86話「フーシェの微笑み」
しおりを挟む
咄嗟に体が動いた。
一瞬が永遠になる、そんな瞬間の後——私は、まだ生かされていることに気づく。
私はフーシェを庇うべく、彼女とラインの間に入っていた。そして、ラインが握る剣は振り下ろされていた。すべては終幕を迎えるかに思われた、だが、私の生命は絶たれない。一度は覚悟を決めたはずの彼が、動きを静止させていたからだ。
煌めく剣先は、私の首の横で止まっている。
刃が肌に触れるか触れないかの際どいところで。
「……ウタさん」
ラインの瞳は私をじっと捉えていた。
彼の隣に立っているビタリーは、腕組みをして眉間にしわを寄せながらも、まだ黙っている。
「お願いします……そこを退いて下さい」
「嫌よ。退かないわ」
彼は私のことを良く思ってくれていた。そして、私の歌のことも、あんなに褒めてくれたのだ。話をしていた時だって、楽しそうにしていたし。あれが演技だったとは思えない。ビタリーは無理でも、彼なら説得できるかもしれない。
迷っていた。フーシェを救うのか、ラインの立場を守るのか。でも、やはり私は、フーシェを見捨てることはできない。だから決めた。私は彼女を護る。
「……ウタ、何てことをするの」
フーシェは驚いた顔をしていた。
私からすれば、殺されることをすんなり受け入れられる彼女の心が、正直よく分からない。
「殺させたりはしないわ」
「……何を言っているの。貴女が死んだら……それこそボナ様が悲しむ」
「大丈夫! 私だって死ぬつもりはないわ。一緒に生きて帰りましょう、フーシェさん」
即座に二撃目が来ることはなかった。それは多分、まだ心を決めきれていない、という証明。
本当に殺すつもりならこんな長時間動きを止めるはずがない。すぐにでも次の斬撃を叩き込んでくるはずだ。
「ライン、止めて。貴方には似合わないわ、こんなこと」
「ごめんなさい、ウタさん。僕だってこんなことしたくない。でも、逆らうわけにはいきません」
「あんな楽しく過ごせたじゃない。笑ってくれたじゃない。私たち、争う必要なんて」
刹那、ラインは左手を剣の持ち手から離す。
「もう止めてくれ!」
そして、私の襟を掴んだ。
体を引っ張り上げられる。足の先が床に届かない。
「僕だってこんなことしたくない!」
「ライン……」
掴み上げて一文叫んだ後、彼はそっと耳打ちしてくる。
「部屋を出たら、全部の角を右に」
思わず「え?」と言いそうになったが、それは発してはならないような気がして、私は吐きかけた声を飲み込む。その後、ラインに手を離され、私の体は垂直落下。負傷するような高さではなかったが、腰を軽く打った。もっとも、緊迫したこの状況では痛みなんてほとんど感じなかったけれど。
ラインはゆっくりとフーシェに歩み寄る。
その時の彼は、死刑台に向かう人間みたいだった。
なぜそんな辛そうな顔をするの? 殺すのは貴方よ。貴方は殺される側ではない。それなのに、どうしてそんな、死ににゆくような顔を。運命を断つ側なのに、どうしてそんなに痛そうなの?
無意味な思考ばかりが脳内を巡る。
「安心して下さい。彼女を斬るつもりはありません」
「……そうね。それが……助かるわ」
鎖を巻かれた両手両足を後ろ側にして、膝で立っているフーシェ。こんな危機的な状況下だというのに、その瞳に焦りの色は浮かんでいない。彼女は冷静だった。
「さようなら」
呟いて、ラインは剣を振り下ろした。
フーシェの生命は絶たれた——かに思われた。
だが彼女の胴と頭が離れることはなく。
実際に断たれたのは、彼女をこの場所に繋ぐ鎖だけであった。
私はそれを信じられない思いで見つめる。フーシェも同様。首を落とされる、そのことにすら心を乱さなかった彼女だが、この瞬間には動揺しているような顔をしていた。
『部屋を出たら、全部の角を右に』
予想しなかった展開に脳内は真っ白。
だが、ふとその言葉を思い出した。
ラインが言った言葉、その真意に手が届いた気がした——彼は私たちをここから逃す気でいたのではないか、と。
もちろんそれが真実かは分からない。私の解釈が正解だという確認をラインに取っている暇などないわけだし。だが、彼はわざわざ掴みかかってまで、私にあんなことを耳打ちした。それには何らかの意図があったはずだ。
私はすぐさま立ち上がる。
そして、フーシェの手を取った。
彼女はまだ「状況が飲み込めない」というような顔をしている。だが、彼女に色々説明している暇はない。ここから逃げ出す。そのためには、一刻も早く走り出さねばならないのだ。たったの一秒二秒が運命を変えてしまう。
私は走った。フーシェの手首を握ったまま。後ろを振り返ることはしない。開いていた扉を通過し、すぐに右へ。通路を行く。ただ、懸命に、薄暗い地下を駆ける。背後からはビタリーが何か叫んでいるのが聞こえた。けれど、私は前だけを見つめる。幸い、人には遭遇しない。一階へ上がり、分岐点ではラインが述べていたように右にばかり進む。次第に、フーシェが走る速度も速くなってきた。
やがて見えてきた入り口。
あの先には光がある。
外は雨だ。このまま出たら濡れるだろう。でも、そんなことはどうでもいい。濡れたって拭けば済む。でも、命は戻らない。だから雨でも走らねばならないのだ、今の私たちは。
「……このまま脱出する気」
「えぇ」
走り続けていると息が苦しい。返事すらまともにできない。一言返すのがやっとだ。けれどもう引き返せないところまで来ているから、私は限界を越えても走る。
「……分かったわ」
その時になって、フーシェは加速をかける。彼女は手首を私の手からするりと抜いて、私の横に並んだ。
「……貴女には借りができたわね」
なぜ彼女はまだ話せるのだろう。そう不思議に思うくらい、私の呼吸は厳しい状態になっている。運動不足のせいだろうが、ここまで走り続けると全身が痛い。脇腹、胸、脚、すべてが軋むような感覚がある。これが平常時であったなら、とっくに倒れ込んでいたことだろう。
やっと光に手が届く。
そう思った、その時だった。
「……ウタッ!!」
フーシェの鋭い叫び。
体が冷たいものに突き飛ばされる。
斜め後ろ向きに倒れ込んでいく刹那、赤い飛沫が視界に散った。
「やっと仕留めた」
ビタリーの声がして、漂う匂いに彼が発砲したのだと理解する。そして、彼が発した言葉に嫌な予感を覚え、入り口の扉の向こう側へ目をやった。そこに横たわっていたのは、フーシェ。
「フーシェさん!」
こんなところで転んでいる場合ではない。すぐに立ち上がり、彼女に駆け寄る。
「何がどうなったの!? 撃たれたの!?」
「……そう、ね」
仰向けに倒れた彼女は、まだ意識はあるようで、返事はする。
「ウタ……貴女は、行って……」
「そんなこと言わないで! 話をするわ! 私が! きっと、分かってくれる!」
「……無理、よ」
「無理じゃない! 今までだって、何回も、色々あったけれど最後は上手くいったわ!」
その時、フーシェは僅かに頬を緩めた。
「……ウタ、ボナ様を……頼むわね」
「止めて! お願いだから、そんなこと言わないで!」
「……貴女なら、あの人を救える」
握っていた左手が徐々に冷えるのを感じて、私は言い様のない恐怖に襲われた。
彼女という灯火が今まさに目の前で消えてゆこうとしているのを感じたら、嫌な記憶が蘇る——母親を失うのだと悟った、あの瞬間が。
「……貴女のこと、嫌いじゃなかったわ。さっきの、借りは……いつか返す……」
「待って、どうして。待ってと言っているの。そんなことを言わないで、って……そんな言葉なんて要らないの。だからどうか、もう一度……」
わけが分からない。どうしてこんなことになってしまったの。彼女にそれほどの罪などなかったはずなのに。
「……ありがとう」
フーシェは最期、そう言って微笑んだ。
生きる世界が変わって。近くにいる人も変わって。それでも、私はまだ変わっていない。
結局今でも、護られて、遺される側なの。
一瞬が永遠になる、そんな瞬間の後——私は、まだ生かされていることに気づく。
私はフーシェを庇うべく、彼女とラインの間に入っていた。そして、ラインが握る剣は振り下ろされていた。すべては終幕を迎えるかに思われた、だが、私の生命は絶たれない。一度は覚悟を決めたはずの彼が、動きを静止させていたからだ。
煌めく剣先は、私の首の横で止まっている。
刃が肌に触れるか触れないかの際どいところで。
「……ウタさん」
ラインの瞳は私をじっと捉えていた。
彼の隣に立っているビタリーは、腕組みをして眉間にしわを寄せながらも、まだ黙っている。
「お願いします……そこを退いて下さい」
「嫌よ。退かないわ」
彼は私のことを良く思ってくれていた。そして、私の歌のことも、あんなに褒めてくれたのだ。話をしていた時だって、楽しそうにしていたし。あれが演技だったとは思えない。ビタリーは無理でも、彼なら説得できるかもしれない。
迷っていた。フーシェを救うのか、ラインの立場を守るのか。でも、やはり私は、フーシェを見捨てることはできない。だから決めた。私は彼女を護る。
「……ウタ、何てことをするの」
フーシェは驚いた顔をしていた。
私からすれば、殺されることをすんなり受け入れられる彼女の心が、正直よく分からない。
「殺させたりはしないわ」
「……何を言っているの。貴女が死んだら……それこそボナ様が悲しむ」
「大丈夫! 私だって死ぬつもりはないわ。一緒に生きて帰りましょう、フーシェさん」
即座に二撃目が来ることはなかった。それは多分、まだ心を決めきれていない、という証明。
本当に殺すつもりならこんな長時間動きを止めるはずがない。すぐにでも次の斬撃を叩き込んでくるはずだ。
「ライン、止めて。貴方には似合わないわ、こんなこと」
「ごめんなさい、ウタさん。僕だってこんなことしたくない。でも、逆らうわけにはいきません」
「あんな楽しく過ごせたじゃない。笑ってくれたじゃない。私たち、争う必要なんて」
刹那、ラインは左手を剣の持ち手から離す。
「もう止めてくれ!」
そして、私の襟を掴んだ。
体を引っ張り上げられる。足の先が床に届かない。
「僕だってこんなことしたくない!」
「ライン……」
掴み上げて一文叫んだ後、彼はそっと耳打ちしてくる。
「部屋を出たら、全部の角を右に」
思わず「え?」と言いそうになったが、それは発してはならないような気がして、私は吐きかけた声を飲み込む。その後、ラインに手を離され、私の体は垂直落下。負傷するような高さではなかったが、腰を軽く打った。もっとも、緊迫したこの状況では痛みなんてほとんど感じなかったけれど。
ラインはゆっくりとフーシェに歩み寄る。
その時の彼は、死刑台に向かう人間みたいだった。
なぜそんな辛そうな顔をするの? 殺すのは貴方よ。貴方は殺される側ではない。それなのに、どうしてそんな、死ににゆくような顔を。運命を断つ側なのに、どうしてそんなに痛そうなの?
無意味な思考ばかりが脳内を巡る。
「安心して下さい。彼女を斬るつもりはありません」
「……そうね。それが……助かるわ」
鎖を巻かれた両手両足を後ろ側にして、膝で立っているフーシェ。こんな危機的な状況下だというのに、その瞳に焦りの色は浮かんでいない。彼女は冷静だった。
「さようなら」
呟いて、ラインは剣を振り下ろした。
フーシェの生命は絶たれた——かに思われた。
だが彼女の胴と頭が離れることはなく。
実際に断たれたのは、彼女をこの場所に繋ぐ鎖だけであった。
私はそれを信じられない思いで見つめる。フーシェも同様。首を落とされる、そのことにすら心を乱さなかった彼女だが、この瞬間には動揺しているような顔をしていた。
『部屋を出たら、全部の角を右に』
予想しなかった展開に脳内は真っ白。
だが、ふとその言葉を思い出した。
ラインが言った言葉、その真意に手が届いた気がした——彼は私たちをここから逃す気でいたのではないか、と。
もちろんそれが真実かは分からない。私の解釈が正解だという確認をラインに取っている暇などないわけだし。だが、彼はわざわざ掴みかかってまで、私にあんなことを耳打ちした。それには何らかの意図があったはずだ。
私はすぐさま立ち上がる。
そして、フーシェの手を取った。
彼女はまだ「状況が飲み込めない」というような顔をしている。だが、彼女に色々説明している暇はない。ここから逃げ出す。そのためには、一刻も早く走り出さねばならないのだ。たったの一秒二秒が運命を変えてしまう。
私は走った。フーシェの手首を握ったまま。後ろを振り返ることはしない。開いていた扉を通過し、すぐに右へ。通路を行く。ただ、懸命に、薄暗い地下を駆ける。背後からはビタリーが何か叫んでいるのが聞こえた。けれど、私は前だけを見つめる。幸い、人には遭遇しない。一階へ上がり、分岐点ではラインが述べていたように右にばかり進む。次第に、フーシェが走る速度も速くなってきた。
やがて見えてきた入り口。
あの先には光がある。
外は雨だ。このまま出たら濡れるだろう。でも、そんなことはどうでもいい。濡れたって拭けば済む。でも、命は戻らない。だから雨でも走らねばならないのだ、今の私たちは。
「……このまま脱出する気」
「えぇ」
走り続けていると息が苦しい。返事すらまともにできない。一言返すのがやっとだ。けれどもう引き返せないところまで来ているから、私は限界を越えても走る。
「……分かったわ」
その時になって、フーシェは加速をかける。彼女は手首を私の手からするりと抜いて、私の横に並んだ。
「……貴女には借りができたわね」
なぜ彼女はまだ話せるのだろう。そう不思議に思うくらい、私の呼吸は厳しい状態になっている。運動不足のせいだろうが、ここまで走り続けると全身が痛い。脇腹、胸、脚、すべてが軋むような感覚がある。これが平常時であったなら、とっくに倒れ込んでいたことだろう。
やっと光に手が届く。
そう思った、その時だった。
「……ウタッ!!」
フーシェの鋭い叫び。
体が冷たいものに突き飛ばされる。
斜め後ろ向きに倒れ込んでいく刹那、赤い飛沫が視界に散った。
「やっと仕留めた」
ビタリーの声がして、漂う匂いに彼が発砲したのだと理解する。そして、彼が発した言葉に嫌な予感を覚え、入り口の扉の向こう側へ目をやった。そこに横たわっていたのは、フーシェ。
「フーシェさん!」
こんなところで転んでいる場合ではない。すぐに立ち上がり、彼女に駆け寄る。
「何がどうなったの!? 撃たれたの!?」
「……そう、ね」
仰向けに倒れた彼女は、まだ意識はあるようで、返事はする。
「ウタ……貴女は、行って……」
「そんなこと言わないで! 話をするわ! 私が! きっと、分かってくれる!」
「……無理、よ」
「無理じゃない! 今までだって、何回も、色々あったけれど最後は上手くいったわ!」
その時、フーシェは僅かに頬を緩めた。
「……ウタ、ボナ様を……頼むわね」
「止めて! お願いだから、そんなこと言わないで!」
「……貴女なら、あの人を救える」
握っていた左手が徐々に冷えるのを感じて、私は言い様のない恐怖に襲われた。
彼女という灯火が今まさに目の前で消えてゆこうとしているのを感じたら、嫌な記憶が蘇る——母親を失うのだと悟った、あの瞬間が。
「……貴女のこと、嫌いじゃなかったわ。さっきの、借りは……いつか返す……」
「待って、どうして。待ってと言っているの。そんなことを言わないで、って……そんな言葉なんて要らないの。だからどうか、もう一度……」
わけが分からない。どうしてこんなことになってしまったの。彼女にそれほどの罪などなかったはずなのに。
「……ありがとう」
フーシェは最期、そう言って微笑んだ。
生きる世界が変わって。近くにいる人も変わって。それでも、私はまだ変わっていない。
結局今でも、護られて、遺される側なの。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説



婚約者の様子がおかしい。明らかに不自然。そんな時、知り合いから、ある情報を得まして……?
四季
恋愛
婚約者の様子がおかしい。
明らかに不自然。
※展開上、一部汚い描写などがあります。ご了承ください。m(_ _)m

婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。しかしその夜……。
四季
恋愛
婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。
しかしその夜……。

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。
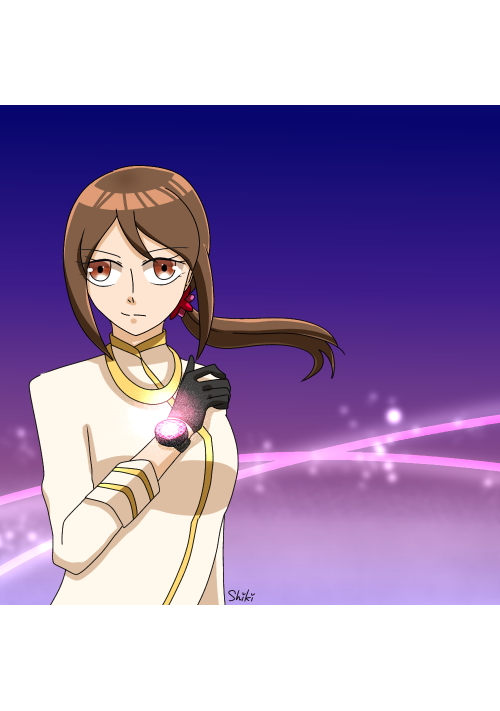
暁のカトレア
四季
恋愛
レヴィアス帝国に謎の生物 "化け物" が出現するようになり約十年。
平凡な毎日を送っていた齢十八の少女 マレイ・チャーム・カトレアは、一人の青年と出会う。
そして、それきっかけに、彼女の人生は大きく動き出すのだった。
※ファンタジー・バトル要素がやや多めです。
※2018.4.7~2018.9.5 執筆

息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。~黙って耐えているのはもう嫌です~
四季
恋愛
息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















