26 / 209
25話「ウタの歌旅」
しおりを挟む
イヴァンからの頼みで、様々な地を回ることになった。とはいえ、私はキエル帝国のことについてそこまで詳しくない。だから、どうすれば良いのだろう、と悩んでいた。しかし、その悩みは、すぐに解決の時が来る。イヴァンから派遣されてきた者が、回ってほしいところの一覧をウィクトルに渡してきたのだ。
「ウタくん、本当に行く気か?」
受け取ったばかりの行き先一覧を眺めながら、ウィクトルが尋ねてきた。
「えぇ。今はそのつもりでいるわ。だって、断るわけにはいかないもの」
「帝国はかなり広いが」
「それは……どういう意味?」
ウィクトルの発言の意図が掴めなかったため、質問してみる。
すると彼はすぐに答えを放つ。
「指示された日程で行くとなると、かなりハードだということだ」
彼が言うのなら間違いではないのだろう。広い国土を旅して回るとなればかなりの労力が必要となるであろうことは、容易に想像がつく。何ら特別なことではない。
「私じゃ無理かしら……」
「無理ということはないだろう。だが、君は、皇帝の命に絶対従わなくてはならない存在ではない。断るなら断ればいい、それだけのことだ」
……もしかして、気を遣ってくれているの?
ふとそれに気がついた時、胸の蝋燭に小さな火が灯ったように感じた。
異星人だとか、母親を殺めた相手だとか、そんなことはどうでもよくなるような、不思議な感覚。
「心配してくれているのね。でも私は大丈夫よ」
「無理はしていないか?」
「えぇ。私の歌が役に立つのなら、私は歌うわ。どこへ行ってでも、ね」
結局私にできることは歌うことだけ。才能も技術も知識もない私にとって、歌は、唯一生き残れるかもしれない道。それほど上手いわけではないけれど、それでも、歌だけは大切にできる。
「そうか、分かった。では共に」
「またよろしくね。ウィクトル」
微笑みかけると、彼は難しい顔で微かに俯く。
「……調子が狂うな、よろしくなんて言われたら」
数日後、出発の朝。
私はウィクトルと二人で待ち合わせの場所へ向かう。するとそこには、既に準備を済ませたリベルテとフーシェがいた。二人は待っていてくれていたみたいだ。自動運転の車ももう待機している。
「待たせたか。リベルテ、フーシェ」
部下二人が先に待ち合わせ場所に着いていたことを知ったウィクトルは、落ち着いた声でそんなことを言う。
それに対し、リベルテとフーシェはほぼ同時に首を左右に動かした。
「……そんなに待っていないわ」
「いえ! 気遣いは不要でございます!」
さらに、フーシェがウィクトルに歩み寄る。
何をするのかな? と思って見ていたら、両手を差し出した。
「……荷物。車に乗せる」
「私一人で問題ない。乗せられる」
「……でもボナ様、二つは大変」
私の分も持ってもらっているせいで、ウィクトルが持つ鞄が二つになってしまっている。彼の荷物を詰めた鞄はそこまで大きくないのでまだしも軽そうだが、私の方の鞄がそこそこ膨らんでしまっていて重そうだ。
「あ! リベルテもお手伝い致しますよ!」
「ボナ様、渡して」
最初は自力で積み込めると訴えていたウィクトルだったが、二人からかなり執拗に声をかけられ、結局最後は二人に任せることにしていた。
リベルテとフーシェが荷物を車内に入れている間に、ウィクトルが話しかけてくる。
「ポーチはそれで問題なかったのか」
「えぇ、大丈夫よ」
私は今、ポーチを持っている。ハンカチや絆創膏など咄嗟に使う可能性があるものだけをまとめ、荷物の鞄とは別に所持しておくことにしたのだ。
ちなみに、今私が肩にかけているこのポーチは、リベルテから借りたもの。
彼は昔から小さめの鞄をよく持っていたそうだ。もちろん現在も持っているわけだが、たった一つしかないわけではない。以前使っていたものも含めれば、処分した分を除いてもそれなりの数になる。
そこで、今回私は、彼の昔持っていたポーチを借りることにした。
彼は一切嫌がらず、快く貸してくれた。
「では乗り込みましょう!」
鞄を車内へ入れる作業が終わったらしく、リベルテが元気そうな声で言ってくる。
それを受けて、私とウィクトルは車に乗り込んだ。
これは乗り込んでから気づいたことだが、今日の車は今までの車とは別物のようだ。なぜ気づいたかというと、車内の広さがまったく違っていたから。自動運転の車であることは共通しているものの、前に乗った時とは内装も内部の広さも全然似ていない。
「向かい合わせの座席なのね。何だか素敵だわ」
三人横に並んで座れるソファのような座席が、向かい合うように二つ。つまり、六人は乗れそうなのだ。しかし今は四人だけだから、席数だけで考えてもかなり余裕がある。
「気に入ったのか、ウタくん」
「えぇ。だって、何だか新鮮だもの。それに、広々しているし」
座席に腰掛けていると、体が横向けに進んでいく。進行方向に向いていない状態というのが実に目新しい。若干の違和感はあるものの、未体験の動き方に心が躍る。
「主とウタ様はやはりお似合いでございますね!」
「……何を言っているの、リベルテ」
無理に口を開いたリベルテは、特に話題がなかったからか、唐突過ぎることを言い出した。そして、リベルテの横に座っているフーシェは、それを聞き逃さなかった。フーシェは何の躊躇いもなく冷ややかに突っ込みをいれる。しかし、リベルテはフーシェの冷ややかさに慣れているようで、笑みを振り撒き続けるだけ。
「ねぇウィクトル。最初の目的地って……どこだった?」
自動運転の車は運転手が必要ない。それはつまり、運転できる者が仲間にいなくても、無関係の者を同行させなくて良いということだ。これは自動運転車の良いところである。親しくない運転手でも近くにいたら気を遣ってしまいそうになるだろうが、その必要がない。そのため、疲れなくて済む。
「最初に向かうのはウェストエナー。帝国の西の端。あそこは君も、前に、少し通過しただろう。もっとも……私にとってはあまり嬉しくない記憶のある場所だが」
「ウタくん、本当に行く気か?」
受け取ったばかりの行き先一覧を眺めながら、ウィクトルが尋ねてきた。
「えぇ。今はそのつもりでいるわ。だって、断るわけにはいかないもの」
「帝国はかなり広いが」
「それは……どういう意味?」
ウィクトルの発言の意図が掴めなかったため、質問してみる。
すると彼はすぐに答えを放つ。
「指示された日程で行くとなると、かなりハードだということだ」
彼が言うのなら間違いではないのだろう。広い国土を旅して回るとなればかなりの労力が必要となるであろうことは、容易に想像がつく。何ら特別なことではない。
「私じゃ無理かしら……」
「無理ということはないだろう。だが、君は、皇帝の命に絶対従わなくてはならない存在ではない。断るなら断ればいい、それだけのことだ」
……もしかして、気を遣ってくれているの?
ふとそれに気がついた時、胸の蝋燭に小さな火が灯ったように感じた。
異星人だとか、母親を殺めた相手だとか、そんなことはどうでもよくなるような、不思議な感覚。
「心配してくれているのね。でも私は大丈夫よ」
「無理はしていないか?」
「えぇ。私の歌が役に立つのなら、私は歌うわ。どこへ行ってでも、ね」
結局私にできることは歌うことだけ。才能も技術も知識もない私にとって、歌は、唯一生き残れるかもしれない道。それほど上手いわけではないけれど、それでも、歌だけは大切にできる。
「そうか、分かった。では共に」
「またよろしくね。ウィクトル」
微笑みかけると、彼は難しい顔で微かに俯く。
「……調子が狂うな、よろしくなんて言われたら」
数日後、出発の朝。
私はウィクトルと二人で待ち合わせの場所へ向かう。するとそこには、既に準備を済ませたリベルテとフーシェがいた。二人は待っていてくれていたみたいだ。自動運転の車ももう待機している。
「待たせたか。リベルテ、フーシェ」
部下二人が先に待ち合わせ場所に着いていたことを知ったウィクトルは、落ち着いた声でそんなことを言う。
それに対し、リベルテとフーシェはほぼ同時に首を左右に動かした。
「……そんなに待っていないわ」
「いえ! 気遣いは不要でございます!」
さらに、フーシェがウィクトルに歩み寄る。
何をするのかな? と思って見ていたら、両手を差し出した。
「……荷物。車に乗せる」
「私一人で問題ない。乗せられる」
「……でもボナ様、二つは大変」
私の分も持ってもらっているせいで、ウィクトルが持つ鞄が二つになってしまっている。彼の荷物を詰めた鞄はそこまで大きくないのでまだしも軽そうだが、私の方の鞄がそこそこ膨らんでしまっていて重そうだ。
「あ! リベルテもお手伝い致しますよ!」
「ボナ様、渡して」
最初は自力で積み込めると訴えていたウィクトルだったが、二人からかなり執拗に声をかけられ、結局最後は二人に任せることにしていた。
リベルテとフーシェが荷物を車内に入れている間に、ウィクトルが話しかけてくる。
「ポーチはそれで問題なかったのか」
「えぇ、大丈夫よ」
私は今、ポーチを持っている。ハンカチや絆創膏など咄嗟に使う可能性があるものだけをまとめ、荷物の鞄とは別に所持しておくことにしたのだ。
ちなみに、今私が肩にかけているこのポーチは、リベルテから借りたもの。
彼は昔から小さめの鞄をよく持っていたそうだ。もちろん現在も持っているわけだが、たった一つしかないわけではない。以前使っていたものも含めれば、処分した分を除いてもそれなりの数になる。
そこで、今回私は、彼の昔持っていたポーチを借りることにした。
彼は一切嫌がらず、快く貸してくれた。
「では乗り込みましょう!」
鞄を車内へ入れる作業が終わったらしく、リベルテが元気そうな声で言ってくる。
それを受けて、私とウィクトルは車に乗り込んだ。
これは乗り込んでから気づいたことだが、今日の車は今までの車とは別物のようだ。なぜ気づいたかというと、車内の広さがまったく違っていたから。自動運転の車であることは共通しているものの、前に乗った時とは内装も内部の広さも全然似ていない。
「向かい合わせの座席なのね。何だか素敵だわ」
三人横に並んで座れるソファのような座席が、向かい合うように二つ。つまり、六人は乗れそうなのだ。しかし今は四人だけだから、席数だけで考えてもかなり余裕がある。
「気に入ったのか、ウタくん」
「えぇ。だって、何だか新鮮だもの。それに、広々しているし」
座席に腰掛けていると、体が横向けに進んでいく。進行方向に向いていない状態というのが実に目新しい。若干の違和感はあるものの、未体験の動き方に心が躍る。
「主とウタ様はやはりお似合いでございますね!」
「……何を言っているの、リベルテ」
無理に口を開いたリベルテは、特に話題がなかったからか、唐突過ぎることを言い出した。そして、リベルテの横に座っているフーシェは、それを聞き逃さなかった。フーシェは何の躊躇いもなく冷ややかに突っ込みをいれる。しかし、リベルテはフーシェの冷ややかさに慣れているようで、笑みを振り撒き続けるだけ。
「ねぇウィクトル。最初の目的地って……どこだった?」
自動運転の車は運転手が必要ない。それはつまり、運転できる者が仲間にいなくても、無関係の者を同行させなくて良いということだ。これは自動運転車の良いところである。親しくない運転手でも近くにいたら気を遣ってしまいそうになるだろうが、その必要がない。そのため、疲れなくて済む。
「最初に向かうのはウェストエナー。帝国の西の端。あそこは君も、前に、少し通過しただろう。もっとも……私にとってはあまり嬉しくない記憶のある場所だが」
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説



婚約者の様子がおかしい。明らかに不自然。そんな時、知り合いから、ある情報を得まして……?
四季
恋愛
婚約者の様子がおかしい。
明らかに不自然。
※展開上、一部汚い描写などがあります。ご了承ください。m(_ _)m

婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。しかしその夜……。
四季
恋愛
婚約者から突如心当たりのないことを言われ責められてしまい、さらには婚約破棄までされました。
しかしその夜……。
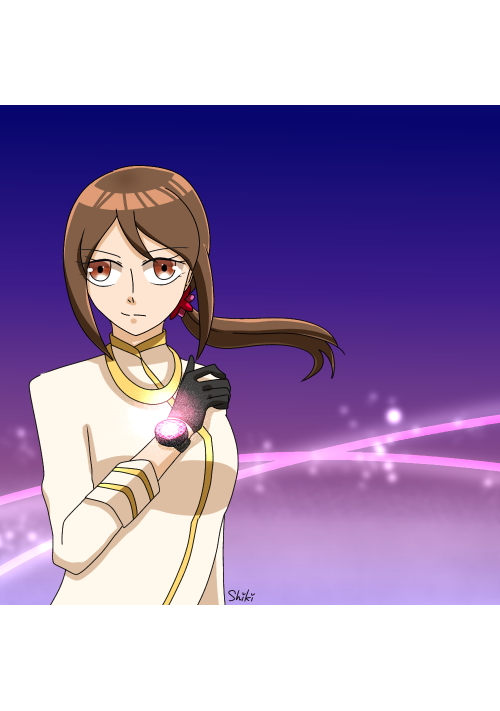
暁のカトレア
四季
恋愛
レヴィアス帝国に謎の生物 "化け物" が出現するようになり約十年。
平凡な毎日を送っていた齢十八の少女 マレイ・チャーム・カトレアは、一人の青年と出会う。
そして、それきっかけに、彼女の人生は大きく動き出すのだった。
※ファンタジー・バトル要素がやや多めです。
※2018.4.7~2018.9.5 執筆

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。


息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。~黙って耐えているのはもう嫌です~
四季
恋愛
息をするように侮辱してくる婚約者に言い返したところ婚約破棄されてしまいました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















