66 / 141
episode.65 それを狙って何になる?
しおりを挟む
あれからも盾のプリンスは時折ここへやって来る。
やたらと気にかけてくれるが……そのたびにミクニが溜め息をつくので若干気まずい。
「急にすまない」
「プリンスさん……今日は何のご用ですか?」
こうして向き合うことにもさすがにもう慣れた。
緊張感はそれほどない。
しかし今日の彼は鞄を持っている――何だろう?
「来ない方が良かっただろうか」
「いえ、べつに、そういうわけではありません」
「実はこれを持ってきた」
彼は鞄の中から一冊の本のようなものとケース入りの数本のペンを取り出した。
「それは?」
「塗り絵というものらしい」
「えっと……塗り絵?」
「あぁそうだ。ここに絵が描かれているのだが、そこに色を塗る娯楽らしい」
「へぇ……」
そんな娯楽があるのは知らなかった。人間の世の中で育った私だけれど、塗り絵なるものを楽しんだことはなかったように思う。だが世界というのは広い。私が知らないところにそういう娯楽があったとしてもおかしな話ではない。ただ私が知らないだけ、ということも、十分考えられる。
「よければ試してみてほしい」
「掘り出し物ですか?」
「そういうことだ。こんなものでも少しは暇潰しにはなるだろう、と思って」
「ありがとうございます」
なぜ今この緊迫した状況の時にそんなものを持ってくるのか……とは思うけれど、まぁ、彼なりの優しさなのなら拒否するのも失礼だろう。
そう思って、一応、その場で挑戦してみることにした。
本のようなものを開くとそこには繊細な線で絵が描かれている。ぱらぱらと一通り眺めてみると、いろんなモチーフの絵があることが分かった。木々と小動物の絵、海の中を連想させるような絵、花の絵、と、ページごとに色々である。ただし、そのすべてが、色はついていないままだ。
取り敢えず木々と小動物の絵に色を塗ってみよう。
それにしても、いちいちインクをつけずとも色を塗ることのできるペン――これは非常に便利だ。
塗り放題である。
私が絵に色を塗っている間、盾のプリンスは近くにいて、ずっとこちらを眺めていた。
「あの」
視線を彼へ向け。
「さっきからこちらばかり見てません? 気のせいだったら……すみませんけど」
言ってから気づく。
これは気のせいだったら恥ずかしいやつでは!? と。
しかし彼はさらりと返してくる。
「見ている」
気のせいではなかったようで安堵。
「愛のプリンセスの件で弱っているのではないかと思っていたが、大丈夫そうで安心した」
「え?」
「君は前から愛のプリンセスのことを気にしていただろう。何だかんだで彼女のことを大切に思っていることは知っていた。だからこそ、君が弱ってはいないかと、気になって」
盾のプリンスは当たり前のことを言っているかのように淡々と言葉を紡ぐ。
「もしかして、それで塗り絵を?」
「悲しい時は何かで気を散らすのが一番かと思って」
「……そういうことだったんですね」
さて、そろそろ塗り絵も完成だ。
「はい! できました!」
慣れないペンの使い方には苦労した。いや、もちろん、常にインクが出るという点はとてもありがたいし便利なのだけれど。ただ、実際に塗る時になると、常にインクが出るがゆえの扱いの難しさもあったのだ。
少々雑な塗り方になってしまった。
そんな塗り絵を見た盾のプリンスは、さらりと「かなりはみ出ている」と言ってくる。私は若干恥ずかしい思いをしつつ「言わないでください……」と返しておいた。
まぁ、確かに、はみ出ているのは事実なのだが……。
何にせよ今回はまだ初回。塗り慣れていないから上手く塗れないのも仕方のないこと。慣れてくれば徐々に上手く塗れるようになるだろう。
――などと自分を励ましていた、その時。
「相変わっらず呑気なやつらだなぁ」
いつか聞いた声。
そして出現するあの時の男。
「はは。また来てやったぜ」
剣のプリンセスに若干似たような格好のその男性を、私は知っている。いや、私だけではない。盾のプリンスも、ミクニも、彼のことは知っているはずだ。だってあの時も二人はその場にいたから。
「……またか」
不愉快極まりない、という顔をするのは、盾のプリンス。
「俺気づいたんだ! プリンセスがいればいつでもここへ入れるーってことに! はっははは。いやーまさかこんな穴があったとはなぁ」
男性の背後には剣と杖のプリンセスが控えていた。
できれば二人とは戦いたくなかった……だって不利ではないか、こちらには高い攻撃力を誇る者はいないというのに。
「しっかしよぉ、盾の野郎は相変わらずクイーンが大好きだなぁ」
「放っておいてほしい」
「親譲りだなぁ、そのクイーンかぶれ」
「……知ったような口を利くな」
盾のプリンスは目もとに少々力を加え低めの声を出した。
「知ったような? 笑わせるなよ。知ってんだよ、俺は」
「何を……」
「なんたって俺は元・剣のプリンスだからな! つまり先代だよ先代!」
正体を明かすと同時に元・剣のプリンスを名乗る男性は斬りかかる。盾のプリンスは一枚の盾で斬撃を防ぐ、が、威力を殺しきれず身体の向きが僅かに傾いた。そこへ、男性は真横から足を出して。蹴られたくらいで大きく体勢を崩しはしないだろうと思ったのも束の間、盾のプリンスは右に向かって飛ばされる。
盾のプリンスはそのまま宙を飛び、壁に激突。
凄まじい威力だ、と、心の底から思った。
前に戦った時とは違っている。いや、前が本気でなかっただけという可能性はあるが。ただ、あの時とは戦闘能力が大きく違う。それだけは確かだ。だって、そうでなければ、そこそこ大きく重さもある盾のプリンスの身体を蹴りだけであれほど飛ばすことなどできるわけがない。
幸い、盾のプリンスはそれほどダメージを負っている様子ではない――その証拠に、既に立ち上がっている。
「今回は手加減はしない。情けないクイーンはここから消えろ」
「……お断りします」
「ふざけんな、断るも何もないんだよ。選べると思うなよ」
攻撃されるかと思ったが、元・剣のプリンスの視線は私には向いていなくて。意図が掴めず混乱する。だが数秒経たないうちに気づく。彼が見ているのは座のすぐ傍にある台に乗った球体だと。
狙いはそれなのか?
でも、それを狙って何になる?
元・剣のプリンスは愛剣を掲げ、球体に向かって振り下ろす。
「クイーン!」
そう呼ぶ声がして。
でも返事はできないまま辺りは白い光に包まれ――そこで意識は途絶えた。
やたらと気にかけてくれるが……そのたびにミクニが溜め息をつくので若干気まずい。
「急にすまない」
「プリンスさん……今日は何のご用ですか?」
こうして向き合うことにもさすがにもう慣れた。
緊張感はそれほどない。
しかし今日の彼は鞄を持っている――何だろう?
「来ない方が良かっただろうか」
「いえ、べつに、そういうわけではありません」
「実はこれを持ってきた」
彼は鞄の中から一冊の本のようなものとケース入りの数本のペンを取り出した。
「それは?」
「塗り絵というものらしい」
「えっと……塗り絵?」
「あぁそうだ。ここに絵が描かれているのだが、そこに色を塗る娯楽らしい」
「へぇ……」
そんな娯楽があるのは知らなかった。人間の世の中で育った私だけれど、塗り絵なるものを楽しんだことはなかったように思う。だが世界というのは広い。私が知らないところにそういう娯楽があったとしてもおかしな話ではない。ただ私が知らないだけ、ということも、十分考えられる。
「よければ試してみてほしい」
「掘り出し物ですか?」
「そういうことだ。こんなものでも少しは暇潰しにはなるだろう、と思って」
「ありがとうございます」
なぜ今この緊迫した状況の時にそんなものを持ってくるのか……とは思うけれど、まぁ、彼なりの優しさなのなら拒否するのも失礼だろう。
そう思って、一応、その場で挑戦してみることにした。
本のようなものを開くとそこには繊細な線で絵が描かれている。ぱらぱらと一通り眺めてみると、いろんなモチーフの絵があることが分かった。木々と小動物の絵、海の中を連想させるような絵、花の絵、と、ページごとに色々である。ただし、そのすべてが、色はついていないままだ。
取り敢えず木々と小動物の絵に色を塗ってみよう。
それにしても、いちいちインクをつけずとも色を塗ることのできるペン――これは非常に便利だ。
塗り放題である。
私が絵に色を塗っている間、盾のプリンスは近くにいて、ずっとこちらを眺めていた。
「あの」
視線を彼へ向け。
「さっきからこちらばかり見てません? 気のせいだったら……すみませんけど」
言ってから気づく。
これは気のせいだったら恥ずかしいやつでは!? と。
しかし彼はさらりと返してくる。
「見ている」
気のせいではなかったようで安堵。
「愛のプリンセスの件で弱っているのではないかと思っていたが、大丈夫そうで安心した」
「え?」
「君は前から愛のプリンセスのことを気にしていただろう。何だかんだで彼女のことを大切に思っていることは知っていた。だからこそ、君が弱ってはいないかと、気になって」
盾のプリンスは当たり前のことを言っているかのように淡々と言葉を紡ぐ。
「もしかして、それで塗り絵を?」
「悲しい時は何かで気を散らすのが一番かと思って」
「……そういうことだったんですね」
さて、そろそろ塗り絵も完成だ。
「はい! できました!」
慣れないペンの使い方には苦労した。いや、もちろん、常にインクが出るという点はとてもありがたいし便利なのだけれど。ただ、実際に塗る時になると、常にインクが出るがゆえの扱いの難しさもあったのだ。
少々雑な塗り方になってしまった。
そんな塗り絵を見た盾のプリンスは、さらりと「かなりはみ出ている」と言ってくる。私は若干恥ずかしい思いをしつつ「言わないでください……」と返しておいた。
まぁ、確かに、はみ出ているのは事実なのだが……。
何にせよ今回はまだ初回。塗り慣れていないから上手く塗れないのも仕方のないこと。慣れてくれば徐々に上手く塗れるようになるだろう。
――などと自分を励ましていた、その時。
「相変わっらず呑気なやつらだなぁ」
いつか聞いた声。
そして出現するあの時の男。
「はは。また来てやったぜ」
剣のプリンセスに若干似たような格好のその男性を、私は知っている。いや、私だけではない。盾のプリンスも、ミクニも、彼のことは知っているはずだ。だってあの時も二人はその場にいたから。
「……またか」
不愉快極まりない、という顔をするのは、盾のプリンス。
「俺気づいたんだ! プリンセスがいればいつでもここへ入れるーってことに! はっははは。いやーまさかこんな穴があったとはなぁ」
男性の背後には剣と杖のプリンセスが控えていた。
できれば二人とは戦いたくなかった……だって不利ではないか、こちらには高い攻撃力を誇る者はいないというのに。
「しっかしよぉ、盾の野郎は相変わらずクイーンが大好きだなぁ」
「放っておいてほしい」
「親譲りだなぁ、そのクイーンかぶれ」
「……知ったような口を利くな」
盾のプリンスは目もとに少々力を加え低めの声を出した。
「知ったような? 笑わせるなよ。知ってんだよ、俺は」
「何を……」
「なんたって俺は元・剣のプリンスだからな! つまり先代だよ先代!」
正体を明かすと同時に元・剣のプリンスを名乗る男性は斬りかかる。盾のプリンスは一枚の盾で斬撃を防ぐ、が、威力を殺しきれず身体の向きが僅かに傾いた。そこへ、男性は真横から足を出して。蹴られたくらいで大きく体勢を崩しはしないだろうと思ったのも束の間、盾のプリンスは右に向かって飛ばされる。
盾のプリンスはそのまま宙を飛び、壁に激突。
凄まじい威力だ、と、心の底から思った。
前に戦った時とは違っている。いや、前が本気でなかっただけという可能性はあるが。ただ、あの時とは戦闘能力が大きく違う。それだけは確かだ。だって、そうでなければ、そこそこ大きく重さもある盾のプリンスの身体を蹴りだけであれほど飛ばすことなどできるわけがない。
幸い、盾のプリンスはそれほどダメージを負っている様子ではない――その証拠に、既に立ち上がっている。
「今回は手加減はしない。情けないクイーンはここから消えろ」
「……お断りします」
「ふざけんな、断るも何もないんだよ。選べると思うなよ」
攻撃されるかと思ったが、元・剣のプリンスの視線は私には向いていなくて。意図が掴めず混乱する。だが数秒経たないうちに気づく。彼が見ているのは座のすぐ傍にある台に乗った球体だと。
狙いはそれなのか?
でも、それを狙って何になる?
元・剣のプリンスは愛剣を掲げ、球体に向かって振り下ろす。
「クイーン!」
そう呼ぶ声がして。
でも返事はできないまま辺りは白い光に包まれ――そこで意識は途絶えた。
0
あなたにおすすめの小説

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い
青の雀
恋愛
夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。
神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。
もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。
生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。
過去世と同じ轍を踏みたくない……

愛しているなら拘束してほしい
守 秀斗
恋愛
会社員の美夜本理奈子(24才)。ある日、仕事が終わって会社の玄関まで行くと大雨が降っている。びしょ濡れになるのが嫌なので、地下の狭い通路を使って、隣の駅ビルまで行くことにした。すると、途中の部屋でいかがわしい行為をしている二人の男女を見てしまうのだが……。

屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

一目惚れは、嘘でした?
谷川ざくろ
恋愛
代打で参加したお見合いで、「一目惚れです」とまさかのプロポーズをされた下級女官のシエラ・ハウエル。
相手は美しい公爵、アルフレッド・ベルーフィア。
疑わしく思いつつも、病気がちな弟の治療と領地への援助を提示され、婚約を結んだ。
一目惚れと言っていた通り溺愛されて相思相愛となり、幸せな結婚生活を送るシエラだったが、ある夜、夫となったアルフレッドの本音を聞いてしまう。
*ムーンライトノベルズ様でも投稿しています。

ひみつの姫君 ~男爵令嬢なのにくじ引きで王子のいる生徒会の役員になりました!~
らな
恋愛
男爵令嬢のリアはアルノー王国の貴族の子女が通う王立学院の1年生だ。
高位貴族しか入れない生徒会に、なぜかくじ引きで役員になることになってしまい、慌てふためいた。今年の生徒会にはアルノーの第2王子クリスだけではなく、大国リンドブルムの第2王子ジークフェルドまで在籍しているのだ。
冷徹な公爵令息のルーファスと、リアと同じくくじ引きで選ばれた優しい子爵令息のヘンドリックの5人の生徒会メンバーで繰り広げる学園ラブコメ開演!
リアには本人の知らない大きな秘密があります。
リアを取り巻く男性陣のやり取りや友情も楽しんでいただけたら嬉しいです。

【完結】大変申し訳ありませんが、うちのお嬢様に貴方は不釣り合いのようです。
リラ
恋愛
婚約破棄から始まる、有能執事の溺愛…いや、過保護?
お嬢様を絶対守るマンが本気を出したらすごいんです。
ミリアス帝国首都の一等地に屋敷を構える資産家のコルチエット伯爵家で執事として勤めているロバートは、あらゆる事を完璧にこなす有能な執事だ。
そんな彼が生涯を捧げてでも大切に守ろうと誓った伯爵家のご令嬢エミリー・コルチエットがある日、婚約者に一方的に婚約破棄を告げられる事件が起こる。
その事実を知ったロバートは……この執事を怒らせたら怖いぞ!
後に後悔しエミリーとの復縁を望む元婚約者や、彼女に恋心を抱く男達を前に、お嬢様の婿に相応しいか見極めるロバートだったが…?
果たして、ロバートに認められるようなエミリーお嬢様のお婿候補は現れるのだろうか!?
【物語補足情報】
世界観:貴族社会はあるものの、財を成した平民が貴族位を買い新興貴族(ブルジョア)として活躍している時代。
由緒正しい貴族の力は弱まりつつあり、借金を抱える高位貴族も増えていった。
コルチエット家:帝国一の大商会を持つ一族。元々平民だが、エミリーの祖父の代に伯爵位を買い貴族となった資産家。
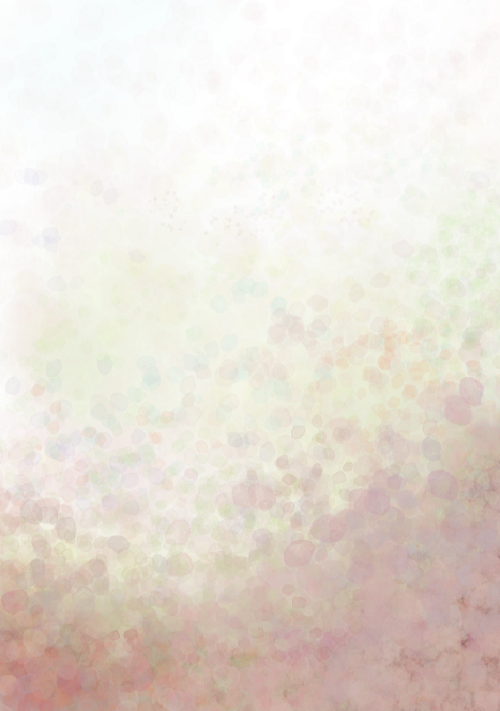
「今とっても幸せですの。ごめんあそばせ♡」 捨てられ者同士、溺れちゃうほど愛し合ってますのでお構いなく!
若松だんご
恋愛
「キサマとはやっていけない。婚約破棄だ。俺が愛してるのは、このマリアルナだ!」
婚約者である王子が開いたパーティ会場で。妹、マリアルナを伴って現れた王子。てっきり結婚の日取りなどを発表するのかと思っていたリューリアは、突然の婚約破棄、妹への婚約変更に驚き戸惑う。
「姉から妹への婚約変更。外聞も悪い。お前も噂に晒されて辛かろう。修道院で余生を過ごせ」
リューリアを慰めたり、憤慨することもない父。マリアルナが王子妃になることを手放しで喜んだ母。
二人は、これまでのリューリアの人生を振り回しただけでなく、これからの未来も勝手に決めて命じる。
四つ違いの妹。母によく似たかわいらしい妹が生まれ、母は姉であ、リューリアの育児を放棄した。
そんなリューリアを不憫に思ったのか、ただの厄介払いだったのか。田舎で暮らしていた祖母の元に預けられて育った。
両親から離れたことは寂しかったけれど、祖母は大切にしてくれたし、祖母の家のお隣、幼なじみのシオンと仲良く遊んで、それなりに楽しい幼少期だったのだけど。
「第二王子と結婚せよ」
十年前、またも家族の都合に振り回され、故郷となった町を離れ、祖母ともシオンとも別れ、未来の王子妃として厳しい教育を受けることになった。
好きになれそうにない相手だったけれど、未来の夫となる王子のために、王子に代わって政務をこなしていた。王子が遊び呆けていても、「男の人はそういうものだ」と文句すら言わせてもらえなかった。
そして、20歳のこの日。またも周囲の都合によって振り回され、周囲の都合によって未来まで決定されてしまった。
冗談じゃないわ。どれだけ人を振り回したら気が済むのよ、この人たち。
腹が立つけれど、どうしたらいいのかわからずに、従う道しか選べなかったリューリア。
せめて。せめて修道女として生きるなら、故郷で生きたい。
自分を大事にしてくれた祖母もいない、思い出だけが残る町。けど、そこで幼なじみのシオンに再会する。
シオンは、結婚していたけれど、奥さんが「真実の愛を見つけた」とかで、行方をくらましていて、最近ようやく離婚が成立したのだという。
真実の愛って、そんなゴロゴロ転がってるものなのかしら。そして、誰かを不幸に、悲しませないと得られないものなのかしら。
というか。真実もニセモノも、愛に真贋なんてあるのかしら。
捨てられた者同士。傷ついたもの同士。
いっしょにいて、いっしょに楽しんで。昔を思い出して。
傷を舐めあってるんじゃない。今を楽しみ、愛を、想いを育んでいるの。だって、わたしも彼も、幼い頃から相手が好きだったってこと、思い出したんだもの。
だから。
わたしたちの見つけた「真実の愛(笑)」、邪魔をしないでくださいな♡

山猿の皇妃
夏菜しの
恋愛
ライヘンベルガー王国の第三王女レティーツィアは、成人する十六歳の誕生日と共に、隣国イスターツ帝国へ和平条約の品として贈られた。
祖国に聞こえてくるイスターツ帝国の噂は、〝山猿〟と言った悪いモノばかり。それでもレティーツィアは自らに課せられた役目だからと山を越えて隣国へ向かった。
嫁いできたレティーツィアを見た皇帝にして夫のヘクトールは、子供に興味は無いと一蹴する。これはライヘンベルガー王国とイスターツ帝国の成人とみなす年の違いの問題だから、レティーツィアにはどうすることも出来ない。
子供だと言われてヘクトールに相手にされないレティーツィアは、妻の責務を果たしていないと言われて次第に冷遇されていく。
一方、レティーツィアには祖国から、将来的に帝国を傀儡とする策が授けられていた。そのためには皇帝ヘクトールの子を産む必要があるのだが……
それが出来たらこんな待遇になってないわ! と彼女は憤慨する。
帝国で居場所をなくし、祖国にも帰ることも出来ない。
行き場を失ったレティーツィアの孤独な戦いが静かに始まる。
※恋愛成分は低め、内容はややダークです
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















