お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

アルファポリスで書籍化されるには
日下奈緒
エッセイ・ノンフィクション
アルファポリスで作品を発表してから、1年。
最初は、見よう見まねで作品を発表していたけれど、最近は楽しくなってきました。
あー、書籍化されたい。

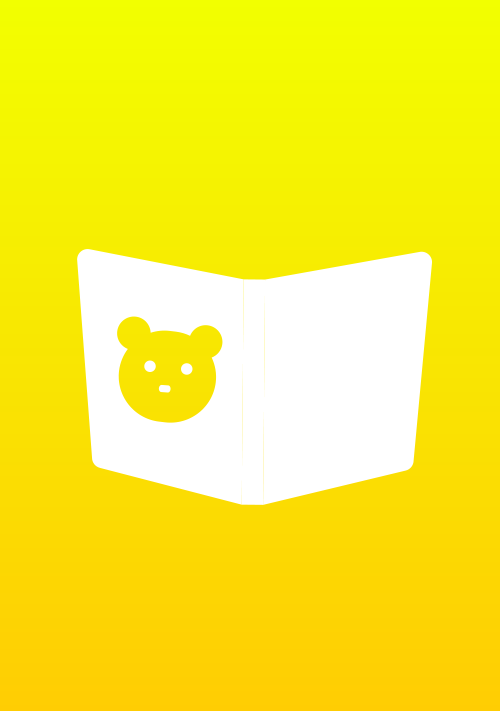
傍若無人な皇太子は、その言動で周りを振り回してきた
歩芽川ゆい
絵本
頭は良いが、性格が破綻している王子、ブルスカメンテ。
その権力も用いて自分の思い通りにならないことなどこの世にはない、と思っているが、婚約者候補の一人、フェロチータ公爵令嬢アフリットだけは面会に来いと命令しても、病弱を理由に一度も来ない。
とうとうしびれをきらしたブルスカメンテは、フェロチータ公爵家に乗り込んでいった。
架空の国のお話です。
ホラーです。
子供に対しての残酷な描写も出てきます。人も死にます。苦手な方は避けてくださいませ。

アルファポリスとカクヨムってどっちが稼げるの?
無責任
エッセイ・ノンフィクション
基本的にはアルファポリスとカクヨムで執筆活動をしています。
どっちが稼げるのだろう?
いろんな方の想いがあるのかと・・・。
2021年4月からカクヨムで、2021年5月からアルファポリスで執筆を開始しました。
あくまで、僕の場合ですが、実データを元に・・・。




100000累計pt突破!アルファポリスの収益 確定スコア 見込みスコアについて
ちゃぼ茶
エッセイ・ノンフィクション
皆様が気になる(ちゃぼ茶も)収益や確定スコア、見込みスコアについてわかる範囲、推測や経験談も含めて記してみました。参考になれればと思います。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















