お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

両親大好きっ子平民聖女様は、モフモフ聖獣様と一緒に出稼ぎライフに勤しんでいます
井藤 美樹
児童書・童話
私の両親はお人好しなの。それも、超が付くほどのお人好し。
ここだけの話、生まれたての赤ちゃんよりもピュアな存在だと、私は内心思ってるほどなの。少なくとも、六歳の私よりもピュアなのは間違いないわ。
なので、すぐ人にだまされる。
でもね、そんな両親が大好きなの。とってもね。
だから、私が防波堤になるしかないよね、必然的に。生まれてくる妹弟のためにね。お姉ちゃん頑張ります。
でもまさか、こんなことになるなんて思いもしなかったよ。
こんな私が〈聖女〉なんて。絶対間違いだよね。教会の偉い人たちは間違いないって言ってるし、すっごく可愛いモフモフに懐かれるし、どうしよう。
えっ!? 聖女って給料が出るの!? なら、なります!! 頑張ります!!
両親大好きっ子平民聖女様と白いモフモフ聖獣様との出稼ぎライフ、ここに開幕です!!

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

ひかりにふれたねこ
1000
児童書・童話
遠い昔、深い森の奥に、ふわふわ浮かぶ、ひかるさかなが住んでいました。
ひかるさかなは、いつも そこにいて、周りを照らしています。
そこに 暗い目をした黒猫:やみねこがやってきました。
やみねこが、ひかるさかなに望んだこととは……?
登場人物
・やみねこ
・ひかるさかな
※ひかりにふれたねこ、完結しました!
宜しくお願いします<(_ _)>

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】
絢郷水沙
ホラー
普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。
下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。
※全話オリジナル作品です。
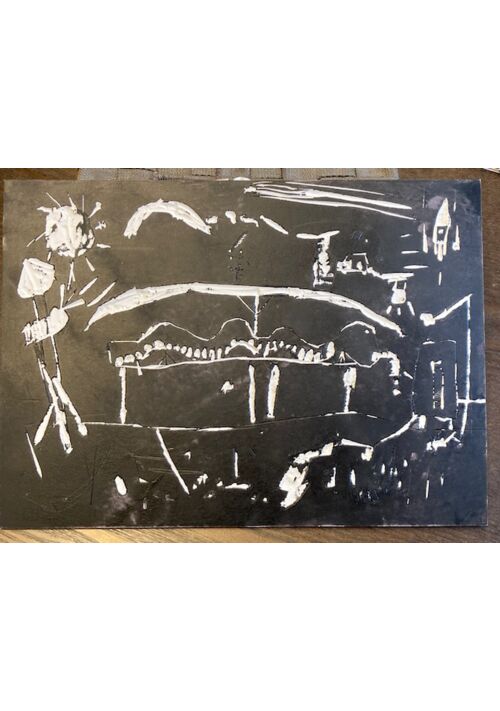
ミズルチと〈竜骨の化石〉
珠邑ミト
児童書・童話
カイトは家族とバラバラに暮らしている〈音読みの一族〉という〈族《うから》〉の少年。彼の一族は、数多ある〈族〉から魂の〈音〉を「読み」、なんの〈族〉か「読みわける」。彼は飛びぬけて「読め」る少年だ。十歳のある日、その力でイトミミズの姿をしている〈族〉を見つけ保護する。ばあちゃんによると、その子は〈出世ミミズ族〉という〈族《うから》〉で、四年かけてミミズから蛇、竜、人と進化し〈竜の一族〉になるという。カイトはこの子にミズルチと名づけ育てることになり……。
一方、世間では怨墨《えんぼく》と呼ばれる、人の負の感情から生まれる墨の化物が活発化していた。これは人に憑りつき操る。これを浄化する墨狩《すみが》りという存在がある。
ミズルチを保護してから三年半後、ミズルチは竜になり、カイトとミズルチは怨墨に知人が憑りつかれたところに遭遇する。これを墨狩りだったばあちゃんと、担任の湯葉《ゆば》先生が狩るのを見て怨墨を知ることに。
カイトとミズルチのルーツをたどる冒険がはじまる。

Vicky!
大秦頼太
児童書・童話
時計職人のお爺さんの勘違いで生まれた人形ヴィッキーが、いたずら妖精のおかげで命を持つ。
ヴィッキーはお爺さんの孫娘マーゴットの心を開き、彼女の友だちとなり、人と触れ合う大切さを教えてくれる。
けれどそんなヴィッキーにも悩みがあった。
「どうしたら人間になれるのだろう」と言う悩みが。
知識を詰め込むだけでは何の意味も無い。そこに心が無ければ、学んだことを役に立たせることは出来ない。
そんな思いを込めました。
※海部守は脚本用のPNです。ブログなどですでに公開済みです。脚本形式なので読みにくいかなと思いますが、せっかくなので色んな人に読んでいただきたいと思い公開します。
・ミュージカル版→ロングバージョン。
・ショートバージョン
の2種類があります。登場人物が少し違うのとショートバージョンには歌がほぼありません。ミュージカル版を作るときの素といった感じです。あと指示も書いてないです。
ミューカル版の歌についてはhttps://youtu.be/UPPr4GVl4Fsで聞けますが伴奏なんかはないので参考程度にしかならないと思います。

異世界子供会:呪われたお母さんを助ける!
克全
児童書・童話
常に生死と隣り合わせの危険魔境内にある貧しい村に住む少年は、村人を助けるために邪神の呪いを受けた母親を助けるために戦う。村の子供会で共に学び育った同級生と一緒にお母さん助けるための冒険をする。

ハート オール デスゲーム/宇宙から来たロボットに拠る地球侵略
桃月熊
児童書・童話
謎の競技(頭脳戦)に強制参加させられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
jokerを当てろ。
水平思考推理ゲーム。(うみがめのすーぷ)
マシュマロ大食いバトル。
携帯ゲーム機。
サイコロ振り。
ルール不明。
偶数 奇数 ルーレット。
苗字を探せ。
ジャンケン最強の手。
大喜利 回答に投票 能力と道具の設定あり。
利き水 百種類から選択。
赤を集めよう。
算数ドリル。
チェス。
人狼ゲームに参加?
使用後に四割の確率で状態異常になるペン。
使用後に八割の確率で状態異常になるペン。
御褒美を選ぼう。
体育館に集合・説明なし。
神経衰弱 カード百枚 ペアは一組。
passwordを推測しろ。
毒薬を当てろ。
他者と被らずに10迄で最も大きい数字。
白線を進む。
現象の名付け親。
討論 超能力の有無の証明vs論破。
Dr.salt登場。
ドミノ。
正反対の意味を内包する同一単語。
選択式野球。
多数派又は少数派。
トランプ七枚選択数字合わせ。
数字のスタンプ押し。
コインの表が出る確率。
鬼不明の鬼ごっこ。
枯葉に書かれた文字。
早押し・完全なる偽者への対処法。
室温調整。
改良・トランプ七枚選択数字合わせ。
言い換え。
二枚のカード 保持と放出。
連携 追跡者から逃亡せよ。
誰にも解けない問題作成。
参加人数を数えて報告。
勝ち抜け四 脱落一 白紙九十五。
肉食え。
トランプで連番五枚。
辞書に載っている単語を作れ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















