179 / 316
「節子の孤独」
しおりを挟む
「節子の孤独」
節子は、75歳の一人暮らし。朝の光が薄く差し込む古いアパートの一室で、彼女はため息をついた。最近、尿失禁が増えてきている。何度下着を取り替えてもすぐにまた汚れてしまい、そのたびに洗濯を繰り返す。洗い終えた下着を干しながら、ふと情けない気持ちがこみ上げてきた。
「こんなことになってしまうなんて…」
節子の生活は、決して楽なものではなかった。夫を亡くしてから数十年、子どももいない彼女は、ずっと一人でこのアパートで暮らしている。かつては働いていたが、年金だけでは生活費を賄うのが精一杯だ。そんな中で尿失禁が増えてしまい、彼女の悩みはますます深刻になっていた。
紙おむつを使えば解決するのかもしれない。しかし、それを買うお金がない。おねしょパットさえも買えない。節子は古いバスタオルを敷いて寝ているが、それも擦り切れて穴が開いてしまった。夜中に目を覚ますと、冷たい湿気が布団に染み込んでいるのを感じ、また泣きたくなる。
「もう少しだけお金があったら…」と節子は思う。しかし、それは夢のまた夢のような話だった。節子の生活費は、毎月の年金だけ。そこから家賃や光熱費、食費を差し引くと、残るお金はほんのわずかだ。医者にかかることも、薬を買うことも、慎重に選ばなければならない。何かを買うたびに、「本当に必要か?」と自問自答しなければならない。
尿失禁の問題も同じだ。紙おむつやおねしょパットを使う余裕などない。彼女は古いタオルを洗っては使い続けるしかなかった。それでも何度も繰り返しているうちに、タオルは擦り切れて、もうボロボロになってしまっている。
「私は情けないほどの下流老人だ…」
その言葉が心の中で響くたびに、涙が溢れそうになる。節子は、自分の境遇に対して無力感を感じていた。こんなふうに泣きそうになっている自分は、素直なのかもしれないと思いながらも、それを誰かに見せることはできない。
ある日、節子は意を決して地域の福祉センターに向かった。自分の状況を少しでも改善する方法があるのではないかと考えたからだ。ドアを開けると、職員の若い女性が温かい笑顔で迎えてくれた。
「いらっしゃいませ。どうされましたか?」
節子は恥ずかしさを感じながらも、自分の問題を話し始めた。「最近、尿失禁がひどくてね。紙おむつを使いたいけど、そんなお金はなくて…」
職員は頷きながら聞いてくれた。「それは大変ですね。でも、おむつやおねしょパットに関して、支援制度があります。収入が限られている場合、助成を受けることができるんです。」
節子は目を見開いた。そんな制度があるとは知らなかったのだ。「本当ですか?でも、なんだか恥ずかしくて…」
「大丈夫ですよ、節子さん。必要なものを手に入れるために助けを求めるのは、決して恥ずかしいことではありません。皆さん、いろんな理由で支援を受けていますし、それで生活が少しでも楽になるなら、遠慮なく利用してほしいと思います。」
節子はその言葉に少しだけ安心感を覚えた。自分が抱えている問題は、決して一人で解決しなければならないものではないのかもしれない。そう思いながら、彼女は申請書類を受け取った。
数日後、支援が決まり、節子は福祉センターから提供された紙おむつを受け取ることができた。そのおむつを手にしたとき、彼女は少しだけほっとした気持ちになった。
「これで少しは安心して眠れるかもしれない…」
その夜、節子は新しいおむつを装着して布団に入った。いつもなら不安でいっぱいだった夜が、少しだけ静かなものに感じられた。布団も少しふかふかしているように思えた。久しぶりに、ゆっくりと深い眠りに落ちていく感覚があった。
しかし、そんな安心も長くは続かなかった。数週間が経つと、支援で提供される紙おむつの量が限られていることに気づいたのだ。決められた数を使い終えると、また自分で何とかしなければならない。節子は再び古いタオルを敷き始めた。支援を受けても、現実はなかなか変わらない。お金の問題は依然として重くのしかかっている。
「これが私の運命なのか…」
節子は一人でいる時間が増えるたびに、その言葉が頭に浮かぶ。こんな生活がずっと続くのだろうか。誰も助けてはくれないのか。そんな思いが心を覆うたびに、胸の奥がきゅっと締め付けられるような気がした。
ある日、節子はスーパーで古い知り合いの美代子と偶然出会った。美代子はいつも明るく、若い頃から社交的な性格だった。節子を見つけると、笑顔で話しかけてきた。
「節子さん、お久しぶりね。元気にしてた?」
「まあ、なんとかね…」と節子は少し笑って答えたが、その笑顔はどこかぎこちない。
美代子はすぐにその様子に気づいた。「何かあったの?」
節子は一瞬ためらったが、思い切って話すことにした。「実は、尿失禁がひどくてね。生活も大変で…」
美代子は真剣な表情で頷いた。「それは辛いわね。でも、誰にも言わずに一人で抱え込んじゃだめよ。私もできることがあれば手伝うから。」
節子は思わず涙がこぼれそうになった。「ありがとう、美代子さん。でも、もう十分よ。自分で何とかするしかないって思ってるの。」
美代子は優しく節子の手を握った。「そんなことないよ。節子さん、一人じゃないんだから。」
その日、美代子との会話を通じて、節子は少しだけ心が軽くなった気がした。自分の孤独感は、周りにいる人々との距離感から来ていたのかもしれない。節子は自分の素直な気持ちをもう少し人に話してみようと思った。
泣きそうになるのは、決して弱さの証ではない。誰かに寄り添ってもらいたい、その素直な願いを認めることも、大切なのかもしれない。そんなふうに、節子は少しずつ、自分の心を開くことを学んでいった。
それでも、現実は変わらない。しかし、孤独に耐えながらも、節子は自分の心の中に少しだけ新しい光を見つけたような気がした。それが本当に何かを変えるかどうかは分からないけれど、少なくとも彼女の胸の内には、新しい一歩を踏み出す勇気が芽生え始めていた。
節子は、75歳の一人暮らし。朝の光が薄く差し込む古いアパートの一室で、彼女はため息をついた。最近、尿失禁が増えてきている。何度下着を取り替えてもすぐにまた汚れてしまい、そのたびに洗濯を繰り返す。洗い終えた下着を干しながら、ふと情けない気持ちがこみ上げてきた。
「こんなことになってしまうなんて…」
節子の生活は、決して楽なものではなかった。夫を亡くしてから数十年、子どももいない彼女は、ずっと一人でこのアパートで暮らしている。かつては働いていたが、年金だけでは生活費を賄うのが精一杯だ。そんな中で尿失禁が増えてしまい、彼女の悩みはますます深刻になっていた。
紙おむつを使えば解決するのかもしれない。しかし、それを買うお金がない。おねしょパットさえも買えない。節子は古いバスタオルを敷いて寝ているが、それも擦り切れて穴が開いてしまった。夜中に目を覚ますと、冷たい湿気が布団に染み込んでいるのを感じ、また泣きたくなる。
「もう少しだけお金があったら…」と節子は思う。しかし、それは夢のまた夢のような話だった。節子の生活費は、毎月の年金だけ。そこから家賃や光熱費、食費を差し引くと、残るお金はほんのわずかだ。医者にかかることも、薬を買うことも、慎重に選ばなければならない。何かを買うたびに、「本当に必要か?」と自問自答しなければならない。
尿失禁の問題も同じだ。紙おむつやおねしょパットを使う余裕などない。彼女は古いタオルを洗っては使い続けるしかなかった。それでも何度も繰り返しているうちに、タオルは擦り切れて、もうボロボロになってしまっている。
「私は情けないほどの下流老人だ…」
その言葉が心の中で響くたびに、涙が溢れそうになる。節子は、自分の境遇に対して無力感を感じていた。こんなふうに泣きそうになっている自分は、素直なのかもしれないと思いながらも、それを誰かに見せることはできない。
ある日、節子は意を決して地域の福祉センターに向かった。自分の状況を少しでも改善する方法があるのではないかと考えたからだ。ドアを開けると、職員の若い女性が温かい笑顔で迎えてくれた。
「いらっしゃいませ。どうされましたか?」
節子は恥ずかしさを感じながらも、自分の問題を話し始めた。「最近、尿失禁がひどくてね。紙おむつを使いたいけど、そんなお金はなくて…」
職員は頷きながら聞いてくれた。「それは大変ですね。でも、おむつやおねしょパットに関して、支援制度があります。収入が限られている場合、助成を受けることができるんです。」
節子は目を見開いた。そんな制度があるとは知らなかったのだ。「本当ですか?でも、なんだか恥ずかしくて…」
「大丈夫ですよ、節子さん。必要なものを手に入れるために助けを求めるのは、決して恥ずかしいことではありません。皆さん、いろんな理由で支援を受けていますし、それで生活が少しでも楽になるなら、遠慮なく利用してほしいと思います。」
節子はその言葉に少しだけ安心感を覚えた。自分が抱えている問題は、決して一人で解決しなければならないものではないのかもしれない。そう思いながら、彼女は申請書類を受け取った。
数日後、支援が決まり、節子は福祉センターから提供された紙おむつを受け取ることができた。そのおむつを手にしたとき、彼女は少しだけほっとした気持ちになった。
「これで少しは安心して眠れるかもしれない…」
その夜、節子は新しいおむつを装着して布団に入った。いつもなら不安でいっぱいだった夜が、少しだけ静かなものに感じられた。布団も少しふかふかしているように思えた。久しぶりに、ゆっくりと深い眠りに落ちていく感覚があった。
しかし、そんな安心も長くは続かなかった。数週間が経つと、支援で提供される紙おむつの量が限られていることに気づいたのだ。決められた数を使い終えると、また自分で何とかしなければならない。節子は再び古いタオルを敷き始めた。支援を受けても、現実はなかなか変わらない。お金の問題は依然として重くのしかかっている。
「これが私の運命なのか…」
節子は一人でいる時間が増えるたびに、その言葉が頭に浮かぶ。こんな生活がずっと続くのだろうか。誰も助けてはくれないのか。そんな思いが心を覆うたびに、胸の奥がきゅっと締め付けられるような気がした。
ある日、節子はスーパーで古い知り合いの美代子と偶然出会った。美代子はいつも明るく、若い頃から社交的な性格だった。節子を見つけると、笑顔で話しかけてきた。
「節子さん、お久しぶりね。元気にしてた?」
「まあ、なんとかね…」と節子は少し笑って答えたが、その笑顔はどこかぎこちない。
美代子はすぐにその様子に気づいた。「何かあったの?」
節子は一瞬ためらったが、思い切って話すことにした。「実は、尿失禁がひどくてね。生活も大変で…」
美代子は真剣な表情で頷いた。「それは辛いわね。でも、誰にも言わずに一人で抱え込んじゃだめよ。私もできることがあれば手伝うから。」
節子は思わず涙がこぼれそうになった。「ありがとう、美代子さん。でも、もう十分よ。自分で何とかするしかないって思ってるの。」
美代子は優しく節子の手を握った。「そんなことないよ。節子さん、一人じゃないんだから。」
その日、美代子との会話を通じて、節子は少しだけ心が軽くなった気がした。自分の孤独感は、周りにいる人々との距離感から来ていたのかもしれない。節子は自分の素直な気持ちをもう少し人に話してみようと思った。
泣きそうになるのは、決して弱さの証ではない。誰かに寄り添ってもらいたい、その素直な願いを認めることも、大切なのかもしれない。そんなふうに、節子は少しずつ、自分の心を開くことを学んでいった。
それでも、現実は変わらない。しかし、孤独に耐えながらも、節子は自分の心の中に少しだけ新しい光を見つけたような気がした。それが本当に何かを変えるかどうかは分からないけれど、少なくとも彼女の胸の内には、新しい一歩を踏み出す勇気が芽生え始めていた。
0
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

【完結】フェリシアの誤算
伽羅
恋愛
前世の記憶を持つフェリシアはルームメイトのジェシカと細々と暮らしていた。流行り病でジェシカを亡くしたフェリシアは、彼女を探しに来た人物に彼女と間違えられたのをいい事にジェシカになりすましてついて行くが、なんと彼女は公爵家の孫だった。
正体を明かして迷惑料としてお金をせびろうと考えていたフェリシアだったが、それを言い出す事も出来ないままズルズルと公爵家で暮らしていく事になり…。





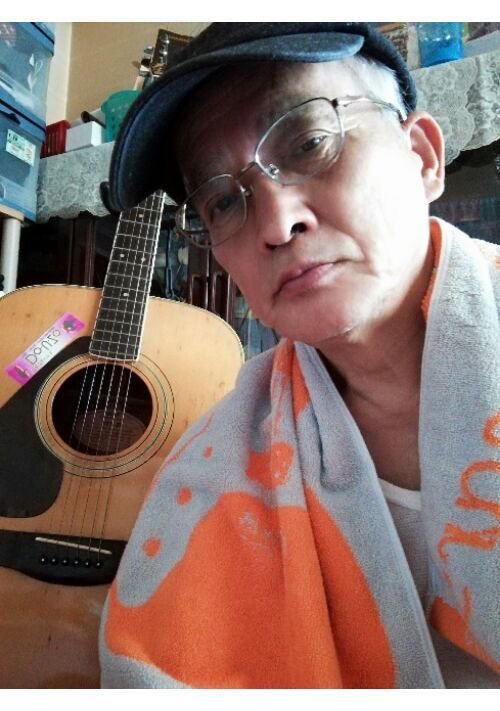

スルドの声(交響) primeira desejo
桜のはなびら
現代文学
小柄な体型に地味な見た目。趣味もない。そんな目立たない少女は、心に少しだけ鬱屈した思いを抱えて生きてきた。
高校生になっても始めたのはバイトだけで、それ以外は変わり映えのない日々。
ある日の出会いが、彼女のそんな生活を一変させた。
出会ったのは、スルド。
サンバのパレードで打楽器隊が使用する打楽器の中でも特に大きな音を轟かせる大太鼓。
姉のこと。
両親のこと。
自分の名前。
生まれた時から自分と共にあったそれらへの想いを、少女はスルドの音に乗せて解き放つ。
※表紙はaiで作成しました。イメージです。実際のスルドはもっと高さのある大太鼓です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















