お気に入りに追加
29
あなたにおすすめの小説

俺は善人にはなれない
気衒い
ファンタジー
とある過去を持つ青年が異世界へ。しかし、神様が転生させてくれた訳でも誰かが王城に召喚した訳でもない。気が付いたら、森の中にいたという状況だった。その後、青年は優秀なステータスと珍しい固有スキルを武器に異世界を渡り歩いていく。そして、道中で沢山の者と出会い、様々な経験をした青年の周りにはいつしか多くの仲間達が集っていた。これはそんな青年が異世界で誰も成し得なかった偉業を達成する物語。

蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。

異世界でぺったんこさん!〜無限収納5段階活用で無双する〜
KeyBow
ファンタジー
間もなく50歳になる銀行マンのおっさんは、高校生達の異世界召喚に巻き込まれた。
何故か若返り、他の召喚者と同じ高校生位の年齢になっていた。
召喚したのは、魔王を討ち滅ぼす為だと伝えられる。自分で2つのスキルを選ぶ事が出来ると言われ、おっさんが選んだのは無限収納と飛翔!
しかし召喚した者達はスキルを制御する為の装飾品と偽り、隷属の首輪を装着しようとしていた・・・
いち早くその嘘に気が付いたおっさんが1人の少女を連れて逃亡を図る。
その後おっさんは無限収納の5段階活用で無双する!・・・はずだ。
上空に飛び、そこから大きな岩を落として押しつぶす。やがて救った少女は口癖のように言う。
またぺったんこですか?・・・
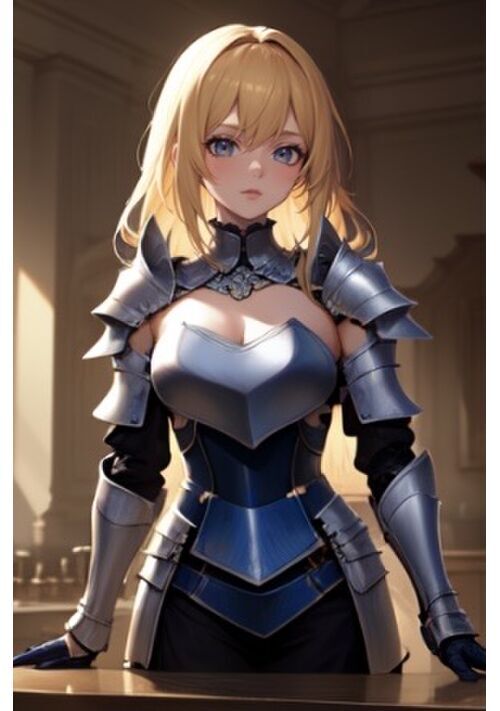
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!

異世界で買った奴隷が強すぎるので説明求む!
夜間救急事務受付
ファンタジー
仕事中、気がつくと知らない世界にいた 佐藤 惣一郎(サトウ ソウイチロウ)
安く買った、視力の悪い奴隷の少女に、瓶の底の様な分厚いメガネを与えると
めちゃめちゃ強かった!
気軽に読めるので、暇つぶしに是非!
涙あり、笑いあり
シリアスなおとぼけ冒険譚!
異世界ラブ冒険ファンタジー!

社畜の俺の部屋にダンジョンの入り口が現れた!? ダンジョン配信で稼ぐのでブラック企業は辞めさせていただきます
さかいおさむ
ファンタジー
ダンジョンが出現し【冒険者】という職業が出来た日本。
冒険者は探索だけではなく、【配信者】としてダンジョンでの冒険を配信するようになる。
底辺サラリーマンのアキラもダンジョン配信者の大ファンだ。
そんなある日、彼の部屋にダンジョンの入り口が現れた。
部屋にダンジョンの入り口が出来るという奇跡のおかげで、アキラも配信者になる。
ダンジョン配信オタクの美人がプロデューサーになり、アキラのダンジョン配信は人気が出てくる。
『アキラちゃんねる』は配信収益で一攫千金を狙う!

貴族家三男の成り上がりライフ 生まれてすぐに人外認定された少年は異世界を満喫する
美原風香
ファンタジー
「残念ながらあなたはお亡くなりになりました」
御山聖夜はトラックに轢かれそうになった少女を助け、代わりに死んでしまう。しかし、聖夜の心の内の一言を聴いた女神から気に入られ、多くの能力を貰って異世界へ転生した。
ーけれども、彼は知らなかった。数多の神から愛された彼は生まれた時点で人外の能力を持っていたことを。表では貴族として、裏では神々の使徒として、異世界のヒエラルキーを駆け上っていく!これは生まれてすぐに人外認定された少年の最強に無双していく、そんなお話。
✳︎不定期更新です。
21/12/17 1巻発売!
22/05/25 2巻発売!
コミカライズ決定!
20/11/19 HOTランキング1位
ありがとうございます!

宝くじ当選を願って氏神様にお百度参りしていたら、異世界に行き来できるようになったので、交易してみた。
克全
ファンタジー
「アルファポリス」と「カクヨム」にも投稿しています。
2020年11月15日「カクヨム」日間異世界ファンタジーランキング91位
2020年11月20日「カクヨム」日間異世界ファンタジーランキング84位
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















