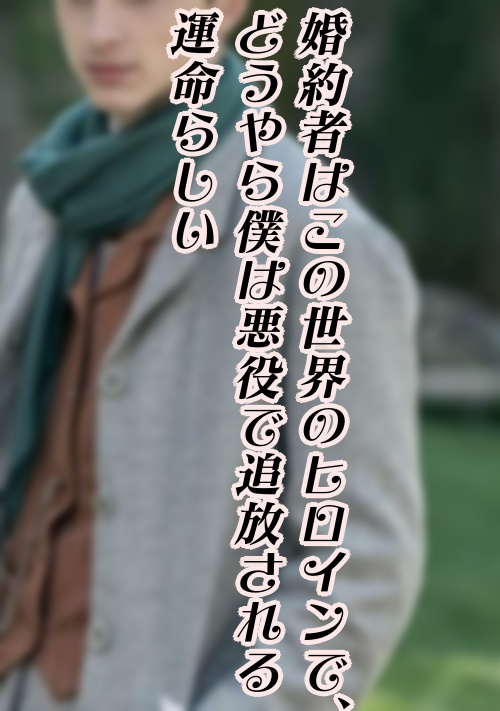299 / 435
二人目の妖精
しおりを挟む
目の前にいる身長30センチ弱の少女。
背中に羽をもち、葉っぱと花びらで作られたタイト目なドレスのような服をまとった姿は、紛うことなく妖精そのものだ。
俺が知る妖精といえば、リッカだけだったが、新しくやってきた妖精は、リッカよりも女性的なフォルムを有しており、何となくだがリッカよりも年上のような印象を覚える。
一人称は僕であったが、性別は女性で間違いない。
やや褐色気味の肌にアッシュブロンドのショートカットの髪型が、某映画に出てくるハリウッド女優で似たようなのがいたなと思わせる。
今しがた口にした、友達を探してやってきたという言葉から察するに、この妖精はもしかしたらリッカを探しているのかもしれない。
現時点でこの辺りにいる妖精といえば、俺の知る限りではリッカと目の前の妖精だけのはずだ。
となれば、目当てはリッカだという答えに行き着くのは自然なことだろう。
しかも、この妖精は俺のところで世話になっているといった。
世話をしている妖精など、リッカ以外に心当たりはない。
「…あの、聞こえてますか?」
観察と考察に思考を割いていたせいで、呆けていたように思われたらしく、不安げな声で呼びかけられてしまった。
いかんいかん。
客を前にしてする態度ではなかったな。
「あ、あぁ、すまない。まさか妖精が尋ねてくるとは思わなくて、ちょっと驚いてしまった。俺のところで世話になっている妖精というのは、もしかしてリッカのことか?確かに彼女はここにいるよ」
「やっぱりここにいたんですね。よかったぁ…」
俺の言葉を聞き、ホッとした顔に変わった妖精に、どうやら彼女はそれなりの苦労をしてここまでやってきたのだろうと思わされた。
「ちょうど今、リッカと朝食をとっていたところだ。ま、こんなとこで立ち話もなんだし、とにかく中へどうぞ」
「あ、はい。じゃあ…お邪魔します」
中へ招き入れ、リッカたちのいるテーブルへと向かう。
と言っても、そう離れているわけではないので扉をくぐってしまえば、卓上に座り込んで食事をとっていたリッカの姿はすぐに見える。
「おー、アンディ。客は誰だった…って、シェスカじゃん。こんなとこまで何しに来たんだ?」
当然リッカからも俺達のほうは丸見えなので、戻ってきた俺の背後をついてくる妖精も目に入っており、知り合いと分かったからか、呆れたような顔で名前を呼んだ。
この妖精の名前はシェスカと言うらしく、リッカの反応から見て、そこそこの親しい間柄が窺えた。
「あんたねぇ…何しに来たじゃないわよ!すぐに戻るって言って出て行って、どんぐらい経ったと思ってるの!?」
リッカの言葉がきっかけとなったのか、それまでの礼儀正しさをかなぐり捨てる勢いで、シェスカは高速でリッカに詰め寄っていった。
さっき外で話したときは、キッチリとした態度だったのだが、今リッカに食って掛かる勢いの様子を見ると、妖精というのはもしかして気性の荒い種族なのだろうか。
初めてリッカと遭遇した時も思ったが、妖精はその可憐な見た目に反して性格に癖が強い気がする。
「どんぐらいって……あ」
何かを思い出したのか、シェスカの剣幕を怪訝そうに見ていたリッカの表情が、一瞬でバツの悪そうなものへと変わった。
「思い出したみたいね。そう、あんた四日ぐらい留守にするって出てったのよ?なのに!十日経っても帰ってこないもんだからって!僕が探しに行かされたの!」
それを聞いて俺がリッカを呼び出した日を思い出してみると、今日で軽く半月ほどは経っているはず。
空中で地団太を踏むという器用さを披露するシェスカは、リッカを探しに行かされたのがよっぽど不満だったようだ。
仲は悪くないと思ったが、この様子だと郷の方ではリッカに振り回されているのかもしれない。
「そういやそんぐらいって言ったっけ。いや、実はこいつらに付き合ってちょっと予定外の用事が出来ちまってさ。シェスカを寄こしたのは爺様連中か?その用事も済んだし、近く戻るって伝えといてくれ。じゃ、よろしく」
リッカの奴、わざわざ探しに来てくれた仲間に、その言い方はまずいだろ。
妖精の里の正確な位置はわからないが、リッカと合流したあの湖を基準にすれば、この場所はだいぶ離れている。
この小さい体でここまで旅してきたのだから、もう少し労わってやったほうがいい。
「は?何その言い方。僕はリッカのために三日かけてここまで飛んできたんだけど?」
そら見たことか。
案の定、シェスカはそれまでの興奮から一転して、能面のような感情の消えた顔に変わり、冷めた目をリッカへ向ける。
何かがカチンと来た爆発寸前の顔といった感じだ。
「分かってるよ。ご苦労さん、用事も済んだろ?帰っていいぞ」
「…このっ!リッカー!」
シェスカの表情の変化に気付いていないのか、変わらない態度のリッカに、ついにシェスカはキレてしまった。
フワリと空中に浮かび上がったシェスカが、声を張り上げながら鋭い動きでリッカへと組みつく。
悪質タックルが可愛いぐらいの、その弾丸のような勢いに、リッカはテーブルから弾き飛ばされ、シェスカもリッカに組み付いたまま、両者は一塊になって空中でクルクルと回りだす。
どちらも妖精の羽による飛行で姿勢を制御しようと試みているのか、複雑な動きで飛び回っている。
「いーってって!やめろって!なにキレてんだよ!シェスカ!」
「うるさい!僕の苦労も知らないで!」
困惑気味のリッカに、怒りに我を忘れているシェスカが殴ったり蹴ったりしている様子は、子供の喧嘩のようでもあるが、攻撃のたびに魔力を波動として周囲にまき散らしているせいで、室内の調度品が色々と影響を受けている。
「あわわわ…。アンディ、どうしよう」
「どうしようったって」
目まぐるしく動き回る二人に、手の出しようもない俺とパーラはただ見ているばかりで、せめて安全な場所にでもと、テーブルの下に揃って潜り込むしかできない。
そのテーブルから覗き見た感じでは、もうリッカ達は取っ組み合いの状態から脱し、今は空中でぶつかったり離れたりを繰り返す、空中格闘戦へと移行していた。
「なんなんだよお前!いっつもあたいの後追っかけてきやがって!」
「あんたがチョロチョロ動きまわるから、周りに迷惑かけないよう見てるんでしょうが!」
交差するたびに文句を言いあうという器用なドッグファイトは、部屋のあちこちに被害が出ていることを忘れれば、かなり見応えのあるショーだ。
錐もみ状態ですれ違い様に攻撃しあい、不規則な軌道を描きつつ離れてまたぶつかるという高度な空中戦に、俺達が噴射措置を使うときの手本として技術を盗めるかと期待もしたが、あまりにも高等テクニックまみれで参考にはなりそうにない。
「長老んとこの畑!草取りを僕に押し付けたのもリッカでしょ!」
「いつの話だよ!知るか!」
「ほんの十年前のことよ!いっつもそう!嫌なことは僕に押し付けてさ!年が近いからって面倒見させられるこっちの身にもなってよ!」
シェスカも不満は吐き出し終わったようだが、今度は今日まで貯めこんでいたものを口にしだした。
広がっていく被害の割りに、言い合いの内容はショボいものへと変わっていく。
「ちっ!それを言うかよ!…今年はハチミツ三回!奢ってやったぞ!」
「僕は十二回は奢らされた!」
「しっかり数えてんじゃっ…ねーよ!」
直上から迫るシェスカの蹴りを、リッカはその場でバク転をするようにして足で迎撃し、二人の足がぶつかりあった衝撃が波となって辺りに広がっていく。
「ひゃー、あの二人すっごいよ。妖精ってこういう戦いするんだね」
「ああ。一撃ごとに周りの空気が震えてやがる。手足へとんでもねぇ量の魔力を込めて、攻撃と防御を両立させてんだな」
二人の戦いを見ながら、俺とパーラは感想を言い合う。
もう部屋の中に被害が出ることはあきらめきっているので、今はただの観客に成り下がっていた。
あの小さい体で重機がぶつかったような衝撃波を生み出しているからくりに、さすが魔力の扱いに長けた妖精種だと感心してしまう。
俺達の使う身体強化とは次元の違うその魔力の運用法に、戦慄すら覚える。
普段のリッカの姿しか知らなかったために、正直、舐めていたのは否めない。
「あ、また壊した。ねぇアンディ、あの壺って何入ってたやつ?」
「なんだったっけ…あぁ、根菜の酢漬けか。そろそろ食べごろだったから出しておいたんだが、失敗したなぁ…ははっ」
もう何度目かになる食材の喪失を見ても、乾いた笑いしか出てこない。
好きにさせるしかないと二人をそのままにした俺が悪いのだが、そろそろここらで被害も打ち止めにならないものだろうか。
祈るしかできない俺はなんて無力なんだ。
「あちゃー。アンディ、このソファはだめだよ。背もたれが穴だらけだもん」
リッカとシェスカの戦いの後片付けをしていると、キッチンにいる俺にパーラがソファの惨状を教えてくれた。
室内はちょいとした嵐にあったような荒れ具合だし、ソファもダメージはあるだろうと思っていたが、穴を空けられたのは予想外だ。
あのソファはかなりしっかりとした作りだったし、ライフル弾でも防ぎきると思っていたのだが、妖精の一撃には耐えられなかったようだ。
「まじか。板でふさいで、布を詰めたら何とかならんか?」
「ならないねぇ。これは買い替えだわ」
雑巾をしぼりながら、また増えた出費にため息が漏れる。
ここまでに壊されたり喪失したものの被害を金銭的価値に換算すると、平民の一家が一年は遊んで暮らせる額に届く。
これはあくまでも貨幣換算での話で、金に換えられない価値のものも含めると損害はもっと大きい。
特に今日までこだわりにこだわって貯めこんだ香辛料や食材がダメになったのが痛く、駆け出しの商人がもし俺と同じ被害を受けたら、ショック死するか首を吊るかのレベルだ。
「はぁー…。二人とも、大分やらかしてくれたな」
頭を抱えながらキッチンを出て、散らかった部屋の中央で反省中の妖精二人に声をかける。
「んぎぎぎぎ…。わ、悪かったよ、アンディ。謝るよ。シェスカがやったことのっ、いくらかはあたいにも責任はあるしっな」
「ひぃ…ひぃ…。な、なにがいくらかよ。あんただって、派手に壊してたじゃないの。ひぃ…」
幾分落ち着いたとはいえ、お互いを非難しあうのをやめない辺り、まだまだ反省は足りないようだ。
さっき俺とパーラには素直に謝ったのに。
「まぁもっと早い内に止めに入らなかった俺も悪いが、やったことの償いはしてもらいたいね。特にダメになった食材には手に入りにくいのも多い。全部とは言わなくとも、多少は何らかの形で返してもらえるとありがたいんだが」
土地や季節別にと、いろんなところからかき集めていた食材だ。
中には次に手に入るのは来年以降というのもある。
同じものでなくてもいいので、可能であれば妖精のコネなんかでも使って、ある程度の補填はして欲しい。
「な、なぁアンディ。あたいらももう反省したからさ、これやめていいか?」
「そ、そうそう。リッカの言う通り、僕たち反省したよ?だからこの、わけわかんないぐるぐる回るのやめさせてくれると嬉しいなー…なんて」
縋るような目つきでリッカ達が懇願するのは、いま彼女達に科している刑罰の終了についてだ。
示し合わせたように揃って目を潤ませてこちらを伺う姿で、改めてリッカ達の様子をじっくりと観察する。
あれだけの騒動を起こした罰として、リッカ達には反省のためにと横倒しにしたバイクの前輪を二人に手押しで回させていた。
世紀末な漫画でも有名な、人力で回させて発電させるようなあれだ。
確かピストリヌゥムという名前の装置だったか。
常にブレーキを軽くかけた状態の車輪を回す作業は、超小柄な二人にはかなりの重労働となっている。
壊れたままだったバイクに少し手を加え、何本かスポークを抜いた車輪の内側にリッカ達が入り、残ったスポークを掴んで回すというその絵は、改めてよく見ると滑稽さの中に残酷さが漂っていた。
なお、この車輪を回しても、小麦粉が作られたり電力が生み出されてもいないので、まったく意味のない作業を強いているだけだったりする。
所謂空役というやつだ。
そのことも、二人を参らせている一因ではあるようだ。
「ん?んー…どうすっかなぁ」
「もうやめさせてもいいんじゃない?どこともつながってない装置って、完全に無意味なやつじゃん、それ」
悩む仕草をリッカ達に見せつけていると、自分の担当を片付け終えたパーラが呆れがでやってきてそんなことを言う。
お仕置きということは分かっているだろうが、もう三十分は休みなくやらされている二人に、パーラもそれなりに同情しているらしい。
「無意味ってことはないだろ。反省させるって意味は込められているぞ」
「いや、私は何も生み出していないってところを言ってんだけど」
空役とはそういうもんだ。
しかし、そろそろいいだろうというパーラの意見に同意する気持ちがないわけではない。
ここに来るまでのことなどをシェスカからも色々と聞きたい。
「…いいだろう。二人とも、それはもう終わりだ」
『ぶはぁ~…』
いいという俺の言葉を聞き、大きく息を吐きだしながらその場に頽れるリッカ達。
荒い呼吸と全身をうっすらと覆う汗は、ともすれば働いた者の勲章にも見えるが、まったく生産性のない作業だったということを考えれば、無駄な仕事だったとも言える。
「えー、もう知ってるとは思うけど、改めて名乗らせてもらうわね。僕の名前はシェスカ、見ての通りの妖精よ。南方霊樹の森の妖精で、そっちのリッカとは同郷。郷じゃリッカの面倒を見てたから、姉みたいなものね」
「なーにが姉だよ。あたいと二十ぐらいしか違わねぇくせに」
「二十年だろうが三十年だろうが、早く生まれて面倒を見てたんだから僕が姉でしょうが」
改めて、テーブルに着いた俺たちはシェスカと互いに名乗りあった。
それを聞いてぶっきらぼうな口調のリッカだが、なんだか照れているように見えるのは気のせいではあるまい。
口ではああ言っても、シェスカを姉と思っている気持ちはあるようで、身内が友達に挨拶をしている時に見せるような顔をしている。
そのシェスカだが、ここに来た目的は既に聞いていた通り、予定日を過ぎても郷に戻ってこないリッカを探しに来たとのこと。
本来なら一人でぶらりとどこかにいっても探しに来るほどリッカは子供でもないし、シェスカも過保護でもないのだが、今回は帰ってくる日を事前に言い残していたため、予定日から大幅に遅れていたのを郷の老人達が心配してシェスカを派遣したわけだ。
ここでシェスカが選ばれたのは、リッカの姉を自負するだけあって普段から一緒にいることが多いせいだとのこと。
自身も郷でやることはあったが、長老経由で命じられては断ることもできず、リッカが残した魔力の跡を追いかけ、今日の未明にようやくこの山へ辿り着いたという。
「魔力の跡ねぇ。妖精ってそういうので追跡できるんだ?」
くたびれた顔で語るシェスカの話に出てきた魔力の跡という言葉に、パーラはテーブルに身を乗り出すようにして興味を示した。
追跡術の心得のあるパーラにしてみれば、未知の追跡手段にはやはり好奇心を抱くらしい。
「妖精っつーか、シェスカの能力だな。あたいの知る限り、シェスカほど魔力の探知が上手いやつは他にいねぇ」
「まぁ自慢ってほどじゃないけど、僕って生まれつき魔力の波動を拾いやすい体質なの。特に、僕らの鱗粉って虚空に溶けてもしばらく残留するから、同じ妖精なら追跡は難しくないわ。…まぁ、今回はなんでかすごい高いところに残留物が漂ってたから、辿るのも大変だったけど」
「あぁ、そりゃあたいが飛空艇で移動したからだな」
「飛空艇?何それ」
シェスカは飛空艇を知らないらしく、リッカの言葉に首をかしげる。
仕草も相まって、こうしてみると可憐な少女のように見えるが、その背後に見える部屋の惨状のせいで、逆に怖さを覚える。
「お前が今いるここ。これが、空を飛ぶんだよ。あたいら妖精よりずっと早く、しかもえらい高いところをな」
「…嘘でしょ?いつの間にか人間が空を飛べるようになったってこと?っていうか、ここって家じゃないの?」
困惑と疑いの混ざった目が俺とパーラに向けられる。
ソーマルガが大々的に発表したおかげで、今の世の中では飛空艇はトレンドなのだが、郷に籠っている妖精族の間では、まだまだメジャーのメの字にすらなれていないらしい。
「人間がというより、そういう乗り物を遺跡で見つけて乗ってるんだ」
「そうそう。私らは飛空艇を家にしてるってだけ」
「ふーん。世間は僕が知るのとは大分違ってきてるってことか。こんなのが空を飛ぶとはねぇ」
俺とパーラの言葉を受け、シェスカは好奇心が刺激されたのか、すぐそばの壁をペタペタとさわり出した。
空を飛ぶということにかけて、妖精の自分にも思うところがあるのか、その様子からは飛空艇にそこそこの興味を抱いているように見える。
「そういえば、パーラさんって言ったっけ?」
飛空艇にはそれ以上興味を持たなかったのか、シェスカがパーラへと声をかけた。
「あ、うん」
「あなたのそれ、どうしたの?見たところ幽星体の延長よね。なんか変な呪いでももらった?」
何やら神妙とも不思議そうともとれる顔のシェスカが見ているのは、パーラというよりその頭にある耳の方へだ。
パッと見た感じでは狼系統の獣人のパーラだが、シェスカは元のパーラを知らないはずなのに、幽星体がはみ出ている状態というのを見事に言い当てた。
俺には見分けは付かないが、妖精には分かりやすいということなのだろう。
呪いとはまた物騒な言葉を口にするものだ。
というか、この世界にも呪いは存在するのか。
魔術が存在する以上、あってもおかしくはないが、今までお目にかかってこなかったので新鮮だ。
「たっはっはっは!呪いってのはいいねぇ。ある意味じゃそうかもな。けど、生憎とこいつのは加護のせいだ」
何が面白いのか、大笑いをしながらリッカがパーラのことを説明しだす。
この場にいる中で加護を授かった経緯を知らないのはシェスカだけなので、転真体との遭遇まで遡って話されていく。
「転真体!?ちょっと、それってほんとなの?」
「嘘じゃねぇよ。あたいはこの目で確かに見たし、歌での対話も見届けた。まぁ、実際にやったのはパーラだけど」
リッカもそうだったが、シェスカも転真体というのには過敏な反応を示す。
妖精にとって、転真体というのがいかに特別な存在かというのが伝わってくる。
「リッカを探しに来て転真体の情報が聞けるなんて、苦労の見返りには十分ね……あれ?もしかして加護って、その転真体の?」
「お、鋭いなシェスカ。その通り、パーラがこうなった原因の加護は、そいつが寄こしやがったんだよ。この姿もそのせいってわけさ」
「ほぉー……え、加護ってこうなるんだっけ?」
「さあ?あたいも加護持ちをそれほど知らねーし。そういうこともあるんじゃね?」
「いやないでしょ。少なくとも僕は聞いたことないよ」
適当なリッカと違い、シェスカは加護についてもそこそこ知識はあるようで、その反応でパーラのこの状態が加護としては普通じゃないことがよくわかった。
「けどパーラの話だと、別段体に悪いことが起きてるってわけじゃないし、特に何かするこたぁないだろ。どうせほっときゃ元の姿に戻るよな?」
「うーん、それはそうかもしれないけど……三割ってとこかな?」
「え、三割って何が?」
渋い顔でつぶやいたシェスカの言葉へ、敏感に反応したのはパーラだ。
「何がって…言いにくいんだけど、獣人の姿で固定される可能性、かな?十日もしたら、どっちに固定されるか結果はわかると思うよ」
「……はい!?ちょっと待ってよ!もしかしたら私、この姿のままになるってこと!?なんで!」
「なんでってあぶばばばばばばっ」
慌てたパーラがテーブルの上にいたシェスカを一瞬にしてつかみ取り、目線の高さでぶんぶんと揺らすという危ない問い詰め方を見せた。
「落ち着けパーラ!それだとシェスカが喋れないだろ」
パーラの腕を抑えて動きを止め、その手からシェスカを解放させると、激しい揺れのせいでか、テーブルの上に降り立った足で座り込んでしまった。
「ご、ごめん、シェスカ」
「……ふぅ、いいよ、気にしないで。急にあんなこと言われたら驚くよね。誰だってそうする。僕だってそうする」
パーラを気遣うようなことを言うが、ボケっとした顔のシェスカが見ている方向にいるのは俺だ。
どうやらまだ焦点は合っていないらしい。
ちょうどいいので、パーラに言ったことの真意を俺が尋ねるとしよう。
「で、どういうことだ?パーラはこのままになるって?」
「いや、絶対そうだってわけじゃないのよ?このまま幽星体の変化が肉体になじんだ時、大体三割の確率でこの狼っぽい特徴が残るかもしれないってだけの話ね」
詳しく聞いてみると、幽星体の変化が肉体に出ている現状がそもそも特殊なため、人間としての姿と獣人の姿のバランスがリアルタイムで変化しているのがシェスカには感じ取れているらしい。
リッカには分からなかったが、魔力の探知能力が高いシェスカだからこその見立てなのだろう。
「三割ね…。七割は人間に戻る可能性が高いと受け取れるが」
「何言ってんのアンディ!三割とか七割とかじゃないって!私にしたら、戻れるか戻れないかの二択なの!」
「む、一理あるな」
一瞬、七割の方に希望を託してみたくなったが、切羽詰まったようなパーラの声に、要はセーフかアウトかの差だと気が付かされた。
「ねぇシェスカ。何とかならない?私、元の体がいいよ」
「何とかって言われても。その体でも別に不便はないんでしょ?ならその状態で残りの人生を歩むってのも悪くは…」
「そういう問題じゃないの!」
諭すシェスカの言葉に、歯をむいて声を張り上げるパーラの迫力が凄い。
狼化の影響によって、怒鳴った顔にはさすがの怖さがある。
「だ、だよねぇ。…あ、じゃあさ、幽星体の中にある、狼化の要因を封印するとかは?ちょっと高度な手だけど、やれないことはないよ」
ほう、封印とな。
そういう手もあるか。
魔術師として暮らして長いが、封印術の存在自体は耳にすれど、今の世で使い手の話は全く耳にしない。
ほとんど幻の技だといっても過言ではないだろう。
「封印か…それってシェスカがやれるの?」
「ううん、僕もリッカも封印術は使えないよ?郷にも使えるって人はいないしね」
「え…じゃあなんで封印の話をしたの?」
「やれる人にやってもらえばいいのよ。封印術って言ったら…今は誰がいるのかしら?」
言うだけ言って心当たりがないとは、シェスカも随分無責任なことを言うものだ。
まぁ世俗には疎い妖精にしてみれば、人間の中で誰が封印術を使えるかなど知っているわけもないが。
「あのさ、あたいも誰が封印術の使い手かってのは分かんねーけど、探しようはあるぞ」
「リッカが?なんだ、お前の知り合いか?」
「あたいのっていうか、お前らも知り合いだな」
意外だな。
俺達とリッカの共通の知り合いで、封印術の当てがあるとは。
いったい誰だ?
「ふっふっふっふ、その顔だと誰のことか見当もついていないな?」
「リッカお願い!勿体ぶらないで教えてよ!」
不敵な笑みで俺達の周りを飛び回るというウザさを見せつけるリッカに、パーラが悲痛な声で先を促す。
自分のことだけに、のんびりと答えを待っていられないようだ。
「…まぁいいや。パーラの気持ちを考えて、サクっと答え合わせしとくか。いいか?封印術ってのは結局魔術の一種だ」
「そりゃあな。むしろ魔術じゃなかったらなんだって話だ」
何をいまさらと、思わず呆れた口調で答えてしまった俺を、パーラがにらんでくる。
リッカの話を遮るなという意思がこもった、射殺すような視線に肩をすくめてしまう。
「アンディの言う通り。つまり、封印術師は魔術師が集まる場所で探せばいいんだよ。術師本人が見つかればそれでいいし、いなければいないでそういうとこなら情報も集めやすい。でだ、この辺りで魔術師が一番集まるっていえばどーこだ?」
順を追った丁寧な説明付きのなぞなぞの答えは、すぐに辿り着けた。
『あ!ディケット!』
「正~解っ!」
異口同音の俺とパーラに、笑顔を浮かべたリッカから花丸の正解を頂いた。
なるほど、リッカの案は実に理にかなったものだ。
世界中から人と教材が集まるディケットなら、封印術の使い手についても知っている人間や情報があってもおかしくはない。
最良なら、生徒や教師に封印術の使い手がいる可能性も無きにしも非ず。
「行ってみる価値はあるな」
「だね」
パーラと顔を見合わせ、ディケット行きが決まる。
「よーし!そうと決まったら早速行こう!あたいも久々にスーリア達に会いたいしな!」
リッカもディケットに行くのが楽しみのようで、踊るようにして室内を飛び回りだした。
友達との再会を思って喜ぶその姿は、天真爛漫そのものといった様子で微笑ましい。
「あいつらどうしてっかなぁ。スーリアの奴、またなんか美味いもん食わして―」
「喜んでるとこ悪いけど、リッカ。あんたはディケットには行けないよ。僕と一緒に郷に帰るんだからね」
水を差すとはこのことかという手本通り、シェスカの呆れた声が室内に響くと、リッカがピシリと動きを止めた。
器用にも、空中で飛んでいる最中の姿勢での停止だ。
「なん…だと」
辛うじてそれだけを口にし、錆びた機械人形のような動きでシェスカを見るリッカの目は、心なしか暗い色に染まっている。
「だってここでの用事は済んだんでしょ?だったら帰るのが当たり前じゃない。僕はあんたを連れ戻すために来たんだからね」
至極まっとうなことを言うシェスカに、リッカは逆らう根拠を持たない。
何せついさっき、用事が済んだから近い内に帰るというのを喧嘩の前に口にしていたのだから。
「…やだ」
「は?何が?」
俯いたリッカがボソリと呟き、それにシェスカが鋭い目で答えた。
その時のシェスカの目と冷たい言いように、俺は嫌な予感を禁じ得ない。
それはパーラも同様らしく、座っている椅子から少し腰を浮かせている。
いつでも動けるようにとのことだろう。
「やだやだやだやだ!あたいはディケットに行く!そんで友達と会って、美味い酒を奢りあうんだ!」
それは死亡フラグだぞ?
「だめよ!あんたは僕と一緒に帰るの!友達と会うのは、一回郷に帰ってからにしなさい!また出直せばいいじゃない!」
「郷に戻ったら、どうせ爺様連中に説教されて、当分郷から出るのを禁止されるにきまってる!」
「分かってるじゃない!そうよ!あんたはそれだけ心配かけたの!」
「うるせー!郷にはもうちょっとしたら戻るから、ここはあたいに任せて、シェスカだけ戻れって!」
徐々に言い合う声が大きくなり始めたリッカとシェスカの姿に、ついさっきも見た喧嘩の直前の熱の高まりを感じている。
これは、来るか?
「っこの!聞き分けなさい!リッカ!」
「だが断る!このリッカ!従えというやつに否というのが一番好きなのさ!」
「リッカー!」
「シェスカー!」
互いの名前を呼びあい、空中に飛び出してぶつかりあう妖精達。
全く同じ光景を見た俺とパーラは、ため息をこぼしながらテーブルの下に潜る。
また始まった喧嘩の止め時を伺いながら、見守る時間が再びやってきてしまった。
片付け途中の室内がまた荒らされていくのを見て、一周してもう達観を覚えてしまう。
こいつら、外でやってくんねーかなぁ。
背中に羽をもち、葉っぱと花びらで作られたタイト目なドレスのような服をまとった姿は、紛うことなく妖精そのものだ。
俺が知る妖精といえば、リッカだけだったが、新しくやってきた妖精は、リッカよりも女性的なフォルムを有しており、何となくだがリッカよりも年上のような印象を覚える。
一人称は僕であったが、性別は女性で間違いない。
やや褐色気味の肌にアッシュブロンドのショートカットの髪型が、某映画に出てくるハリウッド女優で似たようなのがいたなと思わせる。
今しがた口にした、友達を探してやってきたという言葉から察するに、この妖精はもしかしたらリッカを探しているのかもしれない。
現時点でこの辺りにいる妖精といえば、俺の知る限りではリッカと目の前の妖精だけのはずだ。
となれば、目当てはリッカだという答えに行き着くのは自然なことだろう。
しかも、この妖精は俺のところで世話になっているといった。
世話をしている妖精など、リッカ以外に心当たりはない。
「…あの、聞こえてますか?」
観察と考察に思考を割いていたせいで、呆けていたように思われたらしく、不安げな声で呼びかけられてしまった。
いかんいかん。
客を前にしてする態度ではなかったな。
「あ、あぁ、すまない。まさか妖精が尋ねてくるとは思わなくて、ちょっと驚いてしまった。俺のところで世話になっている妖精というのは、もしかしてリッカのことか?確かに彼女はここにいるよ」
「やっぱりここにいたんですね。よかったぁ…」
俺の言葉を聞き、ホッとした顔に変わった妖精に、どうやら彼女はそれなりの苦労をしてここまでやってきたのだろうと思わされた。
「ちょうど今、リッカと朝食をとっていたところだ。ま、こんなとこで立ち話もなんだし、とにかく中へどうぞ」
「あ、はい。じゃあ…お邪魔します」
中へ招き入れ、リッカたちのいるテーブルへと向かう。
と言っても、そう離れているわけではないので扉をくぐってしまえば、卓上に座り込んで食事をとっていたリッカの姿はすぐに見える。
「おー、アンディ。客は誰だった…って、シェスカじゃん。こんなとこまで何しに来たんだ?」
当然リッカからも俺達のほうは丸見えなので、戻ってきた俺の背後をついてくる妖精も目に入っており、知り合いと分かったからか、呆れたような顔で名前を呼んだ。
この妖精の名前はシェスカと言うらしく、リッカの反応から見て、そこそこの親しい間柄が窺えた。
「あんたねぇ…何しに来たじゃないわよ!すぐに戻るって言って出て行って、どんぐらい経ったと思ってるの!?」
リッカの言葉がきっかけとなったのか、それまでの礼儀正しさをかなぐり捨てる勢いで、シェスカは高速でリッカに詰め寄っていった。
さっき外で話したときは、キッチリとした態度だったのだが、今リッカに食って掛かる勢いの様子を見ると、妖精というのはもしかして気性の荒い種族なのだろうか。
初めてリッカと遭遇した時も思ったが、妖精はその可憐な見た目に反して性格に癖が強い気がする。
「どんぐらいって……あ」
何かを思い出したのか、シェスカの剣幕を怪訝そうに見ていたリッカの表情が、一瞬でバツの悪そうなものへと変わった。
「思い出したみたいね。そう、あんた四日ぐらい留守にするって出てったのよ?なのに!十日経っても帰ってこないもんだからって!僕が探しに行かされたの!」
それを聞いて俺がリッカを呼び出した日を思い出してみると、今日で軽く半月ほどは経っているはず。
空中で地団太を踏むという器用さを披露するシェスカは、リッカを探しに行かされたのがよっぽど不満だったようだ。
仲は悪くないと思ったが、この様子だと郷の方ではリッカに振り回されているのかもしれない。
「そういやそんぐらいって言ったっけ。いや、実はこいつらに付き合ってちょっと予定外の用事が出来ちまってさ。シェスカを寄こしたのは爺様連中か?その用事も済んだし、近く戻るって伝えといてくれ。じゃ、よろしく」
リッカの奴、わざわざ探しに来てくれた仲間に、その言い方はまずいだろ。
妖精の里の正確な位置はわからないが、リッカと合流したあの湖を基準にすれば、この場所はだいぶ離れている。
この小さい体でここまで旅してきたのだから、もう少し労わってやったほうがいい。
「は?何その言い方。僕はリッカのために三日かけてここまで飛んできたんだけど?」
そら見たことか。
案の定、シェスカはそれまでの興奮から一転して、能面のような感情の消えた顔に変わり、冷めた目をリッカへ向ける。
何かがカチンと来た爆発寸前の顔といった感じだ。
「分かってるよ。ご苦労さん、用事も済んだろ?帰っていいぞ」
「…このっ!リッカー!」
シェスカの表情の変化に気付いていないのか、変わらない態度のリッカに、ついにシェスカはキレてしまった。
フワリと空中に浮かび上がったシェスカが、声を張り上げながら鋭い動きでリッカへと組みつく。
悪質タックルが可愛いぐらいの、その弾丸のような勢いに、リッカはテーブルから弾き飛ばされ、シェスカもリッカに組み付いたまま、両者は一塊になって空中でクルクルと回りだす。
どちらも妖精の羽による飛行で姿勢を制御しようと試みているのか、複雑な動きで飛び回っている。
「いーってって!やめろって!なにキレてんだよ!シェスカ!」
「うるさい!僕の苦労も知らないで!」
困惑気味のリッカに、怒りに我を忘れているシェスカが殴ったり蹴ったりしている様子は、子供の喧嘩のようでもあるが、攻撃のたびに魔力を波動として周囲にまき散らしているせいで、室内の調度品が色々と影響を受けている。
「あわわわ…。アンディ、どうしよう」
「どうしようったって」
目まぐるしく動き回る二人に、手の出しようもない俺とパーラはただ見ているばかりで、せめて安全な場所にでもと、テーブルの下に揃って潜り込むしかできない。
そのテーブルから覗き見た感じでは、もうリッカ達は取っ組み合いの状態から脱し、今は空中でぶつかったり離れたりを繰り返す、空中格闘戦へと移行していた。
「なんなんだよお前!いっつもあたいの後追っかけてきやがって!」
「あんたがチョロチョロ動きまわるから、周りに迷惑かけないよう見てるんでしょうが!」
交差するたびに文句を言いあうという器用なドッグファイトは、部屋のあちこちに被害が出ていることを忘れれば、かなり見応えのあるショーだ。
錐もみ状態ですれ違い様に攻撃しあい、不規則な軌道を描きつつ離れてまたぶつかるという高度な空中戦に、俺達が噴射措置を使うときの手本として技術を盗めるかと期待もしたが、あまりにも高等テクニックまみれで参考にはなりそうにない。
「長老んとこの畑!草取りを僕に押し付けたのもリッカでしょ!」
「いつの話だよ!知るか!」
「ほんの十年前のことよ!いっつもそう!嫌なことは僕に押し付けてさ!年が近いからって面倒見させられるこっちの身にもなってよ!」
シェスカも不満は吐き出し終わったようだが、今度は今日まで貯めこんでいたものを口にしだした。
広がっていく被害の割りに、言い合いの内容はショボいものへと変わっていく。
「ちっ!それを言うかよ!…今年はハチミツ三回!奢ってやったぞ!」
「僕は十二回は奢らされた!」
「しっかり数えてんじゃっ…ねーよ!」
直上から迫るシェスカの蹴りを、リッカはその場でバク転をするようにして足で迎撃し、二人の足がぶつかりあった衝撃が波となって辺りに広がっていく。
「ひゃー、あの二人すっごいよ。妖精ってこういう戦いするんだね」
「ああ。一撃ごとに周りの空気が震えてやがる。手足へとんでもねぇ量の魔力を込めて、攻撃と防御を両立させてんだな」
二人の戦いを見ながら、俺とパーラは感想を言い合う。
もう部屋の中に被害が出ることはあきらめきっているので、今はただの観客に成り下がっていた。
あの小さい体で重機がぶつかったような衝撃波を生み出しているからくりに、さすが魔力の扱いに長けた妖精種だと感心してしまう。
俺達の使う身体強化とは次元の違うその魔力の運用法に、戦慄すら覚える。
普段のリッカの姿しか知らなかったために、正直、舐めていたのは否めない。
「あ、また壊した。ねぇアンディ、あの壺って何入ってたやつ?」
「なんだったっけ…あぁ、根菜の酢漬けか。そろそろ食べごろだったから出しておいたんだが、失敗したなぁ…ははっ」
もう何度目かになる食材の喪失を見ても、乾いた笑いしか出てこない。
好きにさせるしかないと二人をそのままにした俺が悪いのだが、そろそろここらで被害も打ち止めにならないものだろうか。
祈るしかできない俺はなんて無力なんだ。
「あちゃー。アンディ、このソファはだめだよ。背もたれが穴だらけだもん」
リッカとシェスカの戦いの後片付けをしていると、キッチンにいる俺にパーラがソファの惨状を教えてくれた。
室内はちょいとした嵐にあったような荒れ具合だし、ソファもダメージはあるだろうと思っていたが、穴を空けられたのは予想外だ。
あのソファはかなりしっかりとした作りだったし、ライフル弾でも防ぎきると思っていたのだが、妖精の一撃には耐えられなかったようだ。
「まじか。板でふさいで、布を詰めたら何とかならんか?」
「ならないねぇ。これは買い替えだわ」
雑巾をしぼりながら、また増えた出費にため息が漏れる。
ここまでに壊されたり喪失したものの被害を金銭的価値に換算すると、平民の一家が一年は遊んで暮らせる額に届く。
これはあくまでも貨幣換算での話で、金に換えられない価値のものも含めると損害はもっと大きい。
特に今日までこだわりにこだわって貯めこんだ香辛料や食材がダメになったのが痛く、駆け出しの商人がもし俺と同じ被害を受けたら、ショック死するか首を吊るかのレベルだ。
「はぁー…。二人とも、大分やらかしてくれたな」
頭を抱えながらキッチンを出て、散らかった部屋の中央で反省中の妖精二人に声をかける。
「んぎぎぎぎ…。わ、悪かったよ、アンディ。謝るよ。シェスカがやったことのっ、いくらかはあたいにも責任はあるしっな」
「ひぃ…ひぃ…。な、なにがいくらかよ。あんただって、派手に壊してたじゃないの。ひぃ…」
幾分落ち着いたとはいえ、お互いを非難しあうのをやめない辺り、まだまだ反省は足りないようだ。
さっき俺とパーラには素直に謝ったのに。
「まぁもっと早い内に止めに入らなかった俺も悪いが、やったことの償いはしてもらいたいね。特にダメになった食材には手に入りにくいのも多い。全部とは言わなくとも、多少は何らかの形で返してもらえるとありがたいんだが」
土地や季節別にと、いろんなところからかき集めていた食材だ。
中には次に手に入るのは来年以降というのもある。
同じものでなくてもいいので、可能であれば妖精のコネなんかでも使って、ある程度の補填はして欲しい。
「な、なぁアンディ。あたいらももう反省したからさ、これやめていいか?」
「そ、そうそう。リッカの言う通り、僕たち反省したよ?だからこの、わけわかんないぐるぐる回るのやめさせてくれると嬉しいなー…なんて」
縋るような目つきでリッカ達が懇願するのは、いま彼女達に科している刑罰の終了についてだ。
示し合わせたように揃って目を潤ませてこちらを伺う姿で、改めてリッカ達の様子をじっくりと観察する。
あれだけの騒動を起こした罰として、リッカ達には反省のためにと横倒しにしたバイクの前輪を二人に手押しで回させていた。
世紀末な漫画でも有名な、人力で回させて発電させるようなあれだ。
確かピストリヌゥムという名前の装置だったか。
常にブレーキを軽くかけた状態の車輪を回す作業は、超小柄な二人にはかなりの重労働となっている。
壊れたままだったバイクに少し手を加え、何本かスポークを抜いた車輪の内側にリッカ達が入り、残ったスポークを掴んで回すというその絵は、改めてよく見ると滑稽さの中に残酷さが漂っていた。
なお、この車輪を回しても、小麦粉が作られたり電力が生み出されてもいないので、まったく意味のない作業を強いているだけだったりする。
所謂空役というやつだ。
そのことも、二人を参らせている一因ではあるようだ。
「ん?んー…どうすっかなぁ」
「もうやめさせてもいいんじゃない?どこともつながってない装置って、完全に無意味なやつじゃん、それ」
悩む仕草をリッカ達に見せつけていると、自分の担当を片付け終えたパーラが呆れがでやってきてそんなことを言う。
お仕置きということは分かっているだろうが、もう三十分は休みなくやらされている二人に、パーラもそれなりに同情しているらしい。
「無意味ってことはないだろ。反省させるって意味は込められているぞ」
「いや、私は何も生み出していないってところを言ってんだけど」
空役とはそういうもんだ。
しかし、そろそろいいだろうというパーラの意見に同意する気持ちがないわけではない。
ここに来るまでのことなどをシェスカからも色々と聞きたい。
「…いいだろう。二人とも、それはもう終わりだ」
『ぶはぁ~…』
いいという俺の言葉を聞き、大きく息を吐きだしながらその場に頽れるリッカ達。
荒い呼吸と全身をうっすらと覆う汗は、ともすれば働いた者の勲章にも見えるが、まったく生産性のない作業だったということを考えれば、無駄な仕事だったとも言える。
「えー、もう知ってるとは思うけど、改めて名乗らせてもらうわね。僕の名前はシェスカ、見ての通りの妖精よ。南方霊樹の森の妖精で、そっちのリッカとは同郷。郷じゃリッカの面倒を見てたから、姉みたいなものね」
「なーにが姉だよ。あたいと二十ぐらいしか違わねぇくせに」
「二十年だろうが三十年だろうが、早く生まれて面倒を見てたんだから僕が姉でしょうが」
改めて、テーブルに着いた俺たちはシェスカと互いに名乗りあった。
それを聞いてぶっきらぼうな口調のリッカだが、なんだか照れているように見えるのは気のせいではあるまい。
口ではああ言っても、シェスカを姉と思っている気持ちはあるようで、身内が友達に挨拶をしている時に見せるような顔をしている。
そのシェスカだが、ここに来た目的は既に聞いていた通り、予定日を過ぎても郷に戻ってこないリッカを探しに来たとのこと。
本来なら一人でぶらりとどこかにいっても探しに来るほどリッカは子供でもないし、シェスカも過保護でもないのだが、今回は帰ってくる日を事前に言い残していたため、予定日から大幅に遅れていたのを郷の老人達が心配してシェスカを派遣したわけだ。
ここでシェスカが選ばれたのは、リッカの姉を自負するだけあって普段から一緒にいることが多いせいだとのこと。
自身も郷でやることはあったが、長老経由で命じられては断ることもできず、リッカが残した魔力の跡を追いかけ、今日の未明にようやくこの山へ辿り着いたという。
「魔力の跡ねぇ。妖精ってそういうので追跡できるんだ?」
くたびれた顔で語るシェスカの話に出てきた魔力の跡という言葉に、パーラはテーブルに身を乗り出すようにして興味を示した。
追跡術の心得のあるパーラにしてみれば、未知の追跡手段にはやはり好奇心を抱くらしい。
「妖精っつーか、シェスカの能力だな。あたいの知る限り、シェスカほど魔力の探知が上手いやつは他にいねぇ」
「まぁ自慢ってほどじゃないけど、僕って生まれつき魔力の波動を拾いやすい体質なの。特に、僕らの鱗粉って虚空に溶けてもしばらく残留するから、同じ妖精なら追跡は難しくないわ。…まぁ、今回はなんでかすごい高いところに残留物が漂ってたから、辿るのも大変だったけど」
「あぁ、そりゃあたいが飛空艇で移動したからだな」
「飛空艇?何それ」
シェスカは飛空艇を知らないらしく、リッカの言葉に首をかしげる。
仕草も相まって、こうしてみると可憐な少女のように見えるが、その背後に見える部屋の惨状のせいで、逆に怖さを覚える。
「お前が今いるここ。これが、空を飛ぶんだよ。あたいら妖精よりずっと早く、しかもえらい高いところをな」
「…嘘でしょ?いつの間にか人間が空を飛べるようになったってこと?っていうか、ここって家じゃないの?」
困惑と疑いの混ざった目が俺とパーラに向けられる。
ソーマルガが大々的に発表したおかげで、今の世の中では飛空艇はトレンドなのだが、郷に籠っている妖精族の間では、まだまだメジャーのメの字にすらなれていないらしい。
「人間がというより、そういう乗り物を遺跡で見つけて乗ってるんだ」
「そうそう。私らは飛空艇を家にしてるってだけ」
「ふーん。世間は僕が知るのとは大分違ってきてるってことか。こんなのが空を飛ぶとはねぇ」
俺とパーラの言葉を受け、シェスカは好奇心が刺激されたのか、すぐそばの壁をペタペタとさわり出した。
空を飛ぶということにかけて、妖精の自分にも思うところがあるのか、その様子からは飛空艇にそこそこの興味を抱いているように見える。
「そういえば、パーラさんって言ったっけ?」
飛空艇にはそれ以上興味を持たなかったのか、シェスカがパーラへと声をかけた。
「あ、うん」
「あなたのそれ、どうしたの?見たところ幽星体の延長よね。なんか変な呪いでももらった?」
何やら神妙とも不思議そうともとれる顔のシェスカが見ているのは、パーラというよりその頭にある耳の方へだ。
パッと見た感じでは狼系統の獣人のパーラだが、シェスカは元のパーラを知らないはずなのに、幽星体がはみ出ている状態というのを見事に言い当てた。
俺には見分けは付かないが、妖精には分かりやすいということなのだろう。
呪いとはまた物騒な言葉を口にするものだ。
というか、この世界にも呪いは存在するのか。
魔術が存在する以上、あってもおかしくはないが、今までお目にかかってこなかったので新鮮だ。
「たっはっはっは!呪いってのはいいねぇ。ある意味じゃそうかもな。けど、生憎とこいつのは加護のせいだ」
何が面白いのか、大笑いをしながらリッカがパーラのことを説明しだす。
この場にいる中で加護を授かった経緯を知らないのはシェスカだけなので、転真体との遭遇まで遡って話されていく。
「転真体!?ちょっと、それってほんとなの?」
「嘘じゃねぇよ。あたいはこの目で確かに見たし、歌での対話も見届けた。まぁ、実際にやったのはパーラだけど」
リッカもそうだったが、シェスカも転真体というのには過敏な反応を示す。
妖精にとって、転真体というのがいかに特別な存在かというのが伝わってくる。
「リッカを探しに来て転真体の情報が聞けるなんて、苦労の見返りには十分ね……あれ?もしかして加護って、その転真体の?」
「お、鋭いなシェスカ。その通り、パーラがこうなった原因の加護は、そいつが寄こしやがったんだよ。この姿もそのせいってわけさ」
「ほぉー……え、加護ってこうなるんだっけ?」
「さあ?あたいも加護持ちをそれほど知らねーし。そういうこともあるんじゃね?」
「いやないでしょ。少なくとも僕は聞いたことないよ」
適当なリッカと違い、シェスカは加護についてもそこそこ知識はあるようで、その反応でパーラのこの状態が加護としては普通じゃないことがよくわかった。
「けどパーラの話だと、別段体に悪いことが起きてるってわけじゃないし、特に何かするこたぁないだろ。どうせほっときゃ元の姿に戻るよな?」
「うーん、それはそうかもしれないけど……三割ってとこかな?」
「え、三割って何が?」
渋い顔でつぶやいたシェスカの言葉へ、敏感に反応したのはパーラだ。
「何がって…言いにくいんだけど、獣人の姿で固定される可能性、かな?十日もしたら、どっちに固定されるか結果はわかると思うよ」
「……はい!?ちょっと待ってよ!もしかしたら私、この姿のままになるってこと!?なんで!」
「なんでってあぶばばばばばばっ」
慌てたパーラがテーブルの上にいたシェスカを一瞬にしてつかみ取り、目線の高さでぶんぶんと揺らすという危ない問い詰め方を見せた。
「落ち着けパーラ!それだとシェスカが喋れないだろ」
パーラの腕を抑えて動きを止め、その手からシェスカを解放させると、激しい揺れのせいでか、テーブルの上に降り立った足で座り込んでしまった。
「ご、ごめん、シェスカ」
「……ふぅ、いいよ、気にしないで。急にあんなこと言われたら驚くよね。誰だってそうする。僕だってそうする」
パーラを気遣うようなことを言うが、ボケっとした顔のシェスカが見ている方向にいるのは俺だ。
どうやらまだ焦点は合っていないらしい。
ちょうどいいので、パーラに言ったことの真意を俺が尋ねるとしよう。
「で、どういうことだ?パーラはこのままになるって?」
「いや、絶対そうだってわけじゃないのよ?このまま幽星体の変化が肉体になじんだ時、大体三割の確率でこの狼っぽい特徴が残るかもしれないってだけの話ね」
詳しく聞いてみると、幽星体の変化が肉体に出ている現状がそもそも特殊なため、人間としての姿と獣人の姿のバランスがリアルタイムで変化しているのがシェスカには感じ取れているらしい。
リッカには分からなかったが、魔力の探知能力が高いシェスカだからこその見立てなのだろう。
「三割ね…。七割は人間に戻る可能性が高いと受け取れるが」
「何言ってんのアンディ!三割とか七割とかじゃないって!私にしたら、戻れるか戻れないかの二択なの!」
「む、一理あるな」
一瞬、七割の方に希望を託してみたくなったが、切羽詰まったようなパーラの声に、要はセーフかアウトかの差だと気が付かされた。
「ねぇシェスカ。何とかならない?私、元の体がいいよ」
「何とかって言われても。その体でも別に不便はないんでしょ?ならその状態で残りの人生を歩むってのも悪くは…」
「そういう問題じゃないの!」
諭すシェスカの言葉に、歯をむいて声を張り上げるパーラの迫力が凄い。
狼化の影響によって、怒鳴った顔にはさすがの怖さがある。
「だ、だよねぇ。…あ、じゃあさ、幽星体の中にある、狼化の要因を封印するとかは?ちょっと高度な手だけど、やれないことはないよ」
ほう、封印とな。
そういう手もあるか。
魔術師として暮らして長いが、封印術の存在自体は耳にすれど、今の世で使い手の話は全く耳にしない。
ほとんど幻の技だといっても過言ではないだろう。
「封印か…それってシェスカがやれるの?」
「ううん、僕もリッカも封印術は使えないよ?郷にも使えるって人はいないしね」
「え…じゃあなんで封印の話をしたの?」
「やれる人にやってもらえばいいのよ。封印術って言ったら…今は誰がいるのかしら?」
言うだけ言って心当たりがないとは、シェスカも随分無責任なことを言うものだ。
まぁ世俗には疎い妖精にしてみれば、人間の中で誰が封印術を使えるかなど知っているわけもないが。
「あのさ、あたいも誰が封印術の使い手かってのは分かんねーけど、探しようはあるぞ」
「リッカが?なんだ、お前の知り合いか?」
「あたいのっていうか、お前らも知り合いだな」
意外だな。
俺達とリッカの共通の知り合いで、封印術の当てがあるとは。
いったい誰だ?
「ふっふっふっふ、その顔だと誰のことか見当もついていないな?」
「リッカお願い!勿体ぶらないで教えてよ!」
不敵な笑みで俺達の周りを飛び回るというウザさを見せつけるリッカに、パーラが悲痛な声で先を促す。
自分のことだけに、のんびりと答えを待っていられないようだ。
「…まぁいいや。パーラの気持ちを考えて、サクっと答え合わせしとくか。いいか?封印術ってのは結局魔術の一種だ」
「そりゃあな。むしろ魔術じゃなかったらなんだって話だ」
何をいまさらと、思わず呆れた口調で答えてしまった俺を、パーラがにらんでくる。
リッカの話を遮るなという意思がこもった、射殺すような視線に肩をすくめてしまう。
「アンディの言う通り。つまり、封印術師は魔術師が集まる場所で探せばいいんだよ。術師本人が見つかればそれでいいし、いなければいないでそういうとこなら情報も集めやすい。でだ、この辺りで魔術師が一番集まるっていえばどーこだ?」
順を追った丁寧な説明付きのなぞなぞの答えは、すぐに辿り着けた。
『あ!ディケット!』
「正~解っ!」
異口同音の俺とパーラに、笑顔を浮かべたリッカから花丸の正解を頂いた。
なるほど、リッカの案は実に理にかなったものだ。
世界中から人と教材が集まるディケットなら、封印術の使い手についても知っている人間や情報があってもおかしくはない。
最良なら、生徒や教師に封印術の使い手がいる可能性も無きにしも非ず。
「行ってみる価値はあるな」
「だね」
パーラと顔を見合わせ、ディケット行きが決まる。
「よーし!そうと決まったら早速行こう!あたいも久々にスーリア達に会いたいしな!」
リッカもディケットに行くのが楽しみのようで、踊るようにして室内を飛び回りだした。
友達との再会を思って喜ぶその姿は、天真爛漫そのものといった様子で微笑ましい。
「あいつらどうしてっかなぁ。スーリアの奴、またなんか美味いもん食わして―」
「喜んでるとこ悪いけど、リッカ。あんたはディケットには行けないよ。僕と一緒に郷に帰るんだからね」
水を差すとはこのことかという手本通り、シェスカの呆れた声が室内に響くと、リッカがピシリと動きを止めた。
器用にも、空中で飛んでいる最中の姿勢での停止だ。
「なん…だと」
辛うじてそれだけを口にし、錆びた機械人形のような動きでシェスカを見るリッカの目は、心なしか暗い色に染まっている。
「だってここでの用事は済んだんでしょ?だったら帰るのが当たり前じゃない。僕はあんたを連れ戻すために来たんだからね」
至極まっとうなことを言うシェスカに、リッカは逆らう根拠を持たない。
何せついさっき、用事が済んだから近い内に帰るというのを喧嘩の前に口にしていたのだから。
「…やだ」
「は?何が?」
俯いたリッカがボソリと呟き、それにシェスカが鋭い目で答えた。
その時のシェスカの目と冷たい言いように、俺は嫌な予感を禁じ得ない。
それはパーラも同様らしく、座っている椅子から少し腰を浮かせている。
いつでも動けるようにとのことだろう。
「やだやだやだやだ!あたいはディケットに行く!そんで友達と会って、美味い酒を奢りあうんだ!」
それは死亡フラグだぞ?
「だめよ!あんたは僕と一緒に帰るの!友達と会うのは、一回郷に帰ってからにしなさい!また出直せばいいじゃない!」
「郷に戻ったら、どうせ爺様連中に説教されて、当分郷から出るのを禁止されるにきまってる!」
「分かってるじゃない!そうよ!あんたはそれだけ心配かけたの!」
「うるせー!郷にはもうちょっとしたら戻るから、ここはあたいに任せて、シェスカだけ戻れって!」
徐々に言い合う声が大きくなり始めたリッカとシェスカの姿に、ついさっきも見た喧嘩の直前の熱の高まりを感じている。
これは、来るか?
「っこの!聞き分けなさい!リッカ!」
「だが断る!このリッカ!従えというやつに否というのが一番好きなのさ!」
「リッカー!」
「シェスカー!」
互いの名前を呼びあい、空中に飛び出してぶつかりあう妖精達。
全く同じ光景を見た俺とパーラは、ため息をこぼしながらテーブルの下に潜る。
また始まった喧嘩の止め時を伺いながら、見守る時間が再びやってきてしまった。
片付け途中の室内がまた荒らされていくのを見て、一周してもう達観を覚えてしまう。
こいつら、外でやってくんねーかなぁ。
応援ありがとうございます!
1
お気に入りに追加
1,730
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる