5 / 8
5
しおりを挟む
「何だか顔色が悪いよ?」
「あの、」
「このあと一緒に夕飯でも食べようかと思ってたんだけど、やめとく?」
「ええと……」
心配そうな顔をしている慎兄さんが僕の足の側にしゃがみ込んだ。そうしてソファに座ったままの僕の頬を指でするりと撫でる。まさかそんなことをされるなんて思っていなかった僕は、驚きすぎて手を避けるように体を引いてしまった。
すると心配そうな表情をしていた慎兄さんの顔が、すぐさま困惑したような顔に変わる。
「あの、僕、」
「もしかして、俺に触れられるの嫌だった?」
「あ……」
すぐにでも「そんなことありません!」と言いたかった。それなのに「僕の気持ちを知られるわけにはいかない」と思ったせいで言葉が詰まってしまう。一度詰まると何も出てこなくなって、ますますどうしていいかわからなくなった。
「そっか。それならメッセージなんて送ってくれるはずはないか」
今度は寂しそうな顔になった。「そうじゃない」と言いたいのに、やっぱり言葉が出てこない。
メッセージを送れなかったのは何て送ればいいかわからなかったからだ。ああでもない、こうでもないと考えすぎて、気がついたら何日も経ってしまっていた。
一週間が過ぎた頃、「髪を切ってくれてありがとうございます」でよかったんだと気がついた。それなら変じゃないしお礼を言うこともできる。だけど一週間も経ってからお礼を言うのは変だと思って、結局何も送ることができないままになってしまった。
「それじゃ今日も無理して付き合わせちゃったってことか。気がつかなくてごめんね」
かっこいい顔が寂しそうに笑っている。
(……そんな顔しないで)
かっこいい慎兄さんに、そんな悲しそうな顔は似合わない。そんな顔を僕がさせているんだと思ったら、それだけで自分が嫌いになりそうだった。
「家まで送ってあげるよ。車取ってくるからちょっと待ってて」
「違うんです!」
パーカーを手渡してくれた慎兄さんの左手を慌てて掴んだ。やっぱりちゃんと言わないとまた後悔する。片思いがばれてしまうかもしれないけど、それよりも慎兄さんを傷つけたままじゃ駄目だという気持ちのほうが勝った。
「違うんです! メッセージは、何て送ったらいいかわからなかっただけなんです。毎日何て送ろうか考えたけど難しくて、そしたら一週間経ってて、余計に何を送っていいかわからなくなっただけで!」
「三春くん?」と少し驚いた慎兄さんに、それでも僕は言葉を続けた。
「それに! 慎兄さんに触られたくないとか、そんなこと絶対にないです! 今日だって切ってもらってすごく嬉しかったし、この前はシャンプーとかマッサージとかまでしてもらって、すごくすっごく! 嬉しかったです!」
だからそんな悲しそうな顔をしないでほしい。そう思いながら必死に口を動かした。
僕の様子に驚いたような顔をしていた慎兄さんは「そっか」と言ってニコッと微笑んでくれた。それにホッとしつつ、とんでもないことを言ってしまったと今更ながら後悔する。恥ずかしいやら怖いやら、頭も心も一気にぐちゃっと潰れたようになった。慌てて掴んでいた手を離そうとしたものの、逆に引き留めるように握られてしまった。
「よかった。もしかして嫌われたんじゃないかと思って不安だったんだ」
「き、嫌うなんて、そんなこと絶対にないですっ」
「あはは、そっか。それならよかった」
よかったなんて、それこそ僕のセリフだ。僕が慎兄さんを嫌っているなんて誤解されたままだったら、きっと今夜から違った意味で僕は眠れなくなっていただろう。
「じつはちょっとだけ期待してたんだ」
僕の右手を掴んだまま慎兄さんがそんなことを言い出した。
「三春くんに好きだって言われたのは幼稚園生のときだったし、もう十年以上も前だ。それでもやっぱり期待してた。そんな昔の言葉にすがるなんて自分でもどうかしてると思うけどね」
「あの……?」
「それもこれも何も教えようとしない二海のせいなんだけど」
「二海兄さんが、どうかしたんですか?」
僕の質問に「何でもないよ」と微笑んだ慎兄さんに顔がカッと熱くなる。思わず視線を逸らせると「もう一度聞くけど」と声がした。
「三春くん、恋人はいないんだよね?」
チラッと顔を見てからこくりと頷く。
「もしかして好きな人はいる?」
まるで「俺以外に好きな人はいる?」と言っているように聞こえて慌てて「そんな人、いません!」と答えた。僕は昔からずっと慎兄さんが好きだ。その気持ちは嘘じゃないと言いたくて、つい言葉を続けてしまった。
「僕はずっと慎兄さんが好きだったし、いまだって慎兄さんしか好きじゃないです! ……って、あの、」
自分が余計なことを言ったことに気がついた。しかもずっと好きだったなんて、絶対に気持ち悪がられる。急いで言い繕わなければとわかっているのに、頭がグルグルして言い訳すら思い浮かばない。
「そっか。あのときもだけど、やっぱりそう言ってもらえるのは嬉しい」
「……え?」
いま「嬉しい」って聞こえた気がする。聞き間違いかと思って慎兄さんを見つめた。
「もしかしてそうかなと期待はしてたんだけど、それでも三春くんの口から聞きたかった。それでちょっと意地悪したというか……ははっ、そっか、俺しか好きじゃないのか」
「それは……っ」
「あれ? もしかして気を遣って言ってくれただけ?」
「違います! 僕は慎兄さんしかずっと好きじゃないです! って、ええと、これはその、」
どうしよう。話せば話すほど余計なことを言ってしまう。どうしていいのかわからなくなって俯いた僕に、慎兄さんが「やっぱりかわいいなぁ」なんて言いながら笑う。
「こんなにかわいいから、てっきりもう誰かのお手つきになったかと思っていたんだけど……いや、二海たちが目を光らせてるから、そんなことはあり得ないか」
「え……?」
「何でもないよ」
顔を上げた僕に慎兄さんがニコッと微笑みかけた。それを正面から見てしまった僕が「ひえぇ」と目を瞑ると、するっと頬を撫でられる。
(な、なに? え? どういうこと?)
驚いて目を開くと慎兄さんがじっと僕を見ていた。あまりの目力に俯くことも目を瞑ることもできない。まるで見つめ合っているような状況に段々と顔が熱くなる。思わず変な声が出そうになり、慌てて唇をキュッと噛んだ。すると「やっぱり三春くんはかわいい」と言って、頬をスリスリ撫でていた慎兄さんの手が右の頬を包み込むように動きを止める。
「すごくかわいい」
とんでもなくいい声でそんなことを言うから耳まで熱くなってきた。いま口を開いたら変な声が出そうな気がしてますます唇を強く噛み締める。
そんな僕に「かわいい」と笑った慎兄さんの手が少しだけ動いた。手のひらを頬に当てたまま親指で鼻の頭を撫でられる。その指がゆっくり動いて、今度は噛み締めている唇を撫で始めた。触られた瞬間、首のあたりがぞわっとしてびっくりする。
「あの、慎、兄さん、」
「どうしたんですか」と聞きたかったのに、また唇を撫でられて言葉が続かない。しゃべりかけた唇は少しだけ開いていて、そんな下唇を慎兄さんの親指が撫でた。そのとき爪の先が前歯にコツンと当たって、今度は首だけじゃなく背中までぞわっとする。
「俺に触られるのは嫌じゃない?」
「いや、じゃ、ない、です」
答えている間も親指が唇を撫でるから、うまくしゃべることができない。それでもちゃんと返事をしたくて必死に唇を動かした。
「じゃあ、触られるのは好き?」
「ええ、と、」
一瞬、何て答えればいいのか迷った。触られるのは嫌じゃない。髪を切ってもらったときも、こうして触られるのも嫌だなんて思わない。それどころかもっと触ってほしいとさえ思っている。
(でも、そんなこと言ったらきっと気持ち悪がられる)
だからといって嘘は言いたくなかった。何て返事をすればいいかわからなくて、口をほんの少し開けたまま視線をウロウロさせる。
「ね、好き?」
「好き」という言葉に顔がカァァァと熱くなった。触られるのが好きかと聞かれているだけなのに、まるで慎兄さん自身を好きか尋ねられている気がして体中がそわそわする。
僕は緊張で唇が震えるのを感じながら「す」と唇を突き出した。そうしたらまた親指で唇を撫でられて首筋がゾクゾクする。それでも僕は口を閉じなかった。最後までちゃんと言葉にしたくて「き」と唇を横に広げる。すると爪の先がまたコツンと歯に当たって目が回りそうになった。
「じゃあ、俺のことは好き?」
「え……?」
一瞬、何を言われたのかわからなかった。慌てて視線を向けると微笑んでいる慎兄さんと目が合う。その瞬間、体の中を電気みたいなものが走り抜けたような気がした。
慎兄さんの顔はいつもどおりかっこいい。でも、それだけじゃない気がする。うまく言えないけど、いつもよりグッと色気が増しているように見えた。初めて見る慎兄さんの雰囲気に戸惑いながらも「こういう顔も好きだな」と胸がきゅんとなる。
(そうだ、僕はずっと慎兄さんが好きなんだ)
でも、素直にそう答えていいのかわからない。幼稚園生のときからずっと好きだったなんて気持ち悪がられたりしないだろうか。
(それに僕はこんな田舎者だし、全然大人になってないし)
そんな僕に好きだと言われたら迷惑じゃないだろうか。そう思いながらも慎兄さんが好きだという気持ちがどんどん膨れ上がっていく。
「ね、好き?」
もう一度尋ねられた瞬間、好きだという気持ちがパン! と弾けた気がした。体中から好きという気持ちが勢いよく飛び出す。その中でも一番強い気持ちがお腹の奥から喉を駆け上がった。
「す、好きですっ」
気がついたらそう答えていた。言った途端に心臓がドクンドクンとうるさくなる。これ以上恥ずかしい顔を見られたくなくて俯いた僕の耳に「俺も好きだよ」という慎兄さんの声が聞こえた気がした。
(ぇ……?)
さすがにいまのは聞き間違いに違いない。頭がグルグルしているから都合がいい空耳が聞こえたんだ。
それでもほんの少し期待して視線を上げた。するとキラキラした笑顔の慎兄さんが僕を見ていた。その顔を見ただけで、ますます心臓がドクンドクンとうるさくなる。
(か、かっこよすぎて気絶しそう)
もしかしたら、すでに気絶しているのかもしれない。だから都合がいい空耳が聞こえたのかもしれない。
「夕飯だけど、俺の部屋で食べようか」
そう言った慎兄さんが、手を当てているのとは反対側の頬にチュッとキスをした。一瞬何をされたのかわからなかった僕は、キスだと気づいた途端に茹でダコのように全身が真っ赤になるのがわかった。
「あの、」
「このあと一緒に夕飯でも食べようかと思ってたんだけど、やめとく?」
「ええと……」
心配そうな顔をしている慎兄さんが僕の足の側にしゃがみ込んだ。そうしてソファに座ったままの僕の頬を指でするりと撫でる。まさかそんなことをされるなんて思っていなかった僕は、驚きすぎて手を避けるように体を引いてしまった。
すると心配そうな表情をしていた慎兄さんの顔が、すぐさま困惑したような顔に変わる。
「あの、僕、」
「もしかして、俺に触れられるの嫌だった?」
「あ……」
すぐにでも「そんなことありません!」と言いたかった。それなのに「僕の気持ちを知られるわけにはいかない」と思ったせいで言葉が詰まってしまう。一度詰まると何も出てこなくなって、ますますどうしていいかわからなくなった。
「そっか。それならメッセージなんて送ってくれるはずはないか」
今度は寂しそうな顔になった。「そうじゃない」と言いたいのに、やっぱり言葉が出てこない。
メッセージを送れなかったのは何て送ればいいかわからなかったからだ。ああでもない、こうでもないと考えすぎて、気がついたら何日も経ってしまっていた。
一週間が過ぎた頃、「髪を切ってくれてありがとうございます」でよかったんだと気がついた。それなら変じゃないしお礼を言うこともできる。だけど一週間も経ってからお礼を言うのは変だと思って、結局何も送ることができないままになってしまった。
「それじゃ今日も無理して付き合わせちゃったってことか。気がつかなくてごめんね」
かっこいい顔が寂しそうに笑っている。
(……そんな顔しないで)
かっこいい慎兄さんに、そんな悲しそうな顔は似合わない。そんな顔を僕がさせているんだと思ったら、それだけで自分が嫌いになりそうだった。
「家まで送ってあげるよ。車取ってくるからちょっと待ってて」
「違うんです!」
パーカーを手渡してくれた慎兄さんの左手を慌てて掴んだ。やっぱりちゃんと言わないとまた後悔する。片思いがばれてしまうかもしれないけど、それよりも慎兄さんを傷つけたままじゃ駄目だという気持ちのほうが勝った。
「違うんです! メッセージは、何て送ったらいいかわからなかっただけなんです。毎日何て送ろうか考えたけど難しくて、そしたら一週間経ってて、余計に何を送っていいかわからなくなっただけで!」
「三春くん?」と少し驚いた慎兄さんに、それでも僕は言葉を続けた。
「それに! 慎兄さんに触られたくないとか、そんなこと絶対にないです! 今日だって切ってもらってすごく嬉しかったし、この前はシャンプーとかマッサージとかまでしてもらって、すごくすっごく! 嬉しかったです!」
だからそんな悲しそうな顔をしないでほしい。そう思いながら必死に口を動かした。
僕の様子に驚いたような顔をしていた慎兄さんは「そっか」と言ってニコッと微笑んでくれた。それにホッとしつつ、とんでもないことを言ってしまったと今更ながら後悔する。恥ずかしいやら怖いやら、頭も心も一気にぐちゃっと潰れたようになった。慌てて掴んでいた手を離そうとしたものの、逆に引き留めるように握られてしまった。
「よかった。もしかして嫌われたんじゃないかと思って不安だったんだ」
「き、嫌うなんて、そんなこと絶対にないですっ」
「あはは、そっか。それならよかった」
よかったなんて、それこそ僕のセリフだ。僕が慎兄さんを嫌っているなんて誤解されたままだったら、きっと今夜から違った意味で僕は眠れなくなっていただろう。
「じつはちょっとだけ期待してたんだ」
僕の右手を掴んだまま慎兄さんがそんなことを言い出した。
「三春くんに好きだって言われたのは幼稚園生のときだったし、もう十年以上も前だ。それでもやっぱり期待してた。そんな昔の言葉にすがるなんて自分でもどうかしてると思うけどね」
「あの……?」
「それもこれも何も教えようとしない二海のせいなんだけど」
「二海兄さんが、どうかしたんですか?」
僕の質問に「何でもないよ」と微笑んだ慎兄さんに顔がカッと熱くなる。思わず視線を逸らせると「もう一度聞くけど」と声がした。
「三春くん、恋人はいないんだよね?」
チラッと顔を見てからこくりと頷く。
「もしかして好きな人はいる?」
まるで「俺以外に好きな人はいる?」と言っているように聞こえて慌てて「そんな人、いません!」と答えた。僕は昔からずっと慎兄さんが好きだ。その気持ちは嘘じゃないと言いたくて、つい言葉を続けてしまった。
「僕はずっと慎兄さんが好きだったし、いまだって慎兄さんしか好きじゃないです! ……って、あの、」
自分が余計なことを言ったことに気がついた。しかもずっと好きだったなんて、絶対に気持ち悪がられる。急いで言い繕わなければとわかっているのに、頭がグルグルして言い訳すら思い浮かばない。
「そっか。あのときもだけど、やっぱりそう言ってもらえるのは嬉しい」
「……え?」
いま「嬉しい」って聞こえた気がする。聞き間違いかと思って慎兄さんを見つめた。
「もしかしてそうかなと期待はしてたんだけど、それでも三春くんの口から聞きたかった。それでちょっと意地悪したというか……ははっ、そっか、俺しか好きじゃないのか」
「それは……っ」
「あれ? もしかして気を遣って言ってくれただけ?」
「違います! 僕は慎兄さんしかずっと好きじゃないです! って、ええと、これはその、」
どうしよう。話せば話すほど余計なことを言ってしまう。どうしていいのかわからなくなって俯いた僕に、慎兄さんが「やっぱりかわいいなぁ」なんて言いながら笑う。
「こんなにかわいいから、てっきりもう誰かのお手つきになったかと思っていたんだけど……いや、二海たちが目を光らせてるから、そんなことはあり得ないか」
「え……?」
「何でもないよ」
顔を上げた僕に慎兄さんがニコッと微笑みかけた。それを正面から見てしまった僕が「ひえぇ」と目を瞑ると、するっと頬を撫でられる。
(な、なに? え? どういうこと?)
驚いて目を開くと慎兄さんがじっと僕を見ていた。あまりの目力に俯くことも目を瞑ることもできない。まるで見つめ合っているような状況に段々と顔が熱くなる。思わず変な声が出そうになり、慌てて唇をキュッと噛んだ。すると「やっぱり三春くんはかわいい」と言って、頬をスリスリ撫でていた慎兄さんの手が右の頬を包み込むように動きを止める。
「すごくかわいい」
とんでもなくいい声でそんなことを言うから耳まで熱くなってきた。いま口を開いたら変な声が出そうな気がしてますます唇を強く噛み締める。
そんな僕に「かわいい」と笑った慎兄さんの手が少しだけ動いた。手のひらを頬に当てたまま親指で鼻の頭を撫でられる。その指がゆっくり動いて、今度は噛み締めている唇を撫で始めた。触られた瞬間、首のあたりがぞわっとしてびっくりする。
「あの、慎、兄さん、」
「どうしたんですか」と聞きたかったのに、また唇を撫でられて言葉が続かない。しゃべりかけた唇は少しだけ開いていて、そんな下唇を慎兄さんの親指が撫でた。そのとき爪の先が前歯にコツンと当たって、今度は首だけじゃなく背中までぞわっとする。
「俺に触られるのは嫌じゃない?」
「いや、じゃ、ない、です」
答えている間も親指が唇を撫でるから、うまくしゃべることができない。それでもちゃんと返事をしたくて必死に唇を動かした。
「じゃあ、触られるのは好き?」
「ええ、と、」
一瞬、何て答えればいいのか迷った。触られるのは嫌じゃない。髪を切ってもらったときも、こうして触られるのも嫌だなんて思わない。それどころかもっと触ってほしいとさえ思っている。
(でも、そんなこと言ったらきっと気持ち悪がられる)
だからといって嘘は言いたくなかった。何て返事をすればいいかわからなくて、口をほんの少し開けたまま視線をウロウロさせる。
「ね、好き?」
「好き」という言葉に顔がカァァァと熱くなった。触られるのが好きかと聞かれているだけなのに、まるで慎兄さん自身を好きか尋ねられている気がして体中がそわそわする。
僕は緊張で唇が震えるのを感じながら「す」と唇を突き出した。そうしたらまた親指で唇を撫でられて首筋がゾクゾクする。それでも僕は口を閉じなかった。最後までちゃんと言葉にしたくて「き」と唇を横に広げる。すると爪の先がまたコツンと歯に当たって目が回りそうになった。
「じゃあ、俺のことは好き?」
「え……?」
一瞬、何を言われたのかわからなかった。慌てて視線を向けると微笑んでいる慎兄さんと目が合う。その瞬間、体の中を電気みたいなものが走り抜けたような気がした。
慎兄さんの顔はいつもどおりかっこいい。でも、それだけじゃない気がする。うまく言えないけど、いつもよりグッと色気が増しているように見えた。初めて見る慎兄さんの雰囲気に戸惑いながらも「こういう顔も好きだな」と胸がきゅんとなる。
(そうだ、僕はずっと慎兄さんが好きなんだ)
でも、素直にそう答えていいのかわからない。幼稚園生のときからずっと好きだったなんて気持ち悪がられたりしないだろうか。
(それに僕はこんな田舎者だし、全然大人になってないし)
そんな僕に好きだと言われたら迷惑じゃないだろうか。そう思いながらも慎兄さんが好きだという気持ちがどんどん膨れ上がっていく。
「ね、好き?」
もう一度尋ねられた瞬間、好きだという気持ちがパン! と弾けた気がした。体中から好きという気持ちが勢いよく飛び出す。その中でも一番強い気持ちがお腹の奥から喉を駆け上がった。
「す、好きですっ」
気がついたらそう答えていた。言った途端に心臓がドクンドクンとうるさくなる。これ以上恥ずかしい顔を見られたくなくて俯いた僕の耳に「俺も好きだよ」という慎兄さんの声が聞こえた気がした。
(ぇ……?)
さすがにいまのは聞き間違いに違いない。頭がグルグルしているから都合がいい空耳が聞こえたんだ。
それでもほんの少し期待して視線を上げた。するとキラキラした笑顔の慎兄さんが僕を見ていた。その顔を見ただけで、ますます心臓がドクンドクンとうるさくなる。
(か、かっこよすぎて気絶しそう)
もしかしたら、すでに気絶しているのかもしれない。だから都合がいい空耳が聞こえたのかもしれない。
「夕飯だけど、俺の部屋で食べようか」
そう言った慎兄さんが、手を当てているのとは反対側の頬にチュッとキスをした。一瞬何をされたのかわからなかった僕は、キスだと気づいた途端に茹でダコのように全身が真っ赤になるのがわかった。
273
お気に入りに追加
278
あなたにおすすめの小説

青少年病棟
暖
BL
性に関する診察・治療を行う病院。
小学生から高校生まで、性に関する悩みを抱えた様々な青少年に対して、外来での診察・治療及び、入院での治療を行なっています。
※性的描写あり。
※患者・医師ともに全員男性です。
※主人公の患者は中学一年生設定。
※結末未定。できるだけリクエスト等には対応してい期待と考えているため、ぜひコメントお願いします。

それ以上近づかないでください。
ぽぽ
BL
「誰がお前のことなんか好きになると思うの?」
地味で冴えない小鳥遊凪は、ある日、憧れの人である蓮見馨に不意に告白をしてしまい、2人は付き合うことになった。
まるで夢のような時間――しかし、その恋はある出来事をきっかけに儚くも終わりを迎える。
転校を機に、馨のことを全てを忘れようと決意した凪。もう二度と彼と会うことはないはずだった。
ところが、あることがきっかけで馨と再会することになる。
「本当に可愛い。」
「凪、俺以外のやつと話していいんだっけ?」
かつてとはまるで別人のような馨の様子に戸惑う凪。
「お願いだから、僕にもう近づかないで」
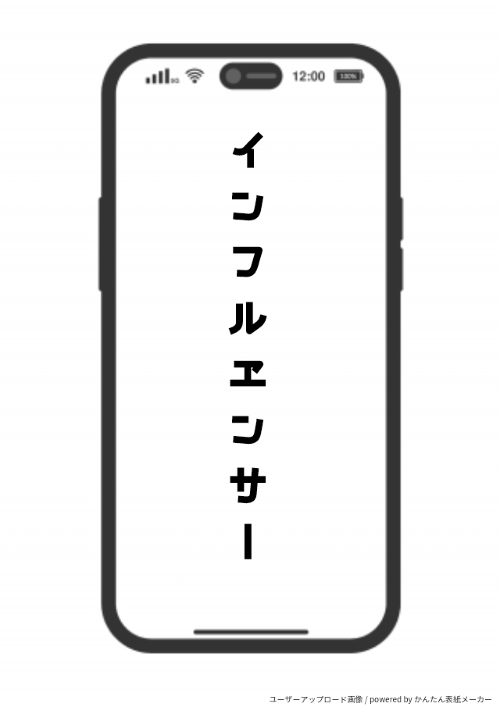
インフルエンサー
うた
BL
イケメン同級生の大衡は、なぜか俺にだけ異様なほど塩対応をする。修学旅行でも大衡と同じ班になってしまって憂鬱な俺だったが、大衡の正体がSNSフォロワー5万人超えの憧れのインフルエンサーだと気づいてしまい……。
※pixivにも投稿しています

【完結】I adore you
ひつじのめい
BL
幼馴染みの蒼はルックスはモテる要素しかないのに、性格まで良くて羨ましく思いながらも夏樹は蒼の事を1番の友達だと思っていた。
そんな時、夏樹に彼女が出来た事が引き金となり2人の関係に変化が訪れる。
※小説家になろうさんでも公開しているものを修正しています。

【旧作】美貌の冒険者は、憧れの騎士の側にいたい
市川パナ
BL
優美な憧れの騎士のようになりたい。けれどいつも魔法が暴走してしまう。
魔法を制御する銀のペンダントを着けてもらったけれど、それでもコントロールできない。
そんな日々の中、勇者と名乗る少年が現れて――。
不器用な美貌の冒険者と、麗しい騎士から始まるお話。
旧タイトル「銀色ペンダントを離さない」です。
第3話から急展開していきます。

死に戻り騎士は、今こそ駆け落ち王子を護ります!
時雨
BL
「駆け落ちの供をしてほしい」
すべては真面目な王子エリアスの、この一言から始まった。
王子に”国を捨てても一緒になりたい人がいる”と打ち明けられた、護衛騎士ランベルト。
発表されたばかりの公爵家令嬢との婚約はなんだったのか!?混乱する騎士の気持ちなど関係ない。
国境へ向かう二人を追う影……騎士ランベルトは追手の剣に倒れた。
後悔と共に途切れた騎士の意識は、死亡した時から三年も前の騎士団の寮で目覚める。
――二人に追手を放った犯人は、一体誰だったのか?
容疑者が浮かんでは消える。そもそも犯人が三年先まで何もしてこない保証はない。
怪しいのは、王位を争う第一王子?裏切られた公爵令嬢?…正体不明の駆け落ち相手?
今度こそ王子エリアスを護るため、過去の記憶よりも積極的に王子に関わるランベルト。
急に距離を縮める騎士を、はじめは警戒するエリアス。ランベルトの昔と変わらぬ態度に、徐々にその警戒も解けていって…?
過去にない行動で変わっていく事象。動き出す影。
ランベルトは今度こそエリアスを護りきれるのか!?
負けず嫌いで頑固で堅実、第二王子(年下) × 面倒見の良い、気の長い一途騎士(年上)のお話です。
-------------------------------------------------------------------
主人公は頑な、王子も頑固なので、ゆるい気持ちで見守っていただけると幸いです。

王子様から逃げられない!
白兪
BL
目を覚ますとBLゲームの主人公になっていた恭弥。この世界が受け入れられず、何とかして元の世界に戻りたいと考えるようになる。ゲームをクリアすれば元の世界に戻れるのでは…?そう思い立つが、思わぬ障壁が立ち塞がる。

イケメンチート王子に転生した俺に待ち受けていたのは予想もしない試練でした
和泉臨音
BL
文武両道、容姿端麗な大国の第二皇子に転生したヴェルダードには黒髪黒目の婚約者エルレがいる。黒髪黒目は魔王になりやすいためこの世界では要注意人物として国家で保護する存在だが、元日本人のヴェルダードからすれば黒色など気にならない。努力家で真面目なエルレを幼い頃から純粋に愛しているのだが、最近ではなぜか二人の関係に壁を感じるようになった。
そんなある日、エルレの弟レイリーからエルレの不貞を告げられる。不安を感じたヴェルダードがエルレの屋敷に赴くと、屋敷から火の手があがっており……。
* 金髪青目イケメンチート転生者皇子 × 黒髪黒目平凡の魔力チート伯爵
* 一部流血シーンがあるので苦手な方はご注意ください
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















