6 / 91
第六話 郭の中
しおりを挟む
ヨシは、邸の夕餉の支度があるからと出かけていった。
夕餉には早すぎる気がするが、材料の調達や下拵えもあるのだろう。
三郎は、蓑と笠をつけ、ミコを連れて畑に出ていった。
確かに武士とは名ばかりの暮らしぶりのようだ。
兄者が、という話も出ていたから家族は、ほかにもいるのだろう。
一緒に住んでいる様子がないところを見ると家を出たのだろうが。
静かにはなったものの、どうにも落ち着かなかった。
人の家に、あがりこんだことなど一度もない。
正しく言えば、あげてくれるものなどいなかったのだ。
とはいえ、しばらくは、ここで世話になるしかあるまい。
体を動かすと筋や節々が悲鳴を上げる。頭も疼く。
自分の家までたどり着くどころか、この街を出ることさえできそうになかった。
しかし、二日間もこのような場所で寝込んでいたのかと思うと、ぞっとする。
よくぞ、寝首をかかれなかったものだ。それどころか怪我の治療と看病まで行うとは。
なぜだ、と問うたところで正直には答えまい。
わかっているのは、目的もなくこのようなことをする人間はいないということだ。
あえて探る必要はないだろう。
いずれ向こうから切り出してくるはずだ。
体を横にすると、わずかに痛みが軽くなった。
熱を帯びた体がだるい。
屋根の板をたたく雨音が眠気を誘う。
気を抜いてはならない、状況を把握しなければならないと思いながらも、うつらうつらと眠りにおちた。
目を覚ましたのは半刻も過ぎた頃だろうか。
かゆはすっかり冷めていた。
椀を手に取り、痛む体に鞭打って家を出る。
雨あがりの澄んだ空気が頬をなでた。
鳥のさえずりに目をやると、雨に洗われた、つややかな椿の葉が目に入った。
蕾もふくらみ始めている。
霞が、陽を浴びた吹晴山を登っていくのが見えた。
左右に長屋と塀が続いていた。薪小屋や納屋らしいものもある。
運よく人の姿はない。
確かに、阿岐権守の使用人たちが住んでいる郭のようだ。
ただし、イダテンが寝ていた長屋の左右に人が住んでいる様子はない。
長屋後方の空堀土手の斜面で雀たちが何かをついばんでいた。
軒下に立てかけてあった板を見つけ道に置く。
その上に、椀の縁にこびりついていた米粒をのせ、痛めた左足を引きずるようにして進む。
頭が疼き、脇腹に痛みが走る。息をするのもつらい。
懐には端布でくるんだ包丁を忍ばせている。
手斧が見当たらなかったのだ。
鬼の子に武器を持たせると危険だと判断したのだろう。
長屋後方の空堀には水汲み場があった。
足元が崩れぬよう大きな岩を敷きつめ、大雨で泥が流れ込まぬよう井桁を備えている。
竹を組んだふたを開けると、澄んだ水が湧いていた。
水が染み出る場所を、さらに掘り進めたのだろう。湧き水は足元より四尺ほど下にある。
釣瓶を下ろし、麻縄をたぐりながら水を汲み上げる。
たった、それだけのことで、腕も脇腹も悲鳴をあげた。
三郎や、それより幼い童がこれを繰り返すのはさぞかし辛かろう。
桶の水に映る自分の顔を見る。
頬には腫れが残り、あちこちが変色していた。
水を口に含むと傷に凍みた。
喉も腫れているのだろう。飲み込もうとしてむせた。
その音に驚いたかのように先ほど置いた板の上から雀が飛び立っていった。
戻ってみると米粒はきれいになくなっていた。
どうやら毒は入っていないようだ。
椀を傾け、冷めたかゆを口に含む。
むせないよう、ゆっくりと咀嚼する――驚いた。
米とはこのように甘くうまいものなのか。
だが、「うまい」と思ったことに、後ろめたさを感じた――おばばは、一度でも、白い米の飯を口にしたことがあっただろうか。
*
枝が板葺の屋根を叩いている。
土手に生えていた木が風に揺られているのだろう。
夜ごとに寒さがつのる。
暗闇の中、板の間の筵の上で、痛みと、熱からくる不調に耐えながら、あたえられた夜着、二重をかけて寝る。
イダテンはこれまで通り、一番奥に寝かされていた。
部屋の造りからすると、イダテンが来るまでは三郎たちが、ここで寝ていたのだろう。
ミコが、すうすうと寝息をたてている。
隣の三郎は、寝返りをうつと歯ぎしりをはじめた。
ヨシは、時折目を覚まし、二人の夜着を掛け直してやっている。
ヨシも三郎も、そして幼いミコでさえ、イダテンを恐れるでもなく迎え入れているように見える。
だが、鬼の子を助けてなんになろう。
ヨシが仕えている国司の阿岐権守と、この地の実質上の支配者である郡司の宗我部国親がうまくいっていないことはイダテンでさえ知っている。
たまにしか街に出ず、他人と話をするのが苦手な、おばばの耳に入ってくるほどに有名な話なのだ。
イダテン自身も聞いたことがある。
むろん話してくれる者はいない。
山菜を取りに来た者が近くにいるイダテンに気づかず話題にしていたのだ。
ならば、イダテンを手なずけて宗我部兄弟の首を獲ろうと考えているのか。
*
ミコが、おぼつかない手つきで箸と椀を握りしめ、粟と稗の飯をかきこんでいた。
イダテンは手をつけていない。
毒見を済ませていないからだ。
さっさと朝餉を終わらせた三郎は独楽の紐かけの工夫に余念がない。
母親のヨシが出がけに三郎に声をかけた。
「イダテンの相手もするんだよ」
「鬼なんかと遊べるかよ……あっっ、いてっ! 何すんだよー!」
振り返りもせず返事をした三郎が悲鳴を上げた。
ヨシが三郎の耳を引っ張っていた。
「夕餉を抜くよ」
「どうせまた、粟や稗だろ」
涙を浮かべながらも三郎は憎まれ口をたたいた。
「何て言い草だい。それさえ食べられない者がいるというのに」
ヨシは、妙に抑揚をつけて続けた。
「そうかい、そうかい。姫様に、なんていえばいいかねえ。今日だって聞かれるかもしれないよ。三郎はイダテンと仲良くやっていますかって」
その言葉に、三郎は、ばつが悪そうな表情をうかべた。
「足の腫れはまだ引いてないからね。遊びに連れて出るのは、もう少し先でいいんだよ」
三郎はヨシの言葉に、しぶしぶうなずいた。
ヨシが出かけると、三郎はことさら大きな声で話しかけてきた。
「おお、ということだ。イダテン。わしも柴刈りと畑のあと独楽の勝負があるでな。飯はそこにある。食ったら椀に甕の水を入れておけ。ミコ、おまえもだ。すんだらついて来い」
「兄上、待って」
急いで残りの飯をかきこんだ、その頬には稗の粒がついている。
そのミコが三郎を追う前に、イダテンのかたわらに籠の形に折った紙を置いていった。
歌が書き込まれた反古紙をていねいに折ってある。
誰かに貰ったのだろう。紙を使って習い事ができるような内所には見えない。
*
ヨシは、邸の夕餉の支度があるからと出かけていった。
夕餉には早すぎる気がするが、材料の調達や下拵えもあるのだろう。
三郎は、蓑と笠をつけ、ミコを連れて畑に出ていった。
確かに武士とは名ばかりの暮らしぶりのようだ。
兄者が、という話も出ていたから家族は、ほかにもいるのだろう。
一緒に住んでいる様子がないところを見ると家を出たのだろうが。
静かにはなったものの、どうにも落ち着かなかった。
人の家に、あがりこんだことなど一度もない。
正しく言えば、あげてくれるものなどいなかったのだ。
とはいえ、しばらくは、ここで世話になるしかあるまい。
体を動かすと筋や節々が悲鳴を上げる。頭も疼く。
自分の家までたどり着くどころか、この街を出ることさえできそうになかった。
しかし、二日間もこのような場所で寝込んでいたのかと思うと、ぞっとする。
よくぞ、寝首をかかれなかったものだ。それどころか怪我の治療と看病まで行うとは。
なぜだ、と問うたところで正直には答えまい。
わかっているのは、目的もなくこのようなことをする人間はいないということだ。
あえて探る必要はないだろう。
いずれ向こうから切り出してくるはずだ。
体を横にすると、わずかに痛みが軽くなった。
熱を帯びた体がだるい。
屋根の板をたたく雨音が眠気を誘う。
気を抜いてはならない、状況を把握しなければならないと思いながらも、うつらうつらと眠りにおちた。
目を覚ましたのは半刻も過ぎた頃だろうか。
かゆはすっかり冷めていた。
椀を手に取り、痛む体に鞭打って家を出る。
雨あがりの澄んだ空気が頬をなでた。
鳥のさえずりに目をやると、雨に洗われた、つややかな椿の葉が目に入った。
蕾もふくらみ始めている。
霞が、陽を浴びた吹晴山を登っていくのが見えた。
左右に長屋と塀が続いていた。薪小屋や納屋らしいものもある。
運よく人の姿はない。
確かに、阿岐権守の使用人たちが住んでいる郭のようだ。
ただし、イダテンが寝ていた長屋の左右に人が住んでいる様子はない。
長屋後方の空堀土手の斜面で雀たちが何かをついばんでいた。
軒下に立てかけてあった板を見つけ道に置く。
その上に、椀の縁にこびりついていた米粒をのせ、痛めた左足を引きずるようにして進む。
頭が疼き、脇腹に痛みが走る。息をするのもつらい。
懐には端布でくるんだ包丁を忍ばせている。
手斧が見当たらなかったのだ。
鬼の子に武器を持たせると危険だと判断したのだろう。
長屋後方の空堀には水汲み場があった。
足元が崩れぬよう大きな岩を敷きつめ、大雨で泥が流れ込まぬよう井桁を備えている。
竹を組んだふたを開けると、澄んだ水が湧いていた。
水が染み出る場所を、さらに掘り進めたのだろう。湧き水は足元より四尺ほど下にある。
釣瓶を下ろし、麻縄をたぐりながら水を汲み上げる。
たった、それだけのことで、腕も脇腹も悲鳴をあげた。
三郎や、それより幼い童がこれを繰り返すのはさぞかし辛かろう。
桶の水に映る自分の顔を見る。
頬には腫れが残り、あちこちが変色していた。
水を口に含むと傷に凍みた。
喉も腫れているのだろう。飲み込もうとしてむせた。
その音に驚いたかのように先ほど置いた板の上から雀が飛び立っていった。
戻ってみると米粒はきれいになくなっていた。
どうやら毒は入っていないようだ。
椀を傾け、冷めたかゆを口に含む。
むせないよう、ゆっくりと咀嚼する――驚いた。
米とはこのように甘くうまいものなのか。
だが、「うまい」と思ったことに、後ろめたさを感じた――おばばは、一度でも、白い米の飯を口にしたことがあっただろうか。
*
枝が板葺の屋根を叩いている。
土手に生えていた木が風に揺られているのだろう。
夜ごとに寒さがつのる。
暗闇の中、板の間の筵の上で、痛みと、熱からくる不調に耐えながら、あたえられた夜着、二重をかけて寝る。
イダテンはこれまで通り、一番奥に寝かされていた。
部屋の造りからすると、イダテンが来るまでは三郎たちが、ここで寝ていたのだろう。
ミコが、すうすうと寝息をたてている。
隣の三郎は、寝返りをうつと歯ぎしりをはじめた。
ヨシは、時折目を覚まし、二人の夜着を掛け直してやっている。
ヨシも三郎も、そして幼いミコでさえ、イダテンを恐れるでもなく迎え入れているように見える。
だが、鬼の子を助けてなんになろう。
ヨシが仕えている国司の阿岐権守と、この地の実質上の支配者である郡司の宗我部国親がうまくいっていないことはイダテンでさえ知っている。
たまにしか街に出ず、他人と話をするのが苦手な、おばばの耳に入ってくるほどに有名な話なのだ。
イダテン自身も聞いたことがある。
むろん話してくれる者はいない。
山菜を取りに来た者が近くにいるイダテンに気づかず話題にしていたのだ。
ならば、イダテンを手なずけて宗我部兄弟の首を獲ろうと考えているのか。
*
ミコが、おぼつかない手つきで箸と椀を握りしめ、粟と稗の飯をかきこんでいた。
イダテンは手をつけていない。
毒見を済ませていないからだ。
さっさと朝餉を終わらせた三郎は独楽の紐かけの工夫に余念がない。
母親のヨシが出がけに三郎に声をかけた。
「イダテンの相手もするんだよ」
「鬼なんかと遊べるかよ……あっっ、いてっ! 何すんだよー!」
振り返りもせず返事をした三郎が悲鳴を上げた。
ヨシが三郎の耳を引っ張っていた。
「夕餉を抜くよ」
「どうせまた、粟や稗だろ」
涙を浮かべながらも三郎は憎まれ口をたたいた。
「何て言い草だい。それさえ食べられない者がいるというのに」
ヨシは、妙に抑揚をつけて続けた。
「そうかい、そうかい。姫様に、なんていえばいいかねえ。今日だって聞かれるかもしれないよ。三郎はイダテンと仲良くやっていますかって」
その言葉に、三郎は、ばつが悪そうな表情をうかべた。
「足の腫れはまだ引いてないからね。遊びに連れて出るのは、もう少し先でいいんだよ」
三郎はヨシの言葉に、しぶしぶうなずいた。
ヨシが出かけると、三郎はことさら大きな声で話しかけてきた。
「おお、ということだ。イダテン。わしも柴刈りと畑のあと独楽の勝負があるでな。飯はそこにある。食ったら椀に甕の水を入れておけ。ミコ、おまえもだ。すんだらついて来い」
「兄上、待って」
急いで残りの飯をかきこんだ、その頬には稗の粒がついている。
そのミコが三郎を追う前に、イダテンのかたわらに籠の形に折った紙を置いていった。
歌が書き込まれた反古紙をていねいに折ってある。
誰かに貰ったのだろう。紙を使って習い事ができるような内所には見えない。
*
夕餉には早すぎる気がするが、材料の調達や下拵えもあるのだろう。
三郎は、蓑と笠をつけ、ミコを連れて畑に出ていった。
確かに武士とは名ばかりの暮らしぶりのようだ。
兄者が、という話も出ていたから家族は、ほかにもいるのだろう。
一緒に住んでいる様子がないところを見ると家を出たのだろうが。
静かにはなったものの、どうにも落ち着かなかった。
人の家に、あがりこんだことなど一度もない。
正しく言えば、あげてくれるものなどいなかったのだ。
とはいえ、しばらくは、ここで世話になるしかあるまい。
体を動かすと筋や節々が悲鳴を上げる。頭も疼く。
自分の家までたどり着くどころか、この街を出ることさえできそうになかった。
しかし、二日間もこのような場所で寝込んでいたのかと思うと、ぞっとする。
よくぞ、寝首をかかれなかったものだ。それどころか怪我の治療と看病まで行うとは。
なぜだ、と問うたところで正直には答えまい。
わかっているのは、目的もなくこのようなことをする人間はいないということだ。
あえて探る必要はないだろう。
いずれ向こうから切り出してくるはずだ。
体を横にすると、わずかに痛みが軽くなった。
熱を帯びた体がだるい。
屋根の板をたたく雨音が眠気を誘う。
気を抜いてはならない、状況を把握しなければならないと思いながらも、うつらうつらと眠りにおちた。
目を覚ましたのは半刻も過ぎた頃だろうか。
かゆはすっかり冷めていた。
椀を手に取り、痛む体に鞭打って家を出る。
雨あがりの澄んだ空気が頬をなでた。
鳥のさえずりに目をやると、雨に洗われた、つややかな椿の葉が目に入った。
蕾もふくらみ始めている。
霞が、陽を浴びた吹晴山を登っていくのが見えた。
左右に長屋と塀が続いていた。薪小屋や納屋らしいものもある。
運よく人の姿はない。
確かに、阿岐権守の使用人たちが住んでいる郭のようだ。
ただし、イダテンが寝ていた長屋の左右に人が住んでいる様子はない。
長屋後方の空堀土手の斜面で雀たちが何かをついばんでいた。
軒下に立てかけてあった板を見つけ道に置く。
その上に、椀の縁にこびりついていた米粒をのせ、痛めた左足を引きずるようにして進む。
頭が疼き、脇腹に痛みが走る。息をするのもつらい。
懐には端布でくるんだ包丁を忍ばせている。
手斧が見当たらなかったのだ。
鬼の子に武器を持たせると危険だと判断したのだろう。
長屋後方の空堀には水汲み場があった。
足元が崩れぬよう大きな岩を敷きつめ、大雨で泥が流れ込まぬよう井桁を備えている。
竹を組んだふたを開けると、澄んだ水が湧いていた。
水が染み出る場所を、さらに掘り進めたのだろう。湧き水は足元より四尺ほど下にある。
釣瓶を下ろし、麻縄をたぐりながら水を汲み上げる。
たった、それだけのことで、腕も脇腹も悲鳴をあげた。
三郎や、それより幼い童がこれを繰り返すのはさぞかし辛かろう。
桶の水に映る自分の顔を見る。
頬には腫れが残り、あちこちが変色していた。
水を口に含むと傷に凍みた。
喉も腫れているのだろう。飲み込もうとしてむせた。
その音に驚いたかのように先ほど置いた板の上から雀が飛び立っていった。
戻ってみると米粒はきれいになくなっていた。
どうやら毒は入っていないようだ。
椀を傾け、冷めたかゆを口に含む。
むせないよう、ゆっくりと咀嚼する――驚いた。
米とはこのように甘くうまいものなのか。
だが、「うまい」と思ったことに、後ろめたさを感じた――おばばは、一度でも、白い米の飯を口にしたことがあっただろうか。
*
枝が板葺の屋根を叩いている。
土手に生えていた木が風に揺られているのだろう。
夜ごとに寒さがつのる。
暗闇の中、板の間の筵の上で、痛みと、熱からくる不調に耐えながら、あたえられた夜着、二重をかけて寝る。
イダテンはこれまで通り、一番奥に寝かされていた。
部屋の造りからすると、イダテンが来るまでは三郎たちが、ここで寝ていたのだろう。
ミコが、すうすうと寝息をたてている。
隣の三郎は、寝返りをうつと歯ぎしりをはじめた。
ヨシは、時折目を覚まし、二人の夜着を掛け直してやっている。
ヨシも三郎も、そして幼いミコでさえ、イダテンを恐れるでもなく迎え入れているように見える。
だが、鬼の子を助けてなんになろう。
ヨシが仕えている国司の阿岐権守と、この地の実質上の支配者である郡司の宗我部国親がうまくいっていないことはイダテンでさえ知っている。
たまにしか街に出ず、他人と話をするのが苦手な、おばばの耳に入ってくるほどに有名な話なのだ。
イダテン自身も聞いたことがある。
むろん話してくれる者はいない。
山菜を取りに来た者が近くにいるイダテンに気づかず話題にしていたのだ。
ならば、イダテンを手なずけて宗我部兄弟の首を獲ろうと考えているのか。
*
ミコが、おぼつかない手つきで箸と椀を握りしめ、粟と稗の飯をかきこんでいた。
イダテンは手をつけていない。
毒見を済ませていないからだ。
さっさと朝餉を終わらせた三郎は独楽の紐かけの工夫に余念がない。
母親のヨシが出がけに三郎に声をかけた。
「イダテンの相手もするんだよ」
「鬼なんかと遊べるかよ……あっっ、いてっ! 何すんだよー!」
振り返りもせず返事をした三郎が悲鳴を上げた。
ヨシが三郎の耳を引っ張っていた。
「夕餉を抜くよ」
「どうせまた、粟や稗だろ」
涙を浮かべながらも三郎は憎まれ口をたたいた。
「何て言い草だい。それさえ食べられない者がいるというのに」
ヨシは、妙に抑揚をつけて続けた。
「そうかい、そうかい。姫様に、なんていえばいいかねえ。今日だって聞かれるかもしれないよ。三郎はイダテンと仲良くやっていますかって」
その言葉に、三郎は、ばつが悪そうな表情をうかべた。
「足の腫れはまだ引いてないからね。遊びに連れて出るのは、もう少し先でいいんだよ」
三郎はヨシの言葉に、しぶしぶうなずいた。
ヨシが出かけると、三郎はことさら大きな声で話しかけてきた。
「おお、ということだ。イダテン。わしも柴刈りと畑のあと独楽の勝負があるでな。飯はそこにある。食ったら椀に甕の水を入れておけ。ミコ、おまえもだ。すんだらついて来い」
「兄上、待って」
急いで残りの飯をかきこんだ、その頬には稗の粒がついている。
そのミコが三郎を追う前に、イダテンのかたわらに籠の形に折った紙を置いていった。
歌が書き込まれた反古紙をていねいに折ってある。
誰かに貰ったのだろう。紙を使って習い事ができるような内所には見えない。
*
ヨシは、邸の夕餉の支度があるからと出かけていった。
夕餉には早すぎる気がするが、材料の調達や下拵えもあるのだろう。
三郎は、蓑と笠をつけ、ミコを連れて畑に出ていった。
確かに武士とは名ばかりの暮らしぶりのようだ。
兄者が、という話も出ていたから家族は、ほかにもいるのだろう。
一緒に住んでいる様子がないところを見ると家を出たのだろうが。
静かにはなったものの、どうにも落ち着かなかった。
人の家に、あがりこんだことなど一度もない。
正しく言えば、あげてくれるものなどいなかったのだ。
とはいえ、しばらくは、ここで世話になるしかあるまい。
体を動かすと筋や節々が悲鳴を上げる。頭も疼く。
自分の家までたどり着くどころか、この街を出ることさえできそうになかった。
しかし、二日間もこのような場所で寝込んでいたのかと思うと、ぞっとする。
よくぞ、寝首をかかれなかったものだ。それどころか怪我の治療と看病まで行うとは。
なぜだ、と問うたところで正直には答えまい。
わかっているのは、目的もなくこのようなことをする人間はいないということだ。
あえて探る必要はないだろう。
いずれ向こうから切り出してくるはずだ。
体を横にすると、わずかに痛みが軽くなった。
熱を帯びた体がだるい。
屋根の板をたたく雨音が眠気を誘う。
気を抜いてはならない、状況を把握しなければならないと思いながらも、うつらうつらと眠りにおちた。
目を覚ましたのは半刻も過ぎた頃だろうか。
かゆはすっかり冷めていた。
椀を手に取り、痛む体に鞭打って家を出る。
雨あがりの澄んだ空気が頬をなでた。
鳥のさえずりに目をやると、雨に洗われた、つややかな椿の葉が目に入った。
蕾もふくらみ始めている。
霞が、陽を浴びた吹晴山を登っていくのが見えた。
左右に長屋と塀が続いていた。薪小屋や納屋らしいものもある。
運よく人の姿はない。
確かに、阿岐権守の使用人たちが住んでいる郭のようだ。
ただし、イダテンが寝ていた長屋の左右に人が住んでいる様子はない。
長屋後方の空堀土手の斜面で雀たちが何かをついばんでいた。
軒下に立てかけてあった板を見つけ道に置く。
その上に、椀の縁にこびりついていた米粒をのせ、痛めた左足を引きずるようにして進む。
頭が疼き、脇腹に痛みが走る。息をするのもつらい。
懐には端布でくるんだ包丁を忍ばせている。
手斧が見当たらなかったのだ。
鬼の子に武器を持たせると危険だと判断したのだろう。
長屋後方の空堀には水汲み場があった。
足元が崩れぬよう大きな岩を敷きつめ、大雨で泥が流れ込まぬよう井桁を備えている。
竹を組んだふたを開けると、澄んだ水が湧いていた。
水が染み出る場所を、さらに掘り進めたのだろう。湧き水は足元より四尺ほど下にある。
釣瓶を下ろし、麻縄をたぐりながら水を汲み上げる。
たった、それだけのことで、腕も脇腹も悲鳴をあげた。
三郎や、それより幼い童がこれを繰り返すのはさぞかし辛かろう。
桶の水に映る自分の顔を見る。
頬には腫れが残り、あちこちが変色していた。
水を口に含むと傷に凍みた。
喉も腫れているのだろう。飲み込もうとしてむせた。
その音に驚いたかのように先ほど置いた板の上から雀が飛び立っていった。
戻ってみると米粒はきれいになくなっていた。
どうやら毒は入っていないようだ。
椀を傾け、冷めたかゆを口に含む。
むせないよう、ゆっくりと咀嚼する――驚いた。
米とはこのように甘くうまいものなのか。
だが、「うまい」と思ったことに、後ろめたさを感じた――おばばは、一度でも、白い米の飯を口にしたことがあっただろうか。
*
枝が板葺の屋根を叩いている。
土手に生えていた木が風に揺られているのだろう。
夜ごとに寒さがつのる。
暗闇の中、板の間の筵の上で、痛みと、熱からくる不調に耐えながら、あたえられた夜着、二重をかけて寝る。
イダテンはこれまで通り、一番奥に寝かされていた。
部屋の造りからすると、イダテンが来るまでは三郎たちが、ここで寝ていたのだろう。
ミコが、すうすうと寝息をたてている。
隣の三郎は、寝返りをうつと歯ぎしりをはじめた。
ヨシは、時折目を覚まし、二人の夜着を掛け直してやっている。
ヨシも三郎も、そして幼いミコでさえ、イダテンを恐れるでもなく迎え入れているように見える。
だが、鬼の子を助けてなんになろう。
ヨシが仕えている国司の阿岐権守と、この地の実質上の支配者である郡司の宗我部国親がうまくいっていないことはイダテンでさえ知っている。
たまにしか街に出ず、他人と話をするのが苦手な、おばばの耳に入ってくるほどに有名な話なのだ。
イダテン自身も聞いたことがある。
むろん話してくれる者はいない。
山菜を取りに来た者が近くにいるイダテンに気づかず話題にしていたのだ。
ならば、イダテンを手なずけて宗我部兄弟の首を獲ろうと考えているのか。
*
ミコが、おぼつかない手つきで箸と椀を握りしめ、粟と稗の飯をかきこんでいた。
イダテンは手をつけていない。
毒見を済ませていないからだ。
さっさと朝餉を終わらせた三郎は独楽の紐かけの工夫に余念がない。
母親のヨシが出がけに三郎に声をかけた。
「イダテンの相手もするんだよ」
「鬼なんかと遊べるかよ……あっっ、いてっ! 何すんだよー!」
振り返りもせず返事をした三郎が悲鳴を上げた。
ヨシが三郎の耳を引っ張っていた。
「夕餉を抜くよ」
「どうせまた、粟や稗だろ」
涙を浮かべながらも三郎は憎まれ口をたたいた。
「何て言い草だい。それさえ食べられない者がいるというのに」
ヨシは、妙に抑揚をつけて続けた。
「そうかい、そうかい。姫様に、なんていえばいいかねえ。今日だって聞かれるかもしれないよ。三郎はイダテンと仲良くやっていますかって」
その言葉に、三郎は、ばつが悪そうな表情をうかべた。
「足の腫れはまだ引いてないからね。遊びに連れて出るのは、もう少し先でいいんだよ」
三郎はヨシの言葉に、しぶしぶうなずいた。
ヨシが出かけると、三郎はことさら大きな声で話しかけてきた。
「おお、ということだ。イダテン。わしも柴刈りと畑のあと独楽の勝負があるでな。飯はそこにある。食ったら椀に甕の水を入れておけ。ミコ、おまえもだ。すんだらついて来い」
「兄上、待って」
急いで残りの飯をかきこんだ、その頬には稗の粒がついている。
そのミコが三郎を追う前に、イダテンのかたわらに籠の形に折った紙を置いていった。
歌が書き込まれた反古紙をていねいに折ってある。
誰かに貰ったのだろう。紙を使って習い事ができるような内所には見えない。
*
4
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

葉桜よ、もう一度 【完結】
五月雨輝
歴史・時代
【第9回歴史・時代小説大賞特別賞受賞作】北の小藩の青年藩士、黒須新九郎は、女中のりよに密かに心を惹かれながら、真面目に職務をこなす日々を送っていた。だが、ある日突然、新九郎は藩の産物を横領して抜け売りしたとの無実の嫌疑をかけられ、切腹寸前にまで追い込まれてしまう。新九郎は自らの嫌疑を晴らすべく奔走するが、それは藩を大きく揺るがす巨大な陰謀と哀しい恋の始まりであった。
謀略と裏切り、友情と恋情が交錯し、武士の道と人の想いの狭間で新九郎は疾走する。

【完結】女神は推考する
仲 奈華 (nakanaka)
歴史・時代
父や夫、兄弟を相次いで失った太后は途方にくれた。
直系の男子が相次いて死亡し、残っているのは幼い皇子か血筋が遠いものしかいない。
強欲な叔父から持ち掛けられたのは、女である私が即位するというものだった。
まだ幼い息子を想い決心する。子孫の為、夫の為、家の為私の役目を果たさなければならない。
今までは子供を産む事が役割だった。だけど、これからは亡き夫に変わり、残された私が守る必要がある。
これは、大王となる私の守る為の物語。
額田部姫(ヌカタベヒメ)
主人公。母が蘇我一族。皇女。
穴穂部皇子(アナホベノミコ)
主人公の従弟。
他田皇子(オサダノオオジ)
皇太子。主人公より16歳年上。後の大王。
広姫(ヒロヒメ)
他田皇子の正妻。他田皇子との間に3人の子供がいる。
彦人皇子(ヒコヒトノミコ)
他田大王と広姫の嫡子。
大兄皇子(オオエノミコ)
主人公の同母兄。
厩戸皇子(ウマヤドノミコ)
大兄皇子の嫡子。主人公の甥。
※飛鳥時代、推古天皇が主人公の小説です。
※歴史的に年齢が分かっていない人物については、推定年齢を記載しています。※異母兄弟についての明記をさけ、母方の親類表記にしています。
※名前については、できるだけ本名を記載するようにしています。(馴染みが無い呼び方かもしれません。)
※史実や事実と異なる表現があります。
※主人公が大王になった後の話を、第2部として追加する可能性があります。その時は完結→連載へ設定変更いたします。

柳鼓の塩小町 江戸深川のしょうけら退治
月芝
歴史・時代
花のお江戸は本所深川、その隅っこにある柳鼓長屋。
なんでも奥にある柳を蹴飛ばせばポンっと鳴くらしい。
そんな長屋の差配の孫娘お七。
なんの因果か、お七は産まれながらに怪異の類にめっぽう強かった。
徳を積んだお坊さまや、修験者らが加持祈祷をして追い払うようなモノどもを相手にし、
「えいや」と塩を投げるだけで悪霊退散。
ゆえについたあだ名が柳鼓の塩小町。
ひと癖もふた癖もある長屋の住人たちと塩小町が織りなす、ちょっと不思議で愉快なお江戸奇譚。

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する
克全
歴史・時代
貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

あさきゆめみし
八神真哉
歴史・時代
山賊に襲われた、わけありの美貌の姫君。
それを助ける正体不明の若き男。
その法力に敵う者なしと謳われる、鬼の法師、酒呑童子。
三者が交わるとき、封印された過去と十種神宝が蘇る。
毎週金曜日更新

Millennium226 【軍神マルスの娘と呼ばれた女 6】 ― 皇帝のいない如月 ―
kei
歴史・時代
周囲の外敵をことごとく鎮定し、向かうところ敵なし! 盤石に見えた帝国の政(まつりごと)。
しかし、その政体を覆す計画が密かに進行していた。
帝国の生きた守り神「軍神マルスの娘」に厳命が下る。
帝都を襲うクーデター計画を粉砕せよ!
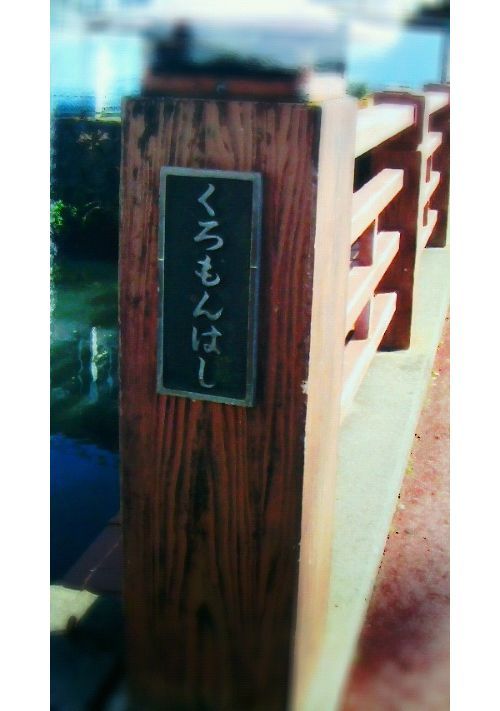
肥後の春を待ち望む
尾方佐羽
歴史・時代
秀吉の天下統一が目前になった天正の頃、肥後(熊本)の国主になった佐々成政に対して国人たちが次から次へと反旗を翻した。それを先導した国人の筆頭格が隈部親永(くまべちかなが)である。彼はなぜ、島津も退くほどの強大な敵に立ち向かったのか。国人たちはどのように戦ったのか。そして、九州人ながら秀吉に従い国人衆とあいまみえることになった若き立花統虎(宗茂)の胸中は……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















