5 / 5
2
しおりを挟むあの日から、俺が物心ついて以来、初めての平穏な生活が待っていた。
美花は俺を否定しなくなったし、俺も一度は殺してしまったという負い目から美花に極力優しく接した。
そしてそんな俺を見て、母さんの態度もどんどん変わっていった。以前は俺の顔も見ずにおどおどしていたが、ひと月が経った今では、俺達の話に混ざってくるようになった。
親父は最初こそあまり変わらなかったが、俺が夕飯の席にいてもすぐ部屋に引っ込まなくなったし、挨拶も交わすようになった。
元々が不器用な人なのだろう。最近では不器用なりに共通の話題を探しているのが見て取れるようになった。俺が話に興味を示すと、口元を僅かに緩ませ、眼鏡を掛け直すのだ。
金色に染め上げていた髪を、せめてもと思い栗色に染め直した時も、三人は笑顔で迎えてくれた。
俺は今、幸せだ。温かい家族に囲まれて、俺自身も優しくなれて。
反面教師とはまさにこういう事をいうのだろう。
あの日、あの事件が起きなかったら、そして雪なる少年に会わなかったら、こうして穏やかに笑う俺は存在しなかったろう。
家族の温かさにも気付かず――気付こうともせずに背を向け、いつまでも肩肘を張って生きていたかもしれない。……心の底では美花を羨みながら。
あの日、俺にとって運命の日となったあの日以来、俺は学校をサボらなくなった。授業も真面目に受けている。仲間にはすっかり腑抜けちまったと散々言われたが、そんな事はどうでも良い。卒業してしまえばもう会う事もないだろう。
それより俺はこの十七年、ずっと出来ずにいた親孝行をしたかった。卒業してフラフラするよりも、両親の望む通り大学へ進学しようと決めたのだ。
頭は中学生並みで、中一にして既に高校受験の為の勉強に励む美花よりも馬鹿だったが、そこそこ名のある大学出身だった母さんと、何より俺のような馬鹿な兄に真剣に勉強を教えてくれた美花のおかげで、俺の成績は急上昇している。
とても充実した日々だった。
そしてその日も俺は夜遅くまで勉強していた。
ふと時計を見ると、午前一時半過ぎ。そろそろ寝ようかとベッドに入りまどろんでいると、隣の部屋のドアが閉まる音が聞こえた。美花がトイレにでも起きたのだろうと、気に留めずにそのまま眠ってしまった。
次に起きたのは、午前三時半を少し過ぎた頃だった。乱暴に階段を駆け上る音に続いて、隣の部屋のドアが勢いよく閉まる音が聞こえたのだ。美花がまたトイレに行ったのだろうと、俺は再び眠りについてしまった。
「……はよ」
「おっはよう、お兄ちゃん」
朝、いつもよりも早く目覚めた俺が台所に入ると、美花が苺ジャムをたっぷり乗せたトーストにかぶりついていた。
「お前、朝からよくそんなの食えるな……」
美花は口いっぱいに頬張ったパンをこれまた甘そうなミルクティーで一気に飲み下し、夏服の襟元をトントンと叩く。
「だって、好きなんだもん。お兄ちゃんも食べる? 元気出るよー」
「うえ、いらねぇ。絶対吐く」
「えー美味しいのにぃ」
丁重に断ると、美花は口を尖らせて不満気に言い、また一口かぶりつく。その歳相応の言動に俺は小さく笑った。
「良かった、元気になったんだな」
「え? 何?」
俺の唐突な言葉に美花は目を瞬かせる。
昨日美花は何となく元気がなかったように感じた。いや、昨日だけではない。最近気付いたのだが、美花は週に一度元気がない日があった。
思春期というやつなのかもしれないが、やはり例の事と関係があるのではないかと勘繰ってしまう。美花は普通の娘とは違うのだ。
「どうしたの?」
美花が怪訝そうに訊く。俺は首を横に振り、テーブルの上の新聞紙を取った。
「別に、何でもないさ」
「そう? まぁいいけど。それより朝っぱらから新聞広げないでよね。オヤジ臭いわよ」
「朝刊は朝読まなくていつ読むんだよ」
挑むように言うと、美花は俺の目の前に人差し指を突きつけた。
「屁理屈ね。更にオヤジ度アップよ」
その仕草があの少年、雪と重なって見えて、俺は目を細めた。
「言ってろ。ガキんちょよりはマシだ」
「何よう!」
美花がふざけて今度は拳を突き出す。その色白で小さい、いかにも弱そうな拳に、俺は思わず吹き出してしまった。
「おはよう大樹。何だか賑やかねえ」
母さんが台所へ入ってきた。母さんは俺と美花を見てクスクス笑う。
「おはよう、母さん。ゴミ出し?」
「違うよ、お兄ちゃん。お母さんは井戸端会議のついでに、ゴミを出してきたのよ」
美花が内緒話をするような仕草をしつつ、大きな声で言った。
「美花ったら……まぁ、そうなんだけどね」
母さんが困ったように笑った。美花もホラね、と得意げに笑う。しかし母さんは俺の朝食を用意しながら笑みを消して続けた。
「それで、聞いた話なんだけどね、どうやらこの町内に変質者が出るみたいなのよ」
「変質者?」
声を揃えて聞き返した俺達に、母さんは眉をひそめて更に続ける。
「そう。今のところ被害にあったのは野良猫二匹と野良犬一匹、それに今朝見つかった飼い犬一匹。どれもお腹が切り開かれてて、中身がすっかりなくなっていたんですって……。
怖いわねぇ。あなた達も気をつけてね。――あら、どうかした?」
うすうす気付いてはいたが、やはり母さんは鈍い。黙っている俺に代わって美花が溜め息をつき、ポツリと呟いた。
「配慮が足りないわよ、お母さん」
俺は味噌汁の中に突っ込んでいた箸を一旦出して固まっていた。母さんはそんな俺に気付くと、頬を赤くして何度も謝った。
「いいよ、母さん。俺、そんな事で物が食えなくなるほど繊細に出来てないから」
「そうね、お兄ちゃんが繊細だったらわたし、驚いちゃうわ」
「何しろ美花、お前の兄だからな」
「どういう意味よう」
再び沸き起こる笑い声。いつも通りの温かくて幸せな朝の風景。
俺はこの時、この幸せはこれから永久不変なものになって行くのだろうと、疑いもしなかった。
翌週、例の動物殺しの犯人が、今度は会社帰りのOLを襲った。警察が同一犯と見たのは、犯行の時間と現場区域の一致、そして何より、想定される凶器の大きさ、刃の形が一致したからで、今回も腹部の中身――内臓は綺麗に切り取られていた、とニュースキャスターは神妙な面持ちで語った。
「うわぁ、惨い」
美花が今日も苺ジャム地獄のトーストにかぶりつきながら、テレビに向かって言う。
「美花、お行儀が悪いわよ。食べるか喋るかどっちかになさい」
「はぁーい。でもさ、本当に怖いよね。こんな事件がご町内で起きちゃうなんて。物騒で夜出歩けないよね」
「お前、夜に出歩く必要なんてないだろ」
「そうでした」
美花は舌をぺろりと出す。
それにしても本当に物騒な話だ。猫や犬だけでは飽き足らず、人間までも手にかけるなんて。
しかも内臓が切り取られていたとは。そんなもの、何に使うのか……考えただけでもおぞましい。まるで悪魔のような犯人だ。――いや、悪魔よりタチが悪い。俺が出会った悪魔――正確には仲介人らしいが――は俺を助けてくれた。
今の幸せを手に入れるきっかけをくれた雪達には感謝の念しかない。
そういえばあれ以来、きちんとしたお礼も言わず終いのままだ。店まではそう遠くないのに、何となく行きそびれていたのだ。
あの店には女子が喜びそうなものが売っていた。来週は美花の十三歳の誕生日だし、丁度良い。緑夢へ行ってみよう。
俺はそう決めて味噌汁を飲み干した。
夕方の駅前は、警察やマスコミ、野次馬で混み合っていた。昨夜の事件は駅隣りの中央公園で起きたのだ。
今朝よりもマスコミや警官の姿は減っていたが、警官数人は未だうろうろしているし、何より野次馬の数が凄い。
ほとんどが中高生で、うち七割は女子生徒だ。恐るべし、野次馬根性。しかも彼女達の中には『緑夢』と書かれた袋を持っている者が少なくなく、これには大層驚いた。こんなに流行っているとは思っていなかったのだ。そしてほんの少し嬉しくなった。
俺は人混みに背を向け、商店街の外れを目指して歩き出した。その途中も、緑の袋を持って歩いてくる少女達や、美花と同じ水色のセーラー服姿の中学生ともすれ違った。
気を良くした俺は、足取りも軽く商店街を進んだ。
商店街にはいろんな店が揃っていて、毎日若者たちで賑っている。
特に書店、雑貨屋、CDショップと大型の三店が隣り合った中心地には、いつもたくさんの人が集まってくる。俺はそれらの人達を眺めながら歩いていた。緑夢まではもう少し距離がある。
そしてそれは商店街二つ目のコンビニの前を通りかかった時だった。
「あれ、もしかして北沢大樹クン?」
声変わり前の高い少年の声で呼びかけられ、俺は目を丸くして振り向いた。俺の知り合いにこんな声の持ち主は、一人しかいない。
「……お前」
「雪だってば。まさか僕の名前忘れてたんじゃないだろうね」
俺の後ろに立って例の綺麗な笑みをこちらに向けていたのは、今から会いに行こうとしていた雪その人だった。
白シャツに黒い細身のパンツと、道行く少年達と似たような格好をしているが、白い髪と端正な顔立ちはやはり目立つ。今も雪を振り返る人達は数え切れない。
……長い前髪を七・三に分ける星型のピンにどんな意味があるのかは分からないが。
「大樹? どうかした?」
「……いや、別に」
そっけなく返すと、雪も興味をなくしたらしく、持っていたコンビニの袋から小さな袋を探り出し、中から棒付きのバニラアイスを取り出して食べ始めた。
「俺、今から緑夢に行く所だったんだ。丁度良かった」
ゆっくりとした足取りで歩き出した雪の隣に並んで歩く。
「僕の店に? ふぅん、物好きだねぇ」
「お前が言うなよ」
「あはは、確かに」
雪は楽しそうに笑った。この笑顔もたった一ヶ月ぶりなのに、少し懐かしいと感じる。
「ところで君、すっかり変わっちゃったね。髪の色まで変えちゃって。ね、どうして?」
雪がまだ半分残ったアイスをマイク代わりに俺に向ける。
「いろいろ思う所があってな。今の俺がいるのはお前のおかげだし。感謝してるよ」
改めて礼を言うと、雪は目を細め、アイスを俺に突きつけた。
「やれば出来るじゃないか、大ちゃん。そんなアナタに僕からこれをプレゼント!」
「食べかけじゃねぇか! いらねぇよ、そんなの。それに大ちゃんはやめろ」
「ちぇ。大樹はワガママだなぁ。このアイス、中のクリームが甘すぎるんだよね」
そう言って雪はアイスを袋に戻し、キョロキョロと辺りを見渡してくずかごを見つけると、近くまで駆け寄ってアイスを放り投げた。捨てるのなら最初から買わなければいいのに。
バニラアイスが好きなら、クリームの入っていないものを買えばいいのだ。
「ねっ、大樹、見てくれた? 僕のナイスシュート」
雪が満面の笑みで戻って来る。
「ああ。でも何でこの間みたいに消失させないんだ? そっちのほうが楽だろうに」
「そんなの、僕みたいな平凡な人間に出来る訳ないだろ。あれをやっていたのはノヴァだよ。彼はとっても優秀な死の神なんだ」
雪は親指と人差し指で円を作り、左目に当てた。あの青年の片眼鏡を真似ているらしい。
「……死神?」
「死の神だってば。『命の支配者』とも呼ばれる悪魔《ゲーデ》。彼はね、死んだ者の全てを識っているんだ」
「死神とどう違うんだ?」
「うーん、君の言う死神って奴は魂を奪いに来るんだろう? ゲーデは寧ろ逆で、死者の蘇生を得意とする。美花ちゃんを蘇らせたのも彼だよ」
雪は何でもない事のように語る。なかなか理解し難いが、あの青年のおかげで今こうしていられる事だけは分かった。
「悪魔にもいろいろいるんだな」
「ま、それは人間にだって言える事だけどね」
当たり障りのない返事をする俺に気付いてか、雪は早々に話を切り上げた。
「やだなぁ、帰るの。何で今日はこんなに忙しいんだ」
雪が眉をひそめて道端にたむろしている女子高生達を眺めると、彼女らは雪と目が合ったと黄色い声を上げる。何か大きな勘違いをしているらしい。俺だけは雪の心情が解っていたので、思わず苦笑してしまう。
普通の男なら、女の子に騒がれるのは多少なりとも嬉しい筈だろうに。
「何なの、あれ。馬鹿みたい」
俺に比べ、雪は別におかしくも何ともないらしい。興味が失せたように視線を戻す。
「確かにな。でもお前こそ、その髪留めは何のつもりだ?」
俺はずっと気になっていた事を口にした。
「え、似合わない? 変?」
「いや、変ではないけど。……いや、変じゃないから変だろう」
我ながらおかしな日本語で返すと、雪はピンを外して手のひらに乗せ、じっと見つめた。
「せっかく美花ちゃんがくれたのにな」
「美花に? あいつ緑夢に行ってるのか」
「うん。美花ちゃんも特別なお客さんだからね。さっきも友達と来てくれたよ」
「へぇ」
初耳だった。まあ、これだけ流行っていればおかしくはないが。それにしても、最近美花が雪に重なって見えたのは、やはり美花が雪の影響を受けていたからだったのだ。
「そういや、店が忙しそうなのに、肝心のお前がこんな所にいていいのか?」
「いいんだよ。店の方はあくまで副業だし。それに僕はちょっとおつかいに出てきただけだから」
雪はコンビニの袋を持ち上げて見せる。
「それを口実に逃げてきたって事か」
「逃げられないから、こうして戻ってきたんじゃないか」
自分の店を前に溜め息をつく雪に笑みを零しながら、俺は先に立って入り口の扉を開け――そして思わず一歩退いた。
店内は見事に女ばっかりだったのだ。予想はしていたものの、やはり抵抗がある。
「どうしたの、大樹。中に入らないの?」
雪が隣に並んでにやりとする。本当に嫌味な奴だ。……しかし雪と一緒で良かった。一人で入るには、かなりの勇気が必要とされる。
「あっ、雪くん!」
「何処行ってたのよー」
「そうそう、せっかく会いに来たのにぃ」
雪が店に足を踏み入れるなり、にわかに店内がざわつき出した。雪は可愛らしく笑って彼女らの輪の中に入って行く。
「猫被りもここまできたら一種の才能だな」
呟くと、そばで商品を並べ直していたノヴァが小さく頷いた。
「天賦の才とは良く言ったものです」
「素敵な褒め言葉をありがとう。二人とも」
雪がよそいきの表情のまま戻ってきた。笑顔が怖い。
「……別に悪い意味じゃねぇよ」
「ふぅん? まぁいいけど」
本当にどうでもよさそうに言って雪はドアの方へ手を振った。見ると、狭い店内にひしめき合っていた客達が揃って帰って行く。
「じゃあね、雪くん。また来るね」
「うん、楽しみに待ってます」
最後の客が店を出た途端、雪は本性を現した。
「なんちゃって。もう来なくて良いっての」
微笑を冷笑に変えて言い捨てる。
「何で一斉に帰ったんだ? もう閉店か?」
「帰らせたんだよ」
雪はさも当然といった風に答えた。どうやって? と更に疑問を浮かべる俺に、察したように続ける。
「中央公園にまた人が集まってたから、何か分かったのかもって言っただけだよ。凄い野次馬根性だよね。好奇心旺盛なのは結構だけど、ああはなりたくないな」
そう言って雪は肩をすくめた。
「それで、大樹は何の用で来たんだっけ?」
「え? あぁ、そうだった」
俺はようやくここへ来た目的を思い出した。
「もうすぐ美花の誕生日なんだ。だから」
「へぇ。随分と妹想いになったものだね」
雪が目を細めて微笑む。その色素の薄い茶色の瞳は、続きをこう語っていた。
『一度は殺してしまったくせに』
俺は再び苦笑した。
結局何が良いか見当もつかなかったので、雪に勧められたお香セットを買う事にした。今一番人気の商品らしく、大抵の客はこれが目当てで来るらしい。種類も豊富で美花もよく買って行くそうだ。
初耳だったが、そういえば美花の部屋はいつも良い匂いがしていた。リラックスや安眠効果、何より良い夢が見られるのが売りらしい。他の店の商品なら信じないが、ここは『緑夢』で、勧めているのは目下の所一番信頼を寄せている雪だ。
俺は良いプレゼントが見つかったと一安心した。
ただ、帰り際のある一言だけ妙に引っかかりを覚えた。
「最近、美花ちゃんに変わった事はない?」
変わった事ならありすぎた。何よりもまず俺自身、すっかり変わってしまったし、親父や母さんだって以前とは比べ物にならない。
当然、美花だってすっかり変わった。そんな事くらい、雪なら承知の上だろう。
――では、一体何の事を言っているのか。
そこまで考えついた時、俺の脳裏をよぎった記憶があった。
一週間前の明け方。
美花が階段を乱暴に駆け上がり、勢いよくドアを閉めた時のあの音が、何故か耳から離れない。
嫌な予感がした。そして、じっと黙り込んだ俺を見つめる雪の瞳が妖しい程に綺麗で、少し怖いと思った。
――俺は雪を信じすぎてはいないだろうか。あいつの事を少し分かったつもりでいたが、本当はちっとも解っていないのではないか……?
夕闇迫る町の中、俺はしばしの間、言い知れぬ虚無感に囚われた。
0
お気に入りに追加
1
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

インター・フォン
ゆずさくら
ホラー
家の外を何気なく見ているとインターフォンに誰がいて、何か細工をしているような気がした。
俺は慌てて外に出るが、誰かを見つけられなかった。気になってインターフォンを調べていくのだが、インターフォンに正体のわからない人物の映像が残り始める。

信者奪還
ゆずさくら
ホラー
直人は太位無教の信者だった。しかし、あることをきっかけに聖人に目をつけられる。聖人から、ある者の獲得を迫られるが、直人はそれを拒否してしまう。教団に逆らった為に監禁された直人の運命は、ひょんなことから、あるトラック運転手に託されることになる……



ゾバズバダドガ〜歯充烏村の呪い〜
ディメンションキャット
ホラー
主人公、加賀 拓斗とその友人である佐々木 湊が訪れたのは外の社会とは隔絶された集落「歯充烏村」だった。
二人は村長から村で過ごす上で、絶対に守らなければならない奇妙なルールを伝えられる。
「人の名前は絶対に濁点を付けて呼ばなければならない」
支離滅裂な言葉を吐き続ける老婆や鶏を使ってアートをする青年、呪いの神『ゾバズバダドガ』。異常が支配するこの村で、次々に起こる矛盾だらけの事象。狂気に満ちた村が徐々に二人を蝕み始めるが、それに気付かない二人。
二人は無事に「歯充烏村」から抜け出せるのだろうか?
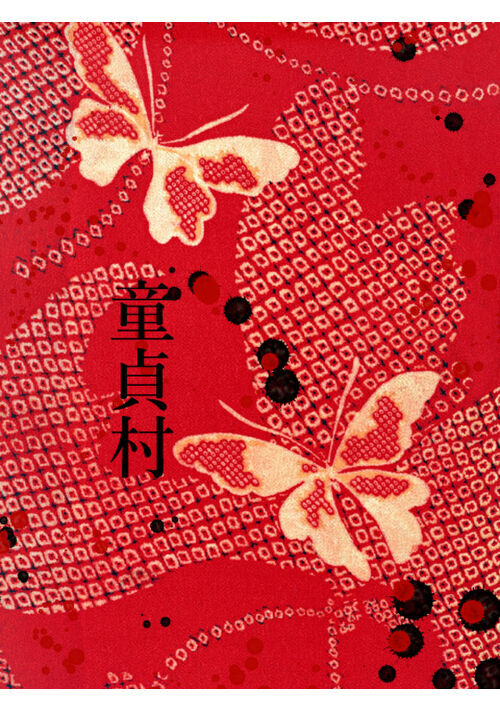
童貞村
雷尾
ホラー
動画サイトで配信活動をしている男の元に、ファンやリスナーから阿嘉黒町の奥地にある廃村の探索をしてほしいと要望が届いた。名前すらもわからないその村では、廃村のはずなのに今でも人が暮らしているだとか、過去に殺人事件があっただとか、その土地を知る者の間では禁足地扱いされているといった不穏な噂がまことしやかに囁かれていた。※BL要素ありです※
作中にでてくるユーチューバー氏は進行役件観測者なので、彼はBLしません。
※ユーチューバー氏はこちら
https://www.alphapolis.co.jp/manga/980286919/965721001


コルチカム
白キツネ
ホラー
都会から遠く、遠く離れた自然が多い田舎町。そんな場所に父親の都合で転校することになった綾香は3人の友人ができる。
少し肌寒く感じるようになった季節、綾香は季節外れの肝試しに誘われた。
4人で旧校舎に足を踏み入れると、綾香たちに不思議な現象が襲い掛かる。
微ホラーです。
他小説投稿サイト様にも掲載しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















