9 / 43
『僕と彼女と互いの想い』
第九話 『何でかしらね。今までこんなに子供が近付いてくることなんてなかったのに』
しおりを挟む
「また近いうちに、ミケに会いに来ましょうね」
チュールを食べ終わったミケを思う存分抱っこし、撫で続けた莉子。
ミケが恩猫であるとともに、莉子はかなりの動物好きである。
充分にモフモフできたことに満足しているようだった。
ミケと別れた僕らは、近くにある大きな公園へと移動した。
この公園は遊具などもあるが、青々とした芝生が多くの面積を占めていた。
その芝生で寝っ転がって睡眠をとる人、本を読む人、サッカーをする人、バドミントンをする人……。
思い思いに寛ぎ、また、はしゃぐ人がいて賑やかな場所となっている。
そんな人たちの様子を見ながら、僕ら二人は並んでベンチに腰掛けた。
「そういえば……、アオにはいつ会わせてくれるの?」
ミケをモフモフした莉子は、猫繋がりで思い付いたのだろう。
僕に質問を投げかけてくる。
「アオはねぇ……」
『アオ』というのは、うちで飼っている猫のことである。
莉子からは会ってみたい旨をそれとなく何度か聞かされていた。
そのたびに僕は「また今度ね」と、お茶を濁していた。
「……そんなにアオをあたしに会わせたくないの?」
言葉に詰まった僕を見て、悲しげな表情を見せる莉子。
「いやいやいや、そういうわけでは……」
アオは人を警戒するというか、気難しいというか、誰にでも懐くわけではなかった。
莉子と仲良くなれるという確信が、僕は未だに持てなかったのだ。
アオに一回試しに会わせるべきか、もしくはきちんと説明をして……。
――僕が真剣に悩んでいたときだった。
「――陸!! 危ないっ!!」
莉子の差し迫ったの声が聞こえるとともに、僕の目前に莉子の手が伸びる。
「お、おぉう……」
急な出来事についていけない僕は情けない声を上げてしまった。
莉子が伸ばした手には、バドミントンの羽根が握られていた。
どうやら、僕に向かって飛んで来た羽根を莉子がキャッチしてくれたようである。
「あぁ、ありがとう……」
ドキドキしながら感謝を伝えていると、一人の女の子がタタッと僕らに近付いてきた。
小学校低学年くらいだろうか。
薄いピンクのブラウスを着ている可愛らしい女の子である。
「あ、あの、、、ごめんなさい……」
手には、子供用思われる短いバドミントンのラケットを持っている。
どうやら誤って、こちらに羽根を打ち込んでしまったらしい。
――マズイ!?
僕はハッとなった。
飛んで来た羽根を、莉子は『攻撃』と判断するのではないだろうか?
つまり、目の前の女の子は敵で……。
「莉子、ちょっと!? 待っ……?」
急いで莉子の方へと手を伸ばすと、莉子はバッグから包丁を取り出すでもなく、殺気を放つでもなかった。
ただ、唇を噛み、手に持った羽根と女の子とを交互に見つめていた。
そして、こちらへと目を向ける。
その目はこう訴えてきていた。
『……私は、どうすれば良いの?』
と。
莉子には弟や妹はいない。
それに、「小さい子供はあたしに近付いてこない」とも以前言っていた。
基本的に莉子は常に人を寄せ付けないオーラを纏い、人との間に壁を作っている。
そんなオーラを纏っていたら、確かに子供は近付けないし、近付こうとも思わないだろう。
図書館で見掛けた莉子に話し掛けたいと思っていた僕が、ミケの力を借りないと近付けないくらいだったのだから。
つまり、莉子は子供と接したことがなく、どのように接すれば良いのか、分からないのである。
だったら――。
「莉子なら、大丈夫だよ」
僕はできるだけ優しく、莉子に語り掛けた。
周りからは莉子は怖いとか、近づき難いとか、思われているかもしれない。
優しさなんて持ち合わせていないと思われているかもしれない。
でも、僕はそうは思わない。
莉子は僕には凄く優しいし、ミケにだって優しく接することができている。
やり方が分からないだけで、できないわけではないのだ。
「――小さな子供相手には、ミケにするみたいに優しく接すれば良いよ」
「う、うん」
頷いた莉子だったが、今度は緊張してしまっていた。
莉子を見ていた女の子が少し警戒をしている。
「莉子、緊張しないようにして。大丈夫、深呼吸してからで良いから」
それを聞いた莉子は、深呼吸をして、ゆっくりと緊張を解いていった。
(うん、莉子なら大丈夫)
まだ少しだけぎこちないながらも、笑顔を作った莉子。
「はい、どうぞ」
女の子に手を伸ばして優しく頭を撫でながら、バドミントンの羽根を手渡した。
「ありがとう、お姉ちゃん!!」
怒られるかもしれないと不安だったのかもしれない。
元気よくお礼を言うと同時に、女の子の曇った表情がパッと晴れやかなものへ変化した。
そして、去っていく女の子の後ろ姿を、莉子は優しい眼差しで見つめていた。
「ありがとう、陸。もう大丈夫よ」
そう言った莉子からは、もう迷いは感じられなかった。
今後、子供が近付いて来ても、きっと大丈夫だろう。
莉子なら、優しく接することができるはずだ。
「でも、何でかしらね。今までこんなに子供が近付いてくることなんてなかったのに」
莉子は、不思議そうな顔をしていた。
「先日も陸と一緒のとき、あたしにぶつかりそうになった子がいたし……」
――どうやら気付いていないらしい。
笑顔で僕と一緒にいるとき、莉子の人を寄せ付けないオーラが非常に弱くなっていることに。
そのことを教えてあげようかと少し思ったが――、すぐに思い直した。
「本当に、何でだろうね」
今はまだ教えなくて良い。
教えたら、気付いてしまうかもしれない。
もしそのオーラを纏ったままだったなら、僕らがこんなにもヤンキーたちに絡まれることはないことに。
そうなったら、優しい莉子はきっと僕を守るために、弱くなったオーラを元に戻すようにしてしまうだろう。
それはちょっと寂しいから……。
「じゃあ、そろそろ行こうか」
話を変えるように、莉子に声を掛ける。
「そうね、それじゃあ……、陸!?」
再度、大きな注意の声を上げた莉子が、僕の前に手を伸ばす。
莉子の手にあったのは、今度はフリスビーだった。
どうやら柔らかい材質で出来ているもののようで、莉子の指ががっつりと食い込んでいる。
また誰かが誤ってこちらに投げてしまったのだろう。
フリスビーが飛んで来た方を見ると、大学生らしき男性がこちらに近付いてくるのが分かった。
莉子の様子を確認すると、にこりと笑顔を返してくる。
「もう大丈夫よ。だって、陸が教えてくれたじゃない」
そう言って、何の迷いなく、バッグから包丁を取り出す莉子。
その行動は自信に満ち溢れている。
「えっ!? ちょっと、何を!?」
「大丈夫、あたしに任せて。『小さな子供には優しく』、つまり、大人には――」
両手に包丁を構え、戦闘態勢を取る莉子。
「『厳しく』ってことよねーー!!」
「そんなことは言ってないーーー!!!」
叫び声を上げつつ、僕は突撃しようとする莉子へと必死に飛びついたのである。
◆ ◆ ◆
この日から莉子は小さな子供に対して優しく接するようになった。
しかしながら、大人に対してはより厳しく接するようになったのである……。
僕は一体どうすれば…………。
チュールを食べ終わったミケを思う存分抱っこし、撫で続けた莉子。
ミケが恩猫であるとともに、莉子はかなりの動物好きである。
充分にモフモフできたことに満足しているようだった。
ミケと別れた僕らは、近くにある大きな公園へと移動した。
この公園は遊具などもあるが、青々とした芝生が多くの面積を占めていた。
その芝生で寝っ転がって睡眠をとる人、本を読む人、サッカーをする人、バドミントンをする人……。
思い思いに寛ぎ、また、はしゃぐ人がいて賑やかな場所となっている。
そんな人たちの様子を見ながら、僕ら二人は並んでベンチに腰掛けた。
「そういえば……、アオにはいつ会わせてくれるの?」
ミケをモフモフした莉子は、猫繋がりで思い付いたのだろう。
僕に質問を投げかけてくる。
「アオはねぇ……」
『アオ』というのは、うちで飼っている猫のことである。
莉子からは会ってみたい旨をそれとなく何度か聞かされていた。
そのたびに僕は「また今度ね」と、お茶を濁していた。
「……そんなにアオをあたしに会わせたくないの?」
言葉に詰まった僕を見て、悲しげな表情を見せる莉子。
「いやいやいや、そういうわけでは……」
アオは人を警戒するというか、気難しいというか、誰にでも懐くわけではなかった。
莉子と仲良くなれるという確信が、僕は未だに持てなかったのだ。
アオに一回試しに会わせるべきか、もしくはきちんと説明をして……。
――僕が真剣に悩んでいたときだった。
「――陸!! 危ないっ!!」
莉子の差し迫ったの声が聞こえるとともに、僕の目前に莉子の手が伸びる。
「お、おぉう……」
急な出来事についていけない僕は情けない声を上げてしまった。
莉子が伸ばした手には、バドミントンの羽根が握られていた。
どうやら、僕に向かって飛んで来た羽根を莉子がキャッチしてくれたようである。
「あぁ、ありがとう……」
ドキドキしながら感謝を伝えていると、一人の女の子がタタッと僕らに近付いてきた。
小学校低学年くらいだろうか。
薄いピンクのブラウスを着ている可愛らしい女の子である。
「あ、あの、、、ごめんなさい……」
手には、子供用思われる短いバドミントンのラケットを持っている。
どうやら誤って、こちらに羽根を打ち込んでしまったらしい。
――マズイ!?
僕はハッとなった。
飛んで来た羽根を、莉子は『攻撃』と判断するのではないだろうか?
つまり、目の前の女の子は敵で……。
「莉子、ちょっと!? 待っ……?」
急いで莉子の方へと手を伸ばすと、莉子はバッグから包丁を取り出すでもなく、殺気を放つでもなかった。
ただ、唇を噛み、手に持った羽根と女の子とを交互に見つめていた。
そして、こちらへと目を向ける。
その目はこう訴えてきていた。
『……私は、どうすれば良いの?』
と。
莉子には弟や妹はいない。
それに、「小さい子供はあたしに近付いてこない」とも以前言っていた。
基本的に莉子は常に人を寄せ付けないオーラを纏い、人との間に壁を作っている。
そんなオーラを纏っていたら、確かに子供は近付けないし、近付こうとも思わないだろう。
図書館で見掛けた莉子に話し掛けたいと思っていた僕が、ミケの力を借りないと近付けないくらいだったのだから。
つまり、莉子は子供と接したことがなく、どのように接すれば良いのか、分からないのである。
だったら――。
「莉子なら、大丈夫だよ」
僕はできるだけ優しく、莉子に語り掛けた。
周りからは莉子は怖いとか、近づき難いとか、思われているかもしれない。
優しさなんて持ち合わせていないと思われているかもしれない。
でも、僕はそうは思わない。
莉子は僕には凄く優しいし、ミケにだって優しく接することができている。
やり方が分からないだけで、できないわけではないのだ。
「――小さな子供相手には、ミケにするみたいに優しく接すれば良いよ」
「う、うん」
頷いた莉子だったが、今度は緊張してしまっていた。
莉子を見ていた女の子が少し警戒をしている。
「莉子、緊張しないようにして。大丈夫、深呼吸してからで良いから」
それを聞いた莉子は、深呼吸をして、ゆっくりと緊張を解いていった。
(うん、莉子なら大丈夫)
まだ少しだけぎこちないながらも、笑顔を作った莉子。
「はい、どうぞ」
女の子に手を伸ばして優しく頭を撫でながら、バドミントンの羽根を手渡した。
「ありがとう、お姉ちゃん!!」
怒られるかもしれないと不安だったのかもしれない。
元気よくお礼を言うと同時に、女の子の曇った表情がパッと晴れやかなものへ変化した。
そして、去っていく女の子の後ろ姿を、莉子は優しい眼差しで見つめていた。
「ありがとう、陸。もう大丈夫よ」
そう言った莉子からは、もう迷いは感じられなかった。
今後、子供が近付いて来ても、きっと大丈夫だろう。
莉子なら、優しく接することができるはずだ。
「でも、何でかしらね。今までこんなに子供が近付いてくることなんてなかったのに」
莉子は、不思議そうな顔をしていた。
「先日も陸と一緒のとき、あたしにぶつかりそうになった子がいたし……」
――どうやら気付いていないらしい。
笑顔で僕と一緒にいるとき、莉子の人を寄せ付けないオーラが非常に弱くなっていることに。
そのことを教えてあげようかと少し思ったが――、すぐに思い直した。
「本当に、何でだろうね」
今はまだ教えなくて良い。
教えたら、気付いてしまうかもしれない。
もしそのオーラを纏ったままだったなら、僕らがこんなにもヤンキーたちに絡まれることはないことに。
そうなったら、優しい莉子はきっと僕を守るために、弱くなったオーラを元に戻すようにしてしまうだろう。
それはちょっと寂しいから……。
「じゃあ、そろそろ行こうか」
話を変えるように、莉子に声を掛ける。
「そうね、それじゃあ……、陸!?」
再度、大きな注意の声を上げた莉子が、僕の前に手を伸ばす。
莉子の手にあったのは、今度はフリスビーだった。
どうやら柔らかい材質で出来ているもののようで、莉子の指ががっつりと食い込んでいる。
また誰かが誤ってこちらに投げてしまったのだろう。
フリスビーが飛んで来た方を見ると、大学生らしき男性がこちらに近付いてくるのが分かった。
莉子の様子を確認すると、にこりと笑顔を返してくる。
「もう大丈夫よ。だって、陸が教えてくれたじゃない」
そう言って、何の迷いなく、バッグから包丁を取り出す莉子。
その行動は自信に満ち溢れている。
「えっ!? ちょっと、何を!?」
「大丈夫、あたしに任せて。『小さな子供には優しく』、つまり、大人には――」
両手に包丁を構え、戦闘態勢を取る莉子。
「『厳しく』ってことよねーー!!」
「そんなことは言ってないーーー!!!」
叫び声を上げつつ、僕は突撃しようとする莉子へと必死に飛びついたのである。
◆ ◆ ◆
この日から莉子は小さな子供に対して優しく接するようになった。
しかしながら、大人に対してはより厳しく接するようになったのである……。
僕は一体どうすれば…………。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

セレナの居場所 ~下賜された側妃~
緑谷めい
恋愛
後宮が廃され、国王エドガルドの側妃だったセレナは、ルーベン・アルファーロ侯爵に下賜された。自らの新たな居場所を作ろうと努力するセレナだったが、夫ルーベンの幼馴染だという伯爵家令嬢クラーラが頻繁に屋敷を訪れることに違和感を覚える。

手が届かないはずの高嶺の花が幼馴染の俺にだけベタベタしてきて、あと少しで我慢も限界かもしれない
みずがめ
恋愛
宮坂葵は可愛くて気立てが良くて社長令嬢で……あと俺の幼馴染だ。
葵は学内でも屈指の人気を誇る女子。けれど彼女に告白をする男子は数える程度しかいなかった。
なぜか? 彼女が高嶺の花すぎたからである。
その美貌と肩書に誰もが気後れしてしまう。葵に告白する数少ない勇者も、ことごとく散っていった。
そんな誰もが憧れる美少女は、今日も俺と二人きりで無防備な姿をさらしていた。
幼馴染だからって、とっくに体つきは大人へと成長しているのだ。彼女がいつまでも子供気分で困っているのは俺ばかりだった。いつかはわからせなければならないだろう。
……本当にわからせられるのは俺の方だということを、この時点ではまだわかっちゃいなかったのだ。

どうして待ってると思った?
しゃーりん
恋愛
1人の男爵令嬢に4人の令息が公開プロポーズ。
しかし、その直後に令嬢は刺殺された。
まるで魅了魔法にかかったかのように令嬢に侍る4人。
しかし、魔法の痕跡は見当たらなかった。
原因がわかったのは、令嬢を刺殺した男爵令息の口から語られたから。
男爵令嬢、男爵令息、4人の令息の誰にも救いのないお話です。

【完結】捨ててください
仲 奈華 (nakanaka)
恋愛
ずっと貴方の側にいた。
でも、あの人と再会してから貴方は私ではなく、あの人を見つめるようになった。
分かっている。
貴方は私の事を愛していない。
私は貴方の側にいるだけで良かったのに。
貴方が、あの人の側へ行きたいと悩んでいる事が私に伝わってくる。
もういいの。
ありがとう貴方。
もう私の事は、、、
捨ててください。
続編投稿しました。
初回完結6月25日
第2回目完結7月18日

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

娼館で元夫と再会しました
無味無臭(不定期更新)
恋愛
公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。
しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。
連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。
「シーク様…」
どうして貴方がここに?
元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

【完結】俺のセフレが幼なじみなんですが?
おもち
恋愛
アプリで知り合った女の子。初対面の彼女は予想より断然可愛かった。事前に取り決めていたとおり、2人は恋愛NGの都合の良い関係(セフレ)になる。何回か関係を続け、ある日、彼女の家まで送ると……、その家は、見覚えのある家だった。
『え、ここ、幼馴染の家なんだけど……?』
※他サイトでも投稿しています。2サイト計60万PV作品です。
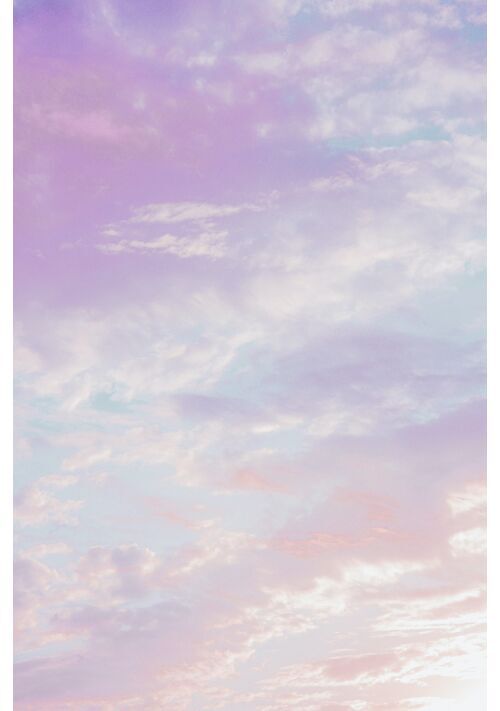
極道に大切に飼われた、お姫様
真木
恋愛
珈涼は父の組のため、生粋の極道、月岡に大切に飼われるようにして暮らすことになる。憧れていた月岡に甲斐甲斐しく世話を焼かれるのも、教え込まれるように夜ごと結ばれるのも、珈涼はただ恐ろしくて殻にこもっていく。繊細で怖がりな少女と、愛情の伝え方が下手な極道の、すれ違いラブストーリー。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















