14 / 31
第二部
《スサノオ》(5)
しおりを挟む
タマモを送った祭礼の一団が黄泉比良坂をおり、出雲の町へと帰っていく。その表情はいずれも憂欝に沈み込み、女官のなかには泣きじゃくってひとりでは歩けず、他の女官に支えられてようやく歩いているものもいた。
その有様を近くの茂みのなかからシュランドとカグヤが眺めていた。
「……あの人たちもつらいのね」
カグヤが同情するように言った。
だが、シュランドは吐き捨てた。
「ふん、最低の卑怯者だよ。女の子ひとり生け贄にして自分たちだけ逃げ帰るなんて」
少年の怒りには容赦がない。
「さあ、行こう。カグヤ。おれたちの手でタマモ姫を助けるんだ」
「ええ」
「まず、確認しておこう」
山道をのぼりながらシュランドが言った。
「おれたちの目的はタマモ姫を助けだして一緒に逃げることだ。戦うことじゃない。だから、なるべくこっそり行くべきだ。できれば、誰にも見つからずにタマモ姫のいるところまでたどり着きたい」
「ええ」
「だから、もし、見つかったら逃げることを一番に考えよう。いったん逃げて、相手をまいて、それからまた進むんだ」
「わかったわ」
「もちろん、タマモ姫の居場所なんてわからないけど、でも、大勢の人間が行き来したおかげで足跡がはっきり残っている。これだけ残っていれば迷うことなんてない」
シュランドはきっぱりと言った。彼は村にいた頃、森のなかに狩りに出かけ、獣の足跡を手がかりに追跡し、ついに仕留めたことが何度もあった。
「足跡をたどっていけば確実にタマモ姫のいるとに着ける。何の心配もないよ」
「ええ、そうね。シュランド」
先に立ってまっすぐに前を見据えて歩くシュランドには見えなかったが、返事を返すカグヤの口もとは微笑ましそうにほころんでいた。
実のところ、シュランドの言っていることはカグヤにとっても百も承知のことばかりだった。カグヤにしても世間知らずのお姫さまなどではない。たったひとりで旅をして、そして、生き残ってきたのだ。美しい少女が雨風や、獣や、おとなたちの欲望から無事に逃れるのはなまなかなことではない。そのなかで培った経験、技量は、シュランドにまさるものでありこそすれ、劣るものではない。
だが、カグヤはあえて出しゃばらなかった。自分を先導し、守ろうとする少年の気負いは彼女にとって不愉快なものではなかった。
ふたりは黄泉比良坂を登っていった。そこはとてもかぐわしい場所だった。花々が咲き乱れ、木の実がなり、小鳥のさえずりが聞こえる。空気のなかには果物の甘い香が満ちていて、嗅いでいるだけで幸せな気分になれるほど。
気温は暑くもなく、寒くもなく、湿度もちょうどいい。それだけではなく、なにか人の心をくつろがせるものが山全体に満ちているような気がする。『安息』という言葉はこの山にためにあるのではないかと思わせるほど。こうして登っていながら気を緩めればついついうたた寝をしてしまうのではないか。そう思えるほどに心地よい場所だった。
この世界には動物同士の殺しあいさえないのではないか。シュランドは半ば本気でそう思った。こんな素敵な場所で血が流れることがあるなんてとても信じられない。理想郷を見出だしたような気さえした。
足跡は右にそれ、いったんくだり、そこからまた登りになった。その先は大きな洞窟のなかにつづいていた。
「あの洞窟のなかみたいだな」と、シュランド。
「……奥深い山の洞窟の向こう、そこは神の住まう異なる世界」
ふいに、カグヤが巫女めいた不思議な口調で言った。
「えっ?」
シュランドがいぶかしそうに少女を見た。カグヤは肩をすくめた。
「民話ではよくそういうことになっているの。山に開いた洞窟の向こうは神さまの世界なのよ」
「……つまり、生け贄を捧げるにはぴったりの場所ってことか」
「そうね」
「じゃあ、タマモ姫は洞窟を抜けた先にいるんだな。よし、もう少しだ」
シュランドは一歩を踏み出そうとした。寸前で立ちどまり、カグヤを見た。
「……後悔しないかい? いのならまだ引き返せる。あの洞窟を越えたらどうなるかわからない。もしかしたら、二度と帰れないかも……」
カグヤは自分を気づかう少年の言葉に微笑みを返した。
「ここで引き返すぐらいなら最初からこないわ。いまさら気を使わないで」
この期におよんでなお、笑顔で語れるカグヤの勇気は大変なものだ。シュランドはすっかりうれしくなった。
「よし、行こう!」
「ええ」
ふたりは笑顔でうなずきあうと、洞窟のなかに入っていった。
洞窟のなかにはかすかな霧が立ちこめていた。霧はほのかな熱を含んでいて肌にじっとりとまとわりついた。
先に進むとだんだん気温が高くなってきた。ふたりは霧だけではなく、汗にも身を濡らしはじめた。
「暑くなってきたね」
シュランドが額をぬぐいながら言った。ぬぐう手のほうも汗と霧でべっとりぬれているので大して意味はない。
「温泉でもあるみたいね」
カグヤが言った。
「かすかに硫黄の匂いがするわ」
やがて、洞窟を出た。ふたりはそこに広がる光景を見て驚きの声をあげた。
洞窟を出た先。そこは天をつくような巨大な植物が繁茂する異様な世界だった。
熱を帯びた霧が立ちこめ、少し向こうは乳白色に染まってなにも見えない。その間を人の胴体よりも太い緑の植物が何本もなんぼんも立ち並んでいる。
カグヤはそっと植物にふれてみた。
「これ、木じゃないわ。ツルよ」
カグヤの言うとおり、その巨大な植物は樹木ではなく、太いツル植物が何本も絡みあったものだった。
「こんな大きなツル植物、見たこともないわ」
「ここはたしかに異世界っていうわけだ」
「そうね」
シュランドの言葉にカグヤもうなずいた。
「それにしてもこんな霧じゃろくに見えないわ。足跡はわかる?」
「う~ん」
シュランドは目をこらして地面を見た。足元まで霧が覆っているため、すぐ下の地面すらよく見えない。だが、その分、地面も湿度を含んでいてやわらかいので足跡は外よりくっきりと残っていた。目を地面に近づけてよく見れば見失う心配はない。
「よし。だいじょうぶだ。行こう」
「まって」
カグヤは言うと、腰紐をほどきはじめた。
なにをする気なのかと驚くシュランドを横目に、カグヤは紐の一端をシュランドに手渡した。
「この霧でははぐれたら見つからないわ。手をつないでいきましょう」
「ああ、そうか」
シュランドはうなずいた。カグヤの注意深さ、冷静さに感心した。
ふたりは手と手を紐で結び、四つんばいになるようにして足跡をたどりはじめた。
しばらく行ったとき、不吉な音がした。やわらかい地面から重いものを力任せに引きぬくときの音。それがいくつもいくつもつづいている。音は近づきつつあった。
シュランドとカグヤは顔を見合わせた。音のする方を見た。霧に閉ざされたその向こう。白い霧をつらぬいて、闇夜に浮かびあがる幽鬼のようにそれは姿を現わした。
うつろな風洞のような窪んだ目。
千年を経た古紙を思わせる、黄ばんでかさかさになった皮膚。
それでいて、どんな人間の勇者も及ばないような盛りあがった筋肉。
吸血の怪物。
尸解仙。
ふたりは息を呑んだ。
尸解仙の群れがふたりめがけてゆっくりと、しかし、着実に近づきつつあった。多い。二十体以上はいる。
「逃げろ!」
シュランドは叫んだ。カグヤの手をとって走り出そうとした。だが、逃げようとしたその先にも尸解仙の群れが壁をなして迫りつつあった。シュランドは再び向きをかえた。そこにも尸解仙がいた。シュランドは必死に頭をめぐらせた。だが、どこを見ても尸解仙のおぞましい姿があった。いつの間にかすっかり囲まれてしまっていたのだ。
「シュランド、あそこ!」
カグヤが指差して叫んだ。
「あそこに隙間があるわ」
「そうか。よし!」
シュランドはカグヤの手をとって全力で走った。尸解仙と尸解仙のわずかな隙間。勢いをつけてそこを強引に突破する。
尸解仙は屈強であり、怪力ではあるが、動きはにぶい。崖を転がる兎のような勢いで走ってきた少年と少女の動きに反応しきれず、ふたりが突破するのを許した。
だが、あきらめることを知らないのもまた尸解仙だった。その古くてぼろぼろになった紙のような頭皮のなかにおさめられた脳髄には血を吸うことしかないかのようだった。尸解仙たちは緩慢に向きをかえるとふたりの獲物めがけてゆっくりと歩き出した。
シュランドとカグヤは必死に走った。心臓がばくばく鳴っていたがかまわなかった。立ちどまれば殺される。ふたりともそのことは承知していた。だから、心臓が破裂するまで走りつづけるつもりだった。
だが、後ろからは尸解仙の群れが着実に追ってきている。
振りきれない。
本来なら……固い地面と開けた視界をもつ草原ででもあれば、ふたりが尸解仙に追いつかれることはありえない。余裕で逃げ切れる。だが、ここは草原ではなかった。深い霧と、巨大なツル植物とに覆われた、泥のようにやわらかい土で占められた湿地だった。
走ろうと力を込めれば込めるほど足は深くめりこみ、引き抜くのに時間がかかる。ツル植物が行く手をさえぎり、真っすく走ることもできない。細かく向きをかえざるをえず、どんなに必死になっても歩くよりのろい速度でしか移動できない。
ツル植物にのぼることも考えた。だが、表面がつるつるして手がかりがないうえに霧で濡れている。つかんでもつかんでもすべってしまい、とてものぼれたものではない。悪戦苦闘しているうちに尸解仙に追いつかれ、捕まってしまう。とにかく、走って逃げるしかなかった。
どれだけ走ったろう。突然、シュランドはなにかにぶつかった。目を見張った。目の前には巨大な壁があった。思わず見上げる。壁はどこまでもつづいていた。その様にシュランドの心を絶望が覆った。霧のせいでわからなかったが、ここは無限に広がる空の下ではなかった。巨大な洞窟のなかだったのだ。
どんなに広くても洞窟は洞窟。洞窟である以上、かならず壁にぶちあたる。逃げつづけることはできないのだ。
後ろからは尸解仙の群れが迫ってくる。ふたりにはもう、走って逃げるだけの気力も残ってはいなかった。
「ここまでみたいね」
カグヤが呟いた。その声には恐れも、恐怖もなかった。あきらめたがゆえの冷静な声だった。
その事実がシュランドを打ちのめした。これはすべておれのせいだ。おれが自分の無力さもわきまえずに無茶をしたから、彼女まで死なせるはめになってしまった。なんて馬鹿
だったんだろう。タマモ姫だけではなく、カグヤまで死なせてしまうなんて。彼女がなんと言おうと、たとえ殴り倒してでもひとりでくるべきだった。そうしていれば少なくともカグヤだけは生き残れたのに……。
「ごめん、カグヤ」
シュランドは言った。
「君の記憶を取り戻してあげるって言ったのに、こんなことに巻き込んじゃって。おれと出会ったばかりにこんなところで……」
「何を言ってるの」
カグヤは笑いながら答えた。絶対の死を前にしてなお、カグヤは微笑みを絶やすことはなかった。
「わたしは自分の意志できたのよ。たとえ、あなたと会わずにひとりで出雲の町を訪れていたとしても同じことをしていたわ。あなたが気にする必要なんてないわ」
「……カグヤ」
少女の言葉が本心か、それとも自分を慰めようとしてのものなのか、シュランドには判断がつかなかった。
カグヤはつづけた。
「あんな健気なお姫さまを見捨てて自分だけ逃げ出したんじゃ後味が悪いものね。やるべきことをやったんだから満足よ。それに……」
カグヤはシュランドを見て照れくさそうに笑った。
「短い間だったけど、あなたに会えて楽しかった」
「……カグヤ」
少女の言葉が少年の心に再び火をつけた。シュランドは薪割り用の小さな斧を両手で握りしめた。絶対、死なせない。そう決意した。カグヤを死なせたりするもんか。おれはどうなっても、彼女だけは絶対、逃がして見せる!
「あきらめるな! まだ機会はある。もう一度やつらの間を突破して、入ってきた洞窟に戻るんだ。そうすればなんとかなる」
「……ええ。そうね」
カグヤは微笑とともにうなずいた。
彼女にはわかっていた。それは不可能だということが。先ほととはちがう。尸解仙の作る壁は厚く、隙間はない。突撃したとしてもその肉の壁にはばまれ、捕まえられるだけ。かりに突破できたとしてもこの霧のなかで洞窟の出口に戻るのは不可能だろう。迷っているうちに結局、捕まってしまう。
だが、カグヤはそのことを口にはしなかった。彼女にはわかっていた。自分だけはなんとしても逃がそうと決意している少年の心が。彼は最後まで決してあきらめはしないだろう。自分のためではなく、わたしのために。それならわたしも最後まで彼の決意に応えよう。彼と付き合ってあらがおう。そう決心していた。
カグヤは自分の短刀を握りしめた。
「付き合うわ、シュランド」
自分の決意を短い言葉に込めた。
「よし……」
シュランドはうなずいた。自分の決意に少年が気づいたかどうか、カグヤにはわからなかった。多分、気づいていないだろう。でも、それでいい。ずっとひとりで旅をしてきて、やっとできた仲間だもの。彼はわたしの記憶を取り戻してくれると言った。そんなことを言ってくれたのは彼ひとり。その彼の思いに殉じることができるのなら悔いはない。
尸解仙の群れがゆっくりと近づきつつあった。シュランドはカグヤにささやいた。
「もう少し近づいたら一気に駆け抜ける。おれの合図で走り出すんだ。振り向かずに、他のことはなにも気にせずに。いいね?」
「ええ」
尸解仙の群れが近づいてくる。シュランドは息を整えた。
「……よし」
小さくつぶやいた。合図を出そうとした。
そして、風が舞った。
その有様を近くの茂みのなかからシュランドとカグヤが眺めていた。
「……あの人たちもつらいのね」
カグヤが同情するように言った。
だが、シュランドは吐き捨てた。
「ふん、最低の卑怯者だよ。女の子ひとり生け贄にして自分たちだけ逃げ帰るなんて」
少年の怒りには容赦がない。
「さあ、行こう。カグヤ。おれたちの手でタマモ姫を助けるんだ」
「ええ」
「まず、確認しておこう」
山道をのぼりながらシュランドが言った。
「おれたちの目的はタマモ姫を助けだして一緒に逃げることだ。戦うことじゃない。だから、なるべくこっそり行くべきだ。できれば、誰にも見つからずにタマモ姫のいるところまでたどり着きたい」
「ええ」
「だから、もし、見つかったら逃げることを一番に考えよう。いったん逃げて、相手をまいて、それからまた進むんだ」
「わかったわ」
「もちろん、タマモ姫の居場所なんてわからないけど、でも、大勢の人間が行き来したおかげで足跡がはっきり残っている。これだけ残っていれば迷うことなんてない」
シュランドはきっぱりと言った。彼は村にいた頃、森のなかに狩りに出かけ、獣の足跡を手がかりに追跡し、ついに仕留めたことが何度もあった。
「足跡をたどっていけば確実にタマモ姫のいるとに着ける。何の心配もないよ」
「ええ、そうね。シュランド」
先に立ってまっすぐに前を見据えて歩くシュランドには見えなかったが、返事を返すカグヤの口もとは微笑ましそうにほころんでいた。
実のところ、シュランドの言っていることはカグヤにとっても百も承知のことばかりだった。カグヤにしても世間知らずのお姫さまなどではない。たったひとりで旅をして、そして、生き残ってきたのだ。美しい少女が雨風や、獣や、おとなたちの欲望から無事に逃れるのはなまなかなことではない。そのなかで培った経験、技量は、シュランドにまさるものでありこそすれ、劣るものではない。
だが、カグヤはあえて出しゃばらなかった。自分を先導し、守ろうとする少年の気負いは彼女にとって不愉快なものではなかった。
ふたりは黄泉比良坂を登っていった。そこはとてもかぐわしい場所だった。花々が咲き乱れ、木の実がなり、小鳥のさえずりが聞こえる。空気のなかには果物の甘い香が満ちていて、嗅いでいるだけで幸せな気分になれるほど。
気温は暑くもなく、寒くもなく、湿度もちょうどいい。それだけではなく、なにか人の心をくつろがせるものが山全体に満ちているような気がする。『安息』という言葉はこの山にためにあるのではないかと思わせるほど。こうして登っていながら気を緩めればついついうたた寝をしてしまうのではないか。そう思えるほどに心地よい場所だった。
この世界には動物同士の殺しあいさえないのではないか。シュランドは半ば本気でそう思った。こんな素敵な場所で血が流れることがあるなんてとても信じられない。理想郷を見出だしたような気さえした。
足跡は右にそれ、いったんくだり、そこからまた登りになった。その先は大きな洞窟のなかにつづいていた。
「あの洞窟のなかみたいだな」と、シュランド。
「……奥深い山の洞窟の向こう、そこは神の住まう異なる世界」
ふいに、カグヤが巫女めいた不思議な口調で言った。
「えっ?」
シュランドがいぶかしそうに少女を見た。カグヤは肩をすくめた。
「民話ではよくそういうことになっているの。山に開いた洞窟の向こうは神さまの世界なのよ」
「……つまり、生け贄を捧げるにはぴったりの場所ってことか」
「そうね」
「じゃあ、タマモ姫は洞窟を抜けた先にいるんだな。よし、もう少しだ」
シュランドは一歩を踏み出そうとした。寸前で立ちどまり、カグヤを見た。
「……後悔しないかい? いのならまだ引き返せる。あの洞窟を越えたらどうなるかわからない。もしかしたら、二度と帰れないかも……」
カグヤは自分を気づかう少年の言葉に微笑みを返した。
「ここで引き返すぐらいなら最初からこないわ。いまさら気を使わないで」
この期におよんでなお、笑顔で語れるカグヤの勇気は大変なものだ。シュランドはすっかりうれしくなった。
「よし、行こう!」
「ええ」
ふたりは笑顔でうなずきあうと、洞窟のなかに入っていった。
洞窟のなかにはかすかな霧が立ちこめていた。霧はほのかな熱を含んでいて肌にじっとりとまとわりついた。
先に進むとだんだん気温が高くなってきた。ふたりは霧だけではなく、汗にも身を濡らしはじめた。
「暑くなってきたね」
シュランドが額をぬぐいながら言った。ぬぐう手のほうも汗と霧でべっとりぬれているので大して意味はない。
「温泉でもあるみたいね」
カグヤが言った。
「かすかに硫黄の匂いがするわ」
やがて、洞窟を出た。ふたりはそこに広がる光景を見て驚きの声をあげた。
洞窟を出た先。そこは天をつくような巨大な植物が繁茂する異様な世界だった。
熱を帯びた霧が立ちこめ、少し向こうは乳白色に染まってなにも見えない。その間を人の胴体よりも太い緑の植物が何本もなんぼんも立ち並んでいる。
カグヤはそっと植物にふれてみた。
「これ、木じゃないわ。ツルよ」
カグヤの言うとおり、その巨大な植物は樹木ではなく、太いツル植物が何本も絡みあったものだった。
「こんな大きなツル植物、見たこともないわ」
「ここはたしかに異世界っていうわけだ」
「そうね」
シュランドの言葉にカグヤもうなずいた。
「それにしてもこんな霧じゃろくに見えないわ。足跡はわかる?」
「う~ん」
シュランドは目をこらして地面を見た。足元まで霧が覆っているため、すぐ下の地面すらよく見えない。だが、その分、地面も湿度を含んでいてやわらかいので足跡は外よりくっきりと残っていた。目を地面に近づけてよく見れば見失う心配はない。
「よし。だいじょうぶだ。行こう」
「まって」
カグヤは言うと、腰紐をほどきはじめた。
なにをする気なのかと驚くシュランドを横目に、カグヤは紐の一端をシュランドに手渡した。
「この霧でははぐれたら見つからないわ。手をつないでいきましょう」
「ああ、そうか」
シュランドはうなずいた。カグヤの注意深さ、冷静さに感心した。
ふたりは手と手を紐で結び、四つんばいになるようにして足跡をたどりはじめた。
しばらく行ったとき、不吉な音がした。やわらかい地面から重いものを力任せに引きぬくときの音。それがいくつもいくつもつづいている。音は近づきつつあった。
シュランドとカグヤは顔を見合わせた。音のする方を見た。霧に閉ざされたその向こう。白い霧をつらぬいて、闇夜に浮かびあがる幽鬼のようにそれは姿を現わした。
うつろな風洞のような窪んだ目。
千年を経た古紙を思わせる、黄ばんでかさかさになった皮膚。
それでいて、どんな人間の勇者も及ばないような盛りあがった筋肉。
吸血の怪物。
尸解仙。
ふたりは息を呑んだ。
尸解仙の群れがふたりめがけてゆっくりと、しかし、着実に近づきつつあった。多い。二十体以上はいる。
「逃げろ!」
シュランドは叫んだ。カグヤの手をとって走り出そうとした。だが、逃げようとしたその先にも尸解仙の群れが壁をなして迫りつつあった。シュランドは再び向きをかえた。そこにも尸解仙がいた。シュランドは必死に頭をめぐらせた。だが、どこを見ても尸解仙のおぞましい姿があった。いつの間にかすっかり囲まれてしまっていたのだ。
「シュランド、あそこ!」
カグヤが指差して叫んだ。
「あそこに隙間があるわ」
「そうか。よし!」
シュランドはカグヤの手をとって全力で走った。尸解仙と尸解仙のわずかな隙間。勢いをつけてそこを強引に突破する。
尸解仙は屈強であり、怪力ではあるが、動きはにぶい。崖を転がる兎のような勢いで走ってきた少年と少女の動きに反応しきれず、ふたりが突破するのを許した。
だが、あきらめることを知らないのもまた尸解仙だった。その古くてぼろぼろになった紙のような頭皮のなかにおさめられた脳髄には血を吸うことしかないかのようだった。尸解仙たちは緩慢に向きをかえるとふたりの獲物めがけてゆっくりと歩き出した。
シュランドとカグヤは必死に走った。心臓がばくばく鳴っていたがかまわなかった。立ちどまれば殺される。ふたりともそのことは承知していた。だから、心臓が破裂するまで走りつづけるつもりだった。
だが、後ろからは尸解仙の群れが着実に追ってきている。
振りきれない。
本来なら……固い地面と開けた視界をもつ草原ででもあれば、ふたりが尸解仙に追いつかれることはありえない。余裕で逃げ切れる。だが、ここは草原ではなかった。深い霧と、巨大なツル植物とに覆われた、泥のようにやわらかい土で占められた湿地だった。
走ろうと力を込めれば込めるほど足は深くめりこみ、引き抜くのに時間がかかる。ツル植物が行く手をさえぎり、真っすく走ることもできない。細かく向きをかえざるをえず、どんなに必死になっても歩くよりのろい速度でしか移動できない。
ツル植物にのぼることも考えた。だが、表面がつるつるして手がかりがないうえに霧で濡れている。つかんでもつかんでもすべってしまい、とてものぼれたものではない。悪戦苦闘しているうちに尸解仙に追いつかれ、捕まってしまう。とにかく、走って逃げるしかなかった。
どれだけ走ったろう。突然、シュランドはなにかにぶつかった。目を見張った。目の前には巨大な壁があった。思わず見上げる。壁はどこまでもつづいていた。その様にシュランドの心を絶望が覆った。霧のせいでわからなかったが、ここは無限に広がる空の下ではなかった。巨大な洞窟のなかだったのだ。
どんなに広くても洞窟は洞窟。洞窟である以上、かならず壁にぶちあたる。逃げつづけることはできないのだ。
後ろからは尸解仙の群れが迫ってくる。ふたりにはもう、走って逃げるだけの気力も残ってはいなかった。
「ここまでみたいね」
カグヤが呟いた。その声には恐れも、恐怖もなかった。あきらめたがゆえの冷静な声だった。
その事実がシュランドを打ちのめした。これはすべておれのせいだ。おれが自分の無力さもわきまえずに無茶をしたから、彼女まで死なせるはめになってしまった。なんて馬鹿
だったんだろう。タマモ姫だけではなく、カグヤまで死なせてしまうなんて。彼女がなんと言おうと、たとえ殴り倒してでもひとりでくるべきだった。そうしていれば少なくともカグヤだけは生き残れたのに……。
「ごめん、カグヤ」
シュランドは言った。
「君の記憶を取り戻してあげるって言ったのに、こんなことに巻き込んじゃって。おれと出会ったばかりにこんなところで……」
「何を言ってるの」
カグヤは笑いながら答えた。絶対の死を前にしてなお、カグヤは微笑みを絶やすことはなかった。
「わたしは自分の意志できたのよ。たとえ、あなたと会わずにひとりで出雲の町を訪れていたとしても同じことをしていたわ。あなたが気にする必要なんてないわ」
「……カグヤ」
少女の言葉が本心か、それとも自分を慰めようとしてのものなのか、シュランドには判断がつかなかった。
カグヤはつづけた。
「あんな健気なお姫さまを見捨てて自分だけ逃げ出したんじゃ後味が悪いものね。やるべきことをやったんだから満足よ。それに……」
カグヤはシュランドを見て照れくさそうに笑った。
「短い間だったけど、あなたに会えて楽しかった」
「……カグヤ」
少女の言葉が少年の心に再び火をつけた。シュランドは薪割り用の小さな斧を両手で握りしめた。絶対、死なせない。そう決意した。カグヤを死なせたりするもんか。おれはどうなっても、彼女だけは絶対、逃がして見せる!
「あきらめるな! まだ機会はある。もう一度やつらの間を突破して、入ってきた洞窟に戻るんだ。そうすればなんとかなる」
「……ええ。そうね」
カグヤは微笑とともにうなずいた。
彼女にはわかっていた。それは不可能だということが。先ほととはちがう。尸解仙の作る壁は厚く、隙間はない。突撃したとしてもその肉の壁にはばまれ、捕まえられるだけ。かりに突破できたとしてもこの霧のなかで洞窟の出口に戻るのは不可能だろう。迷っているうちに結局、捕まってしまう。
だが、カグヤはそのことを口にはしなかった。彼女にはわかっていた。自分だけはなんとしても逃がそうと決意している少年の心が。彼は最後まで決してあきらめはしないだろう。自分のためではなく、わたしのために。それならわたしも最後まで彼の決意に応えよう。彼と付き合ってあらがおう。そう決心していた。
カグヤは自分の短刀を握りしめた。
「付き合うわ、シュランド」
自分の決意を短い言葉に込めた。
「よし……」
シュランドはうなずいた。自分の決意に少年が気づいたかどうか、カグヤにはわからなかった。多分、気づいていないだろう。でも、それでいい。ずっとひとりで旅をしてきて、やっとできた仲間だもの。彼はわたしの記憶を取り戻してくれると言った。そんなことを言ってくれたのは彼ひとり。その彼の思いに殉じることができるのなら悔いはない。
尸解仙の群れがゆっくりと近づきつつあった。シュランドはカグヤにささやいた。
「もう少し近づいたら一気に駆け抜ける。おれの合図で走り出すんだ。振り向かずに、他のことはなにも気にせずに。いいね?」
「ええ」
尸解仙の群れが近づいてくる。シュランドは息を整えた。
「……よし」
小さくつぶやいた。合図を出そうとした。
そして、風が舞った。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく


CREATED WORLD
猫手水晶
SF
惑星アケラは、大気汚染や森林伐採により、いずれ人類が住み続けることができなくなってしまう事がわかった。
惑星アケラに住む人類は絶滅を免れる為に、安全に生活を送れる場所を探す事が必要となった。
宇宙に人間が住める惑星を探そうという提案もあったが、惑星アケラの周りに人が住めるような環境の星はなく、見つける前に人類が絶滅してしまうだろうという理由で、現実性に欠けるものだった。
「人間が住めるような場所を自分で作ろう」という提案もあったが、資材や重力の方向の問題により、それも現実性に欠ける。
そこで科学者は「自分達で世界を構築するのなら、世界をそのまま宇宙に作るのではなく、自分達で『宇宙』にあたる空間を新たに作り出し、その空間で人間が生活できるようにすれば良いのではないか。」と。

日本列島、時震により転移す!
黄昏人
ファンタジー
2023年(現在)、日本列島が後に時震と呼ばれる現象により、500年以上の時を超え1492年(過去)の世界に転移した。移転したのは本州、四国、九州とその周辺の島々であり、現在の日本は過去の時代に飛ばされ、過去の日本は現在の世界に飛ばされた。飛ばされた現在の日本はその文明を支え、国民を食わせるためには早急に莫大な資源と食料が必要である。過去の日本は現在の世界を意識できないが、取り残された北海道と沖縄は国富の大部分を失い、戦国日本を抱え途方にくれる。人々は、政府は何を思いどうふるまうのか。
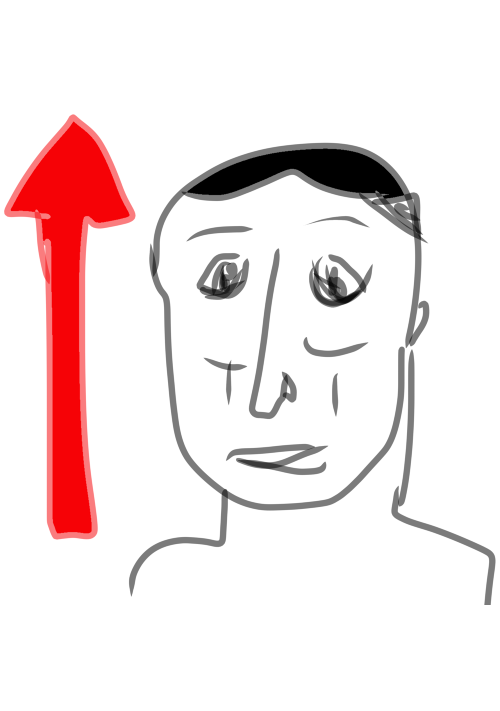
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

💚催眠ハーレムとの日常 - マインドコントロールされた女性たちとの日常生活
XD
恋愛
誰からも拒絶される内気で不細工な少年エドクは、人の心を操り、催眠術と精神支配下に置く不思議な能力を手に入れる。彼はこの力を使って、夢の中でずっと欲しかったもの、彼がずっと愛してきた美しい女性たちのHAREMを作り上げる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















