8 / 31
第一部
《すべての鬼の母》(5)
しおりを挟む
翌日から盗賊たちはさっそく陰陽寮の発掘に乗り出した。さすがに宝探しの専門家。瞬く間に跡地を見付け、総出で塵の山を掘り返しはじめた。町の作りを知るシュランドの案内があったとはいえ、その手際のよさは見事なものだった。とくに塵の山を掘り返す速度はすごかった。組を組んでよどみなく運びだし、とりのぞいていく。シュランドひとりであったら一月かかってもここまで掘り出せたかどうか。
――ろくでもない盗賊集団だが利用価値はあるわけか。
シュランドは胸のうちで『フン』とばかりに呟いた。
陰陽寮の規模は想像以上に巨大なものだった。最も短い一辺でもゆうに千尺を越える長方形の基部。この建物だけで小さな村がすっぽり入るほどの規模がある。まわりを一巡りするだけで結構な時間がかかりそうだ。そして、建物のいちばん奥、最奥の床に巨大な扉があった。人の背丈の二十倍もある。表面には細緻な装飾が施され、扉全体を飾り立てている。その装飾の繊細さ、美しさといい、建物が瓦礫の山と化したというのに傷ひとつついていないその姿といい、人の手で作られたものとはとうてい信じられない。
悪魔の手を借りたのではないか。
そう思ってしまう扉だった。
――この向こうに……。
シュランドは思う。
――この向こうにすべての答えがある。なぜ、親父が、いや、ヤシャビトが人類を裏切ったのか。その答えが。
ゾクゾクした。
体が震えていた。
恐いのではない。
武者震いだ。
そう思い込もうとした。
「……行こう」
心臓を早鐘のように鳴らせたままシュランドは言った。一歩を踏み出した。その肩を分厚い手がつかんで止めた。ハヤトだった。シュランドはハヤトを見上げた。ハヤトは重々しく言った。
「いまはここまでだ」
「なに?」
「この扉を開けるのはまた今度だ」
「どういうことだ⁉あんただって答えを知りたいんだろう⁉ なのに、いまさら臆病風に吹かれたのか⁉」
「あわてるなって言ってんだよ」
それがハヤトの答えだった。
「お宝探しに関しちゃあ、おれの方がずっと上手なんだ。いいか、小僧。お宝を手にするコツはな。あわてないこった。そいつが貴重な秘宝であればあるほど、あわてて手に入れようとすると呪いがかかる。だから、時間をおく。そうすることで呪いが祝福にかわるのさ」
そこまで言うと部下たちに振り返った。
「おい、野郎ども! 今日はここまでだ。明日のお宝との対面に備えて今夜はぱあっといくぞっ!」
頭の叫びに男たちの歓声が響いた。
……盗賊たちの祭りが行なわれている。そのなかでシュランドはひとり、巨大な扉の前にたたずんでいた。
「……ひとりで行く気なの?」
静かな声がした。
シュランドは振り向かなかった。それが誰かはわかっている。
カグヤだ。
カグヤが漆黒の長い髪を篝火の炎に照らしだし、そこに立っているのだ。
なぜ、彼女がここにいるのか、聞く気にもならなかった。それは正しいことだ。そんな気がした。彼女がいま、自分のそばにいるのは当たり前のことなのだと。
シュランドはうなずいた。
「ああ、そうだ。おれはこの先にいかなきゃいけないんだ。もう一秒だってまっていられない。あいつらがその気になるのをまってなんかいられない」
「どうしてそこまで?」
「それは、おれが……」
「あなたが?」
「ヤシャビトの息子だからだ」
その言葉にカグヤは美しい眉をひそめた。
「ヤシャビト?」
「そうだ。知っているだろう? 陰陽の司でありながら《すさまじきもの》とともに高天原を攻め、滅ぼした人類の裏切り者。そのヤシャビトがおれの父親なんだ。
だから、おれはその息子として父親の罪を償わなくちゃならない。そのために……」
シュランドは巨大な扉を両手で殴り付けた。
「そのために力がいる! この奥にこそその力があるはずなんだ。《すさまじきもの》を倒せる力が。おれはその力を手に入れる。そして、《すさまじきもの》を倒し、高天原を再興させ、みんなが安心して暮らせる世界を取り戻すんだ」
シュランドはカグヤに向き直った。真っすぐに見つめた。
「一緒に……きてくれるかい?」
「えっ?」
「君に一緒にきてほしいんだ。君がいてくれればおれはきっとやり遂げられる。だから、頼む。おれと一緒にきてくれ」
生まれてはじめて――。
シュランドは心から頭をさげていた。
コクン、とカグヤの頭が上下に揺れた。
「わかったわ」
「えっ?」
「わたしはあなたに従う。あなたのその目的に」
「ありがとう、カグヤ!」
シュランドは破顔した。全身で喜びを爆発させた。
「君さえいてくれればおれは無敵だ! ハヤトだって、《すさまじきもの》だって相手じゃない。必ずやり遂げられる。さあ、行こう。世界を人間の手に取り戻しに」
「ええ」
シュランドの意気込みにカグヤはやさしい微笑みで答えた。
シュランドは扉に近付いた。扉の前に手をかざした。ただそれだけで扉は音もなく開いた。あまりに簡単に開いたのでシュランドは呆気にとられた。これだけ巨大な扉だ。開けるのには苦労すると覚悟していた。いざとなったらぶん殴り、穴を開け、むりやりこじ開けるつもりだったのだ。それなのにあまりにあっけなく開いてしまったものだから肩透かしを食らわされた気分だった。
「こんな大きな扉が音もなく開くなんて……どういう仕組みなんだ?」
「あなたが陰陽師の血統だから?」
「わからない。でも、なんでもいい。とにかく扉は開いたんだ。これで先に進める。さあ、行こう」
「ええ」
ふたりは扉をくぐった。その先には地下へくだる階段がつづいていた。不思議なことに――。
階段を包む壁は淡い光に満たされていた。
「不思議な壁ね。スベスベしていて柔らかいようでもあり、硬いようでもあり……」
「ああ。こんな壁は他に見たことがない。この高天原でもこの陰陽寮だけだったはずだ」
ふたりは並んで階段をくだりはじめた。
ふたりはひたすら下へしたへとくだって行った。もうずいぶん降りたはずだが、壁全体が淡く光っているおかげで地下深くに降りてきたという実感はまるでない。地上を歩いているのとほとんどかわりない雰囲気だった。
やがて、階段がつきた。降りきったそこは不思議な場所だった。そこは平原。見渡すかぎり、床も、壁も、天井も、すべて銅の鏡のようにスベスベとしてでこぼこひとつない材質で覆われていた。そのすべてが淡い輝きを放っている。
「不思議な場所」
カグヤが陶酔したような口調で言った。シュランドもうなずいた。ここにはたしかに人を酔わせるようななにかがあった。
「……人間か」
いきなり、第三の声がした。地の底から響いてくるかのような重々しい声。
ふたりはぎょっとして顔をあげた。なぜ、いままで気が付かなかったのか。平原の向こう、いちばん奥にそれはいた。
見上げるばかりの巨大な体。長くたくましい首。巨大な翼。四本の足をたたんで座り込んでいる。
ドラゴン。
そう。伝説のドラゴンそのままの姿の生物がそこにいたのだ。
――ろくでもない盗賊集団だが利用価値はあるわけか。
シュランドは胸のうちで『フン』とばかりに呟いた。
陰陽寮の規模は想像以上に巨大なものだった。最も短い一辺でもゆうに千尺を越える長方形の基部。この建物だけで小さな村がすっぽり入るほどの規模がある。まわりを一巡りするだけで結構な時間がかかりそうだ。そして、建物のいちばん奥、最奥の床に巨大な扉があった。人の背丈の二十倍もある。表面には細緻な装飾が施され、扉全体を飾り立てている。その装飾の繊細さ、美しさといい、建物が瓦礫の山と化したというのに傷ひとつついていないその姿といい、人の手で作られたものとはとうてい信じられない。
悪魔の手を借りたのではないか。
そう思ってしまう扉だった。
――この向こうに……。
シュランドは思う。
――この向こうにすべての答えがある。なぜ、親父が、いや、ヤシャビトが人類を裏切ったのか。その答えが。
ゾクゾクした。
体が震えていた。
恐いのではない。
武者震いだ。
そう思い込もうとした。
「……行こう」
心臓を早鐘のように鳴らせたままシュランドは言った。一歩を踏み出した。その肩を分厚い手がつかんで止めた。ハヤトだった。シュランドはハヤトを見上げた。ハヤトは重々しく言った。
「いまはここまでだ」
「なに?」
「この扉を開けるのはまた今度だ」
「どういうことだ⁉あんただって答えを知りたいんだろう⁉ なのに、いまさら臆病風に吹かれたのか⁉」
「あわてるなって言ってんだよ」
それがハヤトの答えだった。
「お宝探しに関しちゃあ、おれの方がずっと上手なんだ。いいか、小僧。お宝を手にするコツはな。あわてないこった。そいつが貴重な秘宝であればあるほど、あわてて手に入れようとすると呪いがかかる。だから、時間をおく。そうすることで呪いが祝福にかわるのさ」
そこまで言うと部下たちに振り返った。
「おい、野郎ども! 今日はここまでだ。明日のお宝との対面に備えて今夜はぱあっといくぞっ!」
頭の叫びに男たちの歓声が響いた。
……盗賊たちの祭りが行なわれている。そのなかでシュランドはひとり、巨大な扉の前にたたずんでいた。
「……ひとりで行く気なの?」
静かな声がした。
シュランドは振り向かなかった。それが誰かはわかっている。
カグヤだ。
カグヤが漆黒の長い髪を篝火の炎に照らしだし、そこに立っているのだ。
なぜ、彼女がここにいるのか、聞く気にもならなかった。それは正しいことだ。そんな気がした。彼女がいま、自分のそばにいるのは当たり前のことなのだと。
シュランドはうなずいた。
「ああ、そうだ。おれはこの先にいかなきゃいけないんだ。もう一秒だってまっていられない。あいつらがその気になるのをまってなんかいられない」
「どうしてそこまで?」
「それは、おれが……」
「あなたが?」
「ヤシャビトの息子だからだ」
その言葉にカグヤは美しい眉をひそめた。
「ヤシャビト?」
「そうだ。知っているだろう? 陰陽の司でありながら《すさまじきもの》とともに高天原を攻め、滅ぼした人類の裏切り者。そのヤシャビトがおれの父親なんだ。
だから、おれはその息子として父親の罪を償わなくちゃならない。そのために……」
シュランドは巨大な扉を両手で殴り付けた。
「そのために力がいる! この奥にこそその力があるはずなんだ。《すさまじきもの》を倒せる力が。おれはその力を手に入れる。そして、《すさまじきもの》を倒し、高天原を再興させ、みんなが安心して暮らせる世界を取り戻すんだ」
シュランドはカグヤに向き直った。真っすぐに見つめた。
「一緒に……きてくれるかい?」
「えっ?」
「君に一緒にきてほしいんだ。君がいてくれればおれはきっとやり遂げられる。だから、頼む。おれと一緒にきてくれ」
生まれてはじめて――。
シュランドは心から頭をさげていた。
コクン、とカグヤの頭が上下に揺れた。
「わかったわ」
「えっ?」
「わたしはあなたに従う。あなたのその目的に」
「ありがとう、カグヤ!」
シュランドは破顔した。全身で喜びを爆発させた。
「君さえいてくれればおれは無敵だ! ハヤトだって、《すさまじきもの》だって相手じゃない。必ずやり遂げられる。さあ、行こう。世界を人間の手に取り戻しに」
「ええ」
シュランドの意気込みにカグヤはやさしい微笑みで答えた。
シュランドは扉に近付いた。扉の前に手をかざした。ただそれだけで扉は音もなく開いた。あまりに簡単に開いたのでシュランドは呆気にとられた。これだけ巨大な扉だ。開けるのには苦労すると覚悟していた。いざとなったらぶん殴り、穴を開け、むりやりこじ開けるつもりだったのだ。それなのにあまりにあっけなく開いてしまったものだから肩透かしを食らわされた気分だった。
「こんな大きな扉が音もなく開くなんて……どういう仕組みなんだ?」
「あなたが陰陽師の血統だから?」
「わからない。でも、なんでもいい。とにかく扉は開いたんだ。これで先に進める。さあ、行こう」
「ええ」
ふたりは扉をくぐった。その先には地下へくだる階段がつづいていた。不思議なことに――。
階段を包む壁は淡い光に満たされていた。
「不思議な壁ね。スベスベしていて柔らかいようでもあり、硬いようでもあり……」
「ああ。こんな壁は他に見たことがない。この高天原でもこの陰陽寮だけだったはずだ」
ふたりは並んで階段をくだりはじめた。
ふたりはひたすら下へしたへとくだって行った。もうずいぶん降りたはずだが、壁全体が淡く光っているおかげで地下深くに降りてきたという実感はまるでない。地上を歩いているのとほとんどかわりない雰囲気だった。
やがて、階段がつきた。降りきったそこは不思議な場所だった。そこは平原。見渡すかぎり、床も、壁も、天井も、すべて銅の鏡のようにスベスベとしてでこぼこひとつない材質で覆われていた。そのすべてが淡い輝きを放っている。
「不思議な場所」
カグヤが陶酔したような口調で言った。シュランドもうなずいた。ここにはたしかに人を酔わせるようななにかがあった。
「……人間か」
いきなり、第三の声がした。地の底から響いてくるかのような重々しい声。
ふたりはぎょっとして顔をあげた。なぜ、いままで気が付かなかったのか。平原の向こう、いちばん奥にそれはいた。
見上げるばかりの巨大な体。長くたくましい首。巨大な翼。四本の足をたたんで座り込んでいる。
ドラゴン。
そう。伝説のドラゴンそのままの姿の生物がそこにいたのだ。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

CREATED WORLD
猫手水晶
SF
惑星アケラは、大気汚染や森林伐採により、いずれ人類が住み続けることができなくなってしまう事がわかった。
惑星アケラに住む人類は絶滅を免れる為に、安全に生活を送れる場所を探す事が必要となった。
宇宙に人間が住める惑星を探そうという提案もあったが、惑星アケラの周りに人が住めるような環境の星はなく、見つける前に人類が絶滅してしまうだろうという理由で、現実性に欠けるものだった。
「人間が住めるような場所を自分で作ろう」という提案もあったが、資材や重力の方向の問題により、それも現実性に欠ける。
そこで科学者は「自分達で世界を構築するのなら、世界をそのまま宇宙に作るのではなく、自分達で『宇宙』にあたる空間を新たに作り出し、その空間で人間が生活できるようにすれば良いのではないか。」と。

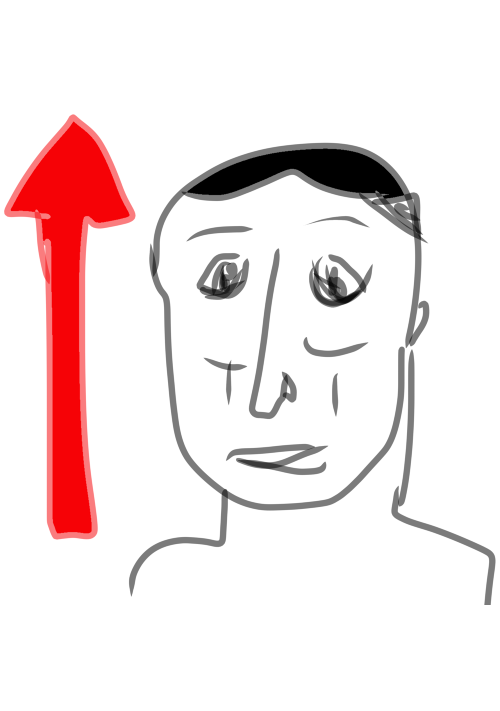
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

日本列島、時震により転移す!
黄昏人
ファンタジー
2023年(現在)、日本列島が後に時震と呼ばれる現象により、500年以上の時を超え1492年(過去)の世界に転移した。移転したのは本州、四国、九州とその周辺の島々であり、現在の日本は過去の時代に飛ばされ、過去の日本は現在の世界に飛ばされた。飛ばされた現在の日本はその文明を支え、国民を食わせるためには早急に莫大な資源と食料が必要である。過去の日本は現在の世界を意識できないが、取り残された北海道と沖縄は国富の大部分を失い、戦国日本を抱え途方にくれる。人々は、政府は何を思いどうふるまうのか。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

💚催眠ハーレムとの日常 - マインドコントロールされた女性たちとの日常生活
XD
恋愛
誰からも拒絶される内気で不細工な少年エドクは、人の心を操り、催眠術と精神支配下に置く不思議な能力を手に入れる。彼はこの力を使って、夢の中でずっと欲しかったもの、彼がずっと愛してきた美しい女性たちのHAREMを作り上げる。

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















