24 / 36
第四話 現実を知る
二四章 戦わないための旅立ち
しおりを挟む
アーデルハイドたちが鬼界島へと渡る日がやってきた。
鬼界島は数十年前のある日、なんの前触れもないままに海の上に現れ、そのままこの大陸へと接近してきた。そして、人類最大の防衛拠点であった沿岸の町エンカウンから望む海岸と地峡でつながった。鬼界島へ渡るならその地峡を使うのが一番、簡単で手っ取り早い。
とは言え、かつてのレオンハルト王国の領土はすでに、王都ユキュノクレストをのぞいた全体が鬼部の支配下にある。当然、エンカウンへと至る大地のいたるところに鬼部の軍勢が居座っている。そのなかを突っ切って鬼界島に向かうなど自殺行為。さすがのアーデルハイドもそこまで大胆な真似はしようとはしなかった。
「鬼界島に乗り込むと言うのに、鬼部の軍勢を怖れていてどうするの」
などと発言して周囲をあわてさせはしたが。
ともかく、周囲の勧めもあって迂回路をとることにした。レオンハルトの隣国、海岸沿いの国スミクトルの港町から小舟を使い、鬼界島に渡ることにした。
これは、いまもただひとり、鬼界島で偵察行動をつづけている逃げ兎ことアルノが鬼界島に侵入する際に使った手でもある。
鬼部という生き物は陸地にしか興味がないらしく、海に対してはまったく警戒していないことはすでにわかっている。
なにしろ、鬼界島のまわりには小舟ひとつ見かけられたことはないのだ。鬼部は海を警戒しないだけではなく、漁の類もしないらしい。食べるのはあくまでも人間。それが鬼部なのだ。
「鬼部が海に関心がないと言うのなら、海から奇襲をかけたらどうだ?」
そう言う意見は熊猛紅蓮隊が鬼界島に乗り込むずっと以前から根強く提案されては来た。しかし、鬼界島から続々と侵攻してくる鬼部の軍勢に対処することに精一杯で大規模な別働隊を編成する余裕がなかった。
また、大陸における人間同士の戦いはあくまでも内陸でのものであり、海を舞台にした戦いなどはなかった。そのために、『海軍』と呼べるほどの存在もなく、軍隊を運べるほどの船団を用意できなかった。
さらに、いくら鬼部が海に対して関心がないとは言っても、大船団を組織して送り込めばさすがに気付かれるのではないか。一度、警戒させてしまえばもう二度と奇襲をかける機会はあるまい。そもそも、鬼界島の地理も、鬼部の軍勢の位置もわからないのに奇襲など仕掛けても効果は見込めない。鬼界島の情報が集まり、攻めるべき地点が判明し、充分な効果が見込めるまでうかつな行動はしない方がいい……といった慎重論もあって、いままで実行されずに来た。
しかし、たった三人が小舟で乗り込む分にはそれらの問題はない。
そのことは逃げ兎が見事に侵入に成功したことからもはっきりしているし、その逃げ兎の報告によって『本当に』鬼部は海に対して警戒の目を向けていないこともわかっている。少人数でこっそり侵入する、と言う場合には現状ではこれが最良の方法であると言える。
アーデルハイドは港町に用意された小舟の上に佇み、同行者たちの訪れをまっていた。じっと海の彼方を見つめ、吹きくる風が髪をたなびかせる。その姿に――。
やってきたカンナとチャップはそろって『ほう……』と、溜め息をついた。
それほどに様になる姿。夭逝の天才画家が残された最後の命を注ぎ込んで描きあげた名画のように決まっている。単なる漁用の小舟に過ぎない舟が、アーデルハイドが乗っているというそれだけで海を征く女神を乗せた神代の船に見えてしまう。『人類随一の美貌』のもつ補正力のすさまじさである。
アーデルハイドがふたりの同行者に訪れに気がついた。視線を向け、短く口にする。
「来たわね」
その姿がやはり、女神のよう。人の魂をもつものなら黙ってひれ伏すしかない美しさに満ちている。
「カンナ。舟の扱いはお願いね」
「はい、任せてください!」
敬愛する女主人にそう言われ、カンナは力強く請け負った。〝歌う鯨〟の一員として、ゲンナディ内海に浮かぶ島で生まれ育ったカンナである。舟の扱いはお手の物だ。
一方でチャップのほうは緊張した面持ちだ。内陸の出身とあって舟に乗るのさえこれがはじめて。三年前、熊猛紅蓮隊の一員として鬼界島に乗り込んだときには鬼界島と海岸とをつなぐ地峡を渡った。
当時はまだエンカウンが陥落しておらず、人類の防衛拠点として――曲がりなりにも――機能していた。そのため、地峡を使って乗り込むのは簡単だった。舟を使う必要はなかったのだ。舟はまったくの未経験。それでいきなり海に出ようというのだ。緊張しない方がどうかしている。
これまでずっと男の振りをしていなければいけないという事情もあって、常に大きすぎる鎧を身にまとっていたチャップだが、さすがに小舟で海に出るとなれば鎧などまとっていられない。そもそも、もう男の振りをする必要もなくなったし、アーデルハイドから武器だけではなく防具も身につけていてはいけないと厳命されている。
「わたしたちは戦いに行くのではなく、鬼部を知りに行く。戦うための武器も、身を守るための防具も必要ありません」と。
と言うわけで、いまは飾り気のない私服姿である。長年、まといつづけてきた鎧を脱いでいるとあって心細そうだが、こればかりは仕方がない。
単純な作りの服だけに体の線がよくわかる。繊細な顔の作りといい、よく見ればたしかに女性のものだと言うことはわかるのだがなにぶん、何年にもわたって男の振りをしてきた身。男たちのなかに混じって生活していたとあって仕種の一つひとつが男っぽい。そのためにちょっと見にはやはり、少年のように見えるのだった。
カンナとチャップが舟に乗り込んだ。そんなふたりにアーデルハイドが話しかけた。
「出発前に確認しておくけど。武器はもっていないでしょうね?」
「えっ?」
アーデルハイドの言葉に――。
カンナの表情が引きつった。
「何度も言ったでしょう。わたしたちは戦いに行くのではなく鬼部を知りに行く。武器はもっていってはいけないと。守っているでしょうね?」
「も、もももちろんです、はい!」
カンナはあからさまにうろたえた。まっすくで素直な性格だけあって嘘やごまかしはできない質である。それ以上にひどいのがチャップで、誰が見ても一目で『図星を指された』ことがわかるぐらい慌てふためき、露骨に視線をそらしている。
「そう。それじゃあ、確認させてもらうわ」
「えっ? いや、ちょ、アーデルハイドさま……!」
「や、うわ、きゃああっ!」
小舟の上に若い娘ふたりの悲鳴が響いた。アーデルハイドの手練手管によっていともたやすく服を脱がされ、裸にむかれてしまった。アーデルハイドの手にした服からは護身用に短剣や暗殺用の暗器などが幾つも落ちてきた。
「何度も駄目だと言ったのにね」
アーデルハイドは手厳しい視線でふたりの同行者を見た。
「で、でも、やっぱり、護身用の武器ぐらいはないと……」
両手で自分の身を抱きしめ、肝心なところを隠しながらカンナが言った。その横ではチャップがやはり、両腕で自分を抱きしめた姿でうずくまっている。
「わたしたちは敵の本拠地に行くの。護身用の短剣なんかをもっていたとして、鬼部の群れに囲まれたら……役に立つと思う?」
「い、いえ……」
その状況では短剣どころか、巨大な両手剣をもっていても役には立たないだろう。
「だったら、もっていても意味はない。却って危険をますだけ。何度もそう言ったでしょう」
「……はい」
「これまでの経験から鬼部が食べるのは自分たちで狩った人間だけだと言うことがわかっている。無抵抗のまま捕えられた人間が食べられた例は確認されていない。武器をもって抵抗したりしたら『食べてください』と言っているようなものよ」
「……はい」
そう言われてはカンナとしてもうなずくしかない。
アーデルハイドははぎ取った服をふたりに返し、短剣や暗器はすべて海に放り投げた。チャップが急いで服を着込みながらアーデルハイドに尋ねた。
「で、でも、アーデルハイドさま……。服を脱がせるの、やたら慣れてません?」
「我がエドウィン家は婚姻政策で成りあがった。それがすべて」
言われてチャップはカンナにささやきかけた。
「な、なあ……。アーデルハイドさまって実はけっこう……」
カンナはチャップを睨み付けた。
「……その先を言ったら殺す」
第四話完
第五話につづく
鬼界島は数十年前のある日、なんの前触れもないままに海の上に現れ、そのままこの大陸へと接近してきた。そして、人類最大の防衛拠点であった沿岸の町エンカウンから望む海岸と地峡でつながった。鬼界島へ渡るならその地峡を使うのが一番、簡単で手っ取り早い。
とは言え、かつてのレオンハルト王国の領土はすでに、王都ユキュノクレストをのぞいた全体が鬼部の支配下にある。当然、エンカウンへと至る大地のいたるところに鬼部の軍勢が居座っている。そのなかを突っ切って鬼界島に向かうなど自殺行為。さすがのアーデルハイドもそこまで大胆な真似はしようとはしなかった。
「鬼界島に乗り込むと言うのに、鬼部の軍勢を怖れていてどうするの」
などと発言して周囲をあわてさせはしたが。
ともかく、周囲の勧めもあって迂回路をとることにした。レオンハルトの隣国、海岸沿いの国スミクトルの港町から小舟を使い、鬼界島に渡ることにした。
これは、いまもただひとり、鬼界島で偵察行動をつづけている逃げ兎ことアルノが鬼界島に侵入する際に使った手でもある。
鬼部という生き物は陸地にしか興味がないらしく、海に対してはまったく警戒していないことはすでにわかっている。
なにしろ、鬼界島のまわりには小舟ひとつ見かけられたことはないのだ。鬼部は海を警戒しないだけではなく、漁の類もしないらしい。食べるのはあくまでも人間。それが鬼部なのだ。
「鬼部が海に関心がないと言うのなら、海から奇襲をかけたらどうだ?」
そう言う意見は熊猛紅蓮隊が鬼界島に乗り込むずっと以前から根強く提案されては来た。しかし、鬼界島から続々と侵攻してくる鬼部の軍勢に対処することに精一杯で大規模な別働隊を編成する余裕がなかった。
また、大陸における人間同士の戦いはあくまでも内陸でのものであり、海を舞台にした戦いなどはなかった。そのために、『海軍』と呼べるほどの存在もなく、軍隊を運べるほどの船団を用意できなかった。
さらに、いくら鬼部が海に対して関心がないとは言っても、大船団を組織して送り込めばさすがに気付かれるのではないか。一度、警戒させてしまえばもう二度と奇襲をかける機会はあるまい。そもそも、鬼界島の地理も、鬼部の軍勢の位置もわからないのに奇襲など仕掛けても効果は見込めない。鬼界島の情報が集まり、攻めるべき地点が判明し、充分な効果が見込めるまでうかつな行動はしない方がいい……といった慎重論もあって、いままで実行されずに来た。
しかし、たった三人が小舟で乗り込む分にはそれらの問題はない。
そのことは逃げ兎が見事に侵入に成功したことからもはっきりしているし、その逃げ兎の報告によって『本当に』鬼部は海に対して警戒の目を向けていないこともわかっている。少人数でこっそり侵入する、と言う場合には現状ではこれが最良の方法であると言える。
アーデルハイドは港町に用意された小舟の上に佇み、同行者たちの訪れをまっていた。じっと海の彼方を見つめ、吹きくる風が髪をたなびかせる。その姿に――。
やってきたカンナとチャップはそろって『ほう……』と、溜め息をついた。
それほどに様になる姿。夭逝の天才画家が残された最後の命を注ぎ込んで描きあげた名画のように決まっている。単なる漁用の小舟に過ぎない舟が、アーデルハイドが乗っているというそれだけで海を征く女神を乗せた神代の船に見えてしまう。『人類随一の美貌』のもつ補正力のすさまじさである。
アーデルハイドがふたりの同行者に訪れに気がついた。視線を向け、短く口にする。
「来たわね」
その姿がやはり、女神のよう。人の魂をもつものなら黙ってひれ伏すしかない美しさに満ちている。
「カンナ。舟の扱いはお願いね」
「はい、任せてください!」
敬愛する女主人にそう言われ、カンナは力強く請け負った。〝歌う鯨〟の一員として、ゲンナディ内海に浮かぶ島で生まれ育ったカンナである。舟の扱いはお手の物だ。
一方でチャップのほうは緊張した面持ちだ。内陸の出身とあって舟に乗るのさえこれがはじめて。三年前、熊猛紅蓮隊の一員として鬼界島に乗り込んだときには鬼界島と海岸とをつなぐ地峡を渡った。
当時はまだエンカウンが陥落しておらず、人類の防衛拠点として――曲がりなりにも――機能していた。そのため、地峡を使って乗り込むのは簡単だった。舟を使う必要はなかったのだ。舟はまったくの未経験。それでいきなり海に出ようというのだ。緊張しない方がどうかしている。
これまでずっと男の振りをしていなければいけないという事情もあって、常に大きすぎる鎧を身にまとっていたチャップだが、さすがに小舟で海に出るとなれば鎧などまとっていられない。そもそも、もう男の振りをする必要もなくなったし、アーデルハイドから武器だけではなく防具も身につけていてはいけないと厳命されている。
「わたしたちは戦いに行くのではなく、鬼部を知りに行く。戦うための武器も、身を守るための防具も必要ありません」と。
と言うわけで、いまは飾り気のない私服姿である。長年、まといつづけてきた鎧を脱いでいるとあって心細そうだが、こればかりは仕方がない。
単純な作りの服だけに体の線がよくわかる。繊細な顔の作りといい、よく見ればたしかに女性のものだと言うことはわかるのだがなにぶん、何年にもわたって男の振りをしてきた身。男たちのなかに混じって生活していたとあって仕種の一つひとつが男っぽい。そのためにちょっと見にはやはり、少年のように見えるのだった。
カンナとチャップが舟に乗り込んだ。そんなふたりにアーデルハイドが話しかけた。
「出発前に確認しておくけど。武器はもっていないでしょうね?」
「えっ?」
アーデルハイドの言葉に――。
カンナの表情が引きつった。
「何度も言ったでしょう。わたしたちは戦いに行くのではなく鬼部を知りに行く。武器はもっていってはいけないと。守っているでしょうね?」
「も、もももちろんです、はい!」
カンナはあからさまにうろたえた。まっすくで素直な性格だけあって嘘やごまかしはできない質である。それ以上にひどいのがチャップで、誰が見ても一目で『図星を指された』ことがわかるぐらい慌てふためき、露骨に視線をそらしている。
「そう。それじゃあ、確認させてもらうわ」
「えっ? いや、ちょ、アーデルハイドさま……!」
「や、うわ、きゃああっ!」
小舟の上に若い娘ふたりの悲鳴が響いた。アーデルハイドの手練手管によっていともたやすく服を脱がされ、裸にむかれてしまった。アーデルハイドの手にした服からは護身用に短剣や暗殺用の暗器などが幾つも落ちてきた。
「何度も駄目だと言ったのにね」
アーデルハイドは手厳しい視線でふたりの同行者を見た。
「で、でも、やっぱり、護身用の武器ぐらいはないと……」
両手で自分の身を抱きしめ、肝心なところを隠しながらカンナが言った。その横ではチャップがやはり、両腕で自分を抱きしめた姿でうずくまっている。
「わたしたちは敵の本拠地に行くの。護身用の短剣なんかをもっていたとして、鬼部の群れに囲まれたら……役に立つと思う?」
「い、いえ……」
その状況では短剣どころか、巨大な両手剣をもっていても役には立たないだろう。
「だったら、もっていても意味はない。却って危険をますだけ。何度もそう言ったでしょう」
「……はい」
「これまでの経験から鬼部が食べるのは自分たちで狩った人間だけだと言うことがわかっている。無抵抗のまま捕えられた人間が食べられた例は確認されていない。武器をもって抵抗したりしたら『食べてください』と言っているようなものよ」
「……はい」
そう言われてはカンナとしてもうなずくしかない。
アーデルハイドははぎ取った服をふたりに返し、短剣や暗器はすべて海に放り投げた。チャップが急いで服を着込みながらアーデルハイドに尋ねた。
「で、でも、アーデルハイドさま……。服を脱がせるの、やたら慣れてません?」
「我がエドウィン家は婚姻政策で成りあがった。それがすべて」
言われてチャップはカンナにささやきかけた。
「な、なあ……。アーデルハイドさまって実はけっこう……」
カンナはチャップを睨み付けた。
「……その先を言ったら殺す」
第四話完
第五話につづく
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説


サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

日本列島、時震により転移す!
黄昏人
ファンタジー
2023年(現在)、日本列島が後に時震と呼ばれる現象により、500年以上の時を超え1492年(過去)の世界に転移した。移転したのは本州、四国、九州とその周辺の島々であり、現在の日本は過去の時代に飛ばされ、過去の日本は現在の世界に飛ばされた。飛ばされた現在の日本はその文明を支え、国民を食わせるためには早急に莫大な資源と食料が必要である。過去の日本は現在の世界を意識できないが、取り残された北海道と沖縄は国富の大部分を失い、戦国日本を抱え途方にくれる。人々は、政府は何を思いどうふるまうのか。

スキルテスター!本来大当たりなはずの数々のスキルがハズレ扱いされるのは大体コイツのせいである
騎士ランチ
ファンタジー
鑑定やアイテム増資といったスキルがハズレ扱いされるのは何故だろうか?その理由はまだ人類がスキルを持たなかった時代まで遡る。人類にスキルを与える事にした神は、実際にスキルを与える前に極少数の人間にスキルを一時的に貸し付け、その効果を調査する事にした。そして、神によって選ばれた男の中にテスターという冒険者がいた。魔王退治を目指していた彼は、他の誰よりもスキルを必要とし、効果の調査に協力的だった。だが、テスターはアホだった。そして、彼を担当し魔王退治に同行していた天使ヒースもアホだった。これは、声のでかいアホ二人の偏った調査結果によって、有用スキルがハズレと呼ばれていくまでの物語である。

極悪家庭教師の溺愛レッスン~悪魔な彼はお隣さん~
恵喜 どうこ
恋愛
「高校合格のお礼をくれない?」
そう言っておねだりしてきたのはお隣の家庭教師のお兄ちゃん。
私よりも10歳上のお兄ちゃんはずっと憧れの人だったんだけど、好きだという告白もないままに男女の関係に発展してしまった私は苦しくて、どうしようもなくて、彼の一挙手一投足にただ振り回されてしまっていた。
葵は私のことを本当はどう思ってるの?
私は葵のことをどう思ってるの?
意地悪なカテキョに翻弄されっぱなし。
こうなったら確かめなくちゃ!
葵の気持ちも、自分の気持ちも!
だけど甘い誘惑が多すぎて――
ちょっぴりスパイスをきかせた大人の男と女子高生のラブストーリーです。

ドマゾネスの掟 ~ドMな褐色少女は僕に責められたがっている~
桂
ファンタジー
探検家の主人公は伝説の部族ドマゾネスを探すために密林の奥へ進むが道に迷ってしまう。
そんな彼をドマゾネスの少女カリナが発見してドマゾネスの村に連れていく。
そして、目覚めた彼はドマゾネスたちから歓迎され、子種を求められるのだった。
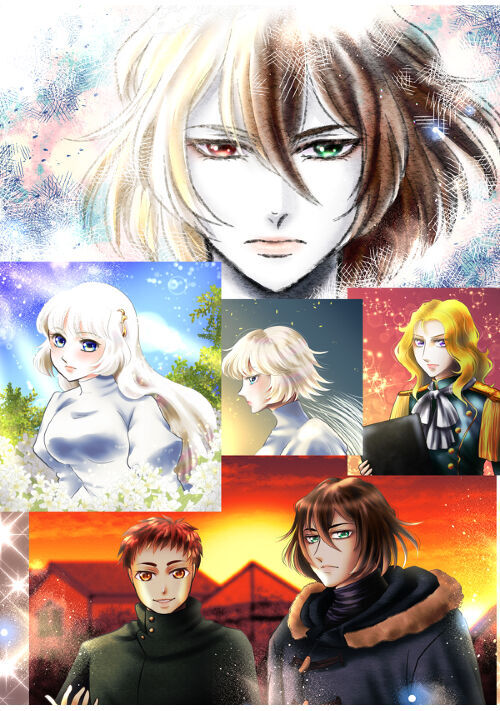
アストルムクロニカ-箱庭幻想譚-(挿し絵有り)
くまのこ
ファンタジー
これは、此処ではない場所と今ではない時代の御伽話。
滅びゆく世界から逃れてきた放浪者たちと、楽園に住む者たち。
二つの異なる世界が混じり合い新しい世界が生まれた。
そこで起きる、数多の国や文明の興亡と、それを眺める者たちの物語。
「彼」が目覚めたのは見知らぬ村の老夫婦の家だった。
過去の記憶を持たぬ「彼」は「フェリクス」と名付けられた。
優しい老夫婦から息子同然に可愛がられ、彼は村で平穏な生活を送っていた。
しかし、身に覚えのない罪を着せられたことを切っ掛けに村を出たフェリクスを待っていたのは、想像もしていなかった悲しみと、苦難の道だった。
自らが何者かを探るフェリクスが、信頼できる仲間と愛する人を得て、真実に辿り着くまで。
完結済み。ハッピーエンドです。
※7話以降でサブタイトルに「◆」が付いているものは、主人公以外のキャラクター視点のエピソードです※
※詳細なバトル描写などが出てくる可能性がある為、保険としてR-15設定しました※
※昔から脳内で温めていた世界観を形にしてみることにしました※
※あくまで御伽話です※
※固有名詞や人名などは、現代日本でも分かりやすいように翻訳したものもありますので御了承ください※
※この作品は「ノベルアッププラス」様、「カクヨム」様、「小説家になろう」様でも掲載しています※

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















