13 / 26
一三章
ウシに嫌われる
しおりを挟む
「おはよう、ひなた。今日も元気そうね」
陽菜はそう言いながら、愛しそうにそのウシの頭をなでてやった。
「『ひなた』って言うの、そのウシ?」
舞楽が尋ねると陽菜はうれしそうにうなずいた。
「ええ、そう。うちの大事な乳牛よ。『ひのきファ―ム』の初代乳牛から代々伝えられてきた直系なの。由緒正しい血統なんだから」
「へえ」
陽菜はまるで我がことのように自慢げに言ったけど、舞楽にはなぜ自慢するようなことなのかピンとこない。気の抜けた返事を返すしかなかった。
「ひなたはね。わたしが育てたの」
「先輩が?」
「ええ。うちでは代々、生まれた子ウシの一頭を残して新しい乳牛にしてきたんだけど、どうも、難産の家系らしくてね。お産にはいつも苦労するのよ。この子もかなりの難産の末にやっと生まれたものだから体質が弱くてね。最初はお乳も満足に飲めないぐらいだったの」
「そうなの?」
大きくで頑丈そうに見えるけど。
「それで、まだ入りたての新人だったわたしに世話係がまわってきたってわけ。知らないことばかりで不安だったけどね」
「そうだったの?」
「当たり前よ。そりゃあ、あなたよりは動物に慣れていたとは思うけど、それでも、きちんと世話をするなんてはじめての体験だったもの。何をするにも『これでいいの?』、『まちがってない?』って、そればっかりで夜も眠れないほどだったわ」
「へえ」
「それでも、とにかく、毎日まいにち、ブラシをかけたり、お湯で温めたり、手ずからミルクを飲ませたりして必死に世話をしたわ。おかげで体力もだんだんついてきて、いまでは毎日きちんとお乳を出してくれて、子供も毎年、生んでくれる立派な乳牛になったわけ。
逆に言うと、ひなたこそわたしの師匠というわけ。ひなたの世話をするためにめいっぱい勉強したものね。おかげでどうにか成長できた。つまり、ひなたはわたしにとって子供であると同時に、育ての親でもあるってわけ」
なるほど。それなら我がことのように自慢するのも当然だ。
「大事なウシなのね」
「そう。とても大切な相手よ。と言うわけで、はい」
と、陽菜は舞楽に大きなブラシを差し出した。
「今日からあなたがひなたの世話をしてね」
「わたしが?」
「ええ」
「いいの? 大事なウシをわたしに任せて。わたし、ウシの世話なんてしたことないけど」
「だからやってもらうのよ。ここでの仕事を覚えてもらうためにね。ひなたの世話ができれば他のクマリたちの世話もできるから」
そういうものか。ともかく、ここで働くことになったのだ。雇い主の采配に文句はつけられない。舞楽はブラシを受け取った。
「それじゃまず、そのブラシでマッサ―ジしてあげて」
「はい」
舞楽はブラシを手にひなたに近づいた。ところが――。
いきなりだった。いきなりひなたが頭を振るって舞楽に襲いかかった。舞楽はとっさに後ろに飛んでよけた。舞楽だから無事ですんだけど普通の女の子だったら吹っ飛ばされているところだ。
「ひなた!」
陽菜が叫んだ。あわててひなたに抱きついてなだめた。
「どうしたの? だいじょうぶ、だいじょうぶ。危ないことなんか何もないから、ねっ?」
陽菜は必死に落ち着かせようとした。ところが、ひなたの警戒は解ける様子もない。舞楽に向かって頭をさげ、四肢を踏ん張り、いまにも襲いかからんばかりの態度。目にははっきり敵意が燃えている。
「……なんか、メチャクチャきらわれてるみたいなんだけど」
「う~ん。まあ、ひなたも神経質なところがあるから。知らない人に会って警戒してるんだと思う。おまけに妊娠中だからよけいピリピリしてるのね。わたしが押さえているからとにかくマッサ―ジしてあげて。慣れれば落ち着くと思うから」
「はい」
舞楽は改めてブラシを手に近づいた。ひなたは威嚇のうなり声を上げている。いきなり襲われた直後にこの態度。普通の女の子なら怖くて震え上がるところだ。しかし、そこは木花舞楽。怖い物知らずの性格で平気で近づき、ブラシをかける。陽菜がそばにいるせいか、ひなたは今度は襲うような真似はしなかった。と言っても、警戒を解く様子はない。
「ダメダメ。もっと力を入れて」
「いいの? わたし、けっこう力ある方だけど」
「相手は人間じゃないのよ。分厚い皮膚に覆われた動物なの。遠慮してたら何にも感じないわ。ゴシゴシこするぐらいでちょうどいいのよ」
そういうものか。ならば、と言うことで舞楽は力を込めてこすりはじめた。
「そう、その調子。ひなたは背中をブラッシングしてもらうのが大好きなの。毎日ブラッシングしてあげてればあなたのことも好きになってくれるわよ」
「別に好きになってもらいたいとは思わないけど」
その一言に陽菜はキッと舞楽を睨み付けた。今回ばかりは本気で怒っている。
「何を言ってるの。クマリは人の心に敏感なの。敵意をもって近づいてくる相手には敵意を返すし、好意をもって近づいてくる相手には好意を返す。あなたはいままで相手の気持ちなんて考えずに生きてきたみたいだけど、ここで働く以上、そんな態度は通用しない。相手のことを思って、考えて、好かれるように努力しなさい。いいわね?」
「好かれなくたって世話さえすればいいんでしょ」
「その態度が通用しないと言ってるのよ。クマリは機械じゃないの。生き物なの。心のこもっていない形ばかりのお世話じゃまともに育たないし、健康にだって影響する。人間の赤ん坊だって愛情抜きで育てられたらまともには育たないでしょう。それと同じよ」
「赤ん坊なんて育てたことないし」
「いちいち口答えしない!」
本気の雷だったけど、だからといって傷ついたり、怯えたりするような可愛げのあるタマではない。平然と肩をすくめただけだった。とにかくブラッシングをつづける。
「黙ってやってちゃダメ。きちんと話しかけて」
「動物相手に話しかけてどうするのよ。言葉なんか通じないでしょ」
「言葉が通じるとか通じないとかそういう問題じゃないの。話しかけるというのは相手に興味をもっているというメッセ―ジなんだから。動物でも、植物でも、いちいち話しかけて興味をもっていることを伝えるのはとても大切なことなの。話しかけるかどうかで育ちが全然ちがうんだから」
「そういうものなの?」
「そういうものなの。そのことはeFREEガ―デンの歴史のなかで確認されているんだから」
「え~と、それじゃあ……って、なにを話せばいいの?」
「何でもいいわよ。大切なのは話しかけること。内容は二の次でいいわ」
「それじゃあ……え~と、ひなた? わたしは木花舞楽、一四歳。なぜか過去の世界からきちゃったんだけど……」
とにかく、思いつくままに話しかけた。こんなことで本当にどうにかなるとは思わなかったけど。
ブラッシングを終えると次は乳搾り。と言っても、乳を搾るのは素人にはむずかしいし、ヒツジたちはともかくひなたは舞楽には決して乳首をさわらせようとはしなかった。無理に搾ろうとすれば後ろ足を振りまわし、蹴りつけようとする始末。そのあまりに激しい抵抗に陽菜もさすがにあきらめた。
「これじゃ、いくら舞楽でも危ないわね。ひなたもストレスが強すぎるし。仕方ないわ。乳搾りはわたしがやるから舞楽は卵を集めて倉庫にもっていって。それが終わったらバケツを洗っておいて」
「はい」
何とも釈然としないものを感じながら舞楽は指示に従った。ニワトリやカモが巣にしている場所から卵を集め、バケツを洗う。これは熱湯消毒も兼ねていて、もうもうと湯気を立てる熱湯のプ―ルにバケツを沈めて柄の長いブラシでゴシゴシこするという豪快なもの。冬なら天国と思えるかも知れないけど、夏にやるにはちょっとつらい。もうもうたる湯気に包まれ、たちまち全身汗だくになってしまう。それでも一度引き受けたことはきちんとやるのが木花舞楽。文句ひとつ言わずにきちんと洗い、日に干して乾かしていく。
乳搾りが終わると放牧の時間。と言っても、食事を終えたものから勝手に農地のなかに出ていくだけ。ヒツジたちは畝の間の通路を歩いて草を食み、ニワトリたちはそのあとをチョコチョコついていく。ニワトリたちの目当てはヒツジが草を食べることで追い出された虫たちだ。虫たちは栄養たっぷりで、ニワトリたちは様々な虫をバランスよく食べて健康に育つ。おまけに害虫退治にもなる。カモたちも勝手に田んぼに行き、水の上をスイスイ泳ぐ。イヌたちは辺りを走り回り、ネコたちは日だまりで丸くなる。まったく、それぞれの性格がよく出ていて見ていて笑えてくるほどだ。
ただし、ウシとブタだけは農地には放さない。周りを囲む樹林帯に連れて行く。
「体の大きいウシには畝間の通路はせまいし、畝の上の作物に口が届いちゃうから。ブタはブタで何でも掘り返す習性があって、丈夫な鼻先で穴だらけにしちゃうし、畝を崩しちゃうから。それに、木の実をたくさん食べて育ったブタの肉って脂が甘くてすごくおいしいのよ!」
とのことだった。
「と言うわけで、よろしくね。舞楽。わたしはすぐにミルクを加工しなきゃいけないから、ひなたとブタたちを樹林帯に連れて行って」
と、陽菜は舞楽にリ―ドを手渡した。
「連れて行くだけでいいの?」
「ええ。樹林帯に放しさえすれば、あとはそれぞれ好きなように過ごすから。ただし、リ―ドは必ず外して持ち帰ってね。つけたままだと体に絡んだりすることがあるから。ああ、それと、農地と樹林帯は柵で遮られているんだけど、扉の鍵を閉め忘れないようにね。必ず声に出して確認して。開けっ放しだと農地の方に入り込んできちゃうから。それだけは徹底して」
「はい」
舞楽は答えてリ―ドを受け取った。ひなたたちを樹林帯に連れて行こうとする。ところが――。
「……全然、動かないんだけど」
ひなたは四肢を踏ん張り、てこでも動こうとしない構え。舞楽は力の限りリ―ドを引いたけど、ビクともしない。当たり前だ。いくら舞楽がこの年齢の女の子としては驚くほどの力持ちとは言え、相手は体重四〇〇キロを超える四足獣。力ずくで引っ張っていけるわけがない。
もともと、動物との相性は悪い。よく馴れた飼い犬でさえ、舞楽が相手となると吠えるか、逃げるか、どちらかだった。舞楽は舞楽で子供と動物はきらいな質。好かれたいと思ったこともないし、小鳥一羽飼ったこともない。……面倒を見るのは母親だけで充分だったし。
でも、だからって、どうしてここまできらわれるのか。いつもの場所に連れて行くだけなのに。動物ってリ―ドを引っ張ればついてくるものなんじゃなかったの?
舞楽は無理やり引っ張っていこうとし、ひなたは頑として抵抗をつづける。ひとりと一頭の綱引きがしばらくつづいた。
やがて、陽菜がため息をついた。頭を振りながらひなたに近づく。そっと手を添えてやさしく語りかける。
「だいじょうぶよ、ひなた。彼女は敵じゃない。わたしたちの新しい仲間。だから、そんなに警戒しないで。ねっ?」
それから舞楽に目を向けた。
「ほら、舞楽。あなたもちゃんと話しかけて」
「え、え~と、ほら、ひなた。別にとって食おうなんてわけじゃないから。いつもの所に行くだけだから。だから、おとなしくついてきて」
ふたりしてさんざん話しかけてようやくひなたは歩き出した。それでも、警戒心は丸出しでちょっと気をそらすとすぐに立ち止まって動かなくなる。舞楽は必死に話しかけつつ、四苦八苦しながら連れて行く。その様子を見て陽菜はため息をついた。
「想像以上にやっかいみたいね。舞楽が早く相手を思いやる気持ちをもってくれればいいんだけど」
とにかく、どうにかこうにかやっとの思いでひなたと二頭のブタを樹林帯に連れ出した。柵の扉を開けて外に出し、リ―ドを外す。その途端、ひなたは駆け出した。一秒だってこんなやつのそばにはいたくないと言わんばかりのその態度。ウシが走るところなんてはじめて見る舞楽は呆気にとられてその後ろ姿を見送った。
きらわれたからと言って傷つくようなタマではない。何しろ、生まれた頃から妬みそねみにやっかみをぶつけられ、動物どころか人間の敵意に囲まれて生きてきたのだ。きらわれるのにはとっくの昔に慣れている。というより、きらわれることこそ舞楽にとっては普通のことだった。だから、いくらきらわれたって気にしたりはしない。でも――。
「……おもしろい気分じゃないわよね、やっぱり」
陽菜に言われたとおり、扉の鍵をかけたことを声に出して確認し、倉庫に戻った。そこでは、陽菜がチ―ズ作りの真っ最中だった。量の少ないヒツジのミルクはそのまま飲用としてボトルにつめ、量の多いウシのミルクでチ―ズを作る。まず、ミルクを殺菌し、乳酸菌を入れる。しばらくしてから凝固剤を入れて静置。ミルクが固まったらホエ―とカ―ドにわける。このカ―ドがチ―ズの原型となる。カ―ドに冷水をかけて冷やし、乳酸菌の働きを抑える。さらにこまかく砕いて九〇度の塩水のなかで練る。湯を捨てて弾力と艶が出るまでさらに練る。丸くちぎってすぐに流水に入れて冷まし、薄い塩水と一緒にパッケ―ジ。
「へえ、チ―ズってこうやって作るんだ。はじめて見た」
『資格がないから』というもっともな理由で関わらせてもらえなかったけど、作り方を見ているだけでも興味深い。家事担当として自分でも作ってみたくなった。
「一口にチ―ズと言ってもいろいろあるから、チ―ズによって、人によって、作り方もいろいろだけどね。これは我が『ひのきファ―ム』に伝わるモッツァレラチ―ズの作り方。はい、どうぞ、食べてみて」
と、陽菜はできたてのモッツァレラチ―ズを舞楽に手渡した。
「いいの? 売り物なんでしょう?」
陽菜は笑った。
「少しぐらいかまわないわよ。どうせ、全部売れるわけじゃないしね」
言いつつ、陽菜は自分でも丸くちぎったチ―ズを口のなかに放り込んだ。
それを見て舞楽も食べてみた。とたんに目を丸くした。
「おいしい」
「でしょ? でしょ?」
できたてのチ―ズを食べたのなんてはじめてだけど、こんなにおいしいものとは知らなかった。ミルクの風味たっぷりで、ジュ―シ―で、自然な甘さが感じられる。自分の時代で食べていたチ―ズとはまったくの別物だった。
「フレッシュチ―ズは鮮度が命。できたてが一番おいしいの。よそには絶対、負けないわ」
陽菜がそう胸を張るのも納得のおいしさだった。
作るのはチ―ズだけではない。その合間にパンやクッキ―も焼き、おにぎりと卵焼きを作って弁当にする。これはアパ―トの住人から夕べのうちに注文を受けて作るのだという。
弁当を包むパッケ―ジは稲藁のシ―ト。シ―トの上におにぎりと卵焼きまを並べ、手慣れた動作で包んでいく。稲藁のシ―トは農作業が少なくなる冬の間に自分で編んだものだという。
「デイリ―メイドってそんなことまでするんだ。大変なのね」
「そうでもないわよ。一連の流れのなかでけっこう自然にできちゃうものよ。それに、一番手間のかかる収穫作業が住人任せだからその分、時間があるのよ」
稲藁は他にもペット用の敷き藁としても使われるし、ネコ用の小さな家を作って売ったりもする。『ひのきファ―ム』の場合は伝統的に稲藁細工だけど、ファ―ムによってはタリスマンやアミュレットといった魔術の護符を作っているところもあるとか。
どれも、eFREEガ―デンで採れた植物から作られているので使い終わったあとにはそのへんに放り出しておけばクマリたちによって食べられ、新しい生命を育む養分となる。舞楽の時代の農業は金を払って肥料を買っていたけど、この時代では肥料をレンタルして稼いでいる。
「やっぱり先輩だったのね。そんなにいろいろできるなんて。見直したわ」
素直なような、失礼なようなことを言う舞楽を陽菜はじっと見つめた。
「なに?」
「怒ってる?」
「なんで?」
陽菜の言葉に舞楽はキョトンとした。
「だって……さっき、けっこうきついこと言っちゃったし」
「なんで? 先輩として言うべきことを言っただけでしょう?」
「それはそうなんだけど」
「なら、いいじゃない。新人が注意されるのは当たり前だし、先輩が気を遣う必要ないわ」
「……舞楽ってけっこう図太い?」
「よく言われる」
その答えに陽菜は吹き出した。
「ならいいわ。あなたにそういう心配はいらないみたいね。じゃあ、これからもビシビシ行くわよ。一人前に育てるのが先輩としての役目だものね」
「よろしく、先輩」
「ではさっそく。怒っているわけでもないのにさっきみたいな態度はとらない方がいいわよ」
「なんで?」
本気でキョトンとする舞楽に陽菜はため息をついた。
「……まあ、いいか。あなたの外見なら許されそうだし。とにかく、朝ご飯にしましょう。お腹減ったでしょう?」
言われて舞楽は自分が恐ろしく腹を空かせていることに気がついた。
陽菜はそう言いながら、愛しそうにそのウシの頭をなでてやった。
「『ひなた』って言うの、そのウシ?」
舞楽が尋ねると陽菜はうれしそうにうなずいた。
「ええ、そう。うちの大事な乳牛よ。『ひのきファ―ム』の初代乳牛から代々伝えられてきた直系なの。由緒正しい血統なんだから」
「へえ」
陽菜はまるで我がことのように自慢げに言ったけど、舞楽にはなぜ自慢するようなことなのかピンとこない。気の抜けた返事を返すしかなかった。
「ひなたはね。わたしが育てたの」
「先輩が?」
「ええ。うちでは代々、生まれた子ウシの一頭を残して新しい乳牛にしてきたんだけど、どうも、難産の家系らしくてね。お産にはいつも苦労するのよ。この子もかなりの難産の末にやっと生まれたものだから体質が弱くてね。最初はお乳も満足に飲めないぐらいだったの」
「そうなの?」
大きくで頑丈そうに見えるけど。
「それで、まだ入りたての新人だったわたしに世話係がまわってきたってわけ。知らないことばかりで不安だったけどね」
「そうだったの?」
「当たり前よ。そりゃあ、あなたよりは動物に慣れていたとは思うけど、それでも、きちんと世話をするなんてはじめての体験だったもの。何をするにも『これでいいの?』、『まちがってない?』って、そればっかりで夜も眠れないほどだったわ」
「へえ」
「それでも、とにかく、毎日まいにち、ブラシをかけたり、お湯で温めたり、手ずからミルクを飲ませたりして必死に世話をしたわ。おかげで体力もだんだんついてきて、いまでは毎日きちんとお乳を出してくれて、子供も毎年、生んでくれる立派な乳牛になったわけ。
逆に言うと、ひなたこそわたしの師匠というわけ。ひなたの世話をするためにめいっぱい勉強したものね。おかげでどうにか成長できた。つまり、ひなたはわたしにとって子供であると同時に、育ての親でもあるってわけ」
なるほど。それなら我がことのように自慢するのも当然だ。
「大事なウシなのね」
「そう。とても大切な相手よ。と言うわけで、はい」
と、陽菜は舞楽に大きなブラシを差し出した。
「今日からあなたがひなたの世話をしてね」
「わたしが?」
「ええ」
「いいの? 大事なウシをわたしに任せて。わたし、ウシの世話なんてしたことないけど」
「だからやってもらうのよ。ここでの仕事を覚えてもらうためにね。ひなたの世話ができれば他のクマリたちの世話もできるから」
そういうものか。ともかく、ここで働くことになったのだ。雇い主の采配に文句はつけられない。舞楽はブラシを受け取った。
「それじゃまず、そのブラシでマッサ―ジしてあげて」
「はい」
舞楽はブラシを手にひなたに近づいた。ところが――。
いきなりだった。いきなりひなたが頭を振るって舞楽に襲いかかった。舞楽はとっさに後ろに飛んでよけた。舞楽だから無事ですんだけど普通の女の子だったら吹っ飛ばされているところだ。
「ひなた!」
陽菜が叫んだ。あわててひなたに抱きついてなだめた。
「どうしたの? だいじょうぶ、だいじょうぶ。危ないことなんか何もないから、ねっ?」
陽菜は必死に落ち着かせようとした。ところが、ひなたの警戒は解ける様子もない。舞楽に向かって頭をさげ、四肢を踏ん張り、いまにも襲いかからんばかりの態度。目にははっきり敵意が燃えている。
「……なんか、メチャクチャきらわれてるみたいなんだけど」
「う~ん。まあ、ひなたも神経質なところがあるから。知らない人に会って警戒してるんだと思う。おまけに妊娠中だからよけいピリピリしてるのね。わたしが押さえているからとにかくマッサ―ジしてあげて。慣れれば落ち着くと思うから」
「はい」
舞楽は改めてブラシを手に近づいた。ひなたは威嚇のうなり声を上げている。いきなり襲われた直後にこの態度。普通の女の子なら怖くて震え上がるところだ。しかし、そこは木花舞楽。怖い物知らずの性格で平気で近づき、ブラシをかける。陽菜がそばにいるせいか、ひなたは今度は襲うような真似はしなかった。と言っても、警戒を解く様子はない。
「ダメダメ。もっと力を入れて」
「いいの? わたし、けっこう力ある方だけど」
「相手は人間じゃないのよ。分厚い皮膚に覆われた動物なの。遠慮してたら何にも感じないわ。ゴシゴシこするぐらいでちょうどいいのよ」
そういうものか。ならば、と言うことで舞楽は力を込めてこすりはじめた。
「そう、その調子。ひなたは背中をブラッシングしてもらうのが大好きなの。毎日ブラッシングしてあげてればあなたのことも好きになってくれるわよ」
「別に好きになってもらいたいとは思わないけど」
その一言に陽菜はキッと舞楽を睨み付けた。今回ばかりは本気で怒っている。
「何を言ってるの。クマリは人の心に敏感なの。敵意をもって近づいてくる相手には敵意を返すし、好意をもって近づいてくる相手には好意を返す。あなたはいままで相手の気持ちなんて考えずに生きてきたみたいだけど、ここで働く以上、そんな態度は通用しない。相手のことを思って、考えて、好かれるように努力しなさい。いいわね?」
「好かれなくたって世話さえすればいいんでしょ」
「その態度が通用しないと言ってるのよ。クマリは機械じゃないの。生き物なの。心のこもっていない形ばかりのお世話じゃまともに育たないし、健康にだって影響する。人間の赤ん坊だって愛情抜きで育てられたらまともには育たないでしょう。それと同じよ」
「赤ん坊なんて育てたことないし」
「いちいち口答えしない!」
本気の雷だったけど、だからといって傷ついたり、怯えたりするような可愛げのあるタマではない。平然と肩をすくめただけだった。とにかくブラッシングをつづける。
「黙ってやってちゃダメ。きちんと話しかけて」
「動物相手に話しかけてどうするのよ。言葉なんか通じないでしょ」
「言葉が通じるとか通じないとかそういう問題じゃないの。話しかけるというのは相手に興味をもっているというメッセ―ジなんだから。動物でも、植物でも、いちいち話しかけて興味をもっていることを伝えるのはとても大切なことなの。話しかけるかどうかで育ちが全然ちがうんだから」
「そういうものなの?」
「そういうものなの。そのことはeFREEガ―デンの歴史のなかで確認されているんだから」
「え~と、それじゃあ……って、なにを話せばいいの?」
「何でもいいわよ。大切なのは話しかけること。内容は二の次でいいわ」
「それじゃあ……え~と、ひなた? わたしは木花舞楽、一四歳。なぜか過去の世界からきちゃったんだけど……」
とにかく、思いつくままに話しかけた。こんなことで本当にどうにかなるとは思わなかったけど。
ブラッシングを終えると次は乳搾り。と言っても、乳を搾るのは素人にはむずかしいし、ヒツジたちはともかくひなたは舞楽には決して乳首をさわらせようとはしなかった。無理に搾ろうとすれば後ろ足を振りまわし、蹴りつけようとする始末。そのあまりに激しい抵抗に陽菜もさすがにあきらめた。
「これじゃ、いくら舞楽でも危ないわね。ひなたもストレスが強すぎるし。仕方ないわ。乳搾りはわたしがやるから舞楽は卵を集めて倉庫にもっていって。それが終わったらバケツを洗っておいて」
「はい」
何とも釈然としないものを感じながら舞楽は指示に従った。ニワトリやカモが巣にしている場所から卵を集め、バケツを洗う。これは熱湯消毒も兼ねていて、もうもうと湯気を立てる熱湯のプ―ルにバケツを沈めて柄の長いブラシでゴシゴシこするという豪快なもの。冬なら天国と思えるかも知れないけど、夏にやるにはちょっとつらい。もうもうたる湯気に包まれ、たちまち全身汗だくになってしまう。それでも一度引き受けたことはきちんとやるのが木花舞楽。文句ひとつ言わずにきちんと洗い、日に干して乾かしていく。
乳搾りが終わると放牧の時間。と言っても、食事を終えたものから勝手に農地のなかに出ていくだけ。ヒツジたちは畝の間の通路を歩いて草を食み、ニワトリたちはそのあとをチョコチョコついていく。ニワトリたちの目当てはヒツジが草を食べることで追い出された虫たちだ。虫たちは栄養たっぷりで、ニワトリたちは様々な虫をバランスよく食べて健康に育つ。おまけに害虫退治にもなる。カモたちも勝手に田んぼに行き、水の上をスイスイ泳ぐ。イヌたちは辺りを走り回り、ネコたちは日だまりで丸くなる。まったく、それぞれの性格がよく出ていて見ていて笑えてくるほどだ。
ただし、ウシとブタだけは農地には放さない。周りを囲む樹林帯に連れて行く。
「体の大きいウシには畝間の通路はせまいし、畝の上の作物に口が届いちゃうから。ブタはブタで何でも掘り返す習性があって、丈夫な鼻先で穴だらけにしちゃうし、畝を崩しちゃうから。それに、木の実をたくさん食べて育ったブタの肉って脂が甘くてすごくおいしいのよ!」
とのことだった。
「と言うわけで、よろしくね。舞楽。わたしはすぐにミルクを加工しなきゃいけないから、ひなたとブタたちを樹林帯に連れて行って」
と、陽菜は舞楽にリ―ドを手渡した。
「連れて行くだけでいいの?」
「ええ。樹林帯に放しさえすれば、あとはそれぞれ好きなように過ごすから。ただし、リ―ドは必ず外して持ち帰ってね。つけたままだと体に絡んだりすることがあるから。ああ、それと、農地と樹林帯は柵で遮られているんだけど、扉の鍵を閉め忘れないようにね。必ず声に出して確認して。開けっ放しだと農地の方に入り込んできちゃうから。それだけは徹底して」
「はい」
舞楽は答えてリ―ドを受け取った。ひなたたちを樹林帯に連れて行こうとする。ところが――。
「……全然、動かないんだけど」
ひなたは四肢を踏ん張り、てこでも動こうとしない構え。舞楽は力の限りリ―ドを引いたけど、ビクともしない。当たり前だ。いくら舞楽がこの年齢の女の子としては驚くほどの力持ちとは言え、相手は体重四〇〇キロを超える四足獣。力ずくで引っ張っていけるわけがない。
もともと、動物との相性は悪い。よく馴れた飼い犬でさえ、舞楽が相手となると吠えるか、逃げるか、どちらかだった。舞楽は舞楽で子供と動物はきらいな質。好かれたいと思ったこともないし、小鳥一羽飼ったこともない。……面倒を見るのは母親だけで充分だったし。
でも、だからって、どうしてここまできらわれるのか。いつもの場所に連れて行くだけなのに。動物ってリ―ドを引っ張ればついてくるものなんじゃなかったの?
舞楽は無理やり引っ張っていこうとし、ひなたは頑として抵抗をつづける。ひとりと一頭の綱引きがしばらくつづいた。
やがて、陽菜がため息をついた。頭を振りながらひなたに近づく。そっと手を添えてやさしく語りかける。
「だいじょうぶよ、ひなた。彼女は敵じゃない。わたしたちの新しい仲間。だから、そんなに警戒しないで。ねっ?」
それから舞楽に目を向けた。
「ほら、舞楽。あなたもちゃんと話しかけて」
「え、え~と、ほら、ひなた。別にとって食おうなんてわけじゃないから。いつもの所に行くだけだから。だから、おとなしくついてきて」
ふたりしてさんざん話しかけてようやくひなたは歩き出した。それでも、警戒心は丸出しでちょっと気をそらすとすぐに立ち止まって動かなくなる。舞楽は必死に話しかけつつ、四苦八苦しながら連れて行く。その様子を見て陽菜はため息をついた。
「想像以上にやっかいみたいね。舞楽が早く相手を思いやる気持ちをもってくれればいいんだけど」
とにかく、どうにかこうにかやっとの思いでひなたと二頭のブタを樹林帯に連れ出した。柵の扉を開けて外に出し、リ―ドを外す。その途端、ひなたは駆け出した。一秒だってこんなやつのそばにはいたくないと言わんばかりのその態度。ウシが走るところなんてはじめて見る舞楽は呆気にとられてその後ろ姿を見送った。
きらわれたからと言って傷つくようなタマではない。何しろ、生まれた頃から妬みそねみにやっかみをぶつけられ、動物どころか人間の敵意に囲まれて生きてきたのだ。きらわれるのにはとっくの昔に慣れている。というより、きらわれることこそ舞楽にとっては普通のことだった。だから、いくらきらわれたって気にしたりはしない。でも――。
「……おもしろい気分じゃないわよね、やっぱり」
陽菜に言われたとおり、扉の鍵をかけたことを声に出して確認し、倉庫に戻った。そこでは、陽菜がチ―ズ作りの真っ最中だった。量の少ないヒツジのミルクはそのまま飲用としてボトルにつめ、量の多いウシのミルクでチ―ズを作る。まず、ミルクを殺菌し、乳酸菌を入れる。しばらくしてから凝固剤を入れて静置。ミルクが固まったらホエ―とカ―ドにわける。このカ―ドがチ―ズの原型となる。カ―ドに冷水をかけて冷やし、乳酸菌の働きを抑える。さらにこまかく砕いて九〇度の塩水のなかで練る。湯を捨てて弾力と艶が出るまでさらに練る。丸くちぎってすぐに流水に入れて冷まし、薄い塩水と一緒にパッケ―ジ。
「へえ、チ―ズってこうやって作るんだ。はじめて見た」
『資格がないから』というもっともな理由で関わらせてもらえなかったけど、作り方を見ているだけでも興味深い。家事担当として自分でも作ってみたくなった。
「一口にチ―ズと言ってもいろいろあるから、チ―ズによって、人によって、作り方もいろいろだけどね。これは我が『ひのきファ―ム』に伝わるモッツァレラチ―ズの作り方。はい、どうぞ、食べてみて」
と、陽菜はできたてのモッツァレラチ―ズを舞楽に手渡した。
「いいの? 売り物なんでしょう?」
陽菜は笑った。
「少しぐらいかまわないわよ。どうせ、全部売れるわけじゃないしね」
言いつつ、陽菜は自分でも丸くちぎったチ―ズを口のなかに放り込んだ。
それを見て舞楽も食べてみた。とたんに目を丸くした。
「おいしい」
「でしょ? でしょ?」
できたてのチ―ズを食べたのなんてはじめてだけど、こんなにおいしいものとは知らなかった。ミルクの風味たっぷりで、ジュ―シ―で、自然な甘さが感じられる。自分の時代で食べていたチ―ズとはまったくの別物だった。
「フレッシュチ―ズは鮮度が命。できたてが一番おいしいの。よそには絶対、負けないわ」
陽菜がそう胸を張るのも納得のおいしさだった。
作るのはチ―ズだけではない。その合間にパンやクッキ―も焼き、おにぎりと卵焼きを作って弁当にする。これはアパ―トの住人から夕べのうちに注文を受けて作るのだという。
弁当を包むパッケ―ジは稲藁のシ―ト。シ―トの上におにぎりと卵焼きまを並べ、手慣れた動作で包んでいく。稲藁のシ―トは農作業が少なくなる冬の間に自分で編んだものだという。
「デイリ―メイドってそんなことまでするんだ。大変なのね」
「そうでもないわよ。一連の流れのなかでけっこう自然にできちゃうものよ。それに、一番手間のかかる収穫作業が住人任せだからその分、時間があるのよ」
稲藁は他にもペット用の敷き藁としても使われるし、ネコ用の小さな家を作って売ったりもする。『ひのきファ―ム』の場合は伝統的に稲藁細工だけど、ファ―ムによってはタリスマンやアミュレットといった魔術の護符を作っているところもあるとか。
どれも、eFREEガ―デンで採れた植物から作られているので使い終わったあとにはそのへんに放り出しておけばクマリたちによって食べられ、新しい生命を育む養分となる。舞楽の時代の農業は金を払って肥料を買っていたけど、この時代では肥料をレンタルして稼いでいる。
「やっぱり先輩だったのね。そんなにいろいろできるなんて。見直したわ」
素直なような、失礼なようなことを言う舞楽を陽菜はじっと見つめた。
「なに?」
「怒ってる?」
「なんで?」
陽菜の言葉に舞楽はキョトンとした。
「だって……さっき、けっこうきついこと言っちゃったし」
「なんで? 先輩として言うべきことを言っただけでしょう?」
「それはそうなんだけど」
「なら、いいじゃない。新人が注意されるのは当たり前だし、先輩が気を遣う必要ないわ」
「……舞楽ってけっこう図太い?」
「よく言われる」
その答えに陽菜は吹き出した。
「ならいいわ。あなたにそういう心配はいらないみたいね。じゃあ、これからもビシビシ行くわよ。一人前に育てるのが先輩としての役目だものね」
「よろしく、先輩」
「ではさっそく。怒っているわけでもないのにさっきみたいな態度はとらない方がいいわよ」
「なんで?」
本気でキョトンとする舞楽に陽菜はため息をついた。
「……まあ、いいか。あなたの外見なら許されそうだし。とにかく、朝ご飯にしましょう。お腹減ったでしょう?」
言われて舞楽は自分が恐ろしく腹を空かせていることに気がついた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

【完結】緑の奇跡 赤の輝石
黄永るり
児童書・童話
15歳の少女クティーは、毎日カレーとナンを作りながら、ドラヴィダ王国の外れにある町の宿で、住み込みで働いていた。
ある日、宿のお客となった少年シャストラと青年グラハの部屋に呼び出されて、一緒に隣国ダルシャナの王都へ行かないかと持ちかけられる。
戸惑うクティーだったが、結局は自由を求めて二人とダルシャナの王都まで旅にでることにした。
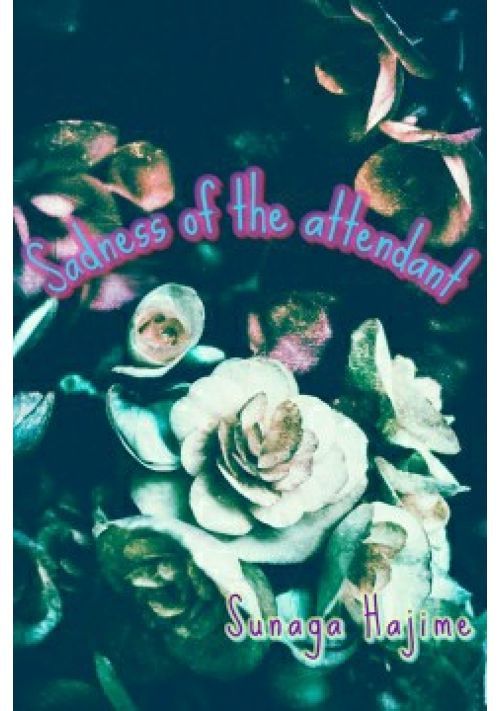
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

宝石アモル
緋村燐
児童書・童話
明護要芽は石が好きな小学五年生。
可愛いけれど石オタクなせいで恋愛とは程遠い生活を送っている。
ある日、イケメン転校生が落とした虹色の石に触ってから石の声が聞こえるようになっちゃって!?
宝石に呪い!?
闇の組織!?
呪いを祓うために手伝えってどういうこと!?

王女様は美しくわらいました
トネリコ
児童書・童話
無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。
それはそれは美しい笑みでした。
「お前程の悪女はおるまいよ」
王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。
きたいの悪女は処刑されました 解説版

忠犬ハジッコ
SoftCareer
児童書・童話
もうすぐ天寿を全うするはずだった老犬ハジッコでしたが、飼い主である高校生・澄子の魂が、偶然出会った付喪神(つくもがみ)の「夜桜」に抜き去られてしまいます。
「夜桜」と戦い力尽きたハジッコの魂は、犬の転生神によって、抜け殻になってしまった澄子の身体に転生し、奪われた澄子の魂を取り戻すべく、仲間達の力を借りながら奮闘努力する……というお話です。
※今まで、オトナ向けの小説ばかり書いておりましたが、
今回は中学生位を読者対象と想定してチャレンジしてみました。
お楽しみいただければうれしいです。


こちら御神楽学園心霊部!
緒方あきら
児童書・童話
取りつかれ体質の主人公、月城灯里が霊に憑かれた事を切っ掛けに心霊部に入部する。そこに数々の心霊体験が舞い込んでくる。事件を解決するごとに部員との絆は深まっていく。けれど、彼らにやってくる心霊事件は身の毛がよだつ恐ろしいものばかりで――。
灯里は取りつかれ体質で、事あるごとに幽霊に取りつかれる。
それがきっかけで学校の心霊部に入部する事になったが、いくつもの事件がやってきて――。
。
部屋に異音がなり、主人公を怯えさせる【トッテさん】。
前世から続く呪いにより死に導かれる生徒を救うが、彼にあげたお札は一週間でボロボロになってしまう【前世の名前】。
通ってはいけない道を通り、自分の影を失い、荒れた祠を修復し祈りを捧げて解決を試みる【竹林の道】。
どこまでもついて来る影が、家まで辿り着いたと安心した主人公の耳元に突然囁きかけてさっていく【楽しかった?】。
封印されていたものを解き放つと、それは江戸時代に封じられた幽霊。彼は門吉と名乗り主人公たちは土地神にするべく扱う【首無し地蔵】。
決して話してはいけない怪談を話してしまい、クラスメイトの背中に危険な影が現れ、咄嗟にこの話は嘘だったと弁明し霊を払う【嘘つき先生】。
事故死してさ迷う亡霊と出くわしてしまう。気付かぬふりをしてやり過ごすがすれ違い様に「見えてるくせに」と囁かれ襲われる【交差点】。
ひたすら振返らせようとする霊、駅まで着いたがトンネルを走る窓が鏡のようになり憑りついた霊の禍々しい姿を見る事になる【うしろ】。
都市伝説の噂を元に、エレベーターで消えてしまった生徒。記憶からさえもその存在を消す神隠し。心霊部は総出で生徒の救出を行った【異世界エレベーター】。
延々と名前を問う不気味な声【名前】。
10の怪異譚からなる心霊ホラー。心霊部の活躍は続いていく。

みかんに殺された獣
あめ
児童書・童話
果物などの食べ物が何も無くなり、生きもののいなくなった森。
その森には1匹の獣と1つの果物。
異種族とかの次元じゃない、果実と生きもの。
そんな2人の切なく悲しいお話。
全10話です。
1話1話の文字数少なめ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















