12 / 26
一二章
意外とまともな先輩
しおりを挟む
陽菜の、というより『ひのきファ―ム』の経営者の家はアパ―トのすぐ隣に建っていた。普通の家を二件、横に並べたぐらいの大きさの左右対称の作りをした家だった。柔らかいアイボリ―色の外壁と大きく張り出したテラスが印象的だった。
「大きな家ね。ここにひとりで住んでるの?」
「本来なら経営者とその後継者の二家族で使うことを前提とした作りだから。おかげでひとりになっちゃってからさびしくて仕方なかったわ。とにかく入りましょう。渡しておくものもあるしね」
ふたりは家のなかに入った。玄関を入ったそこは土がむき出しの広い空間となっていた。
「うわっ。これ、土間ってやつ? はじめて見た」
「農家の家だから、雨や雪の日でも屋外作業ができるよう、土間が用意されているのよ」 「なるほど」
広い土間の左右と正面の三方向には縁側が付いている。正面は和風の襖で仕切られており、左右は広々としたフロ―リングの居間につながっていた。
「この土間をはさんで同じ作りの家が二件、つながっているわけ。バス・トイレ・キッチンもそれぞれに付いているのよ」
なるほど。それなら二家族がお互いの生活のペ―スを守りつつ、同居していける。
「あと、そばにあった建物は作業小屋兼倉庫」
「倉庫? ずいぶん小さく見えたけど」
「地下倉庫になってるのよ」
「ああ、なるほど」
「とにかく、居間にあがって。いまは東側しか使ってないからそっちの方にね」
「はい」
居間は一階部分の半分を占める広々とした空間。南側は一面、窓ガラスになっており、光がたっぷり入る。庭に広がる緑のカ―テンが目にまぶしい。部屋の真ん中にはシンプルだけど丁寧な作りのテ―ブルが置かれている。家具といえばそれぐらい。他にはテレビひとつない。
「やけに家具が少ないのね。もしかして貧乏?」
「……あなた、友だちいる?」
「別にいらない」
「貧乏なんじゃなくていらないのよ。これがあるから」
と、陽菜はA4版の紙ぐらいの大きさをしたものをとりだした。メタリックな光沢をもつポスタ―のようなもの。陽菜が左腕に巻いているのと同じものだ。
「はい、これ」
「なに?」
「Lebabよ」
「リ―バブ?」
「そう。この時代の携帯端末。いまは映像も本も音楽もネットからダウンロ―ドして利用するのが普通だし、支払いも電子マネ―が主流。つまり、Lebabさえあれば他は何もいらないってわけ」
決して貧乏だから家具がないわけじゃないのよ。
陽菜はその点を――怪しく感じられるほど強く――主張した。
「以前いた先輩の使っていた仕事用のものだから、仕事に必要なアプリやデ―タは全部入っているわ。ここで働く以上、あなたにも使い方を覚えてもらわないといけないから」
舞楽はLebabを受け取り、真っ黒な表面にふれてみた。たちまち表面が明るい色にかわり、画面が現われる。画面下半分には舞楽にも馴染みのある配列そのままのキ―ボ―ドが表示されている。試しにキ―ボ―ドにふれてみると指が画面に吸い付くような感触がして画面上部に字が表示される。なるほど。これならタブレット感覚で扱える。
陽菜に言われて本をダウンロ―ドしてみた。画面いっぱいにペ―ジが表示された。Lebabを曲げることでペ―ジをめくれるし、強く曲げれは曲げただけ、パラパラと音を立ててペ―ジがどんどんめくれていく。その感覚はまさに本そのもの。
「でも、携帯端末にしては大きくない? 薄すぎで逆に扱いずらそうだし」
「いくらでも曲げたり、折ったりできるから、小さくたたんで持ち運べばいいのよ。普通はすぐに使えるように腕に巻き付けるか、ちょっと気取って、たたんでパンツの後ろにはさんだりもするわね」
陽菜に言われて舞楽は試してみることにした。左の袖をまくり、Lebabを巻き付ける。どういう仕組みなのか巻き付けただけなのにピッタリ肌に吸い付き、動かない。
一方の端を腕に巻き付けたまま、もう一方の端を伸ばすと、まるで腕からモニタ―が出ているように見える。その態勢のまま片手で楽々、操作が可能。何だか、SFアニメに出てくるアンドロイドになった気分だった。
「へえ。これは便利」
「でしょう?」
と、陽菜。やっぱり、自分が発明したかのように偉そうだ。
「でも、Lebabって変な名前ね。どういう意味?」
舞楽が尋ねると、陽菜はイタズラっぽい笑みを浮かべた。
「わからない?」
「なにが?」
「ちょっとしたしゃれなのよ」
「しゃれ?」
「L・E・B・A・B。逆さにするとB・A・B・E・L、つまり、バベル」
「あっ」
「神の怒りにふれ、言葉をバラバラにされたというバベルの塔の伝説。その伝説にちなんで生森遠見が名付けたのよ」
「これ一枚あれば世界中の人と話ができるから?」
「あ~、それがその……そういうわけじゃなくって」
「なに?」
陽菜は言いずらそうに目をそらした。純真な子供の善意に満ちた答えに後ろめたさを感じるおとなの表情。いかにも気まずい様子で頬などかいてみる。
「Lebabの普及でみんなが自分の世界にこもりきりになり、個々人はバラバラになるにちがいない! っていう理由で名付けたとか……」
舞楽は思わず吹き出した。
「たしかにしゃれの効いている人みたいね、生森遠見って」
「悪もんだから」
ひとしきり、ふたりして笑ったあと、陽菜は表情を改めた。
「さて。それじゃいまからさっそく働いてもらうわけだけど、だいじょうぶ?」
「もちろん」
舞楽は迷いなく断言した。体力はある。徹夜にも慣れている。できない理由は見当たらない。
「じゃあ、まずはこれに着替えて。うちの制服よ」
陽菜がそう言って――やけに嬉しそうに――衣服一式を差し出してきたときには早まったような気もしたけれど。
ともかく、脱衣場に向かって着替えることにした。制服を着て戻ってきた舞楽を見て陽菜の喜ぶまいことか。
「すごい! かわいい! 完璧!」
『ひのきガーデン』の制服とはロングのワンピ―スにフリフリのフリルのついた純白のエプロン、それに紐付きのつば広帽子……と、まごうかたなきメイド服だった。
陽菜は絶賛の声を連呼して舞楽に抱きついた。あまりに勢いよく抱きつかれたので舞楽は一瞬、息ができなくなったほどだ。
メイド服を着た舞楽はたしかにかわいい。何を着てもかわいいし、何も着ないともっとかわいいのだけど、メイド服を着ると持ち前の『レモンとソ―プのような』清潔感と気品がいっそう際立ち、まさに『清純な田園美の体現』といった印象。一目見て誰もがそのまま絵にして飾っておきたいと思う魅力に満ちている。そのことはもちろん舞楽も自覚している。でも、だからって、
「あ~もう、かわいい、かわいい、かわいい! この見た目だけでもう全部、許しちゃう!」
などと大はしゃぎしながら抱きついて、ほおずりしまくらなくてもいいと思うのだ。
「ああ、もう! いいかげんにして!」
舞楽は力ずくで陽菜を引きはがした。
「なにを騒いでるのよ。ただの仕事着にそこまではしゃがなくてもいいでしょ」
「何言ってるの⁉」
と、陽菜は拳を握りしめて力説する。
「いい? デイリ―メイドは特別なの、ただのメイドじゃないのよ。数あるメイド職のなかでただひとつ、女主人が自らその役を担った誇り高い役職なのよ。他のメイドの仕事派は貴族や女主人にふさわしい場所とは見なされなかったけど、酪農室だけは別だったんだから! かのマリ―・アントワネットでさえ、ヴェルサイユ宮殿のなかに小さな村を作ってデイリ―メイドに扮したほどなのよ。その存在は清純さの象徴としてあまたの作品に取り上げられた。つまり! デイリ―メイドこそ数百年の伝統をもつ由緒正しい萌えなのよ!」
――やっぱり、重度のオタクか、この人。
何かというと芝居がかるその態度からそうではないかと疑っていたけど、やっぱりそうだった。舞楽は深々とため息をついた。
「はいはい、わかった、わかったから先輩も早く着替えて。農場の仕事は早いんでしょう? グズグズしてられないはずよ」
だらしない母親とふたり暮らしとあって年上相手に叱るのは慣れている舞楽だった。
「あ、そうね」
と、陽菜はようやく我に返ったようだった。
「これから毎日、このかわいい姿を拝めるんだもの。今日だけでお腹いっぱいになっちやったらもったいないわよね。少しずつ楽しまないと」
そう言い残し、鼻歌など歌いながら脱衣場に向かう陽菜を見て――。
舞楽はいま一度深いふかいため息をついたのだった。
外に出るとそこには目の覚めるような光景が広がっていた。時刻は早朝。地平線のはるか向こうから夏の太陽が顔を見せはじめたところだった。東の空が朝焼けに染まり、朝の光がうすい幕となってはじまりの大地を照らし出す。差しはじめたばかりの朝日は杜を覆う夜の闇を徐々に吹き払い、世界を黄金色に染めあげていく。生い茂る樹木が、生えそろう草が、実り豊かな作物が、朝日を浴びて輝きはじめる。
「……すごい」
舞楽は思わずつぶやいていた。
「どう? きれいでしょ?」
「ええ」
舞楽は心からうなずいた。
「わたしも毎朝、感動するもの。この光景を見られるだけでもこの仕事についた甲斐があったと思えるわ」
その言葉に舞楽はうなずいた。
「よくわかる。経営者の性癖がどうでも、世界は美しく輝くのね」
「……あなた、友だちいる?」
「別にいらない」
すっかり定番になったやりとりを経てふたりは倉庫に向かった。陽菜が指折り数えながら説明する。
「朝起きて最初の仕事はクマリたちのお世話ね」
「家畜のことね」
「家畜じゃなくてクマリ」
と、陽菜はあくまでその点にこだわった。
「杜の動物たちは杜の生態系を守り、わたしたちに日々の糧を与えてくれる大事な存在。『家畜』なんて言う見下した言葉はぜったいに使っちゃダメ。あくまでも敬意を込めて『クマリ』と呼ぶこと。いいわね?」
「……はい」
舞楽はそう答えはしたもののしょせん、動物たちを家畜として利用してきた時代の人間。陽菜がそこまで怒り、強調する理由まではわからなかった。
「では、そういうことで」
と、陽菜は咳払いをひとつしてからつづけた。
「まずはその生神たるクマリたちにご飯をあげて、マッサ―ジして、体調をチェックして、乳しぼりに卵の回収。それが、朝一番の仕事」
倉庫のなかには蓋付きのバケツがいくつも置かれていた。子供の背丈ほどもある大きなバケツを、しかし、舞楽は軽々ともちあげる。それを見て陽菜が目を丸くした。
「すごい。スリムなくせに力あるのね」
「一応、体操部だから」
何とも気乗りのしない答え方だった。『一応』と言うのは所属はしているけどあまり本気ではやっていないから。
もともと、体操がやりたかったわけではない。とにかく、エネルギ―がありあまって使い道がなかったので、何か運動をせずにはいられなかったのだ。と言って、団体競技なんて性に合わない。ひとりでできるものがいい。格闘技やテニスなら一対一だけど、わざわざ他人と勝負する気もない。
となるとあとは陸上や水泳、あるいはダンス系、そして、体操。陸上や水泳は動きが単調だからすぐに飽きそうだった。ダンスは複雑な動きはできるけど、こちらも団体での演舞がある。それに、小学生の頃に近所にバレエ教室があったので通っていたし。
似たようなことをしてもつまらないと思った。結局、ひとりでできて、他人と勝負することなく、むずかしくて複雑な動きができる、そして、いままでにしたことのないこと。
それらのワガママいっぱいの要求を満たしてくれるのは体操だけだったのだ。そういうわけだから本気で体操に打ち込む気なんて最初からなかった。とにかく、あふれるエネルギ―さえどうにかできればそれでよかった。そして、何より――。
いい加減うんざりしているパタ―ンに襲われた。入部早々、異次元の身体能力を見せつける舞楽に顧問の教師がすっかり舞いあがってしまった。
『ぜひ、オリンピック選手に!』
『自分の手でオリンピック選手を育てる』という夢を見てしまったのだろう。舞楽の両肩をガシッとつかみ、燃える瞳でそう言ったものである。舞楽がまるで興味なしなのを見るとことあるごとに誘い、『せっかくの素質をなんで生かそうとしないの』としつこく説教してくる。家にも押しかけて『ぜひ、将来のオリンピック選手としての教育を!』と、詰め寄る始末。その態度にすっかり嫌気がさしてしまった。だから、練習にもあまり出なかった。最近ではすっかりごぶさただ。ただ、あふれるエネルギ―は何とかしないといけないので、人目に付かない近所の空き地などでひとりで床体操の真似事をしている。
「ひとりでやってるの? 危なくない?」
「べつに。練習用の動画を見ればだいたいわかるし。いままで、怪我したことはないわ」
「すごい。本当に完璧超人ね」
「よく言われる」
『性格以外は』ってね。
舞楽はそう付け加えた。その一言に――。
陽菜は『うんうん』とうなずいたのだった。
ふたりはバケツをもってクマリたちのもとに向かった。と言っても、小屋はおろか、柵さえもない。農場の一角に空き地があって、そこにみんなでより集まっている。
「こんなんで逃げたりしないの?」
「だいじょうぶよ。朝夕二回、ここでご飯がもらえるってみんなわかってるから。昼間はあちこち遊びに行ってるけど、夕方にはちゃんと戻ってきて朝までおとなしく寝ているわ」
「へえ」
ふたりが近づくとニワトリたちが一斉に羽をバタバタさせながら走り寄ってきた。少しでも早く食事をもらおうと足下をさかんにつつく。それが合図のようにウシやらブタやらヒツジやら、それに、イヌやネコまでよってくる。ウシが一頭にブタが二頭、ヒツジが四頭、ニワトリ一〇〇羽にカモ五〇羽。そして、イヌが二頭にネコ三匹。それが『ひのきファ―ム』のクマリたち。これだけの数の動物たちが一斉に押しよせ、まわりを取り囲むのだ。ちょっとした動物パニック映画に出演している気分になった。
「はいはい、まって、まって。いまあげるから」
陽菜は困ったように、それでもうれしそうに笑いながらバケツの蓋を取り、中身を次々と開けていった。種類によって与える食事内容はちがうのでそれぞれの『食卓』は決まっている。まちがえないよう、バケツはすべて色違いで、それぞれのクマリの顔をデフォルメしたマ―クも蓋と側面に大きく付いている。
ウシとヒツジにはキャベツの芯やダイコンの皮、メロンやスイカの皮など野菜の残り物。その他、熟しすぎたトマトやキュウリ、小さすぎたり、形が悪かったりするカボチャなど。それはわかるけどサツマイモの茎葉やピ―ナッツの殻まであるのには驚いた。
「そんなもの食べさせてだいじょうぶなの?」
「あら。サツマイモの茎葉やピ―ナッツの殻は乳量を増やすご飯として昔から知られているのよ」
「へえ、そうなの。知らなかった」
ウシとヒツジは野菜と果物だけだけど、ブタ、ニワトリ、カモときたらこちらはもう何でも食べる。茶殻に魚のアラや骨、古くなったご飯やパン、イモの皮に漬け物クズ等々、まさに『生ゴミ』のオンパレ―ド。そんなものでもバンバン食べて肉と卵と皮にかえてくれる。これらの生ゴミはアパ―トの住人たちが出したものだけど、彼らも自分の出したゴミが自分の食べる肉や卵になることを知っているので食べさせてはいけないものは混じっていない。
ただし、何でも食べると言っても肉はダメ。雑食と言っても基本的には草食動物だし、何より『共食い』させるのは気分も悪いし、病気の心配もある。と言うわけで、肉類はイヌやネコの分となる。もちろん、彼らは単なる生ゴミ処理係ではない。作物を狙って農地に侵入してくるネズミや野鳥を追い払う警備員なのだ。
クマリたちの食事は種類を問わず、どれもこれもぷうんと甘酸っぱい匂いが漂っていた。舞楽は気になって尋ねてみた。
「これってなんの匂い? まさか、腐ってるわけじゃないわよね?」
「舞楽。冗談でも怒るわよ。大切な仲間に腐ったものなんて食べさせるわけないでしょう」
「だったら、なんの匂い?」
「乳酸菌を混ぜて発酵させてるのよ。その匂い」
なるほど、乳酸菌か。言われてみればたしかにヨ―グルトっぽい匂いという気がする。
「なんでわざわざ発酵させるの?」
「発酵させることで腐るのを防げるのよ。栄養価も増すしね。そして、何より――」
「なにより?」
わざわざ声を潜める陽菜の芝居がかった仕種に、舞楽も思わず身を乗り出す。
「乳酸菌の働きで腸内環境がよくなるからウンチやオシッコの匂いがしなくなる! これ重要!」
グッと拳を握りしめ、真顔で力説する陽菜だった。
なるほど。言われてみればたしかにあちこちに糞の山があるのにいやな匂いはちっともしない。ハエもいない。自然任せで掃除もしないのに清潔そのものといった印象。
「なるほど。隣にアパ―トがあるのにウンチやオシッコの匂いがしてたら困るものね」
「そういうこと。乳酸発酵させた食べ物をあげることで匂いを消す。この技術のおかげでeFREEガ―デンが可能になったのよ」
「なるほど」
うなずく舞楽の前でクマリたちは旺盛な食欲を発揮してどんどん食事を平らげている。 「さて、舞楽。ここで注目」
陽菜が言った。手を叩いて注意を引く。その表情がいつになく真剣だ。
「ただ眺めているだけじゃだめよ。食事の時間はみんなの健康状態をチェックする大事な時間でもあるんだから。よく見て、観察して、異常があったらすぐ報告。いいわね?」
「異常かどうかはどうすればわかるの?」
「そうね」
と、陽菜は食事に夢中のクマリたちを見渡してから言った。
「いまのところはみんな、健康ね。いまの姿を基準として覚えておいて。皮膚や毛の色艶が悪かったり、目やにがたまっていたり、鼻水をたらしていたりしたら要注意。その他、食欲がなかったり、おとなしすぎたりしている場合もね。くわしい病状なんかはLebabに入っているからちゃんと見て覚えておくこと。いいわね?」
「はい」
――まともなところもあったのね、この人。
と、かなり失礼なことを思いながら答える舞楽であった。
「それから、見るだけではダメよ。触って、抱いて、匂いをかいで、話しかけて、五感すべてで判断するの。大切なのはとにかく相手に興味をもつこと、自分から溶け込もうとすること、距離をおいて眺めているだけじゃ何にもわからないから。いいわね?」
「はい」
「よろしい。さて、それじゃ」
と、陽菜はただ一頭のウシに近づいた。
「大きな家ね。ここにひとりで住んでるの?」
「本来なら経営者とその後継者の二家族で使うことを前提とした作りだから。おかげでひとりになっちゃってからさびしくて仕方なかったわ。とにかく入りましょう。渡しておくものもあるしね」
ふたりは家のなかに入った。玄関を入ったそこは土がむき出しの広い空間となっていた。
「うわっ。これ、土間ってやつ? はじめて見た」
「農家の家だから、雨や雪の日でも屋外作業ができるよう、土間が用意されているのよ」 「なるほど」
広い土間の左右と正面の三方向には縁側が付いている。正面は和風の襖で仕切られており、左右は広々としたフロ―リングの居間につながっていた。
「この土間をはさんで同じ作りの家が二件、つながっているわけ。バス・トイレ・キッチンもそれぞれに付いているのよ」
なるほど。それなら二家族がお互いの生活のペ―スを守りつつ、同居していける。
「あと、そばにあった建物は作業小屋兼倉庫」
「倉庫? ずいぶん小さく見えたけど」
「地下倉庫になってるのよ」
「ああ、なるほど」
「とにかく、居間にあがって。いまは東側しか使ってないからそっちの方にね」
「はい」
居間は一階部分の半分を占める広々とした空間。南側は一面、窓ガラスになっており、光がたっぷり入る。庭に広がる緑のカ―テンが目にまぶしい。部屋の真ん中にはシンプルだけど丁寧な作りのテ―ブルが置かれている。家具といえばそれぐらい。他にはテレビひとつない。
「やけに家具が少ないのね。もしかして貧乏?」
「……あなた、友だちいる?」
「別にいらない」
「貧乏なんじゃなくていらないのよ。これがあるから」
と、陽菜はA4版の紙ぐらいの大きさをしたものをとりだした。メタリックな光沢をもつポスタ―のようなもの。陽菜が左腕に巻いているのと同じものだ。
「はい、これ」
「なに?」
「Lebabよ」
「リ―バブ?」
「そう。この時代の携帯端末。いまは映像も本も音楽もネットからダウンロ―ドして利用するのが普通だし、支払いも電子マネ―が主流。つまり、Lebabさえあれば他は何もいらないってわけ」
決して貧乏だから家具がないわけじゃないのよ。
陽菜はその点を――怪しく感じられるほど強く――主張した。
「以前いた先輩の使っていた仕事用のものだから、仕事に必要なアプリやデ―タは全部入っているわ。ここで働く以上、あなたにも使い方を覚えてもらわないといけないから」
舞楽はLebabを受け取り、真っ黒な表面にふれてみた。たちまち表面が明るい色にかわり、画面が現われる。画面下半分には舞楽にも馴染みのある配列そのままのキ―ボ―ドが表示されている。試しにキ―ボ―ドにふれてみると指が画面に吸い付くような感触がして画面上部に字が表示される。なるほど。これならタブレット感覚で扱える。
陽菜に言われて本をダウンロ―ドしてみた。画面いっぱいにペ―ジが表示された。Lebabを曲げることでペ―ジをめくれるし、強く曲げれは曲げただけ、パラパラと音を立ててペ―ジがどんどんめくれていく。その感覚はまさに本そのもの。
「でも、携帯端末にしては大きくない? 薄すぎで逆に扱いずらそうだし」
「いくらでも曲げたり、折ったりできるから、小さくたたんで持ち運べばいいのよ。普通はすぐに使えるように腕に巻き付けるか、ちょっと気取って、たたんでパンツの後ろにはさんだりもするわね」
陽菜に言われて舞楽は試してみることにした。左の袖をまくり、Lebabを巻き付ける。どういう仕組みなのか巻き付けただけなのにピッタリ肌に吸い付き、動かない。
一方の端を腕に巻き付けたまま、もう一方の端を伸ばすと、まるで腕からモニタ―が出ているように見える。その態勢のまま片手で楽々、操作が可能。何だか、SFアニメに出てくるアンドロイドになった気分だった。
「へえ。これは便利」
「でしょう?」
と、陽菜。やっぱり、自分が発明したかのように偉そうだ。
「でも、Lebabって変な名前ね。どういう意味?」
舞楽が尋ねると、陽菜はイタズラっぽい笑みを浮かべた。
「わからない?」
「なにが?」
「ちょっとしたしゃれなのよ」
「しゃれ?」
「L・E・B・A・B。逆さにするとB・A・B・E・L、つまり、バベル」
「あっ」
「神の怒りにふれ、言葉をバラバラにされたというバベルの塔の伝説。その伝説にちなんで生森遠見が名付けたのよ」
「これ一枚あれば世界中の人と話ができるから?」
「あ~、それがその……そういうわけじゃなくって」
「なに?」
陽菜は言いずらそうに目をそらした。純真な子供の善意に満ちた答えに後ろめたさを感じるおとなの表情。いかにも気まずい様子で頬などかいてみる。
「Lebabの普及でみんなが自分の世界にこもりきりになり、個々人はバラバラになるにちがいない! っていう理由で名付けたとか……」
舞楽は思わず吹き出した。
「たしかにしゃれの効いている人みたいね、生森遠見って」
「悪もんだから」
ひとしきり、ふたりして笑ったあと、陽菜は表情を改めた。
「さて。それじゃいまからさっそく働いてもらうわけだけど、だいじょうぶ?」
「もちろん」
舞楽は迷いなく断言した。体力はある。徹夜にも慣れている。できない理由は見当たらない。
「じゃあ、まずはこれに着替えて。うちの制服よ」
陽菜がそう言って――やけに嬉しそうに――衣服一式を差し出してきたときには早まったような気もしたけれど。
ともかく、脱衣場に向かって着替えることにした。制服を着て戻ってきた舞楽を見て陽菜の喜ぶまいことか。
「すごい! かわいい! 完璧!」
『ひのきガーデン』の制服とはロングのワンピ―スにフリフリのフリルのついた純白のエプロン、それに紐付きのつば広帽子……と、まごうかたなきメイド服だった。
陽菜は絶賛の声を連呼して舞楽に抱きついた。あまりに勢いよく抱きつかれたので舞楽は一瞬、息ができなくなったほどだ。
メイド服を着た舞楽はたしかにかわいい。何を着てもかわいいし、何も着ないともっとかわいいのだけど、メイド服を着ると持ち前の『レモンとソ―プのような』清潔感と気品がいっそう際立ち、まさに『清純な田園美の体現』といった印象。一目見て誰もがそのまま絵にして飾っておきたいと思う魅力に満ちている。そのことはもちろん舞楽も自覚している。でも、だからって、
「あ~もう、かわいい、かわいい、かわいい! この見た目だけでもう全部、許しちゃう!」
などと大はしゃぎしながら抱きついて、ほおずりしまくらなくてもいいと思うのだ。
「ああ、もう! いいかげんにして!」
舞楽は力ずくで陽菜を引きはがした。
「なにを騒いでるのよ。ただの仕事着にそこまではしゃがなくてもいいでしょ」
「何言ってるの⁉」
と、陽菜は拳を握りしめて力説する。
「いい? デイリ―メイドは特別なの、ただのメイドじゃないのよ。数あるメイド職のなかでただひとつ、女主人が自らその役を担った誇り高い役職なのよ。他のメイドの仕事派は貴族や女主人にふさわしい場所とは見なされなかったけど、酪農室だけは別だったんだから! かのマリ―・アントワネットでさえ、ヴェルサイユ宮殿のなかに小さな村を作ってデイリ―メイドに扮したほどなのよ。その存在は清純さの象徴としてあまたの作品に取り上げられた。つまり! デイリ―メイドこそ数百年の伝統をもつ由緒正しい萌えなのよ!」
――やっぱり、重度のオタクか、この人。
何かというと芝居がかるその態度からそうではないかと疑っていたけど、やっぱりそうだった。舞楽は深々とため息をついた。
「はいはい、わかった、わかったから先輩も早く着替えて。農場の仕事は早いんでしょう? グズグズしてられないはずよ」
だらしない母親とふたり暮らしとあって年上相手に叱るのは慣れている舞楽だった。
「あ、そうね」
と、陽菜はようやく我に返ったようだった。
「これから毎日、このかわいい姿を拝めるんだもの。今日だけでお腹いっぱいになっちやったらもったいないわよね。少しずつ楽しまないと」
そう言い残し、鼻歌など歌いながら脱衣場に向かう陽菜を見て――。
舞楽はいま一度深いふかいため息をついたのだった。
外に出るとそこには目の覚めるような光景が広がっていた。時刻は早朝。地平線のはるか向こうから夏の太陽が顔を見せはじめたところだった。東の空が朝焼けに染まり、朝の光がうすい幕となってはじまりの大地を照らし出す。差しはじめたばかりの朝日は杜を覆う夜の闇を徐々に吹き払い、世界を黄金色に染めあげていく。生い茂る樹木が、生えそろう草が、実り豊かな作物が、朝日を浴びて輝きはじめる。
「……すごい」
舞楽は思わずつぶやいていた。
「どう? きれいでしょ?」
「ええ」
舞楽は心からうなずいた。
「わたしも毎朝、感動するもの。この光景を見られるだけでもこの仕事についた甲斐があったと思えるわ」
その言葉に舞楽はうなずいた。
「よくわかる。経営者の性癖がどうでも、世界は美しく輝くのね」
「……あなた、友だちいる?」
「別にいらない」
すっかり定番になったやりとりを経てふたりは倉庫に向かった。陽菜が指折り数えながら説明する。
「朝起きて最初の仕事はクマリたちのお世話ね」
「家畜のことね」
「家畜じゃなくてクマリ」
と、陽菜はあくまでその点にこだわった。
「杜の動物たちは杜の生態系を守り、わたしたちに日々の糧を与えてくれる大事な存在。『家畜』なんて言う見下した言葉はぜったいに使っちゃダメ。あくまでも敬意を込めて『クマリ』と呼ぶこと。いいわね?」
「……はい」
舞楽はそう答えはしたもののしょせん、動物たちを家畜として利用してきた時代の人間。陽菜がそこまで怒り、強調する理由まではわからなかった。
「では、そういうことで」
と、陽菜は咳払いをひとつしてからつづけた。
「まずはその生神たるクマリたちにご飯をあげて、マッサ―ジして、体調をチェックして、乳しぼりに卵の回収。それが、朝一番の仕事」
倉庫のなかには蓋付きのバケツがいくつも置かれていた。子供の背丈ほどもある大きなバケツを、しかし、舞楽は軽々ともちあげる。それを見て陽菜が目を丸くした。
「すごい。スリムなくせに力あるのね」
「一応、体操部だから」
何とも気乗りのしない答え方だった。『一応』と言うのは所属はしているけどあまり本気ではやっていないから。
もともと、体操がやりたかったわけではない。とにかく、エネルギ―がありあまって使い道がなかったので、何か運動をせずにはいられなかったのだ。と言って、団体競技なんて性に合わない。ひとりでできるものがいい。格闘技やテニスなら一対一だけど、わざわざ他人と勝負する気もない。
となるとあとは陸上や水泳、あるいはダンス系、そして、体操。陸上や水泳は動きが単調だからすぐに飽きそうだった。ダンスは複雑な動きはできるけど、こちらも団体での演舞がある。それに、小学生の頃に近所にバレエ教室があったので通っていたし。
似たようなことをしてもつまらないと思った。結局、ひとりでできて、他人と勝負することなく、むずかしくて複雑な動きができる、そして、いままでにしたことのないこと。
それらのワガママいっぱいの要求を満たしてくれるのは体操だけだったのだ。そういうわけだから本気で体操に打ち込む気なんて最初からなかった。とにかく、あふれるエネルギ―さえどうにかできればそれでよかった。そして、何より――。
いい加減うんざりしているパタ―ンに襲われた。入部早々、異次元の身体能力を見せつける舞楽に顧問の教師がすっかり舞いあがってしまった。
『ぜひ、オリンピック選手に!』
『自分の手でオリンピック選手を育てる』という夢を見てしまったのだろう。舞楽の両肩をガシッとつかみ、燃える瞳でそう言ったものである。舞楽がまるで興味なしなのを見るとことあるごとに誘い、『せっかくの素質をなんで生かそうとしないの』としつこく説教してくる。家にも押しかけて『ぜひ、将来のオリンピック選手としての教育を!』と、詰め寄る始末。その態度にすっかり嫌気がさしてしまった。だから、練習にもあまり出なかった。最近ではすっかりごぶさただ。ただ、あふれるエネルギ―は何とかしないといけないので、人目に付かない近所の空き地などでひとりで床体操の真似事をしている。
「ひとりでやってるの? 危なくない?」
「べつに。練習用の動画を見ればだいたいわかるし。いままで、怪我したことはないわ」
「すごい。本当に完璧超人ね」
「よく言われる」
『性格以外は』ってね。
舞楽はそう付け加えた。その一言に――。
陽菜は『うんうん』とうなずいたのだった。
ふたりはバケツをもってクマリたちのもとに向かった。と言っても、小屋はおろか、柵さえもない。農場の一角に空き地があって、そこにみんなでより集まっている。
「こんなんで逃げたりしないの?」
「だいじょうぶよ。朝夕二回、ここでご飯がもらえるってみんなわかってるから。昼間はあちこち遊びに行ってるけど、夕方にはちゃんと戻ってきて朝までおとなしく寝ているわ」
「へえ」
ふたりが近づくとニワトリたちが一斉に羽をバタバタさせながら走り寄ってきた。少しでも早く食事をもらおうと足下をさかんにつつく。それが合図のようにウシやらブタやらヒツジやら、それに、イヌやネコまでよってくる。ウシが一頭にブタが二頭、ヒツジが四頭、ニワトリ一〇〇羽にカモ五〇羽。そして、イヌが二頭にネコ三匹。それが『ひのきファ―ム』のクマリたち。これだけの数の動物たちが一斉に押しよせ、まわりを取り囲むのだ。ちょっとした動物パニック映画に出演している気分になった。
「はいはい、まって、まって。いまあげるから」
陽菜は困ったように、それでもうれしそうに笑いながらバケツの蓋を取り、中身を次々と開けていった。種類によって与える食事内容はちがうのでそれぞれの『食卓』は決まっている。まちがえないよう、バケツはすべて色違いで、それぞれのクマリの顔をデフォルメしたマ―クも蓋と側面に大きく付いている。
ウシとヒツジにはキャベツの芯やダイコンの皮、メロンやスイカの皮など野菜の残り物。その他、熟しすぎたトマトやキュウリ、小さすぎたり、形が悪かったりするカボチャなど。それはわかるけどサツマイモの茎葉やピ―ナッツの殻まであるのには驚いた。
「そんなもの食べさせてだいじょうぶなの?」
「あら。サツマイモの茎葉やピ―ナッツの殻は乳量を増やすご飯として昔から知られているのよ」
「へえ、そうなの。知らなかった」
ウシとヒツジは野菜と果物だけだけど、ブタ、ニワトリ、カモときたらこちらはもう何でも食べる。茶殻に魚のアラや骨、古くなったご飯やパン、イモの皮に漬け物クズ等々、まさに『生ゴミ』のオンパレ―ド。そんなものでもバンバン食べて肉と卵と皮にかえてくれる。これらの生ゴミはアパ―トの住人たちが出したものだけど、彼らも自分の出したゴミが自分の食べる肉や卵になることを知っているので食べさせてはいけないものは混じっていない。
ただし、何でも食べると言っても肉はダメ。雑食と言っても基本的には草食動物だし、何より『共食い』させるのは気分も悪いし、病気の心配もある。と言うわけで、肉類はイヌやネコの分となる。もちろん、彼らは単なる生ゴミ処理係ではない。作物を狙って農地に侵入してくるネズミや野鳥を追い払う警備員なのだ。
クマリたちの食事は種類を問わず、どれもこれもぷうんと甘酸っぱい匂いが漂っていた。舞楽は気になって尋ねてみた。
「これってなんの匂い? まさか、腐ってるわけじゃないわよね?」
「舞楽。冗談でも怒るわよ。大切な仲間に腐ったものなんて食べさせるわけないでしょう」
「だったら、なんの匂い?」
「乳酸菌を混ぜて発酵させてるのよ。その匂い」
なるほど、乳酸菌か。言われてみればたしかにヨ―グルトっぽい匂いという気がする。
「なんでわざわざ発酵させるの?」
「発酵させることで腐るのを防げるのよ。栄養価も増すしね。そして、何より――」
「なにより?」
わざわざ声を潜める陽菜の芝居がかった仕種に、舞楽も思わず身を乗り出す。
「乳酸菌の働きで腸内環境がよくなるからウンチやオシッコの匂いがしなくなる! これ重要!」
グッと拳を握りしめ、真顔で力説する陽菜だった。
なるほど。言われてみればたしかにあちこちに糞の山があるのにいやな匂いはちっともしない。ハエもいない。自然任せで掃除もしないのに清潔そのものといった印象。
「なるほど。隣にアパ―トがあるのにウンチやオシッコの匂いがしてたら困るものね」
「そういうこと。乳酸発酵させた食べ物をあげることで匂いを消す。この技術のおかげでeFREEガ―デンが可能になったのよ」
「なるほど」
うなずく舞楽の前でクマリたちは旺盛な食欲を発揮してどんどん食事を平らげている。 「さて、舞楽。ここで注目」
陽菜が言った。手を叩いて注意を引く。その表情がいつになく真剣だ。
「ただ眺めているだけじゃだめよ。食事の時間はみんなの健康状態をチェックする大事な時間でもあるんだから。よく見て、観察して、異常があったらすぐ報告。いいわね?」
「異常かどうかはどうすればわかるの?」
「そうね」
と、陽菜は食事に夢中のクマリたちを見渡してから言った。
「いまのところはみんな、健康ね。いまの姿を基準として覚えておいて。皮膚や毛の色艶が悪かったり、目やにがたまっていたり、鼻水をたらしていたりしたら要注意。その他、食欲がなかったり、おとなしすぎたりしている場合もね。くわしい病状なんかはLebabに入っているからちゃんと見て覚えておくこと。いいわね?」
「はい」
――まともなところもあったのね、この人。
と、かなり失礼なことを思いながら答える舞楽であった。
「それから、見るだけではダメよ。触って、抱いて、匂いをかいで、話しかけて、五感すべてで判断するの。大切なのはとにかく相手に興味をもつこと、自分から溶け込もうとすること、距離をおいて眺めているだけじゃ何にもわからないから。いいわね?」
「はい」
「よろしい。さて、それじゃ」
と、陽菜はただ一頭のウシに近づいた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

【完結】緑の奇跡 赤の輝石
黄永るり
児童書・童話
15歳の少女クティーは、毎日カレーとナンを作りながら、ドラヴィダ王国の外れにある町の宿で、住み込みで働いていた。
ある日、宿のお客となった少年シャストラと青年グラハの部屋に呼び出されて、一緒に隣国ダルシャナの王都へ行かないかと持ちかけられる。
戸惑うクティーだったが、結局は自由を求めて二人とダルシャナの王都まで旅にでることにした。
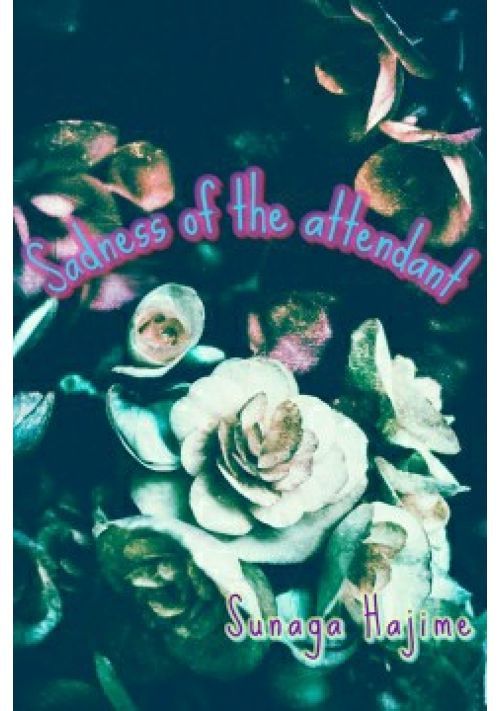
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

宝石アモル
緋村燐
児童書・童話
明護要芽は石が好きな小学五年生。
可愛いけれど石オタクなせいで恋愛とは程遠い生活を送っている。
ある日、イケメン転校生が落とした虹色の石に触ってから石の声が聞こえるようになっちゃって!?
宝石に呪い!?
闇の組織!?
呪いを祓うために手伝えってどういうこと!?

王女様は美しくわらいました
トネリコ
児童書・童話
無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。
それはそれは美しい笑みでした。
「お前程の悪女はおるまいよ」
王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。
きたいの悪女は処刑されました 解説版

忠犬ハジッコ
SoftCareer
児童書・童話
もうすぐ天寿を全うするはずだった老犬ハジッコでしたが、飼い主である高校生・澄子の魂が、偶然出会った付喪神(つくもがみ)の「夜桜」に抜き去られてしまいます。
「夜桜」と戦い力尽きたハジッコの魂は、犬の転生神によって、抜け殻になってしまった澄子の身体に転生し、奪われた澄子の魂を取り戻すべく、仲間達の力を借りながら奮闘努力する……というお話です。
※今まで、オトナ向けの小説ばかり書いておりましたが、
今回は中学生位を読者対象と想定してチャレンジしてみました。
お楽しみいただければうれしいです。


こちら御神楽学園心霊部!
緒方あきら
児童書・童話
取りつかれ体質の主人公、月城灯里が霊に憑かれた事を切っ掛けに心霊部に入部する。そこに数々の心霊体験が舞い込んでくる。事件を解決するごとに部員との絆は深まっていく。けれど、彼らにやってくる心霊事件は身の毛がよだつ恐ろしいものばかりで――。
灯里は取りつかれ体質で、事あるごとに幽霊に取りつかれる。
それがきっかけで学校の心霊部に入部する事になったが、いくつもの事件がやってきて――。
。
部屋に異音がなり、主人公を怯えさせる【トッテさん】。
前世から続く呪いにより死に導かれる生徒を救うが、彼にあげたお札は一週間でボロボロになってしまう【前世の名前】。
通ってはいけない道を通り、自分の影を失い、荒れた祠を修復し祈りを捧げて解決を試みる【竹林の道】。
どこまでもついて来る影が、家まで辿り着いたと安心した主人公の耳元に突然囁きかけてさっていく【楽しかった?】。
封印されていたものを解き放つと、それは江戸時代に封じられた幽霊。彼は門吉と名乗り主人公たちは土地神にするべく扱う【首無し地蔵】。
決して話してはいけない怪談を話してしまい、クラスメイトの背中に危険な影が現れ、咄嗟にこの話は嘘だったと弁明し霊を払う【嘘つき先生】。
事故死してさ迷う亡霊と出くわしてしまう。気付かぬふりをしてやり過ごすがすれ違い様に「見えてるくせに」と囁かれ襲われる【交差点】。
ひたすら振返らせようとする霊、駅まで着いたがトンネルを走る窓が鏡のようになり憑りついた霊の禍々しい姿を見る事になる【うしろ】。
都市伝説の噂を元に、エレベーターで消えてしまった生徒。記憶からさえもその存在を消す神隠し。心霊部は総出で生徒の救出を行った【異世界エレベーター】。
延々と名前を問う不気味な声【名前】。
10の怪異譚からなる心霊ホラー。心霊部の活躍は続いていく。

みかんに殺された獣
あめ
児童書・童話
果物などの食べ物が何も無くなり、生きもののいなくなった森。
その森には1匹の獣と1つの果物。
異種族とかの次元じゃない、果実と生きもの。
そんな2人の切なく悲しいお話。
全10話です。
1話1話の文字数少なめ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















