4 / 26
四章
杜を巡る
しおりを挟む
舞楽は陽菜と並んで杜のなかを歩き出した。物珍しそうにあちこちキョロキョロしながら歩くその姿はまさに『おのぼりさん』。いかにも『姫』という感じの気品と清潔感にあふれた容姿と相まって、異世界の姫さまが魔法によって飛ばされ、はじめて都会にやってきた……と、そう言われても納得できる姿だった。
――この子なら女優になっても絶対、大成功するわよね。
陽菜はそう思った。こうして、ただ歩いているだけでも映画の一シーンのように様になっているのだ。本当の映画に、演出付きで出たならどれほど魅力的になることか。
――なのに、その気がないなんてほんと、もったいないわ。
陽菜はそう思い、こっそりため息をついた。
舞楽は陽菜のそんな思いなど気付きもせず――と言うより、他人の気持ちなどそもそも考えない――飽きることなく辺りを見回している。
その風景は何度見てもやっぱり不思議。都会と森、人と動物、人工物と自然物。それらが決して対立することなく調和を為して存在している。一〇〇年以上先の未来とは言え、やっぱり地球とは思えない。
それにしても――。
こうしてブラブラ歩いていると杜の心地よさがよくわかる。舞楽は両腕を広げて新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んだ。花や果実の香りの混じった空気のなんておいしいこと! こんなおいしい空気、自分の時代ではよほどの山奥に行っても味わえない。いつも気持ちのいい風が吹いているし、足下からほのかな冷気が漂ってくるような気がして夏だというのに暑苦しさが全然ない。
何より、ここには車がない。轢かれる心配もなければ、騒音もない。排気ガスを吸わされることもない。安心して歩いていられる。
『車のない町』というものがこんなに心地いいものだなんて知らなかった。
靴底からふかふかの草の感触が伝わってくる。この感触を直接、味合わないなんてもったいない。舞楽は靴を脱ぎ、ついでに靴下も脱いで素足になった。あまりの心地よさに踊るようにして歩いて行く。陽菜もその姿に感化されたのか、同じように靴を脱いで素足になった。
「ここってすごく気持ちのいい場所よね」
舞楽が大きく空気を吸い込みながら言うと、陽菜は『そうでしょう、そうでしょう』とばかりに胸を張った。心の底からうれしそうな笑顔が自分の杜に対する誇りを現わしていた。
「この世界そのものの成り立ちにも興味はあるけど……都市をこんなふうにした理由も知りたいわね。わたしの時代からは考えられないことだもの」
「そうね」
と、陽菜は顎に指を当てて考え込んだ。
「わたしでも説明できるけど……せっかくだからその道のプロに頼んでみたら?」
「プロ?」
「そう。ほら、あそこにいる人」
と、陽菜が指で差し示した先には辺りに完成した絵を並べつつ、スケッチブックに筆を走らせている若い女性。
「絵描き?」
舞楽は怪訝な様子でつぶやいた。
噂に聞いた似顔絵描きという人だろうか。実際に出会ったことはないけど、そういう人がいたことは知っている。でも、それにしては服装が奇妙。形の整った四角い帽子に若草色のワンピ―ス。胸の部分にはロゴマ―クも入っている。あきらかに制服風。似顔絵描きの服装とは思えない。
「杜先案内人よ」
「杜先案内人?」
「そう。いわゆるウシ飼いなんだけどね。同時に市内の観光案内人でもあるの。だから、杜先案内人。エルフとも呼ばれているわ」
エルフか、なるほど。そう言われてみればたしかに若草色のワンピ―スは植物の葉のようで、森の妖精というイメ―ジにピッタリだ。
「さっきの質問はあの人に答えてもらうといいわ」
陽菜はそう言ってエルフの女性のもとに歩いていった。
「こんにちは」
陽菜が女性の近くで止まり、声をかける。女性はスケッチブックをおいて立ちあがるととびきりの笑顔で迎えてくれた。おもてなしの心が表に現われた素敵な笑顔だ。
「いらっしゃいませ。ご用は何でしょう? 絵でしたらどれでもお好きなものをお選びください。似顔絵も描きますよ。観光でしたら時間を指定してくださればご案内いたします」
「この子を案内してあげて。ここははじめてだから一番、基本のパタ―ンでね」
「はい。かしこまりました」
エルフの女性は優美に一礼するとやさしい笑顔を舞楽に向けた。
「杜先案内人の倉木優美と申します。精一杯、ガイドをつとめさせていただきます。よろしくお願いします」
「こちらこそ。木花舞楽です」
「では、舞楽さま。お手をどうぞ」
優美がたおやかな手を伸ばした。舞楽はそこに自分の手を乗せた。その仕種がお世話されることに慣れているお姫さまのように堂に入っているのが舞楽らしい。
そのままやさしく誘われ、ウシの背へと乗せられていた。
「いいの? ウシの上になんか乗っちゃって」
「はい。これがはじまりの大地の観光作法ですから」
ニッコリ微笑みながらそう言われる。
「ふうん」
ウシの背中に乗るなんてもちろんはじめて。だからといって怖がったり、緊張したりするようなタマではない。乗馬にいそしむ貴族の令嬢のような堂々とした態度で座り込む。
鞍もない、鐙もない、いわゆる裸乗りだけど、それでも乗り心地は悪くなかった。手を置いて体を支えると手のひらから暖かいウシの体温が伝わってくる。陽菜も別のウシに乗った。こちらは足をそろえて横座りしている。
ウシがゆっくりと歩きだす。リズミカルな揺れが伝わり、心地よく体を揺すってくれる。
気分は夜の砂漠を月明かりに照らされて旅する王女さま。自分の時代では決して味わえない体験だ。
――こんなのもいいものね。
とくに動物好きというわけではない舞楽だけど、こういう未知の体験は悪くない。
優美は二頭のウシのリ―ドを引きながら、観光案内のプロらしいなめらかで張りのある声をあげた。
「さて、舞楽さま。ご覧のとおり、はじまりの大地では一切の舗装がなされておりません。それは、創設者たる生森遠見の思想によるものでした。
『市街から車を追い出せばすべての道路は農地となる。ウシやヒツジをはなせば放牧場となり、木を植えれば林業だってできる。ヒツジは乳と肉と毛を与えてくれる。木々は木の葉と実を与えてくれる。蜂蜜だってとれる。薪や炭も作れる。木工品や建築材料ともなる。市街から車を追い出すだけで都市は森となる。そうなれば人間のために自然の森を食い潰す必要はなくなる。人間は都市のなかだけで生きていける』
そうして生森遠見はeFREE世界の市街に車を乗り込むことを禁止し、一切の舗装を廃止しました。市街の地面は自然のままに、草が生えるに任されました。そうして、都市は杜へと生まれ変わったのです」
「それはすてきなことだと思うけど……」
舞楽が口をはさんだ。プロのガイドを途中で遮るのは礼儀に反した行為だったかも知れない。でも、好奇心の方が強かった。何しろ、小さい頃から『黙って授業を聞く』ということができない質。というより、黙っているつもりがない。
だって、授業は生徒のためにあるものでしょう? だったら、気になったことはいくら聞いてもいいはずよね?
あまりに度重なる質問に授業が進まなくなり、教師が困ることもあったけど、そんなことは舞楽には関係ない。自分はただ生徒としての権利を行使しているだけ。いまも同じ。客である以上、ガイドに大して質問する権利はいくらでもあるはずだった。だから、堂々と尋ねた。
「草を生やしていたら伸びすぎて大変なことになっちゃわない?」
手入れされていない小さな空き地や土手が草ぼうぼうになっているのをよく見かける。町全体があんなことになったらとても暮らしていけないはずだ。
優美は気分を害したふうもなくニッコリと微笑んだ。
「そのためのウシやヒツジです。おっしゃるとおり、草は放っておけば育ちすぎてしまい、地面を覆い尽くしてしまいます。といって、いちいち刈り取るために人を雇えば人件費がかかります。ですが、ウシやヒツジをはなしておけば適度な高さに刈り込んでくれます。その上、乳や肉を生産してくれます。
動物たちを市街にはなすことで草刈りに費用がかからない。それどころか、飼料代なしで乳や肉を得られるようになったのです。現在では市街地に常時二〇〇頭ほどの乳牛が飼われており、乳製品需要を賄っております」
「へえ、なるほど。でも、そんなにウシがいたら糞やオシッコの始末が大変じゃない?」
動物の糞や小便が辺りかまわずまき散らされ、悪臭が漂う。そんなところには絶対、住みたくない。
「もちろん、その問題はありました。理屈の上でどんなにすぐれていても道端に糞尿が落ちていたり、病気が発生したりすれば誰も受け入れてはくれません。ですから、その点に関しては徹底的な予防策がとられました。まず、糞尿に関して言えば動物用の携帯トイレが開発されました」
「携帯トイレ?」
「はい。後ろ足の間につけられているこの袋です」
「ああ、なるほど。そういうことだったの」
一体何なのかと気になっていた袋の正体がわかってスッキリした。でも、言われてみれば当然のことだ。むしろ、それと気付かなかったほうがおかしい。何しろ、この杜はたくさんの動物たちがはなされているのにいやな匂いなんて全然しないのだから。
「病気に関してはまず何よりも動物たちを健康に育てること、健康に暮らしていける環境を維持することに心が砕かれました。それは、『動物たちを都市の健康を計るバロメ―タとして活用する』ということでもあります。動物たちが健康に暮らしていられる世界は、人間にとっても健康にいいはずですから」
「ああ、なるほど。ウシたちがのんびりと健康に草を食んでいられる環境は、人間にとっても過ごしやすい。そういうことね」
「はい。おっしゃるとおりです」
「でも、こんなに自然豊かだと虫なんかもすごいんじゃない? わたし、カやハエはきらいなんだけど」
「わたしもきらいです」
優美はおかしそうに微笑んだ。
「ですが、ご覧ください。ほら」
と、優美はたおやかな仕草で右手をあげた。指し示す先には数えることもできないほどのトンボの群れ。
「トンボ?」
「はい。お気付きですか? この杜にはとてもたくさんのトンボがいることを。害虫駆除の一環として杜で育てているのです」
「害虫駆除?」
「はい。トンボは肉食です。幼虫のうちは水のなかで、成虫になってからは空を飛び、昆虫を食べます。ですから、カやハエといった衛生害虫を減らす役に立ってくれるんです」
「へえ。トンボってそんなの食べてたんだ」
はじめて知った。トンボなんて何も食べずにただ飛びまわっているだけかと思っていた。
優美はつづけた。
「あそこの、胸の辺りの黄色っぽいトンボなんて、そのものズバリ、『カトリヤンマ』と言うんですよ」
「そんな名前のトンボがいるんだ。はじめて知った」
「その他にも危険性の低いアシナガバチをふやすことで危険なスズメバチが生きる場所を減らす、ネズミをとってもらうためにフクロウやネコ、ヘビを放す、有害微生物がふえないよう、有益な微生物をふやす……等々、いくつもの対策がたてられています。個々の生き物の健康を管理するのではなく、杜そのものをひとつの生き物とみなし、杜の健康そのものを維持していこうという発想です」
「薬とかは使わないの?」
「よほどの異常発生があれば使うこともあります。ですが、原則としては使用しません。薬品類は有益な生物にとっても毒ですから」
「つまり、全部生き物任せ?」
「はい。おっしゃるとおりです」
「そんなんで全部やっつけられるの?」
舞楽の質問に優美はニッコリと微笑んだ。ただし、今度の笑みはやさしいだけではなく、たしなめるような感じもあった。
「全部やっつける必要はないのです。問題のない数に抑えることさえできればいいのです。カやハエも自然界の大事な一員。彼らを根絶してしまえば彼らを食べて生きている生き物もみんな、死んでしまいます。そんなことになればこの豊かな自然は失われます。好きなもの、美しいものを守るためには、きらいなもの、醜いものの存在も受け入れなくてはならないのです」
「そういうもの?」
「そういうものです」
優美はキッパリと言い切った。
「それに、草の生えた地面は都市を冷やす機能をもっています。植物は暑くなると自らを冷やすために盛んに水分を蒸散させます。その際、地表の熱も同時に奪っていくのです」
なるほど。足下が何となく涼しく感じられたのはそのためか。
「そのため、夏でもさほど気温は上がりません。それに、お気付きでしょうか? 杜のなかは常に風が吹いていることに」
「そう言えば気持ちいい風が吹いているとは思ったけど」
「はじまりの大地の北には里山、南には農業排水を貯えておくための大きなプ―ルがあります。日に当たると陸地は水面よりも暑くなります。里山の空気は上昇し、そのあとにプ―ルの上から空気が流れこみます。そのため、杜のなかは常に風が吹いているのです。
夜になると逆に陸地の方が先に冷えます。そのため、今度は里山からプ―ルに向けて風が吹きます。一日中、欠かすことなく風が吹いているわけです。家屋や建物もその風をさえぎらないよう計算されて配置されています。市内全体を通じて通風が確保されている結果、熱気がこもることがなく、夏でも快適に暮らせるのです。おかげではじまりの大地では真夏でも冷房の必要はほとんどありません」
「へえ、すごいのね」
「はい。まさに自然のク―ラ―です。この仕組みだって、カやハエを含む多くの生き物の存在なしには機能しないのですよ?」
――これって、もしかして叱られてる?
優美の態度も口調もあくまでやさしく、やわらかい。だけど、よく考えてみるとけっこう手厳しい非難をされている。『全部やっつける』というジェノサイドの思想そのものがこの世界では受け入れられないらしい。たとえ相手がカやハエであったとしても。
「そうね。わたしが間違っていたみたい」
舞楽はそう言った。『ごめんなさい』という言葉は知らないけれど、間違いを認められないわけではない。きちんと説明されれば反省はする。
優美はもう一度ニッコリと微笑んだ。今度は心からの優しい笑みだ。
「ご理解いただいて幸いです。さて、舞楽さま。お気付きと思いますが、杜のなかには多くの樹木が植えられております。その数は五万本ほどになります」
「五万本?」
舞楽はその数に目を丸くした。
「はい。それらの樹木は果実の採集、薪や炭の生産、細工物や木工品の原料、建築材などに幅広く利用されております。これらの木々ははじまりの大地の創設期から市民自身の手で植えられてきたものです。
成長すれば伐採し、そのあとにまた新しい苗木を植える。その苗木も市民たちが自宅の庭にドングリやタネをまいて育てたものです。それを繰り返して一〇〇年以上にわたって、市民自身の手で受け継がれてきた偉大なる遺産なのです」
「……すごいのね」
「はい。わたしたちの誇りです」
キッパリと――。
そう断言する優美だった。
たわわに実って垂れ下った枝からひとつ、果実をもいで、食べさせてくれた。
一口食べて舞楽の表情が驚きにかわる。カリッとした堅い食感。ほとばしる酸味とほのかな苦み。おいしいかどうかと言えば自分の時代に食べていたス―パ―の品の方がおいしいだろう。でも、そういったお上品な規格品では味わえない野性の味がした。
例えば、思い切り体を動かして汗をかいた後に食べるなら最高だろう。その一口で疲れも吹き飛ぶにちがいない。小さな実のなかに野性の生命力がギュッとつまっているのだ。 見てみれば実っている果実はどれひとつとして同じものはない。色も大きさもさまざまで、真っ赤で艶やかな果実があるかと思えば、ごく薄い色合いのものもある。赤と黄が入り交じった斑模様のようなものもある。一方の木では大粒の実が少しだけ成っているかと思えば、また別の木には小さな実が鈴なりに実っている。形もス―パ―で見かけるようなツルツルしたものからカボチャのように凸凹したものまで、本当にさまざまだ。
「栽培果樹というものは普通、毎年一定の収穫を得るために枝を切ったり、花を摘んだりします。ですが、杜のなかの果樹はそんな世話はしていません。そのため、実がつくかどうかは樹木次第。枝が折れそうなほど多くの実をつける木があるかと思えば、悲しいぐらいわずかな実しかつけない木もあります。それを見ているだけでも楽しいものです。
見た目だけではなく、味も木ごとにちがいます。甘いもの、酸っぱいもの、苦いもの、生食に向くもの、お菓子作りや調理に向くものなど色々です。木ごとにファンがいて毎年、実のつくのを楽しみにしているんですよ」
「へえ。それっておもしろそう」
舞楽は目を輝かせた。お気に入りの果樹が毎年、自分のために実を実らせてくれる。そう思うと毎日がさぞ楽しいだろう。町中をブラブラ歩いては目についた果実を口に放り込み、自分の好みの味を探すだなんて何ともすてき。ぜひとも杜のなかの果実という果実を食べ比べてみたいものだ。
「もちろん、杜のなかには果樹だけではなく、スギやヒノキといった建築材用の木も数多く植えられています。新しく家を建てるときは自分自身で杜のなかをまわり、それぞれの木を見て、さわって、気に入ったものを自分で選ぶ、というのが一種のステ―タスとなっております。舞楽さまも将来、家を建てられることがありましたらぜひ、ご自分で木をお選びください」
「へえ。そんなこともできるんだ。あれ? でも、木材ってすごい高いって聞いたことあるけど……」
「そんなことはありませんよ。だって、木は大地と水と光さえあれば勝手に育ってくれます。育つのにお金がかからないものに値をつける必要はない。そうでしょう?」
「たしかにそうだけど……」
あれ? じゃあ、何でわたしの時代は『木材は高い』って言われていたわけ? 考えてみれば、今のいままでそんなこと気にしたこともなかった。自分の時代に帰ったらちょっと調べてみようか。
ふと気がつくと民家の屋上に大きな天使が降りていた。
舞楽は小首を傾げた。
「あれって飛行船なんでしょう?」
「はい。杜のなかは車は全面禁止。そのかわりに小型飛行船が開発されたのです。車のかわりにドア・ツ―・ドアの輸送ができるビ―クルといえば飛行船しかありませんでしたから。
ただ、小型といってもやはり、飛行船はかさばります。地面に降ろすとどうしても邪魔になります。大きく広がった翼が家にぶつかることもありますし。そこで、家々の屋上に直接、降りることにしたのです。そのため、杜のなかのすべての建物は平屋根、というより、屋上庭園となっております。これは、屋上庭園とすることで限られた土地を有効利用するためでもあります」
「でも、なんで飛行船が天使の姿をしているわけ? あんな形だと動きにくくない?」
「わかりませんか?」
「はっ?」
優美は会心の笑顔でキッパリと言った。
「絵になるからです」
舞楽はその答えに腹を抱えて笑った。なんというか、ものすごく納得できる答えだ。たしかに、悠久の青空を背景に天使の姿の飛行船が赴く姿は様になる。
絵になりすぎる。
そう言ってもいいぐらいだ。そんな、言ってみれば実用性の欠けらもない理由のためにわざわざ天使の姿の飛行船を作り上げる。
eFREE世界の人々の心意気を思い知らされた気分だった。
人生を楽しみ尽くそう。
そう思う壮大なる遊び心の発現だ。
――すごい人たち。
舞楽はごく自然にそう感じ入っていた。
――この子なら女優になっても絶対、大成功するわよね。
陽菜はそう思った。こうして、ただ歩いているだけでも映画の一シーンのように様になっているのだ。本当の映画に、演出付きで出たならどれほど魅力的になることか。
――なのに、その気がないなんてほんと、もったいないわ。
陽菜はそう思い、こっそりため息をついた。
舞楽は陽菜のそんな思いなど気付きもせず――と言うより、他人の気持ちなどそもそも考えない――飽きることなく辺りを見回している。
その風景は何度見てもやっぱり不思議。都会と森、人と動物、人工物と自然物。それらが決して対立することなく調和を為して存在している。一〇〇年以上先の未来とは言え、やっぱり地球とは思えない。
それにしても――。
こうしてブラブラ歩いていると杜の心地よさがよくわかる。舞楽は両腕を広げて新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んだ。花や果実の香りの混じった空気のなんておいしいこと! こんなおいしい空気、自分の時代ではよほどの山奥に行っても味わえない。いつも気持ちのいい風が吹いているし、足下からほのかな冷気が漂ってくるような気がして夏だというのに暑苦しさが全然ない。
何より、ここには車がない。轢かれる心配もなければ、騒音もない。排気ガスを吸わされることもない。安心して歩いていられる。
『車のない町』というものがこんなに心地いいものだなんて知らなかった。
靴底からふかふかの草の感触が伝わってくる。この感触を直接、味合わないなんてもったいない。舞楽は靴を脱ぎ、ついでに靴下も脱いで素足になった。あまりの心地よさに踊るようにして歩いて行く。陽菜もその姿に感化されたのか、同じように靴を脱いで素足になった。
「ここってすごく気持ちのいい場所よね」
舞楽が大きく空気を吸い込みながら言うと、陽菜は『そうでしょう、そうでしょう』とばかりに胸を張った。心の底からうれしそうな笑顔が自分の杜に対する誇りを現わしていた。
「この世界そのものの成り立ちにも興味はあるけど……都市をこんなふうにした理由も知りたいわね。わたしの時代からは考えられないことだもの」
「そうね」
と、陽菜は顎に指を当てて考え込んだ。
「わたしでも説明できるけど……せっかくだからその道のプロに頼んでみたら?」
「プロ?」
「そう。ほら、あそこにいる人」
と、陽菜が指で差し示した先には辺りに完成した絵を並べつつ、スケッチブックに筆を走らせている若い女性。
「絵描き?」
舞楽は怪訝な様子でつぶやいた。
噂に聞いた似顔絵描きという人だろうか。実際に出会ったことはないけど、そういう人がいたことは知っている。でも、それにしては服装が奇妙。形の整った四角い帽子に若草色のワンピ―ス。胸の部分にはロゴマ―クも入っている。あきらかに制服風。似顔絵描きの服装とは思えない。
「杜先案内人よ」
「杜先案内人?」
「そう。いわゆるウシ飼いなんだけどね。同時に市内の観光案内人でもあるの。だから、杜先案内人。エルフとも呼ばれているわ」
エルフか、なるほど。そう言われてみればたしかに若草色のワンピ―スは植物の葉のようで、森の妖精というイメ―ジにピッタリだ。
「さっきの質問はあの人に答えてもらうといいわ」
陽菜はそう言ってエルフの女性のもとに歩いていった。
「こんにちは」
陽菜が女性の近くで止まり、声をかける。女性はスケッチブックをおいて立ちあがるととびきりの笑顔で迎えてくれた。おもてなしの心が表に現われた素敵な笑顔だ。
「いらっしゃいませ。ご用は何でしょう? 絵でしたらどれでもお好きなものをお選びください。似顔絵も描きますよ。観光でしたら時間を指定してくださればご案内いたします」
「この子を案内してあげて。ここははじめてだから一番、基本のパタ―ンでね」
「はい。かしこまりました」
エルフの女性は優美に一礼するとやさしい笑顔を舞楽に向けた。
「杜先案内人の倉木優美と申します。精一杯、ガイドをつとめさせていただきます。よろしくお願いします」
「こちらこそ。木花舞楽です」
「では、舞楽さま。お手をどうぞ」
優美がたおやかな手を伸ばした。舞楽はそこに自分の手を乗せた。その仕種がお世話されることに慣れているお姫さまのように堂に入っているのが舞楽らしい。
そのままやさしく誘われ、ウシの背へと乗せられていた。
「いいの? ウシの上になんか乗っちゃって」
「はい。これがはじまりの大地の観光作法ですから」
ニッコリ微笑みながらそう言われる。
「ふうん」
ウシの背中に乗るなんてもちろんはじめて。だからといって怖がったり、緊張したりするようなタマではない。乗馬にいそしむ貴族の令嬢のような堂々とした態度で座り込む。
鞍もない、鐙もない、いわゆる裸乗りだけど、それでも乗り心地は悪くなかった。手を置いて体を支えると手のひらから暖かいウシの体温が伝わってくる。陽菜も別のウシに乗った。こちらは足をそろえて横座りしている。
ウシがゆっくりと歩きだす。リズミカルな揺れが伝わり、心地よく体を揺すってくれる。
気分は夜の砂漠を月明かりに照らされて旅する王女さま。自分の時代では決して味わえない体験だ。
――こんなのもいいものね。
とくに動物好きというわけではない舞楽だけど、こういう未知の体験は悪くない。
優美は二頭のウシのリ―ドを引きながら、観光案内のプロらしいなめらかで張りのある声をあげた。
「さて、舞楽さま。ご覧のとおり、はじまりの大地では一切の舗装がなされておりません。それは、創設者たる生森遠見の思想によるものでした。
『市街から車を追い出せばすべての道路は農地となる。ウシやヒツジをはなせば放牧場となり、木を植えれば林業だってできる。ヒツジは乳と肉と毛を与えてくれる。木々は木の葉と実を与えてくれる。蜂蜜だってとれる。薪や炭も作れる。木工品や建築材料ともなる。市街から車を追い出すだけで都市は森となる。そうなれば人間のために自然の森を食い潰す必要はなくなる。人間は都市のなかだけで生きていける』
そうして生森遠見はeFREE世界の市街に車を乗り込むことを禁止し、一切の舗装を廃止しました。市街の地面は自然のままに、草が生えるに任されました。そうして、都市は杜へと生まれ変わったのです」
「それはすてきなことだと思うけど……」
舞楽が口をはさんだ。プロのガイドを途中で遮るのは礼儀に反した行為だったかも知れない。でも、好奇心の方が強かった。何しろ、小さい頃から『黙って授業を聞く』ということができない質。というより、黙っているつもりがない。
だって、授業は生徒のためにあるものでしょう? だったら、気になったことはいくら聞いてもいいはずよね?
あまりに度重なる質問に授業が進まなくなり、教師が困ることもあったけど、そんなことは舞楽には関係ない。自分はただ生徒としての権利を行使しているだけ。いまも同じ。客である以上、ガイドに大して質問する権利はいくらでもあるはずだった。だから、堂々と尋ねた。
「草を生やしていたら伸びすぎて大変なことになっちゃわない?」
手入れされていない小さな空き地や土手が草ぼうぼうになっているのをよく見かける。町全体があんなことになったらとても暮らしていけないはずだ。
優美は気分を害したふうもなくニッコリと微笑んだ。
「そのためのウシやヒツジです。おっしゃるとおり、草は放っておけば育ちすぎてしまい、地面を覆い尽くしてしまいます。といって、いちいち刈り取るために人を雇えば人件費がかかります。ですが、ウシやヒツジをはなしておけば適度な高さに刈り込んでくれます。その上、乳や肉を生産してくれます。
動物たちを市街にはなすことで草刈りに費用がかからない。それどころか、飼料代なしで乳や肉を得られるようになったのです。現在では市街地に常時二〇〇頭ほどの乳牛が飼われており、乳製品需要を賄っております」
「へえ、なるほど。でも、そんなにウシがいたら糞やオシッコの始末が大変じゃない?」
動物の糞や小便が辺りかまわずまき散らされ、悪臭が漂う。そんなところには絶対、住みたくない。
「もちろん、その問題はありました。理屈の上でどんなにすぐれていても道端に糞尿が落ちていたり、病気が発生したりすれば誰も受け入れてはくれません。ですから、その点に関しては徹底的な予防策がとられました。まず、糞尿に関して言えば動物用の携帯トイレが開発されました」
「携帯トイレ?」
「はい。後ろ足の間につけられているこの袋です」
「ああ、なるほど。そういうことだったの」
一体何なのかと気になっていた袋の正体がわかってスッキリした。でも、言われてみれば当然のことだ。むしろ、それと気付かなかったほうがおかしい。何しろ、この杜はたくさんの動物たちがはなされているのにいやな匂いなんて全然しないのだから。
「病気に関してはまず何よりも動物たちを健康に育てること、健康に暮らしていける環境を維持することに心が砕かれました。それは、『動物たちを都市の健康を計るバロメ―タとして活用する』ということでもあります。動物たちが健康に暮らしていられる世界は、人間にとっても健康にいいはずですから」
「ああ、なるほど。ウシたちがのんびりと健康に草を食んでいられる環境は、人間にとっても過ごしやすい。そういうことね」
「はい。おっしゃるとおりです」
「でも、こんなに自然豊かだと虫なんかもすごいんじゃない? わたし、カやハエはきらいなんだけど」
「わたしもきらいです」
優美はおかしそうに微笑んだ。
「ですが、ご覧ください。ほら」
と、優美はたおやかな仕草で右手をあげた。指し示す先には数えることもできないほどのトンボの群れ。
「トンボ?」
「はい。お気付きですか? この杜にはとてもたくさんのトンボがいることを。害虫駆除の一環として杜で育てているのです」
「害虫駆除?」
「はい。トンボは肉食です。幼虫のうちは水のなかで、成虫になってからは空を飛び、昆虫を食べます。ですから、カやハエといった衛生害虫を減らす役に立ってくれるんです」
「へえ。トンボってそんなの食べてたんだ」
はじめて知った。トンボなんて何も食べずにただ飛びまわっているだけかと思っていた。
優美はつづけた。
「あそこの、胸の辺りの黄色っぽいトンボなんて、そのものズバリ、『カトリヤンマ』と言うんですよ」
「そんな名前のトンボがいるんだ。はじめて知った」
「その他にも危険性の低いアシナガバチをふやすことで危険なスズメバチが生きる場所を減らす、ネズミをとってもらうためにフクロウやネコ、ヘビを放す、有害微生物がふえないよう、有益な微生物をふやす……等々、いくつもの対策がたてられています。個々の生き物の健康を管理するのではなく、杜そのものをひとつの生き物とみなし、杜の健康そのものを維持していこうという発想です」
「薬とかは使わないの?」
「よほどの異常発生があれば使うこともあります。ですが、原則としては使用しません。薬品類は有益な生物にとっても毒ですから」
「つまり、全部生き物任せ?」
「はい。おっしゃるとおりです」
「そんなんで全部やっつけられるの?」
舞楽の質問に優美はニッコリと微笑んだ。ただし、今度の笑みはやさしいだけではなく、たしなめるような感じもあった。
「全部やっつける必要はないのです。問題のない数に抑えることさえできればいいのです。カやハエも自然界の大事な一員。彼らを根絶してしまえば彼らを食べて生きている生き物もみんな、死んでしまいます。そんなことになればこの豊かな自然は失われます。好きなもの、美しいものを守るためには、きらいなもの、醜いものの存在も受け入れなくてはならないのです」
「そういうもの?」
「そういうものです」
優美はキッパリと言い切った。
「それに、草の生えた地面は都市を冷やす機能をもっています。植物は暑くなると自らを冷やすために盛んに水分を蒸散させます。その際、地表の熱も同時に奪っていくのです」
なるほど。足下が何となく涼しく感じられたのはそのためか。
「そのため、夏でもさほど気温は上がりません。それに、お気付きでしょうか? 杜のなかは常に風が吹いていることに」
「そう言えば気持ちいい風が吹いているとは思ったけど」
「はじまりの大地の北には里山、南には農業排水を貯えておくための大きなプ―ルがあります。日に当たると陸地は水面よりも暑くなります。里山の空気は上昇し、そのあとにプ―ルの上から空気が流れこみます。そのため、杜のなかは常に風が吹いているのです。
夜になると逆に陸地の方が先に冷えます。そのため、今度は里山からプ―ルに向けて風が吹きます。一日中、欠かすことなく風が吹いているわけです。家屋や建物もその風をさえぎらないよう計算されて配置されています。市内全体を通じて通風が確保されている結果、熱気がこもることがなく、夏でも快適に暮らせるのです。おかげではじまりの大地では真夏でも冷房の必要はほとんどありません」
「へえ、すごいのね」
「はい。まさに自然のク―ラ―です。この仕組みだって、カやハエを含む多くの生き物の存在なしには機能しないのですよ?」
――これって、もしかして叱られてる?
優美の態度も口調もあくまでやさしく、やわらかい。だけど、よく考えてみるとけっこう手厳しい非難をされている。『全部やっつける』というジェノサイドの思想そのものがこの世界では受け入れられないらしい。たとえ相手がカやハエであったとしても。
「そうね。わたしが間違っていたみたい」
舞楽はそう言った。『ごめんなさい』という言葉は知らないけれど、間違いを認められないわけではない。きちんと説明されれば反省はする。
優美はもう一度ニッコリと微笑んだ。今度は心からの優しい笑みだ。
「ご理解いただいて幸いです。さて、舞楽さま。お気付きと思いますが、杜のなかには多くの樹木が植えられております。その数は五万本ほどになります」
「五万本?」
舞楽はその数に目を丸くした。
「はい。それらの樹木は果実の採集、薪や炭の生産、細工物や木工品の原料、建築材などに幅広く利用されております。これらの木々ははじまりの大地の創設期から市民自身の手で植えられてきたものです。
成長すれば伐採し、そのあとにまた新しい苗木を植える。その苗木も市民たちが自宅の庭にドングリやタネをまいて育てたものです。それを繰り返して一〇〇年以上にわたって、市民自身の手で受け継がれてきた偉大なる遺産なのです」
「……すごいのね」
「はい。わたしたちの誇りです」
キッパリと――。
そう断言する優美だった。
たわわに実って垂れ下った枝からひとつ、果実をもいで、食べさせてくれた。
一口食べて舞楽の表情が驚きにかわる。カリッとした堅い食感。ほとばしる酸味とほのかな苦み。おいしいかどうかと言えば自分の時代に食べていたス―パ―の品の方がおいしいだろう。でも、そういったお上品な規格品では味わえない野性の味がした。
例えば、思い切り体を動かして汗をかいた後に食べるなら最高だろう。その一口で疲れも吹き飛ぶにちがいない。小さな実のなかに野性の生命力がギュッとつまっているのだ。 見てみれば実っている果実はどれひとつとして同じものはない。色も大きさもさまざまで、真っ赤で艶やかな果実があるかと思えば、ごく薄い色合いのものもある。赤と黄が入り交じった斑模様のようなものもある。一方の木では大粒の実が少しだけ成っているかと思えば、また別の木には小さな実が鈴なりに実っている。形もス―パ―で見かけるようなツルツルしたものからカボチャのように凸凹したものまで、本当にさまざまだ。
「栽培果樹というものは普通、毎年一定の収穫を得るために枝を切ったり、花を摘んだりします。ですが、杜のなかの果樹はそんな世話はしていません。そのため、実がつくかどうかは樹木次第。枝が折れそうなほど多くの実をつける木があるかと思えば、悲しいぐらいわずかな実しかつけない木もあります。それを見ているだけでも楽しいものです。
見た目だけではなく、味も木ごとにちがいます。甘いもの、酸っぱいもの、苦いもの、生食に向くもの、お菓子作りや調理に向くものなど色々です。木ごとにファンがいて毎年、実のつくのを楽しみにしているんですよ」
「へえ。それっておもしろそう」
舞楽は目を輝かせた。お気に入りの果樹が毎年、自分のために実を実らせてくれる。そう思うと毎日がさぞ楽しいだろう。町中をブラブラ歩いては目についた果実を口に放り込み、自分の好みの味を探すだなんて何ともすてき。ぜひとも杜のなかの果実という果実を食べ比べてみたいものだ。
「もちろん、杜のなかには果樹だけではなく、スギやヒノキといった建築材用の木も数多く植えられています。新しく家を建てるときは自分自身で杜のなかをまわり、それぞれの木を見て、さわって、気に入ったものを自分で選ぶ、というのが一種のステ―タスとなっております。舞楽さまも将来、家を建てられることがありましたらぜひ、ご自分で木をお選びください」
「へえ。そんなこともできるんだ。あれ? でも、木材ってすごい高いって聞いたことあるけど……」
「そんなことはありませんよ。だって、木は大地と水と光さえあれば勝手に育ってくれます。育つのにお金がかからないものに値をつける必要はない。そうでしょう?」
「たしかにそうだけど……」
あれ? じゃあ、何でわたしの時代は『木材は高い』って言われていたわけ? 考えてみれば、今のいままでそんなこと気にしたこともなかった。自分の時代に帰ったらちょっと調べてみようか。
ふと気がつくと民家の屋上に大きな天使が降りていた。
舞楽は小首を傾げた。
「あれって飛行船なんでしょう?」
「はい。杜のなかは車は全面禁止。そのかわりに小型飛行船が開発されたのです。車のかわりにドア・ツ―・ドアの輸送ができるビ―クルといえば飛行船しかありませんでしたから。
ただ、小型といってもやはり、飛行船はかさばります。地面に降ろすとどうしても邪魔になります。大きく広がった翼が家にぶつかることもありますし。そこで、家々の屋上に直接、降りることにしたのです。そのため、杜のなかのすべての建物は平屋根、というより、屋上庭園となっております。これは、屋上庭園とすることで限られた土地を有効利用するためでもあります」
「でも、なんで飛行船が天使の姿をしているわけ? あんな形だと動きにくくない?」
「わかりませんか?」
「はっ?」
優美は会心の笑顔でキッパリと言った。
「絵になるからです」
舞楽はその答えに腹を抱えて笑った。なんというか、ものすごく納得できる答えだ。たしかに、悠久の青空を背景に天使の姿の飛行船が赴く姿は様になる。
絵になりすぎる。
そう言ってもいいぐらいだ。そんな、言ってみれば実用性の欠けらもない理由のためにわざわざ天使の姿の飛行船を作り上げる。
eFREE世界の人々の心意気を思い知らされた気分だった。
人生を楽しみ尽くそう。
そう思う壮大なる遊び心の発現だ。
――すごい人たち。
舞楽はごく自然にそう感じ入っていた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

【完結】緑の奇跡 赤の輝石
黄永るり
児童書・童話
15歳の少女クティーは、毎日カレーとナンを作りながら、ドラヴィダ王国の外れにある町の宿で、住み込みで働いていた。
ある日、宿のお客となった少年シャストラと青年グラハの部屋に呼び出されて、一緒に隣国ダルシャナの王都へ行かないかと持ちかけられる。
戸惑うクティーだったが、結局は自由を求めて二人とダルシャナの王都まで旅にでることにした。
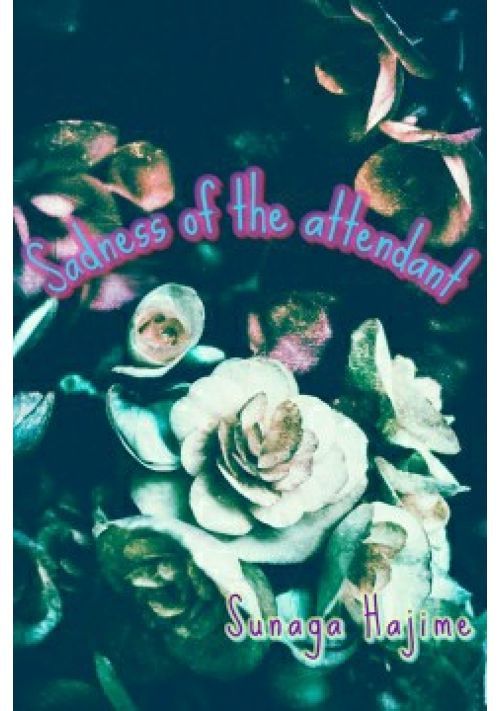
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

忠犬ハジッコ
SoftCareer
児童書・童話
もうすぐ天寿を全うするはずだった老犬ハジッコでしたが、飼い主である高校生・澄子の魂が、偶然出会った付喪神(つくもがみ)の「夜桜」に抜き去られてしまいます。
「夜桜」と戦い力尽きたハジッコの魂は、犬の転生神によって、抜け殻になってしまった澄子の身体に転生し、奪われた澄子の魂を取り戻すべく、仲間達の力を借りながら奮闘努力する……というお話です。
※今まで、オトナ向けの小説ばかり書いておりましたが、
今回は中学生位を読者対象と想定してチャレンジしてみました。
お楽しみいただければうれしいです。

宝石アモル
緋村燐
児童書・童話
明護要芽は石が好きな小学五年生。
可愛いけれど石オタクなせいで恋愛とは程遠い生活を送っている。
ある日、イケメン転校生が落とした虹色の石に触ってから石の声が聞こえるようになっちゃって!?
宝石に呪い!?
闇の組織!?
呪いを祓うために手伝えってどういうこと!?

こちら御神楽学園心霊部!
緒方あきら
児童書・童話
取りつかれ体質の主人公、月城灯里が霊に憑かれた事を切っ掛けに心霊部に入部する。そこに数々の心霊体験が舞い込んでくる。事件を解決するごとに部員との絆は深まっていく。けれど、彼らにやってくる心霊事件は身の毛がよだつ恐ろしいものばかりで――。
灯里は取りつかれ体質で、事あるごとに幽霊に取りつかれる。
それがきっかけで学校の心霊部に入部する事になったが、いくつもの事件がやってきて――。
。
部屋に異音がなり、主人公を怯えさせる【トッテさん】。
前世から続く呪いにより死に導かれる生徒を救うが、彼にあげたお札は一週間でボロボロになってしまう【前世の名前】。
通ってはいけない道を通り、自分の影を失い、荒れた祠を修復し祈りを捧げて解決を試みる【竹林の道】。
どこまでもついて来る影が、家まで辿り着いたと安心した主人公の耳元に突然囁きかけてさっていく【楽しかった?】。
封印されていたものを解き放つと、それは江戸時代に封じられた幽霊。彼は門吉と名乗り主人公たちは土地神にするべく扱う【首無し地蔵】。
決して話してはいけない怪談を話してしまい、クラスメイトの背中に危険な影が現れ、咄嗟にこの話は嘘だったと弁明し霊を払う【嘘つき先生】。
事故死してさ迷う亡霊と出くわしてしまう。気付かぬふりをしてやり過ごすがすれ違い様に「見えてるくせに」と囁かれ襲われる【交差点】。
ひたすら振返らせようとする霊、駅まで着いたがトンネルを走る窓が鏡のようになり憑りついた霊の禍々しい姿を見る事になる【うしろ】。
都市伝説の噂を元に、エレベーターで消えてしまった生徒。記憶からさえもその存在を消す神隠し。心霊部は総出で生徒の救出を行った【異世界エレベーター】。
延々と名前を問う不気味な声【名前】。
10の怪異譚からなる心霊ホラー。心霊部の活躍は続いていく。

みかんに殺された獣
あめ
児童書・童話
果物などの食べ物が何も無くなり、生きもののいなくなった森。
その森には1匹の獣と1つの果物。
異種族とかの次元じゃない、果実と生きもの。
そんな2人の切なく悲しいお話。
全10話です。
1話1話の文字数少なめ。

王女様は美しくわらいました
トネリコ
児童書・童話
無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。
それはそれは美しい笑みでした。
「お前程の悪女はおるまいよ」
王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。
きたいの悪女は処刑されました 解説版

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















