14 / 35
File.3 華の意思を問わぬ庭師
第十話 黄金区の華・モニカ
しおりを挟む
「ああ……暇っすね……」
「ええ……そうですね……」
現在二〇二三年5月14日。前回の誘拐事件のあと、約二週間もの間何も依頼が来ないという異常事態であった。探偵・東敏行と助手・桃山香菜は、あまりの暇さゆえに無気力状態で椅子に寝転がっていた。
「東さん……こんなに依頼が来なくて、利益は大丈夫なんですか?」
「それはまあ……一階の不動産会社がテナント料払ってるし……最悪生活はしていけるっすけど……」
「でも私、最初の仕事から二週間暇なんて、気がおかしくなりそうです……」
「何言ってるんすか……探偵が暇って言うのはいいことっすよ。誰もトラブルに巻き込まれてないんすから……」
そうは言っても、やはり暇というのはどんな苦痛よりも苦痛である。
「香菜さん……しりとりしないっすか?」
「三十分前にやったじゃないですか……」
「あっちむいてほい」
「それは五分前に」
「マジカルバナナ」
「ここ一週間毎日やってますよね?」
「せーので自分の下着の色を言い合う」
「それはやってませんけど、絶対に拒否します……」
「……こんなことならゲーム機位買っときゃよかったなぁ……」
「この事務所も、上の居室も、娯楽なんて無いに等しいですからね……」
二人の間に重苦しい空気が立ち込めまくり、もはや飽和状態を軽く超えていた、その時。
プルルルルルル
事務所の電話が鳴った。東と香菜が跳ね起きた。東が居合切りの達人が如きスピードで受話器を取り上げた。
「はい、こちら東探偵事務所っす!」
ついに仕事が来る! ついに暇から解放される! 二人は今にも手を取り合って喜びたいほどであった。
「はい……はい……わかったっす。日時? 今すぐにでも!」
東が興奮を隠せないまま電話の応対を続け、香菜は固唾を飲んで見守る。
「はい……じゃ、よろしくっす」
ゆっくりと受話器を下ろす東。そのまま香菜の方を向いて、言った。
「今から依頼人が来るっす!!!」
「やったー!!!」
東と香菜は飛び上がって喜んだ。
三十分後、一台の車が事務所の前に止まる。
「あ! あれフェラーリじゃないっすか!? これは期待できそうっすね!」
窓からその様子を見る東の目が¥に変わるのを、香菜は見逃さなかった。
少しして、事務所のインターホンが鳴る。
「香菜さん、開けてあげて!」
東は既にデスクでスタンバイしていた。
「了解です!」
香菜が扉に駆け付け、依頼人を迎え入れる。
「こんにちは、こちらの事務所に依頼の電話を入れたものですが」
やってきたのはスーツに身を包み、サングラスを着ている青年。
多少の威圧感があり、香菜は少しおじけづくも、
「お待ちしておりました! どうぞこちらへ!」
と、二週間ぶりのクライアントを席に誘導する。
「お、お邪魔しますぅ……」
すると、男のあとから若い女性が入ってきた。
「……え? ……え? ……え?」
香菜はその女性を見ると、フリーズした。
「あ、そう来たか……」
東もその女性を知っていた。
「は、初めまして! ご当地アイドル『ラッキーセブン』のモニカですぅ!」
以下、閲覧注意。
「きゃあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ!!! モニカちゃんだあああああああああ!!! 本物だあああああああああ!!! 映像と全然違う!!! マジ可愛い!!! 私今すっごく幸せ!!! もう死んでもいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい!!!」
……今までに何度か説明したが、あらためて説明しよう。香菜は黄金区ご当地アイドル『ラッキーセブン』の大ファンである。その中でもセンターを務める「モニカ」が最推しである。
推しを持つ読者諸君ならば、目の前に推しが現れた時の気持ちがよくわかるだろう。ましてや依頼人として東探偵事務所にかかわってくるとなると、香菜のボルテージはレットゾーンに突入する。
「ありがたやあああああ!!! ありがたやああああああ!!!」
香菜がいよいよ五体投地の姿勢に入った。
「あ、あわわ……大丈夫ですかぁ?」
その発狂具合はモニカに心配させるほどである。
「ああ……サーセン、うちの助手あなたの大ファンでして……」
東もかなり引いていた。
「そうなんですかぁ? ありがとうございますぅ! あの、もし良かったら握手しませんかぁ?」
ここで香菜の言葉にならない叫びが発生するわけだが、これ以上叫び声ばっかり書いても読者の精神に異常をきたしかねないので割愛する。
やっとこさ香菜が落ち着いてきたところで、東が依頼人の情報を整理する。
「えーと、モニカさん、本名杉並モニカさん。日本人の父親とフランス人の母親を持つ二十一歳。職業はアイドルっと……間違いないっすね?」
「はい……間違いないですぅ」
「東さん、何も個人情報の提出までする必要がお有りですか?」
モニカについてきた黒服の青年は、モニカのマネージャーであり、名前を高橋哲也という。年齢は二十九歳で、東より年上、水沼よりは年下である。
「すまないっすね、依頼人の情報は知っとかなきゃならなくて……依頼人が反社会的勢力の一員だったり、実は事件の犯人だったなんてこともよくあるので……個人情報の提出だけでもかなりそういうの減らせるっす」
「そうですか……では依頼についてお話します」
高橋が依頼内容について話し始めた。
数日前、モニカの事務所に脅迫状が届いた。
「武道館公演を中止しろ、さもなくばモニカの命は無いと思え」
ラッキーセブンは一週間後、武道館にてライブを行う予定であった。
勿論99%いたずらであることは確信している。
しかし、もしもこれが残り1%の事例だった場合、取り返しのつかない事態に陥ってしまう。故に事務所は公演中止を決断する手はずであった。
しかし、脅迫を掛けられた当の本人であるモニカが
「ようやく夢が叶うんですぅ! いたずらの脅迫状なんかで夢を諦めさせないでください!」
と猛抗議したため、最終的にモニカにボディーガードをつけよう、という結論にまとまった。
「……で、俺がそのボディーガードになればいいんすか?」
東が丸文字で書かれた脅迫状を読みながら言った。
「そういうことです」
「でもっすよ……わざわざ僕に頼むことっすか? 警察なら多分タダで引き受けてくれるはずっすけど」
いくらビジネスチャンスだからといって、東は依頼を強制することはない。彼が引き受けるのは警察の手に負えない場合や、何らかの理由で警察には言えない・言いたくない場合、民事に関する依頼が来た場合である。
「それが……モニカが警察には連絡するなと……」
「せっかくの武道館ライブだって言うのに、お巡りさんが来たら雰囲気台無しじゃないですか……! 私はファンの皆さんに楽しんで帰ってもらいたいんです!」
「とまあ、このように言うので……」
「さっすがモニカちゃん!! それでこそアイドルの鑑!! 大好き!!!」
「あ、香菜さんはしばらく黙っててくださいっす」
「そこで、関東一の名探偵との呼び声高い東さんにお任せいただこうかと」
「関東一ぃ? 誰っすかそんなこと言いだしたのは……まあいいや、やるっす。モニカさんの命は僕が守るっす!」
「やったぁ! ありがとうございますぅ!」
ここまでは順調に話し合いが進んでいた。しかし、
「それで、報酬の話になるんすけど」
と東が言いかけた時、
「ちょっと待ったあああああ!!!」
東の前に香菜が躍り出る。
「まさかモニカちゃんから大金せしめようなんて思っていませんよね!?」
「何言ってるんすか、せしめるっすよ」
「絶対にさせません!! こんないたいけな美少女からお金とろうなんて……」
「あのね」
東の声色が変わった。
「あのね、僕はプロなんすよ? 香菜さんはまだ探偵業を勘違いしてるっすね。誰が相手だろうと平等に金は取るし平等に仕事はするっす。ましてや依頼人を命に代えても守るってんだから生半可な報酬じゃやってられないっすよ。これ以上邪魔するなら退室してもらうっすけど」
ヨーロッパの家庭では、親は子を怒鳴りつけることはない。
ただ一言、冷淡とも脅迫とも思えるような言い方で、一言「やってはいけない」というと、子供はそれを守るそうだ。
香菜は東からただならぬ恐怖感を感じ、以後モニカ達が退出するまで一言も発しなかった。
「サーセン、うちの助手が場を乱しちゃって……」
「ま、まあ、ああいうのは慣れているので……」
「それで報酬なんすけど……」
「はい、今回は『ラッキーセブン』が所属するフリージア・エンターテイメント名義ですので、そちらに請求書を送っていただければお支払いいたします」
「そっすか、じゃあ前金1000万、依頼達成料1500万でいいっすか?」
高橋は噂以上のぼったくりに正直動揺したが、東の「依頼人を命に代えても守る」という発言を思い出し、彼なら信頼できると判断して
「わかりました。今日中に振り込みましょう」
と答えた。
「それでは、早速……」
「うっす、任務開始っすね!」
東が意気揚々と立ち上がる。
「それじゃ、ちょっと着替えてくるっす!」
と、別室に入っていった。
何も知らないモニカと高橋は、ジャージではボディーガードとしてふさわしくない服装だから着替えるのかと思っていた。
ただ一人、香菜だけが動揺を隠せずにいた。
(東さんが……ジャージ以外に着替える!? あ、前の美術館の事件(File.3参照)でもポロシャツ着てたような……でも何に着替えるの……!?)
二分後、東が出てきた。
「さ、モニカさん! この東敏行がお供するっす!」
香菜は絶句した。
東は高橋と同じような黒服にサングラスで出てきたのだ。
「わぁ! かっこいいですぅ!」
モニカが手を叩いて褒めたが、香菜は普段とは全然違う雰囲気の東に驚愕していた。最初に思ったことは
(肌が黒ければエージェントJだ……)
であった。
「さて、これからどこ行くんすか?」
「えーと、十時半から生放送トーク番組に出演、お昼をはさんで十三時からラッキーセブンで歌番組に出演、十四時から……」
話しながら事務所を出ようとする東、高橋、モニカの三名。そこに香菜もついて来ようとしたが……
「あれ、香菜さん? 何やってるんすか?」
「え、何って、これから仕事……」
「イヤイヤ、香菜さんは留守番っすよ」
「……え?」
第十一話 東に降りかかる災難 に続く
「ええ……そうですね……」
現在二〇二三年5月14日。前回の誘拐事件のあと、約二週間もの間何も依頼が来ないという異常事態であった。探偵・東敏行と助手・桃山香菜は、あまりの暇さゆえに無気力状態で椅子に寝転がっていた。
「東さん……こんなに依頼が来なくて、利益は大丈夫なんですか?」
「それはまあ……一階の不動産会社がテナント料払ってるし……最悪生活はしていけるっすけど……」
「でも私、最初の仕事から二週間暇なんて、気がおかしくなりそうです……」
「何言ってるんすか……探偵が暇って言うのはいいことっすよ。誰もトラブルに巻き込まれてないんすから……」
そうは言っても、やはり暇というのはどんな苦痛よりも苦痛である。
「香菜さん……しりとりしないっすか?」
「三十分前にやったじゃないですか……」
「あっちむいてほい」
「それは五分前に」
「マジカルバナナ」
「ここ一週間毎日やってますよね?」
「せーので自分の下着の色を言い合う」
「それはやってませんけど、絶対に拒否します……」
「……こんなことならゲーム機位買っときゃよかったなぁ……」
「この事務所も、上の居室も、娯楽なんて無いに等しいですからね……」
二人の間に重苦しい空気が立ち込めまくり、もはや飽和状態を軽く超えていた、その時。
プルルルルルル
事務所の電話が鳴った。東と香菜が跳ね起きた。東が居合切りの達人が如きスピードで受話器を取り上げた。
「はい、こちら東探偵事務所っす!」
ついに仕事が来る! ついに暇から解放される! 二人は今にも手を取り合って喜びたいほどであった。
「はい……はい……わかったっす。日時? 今すぐにでも!」
東が興奮を隠せないまま電話の応対を続け、香菜は固唾を飲んで見守る。
「はい……じゃ、よろしくっす」
ゆっくりと受話器を下ろす東。そのまま香菜の方を向いて、言った。
「今から依頼人が来るっす!!!」
「やったー!!!」
東と香菜は飛び上がって喜んだ。
三十分後、一台の車が事務所の前に止まる。
「あ! あれフェラーリじゃないっすか!? これは期待できそうっすね!」
窓からその様子を見る東の目が¥に変わるのを、香菜は見逃さなかった。
少しして、事務所のインターホンが鳴る。
「香菜さん、開けてあげて!」
東は既にデスクでスタンバイしていた。
「了解です!」
香菜が扉に駆け付け、依頼人を迎え入れる。
「こんにちは、こちらの事務所に依頼の電話を入れたものですが」
やってきたのはスーツに身を包み、サングラスを着ている青年。
多少の威圧感があり、香菜は少しおじけづくも、
「お待ちしておりました! どうぞこちらへ!」
と、二週間ぶりのクライアントを席に誘導する。
「お、お邪魔しますぅ……」
すると、男のあとから若い女性が入ってきた。
「……え? ……え? ……え?」
香菜はその女性を見ると、フリーズした。
「あ、そう来たか……」
東もその女性を知っていた。
「は、初めまして! ご当地アイドル『ラッキーセブン』のモニカですぅ!」
以下、閲覧注意。
「きゃあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ!!! モニカちゃんだあああああああああ!!! 本物だあああああああああ!!! 映像と全然違う!!! マジ可愛い!!! 私今すっごく幸せ!!! もう死んでもいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい!!!」
……今までに何度か説明したが、あらためて説明しよう。香菜は黄金区ご当地アイドル『ラッキーセブン』の大ファンである。その中でもセンターを務める「モニカ」が最推しである。
推しを持つ読者諸君ならば、目の前に推しが現れた時の気持ちがよくわかるだろう。ましてや依頼人として東探偵事務所にかかわってくるとなると、香菜のボルテージはレットゾーンに突入する。
「ありがたやあああああ!!! ありがたやああああああ!!!」
香菜がいよいよ五体投地の姿勢に入った。
「あ、あわわ……大丈夫ですかぁ?」
その発狂具合はモニカに心配させるほどである。
「ああ……サーセン、うちの助手あなたの大ファンでして……」
東もかなり引いていた。
「そうなんですかぁ? ありがとうございますぅ! あの、もし良かったら握手しませんかぁ?」
ここで香菜の言葉にならない叫びが発生するわけだが、これ以上叫び声ばっかり書いても読者の精神に異常をきたしかねないので割愛する。
やっとこさ香菜が落ち着いてきたところで、東が依頼人の情報を整理する。
「えーと、モニカさん、本名杉並モニカさん。日本人の父親とフランス人の母親を持つ二十一歳。職業はアイドルっと……間違いないっすね?」
「はい……間違いないですぅ」
「東さん、何も個人情報の提出までする必要がお有りですか?」
モニカについてきた黒服の青年は、モニカのマネージャーであり、名前を高橋哲也という。年齢は二十九歳で、東より年上、水沼よりは年下である。
「すまないっすね、依頼人の情報は知っとかなきゃならなくて……依頼人が反社会的勢力の一員だったり、実は事件の犯人だったなんてこともよくあるので……個人情報の提出だけでもかなりそういうの減らせるっす」
「そうですか……では依頼についてお話します」
高橋が依頼内容について話し始めた。
数日前、モニカの事務所に脅迫状が届いた。
「武道館公演を中止しろ、さもなくばモニカの命は無いと思え」
ラッキーセブンは一週間後、武道館にてライブを行う予定であった。
勿論99%いたずらであることは確信している。
しかし、もしもこれが残り1%の事例だった場合、取り返しのつかない事態に陥ってしまう。故に事務所は公演中止を決断する手はずであった。
しかし、脅迫を掛けられた当の本人であるモニカが
「ようやく夢が叶うんですぅ! いたずらの脅迫状なんかで夢を諦めさせないでください!」
と猛抗議したため、最終的にモニカにボディーガードをつけよう、という結論にまとまった。
「……で、俺がそのボディーガードになればいいんすか?」
東が丸文字で書かれた脅迫状を読みながら言った。
「そういうことです」
「でもっすよ……わざわざ僕に頼むことっすか? 警察なら多分タダで引き受けてくれるはずっすけど」
いくらビジネスチャンスだからといって、東は依頼を強制することはない。彼が引き受けるのは警察の手に負えない場合や、何らかの理由で警察には言えない・言いたくない場合、民事に関する依頼が来た場合である。
「それが……モニカが警察には連絡するなと……」
「せっかくの武道館ライブだって言うのに、お巡りさんが来たら雰囲気台無しじゃないですか……! 私はファンの皆さんに楽しんで帰ってもらいたいんです!」
「とまあ、このように言うので……」
「さっすがモニカちゃん!! それでこそアイドルの鑑!! 大好き!!!」
「あ、香菜さんはしばらく黙っててくださいっす」
「そこで、関東一の名探偵との呼び声高い東さんにお任せいただこうかと」
「関東一ぃ? 誰っすかそんなこと言いだしたのは……まあいいや、やるっす。モニカさんの命は僕が守るっす!」
「やったぁ! ありがとうございますぅ!」
ここまでは順調に話し合いが進んでいた。しかし、
「それで、報酬の話になるんすけど」
と東が言いかけた時、
「ちょっと待ったあああああ!!!」
東の前に香菜が躍り出る。
「まさかモニカちゃんから大金せしめようなんて思っていませんよね!?」
「何言ってるんすか、せしめるっすよ」
「絶対にさせません!! こんないたいけな美少女からお金とろうなんて……」
「あのね」
東の声色が変わった。
「あのね、僕はプロなんすよ? 香菜さんはまだ探偵業を勘違いしてるっすね。誰が相手だろうと平等に金は取るし平等に仕事はするっす。ましてや依頼人を命に代えても守るってんだから生半可な報酬じゃやってられないっすよ。これ以上邪魔するなら退室してもらうっすけど」
ヨーロッパの家庭では、親は子を怒鳴りつけることはない。
ただ一言、冷淡とも脅迫とも思えるような言い方で、一言「やってはいけない」というと、子供はそれを守るそうだ。
香菜は東からただならぬ恐怖感を感じ、以後モニカ達が退出するまで一言も発しなかった。
「サーセン、うちの助手が場を乱しちゃって……」
「ま、まあ、ああいうのは慣れているので……」
「それで報酬なんすけど……」
「はい、今回は『ラッキーセブン』が所属するフリージア・エンターテイメント名義ですので、そちらに請求書を送っていただければお支払いいたします」
「そっすか、じゃあ前金1000万、依頼達成料1500万でいいっすか?」
高橋は噂以上のぼったくりに正直動揺したが、東の「依頼人を命に代えても守る」という発言を思い出し、彼なら信頼できると判断して
「わかりました。今日中に振り込みましょう」
と答えた。
「それでは、早速……」
「うっす、任務開始っすね!」
東が意気揚々と立ち上がる。
「それじゃ、ちょっと着替えてくるっす!」
と、別室に入っていった。
何も知らないモニカと高橋は、ジャージではボディーガードとしてふさわしくない服装だから着替えるのかと思っていた。
ただ一人、香菜だけが動揺を隠せずにいた。
(東さんが……ジャージ以外に着替える!? あ、前の美術館の事件(File.3参照)でもポロシャツ着てたような……でも何に着替えるの……!?)
二分後、東が出てきた。
「さ、モニカさん! この東敏行がお供するっす!」
香菜は絶句した。
東は高橋と同じような黒服にサングラスで出てきたのだ。
「わぁ! かっこいいですぅ!」
モニカが手を叩いて褒めたが、香菜は普段とは全然違う雰囲気の東に驚愕していた。最初に思ったことは
(肌が黒ければエージェントJだ……)
であった。
「さて、これからどこ行くんすか?」
「えーと、十時半から生放送トーク番組に出演、お昼をはさんで十三時からラッキーセブンで歌番組に出演、十四時から……」
話しながら事務所を出ようとする東、高橋、モニカの三名。そこに香菜もついて来ようとしたが……
「あれ、香菜さん? 何やってるんすか?」
「え、何って、これから仕事……」
「イヤイヤ、香菜さんは留守番っすよ」
「……え?」
第十一話 東に降りかかる災難 に続く
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

霊山の裁き
聖岳郎
ミステリー
製薬会社のMRを辞め、探偵となった空木健介。登山と下山後の一杯をこよなく愛する探偵が、初の探偵仕事で事件に巻き込まれる。初仕事は不倫調査の尾行だったが、その男は滋賀県と岐阜県の県境に位置する霊仙山の廃屋で死体で見つかった。死体は一体誰?さらに、空木の元に、女性からの手紙が届き、山形県の霊山、月山に来るように依頼される。その月山の山中でも、死体が発見される。転落死した会社員は事故だったのか?
とある製薬会社の仙台支店に渦巻く、保身とエゴが空木健介によって暴かれていく山岳推理小説。

旧校舎のフーディーニ
澤田慎梧
ミステリー
【「死体の写った写真」から始まる、人の死なないミステリー】
時は1993年。神奈川県立「比企谷(ひきがやつ)高校」一年生の藤本は、担任教師からクラス内で起こった盗難事件の解決を命じられてしまう。
困り果てた彼が頼ったのは、知る人ぞ知る「名探偵」である、奇術部の真白部長だった。
けれども、奇術部部室を訪ねてみると、そこには美少女の死体が転がっていて――。
奇術師にして名探偵、真白部長が学校の些細な謎や心霊現象を鮮やかに解決。
「タネも仕掛けもございます」
★毎週月水金の12時くらいに更新予定
※本作品は連作短編です。出来るだけ話数通りにお読みいただけると幸いです。
※本作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件とは一切関係ありません。
※本作品の主な舞台は1993年(平成五年)ですが、当時の知識が無くてもお楽しみいただけます。
※本作品はカクヨム様にて連載していたものを加筆修正したものとなります。
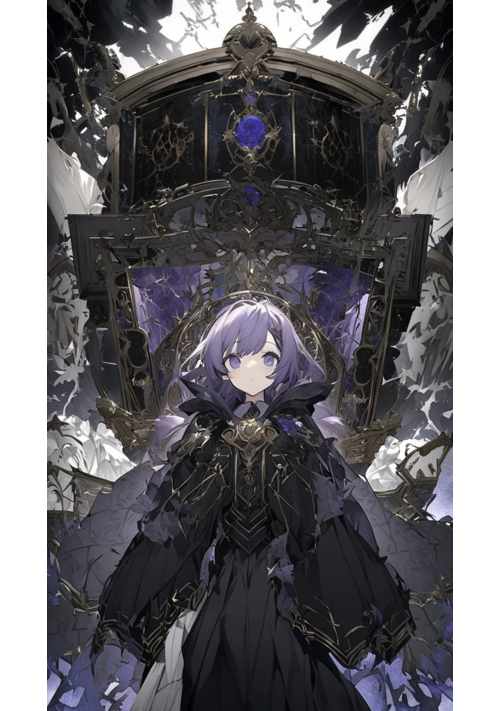
残響鎮魂歌(レクイエム)
葉羽
ミステリー
天才高校生、神藤葉羽は幼馴染の望月彩由美と共に、古びた豪邸で起きた奇妙な心臓発作死の謎に挑む。被害者には外傷がなく、現場にはただ古いレコード盤が残されていた。葉羽が調査を進めるにつれ、豪邸の過去と「時間音響学」という謎めいた技術が浮かび上がる。不可解な現象と幻聴に悩まされる中、葉羽は過去の惨劇と現代の死が共鳴していることに気づく。音に潜む恐怖と、記憶の迷宮が彼を戦慄の真実へと導く。

ヨハネの傲慢(上) 神の処刑
真波馨
ミステリー
K県立浜市で市議会議員の連続失踪事件が発生し、県警察本部は市議会から極秘依頼を受けて議員たちの護衛を任される。公安課に所属する新宮時也もその一端を担うことになった。謎めいた失踪が、やがて汚職事件や殺人へ発展するとは知る由もなく——。

秘密と自殺と片想い
松藤 四十弐
ミステリー
友達が死んだのは、2004年9月の下旬。首を吊り、自らを殺した。十七歳だった。
あいつは誰にも何も言わず、なぜ自殺をしたのか。俺はそれを知ることにした。
※若きウェルテルの悩み、初恋(ツルネーゲフ)、友情(武者小路実篤)のネタバレを含みます。

蠱惑Ⅱ
壺の蓋政五郎
ミステリー
人は歩いていると邪悪な壁に入ってしまう時がある。その壁は透明なカーテンで仕切られている。勢いのある時は壁を弾き迷うことはない。しかし弱っている時、また嘘を吐いた時、憎しみを表に出した時、その壁に迷い込む。蠱惑の続編で不思議な短編集です。

お家に帰る
原口源太郎
ミステリー
裕福な家庭の小学三年生、山口源太郎はその名前からよくいじめられている。その源太郎がある日、誘拐犯たちにさらわれた。山奥の小屋に監禁された源太郎は、翌日に自分が殺されてしまうと知る。部屋を脱出し、家を目指して山を下りる。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















