46 / 57
act.46
しおりを挟む
小さくて細い腕に、包帯が丁寧に巻き付けられる。
「はい、これで大丈夫」
マックスがそう言うと、いかにもいたずらが大好きそうな少年が、安心したように母親を見上げた。
「本当に先生、ありがとうございました」
「いいえ。大したことがなくてよかったですね。お大事に」
マックスが親子を処置室の外まで見送ると、忙しなく人通りのある廊下に、大きな怒鳴り声が響いた。
「ああ、ローズ先生! 治療中でしたか!」
熟年の看護師が、やっと見つけたと言わんばかりにかけよってきた。
「お電話かかってますよ」
「電話?」
マックスが、廊下の先にある受付カウンターに目をやると、受付にいるスタッフが、マックスに向かって受話器を振っていた。
「 ── ああ、すまないね。ありがとう」
マックスは看護師の肩をポンと叩いて、カウンターに向かった。
ERは今日もめまぐるしく、カウンターには様々な人種年齢性別の人が押し寄せている。
マックスはその間をかいくぐって受話器を受け取ると、「はい、ローズですが」と応えた。
『 ── ハロー? マックス先生?』
周囲の雑音がうるさくて、マックスは片耳を手で塞ぎながら、もう一度自分の名前を名乗った。その上で相手の名前を訊ねると、意外な人物の名前が飛び出してきた。
『マックス先生? 俺、クーパーです。ショーン・クーパー』
「え?! ショーン?!」
マックスが思わず声を上げると、隣でカウンターにかじり付いていたパンキーな若者が、チラリとマックスを見た。マックスは慌てて口を塞いで、若者に背を向ける。
「どうしたの? 一体」
まさかマックスも、全米で今話題の当人から電話がかかってくるとは思わない。思わず動揺した声が出てしまった。けれど、同じように相手の声も十分動揺していた。
受話器から聞こえてくるショーンの声は、矢継ぎ早に言葉を繋いだ。
『あの、カルテって残ってますか? 俺が治療を受けた時の晩の』
「え? カルテ? 一応残ってると思うけど・・・。何? どこか具合でも悪いの?」
『いや、そうじゃないんです。ちょっと知りたいことがあって。コウの会社の名前と連絡先が知りたいと思って・・・』
「・・・ん? それじゃダメだよ、君のカルテじゃ」
マックスはキョトンと目を瞬かせた。
『あっ、そうか。コウの、コウのカルテ』
電話口でショーンが慌てて言い直す。相当気が動転してるのか。
「もちろん、彼のカルテもある。けれどその時、会社の連絡先まで書いてたかなぁ・・・。ちょっと待って」
マックスはカウンターの中に入ると、開いているパソコンの前に立ち、受話器を肩と耳に挟んでキーボードを叩いた。
パスワードを打ち込んで、データベースにアクセスする。
本来なら、個人情報を本人以外に漏らすことは十分に配慮せねばならないことだが、ショーンになら大丈夫だろう、とマックスは判断した。何せ、ショーンの切羽詰まりようと言ったら。
マックスは数ヶ月前のカルテ情報にアクセスし、コウゾウ・ハシバの名前で検索をかける。
「── 出た。・・・ええと・・・。ダメだ。自宅の連絡先だけで、会社のことは登録されてない」
マックスがそう答えると、明らかにショーンの声が落胆した。
『 ── そうですか・・・』
そう言って電話を切ろうとする。
「ああ、待って! 何? 詳しい事情、訊かせて?」
『先生は、俺とシンシアが付き合ってるって書いてある記事、見た?』
一瞬マックスの動きが止まった。
「え? もう一度言ってくれる?」
『だから、シンシアと俺が付き合ってるって書いてある記事』
「君、いつからシンシアと付き合うようになったの?」
『デマなんです! 本当は付き合ってません!』
「あ、そうか。そうだよね」
ハハハとマックスは笑った。
現在、シンシアがショーンと非常に仲良くなって、ロスに滞在していることは知っていた。だが、マックスもゴシップ雑誌など読まないタチなので、そんな噂など知る由もなかった訳だ。
シンシアに彼氏ができたとなると、そりゃ大変なことになる。
ジムもああ見えて娘には弱いからきっと動揺するだろうし、それ以上に自分も動揺する。レイチェルやセスだって、口を出してくるだろう。
シンシアは正真正銘『箱入り娘』なのだ。
「で、それが・・・」
『俺、コウとまたケンカしちゃって、今別々に住んでるんです。俺はロスに。コウはC市に。コウがその記事を見て誤解したら大変だと思って連絡を取りたいんだけど、コウの勤める証券会社が分からなくて・・・』
「ああ、そうか。そういうことか。それは不安だよね・・・。でもどうしよう・・・」
『 ── 分からなければいいんです。どうせダメもとのつもりでかけてみただけだから・・・。大変だけど、C市にある証券会社の番号調べて、片っ端から電話してみます』
「けれど、それは大変だよ・・・。待って。証券会社に勤めてるんだよね。彼、トレーダーなの?」
『ううん。アナリストだって言ってた。いつも企業とかを回って研究するんだって、そこの株が上がるかどうか。いろんなところに行ってるみたい』
ふとマックスの中で、何かの回路が繋がった。
「ねぇ、そこにメモ帳ある?」
『え? うん。もちろんあります』
「よければ、今から言う電話番号にかけてみて。ミラーズ社の秘書室直通番号だから。そこでジムを呼んでみるといい。彼なら、何か知ってるかもしれないから。本当は携帯の番号を教えたいところだけど、彼のは事情があって教える訳にはいかないんだ。念のため、一足先に俺の方からも彼の携帯に連絡入れとく」
マックスが電話番号を伝えると、弾むような声で『ありがとうございます!』というショーンの返事が返ってきた。
── こういうの、いま泣いた烏がもう笑った、とでも言うのかな。
マックスは微笑むと電話を一旦切って、病院の外に出て、ウォレスに電話をかけたのだった。
ショーンは受話器を両手で掴み、祈るように額に押しつけると、震える手でマックスに教えてもらった番号を押した。
ショーンもまさか、あのミラーズ社のしかも秘書室に電話をかけることになるとは思わなかった。
否が応でも、ドキドキと胸が高鳴る。
『 ── はい、ミラーズ社秘書室でございます』
いかにも大企業の秘書室といった風な、淡々とした気品のある女性の声が応対した。
「あ、あの・・・クーパーと申しますが、ジム・ウォレスさんはいらっしゃいますか?」
ショーンは声が上擦らないようにと、必死にゆっくりとしゃべった。
『主席社長秘書でございますか?』
主席社長秘書なんだ!
思わずショーンは目を剥く。
なんだか全然想像できない世界で、ショーンは目を白黒させた。
「ええと、あの、そうです」
ショーンの受け答えに、相手も不信に思ったらしい。
『恐れ入りますが、もう一度お名前をおっしゃっていただけますか?』
「えっと、クーパーです」
『どちらのクーパー様ですか?』
「え! ええっと・・・ただのクーパーです・・・」
『ただのクーパー様』
「それじゃ、ダメですか?」
思わず気弱になって、そう聞き返してしまう。
またも動揺して、電話口で歌った方がよく分かるかなぁなんて、とんでもないことを考えてしまう。
── どうしよう、どうしよう・・・
そう思っているうち、ふいに受話器の先の声が代わった。
『ショーン?』
忘れもしない、ウォレスの声だった。
「ジム!!」
思わず名前を叫んでしまって、あっと思う。
「す、すみません・・・。俺、偉そうにミスター・ウォレスの名前・・・」
ショーンがそう言うと、受話器からウォレスの笑い声が零れてきた。
『いやこちらこそ、失礼した。さっきまで部屋を空けていてね。マックスの電話をもらって、急いで戻ってきたんだ。要件はマックスから大体聞いたよ。彼氏の勤め先だね』
「ええ、そうです。C市に支店を置く証券会社で、彼はそこでアナリストの仕事をしているんです。名前は、コウゾウ・ハシバ。日本人です。どなたか、知ってそうな人はいらっしゃいますか?」
藁に縋る気持ちでショーンが一気にそう言うと、ウォレスはすぐに「知ってる」と答えてくれた。ショーンは思わず立ち上がる。
「え?! 本当ですか!! その人の連絡先、教えていただけますか?」
『その必要はない。この私が、その知ってる人、だからね』
あまりの返事に、ショーンは口をパクパクさせた。
ウォレスが今何を言ったのか、すぐには理解できなかった。
ウォレスは、ショーンの声を待たずして、先を続けた。
『ここに彼の名刺があるよ。彼は一度我が社を訪問しているんだ。偶然にも、私が接客した。株式を管理している部署のトップが丁度不在だったのでね』
何という偶然だろう。ジムが、コウと面識があったなんて・・・。
よもや羽柴も、ウォレスが自分の傷の手当をした医者の恋人だなんて気付いてもいないだろう。
ショーンはそこに力強いパワーを感じた。
何か普通の力ではない特別な巡り合わせというか、互いに引き寄せている繋がりというか・・・。
そしてようやく、運命的にショーンは羽柴の会社の番号を手に入れたのだった。
何度目かの電話のベルに、ロジャーは『もう、うんざり』といったような溜息をついた。
その電話のベルは、ロジャーの机のものではなく、パーテーションを挟んだ隣の、羽柴の机のものだ。
しつこく鳴り続けるベルに、「ハイハイ。コウゾウはお休みですよ・・・」と呟きながら、羽柴のデスクに向かった。
ロジャーは、脱力したようにドッカとOAイスに腰掛けると、デスクの上のファイルを手にとってそれを開き、両足を行儀悪くデスクの上に投げ出した。
ロジャーの膝上にあるファイルには、羽柴が休みの間に電話がかかってくる可能性のある顧客のリストが書いてあり、それぞれの対応の仕方が指示してある。
ロジャーはおもむろに受話器を取った。
「ハイ、アナリスト部」
『ハロー? コウ?』
「は?」
羽柴のことを『コウ』だなんて呼ぶ人間は、ひょっとしてひょっとしなくても、ロジャーが知る限りひとりしかいない。
思わず受話器を持つロジャーの手が震えた。
『 ── あ、えっと、すみません。・・・ミスター・ハシバ、いらっしゃいますか?』
声に耳を澄ますと、益々自分の思いついた人物に赤い正解ランプが点滅する。
でも、いや、しかし、もし正解だとしたら・・・・。
『もしもし?』
ロジャーは、ギョロギョロと目玉を動かした。
「もしかして・・・もしかしなくても、その・・・。ショーン君?」
その呼び掛けに、相手もロジャーが誰か分かったようだ。
『あ! え? コーエンさん?』
── ああ、神様!!
あまりの嬉しさに、ロジャーは両手放しで喜んだ。その結果、見事にイスごと後ろにスッ転んでしまったが。
ガタガタガタと突如物々しい音が聞こえたから、余程びっくりしたのだろう。
デスクの下にぶら~んとぶらさがっている受話器から、『大丈夫ですか?!』という声が漏れ出てくる。
正真正銘、スターの声だ。
ロジャーは這いずって受話器を掴むと、「俺の名前を覚えていてくれたのかい?」と思わず早口で捲し立ててしまった。
『え、ええ。去年は素敵なクリスマスパーティーに呼んでくださって、本当にありがとうございました』
── ああ、なんていい子なんだろう! スターなのに、ちっとも威張らないし、礼儀もきちっとしてる。我が儘放題の誰かさんとはえらい違いだ・・・。
ロジャーは、鼻をズズッと鳴らしながら、「きっと家の子ども達も喜ぶよ。君にそう言ってもらえて・・・」と答えた。
『 ── あの、それで・・・』
「あ、ああ。耕造ね。アイツ、休みだよ」
『休み?!』
ショーンが驚いた声を上げる。彼が全く羽柴の行動を掴んでいないことが窺えた。
『あの・・・えっと、いつから?』
とても不安げな声。ロジャーは眉間に皺を寄せた。
「丁度今日からだよ。一週間の予定。新年に取り損ねた分を取ったみたい」
『ああ、それじゃ、ずっと休んでる訳じゃないんですね・・・』
それを聞いて、益々ロジャーは皺を深くする。
「ああ、そうだよ。先々月ぐらいに無断欠勤があったけど、それ以外は別に」
ロジャーはそう言いながら、ふと思い当たる節が出てきた。
「そういえば・・・。あの無断欠勤から、様子がちょっとおかしかったな・・・」
ショーンはロジャーの呟きを聞き逃さない。
『様子がおかしかったって、どんな風に?』
ロジャーは、床にゴロリと寝ころんだ。
「何ていうのか・・・・覇気がないというか・・・。いつもの溌剌としたアイツではなかったな。どこか上の空のところもあったし。でも、仕事はきちんとしてたから・・・。あ、そういやショーン君、何の用事だい? 会社までかけてくるなんて、よっぽど急いだ用事なんだろ? あ、そうだ! ひょっとして君、結婚式のスピーチをアイツに頼むとか・・・?!」
ロジャーは身体を起こし、受話器につっこみを入れる。
『え?!』
今度はショーンの刺々しい声が返ってきた。
『どこでそんな話に?』
「や、だって・・・。耕造が言ってたよ。ショーンに新しい恋人ができたって。いい人そうだって・・・」
『 ── マジで?!』
ショーンの叫び声がして、しばらくの沈黙が流れた。
相手の顔が見えなくても、受話器越し、いや~な空気が流れ出てくる。
「あれ? 違うの? ま、俺もおかしいと思ってたんだ。クリスマスの君達の様子を見てたら・・・」
『ミスター・コーエン。コウが今どこにいるか分かりませんか?』
ロジャーはまるで胸ぐらをショーンに掴まれているような気分になった。
ゴクリと喉が鳴る。
「え、いや。自宅にいなかった?」
『留守電でした』
「そしたらええっと・・・そう! そうだ! 日本! 日本に行ってるはずだよ。休みの前、そう言ってた。今度こそ日本に里帰りするって。出発日は分からないが、休み明けの前々日には戻ってくるって言ったよ。つまり今から6日後かな?」
『日本での立ち寄り先は分かりませんか?』
「いやぁ・・・それは。アイツはあまり日本のことを話さないから。トウキョウに行ったことぐらいしか分からないよ」
『そうですか。ありがとう』
そう言って電話は切れた。
ロジャーは、マジマジと電話を見つめる。
ロジャーにはなんだかそれが、やたらと不思議な物体に見えた。
『あの』ショーン・クーパーと電話で話したなんて・・・。
「何やってるんですか、コーエンさん」
転けたイスの傍らで嬉しさに悶えている“ミーハー”ロジャーのことを覗き込んで、ロジャー以上にミーハーな新人社員ハミルトンが怪訝そうな顔をしている。
ショーン・クーパーの大ファンとか言いながら、平気でショーンのゴシップ記事をネタに悪口や冷やかしを言ったりしているいけ好かない奴だ。
ロジャーはすっくと立ち上がると、いつもの“できる男”ロジャーの表情を浮かべ、イスと受話器を元の位置に返し、ハミルトンを見やって言った。
「 ── 今誰から電話がかかってきてたか」
「は? ・・・さぁ・・・」
首を傾げるハミルトンに、したり顔の笑みを浮かべ、ロジャーは言った。
「教えない」
「はぁ?! なんっすか、それ」
ロジャーはそれに一切答えることなく、フフフフフと不適な笑いを浮かべたまま、ブースを後にしたのだった。
── コウは、あの噂のことを知ってた・・・・。
ショーンは愕然として、受話器を耳から下ろした。
「何だ? 何だって?」
斜め向かいのソファーに腰をかけたルイが、焦った表情でショーンを見る。
それに対してショーンは、ゆっくりとルイを見た。凄く険しい表情で。
「コウ、あの噂のこと、信じたみたい・・・」
「何?!」
ルイが大声を張り上げる。ショーンは、静かに頭を項垂れ、横に振った。
「当たり前だ・・・。一週間も前に出てたくせに、俺は否定もしなかったんだから・・・」
ショーンはそう吐き出すと、溜息を立て続けについて、頭を緩く横に振った。
あまりにショックで、涙も出てこない。
── 日本・・・日本か・・・。
まるでショーンの知らない国。
バルーンのツアーでも、日本は一度だけ行ったことがあるが、ホテルとライブ会場に缶詰状態で、まるっきり分からなかった。空港で行きと帰り、ファンに囲まれたぐらいしか思い出に残っていない。
きっと羽柴は、日本にもう向かったのかもしれない。だから携帯電話もエリア圏外になっているに違いないのだ。
益々ショーンは、絶望の淵に立たされた気分になった。
── これでもし、コウが日本に行ったっきり、帰ってこなかったらどうしよう・・・。
ショーンの両手がガタガタと震えた。
── そうだよ。元々彼にとっては、日本に行くことこそ『帰る』ことなんだから・・・。
今すぐ。今すぐにも日本に行きたい。
せめて、誤解だけは解きたい。
これ以上、『嘘』に負けるのなんか、ごめんだ・・・!!
ショーンはふいに立ち上がると、ショーンの部屋になっているゲストルームに向かった。
ルイが怪訝そうな顔つきをして追いかけてくる。
ショーンは作りつけのクローゼットから旅行用にと買った大きなナイロン製の黒い鞄を取り出した。
チェストの引き出しを開け、次々と服を放り込む。
「ショーン、お前、何してる・・・?」
鬼気迫るショーンの気迫に押されて、ゲストルームに入ってこずに戸口から顔を覗かせるだけのルイが、おそるおそる訊いてくる。
ショーンは一心不乱に旅支度をしながら、「何って、日本に行く。今から、日本に行く」と繰り返した。それを聞いて、ルイがぎょっとする。
「無茶だ、ショーン! 彼の行き先、まるで分かってないんだろう?!」
「行ってみたら、何とかなるかもしれない」
「何とかなるって・・・。おい、ちょっと冷静になれ!」
ルイがとうとう部屋に入ってきて、ショーンの腕を掴んだ。
「お前は、ショーン・クーパーだぞ? 日本でもバルーンの売れ行きは凄いし、そのギタリストのことだって皆知ってる。前回行った時も、空港でもみくちゃにされたじゃないか」
「それはバルーンだったからだよ」
「それだけじゃない。エニグマだって日本で翻訳され、発売されてる。アメリカほどではないにしろ、日本でだって同様の広告展開をしたんだ。単身で当てもなく飛び込むなんて、無謀としか言えない。ちょっと考えれば、分かることだろ?」
「分かるけど、でも!!」
ショーンは手に掴んでいるジーンズを、壁に向かって投げつけた。
歯を食いしばって、右手でグシャリと自分の髪の毛を掴む。
「 ── ショーン・・・」
ルイがショーンの肩にそっと触れると、ショーンは顔をくしゃくしゃに歪めて、「クソッ」と小さく悪態をついた。
「このまま・・・誤解されたまま逢えなくなるなんて・・・。そんな・・・」
いくら羽柴の出した答えに納得しようと思っても、こんな答えじゃ納得できない。
それはショーンのせいでも、まして羽柴のせいでもないところから捻り込まれた結果だったからだ。
「どうして皆して、俺のこと傷つけようとするんだろ・・・。存在もしてない彼女のことをエイズで入院してるって言われたり、付き合ってもいないシンシアとの新居を探してるだなんて言われたり・・・。皆本当の俺のことなんて知らないのに、どうしてそんなことばかり。これって、神様がダメだって言ってるのかな? コウと結ばれるのはダメだって、そういうことなのかな?」
傍らにあるベッドに腰を下ろし、ショーンはガックリと肩を落とした。
一気に目が落ちくぼんだような気がする。
── こんな形の終わりなんて・・・・。
ショーンの瞳にじわりと涙が滲んだ時、唐突に電話が鳴った。
リビングにある親機の音に続いて、ゲストルームにある子機も鳴り始める。
全く身動きしないショーンを横目に、ルイが受話器を取った。
「ハイ、サントロ・・・。はい・・・ええ。はい。居ますけど、今ちょっと・・・はい・・・」
ふいに相手の話を聞いて、ルイはパッと表情を変えた。
ルイがショーンに受話器を差し出す。
ショーンが、のろのろと顔を上げた。
ルイは一言言った。
「神は断じてダメだって言っている訳じゃなさそうだよ」
「?」
ショーンは、怪訝に思ってルイを見上げた。
ルイが、グイッと受話器を押しつける。
ショーンはおそるおそる電話に出た。
「・・・ハロー?」
『── ショーン? 私、リサよ。ねぇあなた、日本に行って歌ってみない?』
それは、先日一週間に渡る日本出張から帰国したばかりのリサの声だった。
「はい、これで大丈夫」
マックスがそう言うと、いかにもいたずらが大好きそうな少年が、安心したように母親を見上げた。
「本当に先生、ありがとうございました」
「いいえ。大したことがなくてよかったですね。お大事に」
マックスが親子を処置室の外まで見送ると、忙しなく人通りのある廊下に、大きな怒鳴り声が響いた。
「ああ、ローズ先生! 治療中でしたか!」
熟年の看護師が、やっと見つけたと言わんばかりにかけよってきた。
「お電話かかってますよ」
「電話?」
マックスが、廊下の先にある受付カウンターに目をやると、受付にいるスタッフが、マックスに向かって受話器を振っていた。
「 ── ああ、すまないね。ありがとう」
マックスは看護師の肩をポンと叩いて、カウンターに向かった。
ERは今日もめまぐるしく、カウンターには様々な人種年齢性別の人が押し寄せている。
マックスはその間をかいくぐって受話器を受け取ると、「はい、ローズですが」と応えた。
『 ── ハロー? マックス先生?』
周囲の雑音がうるさくて、マックスは片耳を手で塞ぎながら、もう一度自分の名前を名乗った。その上で相手の名前を訊ねると、意外な人物の名前が飛び出してきた。
『マックス先生? 俺、クーパーです。ショーン・クーパー』
「え?! ショーン?!」
マックスが思わず声を上げると、隣でカウンターにかじり付いていたパンキーな若者が、チラリとマックスを見た。マックスは慌てて口を塞いで、若者に背を向ける。
「どうしたの? 一体」
まさかマックスも、全米で今話題の当人から電話がかかってくるとは思わない。思わず動揺した声が出てしまった。けれど、同じように相手の声も十分動揺していた。
受話器から聞こえてくるショーンの声は、矢継ぎ早に言葉を繋いだ。
『あの、カルテって残ってますか? 俺が治療を受けた時の晩の』
「え? カルテ? 一応残ってると思うけど・・・。何? どこか具合でも悪いの?」
『いや、そうじゃないんです。ちょっと知りたいことがあって。コウの会社の名前と連絡先が知りたいと思って・・・』
「・・・ん? それじゃダメだよ、君のカルテじゃ」
マックスはキョトンと目を瞬かせた。
『あっ、そうか。コウの、コウのカルテ』
電話口でショーンが慌てて言い直す。相当気が動転してるのか。
「もちろん、彼のカルテもある。けれどその時、会社の連絡先まで書いてたかなぁ・・・。ちょっと待って」
マックスはカウンターの中に入ると、開いているパソコンの前に立ち、受話器を肩と耳に挟んでキーボードを叩いた。
パスワードを打ち込んで、データベースにアクセスする。
本来なら、個人情報を本人以外に漏らすことは十分に配慮せねばならないことだが、ショーンになら大丈夫だろう、とマックスは判断した。何せ、ショーンの切羽詰まりようと言ったら。
マックスは数ヶ月前のカルテ情報にアクセスし、コウゾウ・ハシバの名前で検索をかける。
「── 出た。・・・ええと・・・。ダメだ。自宅の連絡先だけで、会社のことは登録されてない」
マックスがそう答えると、明らかにショーンの声が落胆した。
『 ── そうですか・・・』
そう言って電話を切ろうとする。
「ああ、待って! 何? 詳しい事情、訊かせて?」
『先生は、俺とシンシアが付き合ってるって書いてある記事、見た?』
一瞬マックスの動きが止まった。
「え? もう一度言ってくれる?」
『だから、シンシアと俺が付き合ってるって書いてある記事』
「君、いつからシンシアと付き合うようになったの?」
『デマなんです! 本当は付き合ってません!』
「あ、そうか。そうだよね」
ハハハとマックスは笑った。
現在、シンシアがショーンと非常に仲良くなって、ロスに滞在していることは知っていた。だが、マックスもゴシップ雑誌など読まないタチなので、そんな噂など知る由もなかった訳だ。
シンシアに彼氏ができたとなると、そりゃ大変なことになる。
ジムもああ見えて娘には弱いからきっと動揺するだろうし、それ以上に自分も動揺する。レイチェルやセスだって、口を出してくるだろう。
シンシアは正真正銘『箱入り娘』なのだ。
「で、それが・・・」
『俺、コウとまたケンカしちゃって、今別々に住んでるんです。俺はロスに。コウはC市に。コウがその記事を見て誤解したら大変だと思って連絡を取りたいんだけど、コウの勤める証券会社が分からなくて・・・』
「ああ、そうか。そういうことか。それは不安だよね・・・。でもどうしよう・・・」
『 ── 分からなければいいんです。どうせダメもとのつもりでかけてみただけだから・・・。大変だけど、C市にある証券会社の番号調べて、片っ端から電話してみます』
「けれど、それは大変だよ・・・。待って。証券会社に勤めてるんだよね。彼、トレーダーなの?」
『ううん。アナリストだって言ってた。いつも企業とかを回って研究するんだって、そこの株が上がるかどうか。いろんなところに行ってるみたい』
ふとマックスの中で、何かの回路が繋がった。
「ねぇ、そこにメモ帳ある?」
『え? うん。もちろんあります』
「よければ、今から言う電話番号にかけてみて。ミラーズ社の秘書室直通番号だから。そこでジムを呼んでみるといい。彼なら、何か知ってるかもしれないから。本当は携帯の番号を教えたいところだけど、彼のは事情があって教える訳にはいかないんだ。念のため、一足先に俺の方からも彼の携帯に連絡入れとく」
マックスが電話番号を伝えると、弾むような声で『ありがとうございます!』というショーンの返事が返ってきた。
── こういうの、いま泣いた烏がもう笑った、とでも言うのかな。
マックスは微笑むと電話を一旦切って、病院の外に出て、ウォレスに電話をかけたのだった。
ショーンは受話器を両手で掴み、祈るように額に押しつけると、震える手でマックスに教えてもらった番号を押した。
ショーンもまさか、あのミラーズ社のしかも秘書室に電話をかけることになるとは思わなかった。
否が応でも、ドキドキと胸が高鳴る。
『 ── はい、ミラーズ社秘書室でございます』
いかにも大企業の秘書室といった風な、淡々とした気品のある女性の声が応対した。
「あ、あの・・・クーパーと申しますが、ジム・ウォレスさんはいらっしゃいますか?」
ショーンは声が上擦らないようにと、必死にゆっくりとしゃべった。
『主席社長秘書でございますか?』
主席社長秘書なんだ!
思わずショーンは目を剥く。
なんだか全然想像できない世界で、ショーンは目を白黒させた。
「ええと、あの、そうです」
ショーンの受け答えに、相手も不信に思ったらしい。
『恐れ入りますが、もう一度お名前をおっしゃっていただけますか?』
「えっと、クーパーです」
『どちらのクーパー様ですか?』
「え! ええっと・・・ただのクーパーです・・・」
『ただのクーパー様』
「それじゃ、ダメですか?」
思わず気弱になって、そう聞き返してしまう。
またも動揺して、電話口で歌った方がよく分かるかなぁなんて、とんでもないことを考えてしまう。
── どうしよう、どうしよう・・・
そう思っているうち、ふいに受話器の先の声が代わった。
『ショーン?』
忘れもしない、ウォレスの声だった。
「ジム!!」
思わず名前を叫んでしまって、あっと思う。
「す、すみません・・・。俺、偉そうにミスター・ウォレスの名前・・・」
ショーンがそう言うと、受話器からウォレスの笑い声が零れてきた。
『いやこちらこそ、失礼した。さっきまで部屋を空けていてね。マックスの電話をもらって、急いで戻ってきたんだ。要件はマックスから大体聞いたよ。彼氏の勤め先だね』
「ええ、そうです。C市に支店を置く証券会社で、彼はそこでアナリストの仕事をしているんです。名前は、コウゾウ・ハシバ。日本人です。どなたか、知ってそうな人はいらっしゃいますか?」
藁に縋る気持ちでショーンが一気にそう言うと、ウォレスはすぐに「知ってる」と答えてくれた。ショーンは思わず立ち上がる。
「え?! 本当ですか!! その人の連絡先、教えていただけますか?」
『その必要はない。この私が、その知ってる人、だからね』
あまりの返事に、ショーンは口をパクパクさせた。
ウォレスが今何を言ったのか、すぐには理解できなかった。
ウォレスは、ショーンの声を待たずして、先を続けた。
『ここに彼の名刺があるよ。彼は一度我が社を訪問しているんだ。偶然にも、私が接客した。株式を管理している部署のトップが丁度不在だったのでね』
何という偶然だろう。ジムが、コウと面識があったなんて・・・。
よもや羽柴も、ウォレスが自分の傷の手当をした医者の恋人だなんて気付いてもいないだろう。
ショーンはそこに力強いパワーを感じた。
何か普通の力ではない特別な巡り合わせというか、互いに引き寄せている繋がりというか・・・。
そしてようやく、運命的にショーンは羽柴の会社の番号を手に入れたのだった。
何度目かの電話のベルに、ロジャーは『もう、うんざり』といったような溜息をついた。
その電話のベルは、ロジャーの机のものではなく、パーテーションを挟んだ隣の、羽柴の机のものだ。
しつこく鳴り続けるベルに、「ハイハイ。コウゾウはお休みですよ・・・」と呟きながら、羽柴のデスクに向かった。
ロジャーは、脱力したようにドッカとOAイスに腰掛けると、デスクの上のファイルを手にとってそれを開き、両足を行儀悪くデスクの上に投げ出した。
ロジャーの膝上にあるファイルには、羽柴が休みの間に電話がかかってくる可能性のある顧客のリストが書いてあり、それぞれの対応の仕方が指示してある。
ロジャーはおもむろに受話器を取った。
「ハイ、アナリスト部」
『ハロー? コウ?』
「は?」
羽柴のことを『コウ』だなんて呼ぶ人間は、ひょっとしてひょっとしなくても、ロジャーが知る限りひとりしかいない。
思わず受話器を持つロジャーの手が震えた。
『 ── あ、えっと、すみません。・・・ミスター・ハシバ、いらっしゃいますか?』
声に耳を澄ますと、益々自分の思いついた人物に赤い正解ランプが点滅する。
でも、いや、しかし、もし正解だとしたら・・・・。
『もしもし?』
ロジャーは、ギョロギョロと目玉を動かした。
「もしかして・・・もしかしなくても、その・・・。ショーン君?」
その呼び掛けに、相手もロジャーが誰か分かったようだ。
『あ! え? コーエンさん?』
── ああ、神様!!
あまりの嬉しさに、ロジャーは両手放しで喜んだ。その結果、見事にイスごと後ろにスッ転んでしまったが。
ガタガタガタと突如物々しい音が聞こえたから、余程びっくりしたのだろう。
デスクの下にぶら~んとぶらさがっている受話器から、『大丈夫ですか?!』という声が漏れ出てくる。
正真正銘、スターの声だ。
ロジャーは這いずって受話器を掴むと、「俺の名前を覚えていてくれたのかい?」と思わず早口で捲し立ててしまった。
『え、ええ。去年は素敵なクリスマスパーティーに呼んでくださって、本当にありがとうございました』
── ああ、なんていい子なんだろう! スターなのに、ちっとも威張らないし、礼儀もきちっとしてる。我が儘放題の誰かさんとはえらい違いだ・・・。
ロジャーは、鼻をズズッと鳴らしながら、「きっと家の子ども達も喜ぶよ。君にそう言ってもらえて・・・」と答えた。
『 ── あの、それで・・・』
「あ、ああ。耕造ね。アイツ、休みだよ」
『休み?!』
ショーンが驚いた声を上げる。彼が全く羽柴の行動を掴んでいないことが窺えた。
『あの・・・えっと、いつから?』
とても不安げな声。ロジャーは眉間に皺を寄せた。
「丁度今日からだよ。一週間の予定。新年に取り損ねた分を取ったみたい」
『ああ、それじゃ、ずっと休んでる訳じゃないんですね・・・』
それを聞いて、益々ロジャーは皺を深くする。
「ああ、そうだよ。先々月ぐらいに無断欠勤があったけど、それ以外は別に」
ロジャーはそう言いながら、ふと思い当たる節が出てきた。
「そういえば・・・。あの無断欠勤から、様子がちょっとおかしかったな・・・」
ショーンはロジャーの呟きを聞き逃さない。
『様子がおかしかったって、どんな風に?』
ロジャーは、床にゴロリと寝ころんだ。
「何ていうのか・・・・覇気がないというか・・・。いつもの溌剌としたアイツではなかったな。どこか上の空のところもあったし。でも、仕事はきちんとしてたから・・・。あ、そういやショーン君、何の用事だい? 会社までかけてくるなんて、よっぽど急いだ用事なんだろ? あ、そうだ! ひょっとして君、結婚式のスピーチをアイツに頼むとか・・・?!」
ロジャーは身体を起こし、受話器につっこみを入れる。
『え?!』
今度はショーンの刺々しい声が返ってきた。
『どこでそんな話に?』
「や、だって・・・。耕造が言ってたよ。ショーンに新しい恋人ができたって。いい人そうだって・・・」
『 ── マジで?!』
ショーンの叫び声がして、しばらくの沈黙が流れた。
相手の顔が見えなくても、受話器越し、いや~な空気が流れ出てくる。
「あれ? 違うの? ま、俺もおかしいと思ってたんだ。クリスマスの君達の様子を見てたら・・・」
『ミスター・コーエン。コウが今どこにいるか分かりませんか?』
ロジャーはまるで胸ぐらをショーンに掴まれているような気分になった。
ゴクリと喉が鳴る。
「え、いや。自宅にいなかった?」
『留守電でした』
「そしたらええっと・・・そう! そうだ! 日本! 日本に行ってるはずだよ。休みの前、そう言ってた。今度こそ日本に里帰りするって。出発日は分からないが、休み明けの前々日には戻ってくるって言ったよ。つまり今から6日後かな?」
『日本での立ち寄り先は分かりませんか?』
「いやぁ・・・それは。アイツはあまり日本のことを話さないから。トウキョウに行ったことぐらいしか分からないよ」
『そうですか。ありがとう』
そう言って電話は切れた。
ロジャーは、マジマジと電話を見つめる。
ロジャーにはなんだかそれが、やたらと不思議な物体に見えた。
『あの』ショーン・クーパーと電話で話したなんて・・・。
「何やってるんですか、コーエンさん」
転けたイスの傍らで嬉しさに悶えている“ミーハー”ロジャーのことを覗き込んで、ロジャー以上にミーハーな新人社員ハミルトンが怪訝そうな顔をしている。
ショーン・クーパーの大ファンとか言いながら、平気でショーンのゴシップ記事をネタに悪口や冷やかしを言ったりしているいけ好かない奴だ。
ロジャーはすっくと立ち上がると、いつもの“できる男”ロジャーの表情を浮かべ、イスと受話器を元の位置に返し、ハミルトンを見やって言った。
「 ── 今誰から電話がかかってきてたか」
「は? ・・・さぁ・・・」
首を傾げるハミルトンに、したり顔の笑みを浮かべ、ロジャーは言った。
「教えない」
「はぁ?! なんっすか、それ」
ロジャーはそれに一切答えることなく、フフフフフと不適な笑いを浮かべたまま、ブースを後にしたのだった。
── コウは、あの噂のことを知ってた・・・・。
ショーンは愕然として、受話器を耳から下ろした。
「何だ? 何だって?」
斜め向かいのソファーに腰をかけたルイが、焦った表情でショーンを見る。
それに対してショーンは、ゆっくりとルイを見た。凄く険しい表情で。
「コウ、あの噂のこと、信じたみたい・・・」
「何?!」
ルイが大声を張り上げる。ショーンは、静かに頭を項垂れ、横に振った。
「当たり前だ・・・。一週間も前に出てたくせに、俺は否定もしなかったんだから・・・」
ショーンはそう吐き出すと、溜息を立て続けについて、頭を緩く横に振った。
あまりにショックで、涙も出てこない。
── 日本・・・日本か・・・。
まるでショーンの知らない国。
バルーンのツアーでも、日本は一度だけ行ったことがあるが、ホテルとライブ会場に缶詰状態で、まるっきり分からなかった。空港で行きと帰り、ファンに囲まれたぐらいしか思い出に残っていない。
きっと羽柴は、日本にもう向かったのかもしれない。だから携帯電話もエリア圏外になっているに違いないのだ。
益々ショーンは、絶望の淵に立たされた気分になった。
── これでもし、コウが日本に行ったっきり、帰ってこなかったらどうしよう・・・。
ショーンの両手がガタガタと震えた。
── そうだよ。元々彼にとっては、日本に行くことこそ『帰る』ことなんだから・・・。
今すぐ。今すぐにも日本に行きたい。
せめて、誤解だけは解きたい。
これ以上、『嘘』に負けるのなんか、ごめんだ・・・!!
ショーンはふいに立ち上がると、ショーンの部屋になっているゲストルームに向かった。
ルイが怪訝そうな顔つきをして追いかけてくる。
ショーンは作りつけのクローゼットから旅行用にと買った大きなナイロン製の黒い鞄を取り出した。
チェストの引き出しを開け、次々と服を放り込む。
「ショーン、お前、何してる・・・?」
鬼気迫るショーンの気迫に押されて、ゲストルームに入ってこずに戸口から顔を覗かせるだけのルイが、おそるおそる訊いてくる。
ショーンは一心不乱に旅支度をしながら、「何って、日本に行く。今から、日本に行く」と繰り返した。それを聞いて、ルイがぎょっとする。
「無茶だ、ショーン! 彼の行き先、まるで分かってないんだろう?!」
「行ってみたら、何とかなるかもしれない」
「何とかなるって・・・。おい、ちょっと冷静になれ!」
ルイがとうとう部屋に入ってきて、ショーンの腕を掴んだ。
「お前は、ショーン・クーパーだぞ? 日本でもバルーンの売れ行きは凄いし、そのギタリストのことだって皆知ってる。前回行った時も、空港でもみくちゃにされたじゃないか」
「それはバルーンだったからだよ」
「それだけじゃない。エニグマだって日本で翻訳され、発売されてる。アメリカほどではないにしろ、日本でだって同様の広告展開をしたんだ。単身で当てもなく飛び込むなんて、無謀としか言えない。ちょっと考えれば、分かることだろ?」
「分かるけど、でも!!」
ショーンは手に掴んでいるジーンズを、壁に向かって投げつけた。
歯を食いしばって、右手でグシャリと自分の髪の毛を掴む。
「 ── ショーン・・・」
ルイがショーンの肩にそっと触れると、ショーンは顔をくしゃくしゃに歪めて、「クソッ」と小さく悪態をついた。
「このまま・・・誤解されたまま逢えなくなるなんて・・・。そんな・・・」
いくら羽柴の出した答えに納得しようと思っても、こんな答えじゃ納得できない。
それはショーンのせいでも、まして羽柴のせいでもないところから捻り込まれた結果だったからだ。
「どうして皆して、俺のこと傷つけようとするんだろ・・・。存在もしてない彼女のことをエイズで入院してるって言われたり、付き合ってもいないシンシアとの新居を探してるだなんて言われたり・・・。皆本当の俺のことなんて知らないのに、どうしてそんなことばかり。これって、神様がダメだって言ってるのかな? コウと結ばれるのはダメだって、そういうことなのかな?」
傍らにあるベッドに腰を下ろし、ショーンはガックリと肩を落とした。
一気に目が落ちくぼんだような気がする。
── こんな形の終わりなんて・・・・。
ショーンの瞳にじわりと涙が滲んだ時、唐突に電話が鳴った。
リビングにある親機の音に続いて、ゲストルームにある子機も鳴り始める。
全く身動きしないショーンを横目に、ルイが受話器を取った。
「ハイ、サントロ・・・。はい・・・ええ。はい。居ますけど、今ちょっと・・・はい・・・」
ふいに相手の話を聞いて、ルイはパッと表情を変えた。
ルイがショーンに受話器を差し出す。
ショーンが、のろのろと顔を上げた。
ルイは一言言った。
「神は断じてダメだって言っている訳じゃなさそうだよ」
「?」
ショーンは、怪訝に思ってルイを見上げた。
ルイが、グイッと受話器を押しつける。
ショーンはおそるおそる電話に出た。
「・・・ハロー?」
『── ショーン? 私、リサよ。ねぇあなた、日本に行って歌ってみない?』
それは、先日一週間に渡る日本出張から帰国したばかりのリサの声だった。
0
お気に入りに追加
49
あなたにおすすめの小説

恋した貴方はαなロミオ
須藤慎弥
BL
Ω性の凛太が恋したのは、ロミオに扮したα性の結城先輩でした。
Ω性に引け目を感じている凛太。
凛太を運命の番だと信じているα性の結城。
すれ違う二人を引き寄せたヒート。
ほんわか現代BLオメガバース♡
※二人それぞれの視点が交互に展開します
※R 18要素はほとんどありませんが、表現と受け取り方に個人差があるものと判断しレーティングマークを付けさせていただきますm(*_ _)m
※fujossy様にて行われました「コスプレ」をテーマにした短編コンテスト出品作です

年上の恋人は優しい上司
木野葉ゆる
BL
小さな賃貸専門の不動産屋さんに勤める俺の恋人は、年上で優しい上司。
仕事のこととか、日常のこととか、デートのこととか、日記代わりに綴るSS連作。
基本は受け視点(一人称)です。
一日一花BL企画 参加作品も含まれています。
表紙は松下リサ様(@risa_m1012)に描いて頂きました!!ありがとうございます!!!!
完結済みにいたしました。
6月13日、同人誌を発売しました。

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

早く惚れてよ、怖がりナツ
ぱんなこった。
BL
幼少期のトラウマのせいで男性が怖くて苦手な男子高校生1年の那月(なつ)16歳。女友達はいるものの、男子と上手く話す事すらできず、ずっと周りに煙たがられていた。
このままではダメだと、高校でこそ克服しようと思いつつも何度も玉砕してしまう。
そしてある日、そんな那月をからかってきた同級生達に襲われそうになった時、偶然3年生の彩世(いろせ)がやってくる。
一見、真面目で大人しそうな彩世は、那月を助けてくれて…
那月は初めて、男子…それも先輩とまともに言葉を交わす。
ツンデレ溺愛先輩×男が怖い年下後輩
《表紙はフリーイラスト@oekakimikasuke様のものをお借りしました》
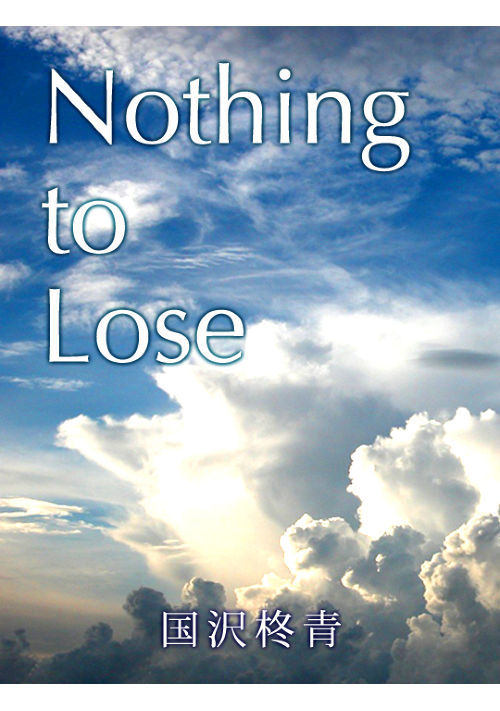
Nothing to Lose
国沢柊青
BL
「タキシードを仕立ててくれ」ある日、老舗の仕立屋・須賀の店に証券アナリストの羽柴が訪れた。いつしか羽柴は、心優しく美しい須賀に惹かれていくのだが、須賀にはその気持ちに応えることのできない秘密を身体に抱えているのだった・・・。
BLオリジナル小説サイト「irregular a.o.」にて公開している作品です。
かなり以前に書いたお話なので、時代背景の関係上、今読むと違和感のある箇所のみ改定して、こちらに投稿しています。
死を扱った作品でもありますので、そういうのが苦手な方はご注意ください。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

相性最高な最悪の男 ~ラブホで会った大嫌いな同僚に執着されて逃げられない~
柊 千鶴
BL
【執着攻め×強気受け】
人付き合いを好まず、常に周囲と一定の距離を置いてきた篠崎には、唯一激しく口論を交わす男がいた。
その仲の悪さから「天敵」と称される同期の男だ。
完璧人間と名高い男とは性格も意見も合わず、顔を合わせればいがみ合う日々を送っていた。
ところがある日。
篠崎が人肌恋しさを慰めるため、出会い系サイトで男を見繕いホテルに向かうと、部屋の中では件の「天敵」月島亮介が待っていた。
「ど、どうしてお前がここにいる⁉」「それはこちらの台詞だ…!」
一夜の過ちとして終わるかと思われた関係は、徐々にふたりの間に変化をもたらし、月島の秘められた執着心が明らかになっていく。
いつも嫌味を言い合っているライバルとマッチングしてしまい、一晩だけの関係で終わるには惜しいほど身体の相性は良く、抜け出せないまま囲われ執着され溺愛されていく話。小説家になろうに投稿した小説の改訂版です。
合わせて漫画もよろしくお願いします。(https://www.alphapolis.co.jp/manga/763604729/304424900)

僕の罪と君の記憶
深山恐竜
BL
——僕は17歳で初恋に落ちた。
そしてその恋は叶った。僕と恋人の和也は幸せな時間を過ごしていたが、ある日和也から別れ話を切り出される。話し合いも十分にできないまま、和也は交通事故で頭を打ち記憶を失ってしまった。
もともと和也はノンケであった。僕は恋仲になることで和也の人生を狂わせてしまったと負い目を抱いていた。別れ話をしていたこともあり、僕は記憶を失った和也に自分たちの関係を伝えなかった。
記憶を失い別人のようになってしまった和也。僕はそのまま和也との関係を断ち切ることにしたのだが……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















