お気に入りに追加
49
あなたにおすすめの小説

恋した貴方はαなロミオ
須藤慎弥
BL
Ω性の凛太が恋したのは、ロミオに扮したα性の結城先輩でした。
Ω性に引け目を感じている凛太。
凛太を運命の番だと信じているα性の結城。
すれ違う二人を引き寄せたヒート。
ほんわか現代BLオメガバース♡
※二人それぞれの視点が交互に展開します
※R 18要素はほとんどありませんが、表現と受け取り方に個人差があるものと判断しレーティングマークを付けさせていただきますm(*_ _)m
※fujossy様にて行われました「コスプレ」をテーマにした短編コンテスト出品作です

年上の恋人は優しい上司
木野葉ゆる
BL
小さな賃貸専門の不動産屋さんに勤める俺の恋人は、年上で優しい上司。
仕事のこととか、日常のこととか、デートのこととか、日記代わりに綴るSS連作。
基本は受け視点(一人称)です。
一日一花BL企画 参加作品も含まれています。
表紙は松下リサ様(@risa_m1012)に描いて頂きました!!ありがとうございます!!!!
完結済みにいたしました。
6月13日、同人誌を発売しました。

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

早く惚れてよ、怖がりナツ
ぱんなこった。
BL
幼少期のトラウマのせいで男性が怖くて苦手な男子高校生1年の那月(なつ)16歳。女友達はいるものの、男子と上手く話す事すらできず、ずっと周りに煙たがられていた。
このままではダメだと、高校でこそ克服しようと思いつつも何度も玉砕してしまう。
そしてある日、そんな那月をからかってきた同級生達に襲われそうになった時、偶然3年生の彩世(いろせ)がやってくる。
一見、真面目で大人しそうな彩世は、那月を助けてくれて…
那月は初めて、男子…それも先輩とまともに言葉を交わす。
ツンデレ溺愛先輩×男が怖い年下後輩
《表紙はフリーイラスト@oekakimikasuke様のものをお借りしました》
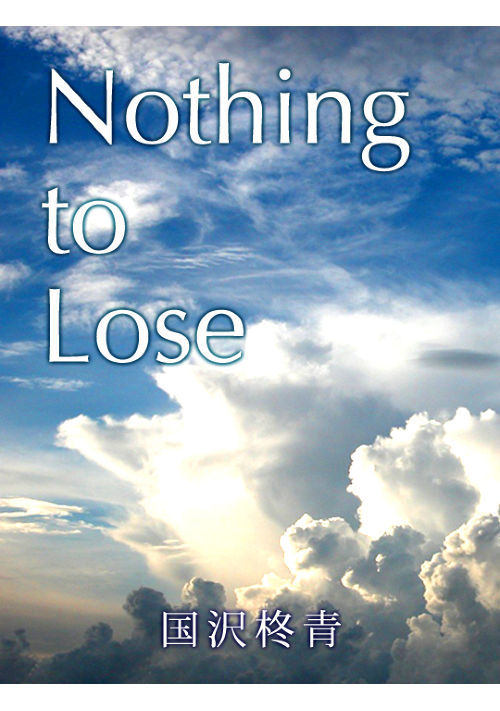
Nothing to Lose
国沢柊青
BL
「タキシードを仕立ててくれ」ある日、老舗の仕立屋・須賀の店に証券アナリストの羽柴が訪れた。いつしか羽柴は、心優しく美しい須賀に惹かれていくのだが、須賀にはその気持ちに応えることのできない秘密を身体に抱えているのだった・・・。
BLオリジナル小説サイト「irregular a.o.」にて公開している作品です。
かなり以前に書いたお話なので、時代背景の関係上、今読むと違和感のある箇所のみ改定して、こちらに投稿しています。
死を扱った作品でもありますので、そういうのが苦手な方はご注意ください。

日本一のイケメン俳優に惚れられてしまったんですが
五右衛門
BL
月井晴彦は過去のトラウマから自信を失い、人と距離を置きながら高校生活を送っていた。ある日、帰り道で少女が複数の男子からナンパされている場面に遭遇する。普段は関わりを避ける晴彦だが、僅かばかりの勇気を出して、手が震えながらも必死に少女を助けた。
しかし、その少女は実は美男子俳優の白銀玲央だった。彼は日本一有名な高校生俳優で、高い演技力と美しすぎる美貌も相まって多くの賞を受賞している天才である。玲央は何かお礼がしたいと言うも、晴彦は動揺してしまい逃げるように立ち去る。しかし数日後、体育館に集まった全校生徒の前で現れたのは、あの時の青年だった──

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

相性最高な最悪の男 ~ラブホで会った大嫌いな同僚に執着されて逃げられない~
柊 千鶴
BL
【執着攻め×強気受け】
人付き合いを好まず、常に周囲と一定の距離を置いてきた篠崎には、唯一激しく口論を交わす男がいた。
その仲の悪さから「天敵」と称される同期の男だ。
完璧人間と名高い男とは性格も意見も合わず、顔を合わせればいがみ合う日々を送っていた。
ところがある日。
篠崎が人肌恋しさを慰めるため、出会い系サイトで男を見繕いホテルに向かうと、部屋の中では件の「天敵」月島亮介が待っていた。
「ど、どうしてお前がここにいる⁉」「それはこちらの台詞だ…!」
一夜の過ちとして終わるかと思われた関係は、徐々にふたりの間に変化をもたらし、月島の秘められた執着心が明らかになっていく。
いつも嫌味を言い合っているライバルとマッチングしてしまい、一晩だけの関係で終わるには惜しいほど身体の相性は良く、抜け出せないまま囲われ執着され溺愛されていく話。小説家になろうに投稿した小説の改訂版です。
合わせて漫画もよろしくお願いします。(https://www.alphapolis.co.jp/manga/763604729/304424900)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















