お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく


10秒で読めるちょっと怖い話。
絢郷水沙
ホラー
ほんのりと不条理な『ギャグ』が香るホラーテイスト・ショートショートです。意味怖的要素も含んでおりますので、意味怖好きならぜひ読んでみてください。(毎日昼頃1話更新中!)
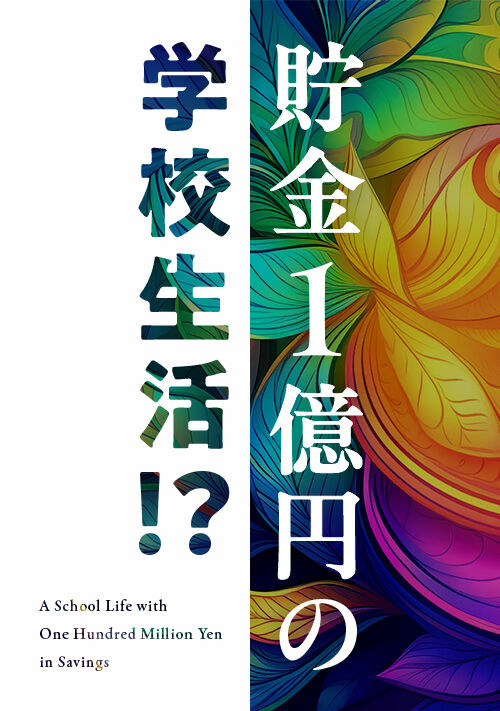
貯金1億円の学校生活!?
白珠ミヅキ
ライト文芸
とある商業学校を舞台に、物語が動き出していきます!
テーマは、お金とビジネスです。
なんだか難しそうなお話になりそう?と思われるかもしれませんが
コミカルな作風で、カンタンに読める作品にまとめていきます。
どうぞ、お付き合いくださいませ!

その後の愛すべき不思議な家族
桐条京介
ライト文芸
血の繋がらない3人が様々な困難を乗り越え、家族としての絆を紡いだ本編【愛すべき不思議な家族】の続編となります。【小説家になろうで200万PV】
ひとつの家族となった3人に、引き続き様々な出来事や苦悩、幸せな日常が訪れ、それらを経て、より確かな家族へと至っていく過程を書いています。
少女が大人になり、大人も年齢を重ね、世代を交代していく中で変わっていくもの、変わらないものを見ていただければと思います。
※この作品は小説家になろう及び他のサイトとの重複投稿作品です。

異世界人生を楽しみたい そのためにも赤ん坊から努力する
カムイイムカ(神威異夢華)
ファンタジー
僕の名前は朝霧 雷斗(アサギリ ライト)
前世の記憶を持ったまま僕は別の世界に転生した
生まれてからすぐに両親の持っていた本を読み魔法があることを学ぶ
魔力は筋力と同じ、訓練をすれば上達する
ということで努力していくことにしました

彼氏彼女の事情『ビッチと噂の黒川さんとお付き合いします!』
KZ
恋愛
初めて目撃した彼氏と彼女というもののワンシーン。その時、その瞬間、初めて自分も彼女がほしいと思った。
だけど好きな女の子どころか、気になる女の子も僕にはいなくて……。
そんな自分が彼女を作るには告白するしかないとたどり着くが、その告白で僕は大きな失態をおかした。
ただ下駄箱にラブレターを入れるというだけの行為に、いざとなったら余裕がなかったのだろう。
僕は隣の席の女の子にラブレターを出したつもりが、ラブレターを女の子のではなくその隣の下駄箱に入れてしまっていたのだ。
そしてその下駄箱は入学から三ヶ月で三人と付き合い、いずれも一ヶ月で別れている女の子の下駄箱だったりした……。
告白されたら断らない、誰とでも付き合う、ビッチと周囲から呼ばれる女の子。
小柄だけど派手派手で、時折とてもしたたかな女の子。
僕は現在そんな女の子とお付き合いしています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















