お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

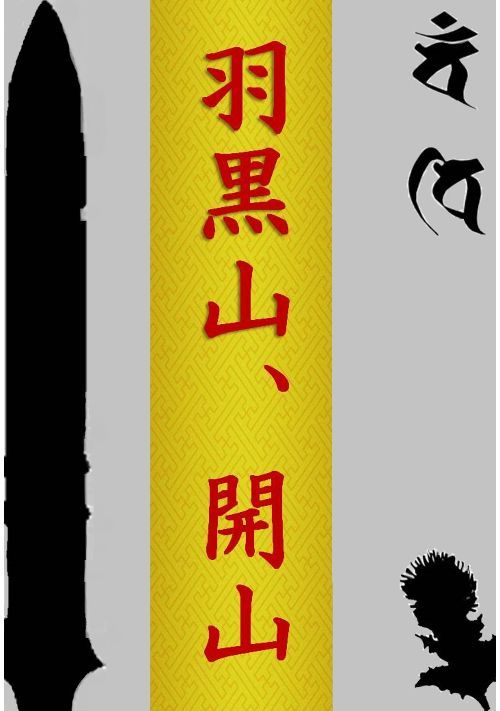
羽黒山、開山
鈴木 了馬
歴史・時代
日本の古代史は改竄された。
いや、正史「日本書紀」は、史実を覆い隠すために作られたと言ってもいい。
ただ、そもそも「歴史」というものは、そのようにしてできるものかもしれないのだが。
ーー崇峻天皇は暗殺された。
ーー崇峻崩御に伴う「殯」の儀式を行わず、死後すぐに赤坂天王山古墳に埋葬された。
正史、日本書紀はそのように書く。
しかし、それが真実である可能性は、10パーセントもあろうか。
むしろ、「殯」がなかったのだから、天皇ではなかった。
すなわち、即位すらしていなかった、と考えるほうが自然ではないのか。
その議論で、鍵となるのは泊瀬部皇子=崇峻天皇の「生年」であろう。
他方、崇峻天皇の第一皇子、蜂子皇子はどうだ。
崇峻天皇の崩御後、皇子は都を逃れ、出羽に赴いた、という伝説が残り、その後1400年、その蜂子皇子が開祖とされる羽黒信仰は脈々と続いてきた。
日本書紀にこそ書かれてはいないが、蜂子皇子伝説が史実である可能性は決して低くないだろう。
そして、蜂子皇子の母である、小手姫の伝説はどうか。
なぜ、587年に福島県の女神山で亡くなったという伝説が残るのか。
日本書紀が、崇峻天皇の崩御年とする、592年よりも、5年も前である。
謎は深まるばかりである。
読み解いても、日本の古代史は、決して真実を教えてはくれない。
数々の記録、伝承の断片をつなぎ、蜂子皇子にまつわる逸話に、一つの流れを持たせるために、筆者はこの物語を編んだ。
なお、この作品で、出羽三部作は完結する。


元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

龍蝨―りゅうのしらみ―
神光寺かをり
歴史・時代
年の暮れも押し迫ってきたその日、
甲州・躑躅ヶ崎館内の真田源五郎の元に、
二つの知らせが届けられた。
一つは「親しい友」との別れ。
もう一つは、新しい命の誕生。
『せめて来年の間は、何事も起きなければ良いな』
微笑む源五郎は、年が明ければは十八歳となる。
これは、ツンデレな兵部と、わがままな源太郎とに振り回される、源五郎の話――。
※この作品は「作者個人サイト【お姫様倶楽部Petit】」「pixiv」「カクヨム」「小説家になろう」でも公開しています。
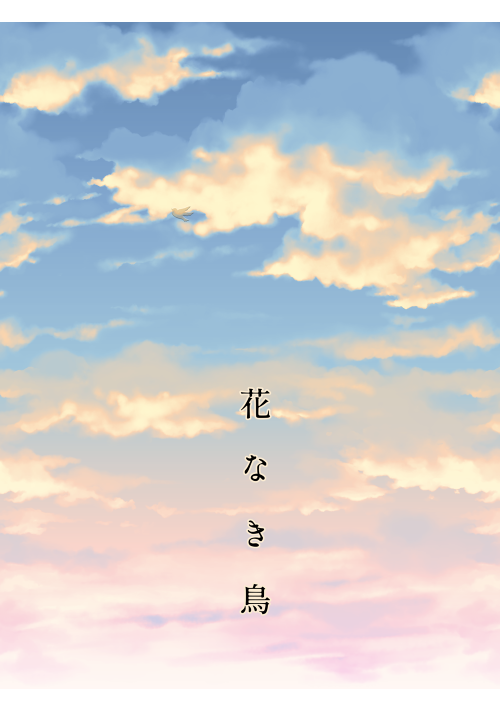
花なき鳥
紫乃森統子
歴史・時代
相添はん 雲のあはひの 彼方(をち)にても──
安政六年、小姓仕えのために城へ上がった大谷武次は、家督を継いで間もない若き主君の帰国に催された春の園遊会で、余興に弓を射ることになる。
武次の放った矢が的にある鳥を縫い留めてしまったことから、謹慎処分を言い渡されてしまうが──

流浪の太刀
石崎楢
歴史・時代
戦国、安土桃山時代を主君を変えながら生き残った一人の侍、高師直の末裔を自称する高師影。高屋又兵衛と名を変えて晩年、油問屋の御隠居となり孫たちに昔話を語る毎日。その口から語られる戦国の世の物語です。

余り侍~喧嘩仲裁稼業~
たい陸
歴史・時代
伊予国の山間にある小津藩は、六万国と小国であった。そこに一人の若い侍が長屋暮らしをしていた。彼の名は伊賀崎余一郎光泰。誰も知らないが、世が世なら、一国一城の主となっていた男だった。酒好き、女好きで働く事は大嫌い。三度の飯より、喧嘩が好きで、好きが高じて、喧嘩仲裁稼業なる片手業で、辛うじて生きている。そんな彼を世の人は、その名前に引っかけて、こう呼んだ。余侍(よざむらい)様と。
第七回歴史・時代小説大賞奨励賞作品
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















