お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

三限目の国語
理科準備室
BL
昭和の4年生の男の子の「ぼく」は学校で授業中にうんこしたくなります。学校の授業中にこれまで入学以来これまで無事に家までガマンできたのですが、今回ばかりはまだ4限目の国語の授業で、給食もあるのでもう家までガマンできそうもなく、「ぼく」は授業をこっそり抜け出して初めての学校のトイレでうんこすることを決意します。でも初めての学校でのうんこは不安がいっぱい・・・それを一つ一つ乗り越えていてうんこするまでの姿を描いていきます。「けしごむ」さんからいただいたイラスト入り。

学校の脇の図書館
理科準備室
BL
図書係で本の好きな男の子の「ぼく」が授業中、学級文庫の本を貸し出している最中にうんこがしたくなります。でも学校でうんこするとからかわれるのが怖くて必死に我慢します。それで何とか終わりの会までは我慢できましたが、もう家までは我慢できそうもありません。そこで思いついたのは学校脇にある市立図書館でうんこすることでした。でも、学校と違って市立図書館には中高生のおにいさん・おねえさんやおじいさんなどいろいろな人が・・・・。「けしごむ」さんからいただいたイラスト入り。
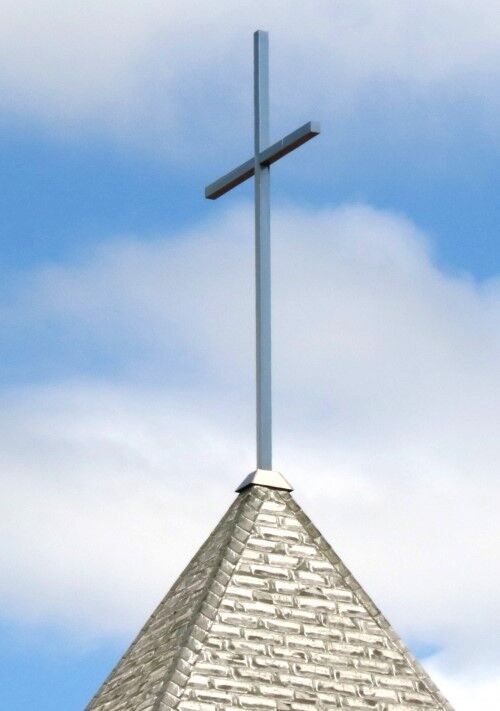
青空
転生新語
現代文学
昨日は娘の、十五才の誕生日だった。そして午前一時過ぎ、寝室で、私は娘から銃を突きつけられていた。
この物語はフィクションです。
カクヨム、小説家になろうに投稿しています。
カクヨム→https://kakuyomu.jp/works/16817330659970259187
小説家になろう→https://ncode.syosetu.com/n6851ih/

お化け屋敷の女たち
瀧けんたろう
現代文学
新橋駅にほどちかい古い雑居ビルは、お化け屋敷かと見まがうほど。地下にある小さな空間で、亜希と舞衣子が熟女Barを始めた。かつて不倫の果てに離婚し、いまはひとり身の亜希。妻子持ちと長年の不倫を続けているどこか奔放な舞衣子。同級生の二人は、やがて五十路に近づいているが、それぞれの人生に、道筋がみえそうで見えない。熟女Barには、ビルのオーナーや様々な客が訪れて賑わっている。ある日、瀬川という男が現れて、亜希はその不思議な男の匂いに、かつて命をかけて身を寄せた男の面影を重ねる。



【完結】【R18百合】会社のゆるふわ後輩女子に抱かれました
千鶴田ルト
恋愛
本編完結済み。細々と特別編を書いていくかもしれません。
レズビアンの月岡美波が起きると、会社の後輩女子の桜庭ハルナと共にベッドで寝ていた。
一体何があったのか? 桜庭ハルナはどういうつもりなのか? 月岡美波はどんな選択をするのか?
おすすめシチュエーション
・後輩に振り回される先輩
・先輩が大好きな後輩
続きは「会社のシゴデキ先輩女子と付き合っています」にて掲載しています。
だいぶ毛色が変わるのでシーズン2として別作品で登録することにしました。
読んでやってくれると幸いです。
「会社のシゴデキ先輩女子と付き合っています」
https://www.alphapolis.co.jp/novel/759377035/615873195
※タイトル画像はAI生成です

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















