3 / 10
35.139.
03
しおりを挟む
「よく言われるよ。このご時世に旅をするだなんて、って。たいてい二言目には言われるし、そう言う人たちはみんな、少しだけ羨ましそうなんだ。」
ヨシキは、時々音の飛んだり跳ねたりするその日本語を聞いて、嬉しいのだか、悲しいのだかといった表情になる。
少し上がった口角。下がった眉尻、そして、エイデンから逸らされる視線。
「きみは、この場所のリーダのようなものかい。」
「あ、ええ、一応は。もともとここにいたのが俺で、他の人たちは、どこかから来たりして。……どうせ死ぬんだから、って、血だらけで転がり込んで来て、寝かせてくれ、って言ってそれからまだ生きて居付いている人もいたりだとかして。」
「でも、誰も争おうとはしないから、他の誰かに統治させようとしたことがない?」
「そう、そうです。誰も、物を取りあったりしないし、時々気が変になって自殺したりはするんですけど、直接誰かを傷つけたり、喧嘩をしたりはしないから、それなら誰かにわざわざ面倒をかけるよりは、俺がこのままリーダーみたいな立場で、やってた方が、いいかなあって。」
俺、ほら、まだ若いですから。
ヨシキが力こぶを作って見せるのを、エイデンはほんわりと笑って、見つめている。
たしかに、ヨシキの言う通り、この繭の中にいる人間が声を荒げているところは、いくらここへ来た日のうちだと言ったって想像がつかない。みなめいめいに外を眺めたり、椅子の背もたれをぎいぎいとやったり、ホワイトボードに、泥まみれの指で絵を描いたりなどしているのだから。
そもそも、会話が少ないのだ。
そして、人生に絶望してしまったから人と関わらないのだ、と、断言できるような陰鬱な空気が流れているわけでもない。
エイデンが疑問に思ったのは、そこだった。
「みんな、ここでは好きなことをして過ごすのかい。」
「そうです。どうせ死ぬからって、みんな。」
「生き延びるために食事を摂ったりは?」
「あんまり、ないですね。たいてい三日くらい何も食べないと、こう、ふらっとどこかへ出かけて死んでたりしますし。生きてたい人も、そんなにいないのかもしれないです。」
だから、俺みたいなのがここでいちばん、長く生きてる人間になるんですよ。そう言うヨシキの横顔は、大きなガラス窓の曇ったのから入りこむ、不安定に鋭利な夕陽に阻まれて見えなかった。
苦しんで、生きようとして死ぬよりは、自分らしく、豊かなまま死にたい。そんな風に思う人間は、なにも彼らだけというわけではない。プライドの高い人間であればあるほど、地位の高い人間であればあるほど尊厳死を望んだ、過去の記録からも明らかなように。
「ヨシキ、君はどうなんだい。」
「死のうと思ったことですか?」
曇った眼鏡を、よれたワイシャツの袖で拭く。そんな仕草が珍しかったのか、ヨシキの顔が、エイデンの方を見た気がした。けれどエイデンは構わず、問いかける。
「そう、……もしくは、生きたくない、と思ったこと。」
ゆがんだ金属製のフレームは、きっと火でも入れなければもとには戻らないだろう。ヒビの入ってしまったレンズは、きっともう替えるよりほかないのだろう。
「……あんまり、ないですね。だって死にたかろうが、生きたくなかろうが、きっと俺の意識って、死ぬ瞬間までは残ってるわけじゃないですか。死ぬときなんて、きっと、こう、糸が切れるようなもんだと思うんです。だから、なんていうか。生き死にのことって、考えるだけ無駄かなあって。」
真鍮だか何だかのフレームを、夕陽が撫でる。ぼやけた視界にはやはりそれは鋭利で痛い。けれど、はたして自分の視界が鮮明だったとして、純粋にその美しさを思うことはできたのだろうか。
「エイデンさんは、あるんですか?」
レンズのヒビに、オレンジ色が染みてゆく。アスファルトの隙間に雨が流れるようだ、と、いつだかにアイビーが形容したことを思い出したけれど、アスファルトに雨が流れるさまなんて、そんな多少の色の違い、自然現象なんて捉えられるほど上等な目をしていないエイデンには、やはり、彼女が何を伝えたかったのかは分からない。
「あるよ、何度か。」
ヨシキは、時々音の飛んだり跳ねたりするその日本語を聞いて、嬉しいのだか、悲しいのだかといった表情になる。
少し上がった口角。下がった眉尻、そして、エイデンから逸らされる視線。
「きみは、この場所のリーダのようなものかい。」
「あ、ええ、一応は。もともとここにいたのが俺で、他の人たちは、どこかから来たりして。……どうせ死ぬんだから、って、血だらけで転がり込んで来て、寝かせてくれ、って言ってそれからまだ生きて居付いている人もいたりだとかして。」
「でも、誰も争おうとはしないから、他の誰かに統治させようとしたことがない?」
「そう、そうです。誰も、物を取りあったりしないし、時々気が変になって自殺したりはするんですけど、直接誰かを傷つけたり、喧嘩をしたりはしないから、それなら誰かにわざわざ面倒をかけるよりは、俺がこのままリーダーみたいな立場で、やってた方が、いいかなあって。」
俺、ほら、まだ若いですから。
ヨシキが力こぶを作って見せるのを、エイデンはほんわりと笑って、見つめている。
たしかに、ヨシキの言う通り、この繭の中にいる人間が声を荒げているところは、いくらここへ来た日のうちだと言ったって想像がつかない。みなめいめいに外を眺めたり、椅子の背もたれをぎいぎいとやったり、ホワイトボードに、泥まみれの指で絵を描いたりなどしているのだから。
そもそも、会話が少ないのだ。
そして、人生に絶望してしまったから人と関わらないのだ、と、断言できるような陰鬱な空気が流れているわけでもない。
エイデンが疑問に思ったのは、そこだった。
「みんな、ここでは好きなことをして過ごすのかい。」
「そうです。どうせ死ぬからって、みんな。」
「生き延びるために食事を摂ったりは?」
「あんまり、ないですね。たいてい三日くらい何も食べないと、こう、ふらっとどこかへ出かけて死んでたりしますし。生きてたい人も、そんなにいないのかもしれないです。」
だから、俺みたいなのがここでいちばん、長く生きてる人間になるんですよ。そう言うヨシキの横顔は、大きなガラス窓の曇ったのから入りこむ、不安定に鋭利な夕陽に阻まれて見えなかった。
苦しんで、生きようとして死ぬよりは、自分らしく、豊かなまま死にたい。そんな風に思う人間は、なにも彼らだけというわけではない。プライドの高い人間であればあるほど、地位の高い人間であればあるほど尊厳死を望んだ、過去の記録からも明らかなように。
「ヨシキ、君はどうなんだい。」
「死のうと思ったことですか?」
曇った眼鏡を、よれたワイシャツの袖で拭く。そんな仕草が珍しかったのか、ヨシキの顔が、エイデンの方を見た気がした。けれどエイデンは構わず、問いかける。
「そう、……もしくは、生きたくない、と思ったこと。」
ゆがんだ金属製のフレームは、きっと火でも入れなければもとには戻らないだろう。ヒビの入ってしまったレンズは、きっともう替えるよりほかないのだろう。
「……あんまり、ないですね。だって死にたかろうが、生きたくなかろうが、きっと俺の意識って、死ぬ瞬間までは残ってるわけじゃないですか。死ぬときなんて、きっと、こう、糸が切れるようなもんだと思うんです。だから、なんていうか。生き死にのことって、考えるだけ無駄かなあって。」
真鍮だか何だかのフレームを、夕陽が撫でる。ぼやけた視界にはやはりそれは鋭利で痛い。けれど、はたして自分の視界が鮮明だったとして、純粋にその美しさを思うことはできたのだろうか。
「エイデンさんは、あるんですか?」
レンズのヒビに、オレンジ色が染みてゆく。アスファルトの隙間に雨が流れるようだ、と、いつだかにアイビーが形容したことを思い出したけれど、アスファルトに雨が流れるさまなんて、そんな多少の色の違い、自然現象なんて捉えられるほど上等な目をしていないエイデンには、やはり、彼女が何を伝えたかったのかは分からない。
「あるよ、何度か。」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説



砂漠と鋼とおっさんと
ゴエモン
SF
2035年ある日地球はジグソーパズルのようにバラバラにされ、以前の形を無視して瞬時に再び繋ぎ合わされた。それから120年後……
男は砂漠で目覚めた。
ここは日本?海外?そもそも地球なのか?
訳がわからないまま男は砂漠を一人歩き始める。
巨大な陸上を走る船サンドスチーム。
屋台で焼き鳥感覚に銃器を売る市場。
ひょんなことから手にした電脳。
生物と機械が合成された機獣(ミュータント)が跋扈する世界の中で、男は生き延びていかねばならない。
荒廃した世界で男はどこへいくのか?
と、ヘヴィな話しではなく、男はその近未来世界で馴染んで楽しみ始めていた。
それでも何とか生活費は稼がにゃならんと、とりあえずハンターになってたま〜に人助け。
女にゃモテずに、振られてばかり。
電脳ナビを相棒に武装ジャイロキャノピーで砂漠を旅する、高密度におっさん達がおりなすSF冒険浪漫活劇!


廃線隧道(ずいどう)
morituna
SF
18世紀末の明治時代に開通した蒸気機関車用のシャチホコ線は、単線だったため、1966年(昭和41)年に廃線になりました。
廃線の際に、レールや枕木は撤去されましたが、多数の隧道(ずいどう;トンネルのこと)は、そのまま残されました。
いつしか、これらの隧道は、雑草や木々の中に埋もれ、人々の記憶から忘れ去られました。
これらの廃線隧道は、時が止まった異世界の雰囲気が感じられると思われるため、俺は、廃線隧道の一つを探検することにした。


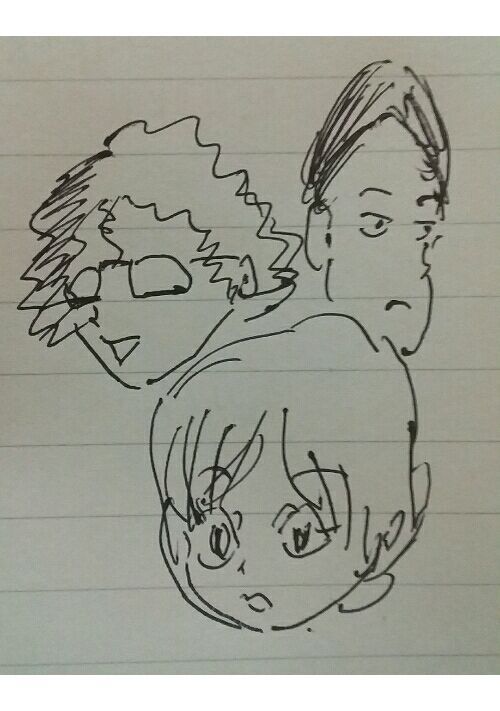
99%のサイエンス
千田 陽斗(せんだ はると)
SF
オカルト雑誌編集者の大宮ノリカ、週刊誌編集者の九条レオ、レオの兄で甲斐性なしのオカルトマニアである九条マコト ひょんなことから3人は各地で起こる不思議なできごとを取材することになる -完全なものなんかこの世界にはない 最高の科学者でさえ99%しかこの世界を理解できない-
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















