29 / 36
五十崎檀子の手記
二十七
しおりを挟む
李大龍は少女の首に向き直ると、静かに何事か囁きかけました。苦しげに頭を動かしていた少女ははっとしたように動きを止め、それから俄かに李大龍の存在に気がついた様子で、黒い大きな瞳をゆっくりと上げました。李大龍の青い瞳と少女の黒い瞳とが重なり合うと、少女の苦悶に歪められた顔はみるみるうちに緩み、清らかな花の顔へと立ち返っていきました。
李大龍はおもむろに右手の人差し指と中指を自分の唇に当て、強く噛んだようでした。二本の指を離したとき、唇に真っ赤な鮮血が付着しているのが、彼の目の光の中に浮かび上がって見えました。──もっとも、薄暗い蔵の中、青白い月明かりのような光の下で見た血の色が、そんなにも鮮やかな赤色に見えたはずはなかったでしょうから、もしかするとこれはわたしの心象であるのかもしれません。
李大龍は少女の額に描かれた花模様の上に、先ほど噛み切った二本の指をそっと押し当て、何かを書きつけるように動かしていきました。しなやかな指先が離された少女の額には、わたしには読めない複雑な形の漢字が一字、書きつけられていました。それは非常に強力な効果を発揮する一字であったのでしょう──少なくともこの首だけの少女にとってはそうであったに違いありません──、愛らしい桃色をその頬に取り戻した少女は深い吐息をついた後、ゆっくりと瞼を閉じていきました。咲きかけた花のつぼみのような唇を時折微笑の形にほころばせながら、安らかな眠りを李大龍の呪言の揺りかごで楽しんでいるのがわかりました。そうやって眠っている少女は、ほんとうにあどけない、可憐な野の花のようにいじらしく見えました。
少女の眠りを確かめると、李大龍は顔を上げ、未だ辺りを漂っている瘴気の残滓に青く光る目を向けました。すると瘴気はゆらゆらと羽衣のように舞いながらだんだんと透き通っていくのでした。瘴気はやがてひとつに寄り集まって李大龍の目の前で軽やかに揺蕩っていましたが、みるみるうちに半透明の結晶石を思わす美しい鳥の姿へと変じ、その翼をゆっくりと蔵の薄闇に広げました。
わたしは驚嘆と感嘆に息を呑み、李大龍と鳥が見つめ合っているその光景を凝然と見つめ続けていました。
鳥はふと長い首を動かして、少女の首を静かに見おろしました。その目には、何か別れを告げているように寂しげな、それでいて毅然とした高貴さが揺らめくように見えました。その姿を見つめるうちに、わたしの目からははらはらと熱い涙がこぼれ落ち始めました。あふれる涙でわたしの視界は滲み、そのために透明な水底の世界にいるようでした。その深い水の世界の中で、李大龍は板の間に片膝を着いた姿勢のまま、ゆっくりと鳥に向かって両腕を広げました。
「过来──」
今度もわたしには李大龍が「おいで──」と泣きたくなるほどにやさしい声で呼びかけたことがわかり、いよいよ嗚咽を上げそうになる喉を押さえて堪えていると、鳥が半透明の石英のような翼をはためかせながら李大龍の胸に舞い降りていくのが見えました。鳥の羽ばたきは宙に美しい波紋を描いて広がり、その波はわたしの足元にまで届いて清らかな水でつま先を湿らせるようでした。
鳥は眩い光を放ちながら李大龍の胸の中へと吸い込まれていきました。涙に濡れたわたしの目に、その光輝は万華鏡のようにきらきらと眩しく反射し、思わず目を眇めながらも鳥の長い尾羽の最後の一枚までが李大龍の体内に消えていくのを見守りました。
鳥のすべてが吸い込まれると、李大龍の体からはかっとひときわ強い閃光が放たれました。あまりの光の強さに、目を開けていることができないほどでした。やがて閉じた瞼の向こうで次第に光が引いて行くのを感じて目を開けると、瞼を伏せてうつむく李大龍の体のまわりを、彼の僕のような妖気が、蔵の天井に届きそうなほどに大きくなったり、或いは彼の体にぴったりと張りつくように小さくなったりするのを繰り返すのが見えました。
やがて妖気が凪いで、静かに顔を上げた李大龍のその瞳からは、あの霊妙な青白い光が消えていました。けれどその瞳には未だやさしい火が、消えもせず灯っているようでした。李大龍は眠り続ける少女の首を、その眼差しで抱くように見つめました。労わるような、慈しむような視線にくるまれた少女の首は、まるで幸福な夢に浸かる喜びを表すように、安らいだ微笑を唇に浮かべました。
李大龍はおもむろに右手の人差し指と中指を自分の唇に当て、強く噛んだようでした。二本の指を離したとき、唇に真っ赤な鮮血が付着しているのが、彼の目の光の中に浮かび上がって見えました。──もっとも、薄暗い蔵の中、青白い月明かりのような光の下で見た血の色が、そんなにも鮮やかな赤色に見えたはずはなかったでしょうから、もしかするとこれはわたしの心象であるのかもしれません。
李大龍は少女の額に描かれた花模様の上に、先ほど噛み切った二本の指をそっと押し当て、何かを書きつけるように動かしていきました。しなやかな指先が離された少女の額には、わたしには読めない複雑な形の漢字が一字、書きつけられていました。それは非常に強力な効果を発揮する一字であったのでしょう──少なくともこの首だけの少女にとってはそうであったに違いありません──、愛らしい桃色をその頬に取り戻した少女は深い吐息をついた後、ゆっくりと瞼を閉じていきました。咲きかけた花のつぼみのような唇を時折微笑の形にほころばせながら、安らかな眠りを李大龍の呪言の揺りかごで楽しんでいるのがわかりました。そうやって眠っている少女は、ほんとうにあどけない、可憐な野の花のようにいじらしく見えました。
少女の眠りを確かめると、李大龍は顔を上げ、未だ辺りを漂っている瘴気の残滓に青く光る目を向けました。すると瘴気はゆらゆらと羽衣のように舞いながらだんだんと透き通っていくのでした。瘴気はやがてひとつに寄り集まって李大龍の目の前で軽やかに揺蕩っていましたが、みるみるうちに半透明の結晶石を思わす美しい鳥の姿へと変じ、その翼をゆっくりと蔵の薄闇に広げました。
わたしは驚嘆と感嘆に息を呑み、李大龍と鳥が見つめ合っているその光景を凝然と見つめ続けていました。
鳥はふと長い首を動かして、少女の首を静かに見おろしました。その目には、何か別れを告げているように寂しげな、それでいて毅然とした高貴さが揺らめくように見えました。その姿を見つめるうちに、わたしの目からははらはらと熱い涙がこぼれ落ち始めました。あふれる涙でわたしの視界は滲み、そのために透明な水底の世界にいるようでした。その深い水の世界の中で、李大龍は板の間に片膝を着いた姿勢のまま、ゆっくりと鳥に向かって両腕を広げました。
「过来──」
今度もわたしには李大龍が「おいで──」と泣きたくなるほどにやさしい声で呼びかけたことがわかり、いよいよ嗚咽を上げそうになる喉を押さえて堪えていると、鳥が半透明の石英のような翼をはためかせながら李大龍の胸に舞い降りていくのが見えました。鳥の羽ばたきは宙に美しい波紋を描いて広がり、その波はわたしの足元にまで届いて清らかな水でつま先を湿らせるようでした。
鳥は眩い光を放ちながら李大龍の胸の中へと吸い込まれていきました。涙に濡れたわたしの目に、その光輝は万華鏡のようにきらきらと眩しく反射し、思わず目を眇めながらも鳥の長い尾羽の最後の一枚までが李大龍の体内に消えていくのを見守りました。
鳥のすべてが吸い込まれると、李大龍の体からはかっとひときわ強い閃光が放たれました。あまりの光の強さに、目を開けていることができないほどでした。やがて閉じた瞼の向こうで次第に光が引いて行くのを感じて目を開けると、瞼を伏せてうつむく李大龍の体のまわりを、彼の僕のような妖気が、蔵の天井に届きそうなほどに大きくなったり、或いは彼の体にぴったりと張りつくように小さくなったりするのを繰り返すのが見えました。
やがて妖気が凪いで、静かに顔を上げた李大龍のその瞳からは、あの霊妙な青白い光が消えていました。けれどその瞳には未だやさしい火が、消えもせず灯っているようでした。李大龍は眠り続ける少女の首を、その眼差しで抱くように見つめました。労わるような、慈しむような視線にくるまれた少女の首は、まるで幸福な夢に浸かる喜びを表すように、安らいだ微笑を唇に浮かべました。
0
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説


七つの不思議のその先に願い事1つ叶えましょう
桜月 翠恋
ホラー
オカルトサークルという名目で今日も怖い話の好きな仲のいい8人が集まり今日も楽しくお話をする
『ねぇねぇ、七不思議、挑戦してみない?』
誰が言ったのか、そんな一言。
この学校の七不思議は他と少し違っていて…
8人が遊び半分に挑戦したのは…
死が待ち受けているゲームだった……

5分で読めるブラックユーモア
夜寝乃もぬけ
ホラー
ようこそ喫茶『BLACK』へ
当店は苦さ、ユニークさ、後味の悪さを焙煎した
【5分で読めるブラックユーモア】しか置いておりません。
ブラックな世界へとドリップできる極上の一品です。
※シュガー好きな方はお口に合いませんので、どうぞお帰り下さい。

THE TOUCH/ザ・タッチ -呪触-
ジャストコーズ/小林正典
ホラー
※アルファポリス「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」サバイバルホラー賞受賞。群馬県の山中で起こった惨殺事件。それから六十年の時が経ち、夏休みを楽しもうと、山にあるログハウスへと泊まりに来た六人の大学生たち。一方、爽やかな自然に場違いなヤクザの三人組も、死体を埋める仕事のため、同所へ訪れていた。大学生が謎の老人と遭遇したことで事態は一変し、不可解な死の連鎖が起こっていく。生死を賭けた呪いの鬼ごっこが、今始まった……。
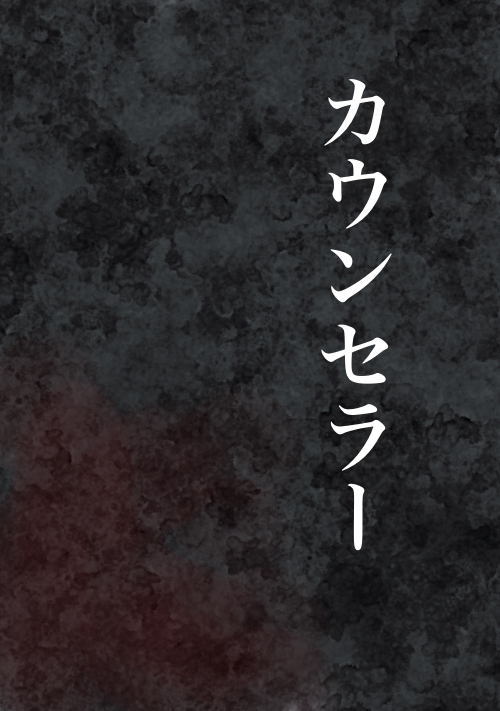
カウンセラー
曇戸晴維
ホラー
あなたは、あなたの生きたい人生を歩んでいますか?
あなたは、あなたでいる意味を見出せていますか?
あなたは、誰かを苦しめてはいませんか?
ひとりの記者がSMバーで出会った、カウンセラー。
彼は、夜の街を練り歩く、不思議な男だった。
※この物語はフィクションです。
あなたの精神を蝕む可能性があります。
もし異常を感じた場合は、医療機関、または然るべき機関への受診をお勧めします。

銀の少女
栗須帳(くりす・とばり)
ホラー
昭和58年。
藤崎柚希(ふじさき・ゆずき)は、いじめに悩まされる日々の中、高校二年の春に田舎の高校に転校、新生活を始めた。
父の大学時代の親友、小倉の隣の家で一人暮らしを始めた柚希に、娘の早苗(さなえ)は少しずつ惹かれていく。
ある日柚希は、銀髪で色白の美少女、桐島紅音(きりしま・あかね)と出会う。
紅音には左手で触れた物の生命力を吸い取り、右手で触れた物の傷を癒す能力があった。その能力で柚希の傷を治した彼女に、柚希は不思議な魅力を感じていく。
全45話。

最終死発電車
真霜ナオ
ホラー
バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。
直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。
外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。
生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。
「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

ゾバズバダドガ〜歯充烏村の呪い〜
ディメンションキャット
ホラー
主人公、加賀 拓斗とその友人である佐々木 湊が訪れたのは外の社会とは隔絶された集落「歯充烏村」だった。
二人は村長から村で過ごす上で、絶対に守らなければならない奇妙なルールを伝えられる。
「人の名前は絶対に濁点を付けて呼ばなければならない」
支離滅裂な言葉を吐き続ける老婆や鶏を使ってアートをする青年、呪いの神『ゾバズバダドガ』。異常が支配するこの村で、次々に起こる矛盾だらけの事象。狂気に満ちた村が徐々に二人を蝕み始めるが、それに気付かない二人。
二人は無事に「歯充烏村」から抜け出せるのだろうか?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















