1 / 1
死が二人を分かつまで
しおりを挟む
「先生、好きでした。……いいえ。ずっと、好きです。今でも」
同窓会で、焼けぼっくいに火がついたなんて話はチラホラ聞いたことがあったが、まさか自分の身にそんな珍事が起こるとは夢にも思っていなかった。
いや、これはタチの悪い冗談か、何かの罰ゲームに違いない。そう確信しながらも、人様から「好き」だなんて言われたのはかれこれ何十年かぶりで、思わず言葉に詰まってしまう。
曖昧に、はは、と笑って動揺を誤魔化した。
「冗談じゃないですよ。柔道部で落ちこぼれだった僕に、親身になってくださった先生が居たから、今の僕があるんです。お陰で無事に定年まで勤め上げました」
そう、今日は教え子たちの還暦祝いの同窓会だった。私はと言えば、もう七十八。
だからこの告白が、いかに馬鹿げているか分かるだろう。
しかも。
「岸谷、刑事が人をからかうもんじゃない。何の罰ゲームなんだ」
私は何とか心を落ち着けて、真っ直ぐに見詰めてくる岸谷のはしばみ色の瞳をレンズ越しに見やる。
でも気まずいほど見詰められるばかりで、私は視線を落として老眼鏡を何度か押し上げた。
「ですから、刑事は定年しました。今の僕は、ただの男です」
「それにしたって、悪い冗談だ」
私はまた、老眼鏡を押し上げる。
岸谷は、還暦だというのに高校生の頃の面影が濃く残る面差しで、上質なグレーの三つ揃いをスマートに着こなしていた。
叩き上げでついこの間まで刑事をやっていた人間らしく、体躯は逞しく、『美丈夫』という言葉がぴたりとくる。
彼は学年に一人は居る、言わばアイドル的な存在で、彼女を取っかえ引っ変えしていたのをよく覚えていた。
かたや私はもう、棺桶に片足を突っ込んだ、枯れ枝のような老人だ。
「悪い冗談だ」
私は何だか上気する額を手の甲で拭って、繰り返す。
「あ……これ。プレゼントするつもりで持ってきたんです。使ってください」
「え? ああ……ありがとう」
包装紙も何もあったもんじゃない、むき出しの藍鼠色のハンカチがスッと差し出されて受け取ると、確かに白い糸で私のイニシャルが刺繍されていた。
汗ばむ額に当てると、仄かに上品な香りがふわりと漂う。私が歴史の授業中に生徒たちに幾つか嗅がせたことのある、平安時代の練香だった。
「……菊花?」
思わず呟くと、くそ真面目だった岸谷の顔が笑み崩れた。目尻に笑いじわが刻まれ、白い歯がチラと覗く。
何故かそれに、健康的な色香を感じた。
「そうです。先生なら、気付いてくれると思ってました」
「岸谷……本気か?」
私はハンカチを握り締め、ポカンと口を開いた。開いた口が塞がらない。まさにそんな心境だった。
嗚呼……またひとつ、白い歯が笑み零れる。
「はは。人間驚くと、本当に口が開くものなんですね」
意識して口を閉じながら、考える。
岸谷が、こんなに手の込んだ悪ふざけをするだろうか? 罰ゲームで、こんなにも眩しく笑うだろうか?
私は困惑して、一番の問題を口にする。
「岸谷……だって私たちは……男同士……じゃないか……」
岸谷は、今度は悪戯っ子のように目を輝かせた。
「おや。衆道や白拍子を教える時に、『愛や生き方の形は、性別にとらわれてはいけない』と教えてくれたのは先生ですが?」
「だが……私はもう……」
「もう、何です? 奥様が七年前に亡くなられたのは、聞きました。お気の毒です。ですが、先生さえ良ければ……もうそろそろ、新しい恋をしても良い頃じゃありませんか?」
不思議と、言葉が素直に響いてきた。でも反対に、罪悪感が込み上げてきて口を割る。
「私はもう、君の要求に応えられる身体ではないのだよ……」
何を言っているんだ、私は。恥じ入る少女のように、俯いて消え入りそうな震える声音で絞り出す。
「ああ……先生。そういう意味じゃないんです。僕も、とっくに」
杖を握っていた方の手に、そっと逞しい岸谷の拳が添えられた。
顔を上げると、思いがけず穏やかに微笑む瞳と目が合って鼓動が速くなる。
「好きです、先生。この近くに、おでんの美味しい居酒屋を知っているんです。試しに僕と、デートして頂けませんか?」
肘を曲げて差し出された。それがエスコートの合図だと気付くのに、五秒かかった。気付いた途端、また顔が上気する。
「先生がお帰りになるので、僕が送っていきます!」
岸谷は、律儀に声を張り上げた。
女性は幾つになっても目敏いものだ。
「あら。先生と岸谷さん、腕組んでらっしゃらなかった?」
「シーッ。うふふ……」
そんなざわざわが遠ざかる。
通行人が見れば、それは『介護』に見えただろう。
「先生は、おでんはお好きですか?」
「あ……ああ」
「何がお好きですか? 僕は、大根が」
「私は、はんぺんかな」
そんな他愛のない会話を交わしながら、私は岸谷の腕にすがってゆっくりと歩く。
老いらくの恋は情が深いなんて言うけれど、この年になってまた恋をするとは思わなかった。
歩調を合わせて歩いてくれる岸谷の優しさに、私は恋の始まりを見出していた。
End.
同窓会で、焼けぼっくいに火がついたなんて話はチラホラ聞いたことがあったが、まさか自分の身にそんな珍事が起こるとは夢にも思っていなかった。
いや、これはタチの悪い冗談か、何かの罰ゲームに違いない。そう確信しながらも、人様から「好き」だなんて言われたのはかれこれ何十年かぶりで、思わず言葉に詰まってしまう。
曖昧に、はは、と笑って動揺を誤魔化した。
「冗談じゃないですよ。柔道部で落ちこぼれだった僕に、親身になってくださった先生が居たから、今の僕があるんです。お陰で無事に定年まで勤め上げました」
そう、今日は教え子たちの還暦祝いの同窓会だった。私はと言えば、もう七十八。
だからこの告白が、いかに馬鹿げているか分かるだろう。
しかも。
「岸谷、刑事が人をからかうもんじゃない。何の罰ゲームなんだ」
私は何とか心を落ち着けて、真っ直ぐに見詰めてくる岸谷のはしばみ色の瞳をレンズ越しに見やる。
でも気まずいほど見詰められるばかりで、私は視線を落として老眼鏡を何度か押し上げた。
「ですから、刑事は定年しました。今の僕は、ただの男です」
「それにしたって、悪い冗談だ」
私はまた、老眼鏡を押し上げる。
岸谷は、還暦だというのに高校生の頃の面影が濃く残る面差しで、上質なグレーの三つ揃いをスマートに着こなしていた。
叩き上げでついこの間まで刑事をやっていた人間らしく、体躯は逞しく、『美丈夫』という言葉がぴたりとくる。
彼は学年に一人は居る、言わばアイドル的な存在で、彼女を取っかえ引っ変えしていたのをよく覚えていた。
かたや私はもう、棺桶に片足を突っ込んだ、枯れ枝のような老人だ。
「悪い冗談だ」
私は何だか上気する額を手の甲で拭って、繰り返す。
「あ……これ。プレゼントするつもりで持ってきたんです。使ってください」
「え? ああ……ありがとう」
包装紙も何もあったもんじゃない、むき出しの藍鼠色のハンカチがスッと差し出されて受け取ると、確かに白い糸で私のイニシャルが刺繍されていた。
汗ばむ額に当てると、仄かに上品な香りがふわりと漂う。私が歴史の授業中に生徒たちに幾つか嗅がせたことのある、平安時代の練香だった。
「……菊花?」
思わず呟くと、くそ真面目だった岸谷の顔が笑み崩れた。目尻に笑いじわが刻まれ、白い歯がチラと覗く。
何故かそれに、健康的な色香を感じた。
「そうです。先生なら、気付いてくれると思ってました」
「岸谷……本気か?」
私はハンカチを握り締め、ポカンと口を開いた。開いた口が塞がらない。まさにそんな心境だった。
嗚呼……またひとつ、白い歯が笑み零れる。
「はは。人間驚くと、本当に口が開くものなんですね」
意識して口を閉じながら、考える。
岸谷が、こんなに手の込んだ悪ふざけをするだろうか? 罰ゲームで、こんなにも眩しく笑うだろうか?
私は困惑して、一番の問題を口にする。
「岸谷……だって私たちは……男同士……じゃないか……」
岸谷は、今度は悪戯っ子のように目を輝かせた。
「おや。衆道や白拍子を教える時に、『愛や生き方の形は、性別にとらわれてはいけない』と教えてくれたのは先生ですが?」
「だが……私はもう……」
「もう、何です? 奥様が七年前に亡くなられたのは、聞きました。お気の毒です。ですが、先生さえ良ければ……もうそろそろ、新しい恋をしても良い頃じゃありませんか?」
不思議と、言葉が素直に響いてきた。でも反対に、罪悪感が込み上げてきて口を割る。
「私はもう、君の要求に応えられる身体ではないのだよ……」
何を言っているんだ、私は。恥じ入る少女のように、俯いて消え入りそうな震える声音で絞り出す。
「ああ……先生。そういう意味じゃないんです。僕も、とっくに」
杖を握っていた方の手に、そっと逞しい岸谷の拳が添えられた。
顔を上げると、思いがけず穏やかに微笑む瞳と目が合って鼓動が速くなる。
「好きです、先生。この近くに、おでんの美味しい居酒屋を知っているんです。試しに僕と、デートして頂けませんか?」
肘を曲げて差し出された。それがエスコートの合図だと気付くのに、五秒かかった。気付いた途端、また顔が上気する。
「先生がお帰りになるので、僕が送っていきます!」
岸谷は、律儀に声を張り上げた。
女性は幾つになっても目敏いものだ。
「あら。先生と岸谷さん、腕組んでらっしゃらなかった?」
「シーッ。うふふ……」
そんなざわざわが遠ざかる。
通行人が見れば、それは『介護』に見えただろう。
「先生は、おでんはお好きですか?」
「あ……ああ」
「何がお好きですか? 僕は、大根が」
「私は、はんぺんかな」
そんな他愛のない会話を交わしながら、私は岸谷の腕にすがってゆっくりと歩く。
老いらくの恋は情が深いなんて言うけれど、この年になってまた恋をするとは思わなかった。
歩調を合わせて歩いてくれる岸谷の優しさに、私は恋の始まりを見出していた。
End.
0
お気に入りに追加
6
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

【完結】義兄に十年片想いしているけれど、もう諦めます
夏ノ宮萄玄
BL
オレには、親の再婚によってできた義兄がいる。彼に対しオレが長年抱き続けてきた想いとは。
――どうしてオレは、この不毛な恋心を捨て去ることができないのだろう。
懊悩する義弟の桧理(かいり)に訪れた終わり。
義兄×義弟。美形で穏やかな社会人義兄と、つい先日まで高校生だった少しマイナス思考の義弟の話。短編小説です。

悩める文官のひとりごと
きりか
BL
幼い頃から憧れていた騎士団に入りたくても、小柄でひ弱なリュカ・アルマンは、学校を卒業と同時に、文官として騎士団に入団する。方向音痴なリュカは、マルーン副団長の部屋と間違え、イザーク団長の部屋に入り込む。
そこでは、惚れ薬を口にした団長がいて…。
エチシーンが書けなくて、朝チュンとなりました。
ムーンライト様にも掲載しております。

獣人の子供が現代社会人の俺の部屋に迷い込んできました。
えっしゃー(エミリオ猫)
BL
突然、ひとり暮らしの俺(会社員)の部屋に、獣人の子供が現れた!
どっから来た?!異世界転移?!仕方ないので面倒を見る、連休中の俺。
そしたら、なぜか俺の事をママだとっ?!
いやいや女じゃないから!え?女って何って、お前、男しか居ない世界の子供なの?!
会社員男性と、異世界獣人のお話。
※6話で完結します。さくっと読めます。
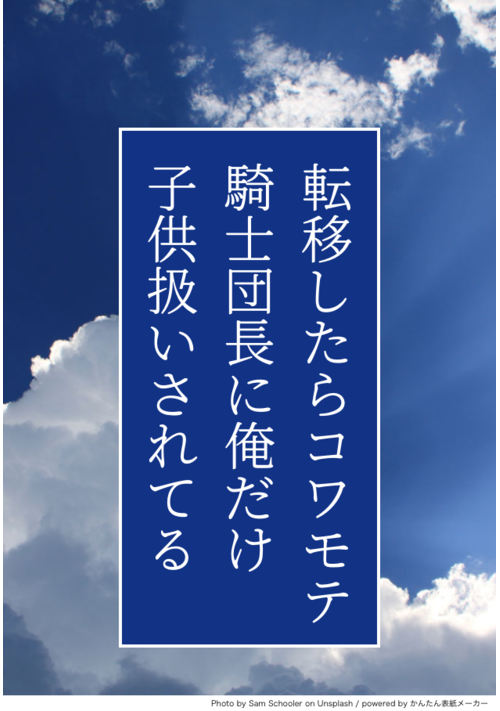
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

完結·助けた犬は騎士団長でした
禅
BL
母を亡くしたクレムは王都を見下ろす丘の森に一人で暮らしていた。
ある日、森の中で傷を負った犬を見つけて介抱する。犬との生活は穏やかで温かく、クレムの孤独を癒していった。
しかし、犬は突然いなくなり、ふたたび孤独な日々に寂しさを覚えていると、城から迎えが現れた。
強引に連れて行かれた王城でクレムの出生の秘密が明かされ……
※完結まで毎日投稿します

告白ゲームの攻略対象にされたので面倒くさい奴になって嫌われることにした
雨宮里玖
BL
《あらすじ》
昼休みに乃木は、イケメン三人の話に聞き耳を立てていた。そこで「それぞれが最初にぶつかった奴を口説いて告白する。それで一番早く告白オッケーもらえた奴が勝ち」という告白ゲームをする話を聞いた。
その直後、乃木は三人のうちで一番のモテ男・早坂とぶつかってしまった。
その日の放課後から早坂は乃木にぐいぐい近づいてきて——。
早坂(18)モッテモテのイケメン帰国子女。勉強運動なんでもできる。物静か。
乃木(18)普通の高校三年生。
波田野(17)早坂の友人。
蓑島(17)早坂の友人。
石井(18)乃木の友人。

Ωの不幸は蜜の味
grotta
BL
俺はΩだけどαとつがいになることが出来ない。うなじに火傷を負ってフェロモン受容機能が損なわれたから噛まれてもつがいになれないのだ――。
Ωの川西望はこれまで不幸な恋ばかりしてきた。
そんな自分でも良いと言ってくれた相手と結婚することになるも、直前で婚約は破棄される。
何もかも諦めかけた時、望に同居を持ちかけてきたのはマンションのオーナーである北条雪哉だった。
6千文字程度のショートショート。
思いついてダダっと書いたので設定ゆるいです。

知らないうちに実ってた
キトー
BL
※BLです。
専門学生の蓮は同級生の翔に告白をするが快い返事はもらえなかった。
振られたショックで逃げて裏路地で泣いていたら追いかけてきた人物がいて──
fujossyや小説家になろうにも掲載中。
感想など反応もらえると嬉しいです!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















