お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説


美少女の秘密を知って付き合うことになった僕に彼女達はなぜかパンツを見せてくれるようになった
釧路太郎
青春
【不定期土曜18時以降更新予定】
僕の彼女の愛ちゃんはクラスの中心人物で学校内でも人気のある女の子だ。
愛ちゃんの彼氏である僕はクラスでも目立たない存在であり、オカルト研究会に所属する性格も暗く見た目も冴えない男子である。
そんな僕が愛ちゃんに告白されて付き合えるようになったのは、誰も知らない彼女の秘密を知ってしまったからなのだ。
そして、なぜか彼女である愛ちゃんは誰もいないところで僕にだけパンツを見せてくれるという謎の行動をとるのであった。
誰にも言えない秘密をもった美少女愛ちゃんとその秘密を知った冴えない僕が送る、爽やかでちょっとだけエッチな青春物語
この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルアッププラス」にも投稿しています
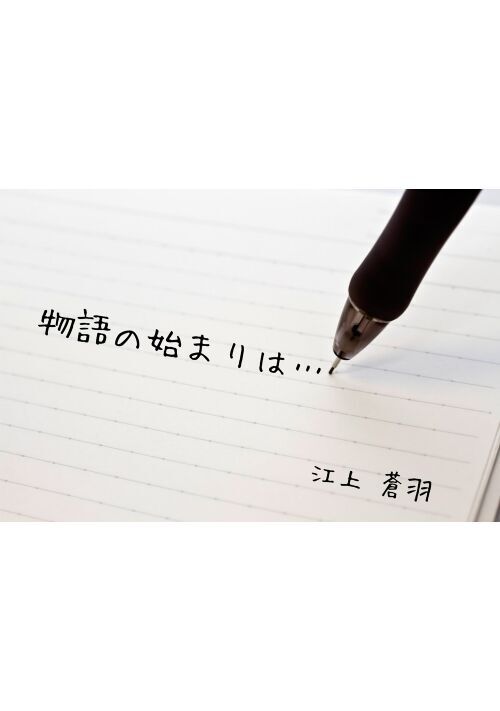
物語の始まりは…
江上蒼羽
青春
***
自他共に認める学校一のイケてる男子、清原聖慈(17)
担任教師から与えられた課題をきっかけに、物語が動き始める。
男子高校生目線の青春物語として書きました。
所々不快に思われる表現があるかと思いますが、作品の中の表現につき、ご理解願いします。
R5.7月頃〜R6.2/19執筆
R6.2/19〜公開開始
***

幼馴染みに告白されたけど断ったって話
家紋武範
青春
失恋したイケメン柊斗は失意の中だったが、彼を幼い頃より思い続けていたものがいた。
幼馴染みのニコル。いつもニコニコしている彼女だが、柊斗は面食いのため、恋人にはできなかった。
※この作品は「大好きな幼なじみが超イケメンの彼女になったので諦めたって話」の続編ですが単独でもお楽しみ頂けます。

冬の夕暮れに君のもとへ
まみはらまさゆき
青春
紘孝は偶然出会った同年代の少女に心を奪われ、そして彼女と付き合い始める。
しかし彼女は複雑な家庭環境にあり、ふたりの交際はそれをさらに複雑化させてしまう・・・。
インターネット普及以後・ケータイ普及以前の熊本を舞台に繰り広げられる、ある青春模様。
20年以上前に「774d」名義で楽天ブログで公表した小説を、改稿の上で再掲載します。
性的な場面はわずかしかありませんが、念のためR15としました。
改稿にあたり、具体的な地名は伏せて全国的に通用する舞台にしようと思いましたが、故郷・熊本への愛着と、方言の持つ味わいは捨てがたく、そのままにしました。
また同様に現在(2020年代)に時代を設定しようと思いましたが、熊本地震以後、いろいろと変わってしまった熊本の風景を心のなかでアップデートできず、1990年代後半のままとしました。

微睡みの狭間に
幽零
青春
私立高校3年生の間泥(マドロ)君はいつも頬杖をついて眠たそうにしています。そんな彼と隣の席の覚芽(サメ)さんは間泥君が気になる様子。そんな彼らの日々を垣間見る短編小説です。
イラスト アイコンメーカー 様

片翼のエール
乃南羽緒
青春
「おまえのテニスに足りないものがある」
高校総体テニス競技個人決勝。
大神謙吾は、一学年上の好敵手に敗北を喫した。
技術、スタミナ、メンタルどれをとっても申し分ないはずの大神のテニスに、ひとつ足りないものがある、と。
それを教えてくれるだろうと好敵手から名指しされたのは、『七浦』という人物。
そいつはまさかの女子で、あまつさえテニス部所属の経験がないヤツだった──。

初恋、n回目
橘花やよい
青春
フィルム越しの彼を、初めて、好きだと思った。
それ以来、彼にずっと、初恋を繰り返している――。
学生カップルの初々しい帰り道。
5分後に初恋をしたくなるラスト、のようなお話。
表紙はヨシュケイ様のフリー素材を使用させていただきました。
エブリスタに投稿したお話です。ノベマでも公開。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















