お気に入りに追加
1
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

時空を歩く既読
幻中六花
SF
愛する彼女が突然、地球上から消えた──。
秋馬が出社できていない理由。
それは、彼女である南那が、突然、大規模な神隠しに遭い、この地球上から姿を消したことだった。
時空を越えていったいどこへ行ってしまったのか。
この作品は、『カクヨム』『小説家になろう』にも掲載しています。
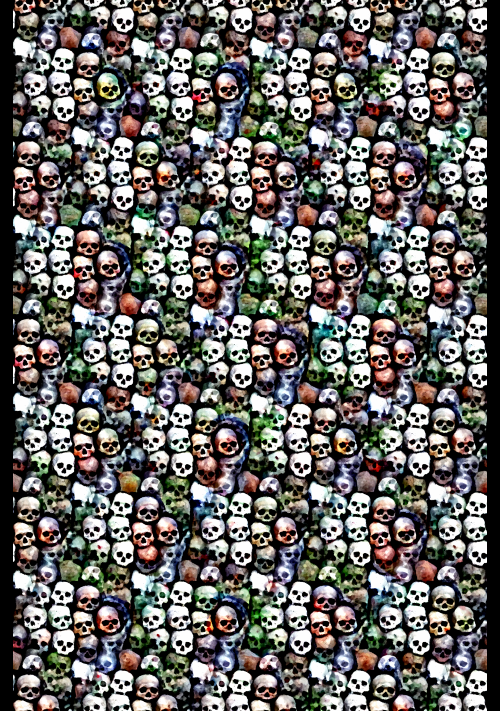


デイノトルーパーズ 自衛隊の敵は6500万年前から来た
ブラックウォーター
SF
沖縄列島の中部に突如原因不明の低気圧と電波障害が発生。
さらに、局地的な地震とともに、石城島のすぐ東の海に突然巨大な島が出現する。
折しも西部普通科連隊を中心とする陸自の混成部隊は、石城島にて米海兵隊との合同離島防衛訓練を行っていた。
訓練の中止が決定されるも、陸自の混成部隊120名は、低気圧の影響で母艦である"ワスプ"への帰還を延期せざるを得なくなる。
豪雨の中夜営する自衛隊員が一人、また一人行方不明となって行く。
わずかな痕跡を頼りに行方不明者の捜索に出た諏訪部二尉の部隊が見たものは、太古の昔に絶滅したはずの恐竜だった。
予想外に高い戦闘力を持つ恐竜たちに対し、通信機器や電子機器を封殺された自衛隊員たちは追い詰められ、島民にも犠牲者が出始める。
島から脱出できなければ死。豪雨と強風の中の脱出作戦が開始される。

宇宙装甲戦艦ハンニバル ――宇宙S級提督への野望――
黒鯛の刺身♪
SF
毎日の仕事で疲れる主人公が、『楽な仕事』と誘われた宇宙ジャンルのVRゲームの世界に飛び込みます。
ゲームの中での姿は一つ目のギガース巨人族。
最初はゲームの中でも辛酸を舐めますが、とある惑星の占い師との出会いにより能力が急浮上!?
乗艦であるハンニバルは鈍重な装甲型。しかし、だんだんと改良が加えられ……。
更に突如現れるワームホール。
その向こうに見えたのは驚愕の世界だった……!?
……さらには、主人公に隠された使命とは!?
様々な事案を解決しながら、ちっちゃいタヌキの砲術長と、トランジスタグラマーなアンドロイドの副官を連れて、主人公は銀河有史史上最も誉れ高いS級宇宙提督へと躍進していきます。
〇主要データ
【艦名】……装甲戦艦ハンニバル
【主砲】……20.6cm連装レーザービーム砲3基
【装備】……各種ミサイルVLS16基
【防御】……重力波シールド
【主機】……エルゴエンジンD-Ⅳ型一基
(以上、第四話時点)
【通貨】……1帝国ドルは現状100円位の想定レート。
『備考』
SF設定は甘々。社会で役に立つ度は0(笑)
残虐描写とエロ描写は控えておりますが、陰鬱な描写はございます。気分がすぐれないとき等はお気を付けください ><。
メンドクサイのがお嫌いな方は3話目からお読みいただいても結構です (*´▽`*)
【お知らせ】……小説家になろう様とノベリズム様にも掲載。
表紙は、秋の桜子様に頂きました(2021/01/21)

フードプリンター
津嶋朋靖(つしまともやす)
SF
ありとあらゆる品物が電子データを元にプリンターで出力される未来世界。料理も例外なくプリンターで作られるようになっていたため、一部の人(趣味で料理する人あるいは料理作家)以外は料理を作らなくなっていた。
そんな時代、食通の鶴岡 懐石は料理作家、朝霞 零の工房に呼ばれる。
その工房で、新しい料理専用プリンターの性能試験への協力を頼まれるのだが……

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















