17 / 54
第3章 過去
籠の鳥は希望を歌う
しおりを挟む
煌狩りたちの本拠地は岩がちな山中に築かれた複雑かつ巨大な城砦で、名を“真鍮の砦”といった。
到着するや否や静夜は永遠を塔の最上階の牢に押し込めた。牢屋番の男に尋ねる。
「父上は?」
「昨日から瑪瑙の窟に。戻られるのは一週間後と」
「…そうか」
永遠の目には、小さくうなずいた静夜がなぜか少し安堵しているように見えた。
「この女をしばらく留め置くから、見張りは耶宵に交替させる。おまえは別の持ち場に移れ」
「はい」
男が姿を消すと静夜は付き従ってきていた耶宵に小声で何かを伝え、永遠には何も言わずに階段を下りていった。
「あんた、副首領に気に入られたみたいだね。この牢は綺麗で設備も良くて砦で一番上等だ。せいぜいくつろいで英気を養いなよ」
「それで最後は死ぬまで煌気を搾り取る気なんだろう」
「それ以外に何があるっての?恨むなら自分の力を恨むんだね」
耶宵はふんっと鼻を鳴らし、階段脇に掘り抜かれた穴蔵のような小部屋に入る。そこが見張り番の詰め所のようだ。
(砦を破壊するのは簡単だし、文を飛ばせば救出部隊を呼ぶこともできるが、そうすると証拠が失われ、最前線に立つ静夜や暁良のような若者たちが命を落とすのは必定…罪を犯しているとは言え、交渉や検分の機会も設けずに血で血を洗う戦いになることは避けたい…)
永遠は牢の内部の設備を確かめた。ごくありふれた寝台や卓や水回りの什器を除けば特別であるとか怪しげというような道具類は見られない。
(煌気を搾取するために何度もここから連れ出されると見て間違いない。幸い証拠や内情を見定める機会は十分にある。焦らずに耐え抜こう)
鉄格子のはめ殺しにされた小さな窓から外を覗く。すでに陽は落ち、月のない星空が真っ暗な丘陵地帯に覆い被さっていた。
永遠を投獄して数日間は静夜は永遠をただ休ませただけで姿を見せなかったが、ついに最初のその日が訪れた。
静夜が数日ぶりに永遠の牢にやってくると彼女は薄汚れた牢の壁に手を当て、優しく静かな声で歌を歌っていた。
「何してる」
永遠は歌うのをやめて振り向き、微笑んだ。
「ああ、おはよう、静夜」
「…何してるのかと訊いてる」
「石や鉄や木が泣いているから、歌を聴かせて慰めてあげてたんだ。無理矢理切り出され、乱暴に運ばれ、ここに打ち立てられて苦しんでたようだ」
当てつけとも取れる奇妙で独特な発言に静夜は思わず眉を逆立てたが、永遠は構わず続ける。
「彼らは自分たちがどんな用や目的のために供され、どんなふうに扱われているかをちゃんと理解している。本当はごく普通の人間たちのささやかな幸せのために身を削ることが彼らの生き甲斐なのに…こんなところでずっと耐え忍んでいたんだね…」
無骨な岩壁に両掌と額をそっとついて聞き取れないほどの小声で何事か語り聞かせている永遠に奇異の剥き出しの視線を注いでいると、耶宵が寄ってきて耳打ちした。
「…起きてからずっとこんな調子なんです」
静夜は深々と溜め息をつき、永遠に向けて面倒臭そうに言った。
「人間が生活するために山林を切り開いたり必要な資材を加工したりするのは当然で、民家だろうと、砦や牢だろうと同じことだ。いちいち気にかけていたらきりがない」
「でもこの場所で喜びや幸せは生まれていない」
「意味がわからない。くだらない歌に力を使うな。おまえが働く場所はここではなく地下だ。出ろ」
言われるまま牢から出され、手枷をはめられる。そして鎖の先を引かれて階段を下りていった。
砦の内部は男女問わず若い団員や下働きの者たちでひしめいていた。大小さまざまな部屋やいくつもの倉庫の前を通り過ぎ、何度も何度も角を曲がり、さらには山の懐を食い破るように穿たれた地下通路と下り階段を二人は進んでいった。
(ここまでは特段異様な気配などはなかったな)
だが静かで何もなさそうに見えるほど何かを隠しているのではないかとの疑念をかき立てる。このいずれかの扉の奥に同胞が他にも大勢囚われているかもしれないと思うとすべての扉を力ずくで開放したい衝動に駆られたが、今はまだ堪えておとなしく静夜についていった。
下り階段が尽きるところでものものしい装飾のある大きな扉が現れた。中に入ってすぐは書物の詰まった棚がびっしりと並ぶ薄暗い書庫で、その次にありとあらゆる武具や使い込まれた種々雑多な道具類の置かれた卓がいくつも続く。さながら知恵と技術の宝庫といった趣きだ。
(…だが、ここも私には関係なさそうだ)
内心つぶやいたとおり静夜は通路を素通りしてその突き当たり、最奥部と思われる両開きの扉の前で足を止め、持っていた鍵で開扉した。永遠は緊張しながら彼に従って中に進入した。そして目の当たりにした光景についに驚愕の眼を見開いた。
(…これは…!!)
そこが山中であることが信じ難いほどの天井高のある広い空間であるというだけでも驚きだったが、それよりも彼女の目を奪ったのは、長い星養いの旅を通じて見聞を深めてきた自分も見たことのない、冷たい光沢を放つ摩訶不思議な装置や器具や仕掛けの数々だった。床と壁一面にずらりと並ぶそれらは部屋の中央に意味ありげにしつらえられた切り込みのある何かの架台と無数の管ですべてつながっていて、絶えずこぽこぽ、カタカタ、ゴトゴトと音を立てていた。静夜はその架台に向かい合った空の椅子を指した。
「そこに座れ。あとは彼らの指示に従えばいい」
彼らとはそれらの装置を操ったり覗き込んだり記録を取ったりしている黒衣の博士たちのことである。彼らは永遠が椅子に腰かけるとわらわらと寄ってきて、あっという間に彼女の四肢を椅子と床に固定して逃げられなくした。永遠は緊張を紛らわせようと博士のひとりに気やすく話しかけた。
「私は極度の痛がりなんだ。怖いことはしないだろうね」
「身体を傷つけるようなことはしません」
痛くないとは言わないその答え方に握り拳が固くなる。
静夜は架台を挟んで永遠の向かいに立ち、鞘から抜いた迦楼羅をその切れ込みに突き刺し、柄頭に両手を添えて立った。
「それでは採煌を始めます」
永遠の緊張が頂点に達したとき、静夜が目を閉じて迦楼羅の力を解放した。同時に博士のひとりが手許の機械を稼働させると、たちまち装置に息が吹き込まれ、仕掛けが順繰りに動き出した。煌気の強制的な吸い上げが始まり、永遠の心臓と煌源がひとりでにドクンと打った。
「ーーーーッ!!!!」
永遠は椅子の上で思わず顎をのけぞらせ、次に苦痛に耐えようと固く身を縮めこわばらせた。煌気が永遠の身体から迦楼羅へ、そして装置へと移り始めると、いかなるからくりによるものか、各種の機器が動作を激しく速め、猛烈に熱量を高めていく。そのうち博士たちがざわざわと浮き足立ち、誰かがもはや感動に近い大声を張り上げた。
「す…すごい力です!!…こんな凄まじい輝きは見たことがありません!!」
ぶるぶると震える肩や拳や逆立った長い金髪から光り輝く煌気が濃密な陽炎のように立ち昇り、極小の稲妻めいた光が弾け、火花が散る。静夜の黒髪の裾も金色の縁取りを帯びて浮かび、全身には力が漲っている。永遠の森羅聖煌は迦楼羅に吸収され、無数の管を通って背後の装置に絶え間なく送り込まれていく。迦楼羅だけでも驚異的な存在だがこの装置は迦楼羅よりも異常に不自然で凶悪で残酷だ!
「っ…ああああああっ!!!!」
それまでは歯を食いしばってなんとか持ちこたえていた永遠がついに苦悶の叫びを上げると、始めは冷静に不動の直立を保っていた静夜も次第にこれは尋常ではないと悟り、そこで採煌を中断した。
「これ以上は危険だ。今日はここまでにする」
「し、しかし、副首領…」
「せっかくの貴重な獲物をたった一回の採煌で殺す気か?これは命令だ。早く止めろ」
落ち着いてはいるが有無を言わせぬ威圧感のある静夜の声色に、博士たちは未練たらたらといった表情で機械を停止させた。圧が下がり、回転が止まり、熱が引くと、永遠の全身からも力が抜けた。椅子の背にぐったりと身を預ける永遠の心拍と呼吸を確かめてから静夜は博士たちと機械の方を見、はっとした。
永遠の正面のやや高いところ、機械群の中央に鎮座しているランタンのような金属の物体の中に、五色に輝く凝縮された煌気の玉が浮かんでいる。これまで数限りない原礎をあの装置にかけてきたが、これほど神々しいまばゆさを生む原礎は見た試しがない。博士たちが興奮して記録や確認作業に躍起になっている様子からもその潜在能力の高さが見て取れる。静夜は計画の速やかな進捗を確信すると同時に、永遠の運命の末期までもが容易に見通せてしまい、混じり合わない二つの感情にひそかに胸を暗くした。
「…姉さん…」
久遠が言葉もないという悲痛な表情で永遠の痩せた身体を抱きしめる。永遠の髪に埋めたその翠緑の瞳が潤んで大きく揺れている。光陰がそっと瞑目して言った。
「…私が父親としての責務を放棄していなければこの場で即座に君を殺しているところだ」
「…どんなに償っても償いきれる罪ではないということはわかっているつもりです…」
峻厳な切れ味の込もる光陰の言葉を、静夜は唇を結んでただじっと受け止め、狭量で頑迷極まる背信者だった過去の自分について語った。
「俺は自分が受けてきた教育を信じて疑いませんでした。自分たちは有害な元凶を減らす狩人であり、原礎は狩り、喰う対象なのだと…原礎が世界中を旅して人間の社会に入り混じろうとするのは人間を常に支配下において自立や成長をさせないよう、また自分たちに対して反乱を起こさないように監視するためだとも教え込まれました。その誤った思い込みを変えてくれたのが永遠だったんです。…ただそのときの俺は、突然初めて目の前に提示された真理をまだ受けつけることができませんでした」
静夜は永遠を牢に連れ帰ると耶宵の手も借りて彼女を寝台に休ませ、少しの間そのままそこで待っていた。どうしても訊いておきたい事柄があったからである。
半時間ほど横になると永遠はまだ青白い顔ながらゆっくりと身体を起こした。
「大丈夫か」
「…自分で強要しておいて、かける言葉がそれか」
「…」
「冗談だ」
悪戯な笑みをうっすらと力なく漏らした永遠に静夜は待ちきれず尋ねた。
「おまえのあの煌気…あれほど強い力を俺は見たことがない。あれはいったい何なんだ」
「いつか訊かれると思ってたよ。私の煌気は“森羅聖煌”…数百年にひとりの割合で生まれ持ってくる特別強力な煌源で、術者さえ意図すれば一夜で砂漠を森と湖に変えることもできる。今の代で所持しているのは私ひとりだけだ」
「そんな強い力があるのになぜ荒れ地や砂漠は不毛のままなんだ?それほどの力を秘蔵して、原礎たちはこの上まだ俺たち人間を支配し管理しようと?」
「私たちは出し惜しみや管理をしているのではない。星の姿形はすべてあるがままで、一様に豊かで生産性が高いことが理想なのではなく、多様で変化に富んでいることこそが真の尊さなんだ。私たちは人間たちの暮らしを見守り手助けをするが、星の姿形に自ら手を加えてまでそれを推し進めることは絶対にしない」
静夜はこの言葉が癪に障ったように目つきを尖らせた。
「無為無策を正当化するのか。ではなぜそんな強い力が君に与えられている?使わないのなら宝の持ち腐れで無意味じゃないか」
「私もそれをずっと考えていて、旅をしながら自分なりに追求してるところなんだが、未だ会得できていない。星のみぞ知る、かな」
軽く肩をすくめて見せた永遠に、静夜の表情は不満と反発をますます色濃くした。鉄格子の向こうでは耶宵がいつになく真剣な顔つきで二人の問答に熱心に聞き入っている。
「おまえがその力を使えば星はもっと豊かに安全になり、貧困や災害に苦しむ者はいなくなるはずだ。それなのに原礎は星の恵みを独占し人間を支配している。原礎の強欲と怠慢こそが俺たちの敵、人間の苦しみの最大の要因だ」
「君の食べているものや飲む水はすべて星の恵みで、その食べ物や水は十二礎のすべての手から手へと受け渡されてきたものだ。君のその身体は礎でできていて、強いて言うなら人間を支配しているのは原礎ではなく星そのものだ」
「だが俺は物心ついたときからそう教えられてきた。現に貧しさや自然の厳しさに苦しむ多くの人々を見てきた。どれも原礎が力を尽くしてさえいれば避けられた死や飢えや悲しみばかりだ」
「だがそれも星が生きている証だ。星は人間の都合のために存在しているのではなく、私たちは星の上に場所と時間を少し借りて星に生かしてもらっているだけの小さな命に過ぎない。考えてみてくれ、苦しみと同じくらい多くの小さな幸せもまた確かに存在しているということを。そして君たちが自分の手で新たな悲しみを増やす必要はないのだということも」
静夜はとっさに語気を強めようと吸い込んだ息を止め、空のまま吐き出し、しかめっ面に掌を当てた。
「…おまえと話していると埒が明かない。…頭痛がする」
彼はまるで毒を少しずつ飲ませられ続けた末に毒に反応せず薬も効かない身になってしまっているようだ。だがその毒は気づかないうちに彼を侵し確実に死と破滅へと至らしめるだろうと思われた。
(煌狩りや採煌のことを大森林が知れば静夜も若者たちも原礎の復讐と制裁を受ける…罰せられるべきは静夜たちを手足のように操り自らの手を汚さない黒幕だ)
やはり静夜はまだ幼いうちから何者かによって誤った方向に意識を教化され、操り人形にされている。しかし彼の魂の根本はまだ毒にも闇にも侵されていない。永遠は疲れた顔に穏やかな微笑みを浮かべて彼を真っ直ぐに見つめた。
「今日は君の考えに今までで一番近づくことができて嬉しかった。君が人間や同志たちを深く案じ、心から愛していることはよくわかった…」
静夜は永遠を撥ねつけるように立ち上がる。
「俺の考えに近づこうとする必要などない。おまえはおとなしく採煌されていればいいだけの身なのだから。次は一週間後だ。それまで身体を休めて煌気を蓄えておけ」
さっと背を向けてつかつかと立ち去っていく静夜を、耶宵が何か言いたそうにしながら結局何も言えずに黙って見送る。彼の足音と気配が階段の下に消えてからようやくぽつりとつぶやいた。
「あんなふうに熱く語る静夜さんを見たのは初めてだ…永遠…あんたって、いったい…」
耶宵は不安げに曇る綺麗な顔を永遠に向けた。永遠はいつの間にか寝台から降りて小さな窓の外の景色をじっと眺めていた。
その夜静夜は誰もいない食堂でひとり酒を飲んでいた。
目の前には葡萄酒の壜と古びたゴブレット、そしてひと摑み分ほどの干し果実と木の実を盛った皿が置かれている。何の変哲もないそれらを頬杖をついて見るともなく見つめながら静夜はぼうっと深い物思いに沈んでいた。
『君のその身体は礎でできていて、強いて言うなら人間を支配しているのは原礎ではなく星そのものだ』
『考えてみてくれ、苦しみと同じくらい多くの小さな幸せもまた確かに存在しているということを』
諄々と道を説く永遠の声がさっきからずっと耳の奥で繰り返されている。
(人間を原礎の手から解放して自由と幸福を勝ち取るために戦ってきたのに…俺はそれを壊そうとしているのか…)
つまみ上げたひと粒の胡桃の実は、指先に少し力を加えただけで簡単にパキンと割れ、粉々に砕けて皿に落ちた。
(…だからと言って、今更俺にどうしろというんだ)
うつむいた額に苦悩と葛藤がまざまざと現れる。初めて浴びた光が強くまぶしいほど、心に巣食った影はいっそう濃く長く伸びていくように思われた。
そうしてひとり座って動かない静夜の姿を、食堂の入り口から暁良が心配そうに見つめていた。
「…」
だが暁良はかける言葉も見つからず、そっと踵を返し、気づかれないよう足早にその場を去った。
さらに数日が経ち、父の明夜が真鍮の砦に戻ってきた。
黙々と雑仕事をこなしている静夜のもとに明夜は早速現れた。今の情婦を伴って。
「帰ったぞ、静夜」
「遠路ご苦労様でした」
口先だけ丁寧にねぎらったきりまた仕事に戻ろうとする静夜を明夜はおどけた苦笑いで引き留める。
「おいおい、父親がせっかく新しい恋人を連れてきたのにつれない奴だな。紹介するぞ。泪だ。泪、これが俺の自慢のひとり息子の静夜」
泪はしなだれかかっていた明夜の腕から離れて静夜に近づいた。わざとらしく肩と腰を揺らして妖艶な微笑みで顔を覗き込んでくると、香水のきつい匂いが鼻を突いて静夜は思わず顔をしかめた。
「あら、ずいぶん男前。全然父親と似てないけど」
「血はつながってないんだからしかたないだろ。顔の話は勘弁してくれよ」
「ほんと、あんたとは似ても似つかないわね。でもまだちょっと初心で純な顔してる」
馴れ馴れしく頬に触れようとしてきたので反射的に顔を引き距離を置く。
(…こういう女には近寄りたくない)
泪はよく見れば美人と言えなくもないが、何しろ色気が過剰で知性も品性も露ほども感じられない。女好きでだらしのない父は今まで何人もの女を連れてきたが、いつも決まって化粧が濃く派手で露出の多い服しか着ない下品な女ばかりだった。知りたくもないがおおかた娼婦か酒場女だろう。それも父が自由気ままな独り身だから許されることで静夜もとうの昔に匙を投げていた。
(どうせまたすぐに飽きて取り替えるだろう)
「こいつは仕事にしか興味ないからな。でもおまえも男なんだから、ときどきは女を抱きたいと思うだろ?」
静夜は戸惑い、内心で用心深く身構えた。
(…いきなり、何を…)
「…任務と鍛練で忙しいので、そんな暇はありません」
「何、別に時間をかけることもない。相手も誰でもいい。部下でも下働きの女でも。なんなら泪をひと晩貸してやろうか」
「まぁ、あんたの息子さん、試していいの?そうね、たまには若くて活きのいい子も悪くないかも…」
「…いいや、やっぱり駄目だ!泪だけは貸さん。若ければいいってもんじゃないぞ。こいつ、後でわからせてやる」
こちらにはお構いなしにじゃれ合い始めるので静夜は目も当てられず、呆れてものも言えずに溜め息をつくばかりだった。
「…父上、それより、首尾の方は…瑪瑙の窟はどうでしたか」
「ん?ああ、計画自体は順調だが、やはりまだ煌気が足りん。今回貢納した分も需要には少し届かなかった。おまえたちにはもっと狩ってきてもらわんと、あの方の機嫌を損ねそうだ」
「わかりました。近いうちに狩りに出ます」
それきり黙り込む静夜の横顔に明夜は目を止めた。
「疲れてるのか?顔色が冴えんぞ」
「いいえ、大丈夫です」
頼むから泪を連れて早く部屋に引っ込んでくれと祈るような気持ちでいたが、明夜はまだしつこく絡んできた。
「時に、聞いたぞ。おまえ、大層な上物を捕まえてきたそうじゃないか」
(もう知られていたか…)
砦に収容した以上部下の口に戸を立てることはできない。覚悟はしていたが、それにしても明夜はこと成果や獲物に関しては恐ろしく耳ざとい。静夜は素直にうなずいた。
「はい。…樹生の若い女で、稀に見る強力な煌源を持っています。数百年にひとりとか」
「でかしたじゃないか静夜。それはぜひとも拝みたい。今すぐ俺をその女のところに連れていけ」
「…わかりました」
本当はたまらなく嫌だったが、断る建前もとっさに思いつかなかったので静夜は諦め、しかたなく明夜を永遠の牢に案内した。
静夜と明夜が上がってきたとき、永遠は鉄格子越しに耶宵と小声で雑談をしていた。二人は気心が知れた友達同士のようにすっかり親しくなっていた。
「この女か。おい、鍵を開けろ」
静夜が耶宵から鍵を受け取って開け、明夜を中に入れる。当然静夜も監視のために一緒に立ち入った。囚人よりもこの父親の方が何をするかわからず厄介だからだ。永遠を見た明夜は開口一番、こうこぼした。
「ふん、女といってもまだ小娘じゃないか。拍子抜けだ」
「外見は小娘かもしれないが、生まれた年はあなたとほとんど変わらないぞ」
永遠の物怖じしない堂々とした態度を明夜は鼻でせせら笑った。
「これはこれは、可愛い顔をして大層なじゃじゃ馬と見える。俺は嫌いじゃないぞ。肉づきは…まだだいぶ薄いようだが…」
案の定、明夜の手が永遠の小さな白い顎に伸びる。その手を永遠が威勢良く払いのけるのと、静夜ががしっと摑んで押さえるのがまったくの同時だった。
「やめてください、父上。扱いは慎重に」
「一人前に紳士気取りか?おまえの獲物は俺の獲物だ。俺がどう扱おうと俺の勝手だ」
牢の外では耶宵がはらはらと息を呑んで見守っている。一気に緊張感を増す雰囲気の中、静夜は形ばかり礼儀に則って互いを相手に紹介した。
「失礼した。俺の父で首領の明夜だ。父上、この原礎が例の樹生・アリスタ・永遠です」
明夜が静夜の実父ではないことをまだ聞かされていない永遠は目の前でふんぞり返っている中年の男を信じられない気持ちで見上げた。
(この無作法で胸のむかつくような男が静夜の父親で、しかも首領だと?大人と子供がまるで逆じゃないか。それに全然似てない)
明夜はけして醜男ではないが、とにかく顔つきも身だしなみも締まりがなくだらしない。身なりを整えてニヤニヤ笑いを引っ込めさえすればまあまあ見られる容姿になるかもしれないが、それでも外見も性格も鋼鉄の剣のようにすらりとして芯の強い美青年である静夜の風格の足許にも及ばない。いい年齢をして鍛練や学問や自己省察も十分ではなさそうだ。こんな男がなぜ静夜の父親であり、首領の座に収まっているのか甚だ疑問だった。
(だがこの男が罪のない静夜や若者たちに精神支配の蠱毒を飲ませ道を誤らせているとしたら油断は禁物…どんな悪事を企んでいるかわからない。私もこの男への言動は慎重にしなければ)
「採煌はしたのか」
「一度だけ。…ただ煌気が強すぎて肉体への負担が大きいようなので、当面は間隔を空け、様子を見ながら量も抑えて採煌します」
「甘い。そんなまどろっこしい配慮などいらん。この女ひとりさえいればわざわざ狩りに出る必要もないんだから、死なない程度にどんどん搾り取れ。…だが、しかし…」
明夜は永遠に手を触れずにぐいと顔を近く寄せた。警戒感も露わに壁ににじり下がる永遠の顔をじろじろと睨め回して、いやらしく舌なめずりをする。
「それにしても…ふん。こいつは面白くなりそうだ」
警戒感を通り越して生理的な嫌悪感に襲われ、永遠は思わず明夜をきつく睨み返した。
到着するや否や静夜は永遠を塔の最上階の牢に押し込めた。牢屋番の男に尋ねる。
「父上は?」
「昨日から瑪瑙の窟に。戻られるのは一週間後と」
「…そうか」
永遠の目には、小さくうなずいた静夜がなぜか少し安堵しているように見えた。
「この女をしばらく留め置くから、見張りは耶宵に交替させる。おまえは別の持ち場に移れ」
「はい」
男が姿を消すと静夜は付き従ってきていた耶宵に小声で何かを伝え、永遠には何も言わずに階段を下りていった。
「あんた、副首領に気に入られたみたいだね。この牢は綺麗で設備も良くて砦で一番上等だ。せいぜいくつろいで英気を養いなよ」
「それで最後は死ぬまで煌気を搾り取る気なんだろう」
「それ以外に何があるっての?恨むなら自分の力を恨むんだね」
耶宵はふんっと鼻を鳴らし、階段脇に掘り抜かれた穴蔵のような小部屋に入る。そこが見張り番の詰め所のようだ。
(砦を破壊するのは簡単だし、文を飛ばせば救出部隊を呼ぶこともできるが、そうすると証拠が失われ、最前線に立つ静夜や暁良のような若者たちが命を落とすのは必定…罪を犯しているとは言え、交渉や検分の機会も設けずに血で血を洗う戦いになることは避けたい…)
永遠は牢の内部の設備を確かめた。ごくありふれた寝台や卓や水回りの什器を除けば特別であるとか怪しげというような道具類は見られない。
(煌気を搾取するために何度もここから連れ出されると見て間違いない。幸い証拠や内情を見定める機会は十分にある。焦らずに耐え抜こう)
鉄格子のはめ殺しにされた小さな窓から外を覗く。すでに陽は落ち、月のない星空が真っ暗な丘陵地帯に覆い被さっていた。
永遠を投獄して数日間は静夜は永遠をただ休ませただけで姿を見せなかったが、ついに最初のその日が訪れた。
静夜が数日ぶりに永遠の牢にやってくると彼女は薄汚れた牢の壁に手を当て、優しく静かな声で歌を歌っていた。
「何してる」
永遠は歌うのをやめて振り向き、微笑んだ。
「ああ、おはよう、静夜」
「…何してるのかと訊いてる」
「石や鉄や木が泣いているから、歌を聴かせて慰めてあげてたんだ。無理矢理切り出され、乱暴に運ばれ、ここに打ち立てられて苦しんでたようだ」
当てつけとも取れる奇妙で独特な発言に静夜は思わず眉を逆立てたが、永遠は構わず続ける。
「彼らは自分たちがどんな用や目的のために供され、どんなふうに扱われているかをちゃんと理解している。本当はごく普通の人間たちのささやかな幸せのために身を削ることが彼らの生き甲斐なのに…こんなところでずっと耐え忍んでいたんだね…」
無骨な岩壁に両掌と額をそっとついて聞き取れないほどの小声で何事か語り聞かせている永遠に奇異の剥き出しの視線を注いでいると、耶宵が寄ってきて耳打ちした。
「…起きてからずっとこんな調子なんです」
静夜は深々と溜め息をつき、永遠に向けて面倒臭そうに言った。
「人間が生活するために山林を切り開いたり必要な資材を加工したりするのは当然で、民家だろうと、砦や牢だろうと同じことだ。いちいち気にかけていたらきりがない」
「でもこの場所で喜びや幸せは生まれていない」
「意味がわからない。くだらない歌に力を使うな。おまえが働く場所はここではなく地下だ。出ろ」
言われるまま牢から出され、手枷をはめられる。そして鎖の先を引かれて階段を下りていった。
砦の内部は男女問わず若い団員や下働きの者たちでひしめいていた。大小さまざまな部屋やいくつもの倉庫の前を通り過ぎ、何度も何度も角を曲がり、さらには山の懐を食い破るように穿たれた地下通路と下り階段を二人は進んでいった。
(ここまでは特段異様な気配などはなかったな)
だが静かで何もなさそうに見えるほど何かを隠しているのではないかとの疑念をかき立てる。このいずれかの扉の奥に同胞が他にも大勢囚われているかもしれないと思うとすべての扉を力ずくで開放したい衝動に駆られたが、今はまだ堪えておとなしく静夜についていった。
下り階段が尽きるところでものものしい装飾のある大きな扉が現れた。中に入ってすぐは書物の詰まった棚がびっしりと並ぶ薄暗い書庫で、その次にありとあらゆる武具や使い込まれた種々雑多な道具類の置かれた卓がいくつも続く。さながら知恵と技術の宝庫といった趣きだ。
(…だが、ここも私には関係なさそうだ)
内心つぶやいたとおり静夜は通路を素通りしてその突き当たり、最奥部と思われる両開きの扉の前で足を止め、持っていた鍵で開扉した。永遠は緊張しながら彼に従って中に進入した。そして目の当たりにした光景についに驚愕の眼を見開いた。
(…これは…!!)
そこが山中であることが信じ難いほどの天井高のある広い空間であるというだけでも驚きだったが、それよりも彼女の目を奪ったのは、長い星養いの旅を通じて見聞を深めてきた自分も見たことのない、冷たい光沢を放つ摩訶不思議な装置や器具や仕掛けの数々だった。床と壁一面にずらりと並ぶそれらは部屋の中央に意味ありげにしつらえられた切り込みのある何かの架台と無数の管ですべてつながっていて、絶えずこぽこぽ、カタカタ、ゴトゴトと音を立てていた。静夜はその架台に向かい合った空の椅子を指した。
「そこに座れ。あとは彼らの指示に従えばいい」
彼らとはそれらの装置を操ったり覗き込んだり記録を取ったりしている黒衣の博士たちのことである。彼らは永遠が椅子に腰かけるとわらわらと寄ってきて、あっという間に彼女の四肢を椅子と床に固定して逃げられなくした。永遠は緊張を紛らわせようと博士のひとりに気やすく話しかけた。
「私は極度の痛がりなんだ。怖いことはしないだろうね」
「身体を傷つけるようなことはしません」
痛くないとは言わないその答え方に握り拳が固くなる。
静夜は架台を挟んで永遠の向かいに立ち、鞘から抜いた迦楼羅をその切れ込みに突き刺し、柄頭に両手を添えて立った。
「それでは採煌を始めます」
永遠の緊張が頂点に達したとき、静夜が目を閉じて迦楼羅の力を解放した。同時に博士のひとりが手許の機械を稼働させると、たちまち装置に息が吹き込まれ、仕掛けが順繰りに動き出した。煌気の強制的な吸い上げが始まり、永遠の心臓と煌源がひとりでにドクンと打った。
「ーーーーッ!!!!」
永遠は椅子の上で思わず顎をのけぞらせ、次に苦痛に耐えようと固く身を縮めこわばらせた。煌気が永遠の身体から迦楼羅へ、そして装置へと移り始めると、いかなるからくりによるものか、各種の機器が動作を激しく速め、猛烈に熱量を高めていく。そのうち博士たちがざわざわと浮き足立ち、誰かがもはや感動に近い大声を張り上げた。
「す…すごい力です!!…こんな凄まじい輝きは見たことがありません!!」
ぶるぶると震える肩や拳や逆立った長い金髪から光り輝く煌気が濃密な陽炎のように立ち昇り、極小の稲妻めいた光が弾け、火花が散る。静夜の黒髪の裾も金色の縁取りを帯びて浮かび、全身には力が漲っている。永遠の森羅聖煌は迦楼羅に吸収され、無数の管を通って背後の装置に絶え間なく送り込まれていく。迦楼羅だけでも驚異的な存在だがこの装置は迦楼羅よりも異常に不自然で凶悪で残酷だ!
「っ…ああああああっ!!!!」
それまでは歯を食いしばってなんとか持ちこたえていた永遠がついに苦悶の叫びを上げると、始めは冷静に不動の直立を保っていた静夜も次第にこれは尋常ではないと悟り、そこで採煌を中断した。
「これ以上は危険だ。今日はここまでにする」
「し、しかし、副首領…」
「せっかくの貴重な獲物をたった一回の採煌で殺す気か?これは命令だ。早く止めろ」
落ち着いてはいるが有無を言わせぬ威圧感のある静夜の声色に、博士たちは未練たらたらといった表情で機械を停止させた。圧が下がり、回転が止まり、熱が引くと、永遠の全身からも力が抜けた。椅子の背にぐったりと身を預ける永遠の心拍と呼吸を確かめてから静夜は博士たちと機械の方を見、はっとした。
永遠の正面のやや高いところ、機械群の中央に鎮座しているランタンのような金属の物体の中に、五色に輝く凝縮された煌気の玉が浮かんでいる。これまで数限りない原礎をあの装置にかけてきたが、これほど神々しいまばゆさを生む原礎は見た試しがない。博士たちが興奮して記録や確認作業に躍起になっている様子からもその潜在能力の高さが見て取れる。静夜は計画の速やかな進捗を確信すると同時に、永遠の運命の末期までもが容易に見通せてしまい、混じり合わない二つの感情にひそかに胸を暗くした。
「…姉さん…」
久遠が言葉もないという悲痛な表情で永遠の痩せた身体を抱きしめる。永遠の髪に埋めたその翠緑の瞳が潤んで大きく揺れている。光陰がそっと瞑目して言った。
「…私が父親としての責務を放棄していなければこの場で即座に君を殺しているところだ」
「…どんなに償っても償いきれる罪ではないということはわかっているつもりです…」
峻厳な切れ味の込もる光陰の言葉を、静夜は唇を結んでただじっと受け止め、狭量で頑迷極まる背信者だった過去の自分について語った。
「俺は自分が受けてきた教育を信じて疑いませんでした。自分たちは有害な元凶を減らす狩人であり、原礎は狩り、喰う対象なのだと…原礎が世界中を旅して人間の社会に入り混じろうとするのは人間を常に支配下において自立や成長をさせないよう、また自分たちに対して反乱を起こさないように監視するためだとも教え込まれました。その誤った思い込みを変えてくれたのが永遠だったんです。…ただそのときの俺は、突然初めて目の前に提示された真理をまだ受けつけることができませんでした」
静夜は永遠を牢に連れ帰ると耶宵の手も借りて彼女を寝台に休ませ、少しの間そのままそこで待っていた。どうしても訊いておきたい事柄があったからである。
半時間ほど横になると永遠はまだ青白い顔ながらゆっくりと身体を起こした。
「大丈夫か」
「…自分で強要しておいて、かける言葉がそれか」
「…」
「冗談だ」
悪戯な笑みをうっすらと力なく漏らした永遠に静夜は待ちきれず尋ねた。
「おまえのあの煌気…あれほど強い力を俺は見たことがない。あれはいったい何なんだ」
「いつか訊かれると思ってたよ。私の煌気は“森羅聖煌”…数百年にひとりの割合で生まれ持ってくる特別強力な煌源で、術者さえ意図すれば一夜で砂漠を森と湖に変えることもできる。今の代で所持しているのは私ひとりだけだ」
「そんな強い力があるのになぜ荒れ地や砂漠は不毛のままなんだ?それほどの力を秘蔵して、原礎たちはこの上まだ俺たち人間を支配し管理しようと?」
「私たちは出し惜しみや管理をしているのではない。星の姿形はすべてあるがままで、一様に豊かで生産性が高いことが理想なのではなく、多様で変化に富んでいることこそが真の尊さなんだ。私たちは人間たちの暮らしを見守り手助けをするが、星の姿形に自ら手を加えてまでそれを推し進めることは絶対にしない」
静夜はこの言葉が癪に障ったように目つきを尖らせた。
「無為無策を正当化するのか。ではなぜそんな強い力が君に与えられている?使わないのなら宝の持ち腐れで無意味じゃないか」
「私もそれをずっと考えていて、旅をしながら自分なりに追求してるところなんだが、未だ会得できていない。星のみぞ知る、かな」
軽く肩をすくめて見せた永遠に、静夜の表情は不満と反発をますます色濃くした。鉄格子の向こうでは耶宵がいつになく真剣な顔つきで二人の問答に熱心に聞き入っている。
「おまえがその力を使えば星はもっと豊かに安全になり、貧困や災害に苦しむ者はいなくなるはずだ。それなのに原礎は星の恵みを独占し人間を支配している。原礎の強欲と怠慢こそが俺たちの敵、人間の苦しみの最大の要因だ」
「君の食べているものや飲む水はすべて星の恵みで、その食べ物や水は十二礎のすべての手から手へと受け渡されてきたものだ。君のその身体は礎でできていて、強いて言うなら人間を支配しているのは原礎ではなく星そのものだ」
「だが俺は物心ついたときからそう教えられてきた。現に貧しさや自然の厳しさに苦しむ多くの人々を見てきた。どれも原礎が力を尽くしてさえいれば避けられた死や飢えや悲しみばかりだ」
「だがそれも星が生きている証だ。星は人間の都合のために存在しているのではなく、私たちは星の上に場所と時間を少し借りて星に生かしてもらっているだけの小さな命に過ぎない。考えてみてくれ、苦しみと同じくらい多くの小さな幸せもまた確かに存在しているということを。そして君たちが自分の手で新たな悲しみを増やす必要はないのだということも」
静夜はとっさに語気を強めようと吸い込んだ息を止め、空のまま吐き出し、しかめっ面に掌を当てた。
「…おまえと話していると埒が明かない。…頭痛がする」
彼はまるで毒を少しずつ飲ませられ続けた末に毒に反応せず薬も効かない身になってしまっているようだ。だがその毒は気づかないうちに彼を侵し確実に死と破滅へと至らしめるだろうと思われた。
(煌狩りや採煌のことを大森林が知れば静夜も若者たちも原礎の復讐と制裁を受ける…罰せられるべきは静夜たちを手足のように操り自らの手を汚さない黒幕だ)
やはり静夜はまだ幼いうちから何者かによって誤った方向に意識を教化され、操り人形にされている。しかし彼の魂の根本はまだ毒にも闇にも侵されていない。永遠は疲れた顔に穏やかな微笑みを浮かべて彼を真っ直ぐに見つめた。
「今日は君の考えに今までで一番近づくことができて嬉しかった。君が人間や同志たちを深く案じ、心から愛していることはよくわかった…」
静夜は永遠を撥ねつけるように立ち上がる。
「俺の考えに近づこうとする必要などない。おまえはおとなしく採煌されていればいいだけの身なのだから。次は一週間後だ。それまで身体を休めて煌気を蓄えておけ」
さっと背を向けてつかつかと立ち去っていく静夜を、耶宵が何か言いたそうにしながら結局何も言えずに黙って見送る。彼の足音と気配が階段の下に消えてからようやくぽつりとつぶやいた。
「あんなふうに熱く語る静夜さんを見たのは初めてだ…永遠…あんたって、いったい…」
耶宵は不安げに曇る綺麗な顔を永遠に向けた。永遠はいつの間にか寝台から降りて小さな窓の外の景色をじっと眺めていた。
その夜静夜は誰もいない食堂でひとり酒を飲んでいた。
目の前には葡萄酒の壜と古びたゴブレット、そしてひと摑み分ほどの干し果実と木の実を盛った皿が置かれている。何の変哲もないそれらを頬杖をついて見るともなく見つめながら静夜はぼうっと深い物思いに沈んでいた。
『君のその身体は礎でできていて、強いて言うなら人間を支配しているのは原礎ではなく星そのものだ』
『考えてみてくれ、苦しみと同じくらい多くの小さな幸せもまた確かに存在しているということを』
諄々と道を説く永遠の声がさっきからずっと耳の奥で繰り返されている。
(人間を原礎の手から解放して自由と幸福を勝ち取るために戦ってきたのに…俺はそれを壊そうとしているのか…)
つまみ上げたひと粒の胡桃の実は、指先に少し力を加えただけで簡単にパキンと割れ、粉々に砕けて皿に落ちた。
(…だからと言って、今更俺にどうしろというんだ)
うつむいた額に苦悩と葛藤がまざまざと現れる。初めて浴びた光が強くまぶしいほど、心に巣食った影はいっそう濃く長く伸びていくように思われた。
そうしてひとり座って動かない静夜の姿を、食堂の入り口から暁良が心配そうに見つめていた。
「…」
だが暁良はかける言葉も見つからず、そっと踵を返し、気づかれないよう足早にその場を去った。
さらに数日が経ち、父の明夜が真鍮の砦に戻ってきた。
黙々と雑仕事をこなしている静夜のもとに明夜は早速現れた。今の情婦を伴って。
「帰ったぞ、静夜」
「遠路ご苦労様でした」
口先だけ丁寧にねぎらったきりまた仕事に戻ろうとする静夜を明夜はおどけた苦笑いで引き留める。
「おいおい、父親がせっかく新しい恋人を連れてきたのにつれない奴だな。紹介するぞ。泪だ。泪、これが俺の自慢のひとり息子の静夜」
泪はしなだれかかっていた明夜の腕から離れて静夜に近づいた。わざとらしく肩と腰を揺らして妖艶な微笑みで顔を覗き込んでくると、香水のきつい匂いが鼻を突いて静夜は思わず顔をしかめた。
「あら、ずいぶん男前。全然父親と似てないけど」
「血はつながってないんだからしかたないだろ。顔の話は勘弁してくれよ」
「ほんと、あんたとは似ても似つかないわね。でもまだちょっと初心で純な顔してる」
馴れ馴れしく頬に触れようとしてきたので反射的に顔を引き距離を置く。
(…こういう女には近寄りたくない)
泪はよく見れば美人と言えなくもないが、何しろ色気が過剰で知性も品性も露ほども感じられない。女好きでだらしのない父は今まで何人もの女を連れてきたが、いつも決まって化粧が濃く派手で露出の多い服しか着ない下品な女ばかりだった。知りたくもないがおおかた娼婦か酒場女だろう。それも父が自由気ままな独り身だから許されることで静夜もとうの昔に匙を投げていた。
(どうせまたすぐに飽きて取り替えるだろう)
「こいつは仕事にしか興味ないからな。でもおまえも男なんだから、ときどきは女を抱きたいと思うだろ?」
静夜は戸惑い、内心で用心深く身構えた。
(…いきなり、何を…)
「…任務と鍛練で忙しいので、そんな暇はありません」
「何、別に時間をかけることもない。相手も誰でもいい。部下でも下働きの女でも。なんなら泪をひと晩貸してやろうか」
「まぁ、あんたの息子さん、試していいの?そうね、たまには若くて活きのいい子も悪くないかも…」
「…いいや、やっぱり駄目だ!泪だけは貸さん。若ければいいってもんじゃないぞ。こいつ、後でわからせてやる」
こちらにはお構いなしにじゃれ合い始めるので静夜は目も当てられず、呆れてものも言えずに溜め息をつくばかりだった。
「…父上、それより、首尾の方は…瑪瑙の窟はどうでしたか」
「ん?ああ、計画自体は順調だが、やはりまだ煌気が足りん。今回貢納した分も需要には少し届かなかった。おまえたちにはもっと狩ってきてもらわんと、あの方の機嫌を損ねそうだ」
「わかりました。近いうちに狩りに出ます」
それきり黙り込む静夜の横顔に明夜は目を止めた。
「疲れてるのか?顔色が冴えんぞ」
「いいえ、大丈夫です」
頼むから泪を連れて早く部屋に引っ込んでくれと祈るような気持ちでいたが、明夜はまだしつこく絡んできた。
「時に、聞いたぞ。おまえ、大層な上物を捕まえてきたそうじゃないか」
(もう知られていたか…)
砦に収容した以上部下の口に戸を立てることはできない。覚悟はしていたが、それにしても明夜はこと成果や獲物に関しては恐ろしく耳ざとい。静夜は素直にうなずいた。
「はい。…樹生の若い女で、稀に見る強力な煌源を持っています。数百年にひとりとか」
「でかしたじゃないか静夜。それはぜひとも拝みたい。今すぐ俺をその女のところに連れていけ」
「…わかりました」
本当はたまらなく嫌だったが、断る建前もとっさに思いつかなかったので静夜は諦め、しかたなく明夜を永遠の牢に案内した。
静夜と明夜が上がってきたとき、永遠は鉄格子越しに耶宵と小声で雑談をしていた。二人は気心が知れた友達同士のようにすっかり親しくなっていた。
「この女か。おい、鍵を開けろ」
静夜が耶宵から鍵を受け取って開け、明夜を中に入れる。当然静夜も監視のために一緒に立ち入った。囚人よりもこの父親の方が何をするかわからず厄介だからだ。永遠を見た明夜は開口一番、こうこぼした。
「ふん、女といってもまだ小娘じゃないか。拍子抜けだ」
「外見は小娘かもしれないが、生まれた年はあなたとほとんど変わらないぞ」
永遠の物怖じしない堂々とした態度を明夜は鼻でせせら笑った。
「これはこれは、可愛い顔をして大層なじゃじゃ馬と見える。俺は嫌いじゃないぞ。肉づきは…まだだいぶ薄いようだが…」
案の定、明夜の手が永遠の小さな白い顎に伸びる。その手を永遠が威勢良く払いのけるのと、静夜ががしっと摑んで押さえるのがまったくの同時だった。
「やめてください、父上。扱いは慎重に」
「一人前に紳士気取りか?おまえの獲物は俺の獲物だ。俺がどう扱おうと俺の勝手だ」
牢の外では耶宵がはらはらと息を呑んで見守っている。一気に緊張感を増す雰囲気の中、静夜は形ばかり礼儀に則って互いを相手に紹介した。
「失礼した。俺の父で首領の明夜だ。父上、この原礎が例の樹生・アリスタ・永遠です」
明夜が静夜の実父ではないことをまだ聞かされていない永遠は目の前でふんぞり返っている中年の男を信じられない気持ちで見上げた。
(この無作法で胸のむかつくような男が静夜の父親で、しかも首領だと?大人と子供がまるで逆じゃないか。それに全然似てない)
明夜はけして醜男ではないが、とにかく顔つきも身だしなみも締まりがなくだらしない。身なりを整えてニヤニヤ笑いを引っ込めさえすればまあまあ見られる容姿になるかもしれないが、それでも外見も性格も鋼鉄の剣のようにすらりとして芯の強い美青年である静夜の風格の足許にも及ばない。いい年齢をして鍛練や学問や自己省察も十分ではなさそうだ。こんな男がなぜ静夜の父親であり、首領の座に収まっているのか甚だ疑問だった。
(だがこの男が罪のない静夜や若者たちに精神支配の蠱毒を飲ませ道を誤らせているとしたら油断は禁物…どんな悪事を企んでいるかわからない。私もこの男への言動は慎重にしなければ)
「採煌はしたのか」
「一度だけ。…ただ煌気が強すぎて肉体への負担が大きいようなので、当面は間隔を空け、様子を見ながら量も抑えて採煌します」
「甘い。そんなまどろっこしい配慮などいらん。この女ひとりさえいればわざわざ狩りに出る必要もないんだから、死なない程度にどんどん搾り取れ。…だが、しかし…」
明夜は永遠に手を触れずにぐいと顔を近く寄せた。警戒感も露わに壁ににじり下がる永遠の顔をじろじろと睨め回して、いやらしく舌なめずりをする。
「それにしても…ふん。こいつは面白くなりそうだ」
警戒感を通り越して生理的な嫌悪感に襲われ、永遠は思わず明夜をきつく睨み返した。
0
お気に入りに追加
22
あなたにおすすめの小説

エリート上司に完全に落とされるまで
琴音
BL
大手食品会社営業の楠木 智也(26)はある日会社の上司一ノ瀬 和樹(34)に告白されて付き合うことになった。
彼は会社ではよくわかんない、掴みどころのない不思議な人だった。スペックは申し分なく有能。いつもニコニコしててチームの空気はいい。俺はそんな彼が分からなくて距離を置いていたんだ。まあ、俺は問題児と会社では思われてるから、変にみんなと仲良くなりたいとも思ってはいなかった。その事情は一ノ瀬は知っている。なのに告白してくるとはいい度胸だと思う。
そんな彼と俺は上手くやれるのか不安の中スタート。俺は彼との付き合いの中で苦悩し、愛されて溺れていったんだ。
社会人同士の年の差カップルのお話です。智也は優柔不断で行き当たりばったり。自分の心すらよくわかってない。そんな智也を和樹は溺愛する。自分の男の本能をくすぐる智也が愛しくて堪らなくて、自分を知って欲しいが先行し過ぎていた。結果智也が不安に思っていることを見落とし、智也去ってしまう結果に。この後和樹は智也を取り戻せるのか。

美貌の騎士候補生は、愛する人を快楽漬けにして飼い慣らす〜僕から逃げないで愛させて〜
飛鷹
BL
騎士養成学校に在席しているパスティには秘密がある。
でも、それを誰かに言うつもりはなく、目的を達成したら静かに自国に戻るつもりだった。
しかし美貌の騎士候補生に捕まり、快楽漬けにされ、甘く喘がされてしまう。
秘密を抱えたまま、パスティは幸せになれるのか。
美貌の騎士候補生のカーディアスは何を考えてパスティに付きまとうのか……。
秘密を抱えた二人が幸せになるまでのお話。

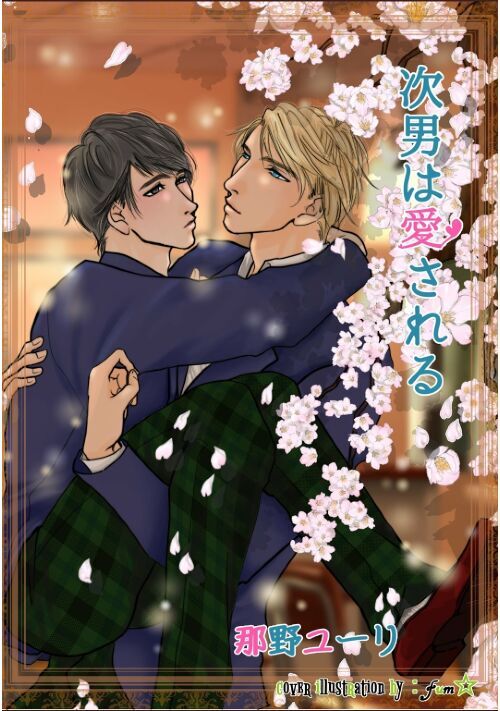
次男は愛される
那野ユーリ
BL
ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男
佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。
素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡
無断転載は厳禁です。
【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】
12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。
近況ボードをご覧下さい。

某国の皇子、冒険者となる
くー
BL
俺が転生したのは、とある帝国という国の皇子だった。
転生してから10年、19歳になった俺は、兄の反対を無視して従者とともに城を抜け出すことにした。
俺の本当の望み、冒険者になる夢を叶えるために……
異世界転生主人公がみんなから愛され、冒険を繰り広げ、成長していく物語です。
主人公は魔法使いとして、仲間と力をあわせて魔物や敵と戦います。
※ BL要素は控えめです。
2020年1月30日(木)完結しました。


お客様と商品
あかまロケ
BL
馬鹿で、不細工で、性格最悪…なオレが、衣食住提供と引き換えに体を売る相手は高校時代一度も面識の無かったエリートモテモテイケメン御曹司で。オレは商品で、相手はお客様。そう思って毎日せっせとお客様に尽くす涙ぐましい努力のオレの物語。(*ムーンライトノベルズ・pixivにも投稿してます。)

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















