198 / 229
最終章 薔薇魔女のキセキ
〈185〉それぞれの思惑
しおりを挟むかっこ、かっこ。
かっこ、かっこ。
街から完全に出るまでは、馬の速さはゆっくりめのトロット。
定期的な蹄の音が石畳を鳴らす中、低くて耳心地の良いルスラーンの声が、レオナの耳元で囁く。
「さっきは悪かった」
「……」
かっこ、かっこ。
かっこ、かっこ。
「……」
「いいの……もう、気にしないで」
せっかくの告白が届かなかったことで、しばらくショックを受けていたレオナ。だがルスラーンの腕の中で馬に揺られているうちに、じわじわと「なんて不器用な人……可愛い」という気持ちの方が勝ってきた。
レオナは――無意識なのだが――俗に言う『スパダリ』なタイプは父のベルナルドや兄のフィリベルトで見慣れすぎていて、並のレベルでは視界に入らなくなってしまっている。さらに、王子や貴族キャラは、エドガーのお陰で、まっ先にうげぇと思ってしまうトラウマ持ち。しかも前世は、恋愛に全く無縁の地味喪女なので、ゼルやディートヘルムのようにグイグイ来られても正直困る。つまり、ルスラーンぐらい不器用で強面の方が好みなのだ。
――この人ほんとに、世界最強の呼び声高い、漆黒の竜騎士なの? 可愛すぎる……でも、相当積極的にならないと気づいてもらえないって、よくわかったわ。
レオナは、胸の奥がしくしくと痛んだ。
災禍の神が身のうちにあるような人間が、普通の恋などできるわけがない。一方で、カミーユの見立て通り、本当にルスラーンが自分を想ってくれているのなら……普通に恋をしてみたい、とも願ってしまう。
――思い切って、甘えてみようかな……今だけでいいの、今だけ。最後の思い出でいいから。普通の恋を、してみたいよ……
横乗りの姿勢で、ルスラーンの腰に手を回して、ぎゅっとしてみる。みしり、と筋肉が詰まっている鍛え上げられた身体を、騎士服越しに感じた。
いつだったか見てしまった、シックスならぬ『テン』パックな彼の腹筋を思い出して、レオナの胸の鼓動が高まる。
「っ、どうした? 辛いか?」
「うん……ちょっと、疲れちゃって……」
「そうか。もっと寄りかかって良いぞ」
かなり大胆なことをしているつもりだが、ルスラーンは、体調を気遣ってくれたようだ。左手に手綱をまとめて持ち直すと、右手でレオナの腰をぐ、と抱いてくれた。レオナが力を抜いても落ちないように。
――んもう! 優しい! 大好き! でも通じない! さすが!
三顧の礼ならぬ、三告白の刑だもんなぁ、とおバカなことを考えたレオナに、イタズラ心が湧き上がった。
「ルス……き……」
「ん?」
「んふふ」
――こうなったら、どさくさに紛れて「好き」って言っちゃうもん!
「……き」
「レオナ? 聞こえなかった」
天気が良く、整備された街道とはいえ、馬上である。
風の音や、時々すれ違う馬車の車輪音、その荷台の荷物がぶつかり合う音、人々の話し声や鳥の声。
馬の呼吸や手綱の擦れる音、帯剣している武器の金属音、衣擦れ音。
レオナの小さな呟きが、馬を操るルスラーンに届かないのは、至極当たり前のことだ。
「なんて言ったんだ? ち?」
「ないしょ!」
「んだよ、気になる」
「んふふふ」
「……楽しいなら、良いけどな」
「うん。たのし。ルス……き」
「おー? わかった、当ててやる。えー……かち?」
「ぶー」
「ぶーてなんだよ」
「間違いっていう、合図ですう」
「はは! なんだそれ。じゃあ……まち?」
「ぶっぶー」
「なに!? あ、もっと間違いってことか?」
「ぴんぽーん!」
「ぴん? 今度はなんだよ」
「ぴんぽんというのが、当たりの合図です」
「ふは。なるほどわかった。んじゃー……ゆき?」
「ぶー!」
「くっそ、外れたかー」
「んふふふ」
――こんなくだらないやり取りを、一緒に楽しんでくれる。なんて、幸せな時間なのだろう。
ルスラーンの腰に抱きついたまま、レオナはその胸元に頬を押し付けた。
「どした? 辛いか?」
馬を操るルスラーンは、チラり、チラりとレオナを見るものの、前方や周辺に常に気を配っているので、なかなか目が合わない。
レオナは、この臆病で優しい最強の騎士が、愛しくてたまらなくなった。
「(す、き)」
顔を上げて、今度は口だけで言ってみた。
ちろ、と目は合ったはずなのだが、返ってきた答えは。
「……あー……降参」
かかっ! とルスラーンの体温が上がった。
耳の上が、赤い気がする。
――え? もしかして……?
レオナが気づいた通り、ルスラーンは、内心激しく動揺していた。
(『好き』って言ってるように見えた……俺の妄想、相当やべぇな……)
「ルス?」
「そろそろ街の外に出る。馬、走らせるから、揺れるぞ」
「……はい」
「疲れたら、遠慮なく言ってくれ。いつでも休むから」
「ありがとう……あのね」
「ん?」
「このまま抱きついてても、い?」
「もちろんだ。しっかり掴まってろ」
「ん……だいすき」
「!? っっ」
(やべぇ! いよいよ俺、『だいすき』って幻聴まで聞こえたぞ……)
ルスラーンは、しばらく悶々としていたが、どうしてもたまらなくなって……馬が揺れるのに合わせて、レオナの頭頂に何度かキスを落とした。レオナは、それに気づかないフリをして――こっそりと泣いた。
そんな二人をチラと振り返る馬上のジョエルは、
「あーあ、これでもかってイチャイチャしてるー」
と肩をすくめるが、ラザールは
「今ぐらい良いだろう。帰国したらまた大変になるんだ」
意外にも許容範囲らしい。
「おー。てっきりラジもレオナのこと好きなんだと思ってたんだけどー」
「特別ではあるが……身内? 妹のような感覚だな、多分」
「はは! そっかー」
「それより、婚約したらやはり変わるものなのか? その、気持ちというか」
「うん、そ……へ? なに、なになにその質問ー!」
「……気にするな、興味があっただけだ」
「怪しいー!」
「うるさい」
そんなジョエルとラザールのやり取りを見ていたヒューゴーは。
「こっちのこれも、大概イチャイチャだよなぁ……」
と、溜息をついたのだった。
※ ※ ※
レオナ達は、当初の予定よりも一日早い、卒業パーティの三日前にローゼン公爵邸へ到着することができた。
フィリベルトが出迎え、レオナをしっかりとハグしたのを見届けた一行。挨拶もそこそこに、休む間もなく今度は騎士団本部へ直行、である。
魔道具を駆使し、馬にかなりの無理をさせ、旅程を大幅に短縮したものの――往復で六日の不在は、当然周囲にかなりの負担を強いた。
マーカム王国戦力ツートップの不在。不安な状況下においても大きな混乱がなかったのは、近衛筆頭ジャンルーカと、第一師団長セレスタンの力によるところが大きい。
おかげで、ユグドラシルの加護を獲得できたのだ。早く伝えて士気をあげなければ! と特にジョエルとラザールは組織の長としての責務を、果たしに行くのである。
それが分かったレオナは、せめて、とそれぞれに回復魔法を施した。
「ありがとー! バタバタでごめんねー、ジャンとセレスが瀕死らしいからー!」
と、ジョエルは割とシャレにならないことを言い
「こっちも、ブリジットが魔王になりつつあるらしい」
と、ラザールが大きな溜息をつく。
ルスラーンは、何か言いたそうにしたものの、結局
「……またな」
と、ぶすりと去っていき――レオナはまた抱きつきたいのを我慢して、その背中を見送った。
そんなレオナはレオナで、ジョエル達との別れの挨拶を済ませるや否や、すぐに報告をしたい! と主張した。着替えた後で、美味しい紅茶とともに再び労ってくれるのは、レオナに対してのみ寛大かつ優しい兄、フィリベルトである。
「頑張ったな、レオナ」
「いいえ、私は何もしておりませんの。皆様のご尽力と、カミーユ殿下のご協力に感謝致しておりますわ、お兄様」
「そうだね……まさか、ホワイトドラゴンの試練が、討伐でないとは。本来なら偉業として大々的に発表したいところだが、そうはいかないのが悔しいね……ヒューゴーも、よくやってくれた。ご苦労だった」
「はっ」
「こちらでも、次の『終末の獣』に備えて準備や根回しは着々と進めていた。今のところ状況に変化はないから、安心して良いよ」
フィリベルトは、そこでティーカップを持ち上げ、こくりと紅茶を一口飲んだ。
「……さて、それは良いとして。どんなワガママな要求を隠しているのかな、我が可愛い妹は」
「っ」
平静を装っていたのに、すぐにバレちゃうのよね、とレオナは自嘲の笑みを漏らす。
「あの……お兄様に、ご無理をご承知で……」
レオナが振り返ると、ヒューゴーの手の中には、封印布に包まれた『百薬の魔石』がある。
「分かっている。レオナ達が旅立った後、王宮図書室の閲覧許可を得て、くまなく文献を調べていた」
ヒューゴーが、背後で息を呑む。
「――残念だが、百薬の魔石に関する記録は、一切見つからなかった」
「左様ですか……」
「ッ……」
あからさまに肩を落とすヒューゴーであるが、
「見せてくれるかい?」
フィリベルトが手を差し出したので、素直に布ごと石を渡す。
「ふむ……静かだね」
「静か、というと?」
「他の竜の魔石……破邪や、黒鋼、赫焉を見てきたけれど、力が強すぎてね。とてもこうして直接触れるものではなかった。ホワイトドラゴンは、何か言っていたかな?」
「憎悪に気をつけろ、これを託す、と」
「そうか……ゼル君のところに、行ってみるかい?」
「良いのですか!」
思わずレオナがソファから立ち上がると
「良いも何も」
フィリベルトは、それを困ったような顔で見ながら、やはり向かいの椅子から立ち上がる。
「それは、レオナの物だからね」
「お兄様……」
「私は、レオナのやりたいことを、そばで見守る。それだけだよ。いてもたってもいられないのだろう? さあ、行こうか」
レオナは、無言でフィリベルトに駆け寄り、抱き着いた。
ヒューゴーは、涙を流して、深く頭を下げた。
※ ※ ※
卒業パーティを明日に控え、マーカム王太子アリスターは、頭を抱えていた。
ベヒモス出現時に避難しないどころか、討伐パーティの邪魔にしかならなかったエドガー(とユリエ)の処遇について、決めなければならないからだ。
本人は
「マーカムの王族としてその場に残って指揮をしたまで!」
と胸を張っており、何度
「逃げることが王族の務め」「そもそも指揮権などない」
などと説明をしても納得せず
「兄上は、僕をそこまで貶めたいのか!」
と憤ってしまい、ついには部屋から出てこなくなった。
王立騎士団第三師団長としてのフィリベルト・ローゼンは、事態を慮って二種類の報告書を提出している。
一つはエドガーには触れず、淡々と戦況と結果を報告したもの。
もう一つはアリスター向けに事細かな説明をしたもの、だ。当然後者は、アリスターのデスクの中に眠っていて、国王には見せていない。フィリベルトは、出してもいいとは言っているが、とても見せられない。
なぜなら、エドガーが割れたカップで指先を切り、その血が滴ったことでベヒモスが出現したと思われる、と書いてあるからだ。なぜそのようなことを? まさか、エドガーが関与しているのか? いったん疑いだすと、キリがなくなってしまった。
アリスターとて、自分の血のつながった弟だ。信じたい。
が、幼少時の屈託のない彼からは、性格がずいぶん変わってしまった。
素直で明るく、裏表がなく、憎めない性格で
「レオナ嬢と結婚して、公爵として兄上を盛り立てたい!」
とキラキラと語っていて可愛いな、と思えていたのは、はるか昔のことのようだ。
「決断、か……王の道とは、残酷なものだな」
教育係のジャンルーカは、既に見限っている。
アリスターの苦悩は今やもう、孤独なものとなってしまっていた――
※ ※ ※
たゆたう水面が、キラキラと真昼の太陽を反射している。
サービアは、ざくざくと無遠慮に草花を踏みしめてやってきた来訪者を、座ったままの姿勢で迎えた。その花も生きてるんだけどなあ、とボンヤリその足を眺めながら、何日かぶりに声を出す。
「……ひさしぶりだね、宿主さん」
「まだ!?」
開口一番が文句とは、めんどうだな、とサービアは思う。
「うん。もう少しかな」
「ぐだぐだと!」
「……待てないなら、今すぐ殺してあげよっか?」
「っっ」
「闘神が左足だけだったからね。足りないんだ」
ゆらり、と立ち上がるサービアが、宿主の顔に陰を作る。
「死ぬ覚悟もないくせに、煽るなよ」
どろり。
「ひっ」
「おまえの闇なんて、ゴミでしかない」
ねろり。
サービアから、何か黒いドロドロしたものが、漏れ出る。
空気に触れると、しゅううう、と気化する。
触りたくなくて、宿主は一歩、二歩と下がり、バランスを崩してしりもちをついた。
「やめ、やめっ!」
「おまえがうごくと、いろいろばれちゃうかもしれないだろ? 言われないと分からないのか。残念だねえ」
わざと、ゆっくり話してあげる僕は、優しいよね?
「明日、卒業パーティ!」
「知ってるよ」
「間に合う!?」
「間に合わないねー」
「なっ」
「あともう少しだけ、イケニエが必要なんだよ。誰か、いない?」
サービアの言葉に宿主は、ニタァ、と笑った――
-----------------------------
お読み頂き、ありがとうございました!
いよいよ卒業パーティです。
0
お気に入りに追加
886
あなたにおすすめの小説

オバサンが転生しましたが何も持ってないので何もできません!
みさちぃ
恋愛
50歳近くのおばさんが異世界転生した!
転生したら普通チートじゃない?何もありませんがっ!!
前世で苦しい思いをしたのでもう一人で生きて行こうかと思います。
とにかく目指すは自由気ままなスローライフ。
森で調合師して暮らすこと!
ひとまず読み漁った小説に沿って悪役令嬢から国外追放を目指しますが…
無理そうです……
更に隣で笑う幼なじみが気になります…
完結済みです。
なろう様にも掲載しています。
副題に*がついているものはアルファポリス様のみになります。
エピローグで完結です。
番外編になります。
※完結設定してしまい新しい話が追加できませんので、以後番外編載せる場合は別に設けるかなろう様のみになります。

婚約破棄されて辺境へ追放されました。でもステータスがほぼMAXだったので平気です!スローライフを楽しむぞっ♪
naturalsoft
恋愛
シオン・スカーレット公爵令嬢は転生者であった。夢だった剣と魔法の世界に転生し、剣の鍛錬と魔法の鍛錬と勉強をずっとしており、攻略者の好感度を上げなかったため、婚約破棄されました。
「あれ?ここって乙女ゲーの世界だったの?」
まっ、いいかっ!
持ち前の能天気さとポジティブ思考で、辺境へ追放されても元気に頑張って生きてます!

魅了が解けた貴男から私へ
砂礫レキ
ファンタジー
貴族学園に通う一人の男爵令嬢が第一王子ダレルに魅了の術をかけた。
彼女に操られたダレルは婚約者のコルネリアを憎み罵り続ける。
そして卒業パーティーでとうとう婚約破棄を宣言した。
しかし魅了の術はその場に運良く居た宮廷魔術師に見破られる。
男爵令嬢は処刑されダレルは正気に戻った。
元凶は裁かれコルネリアへの愛を取り戻したダレル。
しかしそんな彼に半年後、今度はコルネリアが婚約破棄を告げた。
三話完結です。

【完結】勘当されたい悪役は自由に生きる
雨野
恋愛
難病に罹り、15歳で人生を終えた私。
だが気がつくと、生前読んだ漫画の貴族で悪役に転生していた!?タイトルは忘れてしまったし、ラストまで読むことは出来なかったけど…確かこのキャラは、家を勘当され追放されたんじゃなかったっけ?
でも…手足は自由に動くし、ご飯は美味しく食べられる。すうっと深呼吸することだって出来る!!追放ったって殺される訳でもなし、貴族じゃなくなっても問題ないよね?むしろ私、庶民の生活のほうが大歓迎!!
ただ…私が転生したこのキャラ、セレスタン・ラサーニュ。悪役令息、男だったよね?どこからどう見ても女の身体なんですが。上に無いはずのモノがあり、下にあるはずのアレが無いんですが!?どうなってんのよ!!?
1話目はシリアスな感じですが、最終的にはほのぼの目指します。
ずっと病弱だったが故に、目に映る全てのものが輝いて見えるセレスタン。自分が変われば世界も変わる、私は…自由だ!!!
主人公は最初のうちは卑屈だったりしますが、次第に前向きに成長します。それまで見守っていただければと!
愛され主人公のつもりですが、逆ハーレムはありません。逆ハー風味はある。男装主人公なので、側から見るとBLカップルです。
予告なく痛々しい、残酷な描写あり。
サブタイトルに◼️が付いている話はシリアスになりがち。
小説家になろうさんでも掲載しております。そっちのほうが先行公開中。後書きなんかで、ちょいちょいネタ挟んでます。よろしければご覧ください。
こちらでは僅かに加筆&話が増えてたりします。
本編完結。番外編を順次公開していきます。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!

旦那様、前世の記憶を取り戻したので離縁させて頂きます
結城芙由奈@コミカライズ発売中
恋愛
【前世の記憶が戻ったので、貴方はもう用済みです】
ある日突然私は前世の記憶を取り戻し、今自分が置かれている結婚生活がとても理不尽な事に気が付いた。こんな夫ならもういらない。前世の知識を活用すれば、この世界でもきっと女1人で生きていけるはず。そして私はクズ夫に離婚届を突きつけた―。

【完結】【35万pt感謝】転生したらお飾りにもならない王妃のようなので自由にやらせていただきます
宇水涼麻
恋愛
王妃レイジーナは出産を期に入れ替わった。現世の知識と前世の記憶を持ったレイジーナは王子を産む道具である現状の脱却に奮闘する。
さらには息子に殺される運命から逃れられるのか。
中世ヨーロッパ風異世界転生。
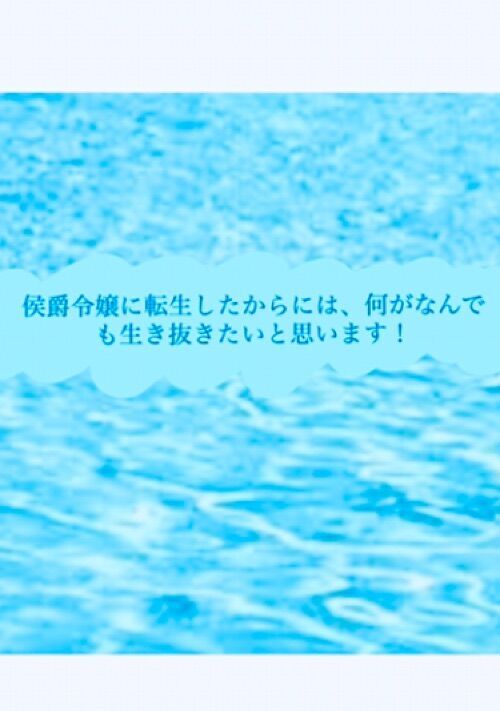
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

【完結】番である私の旦那様
桜もふ
恋愛
異世界であるミーストの世界最強なのが黒竜族!
黒竜族の第一皇子、オパール・ブラック・オニキス(愛称:オール)の番をミースト神が異世界転移させた、それが『私』だ。
バールナ公爵の元へ養女として出向く事になるのだが、1人娘であった義妹が最後まで『自分』が黒竜族の番だと思い込み、魅了の力を使って男性を味方に付け、なにかと嫌味や嫌がらせをして来る。
オールは政務が忙しい身ではあるが、溺愛している私の送り迎えだけは必須事項みたい。
気が抜けるほど甘々なのに、義妹に邪魔されっぱなし。
でも神様からは特別なチートを貰い、世界最強の黒竜族の番に相応しい子になろうと頑張るのだが、なぜかディロ-ルの侯爵子息に学園主催の舞踏会で「お前との婚約を破棄する!」なんて訳の分からない事を言われるし、義妹は最後の最後まで頭お花畑状態で、オールを手に入れようと男の元を転々としながら、絡んで来ます!(鬱陶しいくらい来ます!)
大好きな乙女ゲームや異世界の漫画に出てくる「私がヒロインよ!」な頭の変な……じゃなかった、変わった義妹もいるし、何と言っても、この世界の料理はマズイ、不味すぎるのです!
神様から貰った、特別なスキルを使って異世界の皆と地球へ行き来したり、地球での家族と異世界へ行き来しながら、日本で得た知識や得意な家事(食事)などを、この世界でオールと一緒に自由にのんびりと生きて行こうと思います。
前半は転移する前の私生活から始まります。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















