23 / 27
記憶1.
しおりを挟む
「明けましておめでとうございます」
会社のあちこちで声がしている。年末年始の休み明け、出勤初日はやはりどこか晴れやかな雰囲気が漂う。
しかしそんな気分も休みの間に溜まった書類やメールの返信に追われるうちに、通常モードに戻っていく。
一花は午後三時ごろに一息ついて、コーヒーを口にした。
そういえば、結局、鬼塚さんにまだ挨拶してないなあ。今日は挨拶かねて外回りみたいだし。
榛瑠にも会っていない。どうやら出勤していないらしい。年末に一緒にアメリカに行ったはずの美園さんも休みらしい。
もしかしたら、そもそも帰国していないのかもしれない。このまま、もしかして帰ってこないつもりかな、二人して……。
一花は首に隠すようにかけてあるネックレスを、服の上からそっとなぞる。
「一花さん、この書類お願いできる?」
一瞬ぼうっとしてしまった一花は、声をかけられて慌てて言った。
「あ、はい、わかりました。急ぎですか?」
「明日の昼くらいまでにお願いしたいんだけど」
振り返ると、佐藤がいつも通り微笑みを浮かべながら、そう答える。一花は書類を受け取って目を通した。
その様子を見ながら佐藤が言った。
「そういえば、四条さん会社来てないんだね」
「あ、そうみたいですね」
一花は書類から目を上げずに答えた。
「大変だよね、大丈夫なの?」
「えっと、まあ……」
「ほら、一人暮らしで体調崩すと大変な時あるからさ。でも、そっか、四条さんなら考えて準備してそうだもんね」
「え?」
一花は佐藤の顔を見る。
「体調?」
「え? あれ?」
今度は佐藤が戸惑う。
「知らなかった? 四条さん体調不良で休んでるんだって。僕も知らなくて、仕事の事で電話しちゃって知ったんだけど」
「……え、そうなんですか?」
「うん、大した事ないといいよね。そっか、知らなかったんだ。お見舞い行ってみたら?」
最後を小さな声で佐藤は言うと「じゃあ、書類お願いします」といって席に戻って行った。
一花はパソコンに向かって書類を作りながらもグルグル考えていた。
体調不良? ってことはマンションにいるの? え、じゃあ、美園さんは? 一緒とか? ……それだったら最悪。
でも……。見舞い? 見舞いって行っていいの? 私が? あり? それ。
……あんな態度とっちゃったのに。あんなこと言わせちゃったのに。
一花は思わずため息をついた。と、席を外していた篠山が隣に戻ってきて言った。
「一花さん、仕事増えてます? 私、何にも今日はないから少しもらいましょうか?」
「あ、大丈夫。終業までには終われるから。ありがとう」
答えながら、とりあえずこの仕事終わらせなくっちゃ、と書類に目を落とした。
「で、何でここへ?」
一花は玄関先で紙袋を両手で抱えたまま、その質問に答えた。
「えっと、風邪引いてるって聞いたので、お見舞い」
「休んでなんですが、大したことないですから。感染るといけないので……」
榛瑠は横になっていたのか、いつもはあまり着ないスウェットを着ている。やっぱり起こしちゃったかなあと思いつつ、彼の言葉を遮った。
「平気。私、丈夫だから」
「はい?」
「免疫強いの。ここのところ何年も風邪らしい風邪ひいてないし。屋敷中でみんな風邪ひいたりした年でも風邪引かなかったし」
「それはいいことですけど……」
そう言いながら玄関の壁に肩を預けている。体がだるいなら早くそこ通してよね。
「とにかく、上がらせて。これだけでも置かせて」
そう言って半ば無理やり上がりこむと、一花はキッチンに直行してテーブルに紙袋を置いて中を取り出す。
「なんですか、それ?」
後ろからついてくる形になった榛瑠が覗き込んで言う。
一花は無言で包まれていた布のカバーもとって中身を出した。
「お粥。まだ少しは温かいけどもう一度火にかけたほうがいいかしら?」
一花は小さい土鍋を抱えながら言った。榛瑠は間をおいた後、抑えた笑い声を上げた。
「え? 何で?」
戸惑う一花に直接答えず、榛瑠はなおも笑いながら土鍋を受け取るとコンロにかけた。
「これどうしたんです? 今日、出社したんでしょ?」
そう、時計に目をやりながら榛瑠が言う。まだ夕食時だ。仕事終わってから作ったのなら早すぎる時間だった。
「えっと、家に電話して終業時間に合わせて持ってきてもらった。そんなわけで大丈夫よ。おいしいわよ、心配しないで」
「何の心配?」
「……私が作ったんじゃないってことよ」
一花がそういうと、榛瑠は声を抑えつつも我慢できないとばかりに笑う。そんなにおかしい事言ってないのに、と一花は思う。
程なく鍋が温まると榛瑠は自分でテーブルまで運んだ。
「せっかくですので、いただきますね。ありがとうございます」
「どうぞ召し上がれ」
榛瑠はいつもより明らかにゆっくり食事している。そして、半分ほど残してレンゲをおいた。
「残りは後でいただきます。ごちそうさま」
見た感じより、たぶん調子悪いんだなと一花は思う。
榛瑠は立ち上がって薬を取ってきた。
「インフルエンザじゃないの?」
「違いますよ、病院に行って調べました。インフルエンザなら、あなたを家にはあげませんよ」
「熱は?」
「ありますね」
「……薬飲んだら寝てくださいね」
「はい」
大人しく榛瑠は言うと、服薬して寝室に行く。そこでベットの端に座ると、「あ、しまった」と言った。
「どうしたの?」
「水を持ってくるのを忘れました。喉が渇くんですよね」
「持ってくる、待ってて」
冷蔵庫から水のボトルを持って寝室に戻ると、まだ榛瑠は座ったままだった。水を受け取ると、礼の言葉とともに言う。
「ありがとうございます。ところで、何であなた来たの?」
「え? だから、風邪だって聞いたから……」
「そうじゃなくて、怒ってたんじゃないんですか?」
一花は年末のことを思い出す。確かに、腹が立った瞬間もあったけど、でもあの時はむしろ……。
「ごめんなさい」
一花は立ったまま頭を下げた。
「何のこと?」
「あの時、ひどい態度をとって。つまらない意地をはって傷つけたわ。そんなことする意味なんてないのに。むしろ、あなたが怒ってないかなって思ってたの……」
本当は来るのが怖かった。榛瑠が怒っているかもしれなかったし、何よりお節介だと苛立たせて、これ以上嫌われたくなかった。でも……。
「怒りませんよ、私はそんなに感情的な人間ではありません。あなたは素直に自分の感情を表しただけだし、それは理解できる範囲です」
……やっぱり、微妙に怒ってるじゃない、その言い回し。でも、しょうがない。
一花はむしろ少し嬉しいくらいだった。面白く思ってない事を表にだしてもらえたのだから。
「ごめんなさい」
「うん、まあいいけど、僕は謝らないですけど。とりあえず寝ますね」
そう言ってベットに横になる。額に左腕をのせていてだるそうだった。
「何か欲しいものほかにある? 頭冷やすやつとかいる?」
「いらない。ああ、でも、欲しいものはあるかな」
「なに?」
一花は横になっている榛瑠に上布団をかけようとした。と、不意に腕を掴まれて気づいたら横にされてベットの上で抱きつかれていた。
ちょうど、一花の顔の下、胸のあたりに頭をのせている。
「空っぽなのにな」
「え?」
声がくぐもって聞こえない。
「……落ち着く」
榛瑠がぼそっと呟く。今度は聞こえた。
ああ、もう、まったく。この人は……。
手も体も熱いし。熱が出ると女の子にひっつきたがるの、こうなると、もう本能なのかしら。
しょうがないなあ……。
一花は榛瑠の金色の髪を撫でた。この髪、大好きだなあって思う。
「……怒らないんだ?」
榛瑠が胸に顔を埋めたまま言う。
「いつものことだもの。……あなた覚えてないけど、熱出すと昔からこんなんだったもの。……そうよ、だいたい、子供の時から結構丈夫そうなのに、熱だけは出すのよ。でも、平気なふりするからいちいち心配で」
そう、ずっとそう。
「だから今回も心配で来たのよ。いつもそうしてきたのに、今回は違う、なんて変でしょ?」
元カノが元カレの元に病気だからって来たら、迷惑かもしれない。でも、それ以前の話よ。ずっとこうだったのよ。
「だから来たのよ」
迷惑でも知るものか。心配するのが普通なんだから。例え二人の関係が元に戻らなくても、例え榛瑠がなにも覚えてなくても、例え迷惑に思われても。
私は心配する。今までも、これからも。
「私は勝手に心配するし、押しかけるし。だからあなたも」
一花は榛瑠の頭を軽く指でトントン、とつついた。
「なに?」
「今のあなたを心配する人がいるってこと覚えておいてね」
そうじゃないと、放っておいたらこの先どこかで無茶しかねないし。
「いい? 私だけじゃないのよ。嶋さんや高橋さんや屋敷の人皆んなよ。そうじゃないなら、さすがにお粥作って持ってきてなんて、私だって頼み辛いんだから」
榛瑠は小さく笑ったようだった。それから顔をあげると、一花に笑いかけた。優しい顔で。それからそっとキスをする。
「……ああ、しまったな。風邪をうつしちゃいけないのに」
唇を離すと榛瑠は言った。
「平気、丈夫だから」
目をつぶったまま一花は言った。榛瑠はまた頭をのせる。
きっと、すごくドキドキいってるのがバレちゃってる。
「あ、そうだ。感染るって言えば、美園さんも今日出社してなかったよ? どうして? 一緒だったんでしょ?」
「ああ、二日酔いなんじゃないですか?」
「え?」
「飛行機の隣の座席で、ずっと咳しながら消毒とかいって酒ばっかり頼んでたから。日本についてタクシーに放り込んだんですけど、いい迷惑」
あ、そうなの。笑うとこなのかなんなのか。
「美園の心配もしたの?」
「さすがにそんなに優しくはなれないなあ……。二人とももう帰ってこないのかもと思ったから……」
「まさか」
榛瑠は笑いを含んだ声で言った。そっか、まさかなんだ。ほっとする。嬉しいと思う。
と、また榛瑠が顔を上げて、からかうような笑顔を向けてくる。
「嬉しい?」
この男はっ。
「……嬉しいわよっ」
恥ずかしさを押しのけて、一花は半ば自棄気味に言ってみる。
榛瑠はクスクス笑った。それから一花の首にかかっていた小さな星を指先で引っ掛けた。
「僕の意地悪にいちいちつきあわなくてもいいんですよ」
そんなんじゃない。
「これはつけたいからつけてるのよ。……嬉しかったわ、ありがとう」
榛瑠はネックレスから指を外すと、同じ指で一花の頬にかかっていた髪を優しく払った。
それから、もう一度キスをした。唇をあわせるだけの、穏やかで丁寧なキスだった。
「帰したくなくなるな」
榛瑠が一花の髪に触れながら微笑む。一花は心臓の鼓動と一緒に息を深く一度吸った。
「……帰らなくてもいいわよ? ……夜中に熱上がるかもしれないし……」
「うん、そうだね」
それだけ言って一花から離れると、壁に持たれるようにベットの上で座る。
一花も起きて座った。榛瑠は首をわずかに傾げて一花を見ている。そんな榛瑠を見て一花は小さくため息をついた。
「帰って欲しいのね?」
「そう」
「もう……」
しょうがないなあ。結局こうなんだから。最後は人を寄せ付けない。何で前と同じなのかなあ。
「わかった、帰ります」
「うん」
一花はベットから降りて立つと榛瑠に向き合った。
「そのかわり、調子が悪くなったら、絶対、連絡してね。夜中でもよ? いい?」
「はいはい」
「絶対よ。はっきり言って迷惑とかないから。だって私、高橋さんに車出してもらって乗ってくるだけだもん」
榛瑠は笑った。
「困ったお嬢様だなあ」
「そうよ、いいの、それで」
「わかりました、お嬢様」
一花はドキッとした。榛瑠に慣れ親しんだ声音でこんなふうにお嬢様と呼ばれたのはいつぶりかしら。
「じゃ、はいこれ」
榛瑠はサイドテーブルの引き出しから何か取り出すと一花に差し出した。一花の手のひらの上に置かれたのは見覚えのある鍵だった。
「え?」
「出て行く時、鍵かけていって。玄関まで行くの嫌だし」
「わかった。じゃあ、えっと、そのうち元気になったら返すね」
「そのまま持ってて」
榛瑠は何でもないように、少しだるそうな声で言った。
「……うん、わかった」
一花は鍵をぎゅっと握りしめた。
会社のあちこちで声がしている。年末年始の休み明け、出勤初日はやはりどこか晴れやかな雰囲気が漂う。
しかしそんな気分も休みの間に溜まった書類やメールの返信に追われるうちに、通常モードに戻っていく。
一花は午後三時ごろに一息ついて、コーヒーを口にした。
そういえば、結局、鬼塚さんにまだ挨拶してないなあ。今日は挨拶かねて外回りみたいだし。
榛瑠にも会っていない。どうやら出勤していないらしい。年末に一緒にアメリカに行ったはずの美園さんも休みらしい。
もしかしたら、そもそも帰国していないのかもしれない。このまま、もしかして帰ってこないつもりかな、二人して……。
一花は首に隠すようにかけてあるネックレスを、服の上からそっとなぞる。
「一花さん、この書類お願いできる?」
一瞬ぼうっとしてしまった一花は、声をかけられて慌てて言った。
「あ、はい、わかりました。急ぎですか?」
「明日の昼くらいまでにお願いしたいんだけど」
振り返ると、佐藤がいつも通り微笑みを浮かべながら、そう答える。一花は書類を受け取って目を通した。
その様子を見ながら佐藤が言った。
「そういえば、四条さん会社来てないんだね」
「あ、そうみたいですね」
一花は書類から目を上げずに答えた。
「大変だよね、大丈夫なの?」
「えっと、まあ……」
「ほら、一人暮らしで体調崩すと大変な時あるからさ。でも、そっか、四条さんなら考えて準備してそうだもんね」
「え?」
一花は佐藤の顔を見る。
「体調?」
「え? あれ?」
今度は佐藤が戸惑う。
「知らなかった? 四条さん体調不良で休んでるんだって。僕も知らなくて、仕事の事で電話しちゃって知ったんだけど」
「……え、そうなんですか?」
「うん、大した事ないといいよね。そっか、知らなかったんだ。お見舞い行ってみたら?」
最後を小さな声で佐藤は言うと「じゃあ、書類お願いします」といって席に戻って行った。
一花はパソコンに向かって書類を作りながらもグルグル考えていた。
体調不良? ってことはマンションにいるの? え、じゃあ、美園さんは? 一緒とか? ……それだったら最悪。
でも……。見舞い? 見舞いって行っていいの? 私が? あり? それ。
……あんな態度とっちゃったのに。あんなこと言わせちゃったのに。
一花は思わずため息をついた。と、席を外していた篠山が隣に戻ってきて言った。
「一花さん、仕事増えてます? 私、何にも今日はないから少しもらいましょうか?」
「あ、大丈夫。終業までには終われるから。ありがとう」
答えながら、とりあえずこの仕事終わらせなくっちゃ、と書類に目を落とした。
「で、何でここへ?」
一花は玄関先で紙袋を両手で抱えたまま、その質問に答えた。
「えっと、風邪引いてるって聞いたので、お見舞い」
「休んでなんですが、大したことないですから。感染るといけないので……」
榛瑠は横になっていたのか、いつもはあまり着ないスウェットを着ている。やっぱり起こしちゃったかなあと思いつつ、彼の言葉を遮った。
「平気。私、丈夫だから」
「はい?」
「免疫強いの。ここのところ何年も風邪らしい風邪ひいてないし。屋敷中でみんな風邪ひいたりした年でも風邪引かなかったし」
「それはいいことですけど……」
そう言いながら玄関の壁に肩を預けている。体がだるいなら早くそこ通してよね。
「とにかく、上がらせて。これだけでも置かせて」
そう言って半ば無理やり上がりこむと、一花はキッチンに直行してテーブルに紙袋を置いて中を取り出す。
「なんですか、それ?」
後ろからついてくる形になった榛瑠が覗き込んで言う。
一花は無言で包まれていた布のカバーもとって中身を出した。
「お粥。まだ少しは温かいけどもう一度火にかけたほうがいいかしら?」
一花は小さい土鍋を抱えながら言った。榛瑠は間をおいた後、抑えた笑い声を上げた。
「え? 何で?」
戸惑う一花に直接答えず、榛瑠はなおも笑いながら土鍋を受け取るとコンロにかけた。
「これどうしたんです? 今日、出社したんでしょ?」
そう、時計に目をやりながら榛瑠が言う。まだ夕食時だ。仕事終わってから作ったのなら早すぎる時間だった。
「えっと、家に電話して終業時間に合わせて持ってきてもらった。そんなわけで大丈夫よ。おいしいわよ、心配しないで」
「何の心配?」
「……私が作ったんじゃないってことよ」
一花がそういうと、榛瑠は声を抑えつつも我慢できないとばかりに笑う。そんなにおかしい事言ってないのに、と一花は思う。
程なく鍋が温まると榛瑠は自分でテーブルまで運んだ。
「せっかくですので、いただきますね。ありがとうございます」
「どうぞ召し上がれ」
榛瑠はいつもより明らかにゆっくり食事している。そして、半分ほど残してレンゲをおいた。
「残りは後でいただきます。ごちそうさま」
見た感じより、たぶん調子悪いんだなと一花は思う。
榛瑠は立ち上がって薬を取ってきた。
「インフルエンザじゃないの?」
「違いますよ、病院に行って調べました。インフルエンザなら、あなたを家にはあげませんよ」
「熱は?」
「ありますね」
「……薬飲んだら寝てくださいね」
「はい」
大人しく榛瑠は言うと、服薬して寝室に行く。そこでベットの端に座ると、「あ、しまった」と言った。
「どうしたの?」
「水を持ってくるのを忘れました。喉が渇くんですよね」
「持ってくる、待ってて」
冷蔵庫から水のボトルを持って寝室に戻ると、まだ榛瑠は座ったままだった。水を受け取ると、礼の言葉とともに言う。
「ありがとうございます。ところで、何であなた来たの?」
「え? だから、風邪だって聞いたから……」
「そうじゃなくて、怒ってたんじゃないんですか?」
一花は年末のことを思い出す。確かに、腹が立った瞬間もあったけど、でもあの時はむしろ……。
「ごめんなさい」
一花は立ったまま頭を下げた。
「何のこと?」
「あの時、ひどい態度をとって。つまらない意地をはって傷つけたわ。そんなことする意味なんてないのに。むしろ、あなたが怒ってないかなって思ってたの……」
本当は来るのが怖かった。榛瑠が怒っているかもしれなかったし、何よりお節介だと苛立たせて、これ以上嫌われたくなかった。でも……。
「怒りませんよ、私はそんなに感情的な人間ではありません。あなたは素直に自分の感情を表しただけだし、それは理解できる範囲です」
……やっぱり、微妙に怒ってるじゃない、その言い回し。でも、しょうがない。
一花はむしろ少し嬉しいくらいだった。面白く思ってない事を表にだしてもらえたのだから。
「ごめんなさい」
「うん、まあいいけど、僕は謝らないですけど。とりあえず寝ますね」
そう言ってベットに横になる。額に左腕をのせていてだるそうだった。
「何か欲しいものほかにある? 頭冷やすやつとかいる?」
「いらない。ああ、でも、欲しいものはあるかな」
「なに?」
一花は横になっている榛瑠に上布団をかけようとした。と、不意に腕を掴まれて気づいたら横にされてベットの上で抱きつかれていた。
ちょうど、一花の顔の下、胸のあたりに頭をのせている。
「空っぽなのにな」
「え?」
声がくぐもって聞こえない。
「……落ち着く」
榛瑠がぼそっと呟く。今度は聞こえた。
ああ、もう、まったく。この人は……。
手も体も熱いし。熱が出ると女の子にひっつきたがるの、こうなると、もう本能なのかしら。
しょうがないなあ……。
一花は榛瑠の金色の髪を撫でた。この髪、大好きだなあって思う。
「……怒らないんだ?」
榛瑠が胸に顔を埋めたまま言う。
「いつものことだもの。……あなた覚えてないけど、熱出すと昔からこんなんだったもの。……そうよ、だいたい、子供の時から結構丈夫そうなのに、熱だけは出すのよ。でも、平気なふりするからいちいち心配で」
そう、ずっとそう。
「だから今回も心配で来たのよ。いつもそうしてきたのに、今回は違う、なんて変でしょ?」
元カノが元カレの元に病気だからって来たら、迷惑かもしれない。でも、それ以前の話よ。ずっとこうだったのよ。
「だから来たのよ」
迷惑でも知るものか。心配するのが普通なんだから。例え二人の関係が元に戻らなくても、例え榛瑠がなにも覚えてなくても、例え迷惑に思われても。
私は心配する。今までも、これからも。
「私は勝手に心配するし、押しかけるし。だからあなたも」
一花は榛瑠の頭を軽く指でトントン、とつついた。
「なに?」
「今のあなたを心配する人がいるってこと覚えておいてね」
そうじゃないと、放っておいたらこの先どこかで無茶しかねないし。
「いい? 私だけじゃないのよ。嶋さんや高橋さんや屋敷の人皆んなよ。そうじゃないなら、さすがにお粥作って持ってきてなんて、私だって頼み辛いんだから」
榛瑠は小さく笑ったようだった。それから顔をあげると、一花に笑いかけた。優しい顔で。それからそっとキスをする。
「……ああ、しまったな。風邪をうつしちゃいけないのに」
唇を離すと榛瑠は言った。
「平気、丈夫だから」
目をつぶったまま一花は言った。榛瑠はまた頭をのせる。
きっと、すごくドキドキいってるのがバレちゃってる。
「あ、そうだ。感染るって言えば、美園さんも今日出社してなかったよ? どうして? 一緒だったんでしょ?」
「ああ、二日酔いなんじゃないですか?」
「え?」
「飛行機の隣の座席で、ずっと咳しながら消毒とかいって酒ばっかり頼んでたから。日本についてタクシーに放り込んだんですけど、いい迷惑」
あ、そうなの。笑うとこなのかなんなのか。
「美園の心配もしたの?」
「さすがにそんなに優しくはなれないなあ……。二人とももう帰ってこないのかもと思ったから……」
「まさか」
榛瑠は笑いを含んだ声で言った。そっか、まさかなんだ。ほっとする。嬉しいと思う。
と、また榛瑠が顔を上げて、からかうような笑顔を向けてくる。
「嬉しい?」
この男はっ。
「……嬉しいわよっ」
恥ずかしさを押しのけて、一花は半ば自棄気味に言ってみる。
榛瑠はクスクス笑った。それから一花の首にかかっていた小さな星を指先で引っ掛けた。
「僕の意地悪にいちいちつきあわなくてもいいんですよ」
そんなんじゃない。
「これはつけたいからつけてるのよ。……嬉しかったわ、ありがとう」
榛瑠はネックレスから指を外すと、同じ指で一花の頬にかかっていた髪を優しく払った。
それから、もう一度キスをした。唇をあわせるだけの、穏やかで丁寧なキスだった。
「帰したくなくなるな」
榛瑠が一花の髪に触れながら微笑む。一花は心臓の鼓動と一緒に息を深く一度吸った。
「……帰らなくてもいいわよ? ……夜中に熱上がるかもしれないし……」
「うん、そうだね」
それだけ言って一花から離れると、壁に持たれるようにベットの上で座る。
一花も起きて座った。榛瑠は首をわずかに傾げて一花を見ている。そんな榛瑠を見て一花は小さくため息をついた。
「帰って欲しいのね?」
「そう」
「もう……」
しょうがないなあ。結局こうなんだから。最後は人を寄せ付けない。何で前と同じなのかなあ。
「わかった、帰ります」
「うん」
一花はベットから降りて立つと榛瑠に向き合った。
「そのかわり、調子が悪くなったら、絶対、連絡してね。夜中でもよ? いい?」
「はいはい」
「絶対よ。はっきり言って迷惑とかないから。だって私、高橋さんに車出してもらって乗ってくるだけだもん」
榛瑠は笑った。
「困ったお嬢様だなあ」
「そうよ、いいの、それで」
「わかりました、お嬢様」
一花はドキッとした。榛瑠に慣れ親しんだ声音でこんなふうにお嬢様と呼ばれたのはいつぶりかしら。
「じゃ、はいこれ」
榛瑠はサイドテーブルの引き出しから何か取り出すと一花に差し出した。一花の手のひらの上に置かれたのは見覚えのある鍵だった。
「え?」
「出て行く時、鍵かけていって。玄関まで行くの嫌だし」
「わかった。じゃあ、えっと、そのうち元気になったら返すね」
「そのまま持ってて」
榛瑠は何でもないように、少しだるそうな声で言った。
「……うん、わかった」
一花は鍵をぎゅっと握りしめた。
0
お気に入りに追加
11
あなたにおすすめの小説
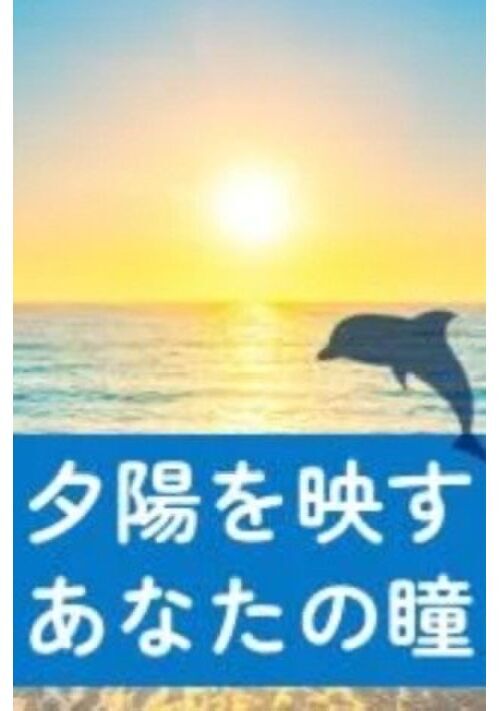
夕陽を映すあなたの瞳
葉月 まい
恋愛
恋愛に興味のないサバサバ女の 心
バリバリの商社マンで優等生タイプの 昴
そんな二人が、
高校の同窓会の幹事をすることに…
意思疎通は上手くいくのか?
ちゃんと幹事は出来るのか?
まさか、恋に発展なんて…
しないですよね?…あれ?
思わぬ二人の恋の行方は??
*✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻
高校の同窓会の幹事をすることになった
心と昴。
8年ぶりに再会し、準備を進めるうちに
いつしか二人は距離を縮めていく…。
高校時代は
決して交わることのなかった二人。
ぎこちなく、でも少しずつ
お互いを想い始め…
☆*:.。. 登場人物 .。.:*☆
久住 心 (26歳)… 水族館の飼育員
Kuzumi Kokoro
伊吹 昴 (26歳)… 海外を飛び回る商社マン
Ibuki Subaru

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


【取り下げ予定】愛されない妃ですので。
ごろごろみかん。
恋愛
王妃になんて、望んでなったわけではない。
国王夫妻のリュシアンとミレーゼの関係は冷えきっていた。
「僕はきみを愛していない」
はっきりそう告げた彼は、ミレーゼ以外の女性を抱き、愛を囁いた。
『お飾り王妃』の名を戴くミレーゼだが、ある日彼女は側妃たちの諍いに巻き込まれ、命を落としてしまう。
(ああ、私の人生ってなんだったんだろう──?)
そう思って人生に終止符を打ったミレーゼだったが、気がつくと結婚前に戻っていた。
しかも、別の人間になっている?
なぜか見知らぬ伯爵令嬢になってしまったミレーゼだが、彼女は決意する。新たな人生、今度はリュシアンに関わることなく、平凡で優しい幸せを掴もう、と。
*年齢制限を18→15に変更しました。

無彩色なキミに恋をして。
氷萌
恋愛
『お嬢様
私に何なりと御用命ください』
紺色のスーツを身に纏い
眉目秀麗で優しい笑顔を持ち合わせる彼は
日本有するハイジュエリーブランド
“Ripple crown”の代表取締役社長兼CEOであり
わたしの父の秘書・執事でもある。
真白 燈冴(28歳)
Togo Masiro
実は彼
仕事じゃ誰にでも優しく
澄んだ白い心を持つ王子のようなのに…
『何をご冗談を。
笑わせないでください。
俺が想っているのは緋奈星さま、貴女ただ1人。
なんなら、お望みとあれば
この気持ちをその体に刻んでも?』
漣 緋奈星(21歳)
Hinase Sazanami
わたしに向ける黒い笑顔は
なぜか“男”だ。

果たされなかった約束
家紋武範
恋愛
子爵家の次男と伯爵の妾の娘の恋。貴族の血筋と言えども不遇な二人は将来を誓い合う。
しかし、ヒロインの妹は伯爵の正妻の子であり、伯爵のご令嗣さま。その妹は優しき主人公に密かに心奪われており、結婚したいと思っていた。
このままでは結婚させられてしまうと主人公はヒロインに他領に逃げようと言うのだが、ヒロインは妹を裏切れないから妹と結婚して欲しいと身を引く。
怒った主人公は、この姉妹に復讐を誓うのであった。
※サディスティックな内容が含まれます。苦手なかたはご注意ください。

アルバートの屈辱
プラネットプラント
恋愛
妻の姉に恋をして妻を蔑ろにするアルバートとそんな夫を愛するのを諦めてしまった妻の話。
『詰んでる不憫系悪役令嬢はチャラ男騎士として生活しています』の10年ほど前の話ですが、ほぼ無関係なので単体で読めます。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















