35 / 62
第三章 死力を尽くして
初めてのイプシロン基地
しおりを挟む
定期便に飛び乗りフィフスへと戻ったミハルは、セントグラードターミナルステーションにあるシャトルライナー乗り場へ駆け込んでいた。
初めてのシャトルライナー。火星圏や地球圏方面は賑わっていたけれど、イプシロン基地方面は閑散としている。そこはまだ一般の利用者に解放されておらず、軍の関係者しかいないためだ。
程なく客車がホームに到着。物資の運搬も兼ねているために、客車が二両ある他は全てが貨物車両である。
ミハルは指定された座席を見つけ、カプセル状になった椅子へと座り込んだ。しばらくすると自動的にカプセルが閉じられ、機能説明や注意事項がモニターに流れていく。
「全てカプセル内で済ませるとか……。到着までこのままかぁ……」
一旦、発車すれば乗客はカプセルから出られない。約十二時間という旅程をカプセル内で過ごす必要があった。
不意に身体が浮き上がったような感覚がして、時を移さず背景が切り替わる。足下も頭上も背後でさえも星の海に埋め尽くされてしまう。
「まるで銀河に浮かんでるみたいね!」
徐に星たちが流れていく。どうやら出発したらしい。ミハルは表示を切り替えることなく、食い入るようにして星たちの煌めきを眺めていた。
「やっぱり宇宙って広いなぁ……」
端的な感想を述べたミハルだが、本当に感動している。リラックスしているのが理由かもしれないけれど、航宙機のコックピットから見る景色とは違って見えていた。意図せず与えられた銀河の旅をミハルは満喫しているようだ。
昼食を食べて少し居眠り。長く休みがもらえなかったからか、随分と疲れが溜まっていたらしい。ミハルは到着を知らせるアナウンスがあるまで熟睡してしまう。
『当機は間もなくイプシロン基地へと着港致します。お忘れ物がないか今一度……』
眠い目をこすりながら外の様子を見ると、そこに主星はなかった。ニュースで見た通りに、この宙域にあったはずの土星は跡形もなくなっていたのだ。
【認証 ミハル・エアハルト一等航宙士】
ギアをかざせばID認証は完了。直ぐさまゲートを飛び出す。ミハルは遂にイプシロン基地へと降り立っていた。
「やっと着いたね!」
想像よりも大きな基地だ。突貫工事で完成にこぎ着けたと聞いていたのに、一般的な居住ユニックよりも遥かに巨大である。
ターミナルには様々な方角への可動床があった。ミハルは司令室へと向かわねばならなかったのだが、行き先が大量に羅列してあったため探し出すのも一苦労である。
ミハルが落ち着きなくキョロキョロと立ち呆けていると、
「ミハル・エアハルト一等航宙士ですか?」
意外にも出迎えがあった。一等航宙士を迎える待遇とは違うような気もする。ミハルは敬礼して応え、彼の案内に従って司令室へと向かった。
応接室のような部屋に通され、しばしソファに腰を掛けるミハル。だが、数分と経たないうちに部屋の扉は開かれた。
「疲れているところすまないな……」
現れたのはクェンティン司令だ。写真で見るよりも厳つい。胸に並ぶ数々の勲章はそのまま彼の権力を示しているかのようだった。
「はい! ミハル・エアハルト一等航宙士です!」
即座に立ち上がって敬礼。それは訓練所で嫌というほど叩き込まれた所作である。少し緊張していたミハルだが、条件反射の如く身体に染みついた動作は緊張を和らげてもいた。
「ああ、結構。座ってくれたまえ……」
言ってクェンティンはソファの前にある机に配属先のデータを映した。
第三航宙戦団第一隊――そこはエース部隊と呼ばれている。ゲートの直前に陣取る第一航宙戦団と第二航宙戦団の所属航宙機が全て無人機であったから、有人機部隊としてのナンバリングは301小隊がトップだった。
「資料にある通り、301小隊はアイリス・マックイーン中尉が率いる部隊だ。しかし、先の戦いで負傷した彼女は三ヶ月以上も戦列を離れることになる。そこで白羽の矢が立ったのが君だ。セントラル基地での功績は既に確認済み。直ぐにでも戦えると評価してのことである」
召集された理由がクェンティンより語られた。ミハルの戦果は確認済みらしい。確かに数字だけを見ればルーキーが残したものとは思えなかっただろう。パイロットが三人しかいない基地では必然と撃墜数が多くなってしまうのだ。
「もしも君が無理だというのならいつでも言ってくれ。その場合の代替要員も考えてある。我々とて無駄死にを強いるつもりはない。ただし、早めに決断してもらわねば困る。また最初から無理だと思うのなら、この場で変更を願ってもらっても構わない」
クェンティンはそんな話を続けた。どうやら承認したはずの彼もルーキーが収まるべき場所だとは考えていないようだ。
「いえ、大丈夫です……」
ミハルは無理矢理に言葉を絞り出す。誘導するような話に抗うのは勇気がいった。だが、本心を欺くよりはずっと楽だ。アイリスの眼前を飛び、実力を見せつける機会は一年前からずっと抱いていた願望である。それを自ら放棄するなんて考えられなかった。
「この配置には感謝しています。私は大尉と約束していますし、決して最後まで泣き言を漏らしません。どうかこのままでお願いします……」
交代を促すようなクェンティンの言葉にミハルは毅然と返した。何の覚悟もないままシャトルに飛び乗った彼女だが、この場所へ辿り着く未来は常々考えていたことなのだ。
「なるほど、あの偏屈が推薦するだけはある……。柔い心では到底301小隊は務まらん。グレッグ大尉のお墨付きとはいえ、少し試させてもらった……」
クェンティンは書類を眺めながら話を進める。
これまでの展開から察するにミハルの出向には一悶着があった模様だ。様々な意見がぶつかり合う中で折り合ったのが、書類に記される内容なのだろう。
「ただ君は仮の隊員となる。技量的に問題があると判断された場合は後方部隊へと異動してもらう。もちろん君が隊員として認められたのなら異動はなしだ。その場合は301小隊で全力を尽くして欲しい」
「了解です……。実力主義であるのなら、私としても望むところです……」
またもへりくだることなく返答をする。心臓は鼓動を早めていたけれど、気持ちを強く持って本心のままに。
「ルーキーにしては堂々としているな? 私を前にしてここまで主張できる者はベテランパイロットにもそうはいない……」
クェンティンは感心しているようだ。一介のパイロットと話をする機会は多くなかったが、稀に機会を得たとしても凡そ相手はしどろもどろである。
「私は別に……。昇進とか考えていませんし……」
「ほう、ならば何を望む? 世界平和を願ったとしても、一介のパイロットにできることなどたかがしれているぞ?」
クェンティンが質問を続けた。昇進を望まない兵士が希望するものとは何かと。
対するミハルは躊躇っている。ここまでは意志のままに返答したけれど、本心を口にして良いのか分からなかった。何しろミハルの望みは兵士として適切じゃない。それが理由でエース部隊から外されてしまっては本末転倒である。
「アイリス・マックイーンに……勝ちたい……」
とても小さな声で返されていた。あわよくば聞こえないようにと。願望を伝えることに躊躇した結果、ミハルは独り言のように呟いている。
ところが、クェンティンにはしっかりと届いていた。二人しかいないこの部屋には何の雑音もなかったのだ。残念ながらミハルの希望は彼に聞かれてしまう。
「ふはは! なんだそれは!? 君の望みはそんなことか!?」
「そ、そんなことって何ですか!? 私はずっとそれを目標にして頑張っています!」
パイロットとしての目標を笑われてしまい、思わずミハルは声を大きくした。仮にも話し相手はイプシロン基地で一番の権力者であったというのに。
「いや、すまん! 私は君の目標を笑ったわけじゃない。一般的な戦闘機パイロットが望むものと、まるで違っていたから笑ってしまったのだ」
笑みを浮かべながら謝罪するクェンティン。寧ろ目標は良いと思えた。ありきたりな返答をされるより、よっぽど好感が持てる。更には勝ちたいと明確に伝えられる若者がどれほどいるだろうかと考えさせられてしまう。
「私こそ申し訳ありません。ついムキになってしまいました……」
言ってミハルは語り出す。アイリスと出会ってから今までのこと。この場所に辿り着くまでに費やした努力の全てを。
ミハルの話を聞き終わったあと、クェンティンは一拍おいて表情を引き締めた。浮かべた笑みは失われ、いよいよ本題に入るのだとミハルに予感させている。
「ミハル君の実力は映像で確認済みだ。また君を推すパイロットはいずれも人類を代表するパイロットである。平時であれば何の問題もなかっただろう……」
クェンティンはシガーカッターに葉巻を差し込む。話途中であったけれど、彼は葉巻をくゆらせ始めた。
「だが、太陽系は危機に瀕している。次の戦闘は必ず勝利せねばならん。だから我々は慎重になっているのだ。若すぎるミハル君に最前線が務まるのかどうかを……」
微かに鼻腔をくすぐる匂いがミハルにも届いていた。
それは考えさせられる話だ。懸念される若さ。ミハルは配備されてから半年も経たないルーキーである。皆が懐疑的になる理由は判然としていた。
「周囲が不安に思われることは承知しています。仮に私のフライトが不適格だと思われたならば、いつでも変更してください。けれど、私は異動を申しつけられるその時まで、301小隊で戦いたい。努力を続けた過去に私は嘘をつきたくありませんから……」
しばし目線を合わせるクェンティン。彼女の評価や木星での実績。ケチを付けるところは本当に年齢しかなかった。会話による確認もそれを肯定するだけだ。
「本来は話すべきではないと考えていたのだが、君があまりに堂々としているものだから敢えて伝えさせてもらった。頑張りますという返答は欲していない。我々が望むものは戦果のみである。期待していいのだな?」
最終的な意思確認が取られた。ミハルの返答は無論のこと決まっている。
「もちろんです。アイリス中尉が驚くほどの戦果。私はそれを求めています……」
彼女の意志が固いことをクェンティンは返答に見ている。
思えばこの面談は気が進まないものだった。ミハルが異動を申し出るというありきたりな展開を予想していたのだ。しかし、思いのほか楽しめている。予想を超えた返答を続けるルーキーに魅せられていた。
「いいだろう。ならばミハル君は301小隊で頑張ってくれ。無理を押し付けた侘びは考えている。仮に戦闘があり、君が無事に生還したとすればそれなりの対応をさせてもらう。それこそグレッグ大尉が話す未来のエースに相応しいものをな……」
元より辞退を強要するつもりはなかった。ミハルの覚悟が本物であり、戦う決意があるのであればクェンティンはそれで良かったのだ。実力に関しては現場の判断。今ここでやる気をそぐような話は予定されていない。
「今日はゆっくり休んでくれたまえ。301小隊に顔を出すのは明日で良い……」
クェンティンはミハルの退出を促した。
スクッと立ち上がり礼をするミハル。少しぎこちない歩き方をしながら扉を開き、もう一度、振り返っては再び敬礼してみせた。
あどけなさが残る容姿。だが、それに比例しない意志の強さ。見かけ通りのパイロットでないことだけはよく分かった。願わくば映像に見たような活躍をクェンティンは望んでいる。人類の危機を救うだけの戦果を上げてくれることを……。
初めてのシャトルライナー。火星圏や地球圏方面は賑わっていたけれど、イプシロン基地方面は閑散としている。そこはまだ一般の利用者に解放されておらず、軍の関係者しかいないためだ。
程なく客車がホームに到着。物資の運搬も兼ねているために、客車が二両ある他は全てが貨物車両である。
ミハルは指定された座席を見つけ、カプセル状になった椅子へと座り込んだ。しばらくすると自動的にカプセルが閉じられ、機能説明や注意事項がモニターに流れていく。
「全てカプセル内で済ませるとか……。到着までこのままかぁ……」
一旦、発車すれば乗客はカプセルから出られない。約十二時間という旅程をカプセル内で過ごす必要があった。
不意に身体が浮き上がったような感覚がして、時を移さず背景が切り替わる。足下も頭上も背後でさえも星の海に埋め尽くされてしまう。
「まるで銀河に浮かんでるみたいね!」
徐に星たちが流れていく。どうやら出発したらしい。ミハルは表示を切り替えることなく、食い入るようにして星たちの煌めきを眺めていた。
「やっぱり宇宙って広いなぁ……」
端的な感想を述べたミハルだが、本当に感動している。リラックスしているのが理由かもしれないけれど、航宙機のコックピットから見る景色とは違って見えていた。意図せず与えられた銀河の旅をミハルは満喫しているようだ。
昼食を食べて少し居眠り。長く休みがもらえなかったからか、随分と疲れが溜まっていたらしい。ミハルは到着を知らせるアナウンスがあるまで熟睡してしまう。
『当機は間もなくイプシロン基地へと着港致します。お忘れ物がないか今一度……』
眠い目をこすりながら外の様子を見ると、そこに主星はなかった。ニュースで見た通りに、この宙域にあったはずの土星は跡形もなくなっていたのだ。
【認証 ミハル・エアハルト一等航宙士】
ギアをかざせばID認証は完了。直ぐさまゲートを飛び出す。ミハルは遂にイプシロン基地へと降り立っていた。
「やっと着いたね!」
想像よりも大きな基地だ。突貫工事で完成にこぎ着けたと聞いていたのに、一般的な居住ユニックよりも遥かに巨大である。
ターミナルには様々な方角への可動床があった。ミハルは司令室へと向かわねばならなかったのだが、行き先が大量に羅列してあったため探し出すのも一苦労である。
ミハルが落ち着きなくキョロキョロと立ち呆けていると、
「ミハル・エアハルト一等航宙士ですか?」
意外にも出迎えがあった。一等航宙士を迎える待遇とは違うような気もする。ミハルは敬礼して応え、彼の案内に従って司令室へと向かった。
応接室のような部屋に通され、しばしソファに腰を掛けるミハル。だが、数分と経たないうちに部屋の扉は開かれた。
「疲れているところすまないな……」
現れたのはクェンティン司令だ。写真で見るよりも厳つい。胸に並ぶ数々の勲章はそのまま彼の権力を示しているかのようだった。
「はい! ミハル・エアハルト一等航宙士です!」
即座に立ち上がって敬礼。それは訓練所で嫌というほど叩き込まれた所作である。少し緊張していたミハルだが、条件反射の如く身体に染みついた動作は緊張を和らげてもいた。
「ああ、結構。座ってくれたまえ……」
言ってクェンティンはソファの前にある机に配属先のデータを映した。
第三航宙戦団第一隊――そこはエース部隊と呼ばれている。ゲートの直前に陣取る第一航宙戦団と第二航宙戦団の所属航宙機が全て無人機であったから、有人機部隊としてのナンバリングは301小隊がトップだった。
「資料にある通り、301小隊はアイリス・マックイーン中尉が率いる部隊だ。しかし、先の戦いで負傷した彼女は三ヶ月以上も戦列を離れることになる。そこで白羽の矢が立ったのが君だ。セントラル基地での功績は既に確認済み。直ぐにでも戦えると評価してのことである」
召集された理由がクェンティンより語られた。ミハルの戦果は確認済みらしい。確かに数字だけを見ればルーキーが残したものとは思えなかっただろう。パイロットが三人しかいない基地では必然と撃墜数が多くなってしまうのだ。
「もしも君が無理だというのならいつでも言ってくれ。その場合の代替要員も考えてある。我々とて無駄死にを強いるつもりはない。ただし、早めに決断してもらわねば困る。また最初から無理だと思うのなら、この場で変更を願ってもらっても構わない」
クェンティンはそんな話を続けた。どうやら承認したはずの彼もルーキーが収まるべき場所だとは考えていないようだ。
「いえ、大丈夫です……」
ミハルは無理矢理に言葉を絞り出す。誘導するような話に抗うのは勇気がいった。だが、本心を欺くよりはずっと楽だ。アイリスの眼前を飛び、実力を見せつける機会は一年前からずっと抱いていた願望である。それを自ら放棄するなんて考えられなかった。
「この配置には感謝しています。私は大尉と約束していますし、決して最後まで泣き言を漏らしません。どうかこのままでお願いします……」
交代を促すようなクェンティンの言葉にミハルは毅然と返した。何の覚悟もないままシャトルに飛び乗った彼女だが、この場所へ辿り着く未来は常々考えていたことなのだ。
「なるほど、あの偏屈が推薦するだけはある……。柔い心では到底301小隊は務まらん。グレッグ大尉のお墨付きとはいえ、少し試させてもらった……」
クェンティンは書類を眺めながら話を進める。
これまでの展開から察するにミハルの出向には一悶着があった模様だ。様々な意見がぶつかり合う中で折り合ったのが、書類に記される内容なのだろう。
「ただ君は仮の隊員となる。技量的に問題があると判断された場合は後方部隊へと異動してもらう。もちろん君が隊員として認められたのなら異動はなしだ。その場合は301小隊で全力を尽くして欲しい」
「了解です……。実力主義であるのなら、私としても望むところです……」
またもへりくだることなく返答をする。心臓は鼓動を早めていたけれど、気持ちを強く持って本心のままに。
「ルーキーにしては堂々としているな? 私を前にしてここまで主張できる者はベテランパイロットにもそうはいない……」
クェンティンは感心しているようだ。一介のパイロットと話をする機会は多くなかったが、稀に機会を得たとしても凡そ相手はしどろもどろである。
「私は別に……。昇進とか考えていませんし……」
「ほう、ならば何を望む? 世界平和を願ったとしても、一介のパイロットにできることなどたかがしれているぞ?」
クェンティンが質問を続けた。昇進を望まない兵士が希望するものとは何かと。
対するミハルは躊躇っている。ここまでは意志のままに返答したけれど、本心を口にして良いのか分からなかった。何しろミハルの望みは兵士として適切じゃない。それが理由でエース部隊から外されてしまっては本末転倒である。
「アイリス・マックイーンに……勝ちたい……」
とても小さな声で返されていた。あわよくば聞こえないようにと。願望を伝えることに躊躇した結果、ミハルは独り言のように呟いている。
ところが、クェンティンにはしっかりと届いていた。二人しかいないこの部屋には何の雑音もなかったのだ。残念ながらミハルの希望は彼に聞かれてしまう。
「ふはは! なんだそれは!? 君の望みはそんなことか!?」
「そ、そんなことって何ですか!? 私はずっとそれを目標にして頑張っています!」
パイロットとしての目標を笑われてしまい、思わずミハルは声を大きくした。仮にも話し相手はイプシロン基地で一番の権力者であったというのに。
「いや、すまん! 私は君の目標を笑ったわけじゃない。一般的な戦闘機パイロットが望むものと、まるで違っていたから笑ってしまったのだ」
笑みを浮かべながら謝罪するクェンティン。寧ろ目標は良いと思えた。ありきたりな返答をされるより、よっぽど好感が持てる。更には勝ちたいと明確に伝えられる若者がどれほどいるだろうかと考えさせられてしまう。
「私こそ申し訳ありません。ついムキになってしまいました……」
言ってミハルは語り出す。アイリスと出会ってから今までのこと。この場所に辿り着くまでに費やした努力の全てを。
ミハルの話を聞き終わったあと、クェンティンは一拍おいて表情を引き締めた。浮かべた笑みは失われ、いよいよ本題に入るのだとミハルに予感させている。
「ミハル君の実力は映像で確認済みだ。また君を推すパイロットはいずれも人類を代表するパイロットである。平時であれば何の問題もなかっただろう……」
クェンティンはシガーカッターに葉巻を差し込む。話途中であったけれど、彼は葉巻をくゆらせ始めた。
「だが、太陽系は危機に瀕している。次の戦闘は必ず勝利せねばならん。だから我々は慎重になっているのだ。若すぎるミハル君に最前線が務まるのかどうかを……」
微かに鼻腔をくすぐる匂いがミハルにも届いていた。
それは考えさせられる話だ。懸念される若さ。ミハルは配備されてから半年も経たないルーキーである。皆が懐疑的になる理由は判然としていた。
「周囲が不安に思われることは承知しています。仮に私のフライトが不適格だと思われたならば、いつでも変更してください。けれど、私は異動を申しつけられるその時まで、301小隊で戦いたい。努力を続けた過去に私は嘘をつきたくありませんから……」
しばし目線を合わせるクェンティン。彼女の評価や木星での実績。ケチを付けるところは本当に年齢しかなかった。会話による確認もそれを肯定するだけだ。
「本来は話すべきではないと考えていたのだが、君があまりに堂々としているものだから敢えて伝えさせてもらった。頑張りますという返答は欲していない。我々が望むものは戦果のみである。期待していいのだな?」
最終的な意思確認が取られた。ミハルの返答は無論のこと決まっている。
「もちろんです。アイリス中尉が驚くほどの戦果。私はそれを求めています……」
彼女の意志が固いことをクェンティンは返答に見ている。
思えばこの面談は気が進まないものだった。ミハルが異動を申し出るというありきたりな展開を予想していたのだ。しかし、思いのほか楽しめている。予想を超えた返答を続けるルーキーに魅せられていた。
「いいだろう。ならばミハル君は301小隊で頑張ってくれ。無理を押し付けた侘びは考えている。仮に戦闘があり、君が無事に生還したとすればそれなりの対応をさせてもらう。それこそグレッグ大尉が話す未来のエースに相応しいものをな……」
元より辞退を強要するつもりはなかった。ミハルの覚悟が本物であり、戦う決意があるのであればクェンティンはそれで良かったのだ。実力に関しては現場の判断。今ここでやる気をそぐような話は予定されていない。
「今日はゆっくり休んでくれたまえ。301小隊に顔を出すのは明日で良い……」
クェンティンはミハルの退出を促した。
スクッと立ち上がり礼をするミハル。少しぎこちない歩き方をしながら扉を開き、もう一度、振り返っては再び敬礼してみせた。
あどけなさが残る容姿。だが、それに比例しない意志の強さ。見かけ通りのパイロットでないことだけはよく分かった。願わくば映像に見たような活躍をクェンティンは望んでいる。人類の危機を救うだけの戦果を上げてくれることを……。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

保健室の秘密...
とんすけ
大衆娯楽
僕のクラスには、保健室に登校している「吉田さん」という女の子がいた。
吉田さんは目が大きくてとても可愛らしく、いつも艶々な髪をなびかせていた。
吉田さんはクラスにあまりなじめておらず、朝のHRが終わると帰りの時間まで保健室で過ごしていた。
僕は吉田さんと話したことはなかったけれど、大人っぽさと綺麗な容姿を持つ吉田さんに密かに惹かれていた。
そんな吉田さんには、ある噂があった。
「授業中に保健室に行けば、性処理をしてくれる子がいる」
それが吉田さんだと、男子の間で噂になっていた。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

【完結】幼馴染にフラれて異世界ハーレム風呂で優しく癒されてますが、好感度アップに未練タラタラなのが役立ってるとは気付かず、世界を救いました。
三矢さくら
ファンタジー
【本編完結】⭐︎気分どん底スタート、あとはアガるだけの異世界純情ハーレム&バトルファンタジー⭐︎
長年思い続けた幼馴染にフラれたショックで目の前が全部真っ白になったと思ったら、これ異世界召喚ですか!?
しかも、フラれたばかりのダダ凹みなのに、まさかのハーレム展開。まったくそんな気分じゃないのに、それが『シキタリ』と言われては断りにくい。毎日混浴ですか。そうですか。赤面しますよ。
ただ、召喚されたお城は、落城寸前の風前の灯火。伝説の『マレビト』として召喚された俺、百海勇吾(18)は、城主代行を任されて、城に襲い掛かる謎のバケモノたちに立ち向かうことに。
といっても、発現するらしいチートは使えないし、お城に唯一いた呪術師の第4王女様は召喚の呪術の影響で、眠りっ放し。
とにかく、俺を取り囲んでる女子たちと、お城の皆さんの気持ちをまとめて闘うしかない!
フラれたばかりで、そんな気分じゃないんだけどなぁ!



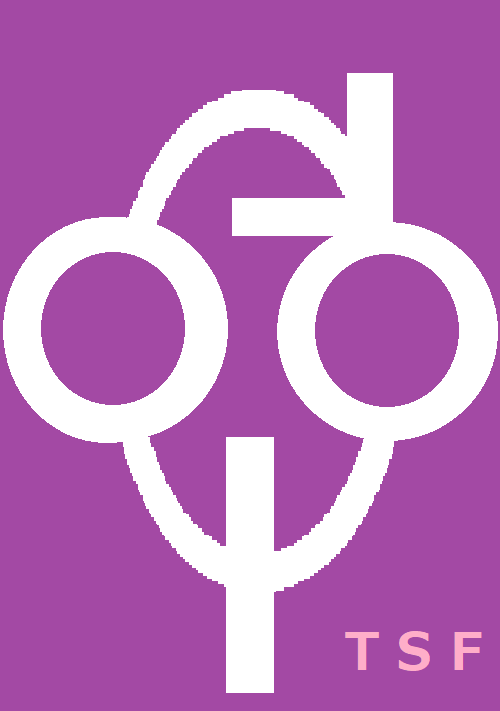
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















