10 / 10
合コンの夜
俺はゲイじゃない
しおりを挟む
「灘。本当に大丈夫かよ?」
「ああ。大丈夫だって。じゃあな」
俺は心配そうな目を向ける友達に手を振って、歩き出した。
かれこれ何日連続で飲んでるかわからない。
でも朝は車で来たいから代行運転を頼んで帰っている。
ふらつく足取り。
さすがに飲みすぎたかな。
俺はベンチに腰掛け、空を見上げる。
雲がない。でも夜空には星は見えない。
街の光が強すぎからだ。
腕時計を見るとまだ11時前だ。
「はあ。なんで早く帰っちゃうんだよ。みんな」
早く帰るとそれだけ一人でいる時間が増えてしまう。だから、遅くまで外で飲むようにしていた。
「ああ、でも今日は結構飲んだから、家に帰ったら直ぐ眠れるかも」
本当に飲みすぎた。頭が体から分離してるみたいに、ふわふわしてる。
「!」
ふいに、吐き気がこみ上げてきた。
反射的に口に手をやってしまい、後悔した。
「うえっつ」
吐瀉物が押さえた手からはみ出し、ベンチを汚す。
やばい。俺何やってんだよ。
ポケットをまさぐり、ハンカチを探すがない。
鞄なんか面倒だから車に置いて来たし。
「はい」
聞き覚えのある声、同時に差し出されたのはテッシュペーパーだった。
「……忠史」
忠史は眉を苦しそうに寄せ、俺を見ていた。
「使ってください」
「ありがとう」
気色悪いと思って別れた。
でも俺は意外に素直にそうお礼を言っていた。
「車まで送ります」
「……必要ないから」
「怖いんですか?」
忠史は少し様子がおかしかった。ちょっと痩せたようにも見える。
俺のせいか……。
俺が逃げたから。
でも、俺は、俺は無理だ。
勇みたいにはなれない。
いや、忠史が王さんみたいに女性のようだったら、大丈夫なのか?
何度かは考えことがある。
でも忠史は立派な男だ。俺なんかより体格がいいし、男らしい。
「灘さん?」
腰を落として俺を見る。
異様に距離が近くになったみたいで、俺は逃げるように立った。
「大丈夫だから。テッシュありがとうな」
またな、とは言えなかった。
会うつもりはない。
あの時木崎の奴が、忠史が俺のことを好きだと言っていた。
忠史もそれを否定しなかった。
そう。だから、もう会わない。
俺は、忠史をそういう風には思えない。
少し歩いて、後ろを振り向いた。
だが、忠史はそこにはいなくて……。
そのことで少し胸が痛かった。
それが嫌で、俺は息を吐くと、歩くスピードを上げた。
俺は、忠史を好きじゃない。
そういう意味で好きじゃないんだ。
あれから、忠史のことを毛嫌いすると思っていた。
でもそんなことはなくて、嫌になるほど思い出した。
それはまるで、俺が、奴に好意をもっているみたいで……。
深く考えるのが嫌で、俺はますます一人になることを避けた。
だから毎晩友達が集まる場所に出かけて飲んだ。
「お客さん、吐いちゃったんですか?」
「すみません。窓開けて運転してください」
雪は降ってない。少しくらい窓を開けてもいいだろう。
俺は代行運転手に答え、後部座席に深く座った。
彼がそれから話しかけることはなかった。
無言の車内。嫌でもさっき街で会った忠史のことを思い出して、俺は用もないのに運転手に話しかけた。
「なんか飲みすぎちゃったみたいで。すみません。匂いきついですか?」
「え、あ、大丈夫ですよ」
客商売だ。素直に同意できないんだろう。
「すみません。直ぐ付きますから。あ、そこ右に回って下さい」
アパートの駐車場に車を停めてもらい、金を払った。ここ数日間でかなりの金を使ってる。ばあちゃんが残してくれた遺産があるから全然痛くはないけど、俺にしてはちょっと使いすぎだ。
でも止められない。
一人になりたくない。
余計なことを考えたくない。
前から一人になるのはいやだったけど、ますます酷くなっていた。
アパートの部屋に入り、先ずは暖房を入れた。それから、シャワーを浴びる。汚れた服を手洗いし、脱水させるために洗濯機にいれた。
音がないといやだからテレビの音をつける。
脱水終わったら干さないと……。
そう思い、ソファーに座った。眠気が訪れ、うたた寝をする。何度もがくんと首がうな垂れ、寝ていたんだと気がついた。
それを繰り返してるうちに体は疲れたらしい。俺はいつの間にかソファーに横になり寝てしまった。
「信雪。いい子にしてるんだよ」
「夕飯は信雪の好きなグラタンだからね」
保育園に俺を送り二人はそのまま帰ってこなかった。
「信雪くん」
先生が泣きそうな顔で俺の手を握ってくれたのを覚えてる。
「信雪くん。どうしてそんなことするのかな」
俺と同じ目線で、話を聞いてくれたえみこさん。彼女が色々教えてくれた。
「大丈夫だよ。俺はもうガキじゃないんだから」
付き合っていた彼と結婚するために、えみこさんは仕事を辞めないといけなくなった。最後の最後まで、彼女は心配そうだった。
真っ暗な家。一人暮らしには勿体ない家にばあちゃんは住んでいた。
ばあちゃんの葬式の夜、俺は一人で家に取り残された。
もう成人していて、怖いなんて言えなかった。
家は静まり返っていた。
テレビが嫌いだったばあちゃんの家には、音を出すものがなかった。
「灘さん」
「忠史?」
夢。これは夢のはず。
でも夢の中に忠史がいた。暗い家の中、何故か奴の姿が眩しい。
「俺がいます。だから安心してください」
奴はにこりと微笑むと俺を抱きしめた。
暖かい。奴の体は暖かかった。
「は、放せ!」
温もりに安らぎを覚えた。
でも俺は、
けたたましい音で起こされた。
夢か。
「嫌な、嫌な夢だ」
わざと言葉に出して、あの安らぎを忘れようとする。
「!」
普段なら不快に感じない俺の着信音が、その存在を誇示するように耳に触る。
「うるさいなあ」
昨日はソファーに横になって寝たらしい。
暖房のお陰で寒さは感じなくてラッキーだった。
「誰だよ。全く」
時間間隔がない俺は半ば切れぎみに電話を取った。
「もしもし?」
「灘。お前、まさか今起きた?」
「あ?」
電話を掛けてきたのは同僚のイケメン町田だ。
「うん」
「今何時か知ってる?」
その言葉ヒヤリと寒気がする。
「10時。10時だよ。お前9時にケイラの実田さんと約束してただろ?取り敢えず俺が対応したけど。もしかして飲み過ぎか?」
図星だった。だが、妙な対抗意識が出てきてしまい「熱があるみたいだから。今日は病欠扱い頼む」
そんな風に答えてしまった。
「……ああ、わかったよ」
半信半疑だったが町田はそう答え、お大事にと電話を切った。
10時、窓から差し込む光は確かに朝のそれだ。
「勇に悪いことしたな」
俺がそう思っていると携帯電話が鳴った。
画面に表示された名前に俺は笑う。
以心伝心かよ。
電話してきたのは勇だった。
「悪いな。王さん大丈夫か?」
「うん。それよりお前顔色悪いけど?」
その夜、俺は勇と飲むことにした。
電話してきた勇は町田から病気だと聞いていたようで心配していた。
確かに単に休んでると、いうよりも病気と言った方がずっと対応はいいから町田の言葉は「間違っていない」
でも勇に余計な心配させてくれるなよ、とちょっとだけ町田に文句を言いたくなった。
電話口で元気そうな俺の様子に安心していた勇だったが、なんとなく久々に二人で話したくなって、彼を飲みに誘ってしまった。
ああ見えて独占欲の強い恋人の王さんが許可するのかと思っていたが、勇は快く誘いに乗ってくれた。
「顔色?悪いか?」
「うん。今日は飲むのは止めた方がいいかも」
「……いや、飲む」
「……少しだけにしろよ」
言い張る俺に勇は苦笑する。
「で、王さんとの生活はどうなんだ?楽しいか?」
「うん」
小さく頷く勇は「可愛い」感じだった。
男が乙女してるんじゃねーと思ったが、元からこいつは「可愛い」に定評があったと思い返す。
そういや、忠史。先輩の勇に対してはどうだったんだろう。
ゲイの奴としては「可愛い」勇に対してそのなんか、恋愛感情を持たなかったのかな。
なんで、俺はそんなこと考えてるんだ。
どうでもいいだろう。忠史のことなんて。
「灘はどう?最近、紀原くんと飲んでないみたいだけど。彼女でもできた?」
「……ああ」
嘘をついた。
俺が忠史と何かあったなんて、知られたくなかった。
「そう。よかった。ちょっと心配してたんだ」
「心配?」
俺が聞き返すと勇は、顔を曇らす。
「実はさ。紀原くんがお前に手を出すんじゃないかと心配だったんだ。手が早いから彼は」
「手が早い?!」
意味深な言葉に俺は聞き返してしまった。
「……えっと、忘れてくれ」
「お前、もしかして忠史になんかされた?」
「……言いたくない。あれはもう忘れたい過去。俺も、紀原くんもそうだと思うよ」
「……そっか」
俺はその時自分がどんな顔をしていたのか、わからない。
胸が押しつぶされ、呼吸が苦しくなった。
「ちょっとトイレいってくる」
だからトイレに逃げた。気持ちを落ち着けたかった。
鏡に映る自分の顔。
勇の言う通りに酷い顔だった。目の下に隈みたいのができてる。
目が充血してて、真っ赤だ。
……忠史と勇の間に何かあったのか。
忘れたい過去ってなんなんだろう?
もやもやとはっきりしない思い。
蛇口を捻り冷たい水で顔を洗う。すっきりすると思ったけど、気持ちは変わらないままだった。
「灘。もう帰ろうか?」
席に戻ったとたん、勇がそんなことを言いだした。
「え?まだ10時だせ」
「お前、本当に大丈夫か?」
「うん。一人になるのが嫌なんだよ」
「……そっか」
彼女がいるのに、一人になるのがいや。
でも勇は聞き返すことはなかった。
「灘。車まで送るよ。っていうか今日はタクシーのほうがいいじゃないか?」
「ううん。代行で帰る。送ってもらう必要はないから」
「必要ないって、どこかだよ。足元ふらふらだぞ?」
勇は俺の腕を支えるように掴んだ。
「必要ない!」
俺はなぜかイライラして、腕を振り払う。
「灘?怒ってる?何か俺……したか?」
勇はその大きい瞳を曇らせて、心配げだ。
本当に「可愛い」表情だ。
だから……
「な、なんでもない。俺、本当に大丈夫だから」
「灘。よくわからないけど、大丈夫だと思えない。お前がしっかり車に乗るのを確認するまで付いていくからな」
勇はやっぱりいい奴だな。
結局俺は勇と一緒に会社近くの駐車場まで歩くことになった。
「あれ?紀原くん?」
しばらく歩き、勇が驚いた声をあげた。
忠史?
まさかと思って勇が見ている方向に目を向ける。
昨日俺が座っていたベンチに忠史の姿が見えた。
奴は俺達に気がつくと、ぎょっとして立ち上がり、逃げるように立ち去る。
「紀原くん?おっかしいな。なんで逃げるんだ?明日、聞いてみよう。人違いなわけないし」
俺は勇がそうぼやくのをただ黙って聞いていた。
★
それからも俺は毎晩飲むのをやめなかった。駐車場近くのベンチを通るたびに、忠史を思い出す。いないのか、と落胆する自分がいて、余計嫌な気持ちになった。
そうして2週間がすぎ、俺は再び忠史と会うことになる。
勇が中国に旅行に行ってるため、会わなければならなくなった。
メールで都合を聞かれ、午後3時にミーティングを設定した。
午後3時ちょうどに内線が鳴り、俺は受話器を取った。
「もしもし。すずた製作所の灘です」
「……ケイラの紀原です」
一呼吸空いた後、忠志がそう答えた。
彼の声を久々に聞き、言葉が詰まる。
しかし息を吐き、落ち着かせるとエントランスのドアを開ける操作をする。
「ドアを開けたから、入ってきて」
電話を切り、俺は彼を迎えるために、受付に向かった。
人件費をできるだけ抑える意味で、俺の会社には受付はいない。
がらんとした空間に忠史が立っていた。
「……忠史。奥に応接室がある。そこで話をしよう。ついてきて」
お客さんと打合せする際は、応接室を使うのが常だ。
午後3時に使うとすでに予約は取っておいた。
応接室は部屋の一番奥だ。パテションで区切られたテーブルを数台通り過ぎながら、俺は女子社員が忠志の姿を見て息を飲むのが分かる。
そうだよな。奴はそこらへんにはなかなかいないイケメンだ。背も高いし。
そんな視線を掻い潜り、応接室に辿りつく。
「どうぞ」
俺はドアを開け、忠史に中に入るように促す。
彼は頷くと中に入った。
窓がなく、机と椅子しかない応接室は、本当なら狭いはずだった。だけど使用してるのは俺達二人だけのためか、妙に広く感じた。
忠史はノート型パソコンをテーブルに置き、俺を見ようともしなかった。
「……お茶とコーヒーどっちがいい?」
俺の会社にはお茶くみ係は存在しない。客をもてなすのは担当者自身の仕事だった。
「すみません。コーヒーいただけますか?」
奴は俯いたままそう答える。
俺は奴の答えに席を離れる口実ができたと、胸を撫で下ろす。
「ちょっと入れてくる」
二人でいると息がつまりそうだった。
応接室から逃げるように出た俺は、真っすぐ給湯室に向かった。
勇が休暇から戻ってきてから遅すぎるため、忠史と会うことになった。この時ばかりは忠史が仕事の取引先であることを恨んだ。
「灘。紀原くんだっけ。めちゃくちゃイケメンだな。なんか、悔しい」
廊下ですれ違った町田がアホみたいなこという。
悔しいって。まあ、普段は会社の女の子の視線を一身に受けてるから、忠史みたいなイケメンがくると持っていかれる感じか。
「……妙な色気があるよな。彼」
答えない俺に町田は笑いながら言葉を続ける。
「色気?なんだよ。それ」
給湯室まで付いてくる奴を鬱陶しく思いながら、俺はインスタントのコーヒーを入れる。砂糖とミルクの小さな袋と、コーヒーの入ったカップを盆に置いて、俺は町田の傍を通り過ぎようとした。
「感じないのか?なんか、つらそうだよ。彼」
「……」
町田が俺の心を見透かすように見つめる。
「まあ、灘もつらそうだな」
「ふざけんな」
町田とは付き合いは浅い。何か知ってるような含みを持ったいい方に俺は頭にきた。
「木崎と俺トモダチなんだよ。だから、知ってる。でも俺は木崎みたいに下品じゃないし。餓えてないから」
「!」
俺は驚きのあまり盆を落とすところだった。
それを支えたのは町田だった。
「危ないなあ。そういうところが灘の可愛いところだよな」
「!」
俺は「可愛い」と言う言葉に寒気を覚える。
「俺もバイなんだ。残念ながら。灘。素直になれば?好きなものは好きだし。男でも女でも関係ないだろ?」
「……うるさい。お前には関係ない」
町田がバイであることに驚いたが、それ以上に奴の言葉に頭にきた。
「本当。頭が固いな。まあ、どう選択するかは個人の自由だから。いいけど」
奴は気がすんだのか、そう言い終ると「じゃあな」と給湯室を後にした。
「はい。コーヒー」
結局コーヒーを作り直し、俺は応接室に戻った。
「ありがとうございます」
忠史は、パソコンの画面だけを見て俺に答える。
それから製品の説明や問題点などを話し合ったが、奴が俺を見ることがなかった。
「他に何か質問はありますか?」
ある程度説明し終わり、奴はこの打合せを締めるためにそう尋ねる。
「……忠史」
傍にいるのに、遠くに奴の存在を感じて寂しさを感じる。だから、俺は振り向いて欲しくてその腕を掴んだ。
びくっと震えた。
「触らないでください」
「……前みたいに友達に戻れないのか?」
気がつくと俺はそう聞いていた。
「もう、彼女ができたんですよね。俺なんかと会わなくて寂しくないですよね?」
勇についた嘘は忠史に伝わっていた。彼女なんかいない。嘘だと答えるか迷う。
無性に寂しかった。
友達と会っても思い出すのは忠史と飲んだこと。
前みたいに会うことは無理なのか。俺の我儘なのか。
言葉を発しない俺に、忠史は微笑む。
諦めた、そんな笑みだ。
「彼女とお幸せに」
パソコンを閉じ、広げた書類をまとめると鞄に仕舞い込む。
「もう、会うことはないと思います。何かを問題があればメールでお聞きします。失礼致します」
すっと立ち上がり、忠史は頭を下げると背を向けた。
また俺は一人になる。
一人ぼっちだ。
「行かないでくれ」
えみこさんに本当に言いたかった言葉。あの時は強がって言えなかった。
でも今度は勇気を出した。
忠史に側にいてほしい。
一緒に飲んだり何処かに行きたかった。
「な、灘さん」
振り向いた忠史は驚いた顔をしていた。
「な、泣かないでください」
「え、俺っ」
頬を触ると水滴が指を濡らした。
泣くつもりなどなく、見られたことが恥ずかしくて俺は片手で顔を覆う。
もう一つの手でポケットに入っているはずのハンカチを探した。
「どうぞ」
ポケットをまさぐっていると、白いハンカチが差し出される。見上げると、優しい笑みを浮かべた忠史がいた。
「使って下さい」
「……ありがとう」
なんてカッコ悪いんだ。俺。
羞恥心でいっぱいになりながらも、忠史が以前のように優しいのが嬉しかった。
「そんな風に呼びとめられて、しかも泣かれるとすごい困ります。彼女もいるのに、なんで」
「彼女は、いない」
嘘をついてもしょうがない。俺はハンカチで涙をぬぐい、忠史に目を向ける。
目を丸くした奴は俺を見つめ返していた。
「勇には嘘をついたんだ。なんかお前ともめてるのが、ばれたくなくて……」
「そうなんですか」
忠史はほっとしたように息を吐く。
「……俺はゲイじゃない。でも、お前と……前みたいに一緒に過ごしたんいんだ。我儘か?」
「……我儘ですね。俺がどれだけ我慢してると思ってるんですか」
「が、我慢?!」
「俺はあなたが好きだから。キスしたり、抱きしめたりしたんです」
「!」
すうっと真剣な瞳を向けられ、俺の心臓が跳ねた。
え、っていうか、俺乙女モード入ってる……。
いや、俺は、俺はゲイじゃないんだ!
「……でも我慢します。泣かれると困るし」
「な、泣かれると困る?!なんだよ、それ!」
「泣いてましたよね。さっき」
「……」
泣くつもりなんかなかった。でも泣いたのは事実で俺は言い返せなくて黙ってしまう。くそっつ、忠史のペースに飲まれてる気がする。
「灘さん、これからも宜しくお願いします」
あでやかな笑みを浮かべた忠史は仕切り直すように、俺に手を差し出した。
「ああ、よろしく」
俺は自然に手を握り返す。
「?!」
急に手をひかれ、バランスがとれなくなった。気が付いたら俺は忠史の腕の中にいた。
「忠史!」
「仲直りの印です」
動揺する俺に構わず、奴は俺を強く抱きしめる。
「離せよ!俺は、普通の友達のつもりなんだからな」
「はいはい。そうですね」
数秒後、満足したのか、奴はあっさりと俺を解放した。
忠史の温もりが心地よかった。
でもそんなこと死んでも言えるわけがない。
俺はゲイじゃないんだから。
「じゃ、灘さん。また電話します」
そうして彼は軽やかに応接室を出て行った。
じわりと、胸の中に広がっていく暖かい気持ち。触れ合った個所はまだ熱をもっているみたいで、ぽかぽかしていた。
……俺はゲイじゃない。
忠史は俺の大事な友達。
それだけだ。
俺は自分に言い聞かせるように心の中で呟くと、コーヒーカップを片付ける。
孤独でいっぱいだった俺の心、でも今は太陽に照らされたみたいに暖かさに満ち溢れていた。
(完)
「ああ。大丈夫だって。じゃあな」
俺は心配そうな目を向ける友達に手を振って、歩き出した。
かれこれ何日連続で飲んでるかわからない。
でも朝は車で来たいから代行運転を頼んで帰っている。
ふらつく足取り。
さすがに飲みすぎたかな。
俺はベンチに腰掛け、空を見上げる。
雲がない。でも夜空には星は見えない。
街の光が強すぎからだ。
腕時計を見るとまだ11時前だ。
「はあ。なんで早く帰っちゃうんだよ。みんな」
早く帰るとそれだけ一人でいる時間が増えてしまう。だから、遅くまで外で飲むようにしていた。
「ああ、でも今日は結構飲んだから、家に帰ったら直ぐ眠れるかも」
本当に飲みすぎた。頭が体から分離してるみたいに、ふわふわしてる。
「!」
ふいに、吐き気がこみ上げてきた。
反射的に口に手をやってしまい、後悔した。
「うえっつ」
吐瀉物が押さえた手からはみ出し、ベンチを汚す。
やばい。俺何やってんだよ。
ポケットをまさぐり、ハンカチを探すがない。
鞄なんか面倒だから車に置いて来たし。
「はい」
聞き覚えのある声、同時に差し出されたのはテッシュペーパーだった。
「……忠史」
忠史は眉を苦しそうに寄せ、俺を見ていた。
「使ってください」
「ありがとう」
気色悪いと思って別れた。
でも俺は意外に素直にそうお礼を言っていた。
「車まで送ります」
「……必要ないから」
「怖いんですか?」
忠史は少し様子がおかしかった。ちょっと痩せたようにも見える。
俺のせいか……。
俺が逃げたから。
でも、俺は、俺は無理だ。
勇みたいにはなれない。
いや、忠史が王さんみたいに女性のようだったら、大丈夫なのか?
何度かは考えことがある。
でも忠史は立派な男だ。俺なんかより体格がいいし、男らしい。
「灘さん?」
腰を落として俺を見る。
異様に距離が近くになったみたいで、俺は逃げるように立った。
「大丈夫だから。テッシュありがとうな」
またな、とは言えなかった。
会うつもりはない。
あの時木崎の奴が、忠史が俺のことを好きだと言っていた。
忠史もそれを否定しなかった。
そう。だから、もう会わない。
俺は、忠史をそういう風には思えない。
少し歩いて、後ろを振り向いた。
だが、忠史はそこにはいなくて……。
そのことで少し胸が痛かった。
それが嫌で、俺は息を吐くと、歩くスピードを上げた。
俺は、忠史を好きじゃない。
そういう意味で好きじゃないんだ。
あれから、忠史のことを毛嫌いすると思っていた。
でもそんなことはなくて、嫌になるほど思い出した。
それはまるで、俺が、奴に好意をもっているみたいで……。
深く考えるのが嫌で、俺はますます一人になることを避けた。
だから毎晩友達が集まる場所に出かけて飲んだ。
「お客さん、吐いちゃったんですか?」
「すみません。窓開けて運転してください」
雪は降ってない。少しくらい窓を開けてもいいだろう。
俺は代行運転手に答え、後部座席に深く座った。
彼がそれから話しかけることはなかった。
無言の車内。嫌でもさっき街で会った忠史のことを思い出して、俺は用もないのに運転手に話しかけた。
「なんか飲みすぎちゃったみたいで。すみません。匂いきついですか?」
「え、あ、大丈夫ですよ」
客商売だ。素直に同意できないんだろう。
「すみません。直ぐ付きますから。あ、そこ右に回って下さい」
アパートの駐車場に車を停めてもらい、金を払った。ここ数日間でかなりの金を使ってる。ばあちゃんが残してくれた遺産があるから全然痛くはないけど、俺にしてはちょっと使いすぎだ。
でも止められない。
一人になりたくない。
余計なことを考えたくない。
前から一人になるのはいやだったけど、ますます酷くなっていた。
アパートの部屋に入り、先ずは暖房を入れた。それから、シャワーを浴びる。汚れた服を手洗いし、脱水させるために洗濯機にいれた。
音がないといやだからテレビの音をつける。
脱水終わったら干さないと……。
そう思い、ソファーに座った。眠気が訪れ、うたた寝をする。何度もがくんと首がうな垂れ、寝ていたんだと気がついた。
それを繰り返してるうちに体は疲れたらしい。俺はいつの間にかソファーに横になり寝てしまった。
「信雪。いい子にしてるんだよ」
「夕飯は信雪の好きなグラタンだからね」
保育園に俺を送り二人はそのまま帰ってこなかった。
「信雪くん」
先生が泣きそうな顔で俺の手を握ってくれたのを覚えてる。
「信雪くん。どうしてそんなことするのかな」
俺と同じ目線で、話を聞いてくれたえみこさん。彼女が色々教えてくれた。
「大丈夫だよ。俺はもうガキじゃないんだから」
付き合っていた彼と結婚するために、えみこさんは仕事を辞めないといけなくなった。最後の最後まで、彼女は心配そうだった。
真っ暗な家。一人暮らしには勿体ない家にばあちゃんは住んでいた。
ばあちゃんの葬式の夜、俺は一人で家に取り残された。
もう成人していて、怖いなんて言えなかった。
家は静まり返っていた。
テレビが嫌いだったばあちゃんの家には、音を出すものがなかった。
「灘さん」
「忠史?」
夢。これは夢のはず。
でも夢の中に忠史がいた。暗い家の中、何故か奴の姿が眩しい。
「俺がいます。だから安心してください」
奴はにこりと微笑むと俺を抱きしめた。
暖かい。奴の体は暖かかった。
「は、放せ!」
温もりに安らぎを覚えた。
でも俺は、
けたたましい音で起こされた。
夢か。
「嫌な、嫌な夢だ」
わざと言葉に出して、あの安らぎを忘れようとする。
「!」
普段なら不快に感じない俺の着信音が、その存在を誇示するように耳に触る。
「うるさいなあ」
昨日はソファーに横になって寝たらしい。
暖房のお陰で寒さは感じなくてラッキーだった。
「誰だよ。全く」
時間間隔がない俺は半ば切れぎみに電話を取った。
「もしもし?」
「灘。お前、まさか今起きた?」
「あ?」
電話を掛けてきたのは同僚のイケメン町田だ。
「うん」
「今何時か知ってる?」
その言葉ヒヤリと寒気がする。
「10時。10時だよ。お前9時にケイラの実田さんと約束してただろ?取り敢えず俺が対応したけど。もしかして飲み過ぎか?」
図星だった。だが、妙な対抗意識が出てきてしまい「熱があるみたいだから。今日は病欠扱い頼む」
そんな風に答えてしまった。
「……ああ、わかったよ」
半信半疑だったが町田はそう答え、お大事にと電話を切った。
10時、窓から差し込む光は確かに朝のそれだ。
「勇に悪いことしたな」
俺がそう思っていると携帯電話が鳴った。
画面に表示された名前に俺は笑う。
以心伝心かよ。
電話してきたのは勇だった。
「悪いな。王さん大丈夫か?」
「うん。それよりお前顔色悪いけど?」
その夜、俺は勇と飲むことにした。
電話してきた勇は町田から病気だと聞いていたようで心配していた。
確かに単に休んでると、いうよりも病気と言った方がずっと対応はいいから町田の言葉は「間違っていない」
でも勇に余計な心配させてくれるなよ、とちょっとだけ町田に文句を言いたくなった。
電話口で元気そうな俺の様子に安心していた勇だったが、なんとなく久々に二人で話したくなって、彼を飲みに誘ってしまった。
ああ見えて独占欲の強い恋人の王さんが許可するのかと思っていたが、勇は快く誘いに乗ってくれた。
「顔色?悪いか?」
「うん。今日は飲むのは止めた方がいいかも」
「……いや、飲む」
「……少しだけにしろよ」
言い張る俺に勇は苦笑する。
「で、王さんとの生活はどうなんだ?楽しいか?」
「うん」
小さく頷く勇は「可愛い」感じだった。
男が乙女してるんじゃねーと思ったが、元からこいつは「可愛い」に定評があったと思い返す。
そういや、忠史。先輩の勇に対してはどうだったんだろう。
ゲイの奴としては「可愛い」勇に対してそのなんか、恋愛感情を持たなかったのかな。
なんで、俺はそんなこと考えてるんだ。
どうでもいいだろう。忠史のことなんて。
「灘はどう?最近、紀原くんと飲んでないみたいだけど。彼女でもできた?」
「……ああ」
嘘をついた。
俺が忠史と何かあったなんて、知られたくなかった。
「そう。よかった。ちょっと心配してたんだ」
「心配?」
俺が聞き返すと勇は、顔を曇らす。
「実はさ。紀原くんがお前に手を出すんじゃないかと心配だったんだ。手が早いから彼は」
「手が早い?!」
意味深な言葉に俺は聞き返してしまった。
「……えっと、忘れてくれ」
「お前、もしかして忠史になんかされた?」
「……言いたくない。あれはもう忘れたい過去。俺も、紀原くんもそうだと思うよ」
「……そっか」
俺はその時自分がどんな顔をしていたのか、わからない。
胸が押しつぶされ、呼吸が苦しくなった。
「ちょっとトイレいってくる」
だからトイレに逃げた。気持ちを落ち着けたかった。
鏡に映る自分の顔。
勇の言う通りに酷い顔だった。目の下に隈みたいのができてる。
目が充血してて、真っ赤だ。
……忠史と勇の間に何かあったのか。
忘れたい過去ってなんなんだろう?
もやもやとはっきりしない思い。
蛇口を捻り冷たい水で顔を洗う。すっきりすると思ったけど、気持ちは変わらないままだった。
「灘。もう帰ろうか?」
席に戻ったとたん、勇がそんなことを言いだした。
「え?まだ10時だせ」
「お前、本当に大丈夫か?」
「うん。一人になるのが嫌なんだよ」
「……そっか」
彼女がいるのに、一人になるのがいや。
でも勇は聞き返すことはなかった。
「灘。車まで送るよ。っていうか今日はタクシーのほうがいいじゃないか?」
「ううん。代行で帰る。送ってもらう必要はないから」
「必要ないって、どこかだよ。足元ふらふらだぞ?」
勇は俺の腕を支えるように掴んだ。
「必要ない!」
俺はなぜかイライラして、腕を振り払う。
「灘?怒ってる?何か俺……したか?」
勇はその大きい瞳を曇らせて、心配げだ。
本当に「可愛い」表情だ。
だから……
「な、なんでもない。俺、本当に大丈夫だから」
「灘。よくわからないけど、大丈夫だと思えない。お前がしっかり車に乗るのを確認するまで付いていくからな」
勇はやっぱりいい奴だな。
結局俺は勇と一緒に会社近くの駐車場まで歩くことになった。
「あれ?紀原くん?」
しばらく歩き、勇が驚いた声をあげた。
忠史?
まさかと思って勇が見ている方向に目を向ける。
昨日俺が座っていたベンチに忠史の姿が見えた。
奴は俺達に気がつくと、ぎょっとして立ち上がり、逃げるように立ち去る。
「紀原くん?おっかしいな。なんで逃げるんだ?明日、聞いてみよう。人違いなわけないし」
俺は勇がそうぼやくのをただ黙って聞いていた。
★
それからも俺は毎晩飲むのをやめなかった。駐車場近くのベンチを通るたびに、忠史を思い出す。いないのか、と落胆する自分がいて、余計嫌な気持ちになった。
そうして2週間がすぎ、俺は再び忠史と会うことになる。
勇が中国に旅行に行ってるため、会わなければならなくなった。
メールで都合を聞かれ、午後3時にミーティングを設定した。
午後3時ちょうどに内線が鳴り、俺は受話器を取った。
「もしもし。すずた製作所の灘です」
「……ケイラの紀原です」
一呼吸空いた後、忠志がそう答えた。
彼の声を久々に聞き、言葉が詰まる。
しかし息を吐き、落ち着かせるとエントランスのドアを開ける操作をする。
「ドアを開けたから、入ってきて」
電話を切り、俺は彼を迎えるために、受付に向かった。
人件費をできるだけ抑える意味で、俺の会社には受付はいない。
がらんとした空間に忠史が立っていた。
「……忠史。奥に応接室がある。そこで話をしよう。ついてきて」
お客さんと打合せする際は、応接室を使うのが常だ。
午後3時に使うとすでに予約は取っておいた。
応接室は部屋の一番奥だ。パテションで区切られたテーブルを数台通り過ぎながら、俺は女子社員が忠志の姿を見て息を飲むのが分かる。
そうだよな。奴はそこらへんにはなかなかいないイケメンだ。背も高いし。
そんな視線を掻い潜り、応接室に辿りつく。
「どうぞ」
俺はドアを開け、忠史に中に入るように促す。
彼は頷くと中に入った。
窓がなく、机と椅子しかない応接室は、本当なら狭いはずだった。だけど使用してるのは俺達二人だけのためか、妙に広く感じた。
忠史はノート型パソコンをテーブルに置き、俺を見ようともしなかった。
「……お茶とコーヒーどっちがいい?」
俺の会社にはお茶くみ係は存在しない。客をもてなすのは担当者自身の仕事だった。
「すみません。コーヒーいただけますか?」
奴は俯いたままそう答える。
俺は奴の答えに席を離れる口実ができたと、胸を撫で下ろす。
「ちょっと入れてくる」
二人でいると息がつまりそうだった。
応接室から逃げるように出た俺は、真っすぐ給湯室に向かった。
勇が休暇から戻ってきてから遅すぎるため、忠史と会うことになった。この時ばかりは忠史が仕事の取引先であることを恨んだ。
「灘。紀原くんだっけ。めちゃくちゃイケメンだな。なんか、悔しい」
廊下ですれ違った町田がアホみたいなこという。
悔しいって。まあ、普段は会社の女の子の視線を一身に受けてるから、忠史みたいなイケメンがくると持っていかれる感じか。
「……妙な色気があるよな。彼」
答えない俺に町田は笑いながら言葉を続ける。
「色気?なんだよ。それ」
給湯室まで付いてくる奴を鬱陶しく思いながら、俺はインスタントのコーヒーを入れる。砂糖とミルクの小さな袋と、コーヒーの入ったカップを盆に置いて、俺は町田の傍を通り過ぎようとした。
「感じないのか?なんか、つらそうだよ。彼」
「……」
町田が俺の心を見透かすように見つめる。
「まあ、灘もつらそうだな」
「ふざけんな」
町田とは付き合いは浅い。何か知ってるような含みを持ったいい方に俺は頭にきた。
「木崎と俺トモダチなんだよ。だから、知ってる。でも俺は木崎みたいに下品じゃないし。餓えてないから」
「!」
俺は驚きのあまり盆を落とすところだった。
それを支えたのは町田だった。
「危ないなあ。そういうところが灘の可愛いところだよな」
「!」
俺は「可愛い」と言う言葉に寒気を覚える。
「俺もバイなんだ。残念ながら。灘。素直になれば?好きなものは好きだし。男でも女でも関係ないだろ?」
「……うるさい。お前には関係ない」
町田がバイであることに驚いたが、それ以上に奴の言葉に頭にきた。
「本当。頭が固いな。まあ、どう選択するかは個人の自由だから。いいけど」
奴は気がすんだのか、そう言い終ると「じゃあな」と給湯室を後にした。
「はい。コーヒー」
結局コーヒーを作り直し、俺は応接室に戻った。
「ありがとうございます」
忠史は、パソコンの画面だけを見て俺に答える。
それから製品の説明や問題点などを話し合ったが、奴が俺を見ることがなかった。
「他に何か質問はありますか?」
ある程度説明し終わり、奴はこの打合せを締めるためにそう尋ねる。
「……忠史」
傍にいるのに、遠くに奴の存在を感じて寂しさを感じる。だから、俺は振り向いて欲しくてその腕を掴んだ。
びくっと震えた。
「触らないでください」
「……前みたいに友達に戻れないのか?」
気がつくと俺はそう聞いていた。
「もう、彼女ができたんですよね。俺なんかと会わなくて寂しくないですよね?」
勇についた嘘は忠史に伝わっていた。彼女なんかいない。嘘だと答えるか迷う。
無性に寂しかった。
友達と会っても思い出すのは忠史と飲んだこと。
前みたいに会うことは無理なのか。俺の我儘なのか。
言葉を発しない俺に、忠史は微笑む。
諦めた、そんな笑みだ。
「彼女とお幸せに」
パソコンを閉じ、広げた書類をまとめると鞄に仕舞い込む。
「もう、会うことはないと思います。何かを問題があればメールでお聞きします。失礼致します」
すっと立ち上がり、忠史は頭を下げると背を向けた。
また俺は一人になる。
一人ぼっちだ。
「行かないでくれ」
えみこさんに本当に言いたかった言葉。あの時は強がって言えなかった。
でも今度は勇気を出した。
忠史に側にいてほしい。
一緒に飲んだり何処かに行きたかった。
「な、灘さん」
振り向いた忠史は驚いた顔をしていた。
「な、泣かないでください」
「え、俺っ」
頬を触ると水滴が指を濡らした。
泣くつもりなどなく、見られたことが恥ずかしくて俺は片手で顔を覆う。
もう一つの手でポケットに入っているはずのハンカチを探した。
「どうぞ」
ポケットをまさぐっていると、白いハンカチが差し出される。見上げると、優しい笑みを浮かべた忠史がいた。
「使って下さい」
「……ありがとう」
なんてカッコ悪いんだ。俺。
羞恥心でいっぱいになりながらも、忠史が以前のように優しいのが嬉しかった。
「そんな風に呼びとめられて、しかも泣かれるとすごい困ります。彼女もいるのに、なんで」
「彼女は、いない」
嘘をついてもしょうがない。俺はハンカチで涙をぬぐい、忠史に目を向ける。
目を丸くした奴は俺を見つめ返していた。
「勇には嘘をついたんだ。なんかお前ともめてるのが、ばれたくなくて……」
「そうなんですか」
忠史はほっとしたように息を吐く。
「……俺はゲイじゃない。でも、お前と……前みたいに一緒に過ごしたんいんだ。我儘か?」
「……我儘ですね。俺がどれだけ我慢してると思ってるんですか」
「が、我慢?!」
「俺はあなたが好きだから。キスしたり、抱きしめたりしたんです」
「!」
すうっと真剣な瞳を向けられ、俺の心臓が跳ねた。
え、っていうか、俺乙女モード入ってる……。
いや、俺は、俺はゲイじゃないんだ!
「……でも我慢します。泣かれると困るし」
「な、泣かれると困る?!なんだよ、それ!」
「泣いてましたよね。さっき」
「……」
泣くつもりなんかなかった。でも泣いたのは事実で俺は言い返せなくて黙ってしまう。くそっつ、忠史のペースに飲まれてる気がする。
「灘さん、これからも宜しくお願いします」
あでやかな笑みを浮かべた忠史は仕切り直すように、俺に手を差し出した。
「ああ、よろしく」
俺は自然に手を握り返す。
「?!」
急に手をひかれ、バランスがとれなくなった。気が付いたら俺は忠史の腕の中にいた。
「忠史!」
「仲直りの印です」
動揺する俺に構わず、奴は俺を強く抱きしめる。
「離せよ!俺は、普通の友達のつもりなんだからな」
「はいはい。そうですね」
数秒後、満足したのか、奴はあっさりと俺を解放した。
忠史の温もりが心地よかった。
でもそんなこと死んでも言えるわけがない。
俺はゲイじゃないんだから。
「じゃ、灘さん。また電話します」
そうして彼は軽やかに応接室を出て行った。
じわりと、胸の中に広がっていく暖かい気持ち。触れ合った個所はまだ熱をもっているみたいで、ぽかぽかしていた。
……俺はゲイじゃない。
忠史は俺の大事な友達。
それだけだ。
俺は自分に言い聞かせるように心の中で呟くと、コーヒーカップを片付ける。
孤独でいっぱいだった俺の心、でも今は太陽に照らされたみたいに暖かさに満ち溢れていた。
(完)
0
お気に入りに追加
8
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説


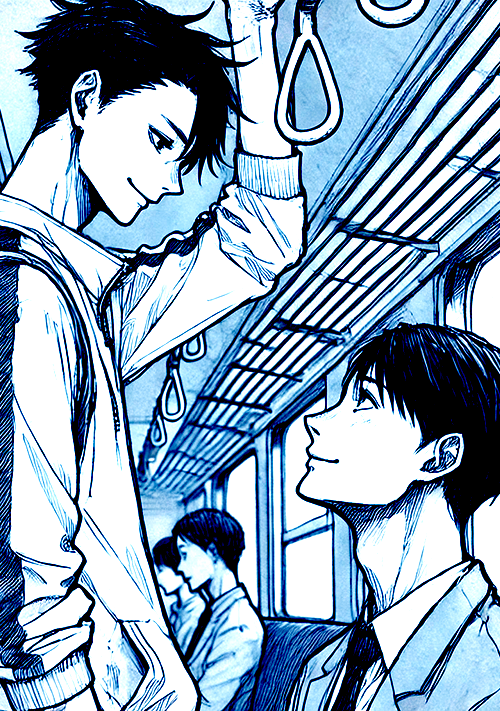
たまにはゆっくり、歩きませんか?
隠岐 旅雨
BL
大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。
よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。
世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……


フローブルー
とぎクロム
BL
——好きだなんて、一生、言えないままだと思ってたから…。
高二の夏。ある出来事をきっかけに、フェロモン発達障害と診断された雨笠 紺(あまがさ こん)は、自分には一生、パートナーも、子供も望めないのだと絶望するも、その後も前向きであろうと、日々を重ね、無事大学を出て、就職を果たす。ところが、そんな新社会人になった紺の前に、高校の同級生、日浦 竜慈(ひうら りゅうじ)が現れ、紺に自分の息子、青磁(せいじ)を預け(押し付け)ていく。——これは、始まり。ひとりと、ひとりの人間が、ゆっくりと、激しく、家族になっていくための…。



ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















