3 / 10
きっかけはクリスマス
3
しおりを挟む
「すげぇ。お菓子作り専門店みたいだ」
俺のアパートに入り、台所を見た灘さんが溜息をつく。
俺にとっては普通だが、ホームベーカーリーとか、ケーキの型とかが家にあるのは驚きらしい。
「忠史……。ブッシュドノエルとか作れる?」
「え、まあ。サンタの砂糖菓子とかは無理ですけど」
「じゃ、ブッシュドノエル作って!俺、アレ大好きなんだよなあ」
灘さんは子供みたいに笑う。
それがなんだか可愛いと思ってしまい、俺ははっと苦い顔になる。
男だったら誰でもいいわけじゃないんだ。
俺は!
「灘さんの家にはオーブンありますよね?」
「うん。天板だっけ?それも付いてるよ」
「だったら、クッキングシートを引けばOKっかあ。あとは」
俺はがさごそとケーキ作りに必要な道具を探す。
材料も買わないと……
「ケーキの材料買わないとやばいよな。どこか行きたい店ある?」
「あります」
連れて行ってもらえるなら、粉とか生クリームとかいいものが揃っている店に行きたい。
俺はそう思い、灘さんに連れていったもらうことにした。
「………やばいな。この店」
「そうですよね。俺、一人で行ってきますから」
女の目線なんてどうでもいい、俺はその店の前で足をすくませた灘さんにそう言った。お菓子作りの店らしく、客層は女性だけ、しかも店内はピンクだった。
俺は俺を好奇の目でみる女たちを無視して、自分の必要なものを探していく。
灘さんを待たせるわけにもいかないし、手際良く。
「すげぇ」
しかし、久々にきたその店で使い勝手がよさそうな道具をみてしまい、俺は時間を忘れてしまった。
「……忠史。探し物見つかった?」
ぼそってそう声が聞こえ、俺ははっと我に変える。
側にいたのはちょっと顔を赤くした灘さんで、俺はいつもと違う彼の様子に気を取られた。
「悪いけど、やっぱりきついな。この店。俺、近くの喫茶店で待ってるから。終わったら電話して」
「あ、もう終わります。会計しますからちょっと待っててください」
俺は買い物籠を抱えるとレジに走る。
いや、灘さんでもあんな顔するんだな。
やっぱり女ばかりの店だから恥ずかしいんだ。
ちょっと可愛かったかも。
イヤイヤ、おかしなことを考えちゃだめだ。
どう考えても好みじゃないんだから!
「お待たせしました」
俺は買い物袋を抱え、店の前で待っていた灘さんに頭を下げる。
「面白いものあったんだ?」
すっかり元の灘さんに戻った様子で、彼はひょいと袋を一つかっさらう。
「いいですよ。俺が持ちます」
「いいって」
彼はそう言うとてくてくと、駐車場に歩いて行った。
「………」
買い物を全て終え、灘さんの家に戻ったのは5時近くだった。
「疲れた?もう5時だよなあ。腹減った?何か食べて行く?」
彼は冷蔵庫に食料品を入れながら、そう聞く。
「いや、いいですよ。俺適当に食べますから」
なんだか、これ以上一緒にいない方がいいような気がして俺はそう答えた。
「あ、でも二人分作るのも一人分作るのも一緒だから食べていけば?酒飲むから帰りは送れないけど」
灘さんにそう言われ、夕飯を共にすることになった。
「うまい」
「そう?よかった」
灘さんの料理は本人が好きなだけあって美味しかった。
これはクリスマスは期待できそうだ。
そうだ、俺も頑張ってケーキ作んなきゃなあ。焼いて冷やしたりだから、昼から休みを取るか。っていうか、それなら自宅で作って運んだ方がよそうだ。
「灘さん。やっぱり俺、家でケーキ作って持ってきますよ。結構作るの時間かかりそうだから、家で作った方がいいかもしんないですし」
「何時から作るの?」
「えっと、多分3時くらい」
「だったらうちに3時くらいにくれば。俺25日は休みを取ること決めたし」
「休み?!」
「うん。なんかさあ、色々作ろうと思ったら休み取った方がいいと思ってさあ。去年はほとんど持ち込みだったけど、今年は作るからさ」
休みって、やっぱり灘さん。ちょっとおかしいかも。
しかも休みとるなら、ケーキとか余裕で買えるんじゃ……
ま、いいか。作るの好きだし。
作ることに対して自分が楽しんでるのがわかり、なんだか苦笑してしまう。
好きな人のために作るわけでもないのにな。
「やっぱりおかしいか。男だけのパーティー。しかも俺達4人だしな」
灘さんは俺の苦笑にちょっと恥ずかしそうに笑う。
なんか、これって照れてるのか?
……もしかして、灘さん。
俺のこと好き?
俺はふいにそんなことを思う。
だって普通は男同志のパーティーでそんな大がかりなことしないし、ましては料理のために休むなんて。
「何?」
俺がじっと見ていたのを不思議がり、灘さんが尋ねる。
「灘さん……」
聞いてどうする。
もし彼が俺のこと好きでも彼は俺の対象外だ。
聞けるわけない。
「ごちそうさまでした。俺、もう帰りますね。25日、3時くらいにまた来ますから」
俺は自分が使っていた食器を持つと台所のシンクに入れる。
「ああ、俺が後で洗うから。置いといて」
「じゃ、遠慮なく」
俺は鞄を掴むと玄関へ歩き出す。その後を灘さんがてくてくと付いてきた。
「今日は買い物に付き合ってくれてありがとう。楽しかった。またな!」
玄関で手をひらひらと振られ、俺はなんだか少し悲しくなる。
「こちらこそ楽しかったです。夕飯も美味しかったです。ご馳走様でした」
しかし俺は自分のおかしな気持ちを振り払うと頭を下げ、玄関のドアを開けた。
俺のアパートに入り、台所を見た灘さんが溜息をつく。
俺にとっては普通だが、ホームベーカーリーとか、ケーキの型とかが家にあるのは驚きらしい。
「忠史……。ブッシュドノエルとか作れる?」
「え、まあ。サンタの砂糖菓子とかは無理ですけど」
「じゃ、ブッシュドノエル作って!俺、アレ大好きなんだよなあ」
灘さんは子供みたいに笑う。
それがなんだか可愛いと思ってしまい、俺ははっと苦い顔になる。
男だったら誰でもいいわけじゃないんだ。
俺は!
「灘さんの家にはオーブンありますよね?」
「うん。天板だっけ?それも付いてるよ」
「だったら、クッキングシートを引けばOKっかあ。あとは」
俺はがさごそとケーキ作りに必要な道具を探す。
材料も買わないと……
「ケーキの材料買わないとやばいよな。どこか行きたい店ある?」
「あります」
連れて行ってもらえるなら、粉とか生クリームとかいいものが揃っている店に行きたい。
俺はそう思い、灘さんに連れていったもらうことにした。
「………やばいな。この店」
「そうですよね。俺、一人で行ってきますから」
女の目線なんてどうでもいい、俺はその店の前で足をすくませた灘さんにそう言った。お菓子作りの店らしく、客層は女性だけ、しかも店内はピンクだった。
俺は俺を好奇の目でみる女たちを無視して、自分の必要なものを探していく。
灘さんを待たせるわけにもいかないし、手際良く。
「すげぇ」
しかし、久々にきたその店で使い勝手がよさそうな道具をみてしまい、俺は時間を忘れてしまった。
「……忠史。探し物見つかった?」
ぼそってそう声が聞こえ、俺ははっと我に変える。
側にいたのはちょっと顔を赤くした灘さんで、俺はいつもと違う彼の様子に気を取られた。
「悪いけど、やっぱりきついな。この店。俺、近くの喫茶店で待ってるから。終わったら電話して」
「あ、もう終わります。会計しますからちょっと待っててください」
俺は買い物籠を抱えるとレジに走る。
いや、灘さんでもあんな顔するんだな。
やっぱり女ばかりの店だから恥ずかしいんだ。
ちょっと可愛かったかも。
イヤイヤ、おかしなことを考えちゃだめだ。
どう考えても好みじゃないんだから!
「お待たせしました」
俺は買い物袋を抱え、店の前で待っていた灘さんに頭を下げる。
「面白いものあったんだ?」
すっかり元の灘さんに戻った様子で、彼はひょいと袋を一つかっさらう。
「いいですよ。俺が持ちます」
「いいって」
彼はそう言うとてくてくと、駐車場に歩いて行った。
「………」
買い物を全て終え、灘さんの家に戻ったのは5時近くだった。
「疲れた?もう5時だよなあ。腹減った?何か食べて行く?」
彼は冷蔵庫に食料品を入れながら、そう聞く。
「いや、いいですよ。俺適当に食べますから」
なんだか、これ以上一緒にいない方がいいような気がして俺はそう答えた。
「あ、でも二人分作るのも一人分作るのも一緒だから食べていけば?酒飲むから帰りは送れないけど」
灘さんにそう言われ、夕飯を共にすることになった。
「うまい」
「そう?よかった」
灘さんの料理は本人が好きなだけあって美味しかった。
これはクリスマスは期待できそうだ。
そうだ、俺も頑張ってケーキ作んなきゃなあ。焼いて冷やしたりだから、昼から休みを取るか。っていうか、それなら自宅で作って運んだ方がよそうだ。
「灘さん。やっぱり俺、家でケーキ作って持ってきますよ。結構作るの時間かかりそうだから、家で作った方がいいかもしんないですし」
「何時から作るの?」
「えっと、多分3時くらい」
「だったらうちに3時くらいにくれば。俺25日は休みを取ること決めたし」
「休み?!」
「うん。なんかさあ、色々作ろうと思ったら休み取った方がいいと思ってさあ。去年はほとんど持ち込みだったけど、今年は作るからさ」
休みって、やっぱり灘さん。ちょっとおかしいかも。
しかも休みとるなら、ケーキとか余裕で買えるんじゃ……
ま、いいか。作るの好きだし。
作ることに対して自分が楽しんでるのがわかり、なんだか苦笑してしまう。
好きな人のために作るわけでもないのにな。
「やっぱりおかしいか。男だけのパーティー。しかも俺達4人だしな」
灘さんは俺の苦笑にちょっと恥ずかしそうに笑う。
なんか、これって照れてるのか?
……もしかして、灘さん。
俺のこと好き?
俺はふいにそんなことを思う。
だって普通は男同志のパーティーでそんな大がかりなことしないし、ましては料理のために休むなんて。
「何?」
俺がじっと見ていたのを不思議がり、灘さんが尋ねる。
「灘さん……」
聞いてどうする。
もし彼が俺のこと好きでも彼は俺の対象外だ。
聞けるわけない。
「ごちそうさまでした。俺、もう帰りますね。25日、3時くらいにまた来ますから」
俺は自分が使っていた食器を持つと台所のシンクに入れる。
「ああ、俺が後で洗うから。置いといて」
「じゃ、遠慮なく」
俺は鞄を掴むと玄関へ歩き出す。その後を灘さんがてくてくと付いてきた。
「今日は買い物に付き合ってくれてありがとう。楽しかった。またな!」
玄関で手をひらひらと振られ、俺はなんだか少し悲しくなる。
「こちらこそ楽しかったです。夕飯も美味しかったです。ご馳走様でした」
しかし俺は自分のおかしな気持ちを振り払うと頭を下げ、玄関のドアを開けた。
0
お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説


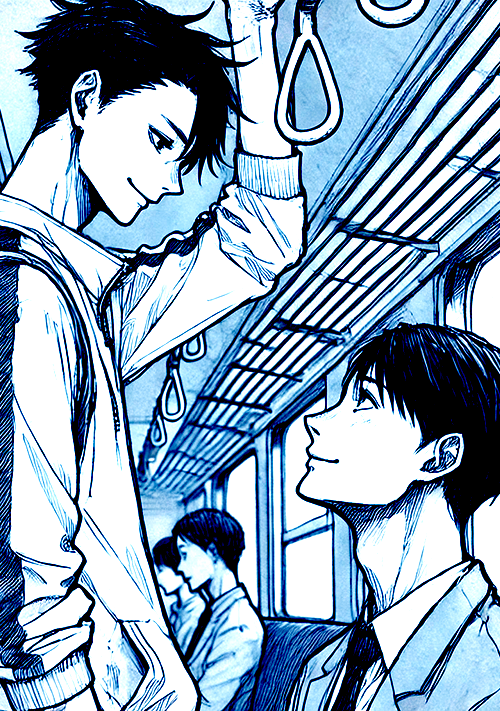
たまにはゆっくり、歩きませんか?
隠岐 旅雨
BL
大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。
よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。
世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……




好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」

離したくない、離して欲しくない
mahiro
BL
自宅と家の往復を繰り返していた所に飲み会の誘いが入った。
久しぶりに友達や学生の頃の先輩方とも会いたかったが、その日も仕事が夜中まで入っていたため断った。
そんなある日、社内で女性社員が芸能人が来ると話しているのを耳にした。
テレビなんて観ていないからどうせ名前を聞いたところで誰か分からないだろ、と思いあまり気にしなかった。
翌日の夜、外での仕事を終えて社内に戻って来るといつものように誰もいなかった。
そんな所に『すみません』と言う声が聞こえた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















