10 / 12
覚悟
しおりを挟む
「メイク?」
怪訝な様子で聞き返してくる陽子さん。その顔は信じられないものを見たとでも言いたげだ。だが私は真剣だ。
「はい。お金が必要なら払います。だからどうか、陽子さんの腕で母に完璧なメイクをしてください!」
深くお辞儀をして頼み込む。すると陽子さんは戸惑ったように聞いてくる。
「ちょっとちょっと、頭を上げて! 別にお金はいらないから! てかなんでまたこんなときにメイクを?」
「こんなときだからこそ、です」
頭を上げると、陽子さんに母を見るよう促す。
「陽子さん。正直に言ってください。母のメイク、どう思いますか?」
「え」
ひく、と陽子さんの口角が引きつる。それから目線をそらして、言いにくそうに言う。
「正直に言うなら……あんまりよくはないわね」
「うっ!」
陽子さんの言葉は母にクリティカルヒットしたようだ。短いうめき声を出してうなだれた母は、顔を覆いながら言う。
「やっぱり私の顔じゃ、何してもだめなのよ」
「ママ、一応言っておくと、今は私の顔だからね」
「そうだけど……でもこんなに私に似ちゃったなら私の顔も同然じゃない」
「それも一理ある、というか、今はそれがめちゃくちゃ大事なことなんだけどね」
「え?」
「陽子さん」
もう一度陽子さんに向き直る。
「以前から話してましたよね、私がこの仕事に就いた理由」
「え? ああ、確かお母様のような人を……あ」
陽子さんは私が何を言いたいか察してくれたのだろう。母を見たあと、私を見てうなずく。
「……分かった。メイクしてあげる」
「ありがとうござ――」
「ただし!」
食い気味に言葉を被せてきた陽子さん。その顔は今まで見た中で一番真剣なものだった。
「メイクの内容はあんたが考えなさい」
「え?! なんでですか⁈」
「さっきあんたが言ったことがそのまんま答えよ」
「さっきって?」
「あんたがこの仕事に就いたのはなんでか、って話よ。ねえ、あんたが一番メイクしたいのは誰なの? 誰の悩みに寄り添いたくてこの仕事を始めたの?」
「それは……」
その答えはひとつしかない。陽子さんの言葉に覚悟を決めた。
「分かりました。やれるだけやってみます!」
そうと決まればあとはやるだけだ。私たちは母を連れて店内に戻ることにした。
はたから見たら私本人でしかない状態で陽子さんが接客をしていたら不自然だ。だが営業成績が落ち込み始めている私に対して陽子さんが研修代わりに接客をするとなれば別だ。同僚たちにはそういう風に事情を説明して、私たちは母にメイクをすることにした。
「お客様がご自分のお顔で一番気にされているところはどこですか?」
母をコスメカウンターに座らせると、陽子さんはテキパキとメイクを落とし、私は仕事モードの口調で話しかけた。
「えっと、その……」
メイクを落として素顔になった母は、コスメカウンターに設置されている鏡から目をそらしながらオドオドと言う。
「目が、嫌で……昔からギョロッとしてて怖い、って言われてて……」
「確かにお客様は黒目がちで印象的な目ですね」
他人から見えていない状態の私と会話していたら変に思われる。そう気を遣った陽子さんが私の台詞を復唱してくれながらメイク道具の用意をしてくれる。
「普段のアイメイクはどのような点にこだわっていますか?」
「なるべく目を小さく見えるようにしたかったから、あまり明るい色は使わないようにしていたわ」
「なるほど」
確かに母は昔から暗めの色を愛用していた。それ自体はいい。問題は塗る量だ。
「落ち着いた色合いを選ばれるのはとてもいいと思います。ただお客様の場合少し塗り過ぎの傾向にあります。適切な量で塗らないと、肌から色が浮いて見えて、余計に目元に注目を浴びてしまう可能性が高くなります」
「そんな……ああ、でも、そう、そうだったのね。目をそらされていたのってそういうことだったのね?」
「原因であった可能性は高いです」
「そう……」
子供の頃は言語化できなかった母のメイクの問題点を、十数年経った今、やっと伝えられた。これが生きている頃だったらどんなに良かっただろう、と思う反面、今こうやって伝えられる奇跡に感謝しながら、メイクの改善方法を考えつつ話す。
「お客様がおっしゃった通り、お客様のお顔の中では目元が一番際立っていると思います。ただ、それは欠点ではなく長所だと思います」
「長所? こんな目が?」
「はい。聞いたことありませんか? コンプレックスはチャームポイントでもある、という考え方」
「私の目もそうってこと?」
「私はそうだと思います。コンプレックスになるほど目立つということは、逆に言うと他の人には魅力的に見えることが多いということです」
母は私の言葉を噛み締めて考えている様子で、少し話しかけづらい雰囲気になった。
この状態で話しかけていいのかどうか、そもそもどういうメイクを提案すればいいのか、と悩んでいたら、さきほどまで私の言葉を復唱するだけだった陽子さんが、大量のアイシャドウを広げながら母に尋ねた。
「お客様は何色がお好きですか?」
「え? えっと……」
誰が見ても、このアイシャドウの中から気に入った色を選べ、と言われている状況。つまりこのあと試し塗りすることになる、というのはなんとなく察せられるものだ。そうなった場合、人は二通りの答え方をする。母の場合は――。
「茶色、かしら」
本当に自分の好きな色を選ぶのではなく、自分に塗られる前提で、似合う色、もしくは無難な色を選ぶ答えだった。
母が本当に好きな色を知っていたため、思わず「違うでしょ」と言いかけた。だがそれは陽子さんに目で制された。
「お客様。茶色、と言われましたが、具体的にはどのような茶色がよろしいでしょうか?」
「どのような? 茶色は茶色以外にないでしょう?」
「いいえ、茶色と一口に言っても様々な色味があります。暗いもの、明るいもの、赤みがかったもの、黄色っぽいもの、などなど、すぐに挙げられるものだけでこれだけの種類があります。さらにこれらの要素を組み合わせた様々な色味があります」
「そう言われると、確かにそうね」
「ええ。なので、我が社も茶色は数種類ご用意してありますし、他の色も複数ご用意しております」
「それはすごいわね」
「ありがとうございます。では……なぜこんなに用意されてると思われますか?」
「え?」
そんなことを問われると思っていなかったようで、母はあごに手を当てて考え始めた。
「そう言われると、確かに不思議ね。気にしたことなかったわ」
母の言葉に陽子さんはにこりと笑う。
「誰しも好きな色というのはありますよね。でもその色が必ずしもパーソナルカラーと合致するとは限りません」
「パーソナルカラー?」
「簡単に言えばその人に似合う色のことです。イエローベースやブルーベースって聞いたことありませんか?」
「イエロー? ブルー?」
きょとんとする母。それもそうだろう。パーソナルカラー自体はそれなりに前からある考え方だが、母が亡くなった当時はまだまだインターネットは普及しておらず、あまりメジャーな考え方ではなかった。
「陽子さん、母が亡くなったのはもう十年以上前ですので、多分知らないかと」
その言葉に陽子さんは納得したように小さくうなずくと、アイシャドウの中から二種類の茶色のものを手に取って母に見せる。
「例えばこの中でお客様に合うのは右のものになります。逆に左のものを選んでしまえば浮いて見えます。これがパーソナルカラーと思っていただいて大丈夫です」
「なるほど」
母は陽子さんの手の中のアイシャドウをまじまじと見つめる。
「じゃあ、この色を試させてもらおうかしら」
そう言って母は右側のアイシャドウを指さす。が、陽子さんはそのアイシャドウを母に塗ることはしなかった。
「お客様。さきほどお好きな色についてうかがいましたよね?」
「ええ、そうね。それで茶色を答えたわ」
「そうですね。ただ……失礼ながら、それは本当に一番好きな色ですか?」
「えっ、と……」
母の目が泳ぐ。その動揺を見逃す陽子さんではない。陽子さんは茶色のアイシャドウを元の位置に戻すと、ピンク色のアイシャドウを数個手に取った。
「お客様、本当はこちらの色がお好きだったりしませんか?」
「えッ⁈」
そんなことを言われると思っていなかったのだろう。母は大きな声を出して驚いたあと、キョロキョロと周りを見つつ小声で陽子さんに尋ねる。
「なんで分かったの?」
「好きな色をお尋ねしたとき、お客様の目線がまっさきにこちらに向いていましたから」
「そういうこと……」
納得した様子を見せた母。だがすぐに新たな疑問を抱いたようだ。
「でもなんでそんなことをわざわざ言うの? パーソナルカラーっていうのがあるなら、私にピンクが似合わないのは明らかなんじゃない? だって今まで……」
そこまで言って母は言葉を切る。だが続きは言わなくても分かった。それは陽子さんも同じようで、陽子さんは母の目をじっと見つめると、今までよりもさらに優しい声色で話し始めた。
「確かに、お客様に似合うピンク色は限られていると思います。ですが、本来なら似合わない色でも、使い方次第でどうにでもなります」
「使い方?」
「はい。それはこれから説明していきますね」
と言って、陽子さんは私にアイコンタクトを送ってきた。〝あんたのターンよ〟という意味なのは言わずもがなだ。私は決意を新たにすると、ファンデーションを指さした。
「まずは肌の色味を整えますね」
母に合う色――正確に言うならば私の体に合う色は知り尽くしている。
私はピンク系統を使うことを考えながら選んだ色のファンデーションの塗り方を説明する。するとその通りに陽子さんが鮮やかな手つきで塗っていき、瞬く間につややかな肌に仕上がった。
「これでベースは大丈夫ですね。肝心のアイシャドウですが……今までお客様は目を目立たせないようなメイクをなさっていたんですよね?」
「ええ。うまくはいってなかったみたいだけど……」
なんともコメントに困る返答に答えあぐねる。すると陽子さんが助け舟を出してくれた。
「それは方法を知らなかっただけです。やり方さえ知れば、ある程度の技術は誰でも身につけられます。お客様も、覚えてしまえばご自分でもやれるようになると思いますよ」
その言葉に、私はある方法を思いつく。
「アイメイクですが、良ければ顔半分はお客様ご自身の手でメイクしてみませんか?」
怪訝な様子で聞き返してくる陽子さん。その顔は信じられないものを見たとでも言いたげだ。だが私は真剣だ。
「はい。お金が必要なら払います。だからどうか、陽子さんの腕で母に完璧なメイクをしてください!」
深くお辞儀をして頼み込む。すると陽子さんは戸惑ったように聞いてくる。
「ちょっとちょっと、頭を上げて! 別にお金はいらないから! てかなんでまたこんなときにメイクを?」
「こんなときだからこそ、です」
頭を上げると、陽子さんに母を見るよう促す。
「陽子さん。正直に言ってください。母のメイク、どう思いますか?」
「え」
ひく、と陽子さんの口角が引きつる。それから目線をそらして、言いにくそうに言う。
「正直に言うなら……あんまりよくはないわね」
「うっ!」
陽子さんの言葉は母にクリティカルヒットしたようだ。短いうめき声を出してうなだれた母は、顔を覆いながら言う。
「やっぱり私の顔じゃ、何してもだめなのよ」
「ママ、一応言っておくと、今は私の顔だからね」
「そうだけど……でもこんなに私に似ちゃったなら私の顔も同然じゃない」
「それも一理ある、というか、今はそれがめちゃくちゃ大事なことなんだけどね」
「え?」
「陽子さん」
もう一度陽子さんに向き直る。
「以前から話してましたよね、私がこの仕事に就いた理由」
「え? ああ、確かお母様のような人を……あ」
陽子さんは私が何を言いたいか察してくれたのだろう。母を見たあと、私を見てうなずく。
「……分かった。メイクしてあげる」
「ありがとうござ――」
「ただし!」
食い気味に言葉を被せてきた陽子さん。その顔は今まで見た中で一番真剣なものだった。
「メイクの内容はあんたが考えなさい」
「え?! なんでですか⁈」
「さっきあんたが言ったことがそのまんま答えよ」
「さっきって?」
「あんたがこの仕事に就いたのはなんでか、って話よ。ねえ、あんたが一番メイクしたいのは誰なの? 誰の悩みに寄り添いたくてこの仕事を始めたの?」
「それは……」
その答えはひとつしかない。陽子さんの言葉に覚悟を決めた。
「分かりました。やれるだけやってみます!」
そうと決まればあとはやるだけだ。私たちは母を連れて店内に戻ることにした。
はたから見たら私本人でしかない状態で陽子さんが接客をしていたら不自然だ。だが営業成績が落ち込み始めている私に対して陽子さんが研修代わりに接客をするとなれば別だ。同僚たちにはそういう風に事情を説明して、私たちは母にメイクをすることにした。
「お客様がご自分のお顔で一番気にされているところはどこですか?」
母をコスメカウンターに座らせると、陽子さんはテキパキとメイクを落とし、私は仕事モードの口調で話しかけた。
「えっと、その……」
メイクを落として素顔になった母は、コスメカウンターに設置されている鏡から目をそらしながらオドオドと言う。
「目が、嫌で……昔からギョロッとしてて怖い、って言われてて……」
「確かにお客様は黒目がちで印象的な目ですね」
他人から見えていない状態の私と会話していたら変に思われる。そう気を遣った陽子さんが私の台詞を復唱してくれながらメイク道具の用意をしてくれる。
「普段のアイメイクはどのような点にこだわっていますか?」
「なるべく目を小さく見えるようにしたかったから、あまり明るい色は使わないようにしていたわ」
「なるほど」
確かに母は昔から暗めの色を愛用していた。それ自体はいい。問題は塗る量だ。
「落ち着いた色合いを選ばれるのはとてもいいと思います。ただお客様の場合少し塗り過ぎの傾向にあります。適切な量で塗らないと、肌から色が浮いて見えて、余計に目元に注目を浴びてしまう可能性が高くなります」
「そんな……ああ、でも、そう、そうだったのね。目をそらされていたのってそういうことだったのね?」
「原因であった可能性は高いです」
「そう……」
子供の頃は言語化できなかった母のメイクの問題点を、十数年経った今、やっと伝えられた。これが生きている頃だったらどんなに良かっただろう、と思う反面、今こうやって伝えられる奇跡に感謝しながら、メイクの改善方法を考えつつ話す。
「お客様がおっしゃった通り、お客様のお顔の中では目元が一番際立っていると思います。ただ、それは欠点ではなく長所だと思います」
「長所? こんな目が?」
「はい。聞いたことありませんか? コンプレックスはチャームポイントでもある、という考え方」
「私の目もそうってこと?」
「私はそうだと思います。コンプレックスになるほど目立つということは、逆に言うと他の人には魅力的に見えることが多いということです」
母は私の言葉を噛み締めて考えている様子で、少し話しかけづらい雰囲気になった。
この状態で話しかけていいのかどうか、そもそもどういうメイクを提案すればいいのか、と悩んでいたら、さきほどまで私の言葉を復唱するだけだった陽子さんが、大量のアイシャドウを広げながら母に尋ねた。
「お客様は何色がお好きですか?」
「え? えっと……」
誰が見ても、このアイシャドウの中から気に入った色を選べ、と言われている状況。つまりこのあと試し塗りすることになる、というのはなんとなく察せられるものだ。そうなった場合、人は二通りの答え方をする。母の場合は――。
「茶色、かしら」
本当に自分の好きな色を選ぶのではなく、自分に塗られる前提で、似合う色、もしくは無難な色を選ぶ答えだった。
母が本当に好きな色を知っていたため、思わず「違うでしょ」と言いかけた。だがそれは陽子さんに目で制された。
「お客様。茶色、と言われましたが、具体的にはどのような茶色がよろしいでしょうか?」
「どのような? 茶色は茶色以外にないでしょう?」
「いいえ、茶色と一口に言っても様々な色味があります。暗いもの、明るいもの、赤みがかったもの、黄色っぽいもの、などなど、すぐに挙げられるものだけでこれだけの種類があります。さらにこれらの要素を組み合わせた様々な色味があります」
「そう言われると、確かにそうね」
「ええ。なので、我が社も茶色は数種類ご用意してありますし、他の色も複数ご用意しております」
「それはすごいわね」
「ありがとうございます。では……なぜこんなに用意されてると思われますか?」
「え?」
そんなことを問われると思っていなかったようで、母はあごに手を当てて考え始めた。
「そう言われると、確かに不思議ね。気にしたことなかったわ」
母の言葉に陽子さんはにこりと笑う。
「誰しも好きな色というのはありますよね。でもその色が必ずしもパーソナルカラーと合致するとは限りません」
「パーソナルカラー?」
「簡単に言えばその人に似合う色のことです。イエローベースやブルーベースって聞いたことありませんか?」
「イエロー? ブルー?」
きょとんとする母。それもそうだろう。パーソナルカラー自体はそれなりに前からある考え方だが、母が亡くなった当時はまだまだインターネットは普及しておらず、あまりメジャーな考え方ではなかった。
「陽子さん、母が亡くなったのはもう十年以上前ですので、多分知らないかと」
その言葉に陽子さんは納得したように小さくうなずくと、アイシャドウの中から二種類の茶色のものを手に取って母に見せる。
「例えばこの中でお客様に合うのは右のものになります。逆に左のものを選んでしまえば浮いて見えます。これがパーソナルカラーと思っていただいて大丈夫です」
「なるほど」
母は陽子さんの手の中のアイシャドウをまじまじと見つめる。
「じゃあ、この色を試させてもらおうかしら」
そう言って母は右側のアイシャドウを指さす。が、陽子さんはそのアイシャドウを母に塗ることはしなかった。
「お客様。さきほどお好きな色についてうかがいましたよね?」
「ええ、そうね。それで茶色を答えたわ」
「そうですね。ただ……失礼ながら、それは本当に一番好きな色ですか?」
「えっ、と……」
母の目が泳ぐ。その動揺を見逃す陽子さんではない。陽子さんは茶色のアイシャドウを元の位置に戻すと、ピンク色のアイシャドウを数個手に取った。
「お客様、本当はこちらの色がお好きだったりしませんか?」
「えッ⁈」
そんなことを言われると思っていなかったのだろう。母は大きな声を出して驚いたあと、キョロキョロと周りを見つつ小声で陽子さんに尋ねる。
「なんで分かったの?」
「好きな色をお尋ねしたとき、お客様の目線がまっさきにこちらに向いていましたから」
「そういうこと……」
納得した様子を見せた母。だがすぐに新たな疑問を抱いたようだ。
「でもなんでそんなことをわざわざ言うの? パーソナルカラーっていうのがあるなら、私にピンクが似合わないのは明らかなんじゃない? だって今まで……」
そこまで言って母は言葉を切る。だが続きは言わなくても分かった。それは陽子さんも同じようで、陽子さんは母の目をじっと見つめると、今までよりもさらに優しい声色で話し始めた。
「確かに、お客様に似合うピンク色は限られていると思います。ですが、本来なら似合わない色でも、使い方次第でどうにでもなります」
「使い方?」
「はい。それはこれから説明していきますね」
と言って、陽子さんは私にアイコンタクトを送ってきた。〝あんたのターンよ〟という意味なのは言わずもがなだ。私は決意を新たにすると、ファンデーションを指さした。
「まずは肌の色味を整えますね」
母に合う色――正確に言うならば私の体に合う色は知り尽くしている。
私はピンク系統を使うことを考えながら選んだ色のファンデーションの塗り方を説明する。するとその通りに陽子さんが鮮やかな手つきで塗っていき、瞬く間につややかな肌に仕上がった。
「これでベースは大丈夫ですね。肝心のアイシャドウですが……今までお客様は目を目立たせないようなメイクをなさっていたんですよね?」
「ええ。うまくはいってなかったみたいだけど……」
なんともコメントに困る返答に答えあぐねる。すると陽子さんが助け舟を出してくれた。
「それは方法を知らなかっただけです。やり方さえ知れば、ある程度の技術は誰でも身につけられます。お客様も、覚えてしまえばご自分でもやれるようになると思いますよ」
その言葉に、私はある方法を思いつく。
「アイメイクですが、良ければ顔半分はお客様ご自身の手でメイクしてみませんか?」
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

生化粧~せいけしょう~(改訂前)
白藤桜空
大衆娯楽
大幅に改訂することにしたので、こちらは一旦完結済みにします。でも物語はまだ完結してません。
改訂後を「生化粧〜せいけしょう〜」として出し直します。
もしこちらを読んでいる方がいらしたら改訂後の生化粧をどうかよろしくお願いします。
メイクアップアーティストのアシスタントの真粧美。忙しい日々を送っていたある日、交通事故に遭う。
真粧美は幽体離脱のようになって自分のねじ曲がった体を見て死を覚悟したが、目が覚めるとベッドの上に寝ていた――自分を見ていた。
自分の意思とは関係なく動き始めた体。その体にはどうやら小学生の頃に死んでしまった真粧美の母親の魂が乗り移っていたようで、周囲を巻き込んで小さな事件を起こしていく。
その後日替わりで母親と体が入れ替わるようになった真粧美は、母親の残していった痕跡に戸惑いながらも、忘れていた大事な思いを思い出していく。
※小説家になろう様でも掲載しております。

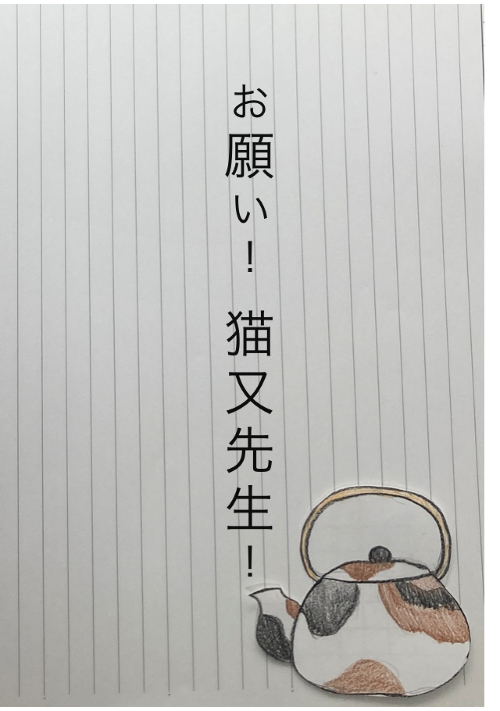
お願い! 猫又先生!
たんぽぽ。
大衆娯楽
お父さんの部屋の押入れで見つけた古い急須をこすると「急須! 急須! 万事急須!」とダミ声がして、オスの三毛猫又が飛び出して来た。
彼は不思議な力を使って、非常にまどろっこしいやり方で、ぼくの願いを叶えてくれるんだ……。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

今日の授業は保健体育
にのみや朱乃
恋愛
(性的描写あり)
僕は家庭教師として、高校三年生のユキの家に行った。
その日はちょうどユキ以外には誰もいなかった。
ユキは勉強したくない、科目を変えようと言う。ユキが提案した科目とは。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

20代前半無職の俺が明日、異世界転移するらしい。
ひさまま
ファンタジー
30代社畜〜の、別バージョンです。
こちらは、麻袋(マジックバック)無し、ハードバージョン。母同伴。
亀更新です。のはずが、終わりました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















