11 / 21
11 のっぽ、合宿ではりきる
しおりを挟む
立川駅に集まった部員たちは言葉を失って、階段口からのっそり現れた長身の少年を見つめた。
「おはようさん…あれ、俺が最後か?」
「ゆ、祐ちゃん、か、髪、いつ切ったの?」
「ああ、これ?夕べ、鏡見ながら、自分で切った…おかしいか?やっぱり…」
祐輝は、中学以来ずっと続けてきたリーゼントをすっぱりとやめて、短く切っていた。
その理由は、誰も知らなかった。
「ううん…とっても素敵…」
竜之介の目はすでにハート型に近かった。
「先輩、いいっすよ。やっと、現代人になったっていうか…痛っ」
安井の頭をこづいた後、祐輝はスポーツバッグをベンチに置いて、ジーパンのポケットをごそごそと探り始める。
それまで黙って祐輝を見ていた沙代子が近づいてきて、髪をかき上げるいつもの仕草をしながら話しかけた。
「 何か 心境の変化でもあったのかしら?ふふ…確かに、少しは変わってもらわないと、コンクールが心配ではあるけど…」
祐輝は携帯の着信を確認すると、にこやかな顔を沙代子に向けた。
「おう…まかせとけ。合宿で俺の進化した姿を見せてやるよ」
「あら、それは楽しみだわ…」
沙代子の言葉が終わらないうちに、ホームに電車が入ってきた。部員たちは手荷物を持って、一斉に移動を始める。
真由は信号待ちのたびに携帯を取り出し、メールを開いて眺めては、思わずクスクスと独りで笑っていた
そこには髪を短く切った祐輝の、照れくさそうな写メールがあった。
昨夜、ベッドでため息ばかりついて眠れずにいた真由の耳に、十二時を過ぎた頃、突然メールの着信を知らせる音楽が聞こえてきた。真由がベッドから跳び起きて、携帯を開くと、その祐輝からのメールがあったのだ。
自転車で二十分あまりかかる学校への道のりも、今朝は少しも長くは感じなかった。
〝先輩…今頃、電車の中ですか?わたしのメール、ちゃんと読んでくれましたか?早く会いたいです。でも、わたし、我慢します。だから、きっと、お返事下さいね〞
鼻の奥がつーんとなって、思わず涙が溢れてくるのを、真由は自分でも驚きながら手でこするのだった。
京葉線の電車の窓の外には、春の日ざしに照らされた東京湾が広がっている。乗り継ぎの時間も含めて、かれこれ一時間半近く満員電車に揺られている演劇部の面々はさすがに疲れた様子で黙り込んでいた。
「祐ちゃん…さっきから、携帯ばっかり眺めてるけど、誰と交信してるの?」
竜之介が、ようやく人が少なくなった通路を祐輝のそばまでやってきた。
「ああ、ゲームだよ、ゲーム…ほら、お前もやるか?」
明らかに、今あわてて画面を切り替えたのは見え見えだったが、竜之介はあえてそれ以上は追及しなかった。
「ねえ、あれはどうだったの?」
竜之介は声をひそめて、祐輝に尋ねた。
「あれ?」
「ほら、あの子よ、木崎…」
祐輝はあわてて竜之介の口を手で押さえ、辺りを見回す。
「ヨッシー…名前を出しちゃあ、おしまいだぞ。いいか、聞けよ…」
うなずく竜之介に、祐輝は真剣な顔でささやいた。
「俺は、生まれ変わった…新生永野祐輝だ…彼女はすごいぞ…インスピレーションの宝庫だ…これからも、彼女にいろいろ教わるつもりだ…いいな、口が裂けてもこのことは秘密だぞ。もちろん、彼女にも近づくな」
竜之介は感激にしゃがれたような声を上げながら、何度もうなづく。
一時間に一通の割合で、真由からのメールが届いていた。内容はたあいもないものだったが、祐輝にとっては貴重な宝物で、元気の源でもあった。
宿舎に着いて早々、休む間もなくランニングに始まり、夕食までみっちりと体力トレーニングが続いた。バスケ部出身の祐輝にとっては、どうということもないメニューのはずだったが、終わる頃には相当へばっていた。やはり体力がかなり落ちていることを思い知らされた。
祐輝がそう感じるくらいだったので、他の部員たちにはまさに地獄の特訓だった。メニューを考えた沙代子自身、予定よりかなり早く練習の終了を告げ、夕食まで休憩を宣言した。
「ああ、もう、あたしダメ……死んじゃうわ」
海岸公園のベンチに倒れ込んだのは、竜之介ばかりではなかった。ほとんどの部員たちが、宿舎に帰る前にあちこちのベンチで体を休めていた。
「あれ?ねえ、部長、祐ちゃんは?」
「まだ、海岸にいたわよ」
祐輝は美浜海岸に続く美しい砂浜を歩きながら、何度も携帯のシャッターを押していた。
真由から『写真、いっぱい送って下さいね』とメールで頼まれていたからだ。
「よし…こんなもんかな。あいつ、まだ部活中かな。ちょっと声を聞きたいな」
写メールを送った後、祐輝は真由の携帯の番号を押そうとして、不意に手を止めた。
「いや、やっぱりやめとこう。今あいつの声聞いたら、飛んで帰りたくなっちまう」
祐輝は携帯を閉じると、目の前に広がる海に目を向けた。愛しいもの、守りたいものがあるということは、こんなにも人に充実感を与えるのだ、と、祐輝は改めて実感するのだった。
夕食後、祐輝たちは体育館を借りて一幕ごとの通し練習を始めた。ところが、その練習は最初から祐輝の独壇場になった。ついこの前まで、ミスを連発していた祐輝とはまるで別人のようだった。彼は完璧に主人公の青年を演じていた。いや、完璧すぎたのだ。
他の部員たちが声もなく舞台に見とれている中で、沙代子は眉間にしわを寄せて、何度も唇をかみしめていた。
「ストップ…はい、オーケーよ。じゃあ、十分間休憩ね」
沙代子は二幕の途中で練習を止めて、竜之介や他の部員たちに囲まれてステージを下りてくる祐輝を待ち受けた。
「ああ、もう、あたし、燃え尽きそうよ。すごい、すごいわ、祐ちゃん……」
「だから、言ったろうが…新生永野祐輝ってな」
「永野君、ちょっと、いい?」
「え、ああ…」
祐輝は、深刻な顔の沙代子を不審に思いながら、彼女の後について体育館の出口へ向かった。
「何だ、部長?俺の演技、まだ不満か?」
「ええ…すごく不満よ」
沙代子は薄暗いロビーの片隅に立って、じっと祐輝を見つめた。
「ちぇっ…俺、一生懸命やってるんだぜ。少しはほめてくれてもいいじゃねえか」ちょっと間があった後、思いがけない言葉が沙代子の口から聞こえてきた。
「ごめんね…」
「えっ…ちょ、ちょっと、部長……」
突然、沙代子が顔を手で覆って涙を流し始めたのを見て、祐輝はあわてた。
「ごめんなさい…えへ…バカみたいよね…あのね、祐輝君…」
沙代子は珍しく下の名前で祐輝を呼んでから、うつむきかげんで続けた。
「あなたの演技は、完璧だったわ。見ていて何度もぞっとしたくらいすごかった…でもね、本番はまだ一ヶ月後なのよ。ピークをそこに合わせなくちゃいけないの…」
「ああ、わかってるよ…ちゃんと、調整するさ」
「いいえ、わかってないわ。あのね、人間の感性って不思議なもので、感動のピークを過ぎると、二度と同じ感動は味わえないの。俗に言う、マンネリ化に陥ってしまうわけ… それは演技にも言えることなのよ。今、あなたと主人公の若者はぴったりと一つに重なっている。でも、このままあなたが役に慣れてきたら、どんどんずれが大きくなっていくの…どんどん永野祐輝が前に出て来ちゃうのよ」
祐輝にはまだ話の内容はよく理解できなかったが、沙代子の真剣なまなざしに負けてうなづいた。
「わかった…それで、どうすりゃいいんだい?」
「あなたはしばらく別メニューで、ギターと歌の練習に打ち込んでほしいの。もちろん体力トレーニングは一緒にやってもらうわ。いい?」
「了解…」
祐輝は手を上げて承諾すると、去っていこうとした。
「祐輝君…」
「ん?まだ、なんかあるのか?」
沙代子はためらいがちに祐輝のそばに近づいてきた。
「嫌な女って思ってるでしょうね…」
「いや、そんなことは一度も思ったことないぜ…」
祐輝は微笑みながら続けた。
「部長はいつも冷静で、正しい判断を下してくれる。みんな信頼してるよ」
「そうね…でも、〝信頼〞イコール〝好き〞じゃないでしょ?」
「え、ま、まあ、それは…」
祐輝は沙代子のまなざしに押されるように、一歩後ろに下がった。
「祐輝君…わたし…」
「休憩時間、終わったよお。二人とも、何やってんのお?」
まるで計ったようなタイミングで、竜之介が体育館の中央付近から、大きな声で叫んだ。
「おう、今行く…さあ、部長、みんな待ってるぜ」
沙代子は明らかにすねた顔で祐輝をにらんでから、つかつかとロビーを出ていった。
「はいはい、三幕、病院の場面から始めるわよ。ほら、ぐずぐずしないの…なあに、ヨッシー、そのメイク。健康なブタじゃないんだから…」
「まっ…ひどおい、あんまりな言い方だわ……」
フロアーのいつもの喧噪を何か遠くのことのように感じながら、祐輝はそっと体育館から出ていき、自分の部屋に戻った。
部屋の中は暗かったが、座卓の上に置いていた携帯が、着信があったことを示す緑の光を放っていた。祐輝は灯りをつけると、さっそく携帯を開いて着信履歴を見た。七時からほぼ二十分おきに、真由からのメールや着信が来ていた。
祐輝はリダイヤルを押して携帯を耳に当てる。二回の呼び出し音のあと、あの一番聞きたかった声が聞こえてきた。
『もしもし、先輩ですか?もしもし…』
祐輝は目をつぶって、うっとりとその声に聞き惚れた。
「やあ、俺だよ…元気だった?」
『もう、びっくりしたじゃないですか。黙ってるんだもん…』
「あはは…ごめん…真由の声に聞き惚れてた…今、何してる?」
『今ですか?ギターを弾いてました。先輩が帰ってきたら、ちゃんと教えてあげられるように練習してるんですよ。ふふ…』
「そっか…楽しみにしてるよ。実は、俺も今からギターの練習なんだ…」
『あ、そうなんだ。ふふ…わかんないところがあったら、電話下さいね』
「ああ、そうするよ……なあ、真由……」
『はい…』
「真由の顔、写真で送ってくれよ」
『あちゃあ、やっぱり、そうきましたか…』
「なんだ?その変なリアクション…」
『いえ、あの、先輩がそう言ったらどうしようって、ずっと悩んでいたんです』
「なんで悩むんだ?」
『だって…先輩には、一番可愛いわたしの写真を持っていて欲しいんです。だから、どんな服着て、どこで写そうかって、迷ってて…』
祐輝は今すぐにでも、真由を抱きしめに飛んでいきたい衝動に駆られた。
「いいから、すぐに送るんだ。あと、一分後だ」
『ええっ…そんな…わ、わかりましたよ…』
「真由…」
『は、はい…』
「大好きだ…」
真由は携帯を耳に当てたまま、わなわなと唇を震わせ始める。すぐに涙が溢れてきて、ぽとぽとと楽譜の上に落ちていった。
『お前、今笑いこらえてるんだろう?いいぜ、笑っても…俺は急性真由中毒さ…大声で叫んでやろうかな。愛してるぜ、真由、おお、マイ・ハニー…』
「せ、先輩っ、もう…ふふ……バカ…」
長いまつげに溜まった涙の滴を手でこすりながら、真由は切ないため息をつく。
「あ、そうだ、ねえ、先輩…?」
『うん、なんだ?』
真由は立ち上がって、机の上に置いていた本を取り上げると、パラパラとページをめくった。
「先輩の血液型、何ですか?」
真由はきっと祐輝はO型だと確信しながら、O型が好きな女の子のタイプのところを眺めた。
『俺は、確かB型だったな。それが、どうかしたのか?』
「ええっ…そ、そんなあ……」
真由はショックを受けて、血液型の相性のところを開いた。真由はA型だ。どんな本を見ても、A型とB型の相性は最悪なのだ。
『なんだ、血液型占いの本かなんか、見てるのか?お前、信じてるのか?』
「ううん、今日限り、信じないことにします。大丈夫です」
『ああ、そうさ。血液型なんかで左右されてたまるかよ。真由は真由で、俺は俺だ。俺は真由が好きだ。真由の何もかもが好きだ』
「うん…わたしだって…先輩が…大好きです…」
しばらくの間、幸せな沈黙が続く。真由はうっとりと目をつぶって、受話器の向こうの祐輝の息を吸い込むように、大きく深呼吸をした。
『真由…』
「はい…」
『そろそろ、ギターの練習始めるから…写真、必ず送るんだぞ』
「うん…頑張ってね」
『おう…じゃあ…』
通話が切れた後も、真由はしばらくの間、そのツーツーという音を聞いていた。こんなに切ないほど幸せな気分を、永遠に心に閉じこめておきたかった。
「おはようさん…あれ、俺が最後か?」
「ゆ、祐ちゃん、か、髪、いつ切ったの?」
「ああ、これ?夕べ、鏡見ながら、自分で切った…おかしいか?やっぱり…」
祐輝は、中学以来ずっと続けてきたリーゼントをすっぱりとやめて、短く切っていた。
その理由は、誰も知らなかった。
「ううん…とっても素敵…」
竜之介の目はすでにハート型に近かった。
「先輩、いいっすよ。やっと、現代人になったっていうか…痛っ」
安井の頭をこづいた後、祐輝はスポーツバッグをベンチに置いて、ジーパンのポケットをごそごそと探り始める。
それまで黙って祐輝を見ていた沙代子が近づいてきて、髪をかき上げるいつもの仕草をしながら話しかけた。
「 何か 心境の変化でもあったのかしら?ふふ…確かに、少しは変わってもらわないと、コンクールが心配ではあるけど…」
祐輝は携帯の着信を確認すると、にこやかな顔を沙代子に向けた。
「おう…まかせとけ。合宿で俺の進化した姿を見せてやるよ」
「あら、それは楽しみだわ…」
沙代子の言葉が終わらないうちに、ホームに電車が入ってきた。部員たちは手荷物を持って、一斉に移動を始める。
真由は信号待ちのたびに携帯を取り出し、メールを開いて眺めては、思わずクスクスと独りで笑っていた
そこには髪を短く切った祐輝の、照れくさそうな写メールがあった。
昨夜、ベッドでため息ばかりついて眠れずにいた真由の耳に、十二時を過ぎた頃、突然メールの着信を知らせる音楽が聞こえてきた。真由がベッドから跳び起きて、携帯を開くと、その祐輝からのメールがあったのだ。
自転車で二十分あまりかかる学校への道のりも、今朝は少しも長くは感じなかった。
〝先輩…今頃、電車の中ですか?わたしのメール、ちゃんと読んでくれましたか?早く会いたいです。でも、わたし、我慢します。だから、きっと、お返事下さいね〞
鼻の奥がつーんとなって、思わず涙が溢れてくるのを、真由は自分でも驚きながら手でこするのだった。
京葉線の電車の窓の外には、春の日ざしに照らされた東京湾が広がっている。乗り継ぎの時間も含めて、かれこれ一時間半近く満員電車に揺られている演劇部の面々はさすがに疲れた様子で黙り込んでいた。
「祐ちゃん…さっきから、携帯ばっかり眺めてるけど、誰と交信してるの?」
竜之介が、ようやく人が少なくなった通路を祐輝のそばまでやってきた。
「ああ、ゲームだよ、ゲーム…ほら、お前もやるか?」
明らかに、今あわてて画面を切り替えたのは見え見えだったが、竜之介はあえてそれ以上は追及しなかった。
「ねえ、あれはどうだったの?」
竜之介は声をひそめて、祐輝に尋ねた。
「あれ?」
「ほら、あの子よ、木崎…」
祐輝はあわてて竜之介の口を手で押さえ、辺りを見回す。
「ヨッシー…名前を出しちゃあ、おしまいだぞ。いいか、聞けよ…」
うなずく竜之介に、祐輝は真剣な顔でささやいた。
「俺は、生まれ変わった…新生永野祐輝だ…彼女はすごいぞ…インスピレーションの宝庫だ…これからも、彼女にいろいろ教わるつもりだ…いいな、口が裂けてもこのことは秘密だぞ。もちろん、彼女にも近づくな」
竜之介は感激にしゃがれたような声を上げながら、何度もうなづく。
一時間に一通の割合で、真由からのメールが届いていた。内容はたあいもないものだったが、祐輝にとっては貴重な宝物で、元気の源でもあった。
宿舎に着いて早々、休む間もなくランニングに始まり、夕食までみっちりと体力トレーニングが続いた。バスケ部出身の祐輝にとっては、どうということもないメニューのはずだったが、終わる頃には相当へばっていた。やはり体力がかなり落ちていることを思い知らされた。
祐輝がそう感じるくらいだったので、他の部員たちにはまさに地獄の特訓だった。メニューを考えた沙代子自身、予定よりかなり早く練習の終了を告げ、夕食まで休憩を宣言した。
「ああ、もう、あたしダメ……死んじゃうわ」
海岸公園のベンチに倒れ込んだのは、竜之介ばかりではなかった。ほとんどの部員たちが、宿舎に帰る前にあちこちのベンチで体を休めていた。
「あれ?ねえ、部長、祐ちゃんは?」
「まだ、海岸にいたわよ」
祐輝は美浜海岸に続く美しい砂浜を歩きながら、何度も携帯のシャッターを押していた。
真由から『写真、いっぱい送って下さいね』とメールで頼まれていたからだ。
「よし…こんなもんかな。あいつ、まだ部活中かな。ちょっと声を聞きたいな」
写メールを送った後、祐輝は真由の携帯の番号を押そうとして、不意に手を止めた。
「いや、やっぱりやめとこう。今あいつの声聞いたら、飛んで帰りたくなっちまう」
祐輝は携帯を閉じると、目の前に広がる海に目を向けた。愛しいもの、守りたいものがあるということは、こんなにも人に充実感を与えるのだ、と、祐輝は改めて実感するのだった。
夕食後、祐輝たちは体育館を借りて一幕ごとの通し練習を始めた。ところが、その練習は最初から祐輝の独壇場になった。ついこの前まで、ミスを連発していた祐輝とはまるで別人のようだった。彼は完璧に主人公の青年を演じていた。いや、完璧すぎたのだ。
他の部員たちが声もなく舞台に見とれている中で、沙代子は眉間にしわを寄せて、何度も唇をかみしめていた。
「ストップ…はい、オーケーよ。じゃあ、十分間休憩ね」
沙代子は二幕の途中で練習を止めて、竜之介や他の部員たちに囲まれてステージを下りてくる祐輝を待ち受けた。
「ああ、もう、あたし、燃え尽きそうよ。すごい、すごいわ、祐ちゃん……」
「だから、言ったろうが…新生永野祐輝ってな」
「永野君、ちょっと、いい?」
「え、ああ…」
祐輝は、深刻な顔の沙代子を不審に思いながら、彼女の後について体育館の出口へ向かった。
「何だ、部長?俺の演技、まだ不満か?」
「ええ…すごく不満よ」
沙代子は薄暗いロビーの片隅に立って、じっと祐輝を見つめた。
「ちぇっ…俺、一生懸命やってるんだぜ。少しはほめてくれてもいいじゃねえか」ちょっと間があった後、思いがけない言葉が沙代子の口から聞こえてきた。
「ごめんね…」
「えっ…ちょ、ちょっと、部長……」
突然、沙代子が顔を手で覆って涙を流し始めたのを見て、祐輝はあわてた。
「ごめんなさい…えへ…バカみたいよね…あのね、祐輝君…」
沙代子は珍しく下の名前で祐輝を呼んでから、うつむきかげんで続けた。
「あなたの演技は、完璧だったわ。見ていて何度もぞっとしたくらいすごかった…でもね、本番はまだ一ヶ月後なのよ。ピークをそこに合わせなくちゃいけないの…」
「ああ、わかってるよ…ちゃんと、調整するさ」
「いいえ、わかってないわ。あのね、人間の感性って不思議なもので、感動のピークを過ぎると、二度と同じ感動は味わえないの。俗に言う、マンネリ化に陥ってしまうわけ… それは演技にも言えることなのよ。今、あなたと主人公の若者はぴったりと一つに重なっている。でも、このままあなたが役に慣れてきたら、どんどんずれが大きくなっていくの…どんどん永野祐輝が前に出て来ちゃうのよ」
祐輝にはまだ話の内容はよく理解できなかったが、沙代子の真剣なまなざしに負けてうなづいた。
「わかった…それで、どうすりゃいいんだい?」
「あなたはしばらく別メニューで、ギターと歌の練習に打ち込んでほしいの。もちろん体力トレーニングは一緒にやってもらうわ。いい?」
「了解…」
祐輝は手を上げて承諾すると、去っていこうとした。
「祐輝君…」
「ん?まだ、なんかあるのか?」
沙代子はためらいがちに祐輝のそばに近づいてきた。
「嫌な女って思ってるでしょうね…」
「いや、そんなことは一度も思ったことないぜ…」
祐輝は微笑みながら続けた。
「部長はいつも冷静で、正しい判断を下してくれる。みんな信頼してるよ」
「そうね…でも、〝信頼〞イコール〝好き〞じゃないでしょ?」
「え、ま、まあ、それは…」
祐輝は沙代子のまなざしに押されるように、一歩後ろに下がった。
「祐輝君…わたし…」
「休憩時間、終わったよお。二人とも、何やってんのお?」
まるで計ったようなタイミングで、竜之介が体育館の中央付近から、大きな声で叫んだ。
「おう、今行く…さあ、部長、みんな待ってるぜ」
沙代子は明らかにすねた顔で祐輝をにらんでから、つかつかとロビーを出ていった。
「はいはい、三幕、病院の場面から始めるわよ。ほら、ぐずぐずしないの…なあに、ヨッシー、そのメイク。健康なブタじゃないんだから…」
「まっ…ひどおい、あんまりな言い方だわ……」
フロアーのいつもの喧噪を何か遠くのことのように感じながら、祐輝はそっと体育館から出ていき、自分の部屋に戻った。
部屋の中は暗かったが、座卓の上に置いていた携帯が、着信があったことを示す緑の光を放っていた。祐輝は灯りをつけると、さっそく携帯を開いて着信履歴を見た。七時からほぼ二十分おきに、真由からのメールや着信が来ていた。
祐輝はリダイヤルを押して携帯を耳に当てる。二回の呼び出し音のあと、あの一番聞きたかった声が聞こえてきた。
『もしもし、先輩ですか?もしもし…』
祐輝は目をつぶって、うっとりとその声に聞き惚れた。
「やあ、俺だよ…元気だった?」
『もう、びっくりしたじゃないですか。黙ってるんだもん…』
「あはは…ごめん…真由の声に聞き惚れてた…今、何してる?」
『今ですか?ギターを弾いてました。先輩が帰ってきたら、ちゃんと教えてあげられるように練習してるんですよ。ふふ…』
「そっか…楽しみにしてるよ。実は、俺も今からギターの練習なんだ…」
『あ、そうなんだ。ふふ…わかんないところがあったら、電話下さいね』
「ああ、そうするよ……なあ、真由……」
『はい…』
「真由の顔、写真で送ってくれよ」
『あちゃあ、やっぱり、そうきましたか…』
「なんだ?その変なリアクション…」
『いえ、あの、先輩がそう言ったらどうしようって、ずっと悩んでいたんです』
「なんで悩むんだ?」
『だって…先輩には、一番可愛いわたしの写真を持っていて欲しいんです。だから、どんな服着て、どこで写そうかって、迷ってて…』
祐輝は今すぐにでも、真由を抱きしめに飛んでいきたい衝動に駆られた。
「いいから、すぐに送るんだ。あと、一分後だ」
『ええっ…そんな…わ、わかりましたよ…』
「真由…」
『は、はい…』
「大好きだ…」
真由は携帯を耳に当てたまま、わなわなと唇を震わせ始める。すぐに涙が溢れてきて、ぽとぽとと楽譜の上に落ちていった。
『お前、今笑いこらえてるんだろう?いいぜ、笑っても…俺は急性真由中毒さ…大声で叫んでやろうかな。愛してるぜ、真由、おお、マイ・ハニー…』
「せ、先輩っ、もう…ふふ……バカ…」
長いまつげに溜まった涙の滴を手でこすりながら、真由は切ないため息をつく。
「あ、そうだ、ねえ、先輩…?」
『うん、なんだ?』
真由は立ち上がって、机の上に置いていた本を取り上げると、パラパラとページをめくった。
「先輩の血液型、何ですか?」
真由はきっと祐輝はO型だと確信しながら、O型が好きな女の子のタイプのところを眺めた。
『俺は、確かB型だったな。それが、どうかしたのか?』
「ええっ…そ、そんなあ……」
真由はショックを受けて、血液型の相性のところを開いた。真由はA型だ。どんな本を見ても、A型とB型の相性は最悪なのだ。
『なんだ、血液型占いの本かなんか、見てるのか?お前、信じてるのか?』
「ううん、今日限り、信じないことにします。大丈夫です」
『ああ、そうさ。血液型なんかで左右されてたまるかよ。真由は真由で、俺は俺だ。俺は真由が好きだ。真由の何もかもが好きだ』
「うん…わたしだって…先輩が…大好きです…」
しばらくの間、幸せな沈黙が続く。真由はうっとりと目をつぶって、受話器の向こうの祐輝の息を吸い込むように、大きく深呼吸をした。
『真由…』
「はい…」
『そろそろ、ギターの練習始めるから…写真、必ず送るんだぞ』
「うん…頑張ってね」
『おう…じゃあ…』
通話が切れた後も、真由はしばらくの間、そのツーツーという音を聞いていた。こんなに切ないほど幸せな気分を、永遠に心に閉じこめておきたかった。
0
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

何故か超絶美少女に嫌われる日常
やまたけ
青春
K市内一と言われる超絶美少女の高校三年生柊美久。そして同じ高校三年生の武智悠斗は、何故か彼女に絡まれ疎まれる。何をしたのか覚えがないが、とにかく何かと文句を言われる毎日。だが、それでも彼女に歯向かえない事情があるようで……。疋田美里という、主人公がバイト先で知り合った可愛い女子高生。彼女の存在がより一層、この物語を複雑化させていくようで。
しょっぱなヒロインから嫌われるという、ちょっとひねくれた恋愛小説。

One-sided
月ヶ瀬 杏
青春
高校一年生の 唯葉は、ひとつ上の先輩・梁井碧斗と付き合っている。
一ヶ月前、どんなに可愛い女の子に告白されても断ってしまうという噂の梁井に玉砕覚悟で告白し、何故か彼女にしてもらうことができたのだ。
告白にオッケーの返事をもらえたことで浮かれる唯葉だが、しばらくして、梁井が唯葉の告白を受け入れた本当の理由に気付いてしまう。
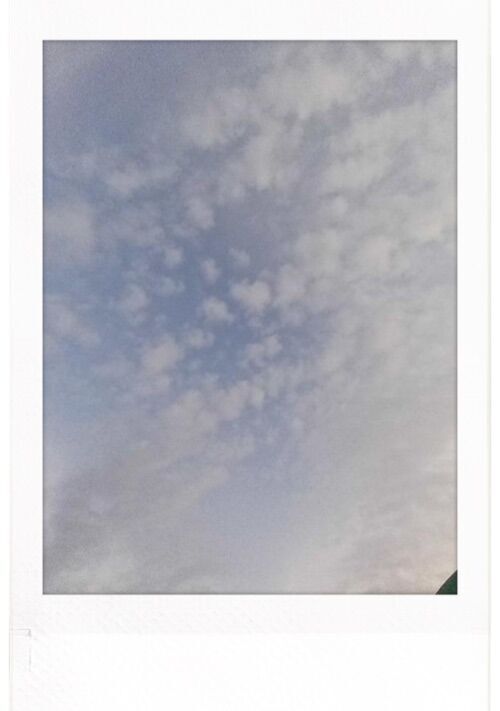
ファンファーレ!
ほしのことば
青春
♡完結まで毎日投稿♡
高校2年生の初夏、ユキは余命1年だと申告された。思えば、今まで「なんとなく」で生きてきた人生。延命治療も勧められたが、ユキは治療はせず、残りの人生を全力で生きることを決意した。
友情・恋愛・行事・学業…。
今まで適当にこなしてきただけの毎日を全力で過ごすことで、ユキの「生」に関する気持ちは段々と動いていく。
主人公のユキの心情を軸に、ユキが全力で生きることで起きる周りの心情の変化も描く。
誰もが感じたことのある青春時代の悩みや感動が、きっとあなたの心に寄り添う作品。

自称未来の妻なヤンデレ転校生に振り回された挙句、最終的に責任を取らされる話
水島紗鳥
青春
成績優秀でスポーツ万能な男子高校生の黒月拓馬は、学校では常に1人だった。
そんなハイスペックぼっちな拓馬の前に未来の妻を自称する日英ハーフの美少女転校生、十六夜アリスが現れた事で平穏だった日常生活が激変する。
凄まじくヤンデレなアリスは拓馬を自分だけの物にするためにありとあらゆる手段を取り、どんどん外堀を埋めていく。
「なあ、サインと判子欲しいって渡された紙が記入済婚姻届なのは気のせいか?」
「気にしない気にしない」
「いや、気にするに決まってるだろ」
ヤンデレなアリスから完全にロックオンされてしまった拓馬の運命はいかに……?(なお、もう一生逃げられない模様)
表紙はイラストレーターの谷川犬兎様に描いていただきました。
小説投稿サイトでの利用許可を頂いております。

片翼のエール
乃南羽緒
青春
「おまえのテニスに足りないものがある」
高校総体テニス競技個人決勝。
大神謙吾は、一学年上の好敵手に敗北を喫した。
技術、スタミナ、メンタルどれをとっても申し分ないはずの大神のテニスに、ひとつ足りないものがある、と。
それを教えてくれるだろうと好敵手から名指しされたのは、『七浦』という人物。
そいつはまさかの女子で、あまつさえテニス部所属の経験がないヤツだった──。

脅され彼女~可愛い女子の弱みを握ったので脅して彼女にしてみたが、健気すぎて幸せにしたいと思った~
みずがめ
青春
陰キャ男子が後輩の女子の弱みを握ってしまった。彼女いない歴=年齢の彼は後輩少女に彼女になってくれとお願いする。脅迫から生まれた恋人関係ではあったが、彼女はとても健気な女の子だった。
ゲス男子×健気女子のコンプレックスにまみれた、もしかしたら純愛になるかもしれないお話。
※この作品は別サイトにも掲載しています。
※表紙イラストは、あっきコタロウさんに描いていただきました。

隣人の女性がDVされてたから助けてみたら、なぜかその人(年下の女子大生)と同棲することになった(なんで?)
チドリ正明@不労所得発売中!!
青春
マンションの隣の部屋から女性の悲鳴と男性の怒鳴り声が聞こえた。
主人公 時田宗利(ときたむねとし)の判断は早かった。迷わず訪問し時間を稼ぎ、確証が取れた段階で警察に通報。DV男を現行犯でとっちめることに成功した。
ちっぽけな勇気と小心者が持つ単なる親切心でやった宗利は日常に戻る。
しかし、しばらくして宗時は見覚えのある女性が部屋の前にしゃがみ込んでいる姿を発見した。
その女性はDVを受けていたあの時の隣人だった。
「頼れる人がいないんです……私と一緒に暮らしてくれませんか?」
これはDVから女性を守ったことで始まる新たな恋物語。

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち
ヒロワークス
ライト文芸
女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。
クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。
それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。
そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!
その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















